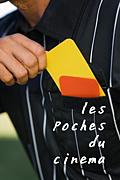おはなし:渡邉大輔/角田亮
進行:鈴木並木
2016年03月27日(日)19時〜21時(延長はなるべくナシの予定)
@阿佐ヶ谷・よるのひるね
http://
参加費500円+要1オーダー
参加自由/申し込み不要/途中入場・退出自由
☆入場時、鈴木に参加費500円をお支払いください。そのうえでお店の方にフードやドリンクのご注文をお願いします。
−−−
☆渡邉大輔(わたなべ・だいすけ)
https:/
1982年生まれ。映画史研究者・批評家。現在、跡見学園女子大学文学部助教、日本大学藝術学部非常勤講師。映画批評、映像メディア論を中心に、文芸評論、ミステリ評論など幅広く批評活動を展開。著作に『イメージの進行形』(人文書院)、共著に『見えない殺人カード』(講談社)『ソーシャル・ドキュメンタリー』(フィルムアート社)『アジア映画で<世界>を見る』(作品社)『日本映画の海外進出』(森話社)など多数。
☆角田亮(つのだ・りょう)
https:/
在野の映画研究者(自称荒地派) 映画について(特にテクノロジーとテクニック)あれこれ書いたり考えたりしています。
−−−
映画はすでに死んでいる。しかし、その死は未だ隠され続け、我々はシネコンや名画座の暗闇でスクリーンを見つめ続けている。いま銀幕に映し出されているのは、既に見たことのがある映画の屍骸なのだ。
急激なデジタル技術の進化によって、百余年に及ぶ35mmフィルム/24コマの映画的聖域が崩れ、解放されたイメージはデータの宇宙を彷徨いながら、3D、VR/ARと形を変えた見世物(スペクタクル)化を繰り返しながら、再び映画と映像が接近・交差して来る様に思える。
果たしてデジタルは映画を殺した真犯人なのだろうか?否、デジタルはトドメの一撃であり、実はもっと昔から映画は腹違いの弟であるテレビとヴィデオによって緩慢な死を迎えている。テレビはその小さなブラウン管の画面のために、「電気紙芝居」と醜悪さが強調されるだけで、メディアの可能性を長らく顧みられて来なかった。その一方で血筋の正当性を謳う映画の神聖なフォーマットは、特権的なスタイルの美学に奉仕するだけで、映画は自らの実験的な革新性を止めてしまった。その間にテレビ/映像は世界の空間を侵食し尽くし、ヴィデオは時間の大衆化を推し進めた。
その結果、二十世紀の終わりに「映画史」は停滞/消滅してしまったように見える。この現象を後ろ向きに嘆いても仕方ない。実際に映像は、毎分毎秒YouTubeにアップロードされ、ハリウッドブロックバスターは興行記録を塗り替え、消化できないほどの深夜アニメが出現しているのだから。
それならば現実に沿ったサブカル/オタク世代に相応しい「映画史」を再構築しようではないか。それはきっと美しくないだろう、ダサく格好良くもないだろう、どんなに語ってもアタマが良く見えないだろう、しかし我々にはそれが必要だろう。
現代の「映画史」は既にある。まだ目を逸らして凝視していないだけだ。
(文/角田亮)
なにやら挑発的なタイトルですが、この程度のアオリ文句で簡単に怒り出したりするようなひとにはそもそもお越しいただかなくてもいいような気もしますし、と同時に、そういうひとにこそぜひとも足をお運びいただきたいような気もしています。
ヒントをひとつだけ申し上げておきましょう。山で迷ったときにはどうすればいいか? 答えは「わかっている地点まで戻る」です。さてでは、わたしたちは一体どこいらへんまで戻ればいいのか。これは死亡宣告ではありません。いったん戻ってまた歩き始めるための、わたしたちと映画にとっての道案内なのです。
(文/鈴木並木)
−−−
☆本篇終了後、おそらく引き続き同じ場所で、2次会があります。ご都合のつく方はこちらもあわせてご参加、ご歓談ください。費用は実費。
進行:鈴木並木
2016年03月27日(日)19時〜21時(延長はなるべくナシの予定)
@阿佐ヶ谷・よるのひるね
http://
参加費500円+要1オーダー
参加自由/申し込み不要/途中入場・退出自由
☆入場時、鈴木に参加費500円をお支払いください。そのうえでお店の方にフードやドリンクのご注文をお願いします。
−−−
☆渡邉大輔(わたなべ・だいすけ)
https:/
1982年生まれ。映画史研究者・批評家。現在、跡見学園女子大学文学部助教、日本大学藝術学部非常勤講師。映画批評、映像メディア論を中心に、文芸評論、ミステリ評論など幅広く批評活動を展開。著作に『イメージの進行形』(人文書院)、共著に『見えない殺人カード』(講談社)『ソーシャル・ドキュメンタリー』(フィルムアート社)『アジア映画で<世界>を見る』(作品社)『日本映画の海外進出』(森話社)など多数。
☆角田亮(つのだ・りょう)
https:/
在野の映画研究者(自称荒地派) 映画について(特にテクノロジーとテクニック)あれこれ書いたり考えたりしています。
−−−
映画はすでに死んでいる。しかし、その死は未だ隠され続け、我々はシネコンや名画座の暗闇でスクリーンを見つめ続けている。いま銀幕に映し出されているのは、既に見たことのがある映画の屍骸なのだ。
急激なデジタル技術の進化によって、百余年に及ぶ35mmフィルム/24コマの映画的聖域が崩れ、解放されたイメージはデータの宇宙を彷徨いながら、3D、VR/ARと形を変えた見世物(スペクタクル)化を繰り返しながら、再び映画と映像が接近・交差して来る様に思える。
果たしてデジタルは映画を殺した真犯人なのだろうか?否、デジタルはトドメの一撃であり、実はもっと昔から映画は腹違いの弟であるテレビとヴィデオによって緩慢な死を迎えている。テレビはその小さなブラウン管の画面のために、「電気紙芝居」と醜悪さが強調されるだけで、メディアの可能性を長らく顧みられて来なかった。その一方で血筋の正当性を謳う映画の神聖なフォーマットは、特権的なスタイルの美学に奉仕するだけで、映画は自らの実験的な革新性を止めてしまった。その間にテレビ/映像は世界の空間を侵食し尽くし、ヴィデオは時間の大衆化を推し進めた。
その結果、二十世紀の終わりに「映画史」は停滞/消滅してしまったように見える。この現象を後ろ向きに嘆いても仕方ない。実際に映像は、毎分毎秒YouTubeにアップロードされ、ハリウッドブロックバスターは興行記録を塗り替え、消化できないほどの深夜アニメが出現しているのだから。
それならば現実に沿ったサブカル/オタク世代に相応しい「映画史」を再構築しようではないか。それはきっと美しくないだろう、ダサく格好良くもないだろう、どんなに語ってもアタマが良く見えないだろう、しかし我々にはそれが必要だろう。
現代の「映画史」は既にある。まだ目を逸らして凝視していないだけだ。
(文/角田亮)
なにやら挑発的なタイトルですが、この程度のアオリ文句で簡単に怒り出したりするようなひとにはそもそもお越しいただかなくてもいいような気もしますし、と同時に、そういうひとにこそぜひとも足をお運びいただきたいような気もしています。
ヒントをひとつだけ申し上げておきましょう。山で迷ったときにはどうすればいいか? 答えは「わかっている地点まで戻る」です。さてでは、わたしたちは一体どこいらへんまで戻ればいいのか。これは死亡宣告ではありません。いったん戻ってまた歩き始めるための、わたしたちと映画にとっての道案内なのです。
(文/鈴木並木)
−−−
☆本篇終了後、おそらく引き続き同じ場所で、2次会があります。ご都合のつく方はこちらもあわせてご参加、ご歓談ください。費用は実費。
|
|
|
|
|
|
|
|
映画のポケット 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
映画のポケットのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90063人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208322人
- 3位
- 酒好き
- 170697人