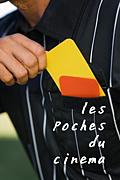Vol.17「“映画的”とは何か」2009/02/21
ゲスト:なんきん
小僧:鈴木並木
02月21日(土)19:00〜21:00(試合展開により延長の場合あり)
@下北沢・気流舎
http://
参加費500円+要1ドリンクオーダー
参加自由/申し込み不要/途中入場・退出自由
今度の「映画のポケット」は何をやるのか、とひとに訊かれまして、このタイトルを伝えたところ、「どういうことをやるのか、全然見当がつかないね」と言われました。あわてて言い換えようとしたものの、うまくいかない。「映画の作り方」でもないし、「映画の成り立ち」とも違う。「映画の秘法」と言えば少しは近くなり、「映画の秘宝」となるとまた遠くなる。英語で言えば、“What makes a movie a movie”。つまり、映画を(ほかのなにものでもなく)映画にするのは何か。
……ということを考えてみる回です。小説でもない、演劇でもない、TVでもない、映画にしかできない、映画ならではの魅力の正体とは何か。そこらの映画館、見終わってロビーに出たところで同じ回を見ていた知り合いに会い、なにも言わなくても分かる、とばかりに、うんうんとうなづきあって別れる、あの感じを再現したい。ただし、映画を見たことのない子供にも分かるように。
もちろん、話を面白くするのはどんなときでも意見の相違ですから、提示された資料に対して「これはちょっと違うんじゃないか」とか「わたしだったらこっちのほうが」とかツッコミを入れていただくのも大歓迎。なんきん先生が、意見を求めていきなりあなたを指名したり、なんてこともあるかもよ。もちろん、小さくなってひっそりと聞いていただくのも大歓迎です。
映画はこうでなくちゃいけない、と規定するよりは、ひょっとしてこれも映画に入れていいんじゃないか? と、可能な限りの映画の拡大解釈をしてみたい気もあります。いずれにしても、みなさんの映画観になんらかのゆさぶりをかける、そんな2時間になるはずです。お楽しみに。
*今回から、お店の使用料がかかるようになったことを受けて、ドリンク代とは別に参加費として500円をいただくことになりました。あしからずご了承ください。詳細は下記をご覧ください。
http://
*なんきんさんのプロフィールは近日中にアップいたします。
ゲスト:なんきん
小僧:鈴木並木
02月21日(土)19:00〜21:00(試合展開により延長の場合あり)
@下北沢・気流舎
http://
参加費500円+要1ドリンクオーダー
参加自由/申し込み不要/途中入場・退出自由
今度の「映画のポケット」は何をやるのか、とひとに訊かれまして、このタイトルを伝えたところ、「どういうことをやるのか、全然見当がつかないね」と言われました。あわてて言い換えようとしたものの、うまくいかない。「映画の作り方」でもないし、「映画の成り立ち」とも違う。「映画の秘法」と言えば少しは近くなり、「映画の秘宝」となるとまた遠くなる。英語で言えば、“What makes a movie a movie”。つまり、映画を(ほかのなにものでもなく)映画にするのは何か。
……ということを考えてみる回です。小説でもない、演劇でもない、TVでもない、映画にしかできない、映画ならではの魅力の正体とは何か。そこらの映画館、見終わってロビーに出たところで同じ回を見ていた知り合いに会い、なにも言わなくても分かる、とばかりに、うんうんとうなづきあって別れる、あの感じを再現したい。ただし、映画を見たことのない子供にも分かるように。
もちろん、話を面白くするのはどんなときでも意見の相違ですから、提示された資料に対して「これはちょっと違うんじゃないか」とか「わたしだったらこっちのほうが」とかツッコミを入れていただくのも大歓迎。なんきん先生が、意見を求めていきなりあなたを指名したり、なんてこともあるかもよ。もちろん、小さくなってひっそりと聞いていただくのも大歓迎です。
映画はこうでなくちゃいけない、と規定するよりは、ひょっとしてこれも映画に入れていいんじゃないか? と、可能な限りの映画の拡大解釈をしてみたい気もあります。いずれにしても、みなさんの映画観になんらかのゆさぶりをかける、そんな2時間になるはずです。お楽しみに。
*今回から、お店の使用料がかかるようになったことを受けて、ドリンク代とは別に参加費として500円をいただくことになりました。あしからずご了承ください。詳細は下記をご覧ください。
http://
*なんきんさんのプロフィールは近日中にアップいたします。
|
|
|
|
コメント(16)
■ 鈴木の口上
映画についていろいろ考えてみましたが、「映画には可能でTVにはできないこと」が本当に存在するのかどうか、断言できない気分になってきました。ですので本日は、ムリに「映画的」を定義づけしてそこに入らないものを排除することはせず、分からないものは分からないものとして、そのうえで、みなさんがいい気分になるような、問答無用の強度のある映像をいくつか提示してみます。
■ 鈴木の紹介作品
*清水宏「港の日本娘」(1933/日本/サイレント)
屋外のシーンのかなりの部分で、いい風が吹いています。風の表現はわりといつも気になるのですが、おそらくその理由は、人為的にコントロールできないものの代表のひとつとして、風を見ているからなのでしょう。ドラ役の井上雪子は1936年に引退、2004年、塩田明彦「カナリア」で68年ぶり(!)に銀幕復帰。
*マルレン・フツィエフ&フェリックス・ミロネル「河向こうの通りの春」(Весна на Заречной улице)(1956/ソ連)
工場訪問シーン。蒸気機関車の煙と工場の煙が盛大に風に流れる。工場内での光の差し込み方にも注目。映画業界関係者の方、どなたかフツィエフ特集をやってください。という意図でセレクト。
*グル・ダット「紙の花」(1959/インド)
インド版「サンセット大通り」的な一篇。主人公たちがドライヴしていると、男女が鈴なりになった車がそばにきて歌い出す。「君も出世ができる」の♪タークラマカーン♪くらい意味が分からない感動(ほめております)。
インド初のシネスコ作品であった本作(使用した資料はシネスコじゃなかった……)は興行的に失敗。結果的にダット最後の監督作品になった(役者としては活躍)。主演女優とは実際に不倫関係にあった、というのはまだ普通の話ですが、彼女の歌の吹き替えをしたのがプレイバック・シンガーだった監督の奥さんだというのがなんだかもう。
*サンチアゴ・アルバレス「ナウ!」(1965/キューバ)、「79歳の春」(1969/キューバ)
「編集の天才」と呼ばれたドキュメンタリスト、アルバレスは、「写真を2枚と編集機(ムビオラ)、そしてちょっと音楽をくれ。君に映画を作ってやろう」と豪語したひと。「ナウ!」を見ると、それがハッタリではないと分かります。彼のいう「緊急映画(cine urgente)」とはつまり、デスクトップ・ムーヴィー、ベッドルーム・ムーヴィーの元祖かも。「79歳の春」の戦闘シーンの編集も明らかにやりすぎで、意味が分からない(ほめております)。
■ 鈴木のその他の推薦作品
*井土紀州「レフト・アローン」(2004)(未ソフト化)
みんながしゃべってるだけ。それなのに「ラザロ」よりスリリングで面白い。
*青山真治「AA」(2005)(未ソフト化)
みんながしゃべってるだけ。それなのに「ユリイカ」より愛にあふれてて面白い。
*市川崑「東京オリンピック」(1965)
映画とはつまり編集(=時間をどう使うか)なのではないか。監督が撮影現場にいる必要すらない、ということは、獄中から演出したというユルマズ・ギュネイ「路」のエピソードでも分かる。
*ハワード・ホークス「ハタリ!」(1962)
猿をつかまえるのにロケットを使うバカバカしさよ。ホークスは男子心をそそります。「自分がその中に入って住んでみたくなるかどうか」は、わたしにとっていい映画のひとつの基準。ホークス、ジャン・ルノワール、マキノ、森崎東がその路線に分類されます。
*マルレン・フツィエフ「私は20歳」(1962)
自在に動くカメラがとらえると、モスクワは60年代きってのおしゃれ都市に見える。驚愕のヌーヴェル・ヴァーグ。現在輸入盤資料取り寄せ中。4月の「映画のポケット」で紹介されることでしょう。
*成瀬巳喜男「流れる」(1956)
与太者がピストルを撃ったり、飛んだり跳ねたりするだけがアクション映画ではありません。人の出し入れとカッティングでアクションを作り出すことだって可能。
*小川紳介「ニッポン国古屋敷村」(1982)(未ソフト化)
映画とはつまり、なんだって載せられるバカでかい皿みたいなもので、しかしたいていのひとはその大きさに気付いてもいないか、気付いていても使い切れずにもてあましているのじゃあるまいか。怒涛の展開を見せるこの映画を見ると、そう思います。3月3日(火)、13日(金)にアテネフランセで上映あり。
*シルヴェスター・スタローン「ランボー 最後の戦場」(2008)
新しいものを何かひとつ、といってこれをあげたら笑われそうですが、知ったこっちゃない。東南アジアで蛇取りのバイトをしてるところとか、ラストが寅さんなところも泣けるのですが、中盤、逃げるランボーと追う敵をとらえたクロス・カッティングの愚直なまでの力強さに震える。
映画についていろいろ考えてみましたが、「映画には可能でTVにはできないこと」が本当に存在するのかどうか、断言できない気分になってきました。ですので本日は、ムリに「映画的」を定義づけしてそこに入らないものを排除することはせず、分からないものは分からないものとして、そのうえで、みなさんがいい気分になるような、問答無用の強度のある映像をいくつか提示してみます。
■ 鈴木の紹介作品
*清水宏「港の日本娘」(1933/日本/サイレント)
屋外のシーンのかなりの部分で、いい風が吹いています。風の表現はわりといつも気になるのですが、おそらくその理由は、人為的にコントロールできないものの代表のひとつとして、風を見ているからなのでしょう。ドラ役の井上雪子は1936年に引退、2004年、塩田明彦「カナリア」で68年ぶり(!)に銀幕復帰。
*マルレン・フツィエフ&フェリックス・ミロネル「河向こうの通りの春」(Весна на Заречной улице)(1956/ソ連)
工場訪問シーン。蒸気機関車の煙と工場の煙が盛大に風に流れる。工場内での光の差し込み方にも注目。映画業界関係者の方、どなたかフツィエフ特集をやってください。という意図でセレクト。
*グル・ダット「紙の花」(1959/インド)
インド版「サンセット大通り」的な一篇。主人公たちがドライヴしていると、男女が鈴なりになった車がそばにきて歌い出す。「君も出世ができる」の♪タークラマカーン♪くらい意味が分からない感動(ほめております)。
インド初のシネスコ作品であった本作(使用した資料はシネスコじゃなかった……)は興行的に失敗。結果的にダット最後の監督作品になった(役者としては活躍)。主演女優とは実際に不倫関係にあった、というのはまだ普通の話ですが、彼女の歌の吹き替えをしたのがプレイバック・シンガーだった監督の奥さんだというのがなんだかもう。
*サンチアゴ・アルバレス「ナウ!」(1965/キューバ)、「79歳の春」(1969/キューバ)
「編集の天才」と呼ばれたドキュメンタリスト、アルバレスは、「写真を2枚と編集機(ムビオラ)、そしてちょっと音楽をくれ。君に映画を作ってやろう」と豪語したひと。「ナウ!」を見ると、それがハッタリではないと分かります。彼のいう「緊急映画(cine urgente)」とはつまり、デスクトップ・ムーヴィー、ベッドルーム・ムーヴィーの元祖かも。「79歳の春」の戦闘シーンの編集も明らかにやりすぎで、意味が分からない(ほめております)。
■ 鈴木のその他の推薦作品
*井土紀州「レフト・アローン」(2004)(未ソフト化)
みんながしゃべってるだけ。それなのに「ラザロ」よりスリリングで面白い。
*青山真治「AA」(2005)(未ソフト化)
みんながしゃべってるだけ。それなのに「ユリイカ」より愛にあふれてて面白い。
*市川崑「東京オリンピック」(1965)
映画とはつまり編集(=時間をどう使うか)なのではないか。監督が撮影現場にいる必要すらない、ということは、獄中から演出したというユルマズ・ギュネイ「路」のエピソードでも分かる。
*ハワード・ホークス「ハタリ!」(1962)
猿をつかまえるのにロケットを使うバカバカしさよ。ホークスは男子心をそそります。「自分がその中に入って住んでみたくなるかどうか」は、わたしにとっていい映画のひとつの基準。ホークス、ジャン・ルノワール、マキノ、森崎東がその路線に分類されます。
*マルレン・フツィエフ「私は20歳」(1962)
自在に動くカメラがとらえると、モスクワは60年代きってのおしゃれ都市に見える。驚愕のヌーヴェル・ヴァーグ。現在輸入盤資料取り寄せ中。4月の「映画のポケット」で紹介されることでしょう。
*成瀬巳喜男「流れる」(1956)
与太者がピストルを撃ったり、飛んだり跳ねたりするだけがアクション映画ではありません。人の出し入れとカッティングでアクションを作り出すことだって可能。
*小川紳介「ニッポン国古屋敷村」(1982)(未ソフト化)
映画とはつまり、なんだって載せられるバカでかい皿みたいなもので、しかしたいていのひとはその大きさに気付いてもいないか、気付いていても使い切れずにもてあましているのじゃあるまいか。怒涛の展開を見せるこの映画を見ると、そう思います。3月3日(火)、13日(金)にアテネフランセで上映あり。
*シルヴェスター・スタローン「ランボー 最後の戦場」(2008)
新しいものを何かひとつ、といってこれをあげたら笑われそうですが、知ったこっちゃない。東南アジアで蛇取りのバイトをしてるところとか、ラストが寅さんなところも泣けるのですが、中盤、逃げるランボーと追う敵をとらえたクロス・カッティングの愚直なまでの力強さに震える。
以下、なんきんさんのレジュメです。レジュメの記載と当日の実際の紹介順は、微妙に異なっています。
−−−
映画のポケットVOL17 「映画的とは何か!?」レジュメ 南木顕生
映画の紹介でストーリーしか語ってない文をよく見ると思います。でも、ストーリーというのは小説でも漫画でも語ることのできるもので、別にことさら映画だけのものではありません。では、役者の芝居というのはどうでしょう。それもその本当のよしあしは演劇のほうが雄弁に伝わると思います。なるほどクローズアップやリアクションカットが入ることでソレはかなり恣意的に伝えることが出来るかもしれません。でもそれはテレビドラマで十分語れますよね。むしろテレビドラマのほうが雄弁に語れるでしょう。
じゃぁ映画って何!? 映画本来の面白さはどこにあるのでしょうか?
また「映画的」って表現よく眼にしますよね。何をもって映画的なんでしょうか?
大きなスクリーンでしか表現できないものだけが「映画的」なのでしょうか?
今の多くの人は昔の映画はテレビモニターやPCの液晶画面でしか体験できないでしょう。それは映画の作り手の当初の想いからズレてしまってるわけで映画はスクリーンでしか真価を発揮しないと思ってるわけですが、それをとやかくいいますまい。小さなモニターでも感じられる「映画」の粋というのもあるのです。
今回の「映画のポケット」では、様々な映画ならではの「表現」を考察することで映画ならではの映画的表現を探ってゆきたいと思います。
■ その? 映画はスペクタクルだ!
とはいってもあくまで参考にスペクタクル場面を見せて「わかりやすい映画的なるモノ」を参考上映します。
☆参考作品1 「アラビアのロレンス」(62)アメリカ=イギリス
監督デビッド・リーン 脚本ロバート・ボルト 撮影フレディ・ヤング
ピーター・オトゥール、アレック・ギネス、アンソニー・クィーン
映画はスペクタクルでこそその真価を発揮する。これは文学や漫画では絶対不可能。また、テレビではこの物量展開は不可能であり、映画ならではの興奮に酔って頂きたい。
チョイスする場面は「アカバ攻略」シーン。紅海に面した交易の拠点であるアカバは支配するオスマントルコ軍によって難攻不落の要塞都市だった。紅海に向けていくつもの砲門が向けられていて海からは近づけない。そこでロレンスたちは背後からアカバを突くことを計画する。そこに至るまでの大冒険は大胆にカットして、アカバを襲撃するスペクタクルシーンをチョイス。ひたすら美しい紅海に向けて虚しくそびえる砲門が「これぞ映画!」
☆参考作品2 「会議は踊る」(31)ドイツ
監督エリック・シャレル 脚本ノルベルト・ファルク 撮影カール・ホフマン
リリアン・ハーヴェイ、ヴィリー・フリッチ
ウィーン会議のさなか、手袋屋の娘クリステルがロシア皇帝の別荘に招かれるシーン。名曲「ただ一度だけ」を歌いながら馬車に乗るクリステル、周囲のエキストラも祝うように唄う後世のハリウッドミュージカルにも影響を与えた名シーン。移動撮影の素晴らしさと音楽の楽しさはまさにスペクタクル。ああ「これぞ映画!」
☆参考作品3 「オペラは踊る」(35)アメリカ
監督サム・ウッド 脚本ジョージ・カウフマン
グルーチョ・マルクス、ハーポ・マルクス、チコ・マルクス
「〜踊る」つながりで超絶コメディを!映画的スペクタクルを笑いに転化するとこうなります。身体を張ったハーポ・マルクスに感動!多くのコメディアンがサイレント出身であるなか音楽としゃべくりで出てきたマルクス兄弟はまさにトーキー映画が生んだスターかもしれない。クライマックスのドタバタは「これぞ映画!」
−−−
映画のポケットVOL17 「映画的とは何か!?」レジュメ 南木顕生
映画の紹介でストーリーしか語ってない文をよく見ると思います。でも、ストーリーというのは小説でも漫画でも語ることのできるもので、別にことさら映画だけのものではありません。では、役者の芝居というのはどうでしょう。それもその本当のよしあしは演劇のほうが雄弁に伝わると思います。なるほどクローズアップやリアクションカットが入ることでソレはかなり恣意的に伝えることが出来るかもしれません。でもそれはテレビドラマで十分語れますよね。むしろテレビドラマのほうが雄弁に語れるでしょう。
じゃぁ映画って何!? 映画本来の面白さはどこにあるのでしょうか?
また「映画的」って表現よく眼にしますよね。何をもって映画的なんでしょうか?
大きなスクリーンでしか表現できないものだけが「映画的」なのでしょうか?
今の多くの人は昔の映画はテレビモニターやPCの液晶画面でしか体験できないでしょう。それは映画の作り手の当初の想いからズレてしまってるわけで映画はスクリーンでしか真価を発揮しないと思ってるわけですが、それをとやかくいいますまい。小さなモニターでも感じられる「映画」の粋というのもあるのです。
今回の「映画のポケット」では、様々な映画ならではの「表現」を考察することで映画ならではの映画的表現を探ってゆきたいと思います。
■ その? 映画はスペクタクルだ!
とはいってもあくまで参考にスペクタクル場面を見せて「わかりやすい映画的なるモノ」を参考上映します。
☆参考作品1 「アラビアのロレンス」(62)アメリカ=イギリス
監督デビッド・リーン 脚本ロバート・ボルト 撮影フレディ・ヤング
ピーター・オトゥール、アレック・ギネス、アンソニー・クィーン
映画はスペクタクルでこそその真価を発揮する。これは文学や漫画では絶対不可能。また、テレビではこの物量展開は不可能であり、映画ならではの興奮に酔って頂きたい。
チョイスする場面は「アカバ攻略」シーン。紅海に面した交易の拠点であるアカバは支配するオスマントルコ軍によって難攻不落の要塞都市だった。紅海に向けていくつもの砲門が向けられていて海からは近づけない。そこでロレンスたちは背後からアカバを突くことを計画する。そこに至るまでの大冒険は大胆にカットして、アカバを襲撃するスペクタクルシーンをチョイス。ひたすら美しい紅海に向けて虚しくそびえる砲門が「これぞ映画!」
☆参考作品2 「会議は踊る」(31)ドイツ
監督エリック・シャレル 脚本ノルベルト・ファルク 撮影カール・ホフマン
リリアン・ハーヴェイ、ヴィリー・フリッチ
ウィーン会議のさなか、手袋屋の娘クリステルがロシア皇帝の別荘に招かれるシーン。名曲「ただ一度だけ」を歌いながら馬車に乗るクリステル、周囲のエキストラも祝うように唄う後世のハリウッドミュージカルにも影響を与えた名シーン。移動撮影の素晴らしさと音楽の楽しさはまさにスペクタクル。ああ「これぞ映画!」
☆参考作品3 「オペラは踊る」(35)アメリカ
監督サム・ウッド 脚本ジョージ・カウフマン
グルーチョ・マルクス、ハーポ・マルクス、チコ・マルクス
「〜踊る」つながりで超絶コメディを!映画的スペクタクルを笑いに転化するとこうなります。身体を張ったハーポ・マルクスに感動!多くのコメディアンがサイレント出身であるなか音楽としゃべくりで出てきたマルクス兄弟はまさにトーキー映画が生んだスターかもしれない。クライマックスのドタバタは「これぞ映画!」
■ その? 映画はデタラメだ!
仮にコメディでなくても映画はデタラメがゆるされるメディアである。
それは映画がリアリズムを基調とした大いなるウソの世界だからである。
コミックのような極端なデフォルメがないぶん映画ならではの誇張はシュールでもあり、それがまさに「これぞ映画」なのだ!
☆参考作品4 「野獣の青春」(63)日活
監督 鈴木清順 脚本 池田一朗、山崎忠昭 撮影 永塚一栄 美術 横尾嘉良
宍戸錠、川地民夫、渡辺美佐子、金子信雄、小林昭二、信欣三、江角英明
これは一見するとハードボイルドかもしれないが、微妙な誇張と絶妙な省略が随所に散りばめられシュールでもリアルでもない独自の世界が展開されてゆく。すべての人物たちがクスリともせず相当ヘンなことをやっているのがとにかく素晴らしい映画の中の映画。
今回は「仮面ライダー」のおやっさん、「ウルトラマン」の村松キャップでお馴染みの小林昭二に注目してみたい。間違いなく彼の代表作だろう。あと信欣三の『特攻野郎』ぶりにも注目だ!これぞ映画!
☆参考作品5 「コンドル」(39)アメリカ
監督ハワード・ホークス 脚本ジュールス・ファースマン 撮影ジョセフ・ウォーカー
ケーリー・グラント、ジーン・アーサー、リタ・ヘイワース、リチャード・バーセルメス
これは飛行機乗りの男たちを描いた名作で、飛行シーンの素晴らしさも映画的と讃えたいのだが、ここでは同僚が事故で死んだ後、「日常にもどることが彼に対する供養だ」とばかり始まる大宴会に注目したい。恐らく彼らは仕事が終わると宴会だったのだろう。監督すら同僚が死んだことを忘れてるかのすさまじいデタラメぶりは感動的ですらある。こういうシチュエーションを日本映画の場合これでもかと哀しみを誘うのだがそんな愚はいっさいなく、ひたすら酔って騒ぐ。ホークスの映画では何人ものスタッフが現場で命を落としたと聞くがその都度こんな宴会が行われ「日常に戻った」のかもしれない。ああ、これぞ映画!
■ その? 映画でしかできない表現とは何か!?
映画には映画ならではの文学的、詩的表現というのがある。文字に書いて表現してもそれがなかなか伝わらない映像表現について考えてみたい。
☆参考作品6 「青春残酷物語」(60)松竹
監督脚本 大島渚 撮影 川又昴
桑野みゆき、川津祐介、久我美子、渡辺文雄、佐藤慶、浜村純
「戦場のメリークリスマス」でのたけし軍曹のアップのストップモーションで終わるラスト、「儀式」で河原崎健三の投げたボールを受ける少年時代の彼らにつながるカット、近くは「御法度」における桜の枝斬りとか、大島渚ほど映画ならではの「詩的表現」にこだわり続けた作家はいないだろう。今回はその原点ともいうべく「青春残酷物語」の有名な『林檎丸齧り』シーンを。
■ ここで「映画にしかできない表現」というテーマの一貫として、鈴木並木さんの一連のオススメ作品を紹介していただきます。(参考作品6〜10)
☆詳細は鈴木のレジュメをご覧ください。
仮にコメディでなくても映画はデタラメがゆるされるメディアである。
それは映画がリアリズムを基調とした大いなるウソの世界だからである。
コミックのような極端なデフォルメがないぶん映画ならではの誇張はシュールでもあり、それがまさに「これぞ映画」なのだ!
☆参考作品4 「野獣の青春」(63)日活
監督 鈴木清順 脚本 池田一朗、山崎忠昭 撮影 永塚一栄 美術 横尾嘉良
宍戸錠、川地民夫、渡辺美佐子、金子信雄、小林昭二、信欣三、江角英明
これは一見するとハードボイルドかもしれないが、微妙な誇張と絶妙な省略が随所に散りばめられシュールでもリアルでもない独自の世界が展開されてゆく。すべての人物たちがクスリともせず相当ヘンなことをやっているのがとにかく素晴らしい映画の中の映画。
今回は「仮面ライダー」のおやっさん、「ウルトラマン」の村松キャップでお馴染みの小林昭二に注目してみたい。間違いなく彼の代表作だろう。あと信欣三の『特攻野郎』ぶりにも注目だ!これぞ映画!
☆参考作品5 「コンドル」(39)アメリカ
監督ハワード・ホークス 脚本ジュールス・ファースマン 撮影ジョセフ・ウォーカー
ケーリー・グラント、ジーン・アーサー、リタ・ヘイワース、リチャード・バーセルメス
これは飛行機乗りの男たちを描いた名作で、飛行シーンの素晴らしさも映画的と讃えたいのだが、ここでは同僚が事故で死んだ後、「日常にもどることが彼に対する供養だ」とばかり始まる大宴会に注目したい。恐らく彼らは仕事が終わると宴会だったのだろう。監督すら同僚が死んだことを忘れてるかのすさまじいデタラメぶりは感動的ですらある。こういうシチュエーションを日本映画の場合これでもかと哀しみを誘うのだがそんな愚はいっさいなく、ひたすら酔って騒ぐ。ホークスの映画では何人ものスタッフが現場で命を落としたと聞くがその都度こんな宴会が行われ「日常に戻った」のかもしれない。ああ、これぞ映画!
■ その? 映画でしかできない表現とは何か!?
映画には映画ならではの文学的、詩的表現というのがある。文字に書いて表現してもそれがなかなか伝わらない映像表現について考えてみたい。
☆参考作品6 「青春残酷物語」(60)松竹
監督脚本 大島渚 撮影 川又昴
桑野みゆき、川津祐介、久我美子、渡辺文雄、佐藤慶、浜村純
「戦場のメリークリスマス」でのたけし軍曹のアップのストップモーションで終わるラスト、「儀式」で河原崎健三の投げたボールを受ける少年時代の彼らにつながるカット、近くは「御法度」における桜の枝斬りとか、大島渚ほど映画ならではの「詩的表現」にこだわり続けた作家はいないだろう。今回はその原点ともいうべく「青春残酷物語」の有名な『林檎丸齧り』シーンを。
■ ここで「映画にしかできない表現」というテーマの一貫として、鈴木並木さんの一連のオススメ作品を紹介していただきます。(参考作品6〜10)
☆詳細は鈴木のレジュメをご覧ください。
■ その? 映画的なるモノは空気に宿る
ドキュメンタリーのような臨場感こそが「映画」なのではないだろうか。リアルに世界を作りこんで空気を切り取るように撮ってゆく。最後にそのように作った二つの映画のラストシーンを見せて締めたいと思います。
☆参考作品11 「悪魔のいけにえ」(74)アメリカ
監督トビー・フーパー 脚本キム・ヒンケル、トビー・フーパー
実在の猟奇殺人事件をモデルにしたスラッシャー映画であるが、この映画が極めてユニークなのは多くのホラー映画が被害者側の視点で描かれるのが、いつの間にか加害者側に作り手たちの想いが移ってしまっているところ。この主客の逆転こそが映画的だと思う。
ラストシーン、なんとかあの『家』から脱出したヒロインで映画は終わらない。明らかに作り手たちは獲物に逃げられて悔しがるレザーフェイスに感情移入している。しかも、結末は感動的なまで「ほったらかし」なのだ。結論なんかなくてもいい。これぞ映画!
☆参考作品12 「ナッシュビル」(76)アメリカ
監督ロバート・アルトマン 脚本ジョーン・テューケスベリー
ヘンリー・ギブスン、カレン・ブラック、リリー・トムリン、ネッド・ビーティ、グエン・ウエルズ、キース・キャラダイン、バーバラ・ハリス、ロニー・ブレイクリー、ジェラルディ・チャップリン、シェリー・デュバル…etc
わが生涯のベストワン映画です。総勢24人の登場人物の日常だけをなんの説明もなく切り取ってつないでいるのだが、彼らひとりひとりの背景やドラマが断片から見えてきて、圧巻のラストシーンになだれこんでゆく。ほぼ即興とアドリブだけで作られたというこの映画にはストーリーなんかなくてもドラマが作れるのだと教えてくれる。これぞ映画、これこそ映画、映画バンザイ!
■ 結論
私にとって、映画とはけっして物語ではないということだ。理に落ちてしまえば言葉にできてしまう。理に落ちない、説明の出来ない感動の正体こそ「映画的」ではないだろうか?と思うわけです。
ドキュメンタリーのような臨場感こそが「映画」なのではないだろうか。リアルに世界を作りこんで空気を切り取るように撮ってゆく。最後にそのように作った二つの映画のラストシーンを見せて締めたいと思います。
☆参考作品11 「悪魔のいけにえ」(74)アメリカ
監督トビー・フーパー 脚本キム・ヒンケル、トビー・フーパー
実在の猟奇殺人事件をモデルにしたスラッシャー映画であるが、この映画が極めてユニークなのは多くのホラー映画が被害者側の視点で描かれるのが、いつの間にか加害者側に作り手たちの想いが移ってしまっているところ。この主客の逆転こそが映画的だと思う。
ラストシーン、なんとかあの『家』から脱出したヒロインで映画は終わらない。明らかに作り手たちは獲物に逃げられて悔しがるレザーフェイスに感情移入している。しかも、結末は感動的なまで「ほったらかし」なのだ。結論なんかなくてもいい。これぞ映画!
☆参考作品12 「ナッシュビル」(76)アメリカ
監督ロバート・アルトマン 脚本ジョーン・テューケスベリー
ヘンリー・ギブスン、カレン・ブラック、リリー・トムリン、ネッド・ビーティ、グエン・ウエルズ、キース・キャラダイン、バーバラ・ハリス、ロニー・ブレイクリー、ジェラルディ・チャップリン、シェリー・デュバル…etc
わが生涯のベストワン映画です。総勢24人の登場人物の日常だけをなんの説明もなく切り取ってつないでいるのだが、彼らひとりひとりの背景やドラマが断片から見えてきて、圧巻のラストシーンになだれこんでゆく。ほぼ即興とアドリブだけで作られたというこの映画にはストーリーなんかなくてもドラマが作れるのだと教えてくれる。これぞ映画、これこそ映画、映画バンザイ!
■ 結論
私にとって、映画とはけっして物語ではないということだ。理に落ちてしまえば言葉にできてしまう。理に落ちない、説明の出来ない感動の正体こそ「映画的」ではないだろうか?と思うわけです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
映画のポケット 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
映画のポケットのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- パニック障害とうつ病
- 8447人
- 2位
- 一行で笑わせろ!
- 82528人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208286人