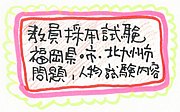2008年実施 福岡県・福岡市・北九州市 教員採用試験 1次試験
教職教養、一般教養
問18 次の各文は,福岡県が策定した「福岡県人権教育・啓発基本指針」(平成15年6月)の一部を抜粋したものである。文中の( ア )〜( オ )に当てはまる語句の正しい組合せを,下の1〜5の中から一つ選びなさい。
人権尊重の精神を育成していくためには,「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏まえて,一人一人の人権を尊重した教育活動を展開することが重要です。
特に,自他の人権を大切にするための知識や態度,実践力を育成するという観点から,( ア )を培うとともに,子どもの抱える心の問題を解決し安心して楽しく学ぶことのできる学校づくりを推進します。
学校教育における取組が有効に機能するためには,教職員が人権の理念に対する認識と人権感覚を高める必要があることから,子どもへの愛情や教育への使命感,( イ )を高めるための研修の充実を図ります。
人権問題に対する感性や( ウ )が態度や行動に現れる人権感覚を育むために,人権教育を促進するための資料や冊子等の内容を充実させるとともに,視聴覚教材等の有効活用を図ります。
近年の高度情報化社会を背景として,インターネットの( エ )を悪用し,インターネット上の電子掲示板やホームページに人権を侵害する情報の書き込みが増加しています。
・・・ 中略 ・・・
また,携帯電話のメール等を使った誹謗中傷等による人権侵害も発生しており,情報の収集・発信における個人の責任や( オ )についての理解を促進させるための教育・啓発に努めます。
ア イ ウ エ オ
1.規範意識 実践的な指導力 良心 匿名性 情報公開
2.公共心 責任感 良心 公共性 情報モラル
3.規範意識 責任感 人権への配慮 公共性 情報モラル
4.規範意識 実践的な指導力 人権への配慮 匿名性 情報モラル
5.公共心 実践的な指導力 良心 匿名性 情報公開
問19 次の各文は,「人権教育の指導方法等の在り方について[第二次とりまとめ]](平成18年1月 人権教育の指導方法等に関する調査研究会議)の一部を抜粋したものである。文中の( ア )〜( オ )に当てはまる語句を語群a〜kから選んだとき,その正しい組合せを,下の1〜5の中から一つ選びなさい。
人権教育は,学校教育において,各教科,道徳,特別活動,総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ,( ア )を通じて推進されるものである。
学校教育において人権教育を進めるに当たっては,人権についての知的理解を深化し,徹底させると共に,児童生徒が( イ )を十分に身に付けるための指導を一層充実することが必要である。
各学校においては,校長のリーダーシップの下,教職員が一体となって人権教育に取り組む体制を整え,人権教育の( ウ ),指導計画の作成や教材の選定・開発などの取組を組織的・継続的に行うことが肝要である。
人権教育が育成を目指す価値や態度には,個人の尊厳をけじめ,自他の人権を尊重することの意義や必要性に対する肯定的な評価と受容,責任感や共感性・連帯性,人権擁護の実現を目指す( エ )などが含まれる。
教職員による厳しさと優しさを兼ね備えた生徒指導と,児童生徒の主体的な学級参加によって,人権の尊重される学校教育を維持するための( オ )に取り組まなければならない。
≪語群≫
a理念の整理 b意欲や態度
c協調性 d国際感覚
e目標設定 fルールの確立
g教育活動全体 h実践力
i一年間 j人権感覚
k環境整備
ア イウ エ オ
1.i c a h f
2.g j e b k
3.g j e h f
4.i d a h f
5.g c e b k
問20 次の(1)〜(5)の各文は,「いじめを早期に発見し,適切に対応できる体制づくり・・・ぬくもりのある学校・地域社会をめざして・・・子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議まとめ(第1次)」(平成19年2月)の一部を抜粋したものである。文中の( ア )〜( オ )にあてはまる語句を語群a〜mから選んだとき,その正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
(1) 教師は,日頃から子ども同士の関係や動向を注意深く見守り,子どものわずかな( ア )にも気を止め声をかけることを心がけ,得られた情報は学校内で共有することが大切である。
(2) 教師は,いじめられている子どもに対して,絶対に見捨てないというメッセージを送ることが大切である。そのため,毎日の( イ )の実施,緊急連絡先の伝達,避難場所の確保,警察や福祉関係機関との連携などあらゆる観点からの支援が大切である。
(3) いじめの事実確認については,複数の教師がチームを組み,同時に複数者から聞き取りを行い,( ウ )のリーダーシップのもと,教育委員会と連携を取りつつ迅速に初期対応の措置を検討する必要がある。
(4) 教師は,クラスや部活動等の( エ )を子どもに任せ,責任感,自他の葛藤の解消方法,感情や行動を制御する方法等を学ばせることが大切である。
(5) 教師は,被害者及び加害者以外の子どもに対し,( オ )と自主自律の意識を高めなければならない。このため,再発防止のために何をすべきか,どのような行動をとり,気をつけるべきことは何か等について,反省と振り返りの機会を設ける必要がある。
≪語群≫
a行動 b校長
cサイン dルールづくり
e声かけ f学級担任
g仲間意識 h変化
i運営 j面談
k規範意識 l健康観察
m当事者意識
アイウエオ
1.c e b i k
2.c l f d g
3.h e b i m
4.h j b d m
5.a j f i k
※ 以下は、試験区分(小・中・養護)で問題が異なります。
小学校教員・中学校教員・養護教員志願者は、問21〜問25を解答しなさい。
高等学校教員志願者は、問26〜問30を解答しなさい。
なお、中高併顕者は、第1希望校種の問題を解答しなさい。
〔小学校教員・中学校教員・養護教員〕
問21 次の文は,新しい小学校及び中学校学習指導要領「第3章 道徳」「第3 指導計画の作成と内容の取扱い」の一部を抜粋したものである。( ア )〜( オ )に当てはまる語句を語群a〜oから選んだとき,その正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
道徳教育を進めるに当たっては,学校や学級内の( ア )を整えるとともに,学校の道徳教育の指導内容が児童(生徒)の( イ )に生かされるようにする必要がある。また,道徳の時間の( ウ ),授業の実施や( エ )の開発や活用などに,保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりするなど,家庭や地域社会との共通理解を深め,( オ )を図るよう配慮する必要がある。
≪語群≫
a教材研究をしたり b学習環境
c道徳教育の充実 d日常生活
e行動 f生き方
g授業を公開したり h人間関係や環境
i雰囲気 j道徳性の育成
k地域人材 l教具
m相互の連携 n地域教材
o内容分析をしたり
アイウエ オ
1.b e o k c
2.b f a l m
3.h f o n j
4.i e g k c
5.h d g n m
問22 次の文は,新しい小学校学習指導要領「第5章 総合的な学習の時間」,及び新しい中学校学習指導要領「第4章 統合的な学習の時間」に示されている「第1 目標」である。文中の( ア )〜( エ )に当てはまる語句を,語群a〜lから選んだときその正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
第1 目 標
横断的・総合的な学習や( ア )な学習を通して,自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する( イ )を育成するとともに,学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的,( ウ )に取り組む態度を育て,( エ )を考えることができるようにする。
≪語群≫
a態度 b 問題解決的
c 自己の生き方 d 計画的
e資質や能力 f 総合的
g 全科的 h 自分自身や社会
i自分の将来 j 探究的
k 協同的 l 知識や技能
アイ ウエ
1.b e k h
2.j e k c
3.g l d h
4.b a d c
5.j a f i
問23 次の各文は,新しい小学校学習指導要領「第6章 特別活動」及び新しい中学校学習指導要領「第5章 特別活動」に示されている「第2 各活動・学校行事の目標及び内容」の学級活動と学校行事の目標について述べたものである。文中の( ア )〜( オ )に当てはまる語句を語群a〜oから選んだとき,その正しい組合せを下の1〜5から一つ選びなさい。
〈学級活動〉
学級活動を通して,望ましい( ア )を形成し,集団の一員として学級や学校におけるよりよい生活づくりに( イ )し,諸問題を解決しようとする自主的,( ウ )な態度や( エ )生活態度を育てる。
〈学校行事〉
学校行事を通して,望ましい( ア )を形成し,集団への所属感や( オ )を深め,公共の精神を養い,協力してよりよい学校生活を築こうとする自主的,( ウ )な態度を育てる。
≪語群≫
a 健康的な b 参加
c 人間関係 d 学級集団
e 自治的 f 参画
g 文化的 h 信頼関係
i 満足感 j 寄与
k 実践的 l 連帯感
m 健全な n 明るい
o 達成感
ア イ ウ エ オ
1.h b e n o
2.c j k m o
3.h f e a l
4.c f k m l
5.d j g a i
問24 次のア〜オの各文は,「不登校への対応の在り方について(通知)」(平成15年5月文部科学省)において,不登校に対する基本的な考え方について述べられているものである。内容として誤っているものを,下の1〜5から一つ選びなさい。
ア 義務教育段階の学校は,自ら学び自ら考える力なども含めた「確かな学力」や基本的な生活習慣,規範意識,集団における社会性等,社会の構成員として必要な資質や能力等をそれぞれの発達段階に応じて育成する機能と責務を有しており,関係者はすべての児童生徒が学校に楽しく通うことができるよう,学校教育の一層の充実のための取組を展開していくことがまずもって重要であること。
イ 学校,家庭,地域が連携協力し,不登校の児童生徒がどのような状態にあり,どのような支援を必要としているのか正しく見極め(「アセスメント」)を行い,適切な機関による支援と多様な学習の機会を児童生徒に提供することが重要であること。その際には,公的機関のみならず,民間施設やNPO等と積極的に連携し,相互に協力・補完し合うことの意義が大きいこと。
ウ 不登校の解決の目標は,児童生徒の将来的な自立に向けて支援することであること。したがって,不登校を「心の問題」としてのみとらえるのではなく,「学力の問題」としてとらえ,本人の学力形成に資するような指導・援助や学習支援等の対応をする必要があること。
エ 児童生徒の立ち直る力を信じることは重要であるが,児童生徒の状況を理解しようとすることもなく,あるいは必要としている支援を行おうとすることもなく,ただ待つだけでは,状況の改善にならないという認識が必要であること。
オ 保護者を支援し不登校となった子どもへの対応に関してその保護者が役割を適切に果たせるよう,時機を失することなく児童生徒本人のみならず家庭への適切な働きかけや支援を行うなど,学校と家庭,関係機関の連携を図ることが不可欠であること。
1. ア 2. イ 3. ウ 4. エ 5. オ
問25 次の(1)〜(5)の各文は,義務教育として行われる普通教育が達成すべきものとして学校 教育法第21条に掲げられた目標の一部である。文中の( )部について正しいものを○,誤っているものを×としたとき,その正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
(1) 学校内外における(自然観察学習)を促進し,生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
(2) 家族と家庭の役割,生活に必要な(衣,食,住,情報,産業)その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
(3) 読書に親しませ,(生活に必要な伝達方法)を正しく理解し,使用する基礎的な能力を養うこと。
(4) (健康,安全で豊かな生活)のために必要な習慣を養うとともに,運動を通じて体力を養い,心身の調和的発達を図ること。
(5) 職業についての基礎的な知識と技能,(勤労を重んずる態度)及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
(1) (2) (3)(4)(5)
1. ○ ○ × ○ ×
2. × ○ × × ○
3. ○ × × ○ ○
4. × ○ ○ ○ ×
5. × × ○ × ○
〔高等学校教員〕
問26 次の文は,現行の高等学校学習指導要領「第1章 総則」「第1款 教育課程編成の一般方針」の一部を抜粋したものである。文中の( ア )〜( オ )にあてはまる語句の正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
道徳教育を進めるに当たっては,特に,道徳的( ア )を高めるとともに,( イ )の精神や( ウ )の精神及び( エ )を果たし( オ )を重んずる態度や人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。
ア イ ウ エ オ
1.行動力 社会奉仕 自立 責任 義務
2.行動力 自律 社会連帯 義務 責任
3.実践力 自立 社会連帯 義務 責任
4.実践力 社会連帯 自律 責任 義務
5.実践力 人間尊重 社会奉仕 責任 義務
問27 次の(1)〜(2)の各文は,現行の高等学校学習指導要領「第1章 総則」「第6款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項」の5の内容の一部を述べたものである。( ア )〜( オ )に当てはまる語句の正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
(1) 学校生活全体を通じて,言語に関する( ア )を深め,言語環境を整え,生徒の( イ )が適正に行われるようにすること。
(2) 学校の教育活動全体を通じて,個々の生徒の( ウ )等の的確な把握に努め,その伸長を図ること。また,生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活によりよく適応するとともに,現在及び将来の生き方を考え行動する( エ )を育成することができるよう,( オ )の機能の充実を図ること。
ア イ ウ エ オ
1.関心や理解 言語活動 個性 計画性 キャリア教育
2.態度や能力 言語活動 特性 計画性 キャリア教育
3.態度や能力 興味や関心 固性 計画性 ガイダンス
4.関心や理解 言語活動 特性 態度や能力 ガイダンス
5.関心や理解 興味や関心 特性 態度や能力 ガイダンス
問28 次の文は,キャリア教育について述べたものである。文中の( ア )〜( ウ )に当てはまる語句の正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
学校の教育活動全体を通してキャリア教育を推進するためには,校長がキャリア教育の意義を十分に認識し,キャリア教育を( ア )の中核に据えることが考えられる。各学校においては,校内の関係する分掌すべてを有機的にかかわらせながら,学校全体でキャリア教育を推進する「キャリア教育推進委員会」などの組織を設けることが有効と考えられる。また,キャリア教育が学校内にとどまらず,家庭や地域との連携・協力を必要とする教育活動であることからも、学校の代表者としでの校長の姿勢は,それらの( イ )関係を深め,よりよい成果を生み出す上でも重要である。
キャリア教育の推進には,全ての教員が,キャリア教育のベースになる児童生徒のキャリア発達や児童生徒を取り巻く社会環境の変化,さらに学校の教育活動全体を通して進められるキャリア教育の在り方などについて,十分な理解を深めることが重要となる。そして,それらを前提として,教員一人一人の資質の向上が,様々な面で求められる。
例えば,一人一人の児童生徒のキャリア発達を促すキャリア教育においては,児童生徒の個々を理解し,その変容を的確にとらえて発達を支援する「キャリア・カウンセリング」や,校外での様々な体験活動場面で,家庭,地域,企業,関係機関・団体の関係者と円滑に連携を進める際にも不可欠な( ウ )能力の向上などがすべての教員に求められる。さらに,キャリア教育の指導者的な立場の教員には,他に必要な能力として,「プログラム開発・運営・評価能力」,「調整能力(コーディネーション能力)」,「指導・助言能力(インストラクション・コンサルテーション能力)」等が考えられる。
ア イ ウ
1.学校経営計画 共同・協力 コミュニケーション
2.学校経営計画 共同・協力 プログラミング
3.学校経営計画 連携・協力 コミュニケーション
4.就業体験計画 連携・協力 コミュニケーション
5.職場体験計画 連携・協力 プログラミング
問29 次の文は,学習指導要領における進路指導の位置づけについて述べたものである。文中の( ア )〜( オ )に当てはまる語句の正しい組合せを下の1〜5から一つ選びなさい。
高等学校においては,進路指導は一個の独立した領域として教育課程に位置づけられている。学習指導要領では,「総則」において,「生徒が自己の( ア )を考え,主体的に進路を選択することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,計画的,組織的な進路指導を行うこと。」,また,「学校においては,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し( イ )の機会の確保に配慮するものとする。」,「現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう,ガイダンスの機能の充実を図ること。」とされている。
「( ウ )」のねらいの一つにも「(2)学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に( エ )に取り組む態度を育て,自己の在り方生き方を考えることができるようにすること。」が設けられている。さらに,学習活動例として,「イ 生徒が興味・関心,( オ )等に応じて設定した課題について,知識や技能の深化,総合化を図る学習活動」「ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動」が示されている。
ア イ ウ エ オ
1.在り方生き方 就業体験 統合的な学習の時間 積極的,計画的 意欲
2.進路適性 体験活動 総合的な学習の時間 積極的,計画的 進路
3.在り方生き方 就業体験 統合的な学習の時間 主体的,創造的 進路
4.進路適性 体験活動 道徳教育 積極的,計画的 意欲
5.在り方生き方 体験活動 道徳教育 主体的,創造的 進路
問30 次の文は,中央教育審議会答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について〜知の循環型社会の構築を目指して〜」(平成20年2月)の一部である。文中の( ア )〜( オ )に当てはまる語句の正しい組合せを下の1〜5から一つ選びなさい。
今後我が国においては,「( ア )」や「社会の要請」に応じて,国民が必要とする力を身に付けるために必要な( イ )が提供され,人々の学習が円滑に行われることが必要である。その際には,( ウ )の理念の下,国民一人一人が生涯にわたって( エ )に多様な選択を行いながら人生を設計していくことができるよう,いつでも「( オ )」や新たな学びへの挑戦,さらにはそれらにより得られた学習成果を生かすことが可能な環境整備を行うことが重要である。
ア イ ウ エ オ
1.生きる力 学習機会 生涯学習 自主的 学び直し
2.個人の要望 学習機会 豊かな人生 主体的 支え合い
3.生きる力 情 報 豊かな人生 自主的 学び直し
4.個人の要望 学習機会 生涯学習 主体的 学び直し
5.生きる力 情 報 豊かな人生 自主的 支え合い
■2008年実施 1次教職教養+一般教養 解答(official) に続く
http://
教職教養、一般教養
問18 次の各文は,福岡県が策定した「福岡県人権教育・啓発基本指針」(平成15年6月)の一部を抜粋したものである。文中の( ア )〜( オ )に当てはまる語句の正しい組合せを,下の1〜5の中から一つ選びなさい。
人権尊重の精神を育成していくためには,「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏まえて,一人一人の人権を尊重した教育活動を展開することが重要です。
特に,自他の人権を大切にするための知識や態度,実践力を育成するという観点から,( ア )を培うとともに,子どもの抱える心の問題を解決し安心して楽しく学ぶことのできる学校づくりを推進します。
学校教育における取組が有効に機能するためには,教職員が人権の理念に対する認識と人権感覚を高める必要があることから,子どもへの愛情や教育への使命感,( イ )を高めるための研修の充実を図ります。
人権問題に対する感性や( ウ )が態度や行動に現れる人権感覚を育むために,人権教育を促進するための資料や冊子等の内容を充実させるとともに,視聴覚教材等の有効活用を図ります。
近年の高度情報化社会を背景として,インターネットの( エ )を悪用し,インターネット上の電子掲示板やホームページに人権を侵害する情報の書き込みが増加しています。
・・・ 中略 ・・・
また,携帯電話のメール等を使った誹謗中傷等による人権侵害も発生しており,情報の収集・発信における個人の責任や( オ )についての理解を促進させるための教育・啓発に努めます。
ア イ ウ エ オ
1.規範意識 実践的な指導力 良心 匿名性 情報公開
2.公共心 責任感 良心 公共性 情報モラル
3.規範意識 責任感 人権への配慮 公共性 情報モラル
4.規範意識 実践的な指導力 人権への配慮 匿名性 情報モラル
5.公共心 実践的な指導力 良心 匿名性 情報公開
問19 次の各文は,「人権教育の指導方法等の在り方について[第二次とりまとめ]](平成18年1月 人権教育の指導方法等に関する調査研究会議)の一部を抜粋したものである。文中の( ア )〜( オ )に当てはまる語句を語群a〜kから選んだとき,その正しい組合せを,下の1〜5の中から一つ選びなさい。
人権教育は,学校教育において,各教科,道徳,特別活動,総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ,( ア )を通じて推進されるものである。
学校教育において人権教育を進めるに当たっては,人権についての知的理解を深化し,徹底させると共に,児童生徒が( イ )を十分に身に付けるための指導を一層充実することが必要である。
各学校においては,校長のリーダーシップの下,教職員が一体となって人権教育に取り組む体制を整え,人権教育の( ウ ),指導計画の作成や教材の選定・開発などの取組を組織的・継続的に行うことが肝要である。
人権教育が育成を目指す価値や態度には,個人の尊厳をけじめ,自他の人権を尊重することの意義や必要性に対する肯定的な評価と受容,責任感や共感性・連帯性,人権擁護の実現を目指す( エ )などが含まれる。
教職員による厳しさと優しさを兼ね備えた生徒指導と,児童生徒の主体的な学級参加によって,人権の尊重される学校教育を維持するための( オ )に取り組まなければならない。
≪語群≫
a理念の整理 b意欲や態度
c協調性 d国際感覚
e目標設定 fルールの確立
g教育活動全体 h実践力
i一年間 j人権感覚
k環境整備
ア イウ エ オ
1.i c a h f
2.g j e b k
3.g j e h f
4.i d a h f
5.g c e b k
問20 次の(1)〜(5)の各文は,「いじめを早期に発見し,適切に対応できる体制づくり・・・ぬくもりのある学校・地域社会をめざして・・・子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議まとめ(第1次)」(平成19年2月)の一部を抜粋したものである。文中の( ア )〜( オ )にあてはまる語句を語群a〜mから選んだとき,その正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
(1) 教師は,日頃から子ども同士の関係や動向を注意深く見守り,子どものわずかな( ア )にも気を止め声をかけることを心がけ,得られた情報は学校内で共有することが大切である。
(2) 教師は,いじめられている子どもに対して,絶対に見捨てないというメッセージを送ることが大切である。そのため,毎日の( イ )の実施,緊急連絡先の伝達,避難場所の確保,警察や福祉関係機関との連携などあらゆる観点からの支援が大切である。
(3) いじめの事実確認については,複数の教師がチームを組み,同時に複数者から聞き取りを行い,( ウ )のリーダーシップのもと,教育委員会と連携を取りつつ迅速に初期対応の措置を検討する必要がある。
(4) 教師は,クラスや部活動等の( エ )を子どもに任せ,責任感,自他の葛藤の解消方法,感情や行動を制御する方法等を学ばせることが大切である。
(5) 教師は,被害者及び加害者以外の子どもに対し,( オ )と自主自律の意識を高めなければならない。このため,再発防止のために何をすべきか,どのような行動をとり,気をつけるべきことは何か等について,反省と振り返りの機会を設ける必要がある。
≪語群≫
a行動 b校長
cサイン dルールづくり
e声かけ f学級担任
g仲間意識 h変化
i運営 j面談
k規範意識 l健康観察
m当事者意識
アイウエオ
1.c e b i k
2.c l f d g
3.h e b i m
4.h j b d m
5.a j f i k
※ 以下は、試験区分(小・中・養護)で問題が異なります。
小学校教員・中学校教員・養護教員志願者は、問21〜問25を解答しなさい。
高等学校教員志願者は、問26〜問30を解答しなさい。
なお、中高併顕者は、第1希望校種の問題を解答しなさい。
〔小学校教員・中学校教員・養護教員〕
問21 次の文は,新しい小学校及び中学校学習指導要領「第3章 道徳」「第3 指導計画の作成と内容の取扱い」の一部を抜粋したものである。( ア )〜( オ )に当てはまる語句を語群a〜oから選んだとき,その正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
道徳教育を進めるに当たっては,学校や学級内の( ア )を整えるとともに,学校の道徳教育の指導内容が児童(生徒)の( イ )に生かされるようにする必要がある。また,道徳の時間の( ウ ),授業の実施や( エ )の開発や活用などに,保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりするなど,家庭や地域社会との共通理解を深め,( オ )を図るよう配慮する必要がある。
≪語群≫
a教材研究をしたり b学習環境
c道徳教育の充実 d日常生活
e行動 f生き方
g授業を公開したり h人間関係や環境
i雰囲気 j道徳性の育成
k地域人材 l教具
m相互の連携 n地域教材
o内容分析をしたり
アイウエ オ
1.b e o k c
2.b f a l m
3.h f o n j
4.i e g k c
5.h d g n m
問22 次の文は,新しい小学校学習指導要領「第5章 総合的な学習の時間」,及び新しい中学校学習指導要領「第4章 統合的な学習の時間」に示されている「第1 目標」である。文中の( ア )〜( エ )に当てはまる語句を,語群a〜lから選んだときその正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
第1 目 標
横断的・総合的な学習や( ア )な学習を通して,自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する( イ )を育成するとともに,学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的,( ウ )に取り組む態度を育て,( エ )を考えることができるようにする。
≪語群≫
a態度 b 問題解決的
c 自己の生き方 d 計画的
e資質や能力 f 総合的
g 全科的 h 自分自身や社会
i自分の将来 j 探究的
k 協同的 l 知識や技能
アイ ウエ
1.b e k h
2.j e k c
3.g l d h
4.b a d c
5.j a f i
問23 次の各文は,新しい小学校学習指導要領「第6章 特別活動」及び新しい中学校学習指導要領「第5章 特別活動」に示されている「第2 各活動・学校行事の目標及び内容」の学級活動と学校行事の目標について述べたものである。文中の( ア )〜( オ )に当てはまる語句を語群a〜oから選んだとき,その正しい組合せを下の1〜5から一つ選びなさい。
〈学級活動〉
学級活動を通して,望ましい( ア )を形成し,集団の一員として学級や学校におけるよりよい生活づくりに( イ )し,諸問題を解決しようとする自主的,( ウ )な態度や( エ )生活態度を育てる。
〈学校行事〉
学校行事を通して,望ましい( ア )を形成し,集団への所属感や( オ )を深め,公共の精神を養い,協力してよりよい学校生活を築こうとする自主的,( ウ )な態度を育てる。
≪語群≫
a 健康的な b 参加
c 人間関係 d 学級集団
e 自治的 f 参画
g 文化的 h 信頼関係
i 満足感 j 寄与
k 実践的 l 連帯感
m 健全な n 明るい
o 達成感
ア イ ウ エ オ
1.h b e n o
2.c j k m o
3.h f e a l
4.c f k m l
5.d j g a i
問24 次のア〜オの各文は,「不登校への対応の在り方について(通知)」(平成15年5月文部科学省)において,不登校に対する基本的な考え方について述べられているものである。内容として誤っているものを,下の1〜5から一つ選びなさい。
ア 義務教育段階の学校は,自ら学び自ら考える力なども含めた「確かな学力」や基本的な生活習慣,規範意識,集団における社会性等,社会の構成員として必要な資質や能力等をそれぞれの発達段階に応じて育成する機能と責務を有しており,関係者はすべての児童生徒が学校に楽しく通うことができるよう,学校教育の一層の充実のための取組を展開していくことがまずもって重要であること。
イ 学校,家庭,地域が連携協力し,不登校の児童生徒がどのような状態にあり,どのような支援を必要としているのか正しく見極め(「アセスメント」)を行い,適切な機関による支援と多様な学習の機会を児童生徒に提供することが重要であること。その際には,公的機関のみならず,民間施設やNPO等と積極的に連携し,相互に協力・補完し合うことの意義が大きいこと。
ウ 不登校の解決の目標は,児童生徒の将来的な自立に向けて支援することであること。したがって,不登校を「心の問題」としてのみとらえるのではなく,「学力の問題」としてとらえ,本人の学力形成に資するような指導・援助や学習支援等の対応をする必要があること。
エ 児童生徒の立ち直る力を信じることは重要であるが,児童生徒の状況を理解しようとすることもなく,あるいは必要としている支援を行おうとすることもなく,ただ待つだけでは,状況の改善にならないという認識が必要であること。
オ 保護者を支援し不登校となった子どもへの対応に関してその保護者が役割を適切に果たせるよう,時機を失することなく児童生徒本人のみならず家庭への適切な働きかけや支援を行うなど,学校と家庭,関係機関の連携を図ることが不可欠であること。
1. ア 2. イ 3. ウ 4. エ 5. オ
問25 次の(1)〜(5)の各文は,義務教育として行われる普通教育が達成すべきものとして学校 教育法第21条に掲げられた目標の一部である。文中の( )部について正しいものを○,誤っているものを×としたとき,その正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
(1) 学校内外における(自然観察学習)を促進し,生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
(2) 家族と家庭の役割,生活に必要な(衣,食,住,情報,産業)その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
(3) 読書に親しませ,(生活に必要な伝達方法)を正しく理解し,使用する基礎的な能力を養うこと。
(4) (健康,安全で豊かな生活)のために必要な習慣を養うとともに,運動を通じて体力を養い,心身の調和的発達を図ること。
(5) 職業についての基礎的な知識と技能,(勤労を重んずる態度)及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
(1) (2) (3)(4)(5)
1. ○ ○ × ○ ×
2. × ○ × × ○
3. ○ × × ○ ○
4. × ○ ○ ○ ×
5. × × ○ × ○
〔高等学校教員〕
問26 次の文は,現行の高等学校学習指導要領「第1章 総則」「第1款 教育課程編成の一般方針」の一部を抜粋したものである。文中の( ア )〜( オ )にあてはまる語句の正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
道徳教育を進めるに当たっては,特に,道徳的( ア )を高めるとともに,( イ )の精神や( ウ )の精神及び( エ )を果たし( オ )を重んずる態度や人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。
ア イ ウ エ オ
1.行動力 社会奉仕 自立 責任 義務
2.行動力 自律 社会連帯 義務 責任
3.実践力 自立 社会連帯 義務 責任
4.実践力 社会連帯 自律 責任 義務
5.実践力 人間尊重 社会奉仕 責任 義務
問27 次の(1)〜(2)の各文は,現行の高等学校学習指導要領「第1章 総則」「第6款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項」の5の内容の一部を述べたものである。( ア )〜( オ )に当てはまる語句の正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
(1) 学校生活全体を通じて,言語に関する( ア )を深め,言語環境を整え,生徒の( イ )が適正に行われるようにすること。
(2) 学校の教育活動全体を通じて,個々の生徒の( ウ )等の的確な把握に努め,その伸長を図ること。また,生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活によりよく適応するとともに,現在及び将来の生き方を考え行動する( エ )を育成することができるよう,( オ )の機能の充実を図ること。
ア イ ウ エ オ
1.関心や理解 言語活動 個性 計画性 キャリア教育
2.態度や能力 言語活動 特性 計画性 キャリア教育
3.態度や能力 興味や関心 固性 計画性 ガイダンス
4.関心や理解 言語活動 特性 態度や能力 ガイダンス
5.関心や理解 興味や関心 特性 態度や能力 ガイダンス
問28 次の文は,キャリア教育について述べたものである。文中の( ア )〜( ウ )に当てはまる語句の正しい組合せを,下の1〜5から一つ選びなさい。
学校の教育活動全体を通してキャリア教育を推進するためには,校長がキャリア教育の意義を十分に認識し,キャリア教育を( ア )の中核に据えることが考えられる。各学校においては,校内の関係する分掌すべてを有機的にかかわらせながら,学校全体でキャリア教育を推進する「キャリア教育推進委員会」などの組織を設けることが有効と考えられる。また,キャリア教育が学校内にとどまらず,家庭や地域との連携・協力を必要とする教育活動であることからも、学校の代表者としでの校長の姿勢は,それらの( イ )関係を深め,よりよい成果を生み出す上でも重要である。
キャリア教育の推進には,全ての教員が,キャリア教育のベースになる児童生徒のキャリア発達や児童生徒を取り巻く社会環境の変化,さらに学校の教育活動全体を通して進められるキャリア教育の在り方などについて,十分な理解を深めることが重要となる。そして,それらを前提として,教員一人一人の資質の向上が,様々な面で求められる。
例えば,一人一人の児童生徒のキャリア発達を促すキャリア教育においては,児童生徒の個々を理解し,その変容を的確にとらえて発達を支援する「キャリア・カウンセリング」や,校外での様々な体験活動場面で,家庭,地域,企業,関係機関・団体の関係者と円滑に連携を進める際にも不可欠な( ウ )能力の向上などがすべての教員に求められる。さらに,キャリア教育の指導者的な立場の教員には,他に必要な能力として,「プログラム開発・運営・評価能力」,「調整能力(コーディネーション能力)」,「指導・助言能力(インストラクション・コンサルテーション能力)」等が考えられる。
ア イ ウ
1.学校経営計画 共同・協力 コミュニケーション
2.学校経営計画 共同・協力 プログラミング
3.学校経営計画 連携・協力 コミュニケーション
4.就業体験計画 連携・協力 コミュニケーション
5.職場体験計画 連携・協力 プログラミング
問29 次の文は,学習指導要領における進路指導の位置づけについて述べたものである。文中の( ア )〜( オ )に当てはまる語句の正しい組合せを下の1〜5から一つ選びなさい。
高等学校においては,進路指導は一個の独立した領域として教育課程に位置づけられている。学習指導要領では,「総則」において,「生徒が自己の( ア )を考え,主体的に進路を選択することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,計画的,組織的な進路指導を行うこと。」,また,「学校においては,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し( イ )の機会の確保に配慮するものとする。」,「現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう,ガイダンスの機能の充実を図ること。」とされている。
「( ウ )」のねらいの一つにも「(2)学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に( エ )に取り組む態度を育て,自己の在り方生き方を考えることができるようにすること。」が設けられている。さらに,学習活動例として,「イ 生徒が興味・関心,( オ )等に応じて設定した課題について,知識や技能の深化,総合化を図る学習活動」「ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動」が示されている。
ア イ ウ エ オ
1.在り方生き方 就業体験 統合的な学習の時間 積極的,計画的 意欲
2.進路適性 体験活動 総合的な学習の時間 積極的,計画的 進路
3.在り方生き方 就業体験 統合的な学習の時間 主体的,創造的 進路
4.進路適性 体験活動 道徳教育 積極的,計画的 意欲
5.在り方生き方 体験活動 道徳教育 主体的,創造的 進路
問30 次の文は,中央教育審議会答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について〜知の循環型社会の構築を目指して〜」(平成20年2月)の一部である。文中の( ア )〜( オ )に当てはまる語句の正しい組合せを下の1〜5から一つ選びなさい。
今後我が国においては,「( ア )」や「社会の要請」に応じて,国民が必要とする力を身に付けるために必要な( イ )が提供され,人々の学習が円滑に行われることが必要である。その際には,( ウ )の理念の下,国民一人一人が生涯にわたって( エ )に多様な選択を行いながら人生を設計していくことができるよう,いつでも「( オ )」や新たな学びへの挑戦,さらにはそれらにより得られた学習成果を生かすことが可能な環境整備を行うことが重要である。
ア イ ウ エ オ
1.生きる力 学習機会 生涯学習 自主的 学び直し
2.個人の要望 学習機会 豊かな人生 主体的 支え合い
3.生きる力 情 報 豊かな人生 自主的 学び直し
4.個人の要望 学習機会 生涯学習 主体的 学び直し
5.生きる力 情 報 豊かな人生 自主的 支え合い
■2008年実施 1次教職教養+一般教養 解答(official) に続く
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
教員採用試験ver福岡県内 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
教員採用試験ver福岡県内のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75496人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196032人
- 3位
- 独り言
- 9045人