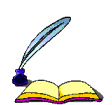◆政府紙幣の発行論議とは?
コロンビア大学のスティグリッツ教授(2001年のノーベル経済学賞受賞者)が4月16日の関税・外国為替等審議会で、「日本の政府はデフレ克服策として紙幣を増刷すべき」と提唱し、物議を醸しました。スティグリッツ教授は、デフレ経済ではインフレ経済とは異なり、発想の転換が必要と強調し、政府が日銀とは別に紙幣を発行し、それで歳出の一部を賄えば、国債を発行せずに財政を賄えて資金供給量を増やせると説明しています。財政規律の喪失の危険性については、世界的に中央銀行の独立性があれば経済が回復するとの証拠はなく、政府紙幣の発行量に制約を設ければ、財政規律を守ることができると指摘しています。
日本のデフレの一因に、日銀の通貨政策の間違いが指摘されます。過去にインフレ対策しか経験せず、責任の追及を恐れる財務省や日銀の官僚には、柔軟な思考を求めることができず、デフレ経済下に適切な対応策がとれないでいるとの指摘です。
スティグリッツ教授に限らず、民間にも経済活性化への柔軟な(通貨の)発想があります。2002年7月23日に千葉商科大学の加藤寛学長が、民主党の田中慶秋衆議院議員に述べたアイディアが有名ですが、その論旨は以下です。
〜〜〜
地方銀行が発行元になって、日銀と同じように自分の銀行の担保をつけて地域通貨を発行する。それを県が保証する。県は土木事業を行っていい。どんな国でも公共事業をゼロにして生存できる国はない。道路だって修理しなければ穴ぼこだらけになる。必要なものは造りましょうと言わないといけない。しかし、カネがない。それなら、そのエコノミカルマネー(経済通貨)を使えばいい。地域で消費経済ができる。賃金ももらえる。そして生活も安定する。
しかし、これは給料の一部でやる。例えば10万円の給料なら2万円をエコ通貨でやる。あとの8万円は普通の通貨で、と言うことだ。2割くらいなら、その地域で使うのはあたりまえだ。こうなると、このカネが流通し始める。2万円のエコ通貨を普通通貨に替えたいと思ったら商品交換所で交換する。今でも新幹線の切符などを割引で売っている。ここで普通通貨(現金)に替える。
この仕組みができているのに、日本ではこの仕組みを使わずにいる。そして、日銀通貨だけが唯一だと思っている。日銀通貨がこんなに使えない通貨だということがわかっていない。これでは日本経済がよくなるわけはない。
地域通貨と呼ぶか第2の通貨と呼ぶか分からないが、1国に2つの制度があれば1国2通貨があるのはあたりまえと、今、ユーロでは考えている。ユーロ圏は世界のドルに対するユーロ通貨を作りたかった。第2の通貨制度をつくった。これを日本もつくるべきだ。そのカネで日本経済は活力をもつ。経済がよくなれば、当然私たちの経済もよくなる。日本が債務国家なら問題だが、債権国家だから何の心配もいらない。日本経済は強くなり、世界から尊敬されるようになる。こうなれば、日本のランキングは韓国の下だ、などと言われることがなくなる。
政府紙幣でデフレを克服せよとの説がある。初代の大蔵大臣、由利公正がこれを成功させた。これは藩札を消し、政府紙幣に統括するために政府が行ったもので、これには西郷隆盛もビックリした。藩札が担保となっている。
〜〜〜
さて、スティグリッツ教授の言う「政府貨幣・政府紙幣」とは何でしょうか? 政府貨幣も国家の信用で発行する貨幣ですが、その材質は政令で定めます。ですから、ペーパー(紙)でも金属でも何でもよい訳です。今、政府貨幣として流通しているものに100円や500円等の6種類の(金属製の)コインがあります。こうしたコイン貨幣は独立行政法人造幣局で鋳造され、流通しています。よく知っている1万円や5000円等の日銀券は、独立行政法人国立印刷局が製造していますが、この日銀券は「日銀」という法人が発行するものです。
現在においても、このように規模はとても小さいながら、「政府貨幣(コイン)」は立派に流通しています。高額な「政府貨幣としての紙幣」はまだ世の中に出てはいませんが、現行法において、高額な政府紙幣を発行することは可能です。
日銀の発行する「日銀券」は、(日銀のB/S上)債務勘定に計上される性格のもので、不換紙幣として金(gold)の裏付けを持たないものです。つまり、日銀の信用(=国の信用)を頼りに流通しています。
政府貨幣も政府の信用(=国の信用)をバックに発行されるものですが、(日銀券とは異なり)発行元の政府の債務には計上されません。100円のコイン貨幣を例にすると、100円の額面から製造にかかる経費(10円と仮定)を引いた差額(90円)が政府(=国)の収入(=貨幣鋳造益)となるのです。
スティグリッツ教授は、政府貨幣としての政府紙幣の発行を大胆に行い、その「紙幣造幣益」をもって、減税や公共投資等の財政政策を展開すべきと提唱しています。つまり、インフレ経済とは異なるデフレ経済の日本では、(債務を計上する性格の)日銀券とは異なり、政府(国)の債務が増えない政府紙幣を発行して、その紙幣造幣益を各種政策発動に利用した方が良いと言っています。さらに、デフレが深刻な日本においては、相当の額の政府紙幣が発行できると考えられる点で利点があり、問題の財政規律を守る観点からは、政府紙幣の発行量に制約を設けれよく、また発行により物価の上昇率が想定値を越えるなら、その発行を抑制すれば良いのです。
日本のマネーサプライ(MS)の伸び低さは日本経済の血液としてのマネーの流通に問題があることを示しています。巨額のマネーサプライが存在するのに、マネーが企業や個人の手元に届いていません。銀行の不良債権がそのMSの伸びの低さの原因の一つですが、不良債権処理を急げば更にデフレを強める結果となります。日本経済のマイナス成長を避けるためには、政府が財政政策を行う他はないのですが、財源が国債の発行では国の財政をより悪化させることになります。誰も考えつかなかった政府紙幣の発行という政策により財源を得て財政政策を行い、MSを増やすという策も、これから時代にあっては課題となりそうです。
◆政府紙幣が無視し続けられる理由
>これだけ好都合な打ち出の小槌がなぜ無視され続けるのか。あまりにも虫が良す
>ぎるからだ。Too good to be trueというわけだ。だが冷静に経済の論理を追っ
>て行くと、戦争や破壊に頼らず赤字財政にも頼らない有効需要の生み方はこれし
>かないと分かる。政府紙幣と日銀券は等価交換が担保シートの借方に政府紙幣
>が来て、同額が貸方に日銀券発行額が来る事になる。こうして見ると日銀に国債
>直接引受けさせているのと原理的にはさほど異ならない行為だと
>いうのが見えてくる。しかし、市場性のある国債と政府紙幣は一方でやはり性格
>の異なるものである。早くこの政策を取れば取るほど、政府紙幣の投入額は小さ
>くて済むであろう。
「政府紙幣が無視し続けられる理由」は、“あまりにも虫が良すぎるから”ではない。
「政府紙幣」が、経済支配層の経済利益を脅かすものだからである。
この理解ができなければ、近代経済システムを理解することもできないだろう。
農業を含むあらゆる経済活動が、通貨をより多く稼ぐことを目的とするようになったのが近代経済システムである。
そのような経済システムを構築したのは、金融家である。
金融家は、中央銀行制度を確立することで、経済社会を貨幣経済化し、日々の経済活動が自分たちの利益に直結するようにしたのである。
貨幣流通が中央銀行の貸し出しから始まるのが近代経済の特質である。
イングランド銀行の創設まで遡らなくとも、米国で1913年に成立した連邦準備法(私的中央銀行制度の確立)をめぐるどろどろした謀略を顧みれば、その経済的権益の大きさがわかるし、それへの執着度合いもわかる。
(リンカーン大統領の暗殺も“中央銀行制度”問題が絡んでいると言われている)
“あまりにも虫が良すぎる”政府紙幣をほいほい発行されることになってしまったら、世界経済を支配している国際金融家の厖大な権益が失われることになる。
国際金融家にとっては、国民生活がどうなるかはどうでもいいことで、国民経済がどうなるかも利潤が最大化できるかどうかが判断基準である。
銀行制度を通じた全般的な「信用創造」が最大の経済権益だが、世界的なデフレ不況のなかで、厖大な保有通貨の運用先は先進諸国の国債に傾斜していくと予測している。
「政府紙幣」は、国債の発行をなくしてしまうものである。
「政府紙幣」は、世界経済支配層にとって、「近代経済システム」を根底からひっくり返してしまう“害毒”なのである。
貸し出しを通じて供給されない通貨を経済支配層が認めるというのは、私の「利潤なき経済社会」を経済支配層が認めるに近いものなのである。
日本が「政府紙幣」を発行して巧く経済を立て直せば、経済苦境に陥っている先進諸国国民がこぞって「政府紙幣」を求めるようになる。
だから、世界経済支配層は、日本政府のそのような暴挙を許す“愚”を犯しはしない。
また、米国政権からの「不良債権処理加速化」要請に抗することもできない日本政府が、そのような背景を持つ「政府紙幣」発行に踏み切ると考えるのはナイーブすぎる判断だろう。
と言うことで、政府紙幣がいくら有益であっても、実行は難しいでしょう。今の日本の状況で、政府がアメリカ≒国際金融家の意向を無視することはできませんから。
私が民間の発意として自治体が信用を裏付ける地域通貨の発行を提案するのは、そのためです。
このような地域通貨を、主体をはっきりさせないまま、同時多発的に発行すれば、多少なりともアメリカ≒国際金融家からのプレッシャーを受けにくくなるのではなかろうかと…。攻撃目標を不明瞭にして、なんとか誤魔化せないものかというトリッキーな戦略なのです。(^^;)
日本人が知らない 恐るべき真実 2003年9月14日 日曜日
http://
コロンビア大学のスティグリッツ教授(2001年のノーベル経済学賞受賞者)が4月16日の関税・外国為替等審議会で、「日本の政府はデフレ克服策として紙幣を増刷すべき」と提唱し、物議を醸しました。スティグリッツ教授は、デフレ経済ではインフレ経済とは異なり、発想の転換が必要と強調し、政府が日銀とは別に紙幣を発行し、それで歳出の一部を賄えば、国債を発行せずに財政を賄えて資金供給量を増やせると説明しています。財政規律の喪失の危険性については、世界的に中央銀行の独立性があれば経済が回復するとの証拠はなく、政府紙幣の発行量に制約を設ければ、財政規律を守ることができると指摘しています。
日本のデフレの一因に、日銀の通貨政策の間違いが指摘されます。過去にインフレ対策しか経験せず、責任の追及を恐れる財務省や日銀の官僚には、柔軟な思考を求めることができず、デフレ経済下に適切な対応策がとれないでいるとの指摘です。
スティグリッツ教授に限らず、民間にも経済活性化への柔軟な(通貨の)発想があります。2002年7月23日に千葉商科大学の加藤寛学長が、民主党の田中慶秋衆議院議員に述べたアイディアが有名ですが、その論旨は以下です。
〜〜〜
地方銀行が発行元になって、日銀と同じように自分の銀行の担保をつけて地域通貨を発行する。それを県が保証する。県は土木事業を行っていい。どんな国でも公共事業をゼロにして生存できる国はない。道路だって修理しなければ穴ぼこだらけになる。必要なものは造りましょうと言わないといけない。しかし、カネがない。それなら、そのエコノミカルマネー(経済通貨)を使えばいい。地域で消費経済ができる。賃金ももらえる。そして生活も安定する。
しかし、これは給料の一部でやる。例えば10万円の給料なら2万円をエコ通貨でやる。あとの8万円は普通の通貨で、と言うことだ。2割くらいなら、その地域で使うのはあたりまえだ。こうなると、このカネが流通し始める。2万円のエコ通貨を普通通貨に替えたいと思ったら商品交換所で交換する。今でも新幹線の切符などを割引で売っている。ここで普通通貨(現金)に替える。
この仕組みができているのに、日本ではこの仕組みを使わずにいる。そして、日銀通貨だけが唯一だと思っている。日銀通貨がこんなに使えない通貨だということがわかっていない。これでは日本経済がよくなるわけはない。
地域通貨と呼ぶか第2の通貨と呼ぶか分からないが、1国に2つの制度があれば1国2通貨があるのはあたりまえと、今、ユーロでは考えている。ユーロ圏は世界のドルに対するユーロ通貨を作りたかった。第2の通貨制度をつくった。これを日本もつくるべきだ。そのカネで日本経済は活力をもつ。経済がよくなれば、当然私たちの経済もよくなる。日本が債務国家なら問題だが、債権国家だから何の心配もいらない。日本経済は強くなり、世界から尊敬されるようになる。こうなれば、日本のランキングは韓国の下だ、などと言われることがなくなる。
政府紙幣でデフレを克服せよとの説がある。初代の大蔵大臣、由利公正がこれを成功させた。これは藩札を消し、政府紙幣に統括するために政府が行ったもので、これには西郷隆盛もビックリした。藩札が担保となっている。
〜〜〜
さて、スティグリッツ教授の言う「政府貨幣・政府紙幣」とは何でしょうか? 政府貨幣も国家の信用で発行する貨幣ですが、その材質は政令で定めます。ですから、ペーパー(紙)でも金属でも何でもよい訳です。今、政府貨幣として流通しているものに100円や500円等の6種類の(金属製の)コインがあります。こうしたコイン貨幣は独立行政法人造幣局で鋳造され、流通しています。よく知っている1万円や5000円等の日銀券は、独立行政法人国立印刷局が製造していますが、この日銀券は「日銀」という法人が発行するものです。
現在においても、このように規模はとても小さいながら、「政府貨幣(コイン)」は立派に流通しています。高額な「政府貨幣としての紙幣」はまだ世の中に出てはいませんが、現行法において、高額な政府紙幣を発行することは可能です。
日銀の発行する「日銀券」は、(日銀のB/S上)債務勘定に計上される性格のもので、不換紙幣として金(gold)の裏付けを持たないものです。つまり、日銀の信用(=国の信用)を頼りに流通しています。
政府貨幣も政府の信用(=国の信用)をバックに発行されるものですが、(日銀券とは異なり)発行元の政府の債務には計上されません。100円のコイン貨幣を例にすると、100円の額面から製造にかかる経費(10円と仮定)を引いた差額(90円)が政府(=国)の収入(=貨幣鋳造益)となるのです。
スティグリッツ教授は、政府貨幣としての政府紙幣の発行を大胆に行い、その「紙幣造幣益」をもって、減税や公共投資等の財政政策を展開すべきと提唱しています。つまり、インフレ経済とは異なるデフレ経済の日本では、(債務を計上する性格の)日銀券とは異なり、政府(国)の債務が増えない政府紙幣を発行して、その紙幣造幣益を各種政策発動に利用した方が良いと言っています。さらに、デフレが深刻な日本においては、相当の額の政府紙幣が発行できると考えられる点で利点があり、問題の財政規律を守る観点からは、政府紙幣の発行量に制約を設けれよく、また発行により物価の上昇率が想定値を越えるなら、その発行を抑制すれば良いのです。
日本のマネーサプライ(MS)の伸び低さは日本経済の血液としてのマネーの流通に問題があることを示しています。巨額のマネーサプライが存在するのに、マネーが企業や個人の手元に届いていません。銀行の不良債権がそのMSの伸びの低さの原因の一つですが、不良債権処理を急げば更にデフレを強める結果となります。日本経済のマイナス成長を避けるためには、政府が財政政策を行う他はないのですが、財源が国債の発行では国の財政をより悪化させることになります。誰も考えつかなかった政府紙幣の発行という政策により財源を得て財政政策を行い、MSを増やすという策も、これから時代にあっては課題となりそうです。
◆政府紙幣が無視し続けられる理由
>これだけ好都合な打ち出の小槌がなぜ無視され続けるのか。あまりにも虫が良す
>ぎるからだ。Too good to be trueというわけだ。だが冷静に経済の論理を追っ
>て行くと、戦争や破壊に頼らず赤字財政にも頼らない有効需要の生み方はこれし
>かないと分かる。政府紙幣と日銀券は等価交換が担保シートの借方に政府紙幣
>が来て、同額が貸方に日銀券発行額が来る事になる。こうして見ると日銀に国債
>直接引受けさせているのと原理的にはさほど異ならない行為だと
>いうのが見えてくる。しかし、市場性のある国債と政府紙幣は一方でやはり性格
>の異なるものである。早くこの政策を取れば取るほど、政府紙幣の投入額は小さ
>くて済むであろう。
「政府紙幣が無視し続けられる理由」は、“あまりにも虫が良すぎるから”ではない。
「政府紙幣」が、経済支配層の経済利益を脅かすものだからである。
この理解ができなければ、近代経済システムを理解することもできないだろう。
農業を含むあらゆる経済活動が、通貨をより多く稼ぐことを目的とするようになったのが近代経済システムである。
そのような経済システムを構築したのは、金融家である。
金融家は、中央銀行制度を確立することで、経済社会を貨幣経済化し、日々の経済活動が自分たちの利益に直結するようにしたのである。
貨幣流通が中央銀行の貸し出しから始まるのが近代経済の特質である。
イングランド銀行の創設まで遡らなくとも、米国で1913年に成立した連邦準備法(私的中央銀行制度の確立)をめぐるどろどろした謀略を顧みれば、その経済的権益の大きさがわかるし、それへの執着度合いもわかる。
(リンカーン大統領の暗殺も“中央銀行制度”問題が絡んでいると言われている)
“あまりにも虫が良すぎる”政府紙幣をほいほい発行されることになってしまったら、世界経済を支配している国際金融家の厖大な権益が失われることになる。
国際金融家にとっては、国民生活がどうなるかはどうでもいいことで、国民経済がどうなるかも利潤が最大化できるかどうかが判断基準である。
銀行制度を通じた全般的な「信用創造」が最大の経済権益だが、世界的なデフレ不況のなかで、厖大な保有通貨の運用先は先進諸国の国債に傾斜していくと予測している。
「政府紙幣」は、国債の発行をなくしてしまうものである。
「政府紙幣」は、世界経済支配層にとって、「近代経済システム」を根底からひっくり返してしまう“害毒”なのである。
貸し出しを通じて供給されない通貨を経済支配層が認めるというのは、私の「利潤なき経済社会」を経済支配層が認めるに近いものなのである。
日本が「政府紙幣」を発行して巧く経済を立て直せば、経済苦境に陥っている先進諸国国民がこぞって「政府紙幣」を求めるようになる。
だから、世界経済支配層は、日本政府のそのような暴挙を許す“愚”を犯しはしない。
また、米国政権からの「不良債権処理加速化」要請に抗することもできない日本政府が、そのような背景を持つ「政府紙幣」発行に踏み切ると考えるのはナイーブすぎる判断だろう。
と言うことで、政府紙幣がいくら有益であっても、実行は難しいでしょう。今の日本の状況で、政府がアメリカ≒国際金融家の意向を無視することはできませんから。
私が民間の発意として自治体が信用を裏付ける地域通貨の発行を提案するのは、そのためです。
このような地域通貨を、主体をはっきりさせないまま、同時多発的に発行すれば、多少なりともアメリカ≒国際金融家からのプレッシャーを受けにくくなるのではなかろうかと…。攻撃目標を不明瞭にして、なんとか誤魔化せないものかというトリッキーな戦略なのです。(^^;)
日本人が知らない 恐るべき真実 2003年9月14日 日曜日
http://
|
|
|
|
コメント(7)
政府自体が発行したわけではないですが
昨年、大阪府という「自治体」で面白い試みが行われました
これは1万円で11500円分の期限付き地域商品券を購入できるというものです
大阪まるごと大売り出しキャンペーン事業
http://www.pref.osaka.jp/yosan/cover/index.php?year=2009&acc=1&form=02&proc=2&ykst=2&bizcd=20092928&seq=1
http://www.pref.osaka.jp/attach/418/00031566/01shokorodo1%28osakaoouridashi%29.pdf
昨年、大阪府という「自治体」で面白い試みが行われました
これは1万円で11500円分の期限付き地域商品券を購入できるというものです
大阪まるごと大売り出しキャンペーン事業
http://www.pref.osaka.jp/yosan/cover/index.php?year=2009&acc=1&form=02&proc=2&ykst=2&bizcd=20092928&seq=1
http://www.pref.osaka.jp/attach/418/00031566/01shokorodo1%28osakaoouridashi%29.pdf
「カネがなければ刷りなさい」
−ケインズも説いた救国の超ウラ技 ケチな減税より国民ボーナスを!
「政府紙幣」を発行し、赤ん坊からお年寄りまで
国民全員に40万円の臨時ボーナスを支給せよ!
丹羽春喜大阪学院大学教授
昭和五年(一九三〇年)兵庫県生まれ。関西学院大学経済学部、
同大学院経済学研究科博士課程卒関西学院大学社会学部教授、
筑波大学社会科学系教授、京都産業大学経済学部教授を経て、
現在、大阪学院大学経済学部教授。経済学博士。日本学術会議第16期会員をも務めた。
著書に『社会主義のジレンマ』『ソ連軍事支出の推計』(「防衛図書出版奨励賞」受賞)
『ケインズ主義の復権』『日本経済再興の経済学』『日本経済繁栄の法則』ほか多数
http://homepage2.nifty.com/niwaharuki/siyokun1998-5.htm
政府貨幣発行で日本経済が蘇る
世界を代表する経済学者達の提言に耳を傾けよ
小野盛司
http://tek.jp/p/index2.html
−ケインズも説いた救国の超ウラ技 ケチな減税より国民ボーナスを!
「政府紙幣」を発行し、赤ん坊からお年寄りまで
国民全員に40万円の臨時ボーナスを支給せよ!
丹羽春喜大阪学院大学教授
昭和五年(一九三〇年)兵庫県生まれ。関西学院大学経済学部、
同大学院経済学研究科博士課程卒関西学院大学社会学部教授、
筑波大学社会科学系教授、京都産業大学経済学部教授を経て、
現在、大阪学院大学経済学部教授。経済学博士。日本学術会議第16期会員をも務めた。
著書に『社会主義のジレンマ』『ソ連軍事支出の推計』(「防衛図書出版奨励賞」受賞)
『ケインズ主義の復権』『日本経済再興の経済学』『日本経済繁栄の法則』ほか多数
http://homepage2.nifty.com/niwaharuki/siyokun1998-5.htm
政府貨幣発行で日本経済が蘇る
世界を代表する経済学者達の提言に耳を傾けよ
小野盛司
http://tek.jp/p/index2.html
ヴェルグルの労働証明書
ゲゼルの自由貨幣理論を実践し、大成功をおさめたのが、オーストリア・チロル地方のヴェルグルです。世界大恐慌の影響は、このヨーロッパの小さな田舎町にも波及していました。当時、人口わずか4300人のこの街には500人の失業者と1000人の失業予備軍がいました。通貨が貯め込まれ、循環が滞っていることが不景気の最大の問題だと考えた当時の町長、ミヒャエル・ウンターグッゲンベルガーは、自由貨幣の発行を実践してみることを決意し、1932年7月の町議会でスタンプ通貨の発行を決議しました。
ウンターグッゲンベルガー自身が地域の貯蓄銀行から32000オーストリア・シリングを借り入れ、それをそのまま預金として預け、それを担保として32000オーストリア・シリングに相当する「労働証明書」という地域通貨を発行しました。
この労働証明書は、1シリング、5シリング、10シリングの三種類からなり、裏面には「諸君、貯め込まれて循環しない貨幣は、世界を大きな危機、そして人類を貧困に陥れた。経済において恐ろしい世界の没落が始まっている。いまこそはっきりとした認識と敢然とした行動で経済機構の凋落を避けなければならない。そうすれば戦争や経済の荒廃を免れ、人類は救済されるだろう。人間は自分がつくりだした労働を交換することで生活している。緩慢にしか循環しないお金が、その労働の交換の大部分を妨げ、何万という労働しようとしている人々の経済生活の空間を失わせているのだ。労働の交換を高めて、そこから疎外された人々をもう一度呼び戻さなければならない。この目的のために、ヴェルグル町の『労働証明書』はつくられた。困窮を癒し、労働とパンを与えよ」と書いてありました。
そして、町が道路整備などの緊急失業者対策事業を起こし、失業者に職を与え、その労働の対価として「労働証明書」という紙幣を与えました。
労働証明書は、月初めにその額面の1%のスタンプ(印紙)を貼らないと使えない仕組みになっていました。つまり、言い換えれば月初めごとにその額面の価値の1%を失ってゆくのです。ですから手元にずっと持っていてもそれだけ損するため、誰もができるだけ早くこのお金を使おうとしました。この「老化するお金」が消費を促進することになり、経済を活性化させたのです。
ゲゼルの自由貨幣理論を実践し、大成功をおさめたのが、オーストリア・チロル地方のヴェルグルです。世界大恐慌の影響は、このヨーロッパの小さな田舎町にも波及していました。当時、人口わずか4300人のこの街には500人の失業者と1000人の失業予備軍がいました。通貨が貯め込まれ、循環が滞っていることが不景気の最大の問題だと考えた当時の町長、ミヒャエル・ウンターグッゲンベルガーは、自由貨幣の発行を実践してみることを決意し、1932年7月の町議会でスタンプ通貨の発行を決議しました。
ウンターグッゲンベルガー自身が地域の貯蓄銀行から32000オーストリア・シリングを借り入れ、それをそのまま預金として預け、それを担保として32000オーストリア・シリングに相当する「労働証明書」という地域通貨を発行しました。
この労働証明書は、1シリング、5シリング、10シリングの三種類からなり、裏面には「諸君、貯め込まれて循環しない貨幣は、世界を大きな危機、そして人類を貧困に陥れた。経済において恐ろしい世界の没落が始まっている。いまこそはっきりとした認識と敢然とした行動で経済機構の凋落を避けなければならない。そうすれば戦争や経済の荒廃を免れ、人類は救済されるだろう。人間は自分がつくりだした労働を交換することで生活している。緩慢にしか循環しないお金が、その労働の交換の大部分を妨げ、何万という労働しようとしている人々の経済生活の空間を失わせているのだ。労働の交換を高めて、そこから疎外された人々をもう一度呼び戻さなければならない。この目的のために、ヴェルグル町の『労働証明書』はつくられた。困窮を癒し、労働とパンを与えよ」と書いてありました。
そして、町が道路整備などの緊急失業者対策事業を起こし、失業者に職を与え、その労働の対価として「労働証明書」という紙幣を与えました。
労働証明書は、月初めにその額面の1%のスタンプ(印紙)を貼らないと使えない仕組みになっていました。つまり、言い換えれば月初めごとにその額面の価値の1%を失ってゆくのです。ですから手元にずっと持っていてもそれだけ損するため、誰もができるだけ早くこのお金を使おうとしました。この「老化するお金」が消費を促進することになり、経済を活性化させたのです。
当初発行した32000シリングに相当する「労働証明書」は、次第に必要以上に多いことがわかり、町に税金として戻ってきた時に、そのうちの3分の1だけが再発行されることになりました。「労働証明書」が流通していた13.5ヵ月の間に流通していた量は平均5490シリング相当に過ぎず、住民一人あたりでは、1.3シリング相当に過ぎません。しかしながら、この「労働証明書」は週平均8回も所有者を変えており、13.5ヵ月の間に平均464回循環し、254万7360シリングに相当する経済活動がおこなわれました。これは通常のオーストリア・シリングに比べて、およそ14倍の流通速度です。回転することで、お金は何倍もの経済効果を生み出すのです。
こうしてヴェルグルはオーストリア初の完全雇用を達成した町になりました。「労働証明書」は公務員の給与や銀行の支払いにも使われ、町中が整備され、上下水道も完備され、ほとんどの家が修繕され、町を取り巻く森も植樹され、税金もすみやかに支払われたのです。
ヴェルグルの成功を目の当たりにして多くの都市はこの制度を取り入れようとしました。1933年6月までに200以上の都市で導入が検討されたのです。しかし、オーストリアの中央銀行によって「国家の通貨システムを乱す」として禁止通達を出され、1933年11月に廃止に追い込まれました。
このようなスタンプ通貨の成功は、大恐慌後の不景気に喘ぐ米国でも非常に関心を持もたれました。全国的な通貨不足を補うために何千もの地域通貨が、あらゆる小さな村や町で発行されたのです。エール大学の教授、アーヴィング・フィッシャーは調査団をヴェルグルに送り、以来、アメリカの自治体にもこのシステムが次第に導入されていきました。そして、このスタンプ通貨を法案化する動きも出ました。
1933年2月18日に、アラバマ州の上院議員ジョン・バングヘッドが「緊急のときは連邦政府も代用貨幣の発行を認める」という法案を提出しました。また、同年2月22日にインディアナ州の下院議員ピーテンヒルも同様の法案を下院に提出。フィッシャーも時の財務省次官ディーン・アヒソンに行政からの支持をお願いしていました。しかし、判断に迷ったアヒソンはハーバード大学のラッセル・スプラーグ教授に見解を求め、スプラーグは「このスタンプ通貨は機能するだろうが、強力な分権的意思決定を前提にしている。大統領と協議すべき問題である」と進言しました。その後の3月4日、ルーズベルト大統領は、スタンプ通貨の使用および発行を禁止し、中央集権化されたニュー・ディール政策を実施。従来の小さな政府による自由放任経済から大きな政府による統制経済へ移行していきました。
http://d.hatena.ne.jp/rainbowring-abe/20050922
こうしてヴェルグルはオーストリア初の完全雇用を達成した町になりました。「労働証明書」は公務員の給与や銀行の支払いにも使われ、町中が整備され、上下水道も完備され、ほとんどの家が修繕され、町を取り巻く森も植樹され、税金もすみやかに支払われたのです。
ヴェルグルの成功を目の当たりにして多くの都市はこの制度を取り入れようとしました。1933年6月までに200以上の都市で導入が検討されたのです。しかし、オーストリアの中央銀行によって「国家の通貨システムを乱す」として禁止通達を出され、1933年11月に廃止に追い込まれました。
このようなスタンプ通貨の成功は、大恐慌後の不景気に喘ぐ米国でも非常に関心を持もたれました。全国的な通貨不足を補うために何千もの地域通貨が、あらゆる小さな村や町で発行されたのです。エール大学の教授、アーヴィング・フィッシャーは調査団をヴェルグルに送り、以来、アメリカの自治体にもこのシステムが次第に導入されていきました。そして、このスタンプ通貨を法案化する動きも出ました。
1933年2月18日に、アラバマ州の上院議員ジョン・バングヘッドが「緊急のときは連邦政府も代用貨幣の発行を認める」という法案を提出しました。また、同年2月22日にインディアナ州の下院議員ピーテンヒルも同様の法案を下院に提出。フィッシャーも時の財務省次官ディーン・アヒソンに行政からの支持をお願いしていました。しかし、判断に迷ったアヒソンはハーバード大学のラッセル・スプラーグ教授に見解を求め、スプラーグは「このスタンプ通貨は機能するだろうが、強力な分権的意思決定を前提にしている。大統領と協議すべき問題である」と進言しました。その後の3月4日、ルーズベルト大統領は、スタンプ通貨の使用および発行を禁止し、中央集権化されたニュー・ディール政策を実施。従来の小さな政府による自由放任経済から大きな政府による統制経済へ移行していきました。
http://d.hatena.ne.jp/rainbowring-abe/20050922
世界初!愛知県豊田市で誕生したコメ兌換通貨の凄味〜「腐るおカネ化」で流通の加速を目指す
通貨単位は”むすび”。1むすびはおにぎり1個分の玄米と交換できる。
愛知県豊田市でコメと交換できる地域通貨が誕生し、今年の5月1日から一部の地域で流通が始まった。その名も“おむすび通貨”だ。
発行元は弁理士で代表を務める吉田大氏や、大学准教授の村田尚生氏などが中心となって立ち上げた「物々交換局」という共同事業組合。吉田氏によれば、コメで価値が担保された地域通貨というのは世界で初めてだという。
通貨単位は“むすび”といい、1むすびは無農薬・有機栽培・天日乾燥の玄米0.5合(おにぎり1個分)と交換できる。この通貨を幅広く流通させることで、荒廃した農山村の振興を図ろうというのが目的だ。
さらに、コメとの交換以外でも、飲食店や雑貨屋など20店舗以上ある協力店舗で代金を支払う際にも利用できる。通常の通貨との交換レートが決まっていないため、販売者と消費者が商品やサービスの価値がいかほどなのか互いに決める形だ。
「価格の裏に隠れた本当のコストを、消費者が意識するきっかけになれば」と、吉田氏は話す。
だが、それだけではない。じつはこのおむすび通貨、これまでの通貨の概念自体を覆すことにもチャレンジしている。それは通貨の“腐るおカネ化” だ。普通のおカネならば、時間が経てば金利分だけ価値が増えるところを、逆に減価させようというのだ。
現在は作付けした年内の間にコメと交換しなければならないが、ゆくゆくは交換可能期間を延ばす予定だという。古米になれば価値が下がるので、それを価値の担保としているおむすび通貨も、自動的に減価するというわけだ。
そうすることで、価値が下がる前に早く使いたくなり、流通速度が上がる。どこか一部の人に留まることなく、社会を循環していくと考えているのだ。
これは「普通のおカネは利息の支払いと金利の受け取りが起こり、貧しい人から富める人のところにおカネが流れて滞留し、富の偏在を招く」(吉田氏)ことに対する挑戦でもある。
おむすび通貨が資金決済法の適用にあたるかどうか検討している東海財務局は、コメを担保にした通貨というのも、腐るおカネというのも「今まで見たことがない」(担当者)と語る。
物々交換局は今後、腐るおカネ化に加え、「流通領域をさらに広げ、農家が収穫したコメの分だけ通貨を自主発行できるようにしたい」と意気込む。
ダイヤモンド・オンライン5月14日(金) 8時30分配信 / 経済 - 経済総合
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100514-00000001-diamond-bus_all
通貨単位は”むすび”。1むすびはおにぎり1個分の玄米と交換できる。
愛知県豊田市でコメと交換できる地域通貨が誕生し、今年の5月1日から一部の地域で流通が始まった。その名も“おむすび通貨”だ。
発行元は弁理士で代表を務める吉田大氏や、大学准教授の村田尚生氏などが中心となって立ち上げた「物々交換局」という共同事業組合。吉田氏によれば、コメで価値が担保された地域通貨というのは世界で初めてだという。
通貨単位は“むすび”といい、1むすびは無農薬・有機栽培・天日乾燥の玄米0.5合(おにぎり1個分)と交換できる。この通貨を幅広く流通させることで、荒廃した農山村の振興を図ろうというのが目的だ。
さらに、コメとの交換以外でも、飲食店や雑貨屋など20店舗以上ある協力店舗で代金を支払う際にも利用できる。通常の通貨との交換レートが決まっていないため、販売者と消費者が商品やサービスの価値がいかほどなのか互いに決める形だ。
「価格の裏に隠れた本当のコストを、消費者が意識するきっかけになれば」と、吉田氏は話す。
だが、それだけではない。じつはこのおむすび通貨、これまでの通貨の概念自体を覆すことにもチャレンジしている。それは通貨の“腐るおカネ化” だ。普通のおカネならば、時間が経てば金利分だけ価値が増えるところを、逆に減価させようというのだ。
現在は作付けした年内の間にコメと交換しなければならないが、ゆくゆくは交換可能期間を延ばす予定だという。古米になれば価値が下がるので、それを価値の担保としているおむすび通貨も、自動的に減価するというわけだ。
そうすることで、価値が下がる前に早く使いたくなり、流通速度が上がる。どこか一部の人に留まることなく、社会を循環していくと考えているのだ。
これは「普通のおカネは利息の支払いと金利の受け取りが起こり、貧しい人から富める人のところにおカネが流れて滞留し、富の偏在を招く」(吉田氏)ことに対する挑戦でもある。
おむすび通貨が資金決済法の適用にあたるかどうか検討している東海財務局は、コメを担保にした通貨というのも、腐るおカネというのも「今まで見たことがない」(担当者)と語る。
物々交換局は今後、腐るおカネ化に加え、「流通領域をさらに広げ、農家が収穫したコメの分だけ通貨を自主発行できるようにしたい」と意気込む。
ダイヤモンド・オンライン5月14日(金) 8時30分配信 / 経済 - 経済総合
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100514-00000001-diamond-bus_all
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
高齢者情報資料室 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
高齢者情報資料室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31946人