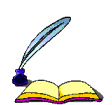75歳からのくらし/上 老人ホームで倹約生活
私はケアハウスに入居しています。支出の明細をお送りしますが倹約の毎日です。国のため、勤労奉仕でまともな教育も受けず、戦後も働き通しでした。職業を選ぶ余裕もない生活を、私たちの世代は送ってきました。それを若い読者に知ってほしく思います。
広島県内に暮らす久子さん(76)=仮名=から届いた手紙には、自身の歩んだ人生への思いと、現在のつましい暮らしぶりが詳細な生活費の内訳とともにつづられていた。社会福祉法人が運営するケアハウスを訪ねた。
◇働きづめ人生…引退後も余裕なく
ケアハウスは、独居に不安のある高齢者のための福祉施設。1日3食、食堂で提供され、体調の悪いときは個室のベッドサイドのブザーを押せば、事務所につながる。入居金は200万円。住んで10年になる。
久子さんはケアハウスを福祉事務所のパンフレットで知った。7カ所の施設を見学し、ここを選んだ。59歳で退職後、乳がんの手術の後遺症で重いものが持てず、買い物にも不自由していた。夫とは43歳で死別。県外に住む長女(47)とは、結婚などを巡って意見が合わず疎遠になった。入居の保証人は友人に頼んだ。
ケアハウスの利用料は所得で決まる。厚生年金が年154万円の久子さんは住居費・食費・事務費合わせ毎月7万2000円。冬は1800円の加算がある。水道代、光熱費、洗濯機などの使用料は別だ。
8年前に介護保険制度が始まり、保険料が年3万5900円、年金から天引きされている。後期高齢者医療制度の保険料は4月、年1万4200円との通知が届いたが、軽減措置で8月、8100円となった。昨年度の国民健康保険料1万4700円より安いが、「来年また上がるのでは」と不安だ。ほかに民間の医療保険の保険料も払う。脳腫瘍(しゅよう)などで入院したとき、差額ベッドや交通費がかさんだためだ。これらを払うと、手元に残るのは月3万円余り。「予想外の出費が多く、この先が心配」と顔を曇らせる。
一昨年の介護保険改正は生活に響いた。「要支援」の認定を受けて週1回、ヘルパーに部屋の掃除を頼んでいたが、自己負担分1200円を節約しようと利用をやめた。ケアハウスに通院付き添いを頼めば1回2000円、認知症などで金銭管理を頼めば管理料月3000円かかる。元気なうちは何でも自分でしたほうが良い。
近くの路線バスが廃止されたのも計算外だった。ケアハウスが町中まで送迎の車を出すようになったが、タクシーを使わないように外出を控える。
*
久子さんは4人姉妹の次女。戦時中は学校で農作業に駆り出された。戦後、大工の父親が仕事に困り、母も亡くなった際、マッチ工場で働くため学校をやめた。
4年後、東京で美容学校に通いながら菓子店で働いたが、結核にかかり、21歳で実家に戻った。結婚し長女が生まれたが、夫も結核患者で療養生活。少しでも手取りの良い仕事を求め、レストランのウエートレスなどを転々とした。医師会館の管理人の仕事が最後の勤めだった。
結核で片肺を切除したため、今も息切れしやすい。倹約を続けて多少ゆとりがあれば、友人と旅行したいと思っている。だがこの先さらに出費が増えるのでは、と不安が募る。バルコニーから夕日を受けて輝く海を眺め、心の安らぎを取り戻す。
*
物価の高騰。迷走する社会保障制度。戦後日本の繁栄を支えながら、老後も不安を抱えて暮らす人は少なくありません。5月の連載を読んでお便りを寄せてくれた読者を訪ねました。【大和田香織】
==============
◇ケアハウス
ケアハウスは軽費老人ホームの一種で独居に不安のある60歳以上が対象。厚生労働省の06年調査では全国に1750カ所あり、04年10月の同省の研究会報告書では70歳以上が入居者の91%を占め、38%が在宅介護サービスを受けていた。重度の介護が必要になると特別養護老人ホームに移ったり、外部の介護サービスを利用する。介護職員の配置を増やし、特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設では、直接介護を受けることができ、企業の参入も認められている。
毎日新聞 2008年9月30日 東京朝刊
--------------------------------------------------------------------
75歳からのくらし/中 細々とリンゴ栽培
◇病気、赤字「もうやめたいが…」
子どもたちが巣立ち、両親を看取(みと)ると、老いの坂道が待っていました。2人そろっているうちは良いですが、1人になったらどうなるのだろうと心配です。
中央アルプスと南アルプスにはさまれた長野県高森町から良子さん(78)=仮名=の手紙が届いた。夫の巌さん(88)=同=と2人暮らし。都心から高速バスで4時間、果樹と田畑が混在する中に築80年の家があった。
2人は主にリンゴの栽培をして暮らす。といっても規模はかつての半分もない。良子さんが54歳で脳腫瘍(しゅよう)の手術を受けたのを機に、年々小さくした。
主な収入は、巌さんの軍人恩給98万円と年金約120万円、良子さんの国民年金79万円。ここから年間の介護保険料2人分11万4000円、後期高齢者医療保険料19万円が天引きされる。
米とリンゴは繁忙期に人手を雇う。田植えや消毒などの手間賃、肥料代、古い耕作機械の修理代などを払うと、利益は年間50万円程度。出荷したリンゴの多くが「規格外」とされ赤字になることもある。「年寄り2人だけじゃ十分手もかけられなくて。草むしりだけでも体に応えますから」と良子さんは言う。
*
終戦後、巌さんは中国からシベリア経由で復員した。農地改革で土地の大半を失った両親に「これ以上土地を減らしたくない」と頼まれて農業を継いだ。生活は苦しく、村で奨励された酪農と果樹園を始めた。
乳牛の飼育は365日休めない。祝い事から帰っても晴れ着を脱ぎ乳しぼりをした。2人の子を両親に預け、牛舎と畑を行き来する毎日。子どもたちが成長すると父母の介護が始まった。消防団や町議など地域の役職で忙しい夫に代わり、良子さんは自動車で2人の通院に走り回った。両親を看取ると自分たちの老後が待っていた。
東京の大学を出た長男(55)は大手企業に勤め、関西に暮らす。勉強が得意で、農業を継がせるつもりはなかったという。町内に嫁いだ長女(53)が時々来て買い物などを手伝ってくれる。
巌さんは白内障を患い、良子さんは関節の痛み止めの注射が欠かせない。町内には福祉バスが走るが、バス停まで遠いので、月数回の通院は古い軽トラックが頼り。ただ、最近は事故が心配で、夜間や雨の日は運転を控えている。ガソリン代も年12万円と安くない。「通院もタクシーを使いたいけど、往復で1万円近くかかる。勤めに出ていれば、年金も上乗せがあったでしょうに」。ため息をつく良子さんの横で巌さんがつぶやいた。「農業をしていると地域のいろんなつながりができる。簡単にはやめられなかったよ」
100メートルほど先の空き家には90代の夫婦が住んでいた。数年前に夫が亡くなり、妻は長男にひきとられた後、施設に移ったと聞く。運転ができなくなったら巌さんたちもここで暮らすのは難しいだろう。だが良子さんは「息子の家に住むつもりはないし、先のことはわからない」と言う。
もう農業はやめよう、と思いながら、今年もリンゴの実がなると、真っ赤に色づく秋を夢見て脚立の上で作業する。離れて暮らす子どもたちも両親が元気でいることを願っているだろう。【大和田香織】
◇農林業、15%が75歳以上
05年農林業センサスの年齢別農業従事者数によると、75歳以上は全国で84万5061人で、全体の15%を占める。食料農業農村白書によると、農家戸数、基幹的農業従事者数が減少するなかで65歳以上の高齢者の割合は増え続けるが、2010年に昭和1ケタ世代が全員後期高齢者に移行すると、農業の生産構造にも大きな影響を及ぼすと懸念されている。
毎日新聞 2008年10月1日 東京朝刊
------------------------------------------------------------------------
75歳からのくらし/下 無年金、支えは家族
◇NPOで収入、健康気遣い
75歳を過ぎて3年がたった。いまになって、後期高齢者とか、長寿者とか名づけられて、世間の注目を浴びるとは。足の痛みとしびれ、高血圧症、十二指腸潰瘍(かいよう)など朝夕、10種類の服薬の毎日である。6年前、くも膜下出血で一夜のうちに妻を亡くしてしまった。つもる苦労が死期を早めたのかと悔やまれた。
東京都北区の石塚有宏(ともひろ)さん(78)は14歳のとき、台東区浅草で東京大空襲に遭った。一家で逃げてきた土地に、今は派遣社員の長女(47)、孫(19)と暮らす。
2階建て木造住宅に「地域に根ざした葬送文化を担う 縁生舎(えんじょうしゃ)」の看板。3年前、石塚さんが中心になって設立したNPO法人だ。葬送について勉強会を開いたり葬儀を企画し、1回2万〜3万円の報酬を得る。年金は無い。
*
浅草の和菓子屋で8人きょうだいの長男に生まれた。父親は戦後、バラックで菓子作りを再開したが、石塚さんは奨学金で大学に進み、研究者を目指した。
だが、大学院進学を前に知人から「長男なのだから家のことを考えて」とさとされた。嫁いできた妻は、両しゅうと、7人の弟妹、住み込みの少年たちのまかないの合間に、菓子作りにも加わった。
長男長女が生まれてまもなく、菓子工場は行き詰まり、転業する。70年代、大手スーパーが進出する高度成長期。石塚さんはスーパーの要請でたこ焼きなどの軽食コーナーを次々出店した。資金繰りが苦しくても、断れば取引を切られる。総菜、マグロ加工……。会社を起こしては倒産し、自宅は何度も競売にかけられた。
最後は67歳で開業した仕出し弁当業。葬儀の裏側を知り、妻の葬儀の喪主を務め、葬儀会社任せの葬送に疑問を持った。ライフワークを見つけた思いがした。蓄えのほとんどと長男夫婦の援助で負債を返し、弁当業を廃業。本を読んだり学習会で知識を得てNPOの活動を始めた。
*
年金には一度も加入していない。国民年金制度が始まった1961年ごろ、店の経営が苦しく相談に行った商工団体で年金の反対運動に加わった。その後も自転車操業の毎日で老後を考える暇はなかった。
両親を看取(みと)った60代のころ、区役所に問い合わせると「今からだと数百万円の保険料納付が必要。貯金したほうがいい」と勧められ、加入をあきらめた。父母の世代は保険料を払わなくても福祉年金を受け取れ、医療費の自己負担もなかった。「でも我々の世代は違う。高齢者も負担を求められる時代に備えて加入しておけばよかった」
NPOで得る収入のほかは、20年ほど前に援助した親族からの貸金返済が月2万円。全部合わせて年収は50万円程度だ。ここから介護保険料2万5000円、後期高齢者医療保険料5400円などを払う。薬代など医療の自己負担は月2000〜3000円。食費・光熱費などは長女が負担する。
老人割引が使えるバスで外出し運動不足に気をつけ、たまに映画を見に行くのが楽しみ。「旅行もしたいが欲を挙げればきりがない。自分の選んだ仕事がお金になり、借金もない。今が青春です」【大和田香織】
◇65歳以上の無年金42万人
社会保険庁の07年12月推計によると、65歳以上の無年金者の数は全国で42万人。国民年金は自営業者や農業従事者のために生まれ、1961年から保険料徴収が始まった。「増税の一環だ」として労働組合や商工団体の一部は反対運動を展開。社会保障総合年表(ぎょうせい)によると、当初の加入は低調で1割に満たなかったという。
毎日新聞 2008年10月2日 東京朝刊
私はケアハウスに入居しています。支出の明細をお送りしますが倹約の毎日です。国のため、勤労奉仕でまともな教育も受けず、戦後も働き通しでした。職業を選ぶ余裕もない生活を、私たちの世代は送ってきました。それを若い読者に知ってほしく思います。
広島県内に暮らす久子さん(76)=仮名=から届いた手紙には、自身の歩んだ人生への思いと、現在のつましい暮らしぶりが詳細な生活費の内訳とともにつづられていた。社会福祉法人が運営するケアハウスを訪ねた。
◇働きづめ人生…引退後も余裕なく
ケアハウスは、独居に不安のある高齢者のための福祉施設。1日3食、食堂で提供され、体調の悪いときは個室のベッドサイドのブザーを押せば、事務所につながる。入居金は200万円。住んで10年になる。
久子さんはケアハウスを福祉事務所のパンフレットで知った。7カ所の施設を見学し、ここを選んだ。59歳で退職後、乳がんの手術の後遺症で重いものが持てず、買い物にも不自由していた。夫とは43歳で死別。県外に住む長女(47)とは、結婚などを巡って意見が合わず疎遠になった。入居の保証人は友人に頼んだ。
ケアハウスの利用料は所得で決まる。厚生年金が年154万円の久子さんは住居費・食費・事務費合わせ毎月7万2000円。冬は1800円の加算がある。水道代、光熱費、洗濯機などの使用料は別だ。
8年前に介護保険制度が始まり、保険料が年3万5900円、年金から天引きされている。後期高齢者医療制度の保険料は4月、年1万4200円との通知が届いたが、軽減措置で8月、8100円となった。昨年度の国民健康保険料1万4700円より安いが、「来年また上がるのでは」と不安だ。ほかに民間の医療保険の保険料も払う。脳腫瘍(しゅよう)などで入院したとき、差額ベッドや交通費がかさんだためだ。これらを払うと、手元に残るのは月3万円余り。「予想外の出費が多く、この先が心配」と顔を曇らせる。
一昨年の介護保険改正は生活に響いた。「要支援」の認定を受けて週1回、ヘルパーに部屋の掃除を頼んでいたが、自己負担分1200円を節約しようと利用をやめた。ケアハウスに通院付き添いを頼めば1回2000円、認知症などで金銭管理を頼めば管理料月3000円かかる。元気なうちは何でも自分でしたほうが良い。
近くの路線バスが廃止されたのも計算外だった。ケアハウスが町中まで送迎の車を出すようになったが、タクシーを使わないように外出を控える。
*
久子さんは4人姉妹の次女。戦時中は学校で農作業に駆り出された。戦後、大工の父親が仕事に困り、母も亡くなった際、マッチ工場で働くため学校をやめた。
4年後、東京で美容学校に通いながら菓子店で働いたが、結核にかかり、21歳で実家に戻った。結婚し長女が生まれたが、夫も結核患者で療養生活。少しでも手取りの良い仕事を求め、レストランのウエートレスなどを転々とした。医師会館の管理人の仕事が最後の勤めだった。
結核で片肺を切除したため、今も息切れしやすい。倹約を続けて多少ゆとりがあれば、友人と旅行したいと思っている。だがこの先さらに出費が増えるのでは、と不安が募る。バルコニーから夕日を受けて輝く海を眺め、心の安らぎを取り戻す。
*
物価の高騰。迷走する社会保障制度。戦後日本の繁栄を支えながら、老後も不安を抱えて暮らす人は少なくありません。5月の連載を読んでお便りを寄せてくれた読者を訪ねました。【大和田香織】
==============
◇ケアハウス
ケアハウスは軽費老人ホームの一種で独居に不安のある60歳以上が対象。厚生労働省の06年調査では全国に1750カ所あり、04年10月の同省の研究会報告書では70歳以上が入居者の91%を占め、38%が在宅介護サービスを受けていた。重度の介護が必要になると特別養護老人ホームに移ったり、外部の介護サービスを利用する。介護職員の配置を増やし、特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設では、直接介護を受けることができ、企業の参入も認められている。
毎日新聞 2008年9月30日 東京朝刊
--------------------------------------------------------------------
75歳からのくらし/中 細々とリンゴ栽培
◇病気、赤字「もうやめたいが…」
子どもたちが巣立ち、両親を看取(みと)ると、老いの坂道が待っていました。2人そろっているうちは良いですが、1人になったらどうなるのだろうと心配です。
中央アルプスと南アルプスにはさまれた長野県高森町から良子さん(78)=仮名=の手紙が届いた。夫の巌さん(88)=同=と2人暮らし。都心から高速バスで4時間、果樹と田畑が混在する中に築80年の家があった。
2人は主にリンゴの栽培をして暮らす。といっても規模はかつての半分もない。良子さんが54歳で脳腫瘍(しゅよう)の手術を受けたのを機に、年々小さくした。
主な収入は、巌さんの軍人恩給98万円と年金約120万円、良子さんの国民年金79万円。ここから年間の介護保険料2人分11万4000円、後期高齢者医療保険料19万円が天引きされる。
米とリンゴは繁忙期に人手を雇う。田植えや消毒などの手間賃、肥料代、古い耕作機械の修理代などを払うと、利益は年間50万円程度。出荷したリンゴの多くが「規格外」とされ赤字になることもある。「年寄り2人だけじゃ十分手もかけられなくて。草むしりだけでも体に応えますから」と良子さんは言う。
*
終戦後、巌さんは中国からシベリア経由で復員した。農地改革で土地の大半を失った両親に「これ以上土地を減らしたくない」と頼まれて農業を継いだ。生活は苦しく、村で奨励された酪農と果樹園を始めた。
乳牛の飼育は365日休めない。祝い事から帰っても晴れ着を脱ぎ乳しぼりをした。2人の子を両親に預け、牛舎と畑を行き来する毎日。子どもたちが成長すると父母の介護が始まった。消防団や町議など地域の役職で忙しい夫に代わり、良子さんは自動車で2人の通院に走り回った。両親を看取ると自分たちの老後が待っていた。
東京の大学を出た長男(55)は大手企業に勤め、関西に暮らす。勉強が得意で、農業を継がせるつもりはなかったという。町内に嫁いだ長女(53)が時々来て買い物などを手伝ってくれる。
巌さんは白内障を患い、良子さんは関節の痛み止めの注射が欠かせない。町内には福祉バスが走るが、バス停まで遠いので、月数回の通院は古い軽トラックが頼り。ただ、最近は事故が心配で、夜間や雨の日は運転を控えている。ガソリン代も年12万円と安くない。「通院もタクシーを使いたいけど、往復で1万円近くかかる。勤めに出ていれば、年金も上乗せがあったでしょうに」。ため息をつく良子さんの横で巌さんがつぶやいた。「農業をしていると地域のいろんなつながりができる。簡単にはやめられなかったよ」
100メートルほど先の空き家には90代の夫婦が住んでいた。数年前に夫が亡くなり、妻は長男にひきとられた後、施設に移ったと聞く。運転ができなくなったら巌さんたちもここで暮らすのは難しいだろう。だが良子さんは「息子の家に住むつもりはないし、先のことはわからない」と言う。
もう農業はやめよう、と思いながら、今年もリンゴの実がなると、真っ赤に色づく秋を夢見て脚立の上で作業する。離れて暮らす子どもたちも両親が元気でいることを願っているだろう。【大和田香織】
◇農林業、15%が75歳以上
05年農林業センサスの年齢別農業従事者数によると、75歳以上は全国で84万5061人で、全体の15%を占める。食料農業農村白書によると、農家戸数、基幹的農業従事者数が減少するなかで65歳以上の高齢者の割合は増え続けるが、2010年に昭和1ケタ世代が全員後期高齢者に移行すると、農業の生産構造にも大きな影響を及ぼすと懸念されている。
毎日新聞 2008年10月1日 東京朝刊
------------------------------------------------------------------------
75歳からのくらし/下 無年金、支えは家族
◇NPOで収入、健康気遣い
75歳を過ぎて3年がたった。いまになって、後期高齢者とか、長寿者とか名づけられて、世間の注目を浴びるとは。足の痛みとしびれ、高血圧症、十二指腸潰瘍(かいよう)など朝夕、10種類の服薬の毎日である。6年前、くも膜下出血で一夜のうちに妻を亡くしてしまった。つもる苦労が死期を早めたのかと悔やまれた。
東京都北区の石塚有宏(ともひろ)さん(78)は14歳のとき、台東区浅草で東京大空襲に遭った。一家で逃げてきた土地に、今は派遣社員の長女(47)、孫(19)と暮らす。
2階建て木造住宅に「地域に根ざした葬送文化を担う 縁生舎(えんじょうしゃ)」の看板。3年前、石塚さんが中心になって設立したNPO法人だ。葬送について勉強会を開いたり葬儀を企画し、1回2万〜3万円の報酬を得る。年金は無い。
*
浅草の和菓子屋で8人きょうだいの長男に生まれた。父親は戦後、バラックで菓子作りを再開したが、石塚さんは奨学金で大学に進み、研究者を目指した。
だが、大学院進学を前に知人から「長男なのだから家のことを考えて」とさとされた。嫁いできた妻は、両しゅうと、7人の弟妹、住み込みの少年たちのまかないの合間に、菓子作りにも加わった。
長男長女が生まれてまもなく、菓子工場は行き詰まり、転業する。70年代、大手スーパーが進出する高度成長期。石塚さんはスーパーの要請でたこ焼きなどの軽食コーナーを次々出店した。資金繰りが苦しくても、断れば取引を切られる。総菜、マグロ加工……。会社を起こしては倒産し、自宅は何度も競売にかけられた。
最後は67歳で開業した仕出し弁当業。葬儀の裏側を知り、妻の葬儀の喪主を務め、葬儀会社任せの葬送に疑問を持った。ライフワークを見つけた思いがした。蓄えのほとんどと長男夫婦の援助で負債を返し、弁当業を廃業。本を読んだり学習会で知識を得てNPOの活動を始めた。
*
年金には一度も加入していない。国民年金制度が始まった1961年ごろ、店の経営が苦しく相談に行った商工団体で年金の反対運動に加わった。その後も自転車操業の毎日で老後を考える暇はなかった。
両親を看取(みと)った60代のころ、区役所に問い合わせると「今からだと数百万円の保険料納付が必要。貯金したほうがいい」と勧められ、加入をあきらめた。父母の世代は保険料を払わなくても福祉年金を受け取れ、医療費の自己負担もなかった。「でも我々の世代は違う。高齢者も負担を求められる時代に備えて加入しておけばよかった」
NPOで得る収入のほかは、20年ほど前に援助した親族からの貸金返済が月2万円。全部合わせて年収は50万円程度だ。ここから介護保険料2万5000円、後期高齢者医療保険料5400円などを払う。薬代など医療の自己負担は月2000〜3000円。食費・光熱費などは長女が負担する。
老人割引が使えるバスで外出し運動不足に気をつけ、たまに映画を見に行くのが楽しみ。「旅行もしたいが欲を挙げればきりがない。自分の選んだ仕事がお金になり、借金もない。今が青春です」【大和田香織】
◇65歳以上の無年金42万人
社会保険庁の07年12月推計によると、65歳以上の無年金者の数は全国で42万人。国民年金は自営業者や農業従事者のために生まれ、1961年から保険料徴収が始まった。「増税の一環だ」として労働組合や商工団体の一部は反対運動を展開。社会保障総合年表(ぎょうせい)によると、当初の加入は低調で1割に満たなかったという。
毎日新聞 2008年10月2日 東京朝刊
|
|
|
|
|
|
|
|
高齢者情報資料室 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
高齢者情報資料室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人