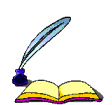2008年8月1日 東京新聞
大きな地震が相次ぐ日本列島。ご家庭の備えは万全だろうか。高齢者や慢性疾患の患者、障害者、幼児などがいる家庭は、いざというときの対策をより注意深く練っていく必要がある。今月は、災害に負けないための備えを医療面から考えていく。 (安藤明夫)
避難所で、高齢の被災者が昼食の分配を手伝おうとしたら、ボランティアの若者が「これは私たちの仕事です。無理しないでください」と、トレーを奪うように取った。
国立長寿医療センター研究所(愛知県大府市)の生活機能賦活研究部長・大川弥生さんは、二〇〇四年の新潟県中越地震の被災地で見た光景に衝撃を受けた。
「援助する側が生活不活発病の知識を持たないために、被災者の役割を奪い、動く機会を奪っていたんです」
「生活不活発病」とは、体を動かさないことで心身の機能が低下する状態。筋力や心肺機能が落ち、うつ病や寝たきりにもつながる。学術名は「廃用症候群」だが、高齢者が不快感を持たずに本質を理解できるようにと大川さんが生活不活発病と名付けた。
地震の半年後、大川さんが同県長岡市内で約二千人を対象に実施した生活機能調査によれば、健康で自立していた高齢者のうち、屋外歩行が難しくなったと感じる人が25%、屋内歩行も難しくなった人が6%いた。病気ではなくても環境の変化によって生活機能が落ちることを示した。
以後、厚生労働省では大地震などの災害のたび、被災地の自治体に生活不活発病予防対策を促す通達を出しているが、「被災者は安静に、無理をさせない」という意識はまだ根強いという。
大川さんは「避難生活では、料理、洗濯、掃除などの活動量も減るし、家庭や地域の中での役割も低下して生活全体が不活発になりやすい。活動の量や質が低下している高齢者を早期発見して、原因を確かめ、手助けをしていく必要がある」と訴える。
その人らしい、いきいきとした生活を取り戻すことが大切で、一般的な対策としては▽散歩やスポーツは生活の活発化に効果的▽避難所では昼間は毛布を畳み、横にならないようにする▽何らかの役割を持つ▽ボランティアによる必要以上の手助け・介護を避ける−などを呼び掛ける。
リスクの高い人を早期発見するために「生活機能チェック表」も作った。<1>屋外歩行<2>自宅内歩行<3>その他の生活行為(食事、入浴、洗面、トイレなど)<4>車いす<5>歩行補助具・装備の使用<6>外出頻度<7>家事<8>家事以外の家の中での役割<9>日中活動性−の各項目ごとに災害前と現在の状態を比較するもので、低下している場合は、早く手を打つことが大切になる。
被災地では、保健師が核となって被災者の状態を調査、理学療法士、作業療法士なども専門分野で手伝っていく形が理想という。
大川さんは「生活不活発病は災害時だけの問題ではありません。日ごろから自分の活動が低下していないか点検し、改善に努めることが、いざという時にも役立つ」とアドバイスする。
大きな地震が相次ぐ日本列島。ご家庭の備えは万全だろうか。高齢者や慢性疾患の患者、障害者、幼児などがいる家庭は、いざというときの対策をより注意深く練っていく必要がある。今月は、災害に負けないための備えを医療面から考えていく。 (安藤明夫)
避難所で、高齢の被災者が昼食の分配を手伝おうとしたら、ボランティアの若者が「これは私たちの仕事です。無理しないでください」と、トレーを奪うように取った。
国立長寿医療センター研究所(愛知県大府市)の生活機能賦活研究部長・大川弥生さんは、二〇〇四年の新潟県中越地震の被災地で見た光景に衝撃を受けた。
「援助する側が生活不活発病の知識を持たないために、被災者の役割を奪い、動く機会を奪っていたんです」
「生活不活発病」とは、体を動かさないことで心身の機能が低下する状態。筋力や心肺機能が落ち、うつ病や寝たきりにもつながる。学術名は「廃用症候群」だが、高齢者が不快感を持たずに本質を理解できるようにと大川さんが生活不活発病と名付けた。
地震の半年後、大川さんが同県長岡市内で約二千人を対象に実施した生活機能調査によれば、健康で自立していた高齢者のうち、屋外歩行が難しくなったと感じる人が25%、屋内歩行も難しくなった人が6%いた。病気ではなくても環境の変化によって生活機能が落ちることを示した。
以後、厚生労働省では大地震などの災害のたび、被災地の自治体に生活不活発病予防対策を促す通達を出しているが、「被災者は安静に、無理をさせない」という意識はまだ根強いという。
大川さんは「避難生活では、料理、洗濯、掃除などの活動量も減るし、家庭や地域の中での役割も低下して生活全体が不活発になりやすい。活動の量や質が低下している高齢者を早期発見して、原因を確かめ、手助けをしていく必要がある」と訴える。
その人らしい、いきいきとした生活を取り戻すことが大切で、一般的な対策としては▽散歩やスポーツは生活の活発化に効果的▽避難所では昼間は毛布を畳み、横にならないようにする▽何らかの役割を持つ▽ボランティアによる必要以上の手助け・介護を避ける−などを呼び掛ける。
リスクの高い人を早期発見するために「生活機能チェック表」も作った。<1>屋外歩行<2>自宅内歩行<3>その他の生活行為(食事、入浴、洗面、トイレなど)<4>車いす<5>歩行補助具・装備の使用<6>外出頻度<7>家事<8>家事以外の家の中での役割<9>日中活動性−の各項目ごとに災害前と現在の状態を比較するもので、低下している場合は、早く手を打つことが大切になる。
被災地では、保健師が核となって被災者の状態を調査、理学療法士、作業療法士なども専門分野で手伝っていく形が理想という。
大川さんは「生活不活発病は災害時だけの問題ではありません。日ごろから自分の活動が低下していないか点検し、改善に努めることが、いざという時にも役立つ」とアドバイスする。
|
|
|
|
|
|
|
|
高齢者情報資料室 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
高齢者情報資料室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90057人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208316人
- 3位
- 酒好き
- 170697人