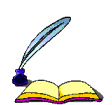医師よ、真実を開示せよ
医学界と医薬業界のただならぬ関係にメス
* 2008年5月20日 火曜日
米デューク大学の医療研究グループは衝撃を受けた。過去1年間に医学雑誌に掲載された、狭まった心臓血管の広がりを保持する「ステント」(多くは金属製の、網目構造で筒状の器具)に関する論文700本以上を精査したところ、2つの重大な情報が欠落していたからだ。1つは、論文の執筆者が医療器具の製造元企業から報酬を受け取っているかどうかについて明示していない論文が、全体の83%に及んでいたことである。
もう1つ、さらに驚くべきなのは、臨床試験などの研究調査に関する論文の72%で、研究費の提供者についての記載がなかったことだ。5月7日にオンライン科学・医学誌「プロスワン(PLoS One)」に発表されたデューク大学のこの論文は、医師と企業の間で資金的つながりが強固になりつつある問題と、そうした関係が適切に情報公開されているかどうかを、改めて疑問視している。
医薬品や医療器具を研究する医師は、そうした製品を作っている企業から資金援助を受けることが多い。連邦政府の医学研究への助成金が減り続ける中、企業と医師の“共生関係”は重要性を増している(BusinessWeek.comの記事を参照:2008年5月8日「Big Drug R&D on Campus」)。
だが近年、企業からカネを受け取った医師が執筆する論文の公正さを疑問視する声が、医学界で強まっている。医師が関係の深い企業の製品に関して公平性を欠く論文を執筆して危険な副作用を軽視したり、製品にとって好ましくない研究結果を公表しなくなったりする恐れがあると、関係者は指摘する。
鎮痛薬の回収騒ぎで開示規定を強化したものの…
心臓病や脳卒中を引き起こすとして2004年に自主回収となった米メルク(MRK)の鎮痛剤・関節炎治療薬「バイオックス」に関する議論をきっかけに、米総合医学雑誌「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン(NEJM)」や米医師会雑誌「ジャーナル・オブ・アメリカン・メディカル・アソシエーション(JAMA)」などの専門誌は、規定を強化し、企業との資金面での協力関係について情報開示することを執筆者に求めている。透明性を確保して、どこからの支援を受けた研究であるかを理解したうえで医師、患者、監督機関、保険会社に研究結果が偏っていないかを判断してもらうことが狙いである。
しかし、デューク大学が発表した論文は、目的が達成されていないことを示唆している。執筆者のほとんどが雑誌の情報開示規定を無視しているうえに、開示された情報にも疑わしいものがあるというのだ。
研究グループは、調査対象とした2985人の執筆者のうち、2006年に公表された雑誌論文で情報開示を行っていた約170人について詳しく調べた。インターネット検索による調査で、利害関係がないと記載している医師の中に、ステントを製造している企業の顧問を務めている者が見つかった。1人はステント製造業者の共同設立者となっていた(デューク大学の論文は、個人名を公表していない)。企業との関係を明示していた75人のうち、常に情報開示を行っていたのは2人だけで、残りは論文によって関係を記載しているものと記載していないものがあった。
今回の研究の代表執筆者であるデューク大学臨床研究所のケビン・ワインフルト氏は、透明性の欠如については、執筆者だけでなく雑誌の編集者の責任も大きいと述べている。情報開示規定を守らせるよう「専門誌は監視を強化すべきだ。今回の我々の研究で目を覚ましてほしい」と、同氏は言う。
企業側からは冷めた反応
情報開示規定は雑誌が定めた自主規制で、開示を法的に義務づけるものではない。全国規模のデータベースを作り、医師と企業の資金面での支援関係をすべて登録させる規制措置を提案する連邦議員もいるが、現在のところ、そうした取り組みは進んでいない。
デューク大学の研究では、企業との利害関係が医学研究の中に深く浸透していることも明らかになった。開示された情報の中で、研究費を支援している企業として多く名前が挙がっていたのが、ステントメーカーの米ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)、米ボストン・サイエンティフィック(BSX)、米メドトロニック(MDT)と製薬会社の米ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(BMY)、仏サノフィ・アベンティス(SNY)だった。ブリストル・マイヤーズとサノフィ・アベンティスは、ステントを使用している患者に広く処方されている抗血栓症薬「プラビックス」を共同で販売している。
http://
ワインフルト氏は、調査を行うに当たって、少なくとも研究全体の資金提供者は明示されているものと予想していたと話す。個々の執筆者の企業との関係を開示することが求められるずっと前から、ほとんどの雑誌は研究費の出資者を明示するよう求めていたからだ。「72%(の論文)で支援者が明示されていないことには驚いた。誰が研究費を提供したかは明示してもらいたい」と、同氏は言う。
BusinessWeekは、上記の5社すべてに取材した。ブリストル・マイヤーズの広報担当者は電子メールによる回答で、「当社が資金提供したり、関与したりしている論文は、必ずその論文中でその旨を明示する」ことを会社の方針としていると述べた。ボストン・サイエンティフィックの広報担当者からは、こんな声明が送られてきた。「当社は、臨床研究や研究成果に関するすべての論文や研究発表で、当社がスポンサーとして関与している旨を明示するよう求めている。学術誌の情報開示規定に従って、どのように当社の関与を報告するかは、個々の執筆者の責任と考えている」。残る3社からは、この記事掲載時までに回答がなかった。
適正な情報開示制度はどうあるべきか
対応策が乏しいとこぼす雑誌編集者もいる。情報開示規定を定めても、執筆者を信用して、守ってくれることを願うほかないのだ。JAMAの編集長で、以前から情報開示を推進してきた医師キャサリン・デアンジェリス氏は、「私は刑事でも、FBI(米連邦捜査局)の捜査官でもない」と言う。JAMAには毎年数千人の執筆者が寄稿しており、すべての開示情報をグーグル(GOOG)で検索して、正しいかどうか確認するよう編集者に求めることはできないと同氏は話す。また、情報開示の要請に応じない執筆者が実に多いことを嘆いてもいる。
「普通に考えれば開示するのが当然だ。開示によって、論文の価値が下がることはない。だが、価値が下がると考えて開示をしなければ、本当に価値が下がってしまう恐れがある」と、デアンジェリス氏は言う。
開示をめぐる議論の根底には、透明性の確保でどんな利点があるのかという大きな疑問がある。すべての執筆者が必ず情報開示をしたとしても、中身の分からない情報があふれるだけになりかねない。ほとんどの場合、開示される情報は企業名の一覧だけだ。執筆者がその企業からいくらもらったのか、支払いは現金か株式か、どんな見返りを得ているかといったことは分からない。
「情報開示の全体的な仕組みが欠陥だらけだ」と、NEJMの元編集長で、『On the Take: How Medicine's Complicity with Big Business Can Endanger Your Health(仮訳:医学界と産業界の癒着関係が健康を危機にさらす)』を著した医師ジェローム・カシレー氏は指摘する。「論文を読み、執筆者の立場が公正なものではないと判明しても、それ以上のことは何も分からない」。
http://
医学界と医薬業界のただならぬ関係にメス
* 2008年5月20日 火曜日
米デューク大学の医療研究グループは衝撃を受けた。過去1年間に医学雑誌に掲載された、狭まった心臓血管の広がりを保持する「ステント」(多くは金属製の、網目構造で筒状の器具)に関する論文700本以上を精査したところ、2つの重大な情報が欠落していたからだ。1つは、論文の執筆者が医療器具の製造元企業から報酬を受け取っているかどうかについて明示していない論文が、全体の83%に及んでいたことである。
もう1つ、さらに驚くべきなのは、臨床試験などの研究調査に関する論文の72%で、研究費の提供者についての記載がなかったことだ。5月7日にオンライン科学・医学誌「プロスワン(PLoS One)」に発表されたデューク大学のこの論文は、医師と企業の間で資金的つながりが強固になりつつある問題と、そうした関係が適切に情報公開されているかどうかを、改めて疑問視している。
医薬品や医療器具を研究する医師は、そうした製品を作っている企業から資金援助を受けることが多い。連邦政府の医学研究への助成金が減り続ける中、企業と医師の“共生関係”は重要性を増している(BusinessWeek.comの記事を参照:2008年5月8日「Big Drug R&D on Campus」)。
だが近年、企業からカネを受け取った医師が執筆する論文の公正さを疑問視する声が、医学界で強まっている。医師が関係の深い企業の製品に関して公平性を欠く論文を執筆して危険な副作用を軽視したり、製品にとって好ましくない研究結果を公表しなくなったりする恐れがあると、関係者は指摘する。
鎮痛薬の回収騒ぎで開示規定を強化したものの…
心臓病や脳卒中を引き起こすとして2004年に自主回収となった米メルク(MRK)の鎮痛剤・関節炎治療薬「バイオックス」に関する議論をきっかけに、米総合医学雑誌「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン(NEJM)」や米医師会雑誌「ジャーナル・オブ・アメリカン・メディカル・アソシエーション(JAMA)」などの専門誌は、規定を強化し、企業との資金面での協力関係について情報開示することを執筆者に求めている。透明性を確保して、どこからの支援を受けた研究であるかを理解したうえで医師、患者、監督機関、保険会社に研究結果が偏っていないかを判断してもらうことが狙いである。
しかし、デューク大学が発表した論文は、目的が達成されていないことを示唆している。執筆者のほとんどが雑誌の情報開示規定を無視しているうえに、開示された情報にも疑わしいものがあるというのだ。
研究グループは、調査対象とした2985人の執筆者のうち、2006年に公表された雑誌論文で情報開示を行っていた約170人について詳しく調べた。インターネット検索による調査で、利害関係がないと記載している医師の中に、ステントを製造している企業の顧問を務めている者が見つかった。1人はステント製造業者の共同設立者となっていた(デューク大学の論文は、個人名を公表していない)。企業との関係を明示していた75人のうち、常に情報開示を行っていたのは2人だけで、残りは論文によって関係を記載しているものと記載していないものがあった。
今回の研究の代表執筆者であるデューク大学臨床研究所のケビン・ワインフルト氏は、透明性の欠如については、執筆者だけでなく雑誌の編集者の責任も大きいと述べている。情報開示規定を守らせるよう「専門誌は監視を強化すべきだ。今回の我々の研究で目を覚ましてほしい」と、同氏は言う。
企業側からは冷めた反応
情報開示規定は雑誌が定めた自主規制で、開示を法的に義務づけるものではない。全国規模のデータベースを作り、医師と企業の資金面での支援関係をすべて登録させる規制措置を提案する連邦議員もいるが、現在のところ、そうした取り組みは進んでいない。
デューク大学の研究では、企業との利害関係が医学研究の中に深く浸透していることも明らかになった。開示された情報の中で、研究費を支援している企業として多く名前が挙がっていたのが、ステントメーカーの米ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)、米ボストン・サイエンティフィック(BSX)、米メドトロニック(MDT)と製薬会社の米ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(BMY)、仏サノフィ・アベンティス(SNY)だった。ブリストル・マイヤーズとサノフィ・アベンティスは、ステントを使用している患者に広く処方されている抗血栓症薬「プラビックス」を共同で販売している。
http://
ワインフルト氏は、調査を行うに当たって、少なくとも研究全体の資金提供者は明示されているものと予想していたと話す。個々の執筆者の企業との関係を開示することが求められるずっと前から、ほとんどの雑誌は研究費の出資者を明示するよう求めていたからだ。「72%(の論文)で支援者が明示されていないことには驚いた。誰が研究費を提供したかは明示してもらいたい」と、同氏は言う。
BusinessWeekは、上記の5社すべてに取材した。ブリストル・マイヤーズの広報担当者は電子メールによる回答で、「当社が資金提供したり、関与したりしている論文は、必ずその論文中でその旨を明示する」ことを会社の方針としていると述べた。ボストン・サイエンティフィックの広報担当者からは、こんな声明が送られてきた。「当社は、臨床研究や研究成果に関するすべての論文や研究発表で、当社がスポンサーとして関与している旨を明示するよう求めている。学術誌の情報開示規定に従って、どのように当社の関与を報告するかは、個々の執筆者の責任と考えている」。残る3社からは、この記事掲載時までに回答がなかった。
適正な情報開示制度はどうあるべきか
対応策が乏しいとこぼす雑誌編集者もいる。情報開示規定を定めても、執筆者を信用して、守ってくれることを願うほかないのだ。JAMAの編集長で、以前から情報開示を推進してきた医師キャサリン・デアンジェリス氏は、「私は刑事でも、FBI(米連邦捜査局)の捜査官でもない」と言う。JAMAには毎年数千人の執筆者が寄稿しており、すべての開示情報をグーグル(GOOG)で検索して、正しいかどうか確認するよう編集者に求めることはできないと同氏は話す。また、情報開示の要請に応じない執筆者が実に多いことを嘆いてもいる。
「普通に考えれば開示するのが当然だ。開示によって、論文の価値が下がることはない。だが、価値が下がると考えて開示をしなければ、本当に価値が下がってしまう恐れがある」と、デアンジェリス氏は言う。
開示をめぐる議論の根底には、透明性の確保でどんな利点があるのかという大きな疑問がある。すべての執筆者が必ず情報開示をしたとしても、中身の分からない情報があふれるだけになりかねない。ほとんどの場合、開示される情報は企業名の一覧だけだ。執筆者がその企業からいくらもらったのか、支払いは現金か株式か、どんな見返りを得ているかといったことは分からない。
「情報開示の全体的な仕組みが欠陥だらけだ」と、NEJMの元編集長で、『On the Take: How Medicine's Complicity with Big Business Can Endanger Your Health(仮訳:医学界と産業界の癒着関係が健康を危機にさらす)』を著した医師ジェローム・カシレー氏は指摘する。「論文を読み、執筆者の立場が公正なものではないと判明しても、それ以上のことは何も分からない」。
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
高齢者情報資料室 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
高齢者情報資料室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37860人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90055人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人