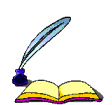浅川 澄一 編集委員
救世主はボランティアか外国人か(2007/11/19)
有償ボランティアを制度化
厚生労働省はこの5月、「65歳以上の高齢者が地元で福祉ボランティア活動をすれば、自分が支払う保険料が少なくなる」という新たな仕組みを介護保険制度に取り込んだ。有償ボランティアを国が公認し、その財源を介護保険に求めたのである。「高齢者が地域活動をして健康を維持すれば要介護者になる人は少なくなりコスト削減になる。だから、この活動を推奨している介護予防事業のひとつとして認める」という理由からだ。
9月から東京都稲城市が始めており、12月からは同千代田区が追随、来春には同世田谷区が導入する。稲城市が始めたのは「介護支援ボランティア制度」。高齢者が、特別養護老人ホームなど福祉施設の食堂で配膳の手助けやレクリエーションの指導、行事の手伝いなどを1時間程度すると、手帳にひとつのスタンプが押される。年度末に1スタンプを100円で換算、現金が高齢者の預金口座に振り込まれる。
現金化できるのは年間50スタンプまで。もし、50時間以上活動すると5000円の収入になる。これを保険料に回すと、同市の1カ月の平均保険料は4500円だから十分におつりがくる。
東京都世田谷区の「せたがや介護支援ボランティア制度」では、高齢者が1回2時間程度の活動をすると、50円相当のシールを張り、年間で6000円(シール120枚分)を上限に現金を渡す。
「ボランティア精神に反する」と異論
こうした介護ボランティアに対して、日本ボランティアコーディネーター協会は「活動時間に応じて換金出来る制度をボランティアと呼ぶのはおかしい」と、反対している。さらに「生活費を稼ぐために就労していたり、家族介護に追われている高齢者も多く、誰でもが参加できるわけではない。参加者だけ保険料を軽減するのは不公平」とも主張する。
ボランティア活動と報酬が結びつくと、「ボランティアという美名の下で、低賃金労働への道を開くことになりかねない」と批判するのは大阪ボランティア協会常務理事の早瀬昇さん。
人手不足を少しでも解消しようと、事業者側が積極的に制度化を要望する可能性が出てくる。「ボランティアの名目で募集すると、パートタイマーやアルバイトよりも意欲のある人が集まりやすい。だが反面、権利義務関係があいまいになり、介護サービスの低下を招きかねない」と早瀬さんは指摘する。
確かに、稲城市が決めた活動内容をみると、「散歩、外出、館内移動の補助」「話し相手」など、施設職員の通常業務と思われる行為を含んでいる。認知症高齢者へのケアは事前に十分な研修が必要であるのは言うまでもないこと。せかしたり、言動を否定するとかえって症状を重度化させかねない。
では、稲城市でボランティア活動を続けてきた人たちの反応はどうか。
会食活動を続けてきたNPO法人「支え合う会みのり」の理事長、中村久美子さんは「場所や内容を限定してボランティアと言うのはどうか、個人的には疑問があるが、厨房設備などで市から20年以上も助成金を受けているので、真正面から異論は唱えにくい立場だ」と、複雑な胸の内を打ち明ける。ただ、みのりでは積極的に取り組む計画はないという。
同市内の特養で十数人の仲間と10年前から洗濯物畳みをしている石川トミさんは、「説明を受けてノートをもらい、毎回活動終了時にスタンプは押してもらっているが、換金しなくてもいい」と、現金の受け取りには乗り気ではない。中には「スタンプ帳もいらない」と施設窓口で断るボランティアもいる。
これまで無償で活動してきた人たちにとっては、金額が少ないとはいえ、現金につながることへの違和感はぬぐえないようだ。「保険料軽減が目的」とうたうような制度に乗ってしまうことも、本来のボランティア活動と相いれないことだろう。
こうした異論を受けてか、なんと東京都千代田区は制度名から「ボランティア」の言葉をはずし、「介護保険サポーター・ポイント制度」と命名した。「ボランティアの本質的なあり方には、様々な考え方があり、混乱を招かないようにした」と説明する。議論に巻き込まれないよう後ろを向いてしまった。だが、介護保険料を財源にするなど仕組みそのものは全く同じだ。
この制度のそもそもは、一昨年に稲城市と千代田区が共同で「介護ボランティアによる保険料軽減プラン」として厚労省に要望し、同省から「保険料は年齢と収入で決まるのが法の趣旨。他の要因を加えない」と拒否された経緯がある。
そこで稲城市は再度昨年6月、内閣府に構造改革特区として提案した。今度は、厚労省が介護保険制度を大幅に改訂した直後で、しかも介護予防を目玉に打ち出していた。「介護予防の中にはいるなら」と方針を一転、積極的に受け入れ、この5月に全国の自治体に通達を発して奨励し始めたわけだ。
会員制有償ボランティアから飛躍
収入を得る福祉ボランティア活動は、これまでも「有償ボランティア」と呼ばれ普及している。地域の主婦グループが、高齢者宅での買い物や調理など家事支援として始めたもので、財団法人さわやか福祉財団などの音頭取りもあり、生協系団体も巻き込んでこの十数年の間に各地で広がった。
「無料だとずっと続けて頼みにくい」という利用者側の気持ちを察して、1時間700〜800円ほどの「謝礼」を設ける福祉系NPOは多い。サービスの受け手と出し手が会員同士だから、納得の上で成り立っている。
だが、今回の新制度は公的制度内の仕組みであり、位置づけが異なる。サービスの受け手はプロの仕事を求めるし、介護保険料の支払者は特定の会員ではない。
少額ではあるが活動報酬は介護保険からの持ち出しである。「総額に対して上限3%の枠内」と厚労省は言うが、「介護保険制度を財政難で重度者重視に改訂したとしながら、元気高齢者に金を回すのは疑問」という反発には答がない。
新制度は地域ボランティアの掘り起こしが狙いだが、これは全市町村にある社会福祉協議会(社協)の本来業務であるはず。世田谷区を除き、他の自治体はスタンプ帳の管理など運営を社協に委ねるが、実は、事業全体を社協がその予算内で手掛ければいいことだろう。
介護者をフィリピンから
一方、人手不足対策として外国人労働者問題も避けて通れない。この春、東京都文京区の特養「くすのきの郷」で、フィリピン人介護者が夜勤勤務を4年半にわたって違法就労していたことが発覚、運営していた社会福祉法人が撤退を迫られた。これを機に、にわかに、外国人介護者が現実味を帯びてきた。
同特養でフィリピン人の就労を決めた施設長は、「現行制度では介護給付があまりに少ない。その中でケアの質を維持するためには、人件費が安くてケアに熟達していた外国人に頼らざるを得なかった。同額の給与で日本人を雇うと、ケアの質が落ちてしまい、利用者のことを考えるととても出来なかった」と話していた。
介護現場での低賃金構造を浮き彫りにした事件である。人件費格差から外国人にその解決策を見いだしたことを、簡単に批判することは出来ないだろう。
福祉先進国の北欧の介護現場では、東欧や北アフリカ出身の介護者が多数働いている。現在の豊かな日本人の日常生活は、中国などアジア諸国で作られた商品で成り立っている。ユニクロの衣類はほぼ100%が中国製であることが、象徴的だ。
労働者の姿が目の前で見えない商品作りと、国内で働くサービス業とは、労働現場は異なるが、日本人の生活要素を構成するという点では違いはない。
日本政府は、関税交渉の結果として、フィリピンから看護師と介護福祉士職を2年間でそれぞれ400人と600人受け入れることを決めている。互いの国の法制度がまだ整わないため、いつから実施するかはまだ不明だ。両専門職とも日本語による国家試験に合格しないと長期就労できない。これではハードルが高すぎて、「現実的でない」という声が聞かれる。「やむなく受け入れは認めたが、本音はノー」というのが厚労省の姿勢だろう。
日本人と結婚して日本国籍を取得すれば、国家資格を得なくても福祉施設で就労できるので、その道しかないというのが実態だ。
外国人労働者については、福祉関係者や連合などがこぞって反対を表明している。ただ、フィリピンの現地を訪問すると考え方に変化が出てくるらしい。11月14日に東京で、NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」が主催する「フィリピンの介護人材養成視察報告会」が開かれた。14人の一行に加わった同法人理事長の樋口恵子さんは「外国人問題では保守的だったが、考えが変わった」と言う。
「日本で働きたいという女性たちの熱い思いに感動した。家族の誰かが海外で働いていると、家が建ち、中流階層に上昇出来るという現実を見てきた。それに、先の戦争で日本人兵士によって70万人近くが殺されたという事実を考慮すると、日本がフィリピンに門戸開放しないのはどうなのか、考えさせられた」と、複雑な心境を明かした。
報告者からは、「公務員の月収が2万円の国で、人手は沢山あるから、要介護者にかかわる介護スタッフ数は日本での6倍も増える」「ミンダナオ国際大学では日本語の研修もしている」「日本の特養待機者向けの有料老人ホームの建設が進んでいて、来年7月には1000人を受け入れられるという」――などの実情が披露された。
樋口さんは、さらに、言葉を続けて「それでも、言葉や食べ物、習慣などの異なる介護者を日本のお年寄りが受け入れることが出来るのか疑問もある。介護の熱い志は、こうした文化の違いを超えられるのだろうか。このテーマをじっくり検討していきたい」と話を結んだ。
ボランティアと外国人――。人手不足に悩む介護現場で、現実的な課題となってきているのは確かなようだ。
救世主はボランティアか外国人か(2007/11/19)
有償ボランティアを制度化
厚生労働省はこの5月、「65歳以上の高齢者が地元で福祉ボランティア活動をすれば、自分が支払う保険料が少なくなる」という新たな仕組みを介護保険制度に取り込んだ。有償ボランティアを国が公認し、その財源を介護保険に求めたのである。「高齢者が地域活動をして健康を維持すれば要介護者になる人は少なくなりコスト削減になる。だから、この活動を推奨している介護予防事業のひとつとして認める」という理由からだ。
9月から東京都稲城市が始めており、12月からは同千代田区が追随、来春には同世田谷区が導入する。稲城市が始めたのは「介護支援ボランティア制度」。高齢者が、特別養護老人ホームなど福祉施設の食堂で配膳の手助けやレクリエーションの指導、行事の手伝いなどを1時間程度すると、手帳にひとつのスタンプが押される。年度末に1スタンプを100円で換算、現金が高齢者の預金口座に振り込まれる。
現金化できるのは年間50スタンプまで。もし、50時間以上活動すると5000円の収入になる。これを保険料に回すと、同市の1カ月の平均保険料は4500円だから十分におつりがくる。
東京都世田谷区の「せたがや介護支援ボランティア制度」では、高齢者が1回2時間程度の活動をすると、50円相当のシールを張り、年間で6000円(シール120枚分)を上限に現金を渡す。
「ボランティア精神に反する」と異論
こうした介護ボランティアに対して、日本ボランティアコーディネーター協会は「活動時間に応じて換金出来る制度をボランティアと呼ぶのはおかしい」と、反対している。さらに「生活費を稼ぐために就労していたり、家族介護に追われている高齢者も多く、誰でもが参加できるわけではない。参加者だけ保険料を軽減するのは不公平」とも主張する。
ボランティア活動と報酬が結びつくと、「ボランティアという美名の下で、低賃金労働への道を開くことになりかねない」と批判するのは大阪ボランティア協会常務理事の早瀬昇さん。
人手不足を少しでも解消しようと、事業者側が積極的に制度化を要望する可能性が出てくる。「ボランティアの名目で募集すると、パートタイマーやアルバイトよりも意欲のある人が集まりやすい。だが反面、権利義務関係があいまいになり、介護サービスの低下を招きかねない」と早瀬さんは指摘する。
確かに、稲城市が決めた活動内容をみると、「散歩、外出、館内移動の補助」「話し相手」など、施設職員の通常業務と思われる行為を含んでいる。認知症高齢者へのケアは事前に十分な研修が必要であるのは言うまでもないこと。せかしたり、言動を否定するとかえって症状を重度化させかねない。
では、稲城市でボランティア活動を続けてきた人たちの反応はどうか。
会食活動を続けてきたNPO法人「支え合う会みのり」の理事長、中村久美子さんは「場所や内容を限定してボランティアと言うのはどうか、個人的には疑問があるが、厨房設備などで市から20年以上も助成金を受けているので、真正面から異論は唱えにくい立場だ」と、複雑な胸の内を打ち明ける。ただ、みのりでは積極的に取り組む計画はないという。
同市内の特養で十数人の仲間と10年前から洗濯物畳みをしている石川トミさんは、「説明を受けてノートをもらい、毎回活動終了時にスタンプは押してもらっているが、換金しなくてもいい」と、現金の受け取りには乗り気ではない。中には「スタンプ帳もいらない」と施設窓口で断るボランティアもいる。
これまで無償で活動してきた人たちにとっては、金額が少ないとはいえ、現金につながることへの違和感はぬぐえないようだ。「保険料軽減が目的」とうたうような制度に乗ってしまうことも、本来のボランティア活動と相いれないことだろう。
こうした異論を受けてか、なんと東京都千代田区は制度名から「ボランティア」の言葉をはずし、「介護保険サポーター・ポイント制度」と命名した。「ボランティアの本質的なあり方には、様々な考え方があり、混乱を招かないようにした」と説明する。議論に巻き込まれないよう後ろを向いてしまった。だが、介護保険料を財源にするなど仕組みそのものは全く同じだ。
この制度のそもそもは、一昨年に稲城市と千代田区が共同で「介護ボランティアによる保険料軽減プラン」として厚労省に要望し、同省から「保険料は年齢と収入で決まるのが法の趣旨。他の要因を加えない」と拒否された経緯がある。
そこで稲城市は再度昨年6月、内閣府に構造改革特区として提案した。今度は、厚労省が介護保険制度を大幅に改訂した直後で、しかも介護予防を目玉に打ち出していた。「介護予防の中にはいるなら」と方針を一転、積極的に受け入れ、この5月に全国の自治体に通達を発して奨励し始めたわけだ。
会員制有償ボランティアから飛躍
収入を得る福祉ボランティア活動は、これまでも「有償ボランティア」と呼ばれ普及している。地域の主婦グループが、高齢者宅での買い物や調理など家事支援として始めたもので、財団法人さわやか福祉財団などの音頭取りもあり、生協系団体も巻き込んでこの十数年の間に各地で広がった。
「無料だとずっと続けて頼みにくい」という利用者側の気持ちを察して、1時間700〜800円ほどの「謝礼」を設ける福祉系NPOは多い。サービスの受け手と出し手が会員同士だから、納得の上で成り立っている。
だが、今回の新制度は公的制度内の仕組みであり、位置づけが異なる。サービスの受け手はプロの仕事を求めるし、介護保険料の支払者は特定の会員ではない。
少額ではあるが活動報酬は介護保険からの持ち出しである。「総額に対して上限3%の枠内」と厚労省は言うが、「介護保険制度を財政難で重度者重視に改訂したとしながら、元気高齢者に金を回すのは疑問」という反発には答がない。
新制度は地域ボランティアの掘り起こしが狙いだが、これは全市町村にある社会福祉協議会(社協)の本来業務であるはず。世田谷区を除き、他の自治体はスタンプ帳の管理など運営を社協に委ねるが、実は、事業全体を社協がその予算内で手掛ければいいことだろう。
介護者をフィリピンから
一方、人手不足対策として外国人労働者問題も避けて通れない。この春、東京都文京区の特養「くすのきの郷」で、フィリピン人介護者が夜勤勤務を4年半にわたって違法就労していたことが発覚、運営していた社会福祉法人が撤退を迫られた。これを機に、にわかに、外国人介護者が現実味を帯びてきた。
同特養でフィリピン人の就労を決めた施設長は、「現行制度では介護給付があまりに少ない。その中でケアの質を維持するためには、人件費が安くてケアに熟達していた外国人に頼らざるを得なかった。同額の給与で日本人を雇うと、ケアの質が落ちてしまい、利用者のことを考えるととても出来なかった」と話していた。
介護現場での低賃金構造を浮き彫りにした事件である。人件費格差から外国人にその解決策を見いだしたことを、簡単に批判することは出来ないだろう。
福祉先進国の北欧の介護現場では、東欧や北アフリカ出身の介護者が多数働いている。現在の豊かな日本人の日常生活は、中国などアジア諸国で作られた商品で成り立っている。ユニクロの衣類はほぼ100%が中国製であることが、象徴的だ。
労働者の姿が目の前で見えない商品作りと、国内で働くサービス業とは、労働現場は異なるが、日本人の生活要素を構成するという点では違いはない。
日本政府は、関税交渉の結果として、フィリピンから看護師と介護福祉士職を2年間でそれぞれ400人と600人受け入れることを決めている。互いの国の法制度がまだ整わないため、いつから実施するかはまだ不明だ。両専門職とも日本語による国家試験に合格しないと長期就労できない。これではハードルが高すぎて、「現実的でない」という声が聞かれる。「やむなく受け入れは認めたが、本音はノー」というのが厚労省の姿勢だろう。
日本人と結婚して日本国籍を取得すれば、国家資格を得なくても福祉施設で就労できるので、その道しかないというのが実態だ。
外国人労働者については、福祉関係者や連合などがこぞって反対を表明している。ただ、フィリピンの現地を訪問すると考え方に変化が出てくるらしい。11月14日に東京で、NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」が主催する「フィリピンの介護人材養成視察報告会」が開かれた。14人の一行に加わった同法人理事長の樋口恵子さんは「外国人問題では保守的だったが、考えが変わった」と言う。
「日本で働きたいという女性たちの熱い思いに感動した。家族の誰かが海外で働いていると、家が建ち、中流階層に上昇出来るという現実を見てきた。それに、先の戦争で日本人兵士によって70万人近くが殺されたという事実を考慮すると、日本がフィリピンに門戸開放しないのはどうなのか、考えさせられた」と、複雑な心境を明かした。
報告者からは、「公務員の月収が2万円の国で、人手は沢山あるから、要介護者にかかわる介護スタッフ数は日本での6倍も増える」「ミンダナオ国際大学では日本語の研修もしている」「日本の特養待機者向けの有料老人ホームの建設が進んでいて、来年7月には1000人を受け入れられるという」――などの実情が披露された。
樋口さんは、さらに、言葉を続けて「それでも、言葉や食べ物、習慣などの異なる介護者を日本のお年寄りが受け入れることが出来るのか疑問もある。介護の熱い志は、こうした文化の違いを超えられるのだろうか。このテーマをじっくり検討していきたい」と話を結んだ。
ボランティアと外国人――。人手不足に悩む介護現場で、現実的な課題となってきているのは確かなようだ。
|
|
|
|
|
|
|
|
高齢者情報資料室 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
高齢者情報資料室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90063人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208311人
- 3位
- 酒好き
- 170692人