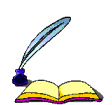後期高齢者医療制度の保険料、都で約10万2000円
医療費負担増で試算
来年4月から75歳以上を対象に創設される後期高齢者医療制度で、1人が年間に負担する平均保険料が東京都で約10万2000円、大阪府では10万1449円と見込まれることが、制度の運営主体となる両都府の広域連合の試算でわかった。
厚生労働省が試算した平均的な年金受給者の年間保険料7万4400円を大きく上回っており、全国で最高水準となりそうだ。
保険料は、都道府県ごとに設立された「後期高齢者医療広域連合」が、対象となる高齢者の総医療費や所得水準などを基に共通の方式で算定。高齢者の年金などから天引きで徴収する。
東京都の対象者は約116万人。1人あたりの老人医療費は約78万円(2004年度)で全国18位だが、年金を含めた1人あたりの所得が全国平均の1・72倍となることが影響した。対象者が約77万人の大阪府は医療費が約91万円(同)で全国3位。所得は1・14倍で、高水準の医療費と所得が保険料を押し上げた。
1人あたりの医療費が約96万円(同)で全国で最も高い福岡県は所得が全国平均の0・93倍で、保険料の試算額は約8万5000円にとどまっている。
各都道府県の広域連合は試算作業を進めており、大半は11月の広域連合議会で保険料を決定する。
同省によると、7万4400円という平均保険料は厚生年金の平均的受給者(年額208万円)のケースで、基礎年金受給者(同79万円)は1万800円と試算している。
新制度については「高齢者の中には、急激な負担増で医療を受けられなくなる人も出る」との批判もあり、与党プロジェクトチームは10月、新たに保険料負担が必要となる75歳以上について来年4〜9月末までの半年間は保険料を免除し、その後半年間は9割減額する負担増凍結案を決定。制度の見直しも検討されている。
後期高齢者医療制度 75歳以上の高齢者と、寝たきりなど障害のある65〜74歳が対象(生活保護受給者を除く)で、現行の国民健康保険などの老人保健制度から移行する。保険料は、被保険者が等しく支払う「均等割り」と、年金などの収入に応じて支払う「所得割り」で構成。
(2007年11月2日 読売新聞)
YOL内関連情報
75歳以上の医療制度(2007年2月6日 読売新聞)
市町村が連合 医療費抑制図る
75歳以上を対象に2008年度から導入される新しい高齢者医療制度の準備が活発化している。運営主体として、都道府県別に広域連合の設立が相次ぐ中、課題も見えてきた。超高齢時代の医療はどう変わるのか。(阿部文彦、内田健司)
最重要課題
「医療費適正化は避けて通れない課題だ」
全国26県で一斉に広域連合が設立された1日、高知県では、橋本大二郎知事が「高知県後期高齢者医療広域連合」設立記念式典で、市町村長や県医師会長らを前に決意を披露した。
同県の高齢化率は、全国3位の25・9%(05年国勢調査)。高齢者が長期入院する療養病床のベッド数は、人口当たりだと全国一。高齢者医療対策は、県政の最重要課題の一つとして位置付けられている。
式典に先立ち実施された連合長選挙で、県内35市町村のかじ取り役として選出された岡崎誠也高知市長は、「県全体の医療を守る観点で円滑なスタートを目指したい」と強調。今後、首長や市町村議から広域連合議会の議員(定数10)を選び、11月には保険料を決める。
医療制度改革の柱として昨年、国会で成立した新高齢者医療制度は、75歳以上の後期高齢者(生活保護受給者を除く)と、65〜74歳の寝たきりの人らが対象。加入者から保険料を徴収する保険制度だが、財源の大半は公費や現役世代からの支援金で賄われる。国民健康保険(国保)や組合健保、政府管掌健保などに加入している人も、75歳になると自動的に新制度に移行する。
責任の所在
新制度の運営主体として保険料を決めたりするのが、都道府県単位の広域連合だ。広域連合は広域的な行政事務を行う特別地方公共団体だが、都道府県単位で全国一律に設置されるのは例がない。
なぜ、広域連合なのか。
政府は当初、市町村を新高齢者医療制度の運営主体として想定していた。高齢者にとって身近な存在で、介護保険や国保の運営主体でもあるからだ。
しかし、国保の赤字に苦しむ市町村の反対が強く、都道府県も引き受けに難色を示した。とはいえ、規模を拡大して財政基盤を安定させる必要があり、「都道府県単位の広域連合」という形で落ち着いた。
現行の老人保健制度は、老人医療費の負担を現役世代に割り振る財政調整の仕組みで、運営主体が存在しない。このため、増え続ける老人医療費をだれが適正化するのかがあいまいだったが、新制度により責任の所在が明確になった。
新制度では、医療費の高低が保険料に直結するため、医療費適正化の動機付けが働きそうだ。
一人当たりの老人医療費は、最高の福岡県(約97万円)と最低の長野県(約63万円)で1・5倍も違う。今後、市町村による医療費抑制の取り組みが活発化すると期待されるが、どのように健康管理への自覚を高めるかがカギになる。
調整機能
準備が進むにつれ、課題も見え始めた。
広域連合の重要な役割に、2年ごとの保険料決定があるが、円滑に決まるのかとの懸念がある。
保険料は都道府県内で原則一律とされており、医療機関の数や保険料の徴収状況の違いを理由に、地域間対立が起きる可能性もある。広域連合議会がどう調整するのかも未知数だ。新制度の運営に直接関与しないが、都道府県の役割も重い。医療費適正化計画を策定する責務を負うからだ。介護保険と在宅医療の連携体制を整備し、医療の質を確保するなど、住民や患者の視点を重視した計画を作成する力量が問われる。
根強い懸念
先進国を見ると、独立した高齢者医療保険制度は、国民皆保険制度がない米国に65歳以上と障害者を対象にしたメディケアがある程度。日本医科大の長谷川敏彦教授(医療管理学)は「超高齢社会のパイオニアである日本の取り組みは、世界が注目する実験だ」と話す。
一方で、医療費適正化を最優先課題として掲げることへの懸念もある。
浅野史郎・前宮城県知事は「長野県の医療費の安さが手本とされるが、医療費適正化が目的だったわけではなく、地域医療を充実させた結果に過ぎない。高齢者医療の目標は、健やかな老後を県民に送ってもらうことだ」と話している。
広域連合
特定の行政事務について、既存の行政区分を変えずに都道府県や市町村が協力、広域行政を行う特別地方公共団体。国、県などから権限移譲されるため、一部事務組合に比べ独立性が高い。市町村などの組み合わせに制限はない。介護保険やごみ処理施設の運営などで活用されている。
重くなる負担
後期高齢者医療制度によって、高齢者の負担はどうなるのだろうか。
厚生労働省の試算によると、制度が発足する2008年度の保険料は、厚生年金の平均的な年金額(年208万円)の受給者は月額6200円、基礎年金受給者(年79万円)は同900円となる。また、自営業者やサラリーマンの子供と同居する基礎年金受給者(子の年収390万円)は、同3100円となる。試算はあくまで目安で、収入が高かったり、在住する都道府県の高齢者医療費が高い場合は、保険料も高くなる。
75歳以上の窓口負担は、現行と同じ原則1割(高齢者夫婦2人世帯で年収約520万円以上の現役並み所得者は3割)だが、70〜74歳は原則2割に上がる。
医療、介護の自己負担の合計額が高額になった場合の軽減措置も新たに設けられる。しかし、高齢化の進行により、医療、介護ともに保険料のアップが見込まれるため、高齢者の負担は重くなりそうだ。
[プラスα]高齢者向け民間保険
公的保険を補完する高齢者向け民間保険への関心が高まっている。
その代表が、病歴があっても加入できる「無選択保険」。通常の医療保険は医師の診査や病歴の告知が必要だが、このタイプはどちらも不要。ただし、「契約以前の既往症は対象にならない」などの細かな免責事項があり、注意が必要だ。高齢者に多い糖尿病、高血圧疾患、がんなどの生活習慣病を手厚く保障する保険もある。
一方で、苦情も近年急増している。支払われるべき保険金が支払われないなどのトラブルのほか、パンフレットやテレビ広告の説明不足による苦情も多い。
国民生活センターでは、保障内容を綿密に確認したり、通院歴などの告知を口頭で済ませず、書類に記入することなどを助言。トラブルが起きた場合は、都道府県や政令指定都市などの消費生活センターに相談するよう呼びかけている。
公的保険には、自己負担を一定の金額で抑える高額療養費制度もある。貯金や年金収入を勘案したうえで契約したい。(彦)
新制度の主体、後期高齢者医療広域連合が26県で発足
(2007年2月2日 読売新聞)
75歳以上を対象にした新たな高齢者医療制度の運営主体となる後期高齢者医療広域連合が1日、全国26県で一斉に発足した。
新制度では保険料を広域連合ごとに決めることになっており、2008年4月の制度スタートに向けた準備作業が各地で本格化する。
広域連合は地方自治体の一種で、都道府県ごとに全市町村が集まって設立される。すでに設立されていた長崎など7府県と合わせた広域連合の数は33となり、3月中には全国で出そろう。
現行制度では、高齢者は市町村単位の国民健康保険、大企業の組合健康保険、中小企業従業員の政府管掌健康保険など別々の制度に加入している。08年度以降、75歳以上と65〜74歳の寝たきりの人など(生活保護受給者は除く)は、広域連合ごとに運営される新制度に加入する。保険料は、地域ごとの医療費水準を基に決められる。これまで被扶養者で保険料を払っていなかった高齢者も、所得に応じて保険料を徴収される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
75歳以上医療、公費負担の割合は「4対1対1」
(2006年1月26日 読売新聞)
厚生労働省は25日、2008年度から75歳以上の高齢者が加入する「後期高齢者医療制度」の概要を明らかにした。
国と都道府県、市町村がそれぞれ4対1対1の割合で公費を負担し、高齢者からは、年金からの天引きや口座振替などで保険料を徴収する。
高齢者の保険料は、原則均一の応益部分と所得比例の応能部分に分かれ、厚生年金の受給額が年208万円のモデル受給者の場合、保険料が全体で月額6200円になるとしている。
患者が病院などで払う窓口負担は1割で、残る9割を公費と保険料で折半する。
また、後期高齢者医療制度の創設と合わせ、国民健康保険に加入している65〜74歳の前期高齢者についても、年金からの保険料の天引きを導入する。
|
|
|
|
|
|
|
|
高齢者情報資料室 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
高齢者情報資料室のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- パニック障害とうつ病
- 8447人
- 2位
- 一行で笑わせろ!
- 82528人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208286人