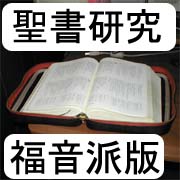久しぶりの書き込み、これも学校で調べたもの(^^;;
まだまだ、研究の余地はありまくりです。
---------------------------------------------
1. 序
リベラルな信仰を持っている人の間では、セカンドチャンスといって死んだ後も、悔い改めて救われるチャンスがあると考える人たちがいる。その根拠となる聖書箇所が本選択レポートで取り上げる。第1ペテロの手紙 3章19節である。はたして、本当にそのように死後の救いの可能性がると言うことができるだろうか? 様々な解釈説を見ながら考察する。
2. 聖書箇所と文脈
聖書箇所
『キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは、肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神のみもとに導くためでした。その霊において、キリストは捕らわれの霊たちのところに行って、みことばを語られたのです。昔、ノアの時代に、箱舟が造られていた間、神が忍耐して待っておられたときに、従わなかった霊たちのことです。
(1ペテロ3:18-20a)』
文脈
この箇所は8節『最後に申します。あなたがたはみな、心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、あわれみ深く、謙遜でありなさい。』という兄弟愛の勧めから、14・15節『いや、たとい義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ、心の中でキリストを主としてあがめなさい。そして、あなたがたのうちにある希望について説明を求める人には、だれにでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。』と苦しみの中においても兄弟愛をなし、そのような状況の中にあっても兄弟愛をさせる根拠たる希望を弁明できるようにせよ。と勧めの内容が発展し、17節『もし、神のみこころなら、善を行って苦しみを受けるのが、悪を行って苦しみを受けるよりよい』として、18節以降苦しみの中でも善い業(兄弟愛)をなすことの方がよりよい解説をキリストの例を模範にする形で提示している。問題の19節は苦しみの中で兄弟愛をなす根拠を説明する文脈の中に配置されているのである。
3. 緒解釈説
1ペテロ3:19は上記のような文脈の中に配置されているわけであるが、その解釈には諸説がある。また、諸説の着眼するポイントも、「『その霊において』とはどのような状態にあってのことか?」「『捕らわれの霊たち』とは誰の事を指すのか?」「『みことばを宣べ伝えた』とあるがどのような内容であったのか?」複数ある。 まずは、緒解釈説を一覧する。
解釈説1:
『捕らわれの霊たちに宣教をしたのは、キリストではなくエノクである。』
解説1:
原文の書き出しが、『ἐν ᾡ̂ καὶ』となっているが、古くある大文字写本は全て大文字で文字間もあいていなかったため、本来『エノクもまた・・・』となっていたものが、『ἐν ᾡ̂ καὶ』になってしまった。現在の書き出しは異読である推測する。(R・ハリス)
解説2:
『エノクは神とともに歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。(創世記5:24)』に基づくユダヤ教の伝承があり、その伝承によればエノクが最後の審判にあずかる。という。 この解説だと、エノクは霊に福音を語ったのではなく、神にそむいた御使いに最後の審判を告げたと解釈する。(J・モファット)
難点:
現在の本文研究及び写本の証拠は解説1のような異読の可能性を示していない。文脈からここで突然エノクの伝説を挿入するのは不適当である。
解釈説2:
『受肉以前のキリストがノアの時代に聖霊によって宣教した。』
解説1:
『霊において』を受肉以前のキリストが聖霊によって行ったことと解釈する。『捕らわれの霊』は、ノアの時代は宣教の対象であったが、『今』は捕らわれている。と解釈する。つまり、死者が捕らわれているハデスにキリストが行ったわけではない。という解釈。(アウグスティヌス、トマス・アクナス、J・B・ライトフット)
解釈説3:
『使徒たちが罪に捕らわれている人々に聖霊によってキリストの名代として遣われ、宣教した。』
解説1:
『霊において』というのは、使徒たちが霊、つまり聖霊によってキリストの代わりに、『捕らわれの霊』つまり罪に捕らわれている人々に福音を伝えた。と理解する。20節に対しては、ノアの頃8名しか救われなかったが、使徒たちの時代には数千人の人々が一挙に救われたことを暗示しているとする。(グロティウス、G・トマス)
解釈説4:
『キリストは十字架につけられて死んだ後、そして復活する前に、霊において生かされて、ハデスに捕らわれている霊たちに宣べ伝えた』
解説1:
この解釈においては、『霊において』というのは、キリストは十字架につけられて死んだ後、そして復活する前の状態であると理解する。
4-1-1 『宣べ伝えたのは、福音ではなく、断罪である』
解説4-1:
該当箇所で用いられている「宣べ伝える」に相当するギリシャ語はκηρυσσωで、この単語は普通、喜びの訪れを告げる、福音を告げるのには用いられない。(1コリント9:27は除く)また、ペテロの手紙で4回福音の宣言について言及しているが、そのいずれにもこの単語は用いられていない。もし、福音を宣べ伝えるのだとすると、ευαγγελιζωを用いるほうが適切である。それゆえ、この箇所は福音を告げ知らせているのではなく、断罪していると理解する。(スティブス)
4-1-2 『宣べ伝えたのは、福音ではなく、勝利の宣言である』(Hard Saying)
4-1-2の解説:
福音を伝えたのではないことは、4-1-1と同じ理由。また、勝利の宣言の方がより文脈に適しているため。(苦しみの中で兄弟愛をなす根拠としては、断罪よりキリストの勝利の方が適している。)
4-2-1 『『捕らわれの霊たち』とは、死んだ悪しき人たちを含むかもしれないが、主には超自然的な天的存在を意味している。』(セルウィン)
4-2-2 『『捕らわれの霊たち』とは、死んだ悪しき人たちを含まない、主には超自然的な天的存在、堕落した天使を意味している。』(Hard Saying)
4-2-2の解説:
この箇所で霊として使われているギリシャ語πνευμαという単語の新約聖書 (New Testament) においての使用を見るとき、それが死んだ人々についてほとんど決して使われない。また、それが死んだ人々について使われるときは、それが死んだ人々(例えば、 ヘブル書 12:23)であることを明確にするいずれかの方法で常に限定されている。しかし、この箇所でそのように死んだ人たちの霊であるという限定はなされていない。それゆえ、『捕らわれの霊たち』を死んだ人々として理解することはできない。
しかし、20節で『ノアの時代に・・・従わなかった霊たちのことです。』とあるので、創世記6:2の『神の子ら』を指していると考える。この『神の子ら』という用語は、神の民の群れからくる霊的な存在に関連しており、新約聖書ユダ6では、『自分のおるべき所を捨てた』存在としてあげられ、?ペテロ2:4では罪を犯した御使いとして取り上げられている。さらにユダヤの他の作品(エノク書)では、「これらの堕落した天使が刑務所に捕らわれている」とある。これら罪を犯した天使はユダヤ教徒の間で捕らわれている者として知られているもので、その面からも『捕らわれの霊たち』とは、死んだ悪しき人たちを含まない、主には超自然的な天的存在、堕落した天使を意味している。と考えられる。
4-2-3 『『捕らわれの霊たち』とは、救いを待ち望んでいた人々である。』(カルヴァン)
4-2-3の解説
『捕らわれ』を「物見やぐら」と理解している。
4-2-4-1 『『捕らわれの霊たち』とは、ノアの時代に神に従わなかった人たちのことであり、第2の悔い改めのチャンスを与えた。』 (フロンミューラー)
4-2-4-2 『『捕らわれの霊たち』とは、ノアの時代に神に従わなかった人たちと同様に不信仰のために死に、ハデスで苦しんでいる霊のことであり、第2の悔い改めのチャンスを与えた。』 (黒崎幸吉)
4. 妥当性のある解釈の選出と結論
以上の緒解釈説から「『その霊において』とはどのような状態にあってのことか?」「『捕らわれの霊たち』とは誰の事を指すのか?」「『みことばを宣べ伝えた』とあるがどのような内容であったのか?」という三つのポイントで妥当性があると思われる解釈を選出する。
1)『その霊において』とはどのような状態にあってのことか?
解釈説4:『キリストは十字架につけられて死んだ後、そして復活する前に、霊において生かされて、ハデスに捕らわれている霊たちに宣べ伝えた』が妥当性があるように思われる。他に「受肉以前のキリストがノアの時代に聖霊によって宣教した。」や「使徒たちが罪に捕らわれている人々に聖霊によってキリストの名代として遣われ、宣教した。」といった解釈もあったが、参考にした資料からはそのように解釈できる客観的な理由が見当たらなかった。解釈説4もそれほど深い根拠は述べられていないが、18節の『肉においては死に渡され、霊においては生かされて、』ということばに続く19節の解釈であるため、妥当性があると思われる。
2)『捕らわれの霊たち』とは誰の事を指すのか?
4-2-2 『『捕らわれの霊たち』とは、死んだ悪しき人たちを含まない、主には超自然的な天的存在、堕落した天使を意味している。』が比較的妥当性があるように思われる。霊の用例からの死んだ人々でないということは妥当だと思われるため、他のノア時代の不従順な人たちや神を信じずに死んだ人たちというのは除外される。しかし、「超自然的な天的存在、堕落した天使を意味している」を意味しているかどうかは根拠としている聖書箇所を見てみると、直接的に結びつくものではないので、さらなる検討の余地があると思われる。
3)『みことばを宣べ伝えた』とあるがどのような内容であったのか?
4-1-2 『宣べ伝えたのは、福音ではなく、勝利の宣言である』(Hard Saying)が妥当であると思われる。これも4-1-1と同様の原語の用例からの検証で、福音が述べられたわけではない。ということは、妥当性がある。また、『捕らわれの霊』に対しての断罪ではなく、勝利の宣言であるというのは、苦しみの中で兄弟愛をなす根拠としての文脈的配置としても妥当性があると思われる。ただ、結果的には同じことなのかもしれない。
参考文献
・ Hard Saying of the bible, IVP
・ 新聖書注解、いのちのことば社
・ Expositor’s Bible Commentary New Testament, Frank E.Gaebelein, Zondervan
・ Michaels, J. R. 1998. Vol. 49: Word Biblical Commentary : 1 Peter (electronic ed.).
・ The New International Commentary of The New Testament, The First Epistle of Peter, Peter H. Davids
まだまだ、研究の余地はありまくりです。
---------------------------------------------
1. 序
リベラルな信仰を持っている人の間では、セカンドチャンスといって死んだ後も、悔い改めて救われるチャンスがあると考える人たちがいる。その根拠となる聖書箇所が本選択レポートで取り上げる。第1ペテロの手紙 3章19節である。はたして、本当にそのように死後の救いの可能性がると言うことができるだろうか? 様々な解釈説を見ながら考察する。
2. 聖書箇所と文脈
聖書箇所
『キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは、肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神のみもとに導くためでした。その霊において、キリストは捕らわれの霊たちのところに行って、みことばを語られたのです。昔、ノアの時代に、箱舟が造られていた間、神が忍耐して待っておられたときに、従わなかった霊たちのことです。
(1ペテロ3:18-20a)』
文脈
この箇所は8節『最後に申します。あなたがたはみな、心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、あわれみ深く、謙遜でありなさい。』という兄弟愛の勧めから、14・15節『いや、たとい義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ、心の中でキリストを主としてあがめなさい。そして、あなたがたのうちにある希望について説明を求める人には、だれにでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。』と苦しみの中においても兄弟愛をなし、そのような状況の中にあっても兄弟愛をさせる根拠たる希望を弁明できるようにせよ。と勧めの内容が発展し、17節『もし、神のみこころなら、善を行って苦しみを受けるのが、悪を行って苦しみを受けるよりよい』として、18節以降苦しみの中でも善い業(兄弟愛)をなすことの方がよりよい解説をキリストの例を模範にする形で提示している。問題の19節は苦しみの中で兄弟愛をなす根拠を説明する文脈の中に配置されているのである。
3. 緒解釈説
1ペテロ3:19は上記のような文脈の中に配置されているわけであるが、その解釈には諸説がある。また、諸説の着眼するポイントも、「『その霊において』とはどのような状態にあってのことか?」「『捕らわれの霊たち』とは誰の事を指すのか?」「『みことばを宣べ伝えた』とあるがどのような内容であったのか?」複数ある。 まずは、緒解釈説を一覧する。
解釈説1:
『捕らわれの霊たちに宣教をしたのは、キリストではなくエノクである。』
解説1:
原文の書き出しが、『ἐν ᾡ̂ καὶ』となっているが、古くある大文字写本は全て大文字で文字間もあいていなかったため、本来『エノクもまた・・・』となっていたものが、『ἐν ᾡ̂ καὶ』になってしまった。現在の書き出しは異読である推測する。(R・ハリス)
解説2:
『エノクは神とともに歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。(創世記5:24)』に基づくユダヤ教の伝承があり、その伝承によればエノクが最後の審判にあずかる。という。 この解説だと、エノクは霊に福音を語ったのではなく、神にそむいた御使いに最後の審判を告げたと解釈する。(J・モファット)
難点:
現在の本文研究及び写本の証拠は解説1のような異読の可能性を示していない。文脈からここで突然エノクの伝説を挿入するのは不適当である。
解釈説2:
『受肉以前のキリストがノアの時代に聖霊によって宣教した。』
解説1:
『霊において』を受肉以前のキリストが聖霊によって行ったことと解釈する。『捕らわれの霊』は、ノアの時代は宣教の対象であったが、『今』は捕らわれている。と解釈する。つまり、死者が捕らわれているハデスにキリストが行ったわけではない。という解釈。(アウグスティヌス、トマス・アクナス、J・B・ライトフット)
解釈説3:
『使徒たちが罪に捕らわれている人々に聖霊によってキリストの名代として遣われ、宣教した。』
解説1:
『霊において』というのは、使徒たちが霊、つまり聖霊によってキリストの代わりに、『捕らわれの霊』つまり罪に捕らわれている人々に福音を伝えた。と理解する。20節に対しては、ノアの頃8名しか救われなかったが、使徒たちの時代には数千人の人々が一挙に救われたことを暗示しているとする。(グロティウス、G・トマス)
解釈説4:
『キリストは十字架につけられて死んだ後、そして復活する前に、霊において生かされて、ハデスに捕らわれている霊たちに宣べ伝えた』
解説1:
この解釈においては、『霊において』というのは、キリストは十字架につけられて死んだ後、そして復活する前の状態であると理解する。
4-1-1 『宣べ伝えたのは、福音ではなく、断罪である』
解説4-1:
該当箇所で用いられている「宣べ伝える」に相当するギリシャ語はκηρυσσωで、この単語は普通、喜びの訪れを告げる、福音を告げるのには用いられない。(1コリント9:27は除く)また、ペテロの手紙で4回福音の宣言について言及しているが、そのいずれにもこの単語は用いられていない。もし、福音を宣べ伝えるのだとすると、ευαγγελιζωを用いるほうが適切である。それゆえ、この箇所は福音を告げ知らせているのではなく、断罪していると理解する。(スティブス)
4-1-2 『宣べ伝えたのは、福音ではなく、勝利の宣言である』(Hard Saying)
4-1-2の解説:
福音を伝えたのではないことは、4-1-1と同じ理由。また、勝利の宣言の方がより文脈に適しているため。(苦しみの中で兄弟愛をなす根拠としては、断罪よりキリストの勝利の方が適している。)
4-2-1 『『捕らわれの霊たち』とは、死んだ悪しき人たちを含むかもしれないが、主には超自然的な天的存在を意味している。』(セルウィン)
4-2-2 『『捕らわれの霊たち』とは、死んだ悪しき人たちを含まない、主には超自然的な天的存在、堕落した天使を意味している。』(Hard Saying)
4-2-2の解説:
この箇所で霊として使われているギリシャ語πνευμαという単語の新約聖書 (New Testament) においての使用を見るとき、それが死んだ人々についてほとんど決して使われない。また、それが死んだ人々について使われるときは、それが死んだ人々(例えば、 ヘブル書 12:23)であることを明確にするいずれかの方法で常に限定されている。しかし、この箇所でそのように死んだ人たちの霊であるという限定はなされていない。それゆえ、『捕らわれの霊たち』を死んだ人々として理解することはできない。
しかし、20節で『ノアの時代に・・・従わなかった霊たちのことです。』とあるので、創世記6:2の『神の子ら』を指していると考える。この『神の子ら』という用語は、神の民の群れからくる霊的な存在に関連しており、新約聖書ユダ6では、『自分のおるべき所を捨てた』存在としてあげられ、?ペテロ2:4では罪を犯した御使いとして取り上げられている。さらにユダヤの他の作品(エノク書)では、「これらの堕落した天使が刑務所に捕らわれている」とある。これら罪を犯した天使はユダヤ教徒の間で捕らわれている者として知られているもので、その面からも『捕らわれの霊たち』とは、死んだ悪しき人たちを含まない、主には超自然的な天的存在、堕落した天使を意味している。と考えられる。
4-2-3 『『捕らわれの霊たち』とは、救いを待ち望んでいた人々である。』(カルヴァン)
4-2-3の解説
『捕らわれ』を「物見やぐら」と理解している。
4-2-4-1 『『捕らわれの霊たち』とは、ノアの時代に神に従わなかった人たちのことであり、第2の悔い改めのチャンスを与えた。』 (フロンミューラー)
4-2-4-2 『『捕らわれの霊たち』とは、ノアの時代に神に従わなかった人たちと同様に不信仰のために死に、ハデスで苦しんでいる霊のことであり、第2の悔い改めのチャンスを与えた。』 (黒崎幸吉)
4. 妥当性のある解釈の選出と結論
以上の緒解釈説から「『その霊において』とはどのような状態にあってのことか?」「『捕らわれの霊たち』とは誰の事を指すのか?」「『みことばを宣べ伝えた』とあるがどのような内容であったのか?」という三つのポイントで妥当性があると思われる解釈を選出する。
1)『その霊において』とはどのような状態にあってのことか?
解釈説4:『キリストは十字架につけられて死んだ後、そして復活する前に、霊において生かされて、ハデスに捕らわれている霊たちに宣べ伝えた』が妥当性があるように思われる。他に「受肉以前のキリストがノアの時代に聖霊によって宣教した。」や「使徒たちが罪に捕らわれている人々に聖霊によってキリストの名代として遣われ、宣教した。」といった解釈もあったが、参考にした資料からはそのように解釈できる客観的な理由が見当たらなかった。解釈説4もそれほど深い根拠は述べられていないが、18節の『肉においては死に渡され、霊においては生かされて、』ということばに続く19節の解釈であるため、妥当性があると思われる。
2)『捕らわれの霊たち』とは誰の事を指すのか?
4-2-2 『『捕らわれの霊たち』とは、死んだ悪しき人たちを含まない、主には超自然的な天的存在、堕落した天使を意味している。』が比較的妥当性があるように思われる。霊の用例からの死んだ人々でないということは妥当だと思われるため、他のノア時代の不従順な人たちや神を信じずに死んだ人たちというのは除外される。しかし、「超自然的な天的存在、堕落した天使を意味している」を意味しているかどうかは根拠としている聖書箇所を見てみると、直接的に結びつくものではないので、さらなる検討の余地があると思われる。
3)『みことばを宣べ伝えた』とあるがどのような内容であったのか?
4-1-2 『宣べ伝えたのは、福音ではなく、勝利の宣言である』(Hard Saying)が妥当であると思われる。これも4-1-1と同様の原語の用例からの検証で、福音が述べられたわけではない。ということは、妥当性がある。また、『捕らわれの霊』に対しての断罪ではなく、勝利の宣言であるというのは、苦しみの中で兄弟愛をなす根拠としての文脈的配置としても妥当性があると思われる。ただ、結果的には同じことなのかもしれない。
参考文献
・ Hard Saying of the bible, IVP
・ 新聖書注解、いのちのことば社
・ Expositor’s Bible Commentary New Testament, Frank E.Gaebelein, Zondervan
・ Michaels, J. R. 1998. Vol. 49: Word Biblical Commentary : 1 Peter (electronic ed.).
・ The New International Commentary of The New Testament, The First Epistle of Peter, Peter H. Davids
|
|
|
|
|
|
|
|
聖書研究 福音派版 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
聖書研究 福音派版のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82541人
- 2位
- 酒好き
- 170695人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90065人