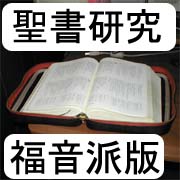2テモテ2:1-7 [苦しみを共にするクリスチャン]
1. 序論
クリスチャンに与えられたもっとも大きな使命は、キリストの福音を伝えることである。しかし、実際に私たちは福音宣教と聞くときどうしてもしり込みをしてしまいがちである。なぜ? 宣教の働きが困難を伴うものであるということを私たちが肌で感じ知っているからである。パウロの愛弟子テモテもまたその牧会者としての生活の中で困難を肌で感じ、臆病になっていた。パウロはこのテモテに対して手紙を送っている。私たちはパウロからテモテに対して送られた言葉を通して、献身者の歩みがどのようなものであるのかをもう一度確認したいと思う。
2. 書簡の背景と文脈
書簡の背景
第2テモテへの手紙は、新約聖書に収められているパウロが書いた手紙の中でも、恐らく最後に書かれたものである。しかも、パウロが殉職する前の時期、4:6-8で「私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。」と語っていることからも、パウロ自身、自分のこの世における最後の時が近いことを意識していた。パウロはこの自分に与えられた最後の時間に、伝説ではエペソで牧会をしており、比較的気弱だったと思われるパウロの愛弟子テモテに向かって福音宣教について、その召しについて、そして、牧会について語り励ましている。
パウロがこの手紙を書きとめるにあたって、彼が今まで福音を伝える働きをしてきたうえで、教えられたこと、思わされたこと、そして、確信したことのすべてが心にあり、そして、パウロと歩みをともにし多く教えられたテモテは既に多くのことをパウロから引き継いでいたため、この手紙の短さ以上の圧縮された福音宣教に対する思いが込められていると思われる。それゆえ、この手紙は他の手紙で用いられているような表現を説明を伴わずに用いられており、テモテが既に聞いているという前提の上で書かれている。その為、この手紙を読むにあたってパウロがどのように福音と福音宣教の召しを理解することが必要である。
文脈
今日の箇所2:1-7の前に、パウロは1章の6-14節で「福音宣教に召されているということは、それに伴う苦しみをともにすることである。」と伝えている。確かにパウロが歩んだ宣教の歩みは平坦なものではなく、現実死に直面する苦しみを伴ったものであった。それは同じ福音宣教に召された者も負うべきものであり、13節 「キリスト・イエスにある信仰と愛をもって、私から聞いた健全なことばを手本にしなさい。」とはげました。
パウロのこの世における最後時期、パウロに従い続ける者とパウロから離れる者が当然でてきた。1:15は、パウロから離れた人の例、16-18節はパウロに従った人の例としてオネシポロをあげている。
3. 解釈
強くされ続ける
「そこで」
1節のはじめに「そこで」とある。これは明らかにその前の節、1:15-18に書かれているパウロから離れた人たちとパウロに従った人たちの例を踏まえている言葉である。
パウロから離れていった人たち(1:15)も、はじめはパウロのことばを聞いて従った人たちであった。しかし、パウロの投獄、パウロの最後の時が近づくにつれ、体験する困難に耐えることができずに離れていった。その中にはテモテの知人もいた。それとは逆にオネシポロはパウロの投獄も物ともせずにパウロを愛し続けていた。
「そこで」という言葉の中には、パウロの投獄に見えるような苦しみが伴う状況にあって、パウロが歩んだ道から離れる事とパウロに従うという2つの選択肢の中から一つを選ぶことが要求される。ということを示している。そして、パウロは、パウロから離れた人の例より、パウロを愛したオネシポロに対する記載が後半に配置され、長めに言及されていることからも、当然、パウロはテモテにこのオネシポロに習うことを求めている。
「キリスト・イエスにある恵みによって強くなりなさい。」
離れるか、従うかを選ぶ状況にあって、従う方を選ぶように要求した上で、パウロは「キリスト・イエスにある恵みによって強くなりなさい。」と言うのである。
しかも、新改訳ではニュアンスが伝わりにくいかもしれないが、非常に強い命令である。
原語のニュアンスが分かりやすいように言い換えるのならば、「あなたは、キリスト・イエスと共にある恵みによって強くさせられ続けなさい。」 となる。明らかに苦難が見える状況にあって、そして、あえて苦難が伴う道を選ばなければいけない時、パウロがその生き方を通して示した道、オネシポロが選んだ道を選んで歩むために、自分の強さや力に頼って歩むのではなく、キリスト・イエスと共にある恵みによって強くさせられ続けて歩みなさい。 と言っているのである。
気弱なテモテ、臆病になりがちだったテモテに対して、苦しみを伴う道を歩むことを要求するためには、福音宣教の召しは自分の力ではなく、キリストにある恵みに強められ続けられることによってまっとうされることをもう一度思い起こさせる必要があったのだろう。
福音宣教の召しは牧師や宣教師だけに任されているものではない、すべてのクリスチャンに対して与えられているものである。日本は宗教の自由を認めているが、学校や会社、また、ノンクリスチャンの配偶者がいる家庭において宣教活動をすることを認めていない場合が多い。私たちはその時においてパウロの同労者たちと同じように宣教活動から離れるか、続けるかの選択を迫られる。私たちはどのようにして続けることができるのだろうか。それは、何よりキリストの恵みに強められ続けることによってのみ続けることができるのである。私たちは耐えずキリストと交わり強められ続けなければならない。
ゆだねる
パウロは続いてテモテにパウロから聞いたことを忠実な人たちにゆだねることを勧める。
「私から聞いたこと」とは特定の何かではなく、パウロがその福音宣教の歩みの中で語ってきたキリスト教信仰と福音のことである。それはパウロからテモテへ直接語られただけでなく、多くの証人を通して(前でと訳されているが通しての方が適切)テモテへ語られ、委ねられてた。パウロはテモテに福音宣教の歩みを引き継ぐだけでなく、テモテ自身もこの福音宣教の歩みを引き継ぐでことのできる「教える力のある忠実な(信頼できる)人たち」に委ねることように勧めている。
福音宣教における苦しみを共にする歩みは、自分だけに留まるのではなく、引継ぎ続けていくべきものなのである。主が再びこられる時まで、引継ぎ続けることで、はじめてキリストから人に託されたこの召しをまっとうしたと言えるのではないだろうか。私たちは自らが福音宣教をするのと同時に、この働きをゆだねていく必要があるのである。
徹底的な献身
3節で「キリスト・イエスのりっぱな兵士として、私と苦しみをともにしてください。」とパウロは言う。苦しみをともにしてください。とは、1:8で既にテモテに対して言われていることであるが、その様子を「キリスト・イエスのりっぱな兵士」と表現している。この兵士、そして、5節、6節の競技者、農夫という表現はパウロが信仰者の歩み、パウロ自身の歩みをさして他の手紙で用いた表現であるが、パウロは4-6節の3つの比喩的表現を用いて、キリストの兵士として苦しみを共にするための徹底的な献身を伝えている。
「兵士」(4節)
4節は福音宣教の献身者を兵士として比喩的に表現している。その強調ポイントは、「日常生活のことに掛かり合っている者はだれもありません。」である。この強調は献身者は世俗とはなれなければならない、中世の修道院のような閉鎖的な空間に身を置かなければならないということではない。そうではなくて、献身者の目的意識をどこに置くか。 ということである。兵士は何より「徴募した者を喜ばせる」ことを目的としなければならない、徴募した者とはその部隊の指揮官である。兵士は指揮官の目的を知り、また何を望んでいるかをしり、それを達成することを第一の目標としなければならない。福音宣教の献身者にとって指揮官とはキリスト・イエスであり、その喜びは福音が世界に広められることである。パウロが教会の牧会をする中で、また、宣教の働きをする中で、キリストの喜びである福音が広められる事より他の事に目向けさせようとする物事があった、それは福音宣教に伴う日常生活の苦しみや困難であったり、この世のさまざまな誤った教えであったり、さらに言うならば信徒の党派心からくる分裂なのがあった。しかし、献身者が一番の目的とすべきは指揮官たるキリストに仕えることであり、キリストの御心にすべてをゆだねる徹底的な献身である。それこそが苦しみを共にする献身者に求められる姿の一つである。
牧師や宣教師という職業にいなかったとしても、クリスチャンは献身者であり、御言葉が求める姿は同じである。働いてお金を稼ぐのは当然である。学生が知識を学ぶのも当然である。夫婦がそれぞれの立場で家族を愛し、家族のために仕えるのも当然である。しかし、例えどのような職業や立場にあったとしても、キリスト者の歩みとその目的はキリストに仕えるということであり、それぞれの仕事や立場はその延長線上にある。
「競技者」(5節)
献身者の第二の比喩的表現は「競技者」である。その強調のポイントは、「規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません」ということである。ルールの全くない競技は競技として成り立つことができない。競技者がその競技のルールを守らないのならば、すでに競技者ではないのである。この箇所には「規定」という言葉が、献身者にとって具体的に何をさしているのかを示す説明がない。しかし、それはテモテが既に聞いた言葉の中にあった。つまり、パウロが伝えたメッセージ、キリストのことばの中にあった。キリストに従う献身者の歩みは、御言葉という規則、道に従う歩みである。
今の時代、包括主義や自由主義が盛んに強調されている。しかし、聖書が教えるキリスト者、献身者の歩みは、どのような歩みをしても同じであるといった無分別な包括主義に陥るのではなく、与えられた自由を用いて感情や直感のまま勝手に振舞うのを容認するのでもなく、御言葉がなんと教え、どのように導いているかを注意深く聞いてそれに徹底的に従う歩みが求められているのである。
そうすることによって、競技者が競技し終えたときに、その勝者に対して花束の祝福の冠をかぶせられるように、献身者として歩みをこの世においてまっとうしたとき、献身者に与えられる祝福の冠を私たちは与えられるのである。
「農夫」(6節)
最後の献身者の比喩的表現は「農夫」であり、その強調ポイントは「労苦した農夫」ということである。この「労苦する」とは「骨を折って働くこと」であり、それは肉体的にも、精神的にも、そして、霊的にも努力することである。キリスト・イエスのりっぱな兵士として、苦労をともにする献身者の歩みは、全人格的に骨を折るという行動を伴う徹底的な献身でなければならない。
そして、この節でも労苦した献身者が、「まず第一に収穫の分け前にあずかるべきです。」と述べている。献身者は今、楽に過ごすというより、やがて与えられる分け前に目を向けながら、今の世にあっては、自分ができる最善を尽くすべきなのである。
4. 結論
苦しみをともにする献身者の歩みを御言葉から学んだ。それはキリストの喜びをまず第一にし、キリストの御言葉に従い、全人格的に労苦する行動を伴う歩みである。私たちがこの歩みをしようとするとき、それはいかにも苦しく避けて通りたいと思う。そう思う時、2:1の御言葉に目を留めましょう。「あなたはキリスト・イエスにある恵みによって強くされ続けなさい。」
献身者として苦しみを共にする歩みは、主の恵みにより頼むことからはじまる。だから、祈りましょう。「主よ。どうかパウロより、テモテよりも弱い私たちを福音宣教の苦しみを共にする献身者へと日々、強めてください。」
参考文献
・ 新聖書注解 いのちのことば社
・ Expositor’s Bible Commentary Old Testament, Frank E.Gaebelein, Zondervan
・ THE INTERNATIONAL CRITICAL COMMENTARY, THE PASTORAL EPISTLES, L. HOWARD MARSHALL, T&T CLARK
・ NEW INTERNATIONAL BIBLICAL COMMENTARY, 1 AND 2 TIMOTH, TITUS, GORDON D. FEE, HENDRICKSON PUBLISHERS
1. 序論
クリスチャンに与えられたもっとも大きな使命は、キリストの福音を伝えることである。しかし、実際に私たちは福音宣教と聞くときどうしてもしり込みをしてしまいがちである。なぜ? 宣教の働きが困難を伴うものであるということを私たちが肌で感じ知っているからである。パウロの愛弟子テモテもまたその牧会者としての生活の中で困難を肌で感じ、臆病になっていた。パウロはこのテモテに対して手紙を送っている。私たちはパウロからテモテに対して送られた言葉を通して、献身者の歩みがどのようなものであるのかをもう一度確認したいと思う。
2. 書簡の背景と文脈
書簡の背景
第2テモテへの手紙は、新約聖書に収められているパウロが書いた手紙の中でも、恐らく最後に書かれたものである。しかも、パウロが殉職する前の時期、4:6-8で「私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。」と語っていることからも、パウロ自身、自分のこの世における最後の時が近いことを意識していた。パウロはこの自分に与えられた最後の時間に、伝説ではエペソで牧会をしており、比較的気弱だったと思われるパウロの愛弟子テモテに向かって福音宣教について、その召しについて、そして、牧会について語り励ましている。
パウロがこの手紙を書きとめるにあたって、彼が今まで福音を伝える働きをしてきたうえで、教えられたこと、思わされたこと、そして、確信したことのすべてが心にあり、そして、パウロと歩みをともにし多く教えられたテモテは既に多くのことをパウロから引き継いでいたため、この手紙の短さ以上の圧縮された福音宣教に対する思いが込められていると思われる。それゆえ、この手紙は他の手紙で用いられているような表現を説明を伴わずに用いられており、テモテが既に聞いているという前提の上で書かれている。その為、この手紙を読むにあたってパウロがどのように福音と福音宣教の召しを理解することが必要である。
文脈
今日の箇所2:1-7の前に、パウロは1章の6-14節で「福音宣教に召されているということは、それに伴う苦しみをともにすることである。」と伝えている。確かにパウロが歩んだ宣教の歩みは平坦なものではなく、現実死に直面する苦しみを伴ったものであった。それは同じ福音宣教に召された者も負うべきものであり、13節 「キリスト・イエスにある信仰と愛をもって、私から聞いた健全なことばを手本にしなさい。」とはげました。
パウロのこの世における最後時期、パウロに従い続ける者とパウロから離れる者が当然でてきた。1:15は、パウロから離れた人の例、16-18節はパウロに従った人の例としてオネシポロをあげている。
3. 解釈
強くされ続ける
「そこで」
1節のはじめに「そこで」とある。これは明らかにその前の節、1:15-18に書かれているパウロから離れた人たちとパウロに従った人たちの例を踏まえている言葉である。
パウロから離れていった人たち(1:15)も、はじめはパウロのことばを聞いて従った人たちであった。しかし、パウロの投獄、パウロの最後の時が近づくにつれ、体験する困難に耐えることができずに離れていった。その中にはテモテの知人もいた。それとは逆にオネシポロはパウロの投獄も物ともせずにパウロを愛し続けていた。
「そこで」という言葉の中には、パウロの投獄に見えるような苦しみが伴う状況にあって、パウロが歩んだ道から離れる事とパウロに従うという2つの選択肢の中から一つを選ぶことが要求される。ということを示している。そして、パウロは、パウロから離れた人の例より、パウロを愛したオネシポロに対する記載が後半に配置され、長めに言及されていることからも、当然、パウロはテモテにこのオネシポロに習うことを求めている。
「キリスト・イエスにある恵みによって強くなりなさい。」
離れるか、従うかを選ぶ状況にあって、従う方を選ぶように要求した上で、パウロは「キリスト・イエスにある恵みによって強くなりなさい。」と言うのである。
しかも、新改訳ではニュアンスが伝わりにくいかもしれないが、非常に強い命令である。
原語のニュアンスが分かりやすいように言い換えるのならば、「あなたは、キリスト・イエスと共にある恵みによって強くさせられ続けなさい。」 となる。明らかに苦難が見える状況にあって、そして、あえて苦難が伴う道を選ばなければいけない時、パウロがその生き方を通して示した道、オネシポロが選んだ道を選んで歩むために、自分の強さや力に頼って歩むのではなく、キリスト・イエスと共にある恵みによって強くさせられ続けて歩みなさい。 と言っているのである。
気弱なテモテ、臆病になりがちだったテモテに対して、苦しみを伴う道を歩むことを要求するためには、福音宣教の召しは自分の力ではなく、キリストにある恵みに強められ続けられることによってまっとうされることをもう一度思い起こさせる必要があったのだろう。
福音宣教の召しは牧師や宣教師だけに任されているものではない、すべてのクリスチャンに対して与えられているものである。日本は宗教の自由を認めているが、学校や会社、また、ノンクリスチャンの配偶者がいる家庭において宣教活動をすることを認めていない場合が多い。私たちはその時においてパウロの同労者たちと同じように宣教活動から離れるか、続けるかの選択を迫られる。私たちはどのようにして続けることができるのだろうか。それは、何よりキリストの恵みに強められ続けることによってのみ続けることができるのである。私たちは耐えずキリストと交わり強められ続けなければならない。
ゆだねる
パウロは続いてテモテにパウロから聞いたことを忠実な人たちにゆだねることを勧める。
「私から聞いたこと」とは特定の何かではなく、パウロがその福音宣教の歩みの中で語ってきたキリスト教信仰と福音のことである。それはパウロからテモテへ直接語られただけでなく、多くの証人を通して(前でと訳されているが通しての方が適切)テモテへ語られ、委ねられてた。パウロはテモテに福音宣教の歩みを引き継ぐだけでなく、テモテ自身もこの福音宣教の歩みを引き継ぐでことのできる「教える力のある忠実な(信頼できる)人たち」に委ねることように勧めている。
福音宣教における苦しみを共にする歩みは、自分だけに留まるのではなく、引継ぎ続けていくべきものなのである。主が再びこられる時まで、引継ぎ続けることで、はじめてキリストから人に託されたこの召しをまっとうしたと言えるのではないだろうか。私たちは自らが福音宣教をするのと同時に、この働きをゆだねていく必要があるのである。
徹底的な献身
3節で「キリスト・イエスのりっぱな兵士として、私と苦しみをともにしてください。」とパウロは言う。苦しみをともにしてください。とは、1:8で既にテモテに対して言われていることであるが、その様子を「キリスト・イエスのりっぱな兵士」と表現している。この兵士、そして、5節、6節の競技者、農夫という表現はパウロが信仰者の歩み、パウロ自身の歩みをさして他の手紙で用いた表現であるが、パウロは4-6節の3つの比喩的表現を用いて、キリストの兵士として苦しみを共にするための徹底的な献身を伝えている。
「兵士」(4節)
4節は福音宣教の献身者を兵士として比喩的に表現している。その強調ポイントは、「日常生活のことに掛かり合っている者はだれもありません。」である。この強調は献身者は世俗とはなれなければならない、中世の修道院のような閉鎖的な空間に身を置かなければならないということではない。そうではなくて、献身者の目的意識をどこに置くか。 ということである。兵士は何より「徴募した者を喜ばせる」ことを目的としなければならない、徴募した者とはその部隊の指揮官である。兵士は指揮官の目的を知り、また何を望んでいるかをしり、それを達成することを第一の目標としなければならない。福音宣教の献身者にとって指揮官とはキリスト・イエスであり、その喜びは福音が世界に広められることである。パウロが教会の牧会をする中で、また、宣教の働きをする中で、キリストの喜びである福音が広められる事より他の事に目向けさせようとする物事があった、それは福音宣教に伴う日常生活の苦しみや困難であったり、この世のさまざまな誤った教えであったり、さらに言うならば信徒の党派心からくる分裂なのがあった。しかし、献身者が一番の目的とすべきは指揮官たるキリストに仕えることであり、キリストの御心にすべてをゆだねる徹底的な献身である。それこそが苦しみを共にする献身者に求められる姿の一つである。
牧師や宣教師という職業にいなかったとしても、クリスチャンは献身者であり、御言葉が求める姿は同じである。働いてお金を稼ぐのは当然である。学生が知識を学ぶのも当然である。夫婦がそれぞれの立場で家族を愛し、家族のために仕えるのも当然である。しかし、例えどのような職業や立場にあったとしても、キリスト者の歩みとその目的はキリストに仕えるということであり、それぞれの仕事や立場はその延長線上にある。
「競技者」(5節)
献身者の第二の比喩的表現は「競技者」である。その強調のポイントは、「規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません」ということである。ルールの全くない競技は競技として成り立つことができない。競技者がその競技のルールを守らないのならば、すでに競技者ではないのである。この箇所には「規定」という言葉が、献身者にとって具体的に何をさしているのかを示す説明がない。しかし、それはテモテが既に聞いた言葉の中にあった。つまり、パウロが伝えたメッセージ、キリストのことばの中にあった。キリストに従う献身者の歩みは、御言葉という規則、道に従う歩みである。
今の時代、包括主義や自由主義が盛んに強調されている。しかし、聖書が教えるキリスト者、献身者の歩みは、どのような歩みをしても同じであるといった無分別な包括主義に陥るのではなく、与えられた自由を用いて感情や直感のまま勝手に振舞うのを容認するのでもなく、御言葉がなんと教え、どのように導いているかを注意深く聞いてそれに徹底的に従う歩みが求められているのである。
そうすることによって、競技者が競技し終えたときに、その勝者に対して花束の祝福の冠をかぶせられるように、献身者として歩みをこの世においてまっとうしたとき、献身者に与えられる祝福の冠を私たちは与えられるのである。
「農夫」(6節)
最後の献身者の比喩的表現は「農夫」であり、その強調ポイントは「労苦した農夫」ということである。この「労苦する」とは「骨を折って働くこと」であり、それは肉体的にも、精神的にも、そして、霊的にも努力することである。キリスト・イエスのりっぱな兵士として、苦労をともにする献身者の歩みは、全人格的に骨を折るという行動を伴う徹底的な献身でなければならない。
そして、この節でも労苦した献身者が、「まず第一に収穫の分け前にあずかるべきです。」と述べている。献身者は今、楽に過ごすというより、やがて与えられる分け前に目を向けながら、今の世にあっては、自分ができる最善を尽くすべきなのである。
4. 結論
苦しみをともにする献身者の歩みを御言葉から学んだ。それはキリストの喜びをまず第一にし、キリストの御言葉に従い、全人格的に労苦する行動を伴う歩みである。私たちがこの歩みをしようとするとき、それはいかにも苦しく避けて通りたいと思う。そう思う時、2:1の御言葉に目を留めましょう。「あなたはキリスト・イエスにある恵みによって強くされ続けなさい。」
献身者として苦しみを共にする歩みは、主の恵みにより頼むことからはじまる。だから、祈りましょう。「主よ。どうかパウロより、テモテよりも弱い私たちを福音宣教の苦しみを共にする献身者へと日々、強めてください。」
参考文献
・ 新聖書注解 いのちのことば社
・ Expositor’s Bible Commentary Old Testament, Frank E.Gaebelein, Zondervan
・ THE INTERNATIONAL CRITICAL COMMENTARY, THE PASTORAL EPISTLES, L. HOWARD MARSHALL, T&T CLARK
・ NEW INTERNATIONAL BIBLICAL COMMENTARY, 1 AND 2 TIMOTH, TITUS, GORDON D. FEE, HENDRICKSON PUBLISHERS
|
|
|
|
|
|
|
|
聖書研究 福音派版 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
聖書研究 福音派版のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37859人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人