同性愛をはじめとするセクシャルマイノリティに属する人々は、過去のいつの時代にも、どの地域にも存在してきました。ある特定の時代やある特定の地域のみに存在したということではありません。ただ、その時代・その地域に根ざした文化によるその場所、その時々の評価され方や位置づけられ方があったのだと言えるのでしょう。
セクシャルマイノリティはもちろん、同性愛という言葉も比較的新しい言葉ですが、その同性愛の意味するところは、つい最近までは往々にして男性同士の恋愛関係を示すものでした。けれども女性同士の恋愛関係も存在してきたはずですし、自分を生物学的な異性とみなして生きた人もいたに違いありません。しかし、男性同士の関係以外の多くは、歴史の中に埋もれてしまってその痕跡を残すことは少なかったのだろうと思われます。だから、ここでは「同性愛」という言葉を使用してますが、その意味するところは男性の同性愛です。
世界の歴史を見渡すと、同性愛にとってはたくさんの不遇の時代や地域があったことがわかります。けれども、そのことがすなわち同性愛が間違ったあり方であることを示すことにはなりません。同性愛に光があたったり、比較的優しい時代や地域も存在しました。代表的な例としては、キリスト以前のギリシア・ローマ社会や明治時代以前の日本社会がそうです。中世から近世初期にかけての日本の武士や、古代ギリシア・古代ローマのように、男性間の同性愛行為が制度化されていたり、公然と行われた文化も存在しました。ここでは取り上げませんが、アジアでは明・清朝時代の中国福建省での同性愛の風習があります。また古代より世界のいくつもの部族が同性愛者をシャーマンとして活用した例も知られています。
古代ギリシアでは、制度化されていた少年愛を同性愛として含めると、同性愛は単なる恋愛・性愛のバリエーションの一つだったともいえます。異性愛との区別自体が無く、同性と肉体関係を持っても同性愛者という概念自体が存在しなかったともいわれます。当時のギリシアにおける自由民成人男性の性対象は女性、少年、奴隷、外国人のうちどれを選んでもよく、むしろ生涯で片方の性にしか性欲が湧かないことは通常ではないとされていたといわれています。但し、このような制度に組み込まれた少年愛における同性愛的関係は、概ね成人男性と思春期前後の少年のあいだで結ばれるもので、これらは集団の結束を強固にする目的があったり、何らかの意味で現代的な同性愛とは異なるものだと指摘する見方もあります。
日本においても、場所や状況によっては同性愛が公然と行われました。古くから寺院においては、女人禁制の掟があり、女性と性交渉をすることは禁じられていましたが、同性間での性交渉を禁じる掟というものはなく、同性を性的対象と見なすことには隔たりがなかったといわれます。初めて日本に同性愛関係をもちこんだのは、中国から帰国した空海(弘法大師)とも言われますが、そうなると当時の中国にも同性愛の風習があったことになります。平安時代末期には貴族や武士の間にも男色が広がり、中世の武家社会では主従関係の価値観と重ね合わせられ、衆道が大いに流行しました。戦国時代の武家社会では、織田信長をはじめとして名だたる武将の多くが寵愛する小姓を男色相手にしていたといわれています。同性を性的対象と見なさなかった豊臣秀吉は、むしろ例外的な存在だったと言われています。秀吉が農民出身のため武家社会における男色の風習になじめなかったこともその一因として考えられますが、庶民や農民階層においても、男色行為は行われていました。江戸時代には男色は町人の間にも流行しています。
ところで、江戸時代の町人が通う銭湯などは、男女混浴が当たり前で、これを見た西洋人はなんて野蛮な民族だろうと驚いたと言います。にもかかわらず一方では、男女の乱れた関係がそこで行われるわけでもないので、そのことを逆に公衆道徳の高さであると評価する西洋人もいました。しかし、果たしてこのことがそのまま公衆道徳の高さと言い切れるかどうか。もしかしたら、当時の時代の人たちの性の感覚をうかがい知れるエピソードかもしれません。つまり、当時の人たちは現代の私たちほど性の違いを意識していなかったかもしれないということです。これを逆に発想するならば、古代ギリシアほどでもないにしても、恋愛対象もバラエティに富んでいて、同性に対してもさほど抵抗がなかったのかもしれません。
このような日本社会の同性愛に対する寛容な態度も、明治時代に入ると次第に暗転していきました。理由は、富国政策と性科学思想の流入です。国を富ませるためには、国内の生産力を上げていかなければなりません。そのためには人口を増やしていく必要があります。生めよ増やせよを国是とする以上、それに貢献できない人や価値は次第に追いやられていきました。当時多産が貧困を生み出す大きな原因であることに注目して、多産に反対する社会運動家もいましたが、これに対し国家は警察を動員して取り締まりました。それほどまでに富国強兵政策とはあからさまで、半強制的であったことがわかります。このような潮流の中では健康な男女が未婚でいたり、子供のいない夫婦であったりすることがどれほど圧力を感じることであったか容易に想像できます。さらに、大正時代には初期の性科学思想が日本にも流入し、キリスト教的価値観の色濃く残る視点から、同性愛は異常性愛の一つであるとされてしまいます。変態という言葉はこの頃から出回り始め、次第に同性愛を自覚した人たちは自分自身を変態であると自らを貶めてしまうようになってしまいました。それらの影響は今も残っています。
さて、再びヨーロッパ。キリスト以降のヨーロッパ社会は20世紀中ごろまで同性愛に対しては厳しい態度をとっていきます。聖書には「汝、女と寝るように男と寝るなかれ」とあり、これを根拠にキリスト教社会では表向き同性愛は禁止されていました。もちろん、同性愛者が存在しなかったというわけではありません。しかし、一般に肩身の狭い思いをしながら一生を送らなければならなかったことでしょう。
当初キリスト教社会では相当な期間、同性愛を「罪」とみなしていました。ところが、西洋で発祥した科学はやがて性をも対象として性科学が誕生します。この性科学によって同性愛は「罪」ではなく、「自然に反する異常なもの」と定義されるようになりました。このことで同性愛は一旦「独房」を出ることができましたが、今度は強制的に「入院」させられることになったわけです。実はこの性科学が定義する「自然」という概念の中に「男女の性愛のみが正統である」というキリスト以来の価値観が入り込んでいたことが原因でした。このため同性愛は引き続き苦難の憂き目をみることになります。1990年に国連機関の WHO が同性愛を国際障害疾病分類 から削除するまでこのような思想が生きていました。
そもそもキリストその人が同性愛を禁じるよう言ったかどうかは甚だ疑問の余地があります。聖書は多くの歴代の聖職者が手を加えて出来上がったものでしょうから、上記の聖書の言葉も誰かに後で付け加えられたものと考えられます。キリスト教が本格的にヨーロッパに広がったのはローマ帝国がキリスト教を国教に定めたのがきっかけですが、時の為政者たちの考えが多分に入りこんでいると思われます。国教化以前の賢帝といわれるマルクス・アウレリウスなども既に日記の中で「昨今の少年愛の風習は困ったものだ」と記しているは残念ですが、キリスト国教化以降の歴代の皇帝や教皇らによって、同性愛の禁止が堅持されてきたのだと思われます。その真意はやはり家族を基にした人口政策にあったのではないでしょうか?いずれにしろ、答えはキリスト本人よりもキリスト以降の為政者の胸の中にあったと思われます。
キリスト教の伝播と発展につれ、それに基づく性に対する倫理観が信者に広がるにつれ、同性愛の旗色は悪くなる一方だったのは間違いないと思われます。しかし、それで同性愛がヨーロッパ中世以降からまったく姿を消したわけではありませんでした。実は西欧での同性愛の伝統は、むしろ上層階級の中では脈々と生き続けます。ギリシア・ローマ時代の文化を引き継ぐヨーロッパ的教養の担い手であった貴族たちは、まだしばらくの間キリスト教的な倫理の外側にいることができる特権的な立場だったのかもしれません。むしろ、それより下層の市民が力を持つにつれ、かつて市民に課された性道徳が次第に上層の貴族たちにも影響を及ぼすようになります。ついに同性愛がすっかりヨーロッパに居場所をなくしたかのように見えるのは、市民社会が到来する18世紀頃のことです。ところが今度は、その市民社会は次第に世俗化の色彩を強め、一方でキリスト教の影響が低下する方向へ向かいます。
ヨーロッパ社会では、フランス革命以来市民社会の誕生により、徐々にキリスト教の影響が後退し、20世紀の末には多くの国家が世俗化したといわれます。恋愛観・結婚観が多様になっていった結果、21世紀に入って同性愛者たちが念願にしていた同性婚を認める国家すら誕生するようになりました。このような同性愛者の権利拡張に対して、それを進める大きな原動力になったのは、第二次世界大戦時にナチスドイツが行った同性愛者に対する弾圧と虐殺に対する猛省であるといわれています。ナチスは同性愛者にピンクの逆三角形の焼印を施し、次々と大量に虐殺していきました。理由はやはり同性愛者は民族の発展に役立たないというものでした。もちろん、同性愛をはじめとするセクシャルマイノリティ当事者の人たちの長年の人権を求める運動こそが直接的な貢献になりますが、このような歴史的な背景があることは忘れてはならない事実です。
このようにして、皮肉なことに、かつて同性愛にとって暗黒の地域であったはずのヨーロッパ諸国が世界に先駆けて世界のセクシャルマイノリティが羨む先進的な地域に変貌して、21世紀が幕を開けたのです。現在同性婚を認める国々・地域は、オランダ、ベルギー、スペイン、スウェーデン、ノルウェー、ポルトガル、アイスランド、南アフリカ、カナダとアメリカ合衆国の一部の州、そして南米のアルゼンチンだけですが、同性婚に準じるパートナーシップを認める国を含めるともっと多数に及びます。その多くはヨーロッパの国々です。
ちなみにヨーロッパ諸国で次々と同性婚やそれに準じる制度の立ち上げが成功したことについては、昨今の政策的な背景にも目を配る必要がありそうです。
イギリスの例で見ます。イギリスでは、1970年代頃「ゆりかごから墓場まで」と謳われた福祉政策が財政難の壁にぶつかり破綻しました。替わって登場してきたのは、サッチャー首相に代表される新自由主義に基づく政策でした。この政策の下では福祉予算など国家による支出が極力抑制され、それまで規制してきた分野の緩和を行うことで、市場経済を拡大強化し、そこから税収を確保することで、なるべく小さな政府で国家を運営していこうとしました。また、自助努力が重んじられ、社会政策的には保守的な政策が進められました。例えば家族の形態として伝統的な父母に実子というパターンが重んじられ、それに反する同性同士の「夫婦」など到底考えられませんでした。
しかし、この新自由主義による政策は一定の功績を残しつつも破綻します。一番の問題は貧富の差を拡大してしまい、そのことが足元から社会を不安定にしてしまうことでした。サッチャー首相が辞任した後保守党は勢力を失い、伝統的に社会民主主義の政策をとる労働党の人気が回復しました。その後カリスマ的な人気を誇るトニー・ブレア首相の登場でいよいよ労働党による政策転換が行われることになりました。
ところで、ヨーロッパの伝統的な社会民主主義は福祉予算を手厚くする大きな政府を目指しますが、新しい労働党政権は、この従来の社会民主主義とは一線を画す政策を展開します。なぜなら、財政事情は相変わらず厳しい状況であり、簡単には支出を増やすことができないからです。つまり小さな政府を維持しつつ、どうやって社会を安定させていくかという難題に挑戦しなければなりませんでした。そこで注目されたのが、イギリスの社会学者アンソニー・ギデンスが提唱する「第三の道」という考え方です。
新自由主義による政策ではあたかも世の中が政府と市場というたった二つの領域でしか成り立っていないかのように捉えられます。そのため、地域社会や家族など人々がボランタリーに結びついている活動領域は無視されたり、あるいは逆に過当な責任を押し付けられたりすることになります。すると地域社会が疲弊したり、家族関係がすっかり破綻してしまったりしても公的な責任では何の手当てもされることはありません。その結果、地域社会や家族がバラバラになってはじき出された個人が自己責任の名のもと矛盾を強要されることになるのです。
そこでギデンスは、政府と市場の他に「社会」という領域が存在することに注目しました。地域社会や家族など、人間が生きていくのに必要な人間同士のつながりによって成り立っている領域を「社会」と定義して、この「社会」を層の厚い安定したものにするためにも政府は徹底的にこの「社会」を支援しなければならないと主張したのでした。これを「社会支援国家」と呼びます。なるべく個人を「社会」の中に包摂して、無力な個人が矛盾の矢面に立たされないようにするためにも、「社会」を強く大きなものにしなければならない。
その「社会」の一環である家族について考えましょう。伝統的に家族とは、一組の夫婦がいて、他に血のつながった子供がいる、現代では「核家族」が代表的な概念でしょう。しかし、現実的には、血のつながりがなくても、例えば同性同士であたかも夫婦のように助け合って生きているカップルも存在します。つまりそのカップルは従来の定義では夫婦とも家族とも言えないけれど、「社会」の中で期待される家族の機能を有しているとみなされるのです。つまり、この「社会」で期待されるのは、従来の定義に則っていることではなく、その機能を有していることであることになります。ヨーロッパにおいて、同性同士でも一つの生活のユニットとしてみなされるようになったのは、このような政策の潮流が背後にあるからだということを忘れてはいけないと思います。そこから考えられる結論は、同性婚は単に権利や自由による獲得の産物なのではなく、今後の重要な社会構成の一員であるということです。
アメリカの政治哲学者マイケル・サンデルは、自由主義の新しい潮流の一つとしてコミュニタリズム(共同体主義)を提唱しています。選択の自由があることこそが正義あると考える従来のリベラリズムの枠組みの中では、同性婚は選択の自由の一環として守られるべきものであるとされるのにとどまるのに対し、善の価値との一致を正義として重視するコミュニタリズムにおいては、結婚の本質的な意義や目的(これは決して生殖ではなく、二人の人間が永久の関係性を誓い合い、他者や国家がこれを祝福すること)に合致している限りにおいて同性婚は支持されるべきものだと考えます。
セクシャルマイノリティとは新しい概念です。かつては男性の同性愛者のことのように語られることが多かったのですが、近年になり多くの人が自分の性の意識や指向を表明するようになると、その内容は実に多様であることがわかってきました。恋愛の性の対象を区別する性の指向の他に、自らの性の意識が肉体とは別の性であると認識する人々もいることがわかりました。前者の性指向という軸と後者の性自認というもう一つの軸の2つの軸の組み合わせで、複数のセクシャルマイノリティのカテゴリーが規定されます。性指向の軸では、ホモセクシャル(ゲイ/レズビアン)、バイセクシャルそしてヘテロセクシャル、性自認の軸では、トランスジェンダー、トランスセクシャル、インターセクシャルなどに大別されます。本来的には、この性指向と性自認の軸は全く異なるものですが、同じ性にかかわる少数派ということで、セクシャルマイノリティという同じくくりの中に入れられているのが実情です。
多様性について語るなら、そもそも主体の捉え方やアイデンティティについては、どの地域あるいはどの歴史の中でそれを語るかによっても本来は大きく異なるものだった、と考えられます。(例えば、タチの男性は同性愛者とは自他共に認識されない地域も存在します。) しかし、現代のグローバル化の流れの中では、それらは良くも悪くも世界中で一元化されつつあるように見えます。それぞれの国家や地域のローカルなメインカルチャーのもと、グローバルなサブカルチャーの担い手としてのLGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスセクシャル)の人々が営むライフスタイルのどこか似通った傾向を世界中で見出すことができるようになりました。(例えば、ゲイが好むポップミュージックには世界中である特定の傾向が見られることなど。) 世界的なSNSで世界中のLGBTの人々が容易につながりあえるのはその現れなのではないでしょうか?
ところで、性自認の軸に関わることでは、20世紀の後半から性同一性障害(GID)という言葉が取りざたされるようになりました。性同一性障害とは、生物学的には完全に正常であり、しかも自分の肉体がどちらの性に所属しているかをはっきり認知していながら、その反面で、人格的には自分が別の性に属していると確信している状態(日本精神神経学会)を指し、病名あるいは障害名とされます。しばしば簡潔に「心の性と身体の性が食い違った状態」と記述されますが、症状の度合いは、自分の持つ外性器に非常な嫌悪感を持ち外科的処置を必要とする状態から、異性装を行うことで耐えられる状態まで様々です。当事者たちは程度の差こそあれ、この肉体の性と心の性の食い違いからくる様々な悩みや苦しみを抱えて生きることになります。これに対し医学の方面から解決を図るための対処として敢えて「障害」と位置づけになっているものと思われます。近年になってこういう人たちが現れたのか、同性愛と同じように昔からあったパターンなのかどうかはわかりません。いずれにしろ近年の医学が、このような人たちのニーズに応えることのできる進歩を果たしたことで当事者たちに新しい選択肢を与えることができるようになった結果、見えにくかった存在を掘り起こす役割を果たしたとも言えそうです。
このように人間の性には色彩のグラディエーションのように様々な様態があることがわかってくると、そのそれぞれに概念と名前が与えられ、細かく区別分類されるようになってきました。そのことは、それぞれの当事者たちにある種のアイデンティティを与えて、勇気づける反面、混乱を与えている側面もあります。西洋由来の現代文化には、物事を分析し、差異を発見し、あたかもまるで異なるものであるかのように次々と分類していくという傾向がありますが、今、性の分野でも同じことが起こっているように見えます。
しかし、かつての古代ギリシアや近代以前の日本で見たように、自分が何者であるかを問うことなく、あるがままの感情を自分で受け入れ、他者にも受け入れられる恋愛観、世界観も存在しうるのだということをセクャルマイノリティの歴史の研究を通して知ることができるように思われます。
セクシャルマイノリティはもちろん、同性愛という言葉も比較的新しい言葉ですが、その同性愛の意味するところは、つい最近までは往々にして男性同士の恋愛関係を示すものでした。けれども女性同士の恋愛関係も存在してきたはずですし、自分を生物学的な異性とみなして生きた人もいたに違いありません。しかし、男性同士の関係以外の多くは、歴史の中に埋もれてしまってその痕跡を残すことは少なかったのだろうと思われます。だから、ここでは「同性愛」という言葉を使用してますが、その意味するところは男性の同性愛です。
世界の歴史を見渡すと、同性愛にとってはたくさんの不遇の時代や地域があったことがわかります。けれども、そのことがすなわち同性愛が間違ったあり方であることを示すことにはなりません。同性愛に光があたったり、比較的優しい時代や地域も存在しました。代表的な例としては、キリスト以前のギリシア・ローマ社会や明治時代以前の日本社会がそうです。中世から近世初期にかけての日本の武士や、古代ギリシア・古代ローマのように、男性間の同性愛行為が制度化されていたり、公然と行われた文化も存在しました。ここでは取り上げませんが、アジアでは明・清朝時代の中国福建省での同性愛の風習があります。また古代より世界のいくつもの部族が同性愛者をシャーマンとして活用した例も知られています。
古代ギリシアでは、制度化されていた少年愛を同性愛として含めると、同性愛は単なる恋愛・性愛のバリエーションの一つだったともいえます。異性愛との区別自体が無く、同性と肉体関係を持っても同性愛者という概念自体が存在しなかったともいわれます。当時のギリシアにおける自由民成人男性の性対象は女性、少年、奴隷、外国人のうちどれを選んでもよく、むしろ生涯で片方の性にしか性欲が湧かないことは通常ではないとされていたといわれています。但し、このような制度に組み込まれた少年愛における同性愛的関係は、概ね成人男性と思春期前後の少年のあいだで結ばれるもので、これらは集団の結束を強固にする目的があったり、何らかの意味で現代的な同性愛とは異なるものだと指摘する見方もあります。
日本においても、場所や状況によっては同性愛が公然と行われました。古くから寺院においては、女人禁制の掟があり、女性と性交渉をすることは禁じられていましたが、同性間での性交渉を禁じる掟というものはなく、同性を性的対象と見なすことには隔たりがなかったといわれます。初めて日本に同性愛関係をもちこんだのは、中国から帰国した空海(弘法大師)とも言われますが、そうなると当時の中国にも同性愛の風習があったことになります。平安時代末期には貴族や武士の間にも男色が広がり、中世の武家社会では主従関係の価値観と重ね合わせられ、衆道が大いに流行しました。戦国時代の武家社会では、織田信長をはじめとして名だたる武将の多くが寵愛する小姓を男色相手にしていたといわれています。同性を性的対象と見なさなかった豊臣秀吉は、むしろ例外的な存在だったと言われています。秀吉が農民出身のため武家社会における男色の風習になじめなかったこともその一因として考えられますが、庶民や農民階層においても、男色行為は行われていました。江戸時代には男色は町人の間にも流行しています。
ところで、江戸時代の町人が通う銭湯などは、男女混浴が当たり前で、これを見た西洋人はなんて野蛮な民族だろうと驚いたと言います。にもかかわらず一方では、男女の乱れた関係がそこで行われるわけでもないので、そのことを逆に公衆道徳の高さであると評価する西洋人もいました。しかし、果たしてこのことがそのまま公衆道徳の高さと言い切れるかどうか。もしかしたら、当時の時代の人たちの性の感覚をうかがい知れるエピソードかもしれません。つまり、当時の人たちは現代の私たちほど性の違いを意識していなかったかもしれないということです。これを逆に発想するならば、古代ギリシアほどでもないにしても、恋愛対象もバラエティに富んでいて、同性に対してもさほど抵抗がなかったのかもしれません。
このような日本社会の同性愛に対する寛容な態度も、明治時代に入ると次第に暗転していきました。理由は、富国政策と性科学思想の流入です。国を富ませるためには、国内の生産力を上げていかなければなりません。そのためには人口を増やしていく必要があります。生めよ増やせよを国是とする以上、それに貢献できない人や価値は次第に追いやられていきました。当時多産が貧困を生み出す大きな原因であることに注目して、多産に反対する社会運動家もいましたが、これに対し国家は警察を動員して取り締まりました。それほどまでに富国強兵政策とはあからさまで、半強制的であったことがわかります。このような潮流の中では健康な男女が未婚でいたり、子供のいない夫婦であったりすることがどれほど圧力を感じることであったか容易に想像できます。さらに、大正時代には初期の性科学思想が日本にも流入し、キリスト教的価値観の色濃く残る視点から、同性愛は異常性愛の一つであるとされてしまいます。変態という言葉はこの頃から出回り始め、次第に同性愛を自覚した人たちは自分自身を変態であると自らを貶めてしまうようになってしまいました。それらの影響は今も残っています。
さて、再びヨーロッパ。キリスト以降のヨーロッパ社会は20世紀中ごろまで同性愛に対しては厳しい態度をとっていきます。聖書には「汝、女と寝るように男と寝るなかれ」とあり、これを根拠にキリスト教社会では表向き同性愛は禁止されていました。もちろん、同性愛者が存在しなかったというわけではありません。しかし、一般に肩身の狭い思いをしながら一生を送らなければならなかったことでしょう。
当初キリスト教社会では相当な期間、同性愛を「罪」とみなしていました。ところが、西洋で発祥した科学はやがて性をも対象として性科学が誕生します。この性科学によって同性愛は「罪」ではなく、「自然に反する異常なもの」と定義されるようになりました。このことで同性愛は一旦「独房」を出ることができましたが、今度は強制的に「入院」させられることになったわけです。実はこの性科学が定義する「自然」という概念の中に「男女の性愛のみが正統である」というキリスト以来の価値観が入り込んでいたことが原因でした。このため同性愛は引き続き苦難の憂き目をみることになります。1990年に国連機関の WHO が同性愛を国際障害疾病分類 から削除するまでこのような思想が生きていました。
そもそもキリストその人が同性愛を禁じるよう言ったかどうかは甚だ疑問の余地があります。聖書は多くの歴代の聖職者が手を加えて出来上がったものでしょうから、上記の聖書の言葉も誰かに後で付け加えられたものと考えられます。キリスト教が本格的にヨーロッパに広がったのはローマ帝国がキリスト教を国教に定めたのがきっかけですが、時の為政者たちの考えが多分に入りこんでいると思われます。国教化以前の賢帝といわれるマルクス・アウレリウスなども既に日記の中で「昨今の少年愛の風習は困ったものだ」と記しているは残念ですが、キリスト国教化以降の歴代の皇帝や教皇らによって、同性愛の禁止が堅持されてきたのだと思われます。その真意はやはり家族を基にした人口政策にあったのではないでしょうか?いずれにしろ、答えはキリスト本人よりもキリスト以降の為政者の胸の中にあったと思われます。
キリスト教の伝播と発展につれ、それに基づく性に対する倫理観が信者に広がるにつれ、同性愛の旗色は悪くなる一方だったのは間違いないと思われます。しかし、それで同性愛がヨーロッパ中世以降からまったく姿を消したわけではありませんでした。実は西欧での同性愛の伝統は、むしろ上層階級の中では脈々と生き続けます。ギリシア・ローマ時代の文化を引き継ぐヨーロッパ的教養の担い手であった貴族たちは、まだしばらくの間キリスト教的な倫理の外側にいることができる特権的な立場だったのかもしれません。むしろ、それより下層の市民が力を持つにつれ、かつて市民に課された性道徳が次第に上層の貴族たちにも影響を及ぼすようになります。ついに同性愛がすっかりヨーロッパに居場所をなくしたかのように見えるのは、市民社会が到来する18世紀頃のことです。ところが今度は、その市民社会は次第に世俗化の色彩を強め、一方でキリスト教の影響が低下する方向へ向かいます。
ヨーロッパ社会では、フランス革命以来市民社会の誕生により、徐々にキリスト教の影響が後退し、20世紀の末には多くの国家が世俗化したといわれます。恋愛観・結婚観が多様になっていった結果、21世紀に入って同性愛者たちが念願にしていた同性婚を認める国家すら誕生するようになりました。このような同性愛者の権利拡張に対して、それを進める大きな原動力になったのは、第二次世界大戦時にナチスドイツが行った同性愛者に対する弾圧と虐殺に対する猛省であるといわれています。ナチスは同性愛者にピンクの逆三角形の焼印を施し、次々と大量に虐殺していきました。理由はやはり同性愛者は民族の発展に役立たないというものでした。もちろん、同性愛をはじめとするセクシャルマイノリティ当事者の人たちの長年の人権を求める運動こそが直接的な貢献になりますが、このような歴史的な背景があることは忘れてはならない事実です。
このようにして、皮肉なことに、かつて同性愛にとって暗黒の地域であったはずのヨーロッパ諸国が世界に先駆けて世界のセクシャルマイノリティが羨む先進的な地域に変貌して、21世紀が幕を開けたのです。現在同性婚を認める国々・地域は、オランダ、ベルギー、スペイン、スウェーデン、ノルウェー、ポルトガル、アイスランド、南アフリカ、カナダとアメリカ合衆国の一部の州、そして南米のアルゼンチンだけですが、同性婚に準じるパートナーシップを認める国を含めるともっと多数に及びます。その多くはヨーロッパの国々です。
ちなみにヨーロッパ諸国で次々と同性婚やそれに準じる制度の立ち上げが成功したことについては、昨今の政策的な背景にも目を配る必要がありそうです。
イギリスの例で見ます。イギリスでは、1970年代頃「ゆりかごから墓場まで」と謳われた福祉政策が財政難の壁にぶつかり破綻しました。替わって登場してきたのは、サッチャー首相に代表される新自由主義に基づく政策でした。この政策の下では福祉予算など国家による支出が極力抑制され、それまで規制してきた分野の緩和を行うことで、市場経済を拡大強化し、そこから税収を確保することで、なるべく小さな政府で国家を運営していこうとしました。また、自助努力が重んじられ、社会政策的には保守的な政策が進められました。例えば家族の形態として伝統的な父母に実子というパターンが重んじられ、それに反する同性同士の「夫婦」など到底考えられませんでした。
しかし、この新自由主義による政策は一定の功績を残しつつも破綻します。一番の問題は貧富の差を拡大してしまい、そのことが足元から社会を不安定にしてしまうことでした。サッチャー首相が辞任した後保守党は勢力を失い、伝統的に社会民主主義の政策をとる労働党の人気が回復しました。その後カリスマ的な人気を誇るトニー・ブレア首相の登場でいよいよ労働党による政策転換が行われることになりました。
ところで、ヨーロッパの伝統的な社会民主主義は福祉予算を手厚くする大きな政府を目指しますが、新しい労働党政権は、この従来の社会民主主義とは一線を画す政策を展開します。なぜなら、財政事情は相変わらず厳しい状況であり、簡単には支出を増やすことができないからです。つまり小さな政府を維持しつつ、どうやって社会を安定させていくかという難題に挑戦しなければなりませんでした。そこで注目されたのが、イギリスの社会学者アンソニー・ギデンスが提唱する「第三の道」という考え方です。
新自由主義による政策ではあたかも世の中が政府と市場というたった二つの領域でしか成り立っていないかのように捉えられます。そのため、地域社会や家族など人々がボランタリーに結びついている活動領域は無視されたり、あるいは逆に過当な責任を押し付けられたりすることになります。すると地域社会が疲弊したり、家族関係がすっかり破綻してしまったりしても公的な責任では何の手当てもされることはありません。その結果、地域社会や家族がバラバラになってはじき出された個人が自己責任の名のもと矛盾を強要されることになるのです。
そこでギデンスは、政府と市場の他に「社会」という領域が存在することに注目しました。地域社会や家族など、人間が生きていくのに必要な人間同士のつながりによって成り立っている領域を「社会」と定義して、この「社会」を層の厚い安定したものにするためにも政府は徹底的にこの「社会」を支援しなければならないと主張したのでした。これを「社会支援国家」と呼びます。なるべく個人を「社会」の中に包摂して、無力な個人が矛盾の矢面に立たされないようにするためにも、「社会」を強く大きなものにしなければならない。
その「社会」の一環である家族について考えましょう。伝統的に家族とは、一組の夫婦がいて、他に血のつながった子供がいる、現代では「核家族」が代表的な概念でしょう。しかし、現実的には、血のつながりがなくても、例えば同性同士であたかも夫婦のように助け合って生きているカップルも存在します。つまりそのカップルは従来の定義では夫婦とも家族とも言えないけれど、「社会」の中で期待される家族の機能を有しているとみなされるのです。つまり、この「社会」で期待されるのは、従来の定義に則っていることではなく、その機能を有していることであることになります。ヨーロッパにおいて、同性同士でも一つの生活のユニットとしてみなされるようになったのは、このような政策の潮流が背後にあるからだということを忘れてはいけないと思います。そこから考えられる結論は、同性婚は単に権利や自由による獲得の産物なのではなく、今後の重要な社会構成の一員であるということです。
アメリカの政治哲学者マイケル・サンデルは、自由主義の新しい潮流の一つとしてコミュニタリズム(共同体主義)を提唱しています。選択の自由があることこそが正義あると考える従来のリベラリズムの枠組みの中では、同性婚は選択の自由の一環として守られるべきものであるとされるのにとどまるのに対し、善の価値との一致を正義として重視するコミュニタリズムにおいては、結婚の本質的な意義や目的(これは決して生殖ではなく、二人の人間が永久の関係性を誓い合い、他者や国家がこれを祝福すること)に合致している限りにおいて同性婚は支持されるべきものだと考えます。
セクシャルマイノリティとは新しい概念です。かつては男性の同性愛者のことのように語られることが多かったのですが、近年になり多くの人が自分の性の意識や指向を表明するようになると、その内容は実に多様であることがわかってきました。恋愛の性の対象を区別する性の指向の他に、自らの性の意識が肉体とは別の性であると認識する人々もいることがわかりました。前者の性指向という軸と後者の性自認というもう一つの軸の2つの軸の組み合わせで、複数のセクシャルマイノリティのカテゴリーが規定されます。性指向の軸では、ホモセクシャル(ゲイ/レズビアン)、バイセクシャルそしてヘテロセクシャル、性自認の軸では、トランスジェンダー、トランスセクシャル、インターセクシャルなどに大別されます。本来的には、この性指向と性自認の軸は全く異なるものですが、同じ性にかかわる少数派ということで、セクシャルマイノリティという同じくくりの中に入れられているのが実情です。
多様性について語るなら、そもそも主体の捉え方やアイデンティティについては、どの地域あるいはどの歴史の中でそれを語るかによっても本来は大きく異なるものだった、と考えられます。(例えば、タチの男性は同性愛者とは自他共に認識されない地域も存在します。) しかし、現代のグローバル化の流れの中では、それらは良くも悪くも世界中で一元化されつつあるように見えます。それぞれの国家や地域のローカルなメインカルチャーのもと、グローバルなサブカルチャーの担い手としてのLGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスセクシャル)の人々が営むライフスタイルのどこか似通った傾向を世界中で見出すことができるようになりました。(例えば、ゲイが好むポップミュージックには世界中である特定の傾向が見られることなど。) 世界的なSNSで世界中のLGBTの人々が容易につながりあえるのはその現れなのではないでしょうか?
ところで、性自認の軸に関わることでは、20世紀の後半から性同一性障害(GID)という言葉が取りざたされるようになりました。性同一性障害とは、生物学的には完全に正常であり、しかも自分の肉体がどちらの性に所属しているかをはっきり認知していながら、その反面で、人格的には自分が別の性に属していると確信している状態(日本精神神経学会)を指し、病名あるいは障害名とされます。しばしば簡潔に「心の性と身体の性が食い違った状態」と記述されますが、症状の度合いは、自分の持つ外性器に非常な嫌悪感を持ち外科的処置を必要とする状態から、異性装を行うことで耐えられる状態まで様々です。当事者たちは程度の差こそあれ、この肉体の性と心の性の食い違いからくる様々な悩みや苦しみを抱えて生きることになります。これに対し医学の方面から解決を図るための対処として敢えて「障害」と位置づけになっているものと思われます。近年になってこういう人たちが現れたのか、同性愛と同じように昔からあったパターンなのかどうかはわかりません。いずれにしろ近年の医学が、このような人たちのニーズに応えることのできる進歩を果たしたことで当事者たちに新しい選択肢を与えることができるようになった結果、見えにくかった存在を掘り起こす役割を果たしたとも言えそうです。
このように人間の性には色彩のグラディエーションのように様々な様態があることがわかってくると、そのそれぞれに概念と名前が与えられ、細かく区別分類されるようになってきました。そのことは、それぞれの当事者たちにある種のアイデンティティを与えて、勇気づける反面、混乱を与えている側面もあります。西洋由来の現代文化には、物事を分析し、差異を発見し、あたかもまるで異なるものであるかのように次々と分類していくという傾向がありますが、今、性の分野でも同じことが起こっているように見えます。
しかし、かつての古代ギリシアや近代以前の日本で見たように、自分が何者であるかを問うことなく、あるがままの感情を自分で受け入れ、他者にも受け入れられる恋愛観、世界観も存在しうるのだということをセクャルマイノリティの歴史の研究を通して知ることができるように思われます。
|
|
|
|
|
|
|
|
越☆中☆人 (えちゅうど) 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
越☆中☆人 (えちゅうど)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75487人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6446人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208289人
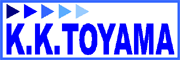











![セックスレス[for gay]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/49/73/2134973_206s.jpg)











