このところ日本の貿易収支が赤字に陥った話、そしてそのことにも絡んで、日本の財政赤字破綻の日が迫っており、急激な金利急騰という恐怖が日本を襲うのではないかという不安、そして財政再建のための消費税増税の話が入り組みあって盛んに議論されている。
こうした話を整理していくためには、なんとなく納得できる分かりやすい固定観念、例えば「円高は日本経済を駄目にして、円安はハッピー」のような単純な思い込みを忘れ、もう少し突っ込んで状況を確認する必要がある。
今回はまずは日本の貿易収支の話を取り上げたいと思う。
まず事実として2011年に日本の貿易収支は赤字になった。輸出が65.6兆円、輸入が68.1兆円で、その差額の2.5兆円が赤字というわけだ。日本が海外に対して物を売って得たお金の合計より、日本が海外から輸入して支払ったお金の合計ほうが多かったという事実である。
それが何故話題になるかといえば、貿易立国と呼ばれる日本では、1980年以来、ずっと貿易黒字の状態にあり、31年ぶりに赤字になったからだ。よく赤字転落という表現を目にするが、これは正しくない。黒字が良くて、赤字が悪いというわけではないから、転落というようなマイナスのイメージで捉える必要は全くない。黒字、赤字は結果に過ぎず、大切なことは、その国の特徴に合った形で輸出も輸入も増加し、貿易量そのものを拡大することで、日本という国を活性化させることにほかならない。
そして貿易収支赤字の話が、なぜ国債暴落、金利急騰にまで話が展開されるのか?それは次の理由による。「日本の財政状態は先進国中、際立って最悪であるものの、国債の90%以上が国内で消化されているから、ギリシャとは異なり、日本の金利は低位安定している」という説明である。つまり貿易収支が赤字となり、その額が大きくなり、やがて所得収支の黒字を上回る赤字となった場合、日本は経常収支赤字国となる。そうなれば国内のお金だけでは国の運営を出来ずに、米国、あるいはギリシャのように海外の資金を引き寄せなければならず、日本は財務状態に見合う金利を要求されるだろうという展開に話が進むのである。そして人によっては、そういう状態は数年で実現すると予想している。
この経常収支の話と国債の議論は、今回は説明しない。そう単純でもないからだ。今回は貿易収支に話を絞る。
さて、その貿易収支をもう少し詳しく見ていく。
2011年の貿易収支の赤字は、輸出も確かに減ったが、輸入が大きく増加したことが、赤字になった主因である。2011年にはタイの洪水、そして東日本大震災という大きな特殊要因があった。この影響は大きい。特に輸入に関しては、原発の停止による代替の化石燃料確保のために、液化天然ガスの輸入が急増したことはよく知られている。中部電力のお偉いさんだかが、震災後にカタールに飛んでゆき、同国から安定的な長期供給契約を取り付けてきたことは有名だ。実際に昨年4月から年末までの天然ガス輸入量は前年同期比50%近く、金額にして4兆円弱というから、かなりのインパクトだ。
そしてエネルギー輸入に関しては2012年も同様に膨張することは確実だ。現在、日本の原発は93%が稼働停止しており、残りの稼働中の3基も4月には稼働停止になる。原発再開のハードルは高いことから、化石燃料頼みの状況は続く。さらに世界的な金融緩和の影響を受けた金余りの副作用により、原油価格はもとよりエネルギー価格はじりじりと上昇しており、輸入代金は必然的に増える傾向にある。
ところで日本の貿易構造が大きく変化しているということは極めて重要だ。
2009年貿易統計では、1990年には27.5%もの貿易比率であった米国との取引が13.5%にまで低下し、同様にかって3.5%に過ぎなかった中国との貿易比率が20.5%、更に香港、シンガポール、台湾といった中華圏を含めると30.7%に達し、アジア全体では50%、ユーラシア込みで75%という状況にある。この傾向は更に進んでおり、2011年の米国の比率は11%台まで低下したようだ。
そして貿易収支で見ると、日本はアジアとの貿易で6.3兆円の貿易黒字を稼ぎ出している。北米、欧州との貿易でも黒字である。一方で中東との取引では10.9兆円の赤字、オセアニアとの取引でも3兆円の赤字である。中東、オセアニアからのエネルギー輸入を中心とする貿易赤字を、2011年はアジア、北米、欧州との貿易から生じる黒字で埋め切れなかったというのが総括ということになる。そして、興味深いのはアジアとの貿易である。
日本はアジアとの貿易で6.3兆円という巨額の黒字を出しているが、最大の黒字計上は、対韓国貿易であり、その次に台湾、シンガポール取引である。日本では、家電製品を中心に韓国企業に一方的にやられているイメージが強く、それは事実であるが、2国間の貿易で捉えた場合、日本は韓国から大いに稼がせてもらっており、逆に韓国政府にしてみれば、対日赤字は腹立たしい問題なのである。ちなみに日本がアジア貿易で赤字が大きいのは、インドネシア、マレーシアとの取引で、やはりエネルギーや資源に絡んでいる。
さて、このような状況を考えると、現在の日本企業を苦しめている円高とは本当に悪なのだろうか?日本の輸出企業にとって円高が競争力の点で大きな問題になっていることは確かであるが、上述したように日本の貿易構造は過去20年でとてつもない変化をしている。それだけではない。継続的なドル安により、貿易取引における非ドル建て取引も拡大している。日本のアジア向け輸出の既に48.1%が円建て取引であり、逆に輸入の71.5%がドル建てという実態も重い。
考えてみれば当然の話だが、10年前は日本の輸出企業は1ドル=100円より円高では、全て採算割れで赤字になると指摘されていた。現在は100円どころから78円という水準だ。企業のコスト削減だけで何とかできるわけないだろう。企業の努力により、貿易構造、貿易の仕組み自体が大きく変わっているからこそ、何とかなっているのである。
つまり円高、円高と騒ぐべきは、対ドル円相場ではなく、対アジア通貨が重要になっているということである。日本政府の正しい戦略とは、ドル円相場の円高水準に慌てて、大量の介入を実施することではなく、中国を中心とする新興アジア通貨のフロート制以降、あるいは適正な水準への誘導等について、世界レベルで交渉することなのである。それを介入などで人為的な為替操作を行ってしまえば、交渉国の相手国に「あんたに言われたくないよ!」と一蹴されてしまうし、本来は手を取って共に交渉に当たるべき米国からも、「いい加減にしろ!」と名指しで批判されるはめになるのだ。
ところで日本では、ドル円相場の円高対策として、為替介入をもっとやれとか、日銀はもっと金融緩和せよ!という主張が強い。しかし、そういう政策が実際はどれだけコストと副作用がを含んでいるかという負の側面がほとんど議論されていない。
次回はそのような負の副作用をテーマにしよう。
こうした話を整理していくためには、なんとなく納得できる分かりやすい固定観念、例えば「円高は日本経済を駄目にして、円安はハッピー」のような単純な思い込みを忘れ、もう少し突っ込んで状況を確認する必要がある。
今回はまずは日本の貿易収支の話を取り上げたいと思う。
まず事実として2011年に日本の貿易収支は赤字になった。輸出が65.6兆円、輸入が68.1兆円で、その差額の2.5兆円が赤字というわけだ。日本が海外に対して物を売って得たお金の合計より、日本が海外から輸入して支払ったお金の合計ほうが多かったという事実である。
それが何故話題になるかといえば、貿易立国と呼ばれる日本では、1980年以来、ずっと貿易黒字の状態にあり、31年ぶりに赤字になったからだ。よく赤字転落という表現を目にするが、これは正しくない。黒字が良くて、赤字が悪いというわけではないから、転落というようなマイナスのイメージで捉える必要は全くない。黒字、赤字は結果に過ぎず、大切なことは、その国の特徴に合った形で輸出も輸入も増加し、貿易量そのものを拡大することで、日本という国を活性化させることにほかならない。
そして貿易収支赤字の話が、なぜ国債暴落、金利急騰にまで話が展開されるのか?それは次の理由による。「日本の財政状態は先進国中、際立って最悪であるものの、国債の90%以上が国内で消化されているから、ギリシャとは異なり、日本の金利は低位安定している」という説明である。つまり貿易収支が赤字となり、その額が大きくなり、やがて所得収支の黒字を上回る赤字となった場合、日本は経常収支赤字国となる。そうなれば国内のお金だけでは国の運営を出来ずに、米国、あるいはギリシャのように海外の資金を引き寄せなければならず、日本は財務状態に見合う金利を要求されるだろうという展開に話が進むのである。そして人によっては、そういう状態は数年で実現すると予想している。
この経常収支の話と国債の議論は、今回は説明しない。そう単純でもないからだ。今回は貿易収支に話を絞る。
さて、その貿易収支をもう少し詳しく見ていく。
2011年の貿易収支の赤字は、輸出も確かに減ったが、輸入が大きく増加したことが、赤字になった主因である。2011年にはタイの洪水、そして東日本大震災という大きな特殊要因があった。この影響は大きい。特に輸入に関しては、原発の停止による代替の化石燃料確保のために、液化天然ガスの輸入が急増したことはよく知られている。中部電力のお偉いさんだかが、震災後にカタールに飛んでゆき、同国から安定的な長期供給契約を取り付けてきたことは有名だ。実際に昨年4月から年末までの天然ガス輸入量は前年同期比50%近く、金額にして4兆円弱というから、かなりのインパクトだ。
そしてエネルギー輸入に関しては2012年も同様に膨張することは確実だ。現在、日本の原発は93%が稼働停止しており、残りの稼働中の3基も4月には稼働停止になる。原発再開のハードルは高いことから、化石燃料頼みの状況は続く。さらに世界的な金融緩和の影響を受けた金余りの副作用により、原油価格はもとよりエネルギー価格はじりじりと上昇しており、輸入代金は必然的に増える傾向にある。
ところで日本の貿易構造が大きく変化しているということは極めて重要だ。
2009年貿易統計では、1990年には27.5%もの貿易比率であった米国との取引が13.5%にまで低下し、同様にかって3.5%に過ぎなかった中国との貿易比率が20.5%、更に香港、シンガポール、台湾といった中華圏を含めると30.7%に達し、アジア全体では50%、ユーラシア込みで75%という状況にある。この傾向は更に進んでおり、2011年の米国の比率は11%台まで低下したようだ。
そして貿易収支で見ると、日本はアジアとの貿易で6.3兆円の貿易黒字を稼ぎ出している。北米、欧州との貿易でも黒字である。一方で中東との取引では10.9兆円の赤字、オセアニアとの取引でも3兆円の赤字である。中東、オセアニアからのエネルギー輸入を中心とする貿易赤字を、2011年はアジア、北米、欧州との貿易から生じる黒字で埋め切れなかったというのが総括ということになる。そして、興味深いのはアジアとの貿易である。
日本はアジアとの貿易で6.3兆円という巨額の黒字を出しているが、最大の黒字計上は、対韓国貿易であり、その次に台湾、シンガポール取引である。日本では、家電製品を中心に韓国企業に一方的にやられているイメージが強く、それは事実であるが、2国間の貿易で捉えた場合、日本は韓国から大いに稼がせてもらっており、逆に韓国政府にしてみれば、対日赤字は腹立たしい問題なのである。ちなみに日本がアジア貿易で赤字が大きいのは、インドネシア、マレーシアとの取引で、やはりエネルギーや資源に絡んでいる。
さて、このような状況を考えると、現在の日本企業を苦しめている円高とは本当に悪なのだろうか?日本の輸出企業にとって円高が競争力の点で大きな問題になっていることは確かであるが、上述したように日本の貿易構造は過去20年でとてつもない変化をしている。それだけではない。継続的なドル安により、貿易取引における非ドル建て取引も拡大している。日本のアジア向け輸出の既に48.1%が円建て取引であり、逆に輸入の71.5%がドル建てという実態も重い。
考えてみれば当然の話だが、10年前は日本の輸出企業は1ドル=100円より円高では、全て採算割れで赤字になると指摘されていた。現在は100円どころから78円という水準だ。企業のコスト削減だけで何とかできるわけないだろう。企業の努力により、貿易構造、貿易の仕組み自体が大きく変わっているからこそ、何とかなっているのである。
つまり円高、円高と騒ぐべきは、対ドル円相場ではなく、対アジア通貨が重要になっているということである。日本政府の正しい戦略とは、ドル円相場の円高水準に慌てて、大量の介入を実施することではなく、中国を中心とする新興アジア通貨のフロート制以降、あるいは適正な水準への誘導等について、世界レベルで交渉することなのである。それを介入などで人為的な為替操作を行ってしまえば、交渉国の相手国に「あんたに言われたくないよ!」と一蹴されてしまうし、本来は手を取って共に交渉に当たるべき米国からも、「いい加減にしろ!」と名指しで批判されるはめになるのだ。
ところで日本では、ドル円相場の円高対策として、為替介入をもっとやれとか、日銀はもっと金融緩和せよ!という主張が強い。しかし、そういう政策が実際はどれだけコストと副作用がを含んでいるかという負の側面がほとんど議論されていない。
次回はそのような負の副作用をテーマにしよう。
|
|
|
|
|
|
|
|
現場の外国為替! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
現場の外国為替!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208312人
- 3位
- 酒好き
- 170695人
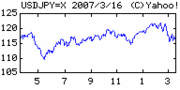














![[dir] FX](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/69/70/2046970_106s.jpg)








