現在の世界経済の状況をざっくりと捉えておきたい。
・米国、日本がほぼゼロパーセントの金利、欧州、英国も1%そこそこの超低金利、一方でインドのインフレ率を9%、中国も5%以上、そしてブラジルの金利は12.25%。この圧倒的な金利格差がなぜ存在しているのか?それがこの世界情勢を理解するポイントの一つである。
(米国)
米国は混迷している。なぜか?バーナンキFRB議長自体が「どうも、よく分からん」と言っているからだ。どういうことか?リーマンショックが起こったのが2008年の9月、10月には金融市場の流動性危機を巻き起こし、100年に1度とも称される金融パニックに発展した。そこから米国政府、いや世界中の政府と中央銀行が肩を組み一丸となって、このパニックの沈静化に立ち向かった。政府は大規模な財政支出、中央銀行は極端な金融緩和である。これで金融市場は安定した。金融機能は正常化した。
しかし、金融は安定しても景気はなかなか戻らずに、米国景気は「2番底」に陥るのでは?というような懸念が常につきまとってきた。その象徴は労働市場と住宅市場にあり、労働市場はリーマンブラザーズ発生前の失業率6%前後の水準から10%を突破し、あれからもうすぐ3年になるのに、まだ9%台で推移している。住宅市場は州により状況は異なるが、一言でいえば「不安定」である。
あまりに経済が弱いので、リーマンショックから2年経過した昨年の11月にFRBはQE2という量的緩和第2弾を打ち出し、FRBによる6000億ドル規模の債券買取を決定した。エコノミストの試算では実に0.75%の利下げ効果に匹敵するとのことで、すでに金利が0%〜0.25%の米国では、実質マイナス金利で強烈に経済を刺激したのである。FRBの思惑通り昨年の11月より株価は大幅に上昇した。とにかく世界中が低金利で金が余りに余っているのである。実際の経済は弱いけど、お金のフローにより、投機的なマネー等によりとにかく株価を上昇させる。株価が上昇すると人々のマインドも明るくなり、後付で景気も回復する。こういうシナリオであり、実際に株価は上昇した。しかし思惑通りに株価は上がったが、同時に原油価格も上昇し、ガソリン価格が急騰してしまった。さらに今年の3月の日本の震災の影響でサプライ・チェーン問題(日本からの部品が途絶える)大事件が発生した。
5月になり米国で発表された経済指標は軒並み驚くほど悪く、米国政府、FRBを震撼させるものだった。バーナンキ議長は「この経済減速は日本の震災の影響とガソリン価格の上昇によるものだが、それ以外の要因はよく分からない」と頭をかいた。実際この2つの要因では説明できないほど、経済は悪いのである。おりしもQE2の期限は6月末であり、それを予定通り止めるシナリオで動いていたところに、この景気減速である。
そして悪いことに政府はまるで無策の状態にある。というよりもそれどころではなく、連邦政府債務上限問題が難航しているのだ。さすがに最近国民の間では、TEAパーティの連中への風当たりは強くなってきてはいるが、それでも連邦債務削減を声高に叫んで支持者を集めた連中は、今更その方針を変更できるはずもない。これだけ経済が落ち込んでも、財政政策、減税などとは真逆の方向で政府は進んでいる。政府ばかりではなく、各州も財政難への対応から、なにかと税金引き上げを目論んでいる。
しかも米国はこれから大統領選挙を迎える。
政府は何もできない。中央銀行もほとんど無力。
できることはドル安誘導と中国等の成長に便乗する外部要因頼みである。
(欧州)
欧州は相変わらず信用危機とユーロの信認問題に揺れている。ガタガタだ。まずギリシャの信用問題は今更詳しく説明するまでもないが、問題は一朝一夕に解決しないことだ。当座の危機は回避しても、今後も事あるごとに同様の問題がつきまとう。
ユーロという欧州の大きな挑戦は確かに成功した。大成功である。一方で成功の為に細部は目をつぶってきたのも事実で、それが発足から10年以上が経過し、いろいろな制度矛盾が目立つようになっているのが現状である。ユーロは複数の国が同じ通貨を使用することから、その通貨の信用維持のために、「財政規律」を重んじた。これがよくでるマーストリヒト条約の一部である。その根幹となる財政規律が実はボロボロであることが昨年露呈した。あれから1年、ユーロはずっとその問題に追われている。そして悪いことにユーロ圏全体で今や「放漫経済は悪であり、財政を緊縮するのが急務」という愚かなコンセンサスができあがってしまっている。ユーロ圏の政府は景気が悪くても、財政政策をとることができないのである。では、景気はユーロ圏の中央銀行であるECBに任せるのか?ECBは、各国の景気になど責任を負っていない。ECBは通貨の番人であり、景気よりも物価の安定にその責を負っている。だからECBは最近のインフレ懸念への対応として既に利上げを実施した。今後も必要に応じて利上げを行う予定である。
経済に対して、中央銀行、政府がばらばらであり、ユーロ圏もやはり外部頼みなのである。
(中東)
昨年から今年前半の主役はアフリカ、中東だった。チュニジアのジャスミン革命、そしてエジプトのムバラク政権の退陣、民主化の勢いはシリア、バーレーン、イラン、リビア、サウジアラビアにも確実に影響を及ぼした。最近はあまり報道されていないが、今もなお、こうした動きは続いている。
今回の一連の民主化デモの動きは、食料の高騰、インフレにより庶民の生活が圧迫されていたことが大きな要因として挙げられている。そのインフレの原因は、天候などの自然要因ばかりではなく、世界の先進国の中央銀行の過剰流動性がある。この地域の多くの国にとって、リーマンブラザーズの破綻による直接的な影響はまるでない。ところがあれ以降、世界の中央銀行がばんばんお金を刷ってばらまくため、世界中が過剰流動性、インフレになっているのだ。
そして、もう一つ重要な点は、中東からいよいよ米国が退散するということである。アフガンからの撤退も開始する。1968年、イギリスがこの地域から撤退し、代わって米国がこの地域に影響力を発揮してきた。その米国がブッシュによるイラク戦争、その統治に失敗し、アフガンも泥沼化し、もはやこの地域に関わる余力が米国にはない事が明白となった。オバマは静かに静かにこの地域から退散を開始している。
この米国なき中東は、今後どのように動くのだろうか?
次回はアジア、とりわけ中国、そして南米を取り上げる。
・米国、日本がほぼゼロパーセントの金利、欧州、英国も1%そこそこの超低金利、一方でインドのインフレ率を9%、中国も5%以上、そしてブラジルの金利は12.25%。この圧倒的な金利格差がなぜ存在しているのか?それがこの世界情勢を理解するポイントの一つである。
(米国)
米国は混迷している。なぜか?バーナンキFRB議長自体が「どうも、よく分からん」と言っているからだ。どういうことか?リーマンショックが起こったのが2008年の9月、10月には金融市場の流動性危機を巻き起こし、100年に1度とも称される金融パニックに発展した。そこから米国政府、いや世界中の政府と中央銀行が肩を組み一丸となって、このパニックの沈静化に立ち向かった。政府は大規模な財政支出、中央銀行は極端な金融緩和である。これで金融市場は安定した。金融機能は正常化した。
しかし、金融は安定しても景気はなかなか戻らずに、米国景気は「2番底」に陥るのでは?というような懸念が常につきまとってきた。その象徴は労働市場と住宅市場にあり、労働市場はリーマンブラザーズ発生前の失業率6%前後の水準から10%を突破し、あれからもうすぐ3年になるのに、まだ9%台で推移している。住宅市場は州により状況は異なるが、一言でいえば「不安定」である。
あまりに経済が弱いので、リーマンショックから2年経過した昨年の11月にFRBはQE2という量的緩和第2弾を打ち出し、FRBによる6000億ドル規模の債券買取を決定した。エコノミストの試算では実に0.75%の利下げ効果に匹敵するとのことで、すでに金利が0%〜0.25%の米国では、実質マイナス金利で強烈に経済を刺激したのである。FRBの思惑通り昨年の11月より株価は大幅に上昇した。とにかく世界中が低金利で金が余りに余っているのである。実際の経済は弱いけど、お金のフローにより、投機的なマネー等によりとにかく株価を上昇させる。株価が上昇すると人々のマインドも明るくなり、後付で景気も回復する。こういうシナリオであり、実際に株価は上昇した。しかし思惑通りに株価は上がったが、同時に原油価格も上昇し、ガソリン価格が急騰してしまった。さらに今年の3月の日本の震災の影響でサプライ・チェーン問題(日本からの部品が途絶える)大事件が発生した。
5月になり米国で発表された経済指標は軒並み驚くほど悪く、米国政府、FRBを震撼させるものだった。バーナンキ議長は「この経済減速は日本の震災の影響とガソリン価格の上昇によるものだが、それ以外の要因はよく分からない」と頭をかいた。実際この2つの要因では説明できないほど、経済は悪いのである。おりしもQE2の期限は6月末であり、それを予定通り止めるシナリオで動いていたところに、この景気減速である。
そして悪いことに政府はまるで無策の状態にある。というよりもそれどころではなく、連邦政府債務上限問題が難航しているのだ。さすがに最近国民の間では、TEAパーティの連中への風当たりは強くなってきてはいるが、それでも連邦債務削減を声高に叫んで支持者を集めた連中は、今更その方針を変更できるはずもない。これだけ経済が落ち込んでも、財政政策、減税などとは真逆の方向で政府は進んでいる。政府ばかりではなく、各州も財政難への対応から、なにかと税金引き上げを目論んでいる。
しかも米国はこれから大統領選挙を迎える。
政府は何もできない。中央銀行もほとんど無力。
できることはドル安誘導と中国等の成長に便乗する外部要因頼みである。
(欧州)
欧州は相変わらず信用危機とユーロの信認問題に揺れている。ガタガタだ。まずギリシャの信用問題は今更詳しく説明するまでもないが、問題は一朝一夕に解決しないことだ。当座の危機は回避しても、今後も事あるごとに同様の問題がつきまとう。
ユーロという欧州の大きな挑戦は確かに成功した。大成功である。一方で成功の為に細部は目をつぶってきたのも事実で、それが発足から10年以上が経過し、いろいろな制度矛盾が目立つようになっているのが現状である。ユーロは複数の国が同じ通貨を使用することから、その通貨の信用維持のために、「財政規律」を重んじた。これがよくでるマーストリヒト条約の一部である。その根幹となる財政規律が実はボロボロであることが昨年露呈した。あれから1年、ユーロはずっとその問題に追われている。そして悪いことにユーロ圏全体で今や「放漫経済は悪であり、財政を緊縮するのが急務」という愚かなコンセンサスができあがってしまっている。ユーロ圏の政府は景気が悪くても、財政政策をとることができないのである。では、景気はユーロ圏の中央銀行であるECBに任せるのか?ECBは、各国の景気になど責任を負っていない。ECBは通貨の番人であり、景気よりも物価の安定にその責を負っている。だからECBは最近のインフレ懸念への対応として既に利上げを実施した。今後も必要に応じて利上げを行う予定である。
経済に対して、中央銀行、政府がばらばらであり、ユーロ圏もやはり外部頼みなのである。
(中東)
昨年から今年前半の主役はアフリカ、中東だった。チュニジアのジャスミン革命、そしてエジプトのムバラク政権の退陣、民主化の勢いはシリア、バーレーン、イラン、リビア、サウジアラビアにも確実に影響を及ぼした。最近はあまり報道されていないが、今もなお、こうした動きは続いている。
今回の一連の民主化デモの動きは、食料の高騰、インフレにより庶民の生活が圧迫されていたことが大きな要因として挙げられている。そのインフレの原因は、天候などの自然要因ばかりではなく、世界の先進国の中央銀行の過剰流動性がある。この地域の多くの国にとって、リーマンブラザーズの破綻による直接的な影響はまるでない。ところがあれ以降、世界の中央銀行がばんばんお金を刷ってばらまくため、世界中が過剰流動性、インフレになっているのだ。
そして、もう一つ重要な点は、中東からいよいよ米国が退散するということである。アフガンからの撤退も開始する。1968年、イギリスがこの地域から撤退し、代わって米国がこの地域に影響力を発揮してきた。その米国がブッシュによるイラク戦争、その統治に失敗し、アフガンも泥沼化し、もはやこの地域に関わる余力が米国にはない事が明白となった。オバマは静かに静かにこの地域から退散を開始している。
この米国なき中東は、今後どのように動くのだろうか?
次回はアジア、とりわけ中国、そして南米を取り上げる。
|
|
|
|
|
|
|
|
現場の外国為替! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
現場の外国為替!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37865人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90064人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人
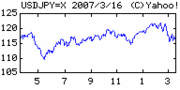














![[dir] FX](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/69/70/2046970_106s.jpg)








