よく新聞報道で、「通貨安競争」という言葉が使われる。
とくに現在1ドル=80円に迫るような円高の局面で、「米国は通貨安により輸出を増加させようという狙いがある」というような論調が目立つ。
しかし、これは疑問だ。そもそも今のドル安はなぜ生じているのかといえば、このコラムを見ていただいているかたにはお分かりの通り、「金融緩和によるドルの相対的な魅力の低下」だ。世界最大の債務国である米国の、世界から資金をひきつける力=魅力が低下していることが大きな要因の一つである。
さて、ここで問題なのは、米国に限らず先進国において金利を決定するのは、政府ではなく中央銀行であるということだ。「中央銀行の独立性」という言葉があるように、各国の中央銀行は物価の安定、雇用の安定などのそれぞれの目的のために、自分達で検討し議論を重ねて金利やその他の金融政策を決定する。
この権限は政府にはない。選挙で選ばれる政治家は、ときに有権者にうける政策を実行しようとする傾向があり、財政政策については権限を持つものの、金融政策に対する権限はもっていない。経済への影響を考えた場合、このような方法がバランスが取れているのだろう。(もちろん究極的には、中央銀行に関する法律さえも変更することで、政府は金融政策の権限も取り戻すことは可能で、日本では政治家が日銀法を変更するぞ!という脅しをしばしば日銀に使用している)
話を戻すと、現在の相場が各国の金融緩和、金融政策を原因としているとすれば、通貨安競争を実施しているのは、政府ではなく各国の中央銀行であるということになる。これはナンセンスだ。
中国や韓国、日本のように政府が為替市場に介入して通貨安を引き起こすような行動をとれば、それは直接的な通貨切り下げ競争と批判されるかもしれないし、また国際的な会議において(G8や、G20)、かってのプラザ合意のようにドルを切り下げるような決定をすれば、これは政府による通貨安政策といえる。
しかし、現在の状況では政府は「為替に対するコメント」することでしか、影響力をもっていない。
こういう事情を考えと、実は今後の相場を考える上での重要な展望が見えてくる。
なぜ世界の国々、特に米国では金融緩和をするのか?
それは簡単で、リーマンショック後に落ち込んだ失業率がいつまでたっても改善しないからだ。住宅市場も動揺である。政府や中央銀行の政策により、金融市場はほとんど完全に復活した。極度の金融緩和を受けて、株式市場も回復している。しかし、労働市場や住宅市場の改善が鈍く、ひいては米国経済が力強く回復できていないことが原因なのである。
そして恐ろしいことは、リーマンショックからももう2年も経過していることである。つまり、今後もFRBが金融緩和を継続しても、それがすぐに米国の労働市場を回復させるとは思えず、この環境は長期間継続するということを意味する。
この現状は日本人には理解しやすいだろう。日本は15年以上もほとんど金利のない世界で生きている。そして、この15年間の間に戦後最長と呼ばれる景気回復期間もあった。しかし、誰も景気の良さを感じられず、むしろ生活の困窮にいらだっている。
これが、米国の日本化現象である。
私は、米国は人口が毎年増加していることや、潜在能力の強さから、日本のような長期間の低迷が続くとは予想していないが、少なくとも現在は混迷している。
ここからが重要だが、まず整理しておく。
・今の為替相場は、各国の金融政策に反応している展開である。
・米国では超金融緩和も2年も継続しているのに、失業率等の労働市場の改善は全く確認されない。
・米国の金融緩和政策は今後も相当期間継続する。
つまり、簡単に言えば今の環境が継続するという事だ。これは「ドル安は相当期間継続する」と言っているに等しい。(個人的にはドル安は十分進行しており、ここからはそれほど激しいドル安は起こらないと予想しているが、大きなドル反発も見込めない)
通貨安競争の犯人が政府であれば、問題はシンプルだ。世界の会議で話し合えばよい。為替へのコメントを控えればよい。しかし、実は政府はほとんど無力で、中央銀行が意図せざる犯人であるならば、問題はあまりに複雑である。日本の場合は、より特殊な道を歩み始めている。中央銀行が政府と一体化を始めているからである。前回決定した金融政策(基金の設立等)は、賛否両論あろうが、日銀OBは涙していることだろう。
そして、日銀は次回の金融政策決定会合は、米国のFOMCの直後に前倒しすることを決めた。これは米国で予想を上回る金融緩和が実施あれ、為替市場が円高に進んだ場合に、日銀もそれに追随して、すぐに追加の金融緩和を行う準備であり、メッセージである。これでは、まさに金融緩和競争、通貨安競争である。
円高は確かに深刻かもしれないが、過剰な新聞報道により、円高を阻止するために日銀が何でもやるというのは、これまでの金融の歴史(いろいろな教訓から学んだこと)を無視する行為で、その副作用は必ずあるだろう。円高を阻止するのは、中央銀行ではなく、政府の役目である。
どうしても、円高を止めるならば、金融緩和競争による為替変動の構図を中断させ、政府主導による協調介入の取り付け、ブラジル等の政府のように税金や規制の検討等、政府がその責任を取るべきではないだろうか。
とくに現在1ドル=80円に迫るような円高の局面で、「米国は通貨安により輸出を増加させようという狙いがある」というような論調が目立つ。
しかし、これは疑問だ。そもそも今のドル安はなぜ生じているのかといえば、このコラムを見ていただいているかたにはお分かりの通り、「金融緩和によるドルの相対的な魅力の低下」だ。世界最大の債務国である米国の、世界から資金をひきつける力=魅力が低下していることが大きな要因の一つである。
さて、ここで問題なのは、米国に限らず先進国において金利を決定するのは、政府ではなく中央銀行であるということだ。「中央銀行の独立性」という言葉があるように、各国の中央銀行は物価の安定、雇用の安定などのそれぞれの目的のために、自分達で検討し議論を重ねて金利やその他の金融政策を決定する。
この権限は政府にはない。選挙で選ばれる政治家は、ときに有権者にうける政策を実行しようとする傾向があり、財政政策については権限を持つものの、金融政策に対する権限はもっていない。経済への影響を考えた場合、このような方法がバランスが取れているのだろう。(もちろん究極的には、中央銀行に関する法律さえも変更することで、政府は金融政策の権限も取り戻すことは可能で、日本では政治家が日銀法を変更するぞ!という脅しをしばしば日銀に使用している)
話を戻すと、現在の相場が各国の金融緩和、金融政策を原因としているとすれば、通貨安競争を実施しているのは、政府ではなく各国の中央銀行であるということになる。これはナンセンスだ。
中国や韓国、日本のように政府が為替市場に介入して通貨安を引き起こすような行動をとれば、それは直接的な通貨切り下げ競争と批判されるかもしれないし、また国際的な会議において(G8や、G20)、かってのプラザ合意のようにドルを切り下げるような決定をすれば、これは政府による通貨安政策といえる。
しかし、現在の状況では政府は「為替に対するコメント」することでしか、影響力をもっていない。
こういう事情を考えと、実は今後の相場を考える上での重要な展望が見えてくる。
なぜ世界の国々、特に米国では金融緩和をするのか?
それは簡単で、リーマンショック後に落ち込んだ失業率がいつまでたっても改善しないからだ。住宅市場も動揺である。政府や中央銀行の政策により、金融市場はほとんど完全に復活した。極度の金融緩和を受けて、株式市場も回復している。しかし、労働市場や住宅市場の改善が鈍く、ひいては米国経済が力強く回復できていないことが原因なのである。
そして恐ろしいことは、リーマンショックからももう2年も経過していることである。つまり、今後もFRBが金融緩和を継続しても、それがすぐに米国の労働市場を回復させるとは思えず、この環境は長期間継続するということを意味する。
この現状は日本人には理解しやすいだろう。日本は15年以上もほとんど金利のない世界で生きている。そして、この15年間の間に戦後最長と呼ばれる景気回復期間もあった。しかし、誰も景気の良さを感じられず、むしろ生活の困窮にいらだっている。
これが、米国の日本化現象である。
私は、米国は人口が毎年増加していることや、潜在能力の強さから、日本のような長期間の低迷が続くとは予想していないが、少なくとも現在は混迷している。
ここからが重要だが、まず整理しておく。
・今の為替相場は、各国の金融政策に反応している展開である。
・米国では超金融緩和も2年も継続しているのに、失業率等の労働市場の改善は全く確認されない。
・米国の金融緩和政策は今後も相当期間継続する。
つまり、簡単に言えば今の環境が継続するという事だ。これは「ドル安は相当期間継続する」と言っているに等しい。(個人的にはドル安は十分進行しており、ここからはそれほど激しいドル安は起こらないと予想しているが、大きなドル反発も見込めない)
通貨安競争の犯人が政府であれば、問題はシンプルだ。世界の会議で話し合えばよい。為替へのコメントを控えればよい。しかし、実は政府はほとんど無力で、中央銀行が意図せざる犯人であるならば、問題はあまりに複雑である。日本の場合は、より特殊な道を歩み始めている。中央銀行が政府と一体化を始めているからである。前回決定した金融政策(基金の設立等)は、賛否両論あろうが、日銀OBは涙していることだろう。
そして、日銀は次回の金融政策決定会合は、米国のFOMCの直後に前倒しすることを決めた。これは米国で予想を上回る金融緩和が実施あれ、為替市場が円高に進んだ場合に、日銀もそれに追随して、すぐに追加の金融緩和を行う準備であり、メッセージである。これでは、まさに金融緩和競争、通貨安競争である。
円高は確かに深刻かもしれないが、過剰な新聞報道により、円高を阻止するために日銀が何でもやるというのは、これまでの金融の歴史(いろいろな教訓から学んだこと)を無視する行為で、その副作用は必ずあるだろう。円高を阻止するのは、中央銀行ではなく、政府の役目である。
どうしても、円高を止めるならば、金融緩和競争による為替変動の構図を中断させ、政府主導による協調介入の取り付け、ブラジル等の政府のように税金や規制の検討等、政府がその責任を取るべきではないだろうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
現場の外国為替! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
現場の外国為替!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37865人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90064人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人
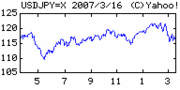














![[dir] FX](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/69/70/2046970_106s.jpg)








