「円高は日本の問題ではなく、米国の問題、ドル安の問題である」 藤井財務相はしばしばそのように発言している。確かにその通りだ。これまでのところは・・・
昨年のリーマンショック以降の嵐のような相場クラッシュの中で、円はほぼ独歩高となり全ての主要通貨に対して大幅に円高が進行した。しかし主要国の株価が3月で底を打ち反転し、経済も徐々に明るさを取り戻す中で、円はドル以外の通貨に対しては急速に弱くなった。例えば円はユーロに対して2月2日には114円台まで円高が進行していたが、現在(11月24日)は133円近辺の推移で20円ほど円安にふれている。ポンド円も1月23日には122円42銭まで円高が急激に進んだが、現在は148円近辺での推移だ。ドル円相場だけは現在も88円台で取引されており、年初来の円高値からそう遠くない水準にある。つまりは今年の相場は年初以降は、相変わらずドルも円も弱かったということで、円は全体的に俯瞰すれば円高どころか円安の状況であり、藤井財務相の言葉どおり、ドル円相場で円高が進行しているとすれば、「ドルがあまりに弱い」という米国側の理由に拠ると言えるだろう。
確かに考えてみれば、ここ10年の間日本を理由とした円高はあまり見られなかった。円高が起こる時は、今のようにドル安の裏返しとの円高進行や、何か市場でパニックが起こった時にポジションの巻き戻しによる円高などであった。
しかし、今日のテーマはいつまでそのようなコメントができるのか?ということである。つまり、米国サイドの理由でなく日本サイドの理由による円高は想定されないのかということである。実はこの問題は非常に興味深いテーマであると同時に、あまりに大きく幅広い問題であり、ポイントを絞りにくいのだが、今回私は日本の長期金利に注目してみたい。
日本で暮らしていると分かりにくいのだが、日本の長期金利は大きな謎に包まれている。異常に金利が低いのである。現在の日本の10年金利は1.3%近辺で推移している。米国の10年金利は3.3%台である。日米の政策金利はほぼゼロであり、短期金利についてはLiborで比べれば日本の金利は米国のそれを上回っている。ちなみに米国の10年金利も現在は歴史的に低い水準だ。それにも拘らず長期金利についてはこれだけの差がある。それは何故だろうか?
何故この国の長期金利はこんなにも低いのだろうか?そして今後この長期金利は上昇するのだろうか?そして長期金利が上昇すると為替相場はどうなるのか?これが今日の本論である。
まずそもそも長期金利とは何か?中央銀行、例えば米国のFRBがFOMCで決定しているFFレートとは無担保の翌日物金利である。つまり今日借りて明日返済する場合の政策金利を決定している。この金利が全ての金利のベースになることは言うまでもない。期間が長くなるということは、その期間に世の中でいろいろなことが起こる可能性を意味する。従って通常の金融環境では、長い期間の金利は、短期間の金利よりも利率が高くなる。こういう要因をリスクプレミアムと呼ぶ。また人類が生活を営むということは成長であり、これまた通常の環境では緩やかなインフレを生む。将来のこの国のインフレの動向への予想を期待インフレ率と呼ぶ。難しい話はできるだけ避けよう。大事なことは、長期金利とは政府が決定した短期金利の上に、人々の将来への思惑や期待、不安、需給などを反映して、市場で日々決定されていくということだ。「長期金利はコントロールできない」と指摘されるが、それはそこに人間の感情、先行きへの見通しが反映されるからだ。
もう一つ非常に重要なことがある。それは理論でなく、実際の売買、取引の問題である。新聞でたびたび話題になるが、日本の政府債務残高は先進国の中で際立って悪い状態であり、国債の消化が心配だというような記事である。民間の世界では住宅ローン等を例外とすれば、10年もの長期間の取引などほとんどない。銀行もお客さんに10年も資金を融資するなんてことはない。10年という期間が過ぎるからだ。しかし、国は10年物の国債を発行して民間から借金している。それが可能なのは国に信用力があるからだ。日本に住んでいる人で、本気で日本が破綻すると考えている人はそう多くない。
世の中の価格は何でも需給で決まる。国債も同様だ。先に挙げたようなことを理由に10年間の長期金利の水準が決まるが、実際に政府が発行する国債を買ってくれる人がいなければ、金利は上昇してしまう。逆に多くの人が国債を買いたいと考え(進んで政府にお金を貸す)れば、金利は低くなる。
日本の政府債務残高は2010年には200%近辺まで上昇し、国債の新規発行額もGDPの10%を超える50兆円以上まで膨らむ見通しである。これは国の信用力が落ち、その状態の中で更に巨額の借金をしようという試みであり、普通であれば金利が上昇しても不思議ではない。ところが日本の長期金利の水準は今でも異常に低い。
何故か?そこに日本の独自の秘密がある。これまでの日本の長期金利は以下の要因で支えられてきた。
? 国内の貯蓄が潤沢でお金が余っていること。そしてそのお金が向かうべき魅力的な投資機会が国内に乏しかったこと。
? 魅力的な投資機会が国内に乏しいにも関わらず、国内の投資家は海外投資に慎重で、国内へのバイアスが強かったこと。
? 長い間デフレに苦しめられたこともあり、将来の予想インフレ率が低い。
? 日本の国債の特徴として、海外保有比率が1割弱と低く、ほとんどが国内勢によって保有されており、さらに国内保有の7割が金融機関であるため、何か事が起こっても狼狽した債券売りが起こりにくかったこと。ちなみに米国の場合は、海外保有比率が約5割で、国内保有者のうち金融機関の割合は約3割に過ぎない。
さて、今後もこの環境は続くのだろうか?まず?に関しては日本の貯蓄率はどんどん低下している。特に今後は高齢化の進展で貯蓄率の低下は一段と進むだろう。政府は巨額の政府債務の補填のために、今後も巨額の国債発行によってお金を集めなければならない。消費税の引き上げ等をしても、この構図は変わらない。国内の民間部門の貯蓄で国債の発行を消化できなくなれば、海外投資家に頼らざるを得ないが、そのためには海外投資家に魅力的なレベルまで国債の利回りを上げなければならない。そうしなければ、わざわざ海外投資家は日本国債を保有しようとはしない。
?については近年では投資機会の多様化が進んでいるが、国債の最大の保有層である金融機関の投資スタイルは一朝一夕には変わらない。ここは非常に保守的であり、収益性よりもむしろ安全性が重視されるため、今後もホームバイアスは強いだろう。
?については日本の成熟国としての立場、高齢化等を考えると、今後も予想インフレ率は低いだろう。この国の潜在成長率も低いのだ。従って、長期金利が上昇しても他国を超えるような上昇ではなく、あくまでこれまでの異常な低金利の修正に過ぎない可能性が強い。
こうしてみてくると、日本の金利が上昇するかどうかの主要因は、日本の政府債務残高と国内民間部門の貯蓄のバランスの関係が最も大きくなりそうだ。恐らくすぐに懸念すべき事態が起こる可能性はないが、将来的には考えられるシナリオだ。
そしてもしも日本の長期金利が上昇すると、実は大きな円高を招く可能性がある。それは国内投資家がますますホームバイアスを強め、海外の資産を売却して国債に戻ることも考えられるし、海外の中央銀行が外貨準備のバランスのために日本国債に巨額の投資をすることも考えられる。そしてそれらは円高圧力となる。
次回は円高と介入について考えてみたい。
昨年のリーマンショック以降の嵐のような相場クラッシュの中で、円はほぼ独歩高となり全ての主要通貨に対して大幅に円高が進行した。しかし主要国の株価が3月で底を打ち反転し、経済も徐々に明るさを取り戻す中で、円はドル以外の通貨に対しては急速に弱くなった。例えば円はユーロに対して2月2日には114円台まで円高が進行していたが、現在(11月24日)は133円近辺の推移で20円ほど円安にふれている。ポンド円も1月23日には122円42銭まで円高が急激に進んだが、現在は148円近辺での推移だ。ドル円相場だけは現在も88円台で取引されており、年初来の円高値からそう遠くない水準にある。つまりは今年の相場は年初以降は、相変わらずドルも円も弱かったということで、円は全体的に俯瞰すれば円高どころか円安の状況であり、藤井財務相の言葉どおり、ドル円相場で円高が進行しているとすれば、「ドルがあまりに弱い」という米国側の理由に拠ると言えるだろう。
確かに考えてみれば、ここ10年の間日本を理由とした円高はあまり見られなかった。円高が起こる時は、今のようにドル安の裏返しとの円高進行や、何か市場でパニックが起こった時にポジションの巻き戻しによる円高などであった。
しかし、今日のテーマはいつまでそのようなコメントができるのか?ということである。つまり、米国サイドの理由でなく日本サイドの理由による円高は想定されないのかということである。実はこの問題は非常に興味深いテーマであると同時に、あまりに大きく幅広い問題であり、ポイントを絞りにくいのだが、今回私は日本の長期金利に注目してみたい。
日本で暮らしていると分かりにくいのだが、日本の長期金利は大きな謎に包まれている。異常に金利が低いのである。現在の日本の10年金利は1.3%近辺で推移している。米国の10年金利は3.3%台である。日米の政策金利はほぼゼロであり、短期金利についてはLiborで比べれば日本の金利は米国のそれを上回っている。ちなみに米国の10年金利も現在は歴史的に低い水準だ。それにも拘らず長期金利についてはこれだけの差がある。それは何故だろうか?
何故この国の長期金利はこんなにも低いのだろうか?そして今後この長期金利は上昇するのだろうか?そして長期金利が上昇すると為替相場はどうなるのか?これが今日の本論である。
まずそもそも長期金利とは何か?中央銀行、例えば米国のFRBがFOMCで決定しているFFレートとは無担保の翌日物金利である。つまり今日借りて明日返済する場合の政策金利を決定している。この金利が全ての金利のベースになることは言うまでもない。期間が長くなるということは、その期間に世の中でいろいろなことが起こる可能性を意味する。従って通常の金融環境では、長い期間の金利は、短期間の金利よりも利率が高くなる。こういう要因をリスクプレミアムと呼ぶ。また人類が生活を営むということは成長であり、これまた通常の環境では緩やかなインフレを生む。将来のこの国のインフレの動向への予想を期待インフレ率と呼ぶ。難しい話はできるだけ避けよう。大事なことは、長期金利とは政府が決定した短期金利の上に、人々の将来への思惑や期待、不安、需給などを反映して、市場で日々決定されていくということだ。「長期金利はコントロールできない」と指摘されるが、それはそこに人間の感情、先行きへの見通しが反映されるからだ。
もう一つ非常に重要なことがある。それは理論でなく、実際の売買、取引の問題である。新聞でたびたび話題になるが、日本の政府債務残高は先進国の中で際立って悪い状態であり、国債の消化が心配だというような記事である。民間の世界では住宅ローン等を例外とすれば、10年もの長期間の取引などほとんどない。銀行もお客さんに10年も資金を融資するなんてことはない。10年という期間が過ぎるからだ。しかし、国は10年物の国債を発行して民間から借金している。それが可能なのは国に信用力があるからだ。日本に住んでいる人で、本気で日本が破綻すると考えている人はそう多くない。
世の中の価格は何でも需給で決まる。国債も同様だ。先に挙げたようなことを理由に10年間の長期金利の水準が決まるが、実際に政府が発行する国債を買ってくれる人がいなければ、金利は上昇してしまう。逆に多くの人が国債を買いたいと考え(進んで政府にお金を貸す)れば、金利は低くなる。
日本の政府債務残高は2010年には200%近辺まで上昇し、国債の新規発行額もGDPの10%を超える50兆円以上まで膨らむ見通しである。これは国の信用力が落ち、その状態の中で更に巨額の借金をしようという試みであり、普通であれば金利が上昇しても不思議ではない。ところが日本の長期金利の水準は今でも異常に低い。
何故か?そこに日本の独自の秘密がある。これまでの日本の長期金利は以下の要因で支えられてきた。
? 国内の貯蓄が潤沢でお金が余っていること。そしてそのお金が向かうべき魅力的な投資機会が国内に乏しかったこと。
? 魅力的な投資機会が国内に乏しいにも関わらず、国内の投資家は海外投資に慎重で、国内へのバイアスが強かったこと。
? 長い間デフレに苦しめられたこともあり、将来の予想インフレ率が低い。
? 日本の国債の特徴として、海外保有比率が1割弱と低く、ほとんどが国内勢によって保有されており、さらに国内保有の7割が金融機関であるため、何か事が起こっても狼狽した債券売りが起こりにくかったこと。ちなみに米国の場合は、海外保有比率が約5割で、国内保有者のうち金融機関の割合は約3割に過ぎない。
さて、今後もこの環境は続くのだろうか?まず?に関しては日本の貯蓄率はどんどん低下している。特に今後は高齢化の進展で貯蓄率の低下は一段と進むだろう。政府は巨額の政府債務の補填のために、今後も巨額の国債発行によってお金を集めなければならない。消費税の引き上げ等をしても、この構図は変わらない。国内の民間部門の貯蓄で国債の発行を消化できなくなれば、海外投資家に頼らざるを得ないが、そのためには海外投資家に魅力的なレベルまで国債の利回りを上げなければならない。そうしなければ、わざわざ海外投資家は日本国債を保有しようとはしない。
?については近年では投資機会の多様化が進んでいるが、国債の最大の保有層である金融機関の投資スタイルは一朝一夕には変わらない。ここは非常に保守的であり、収益性よりもむしろ安全性が重視されるため、今後もホームバイアスは強いだろう。
?については日本の成熟国としての立場、高齢化等を考えると、今後も予想インフレ率は低いだろう。この国の潜在成長率も低いのだ。従って、長期金利が上昇しても他国を超えるような上昇ではなく、あくまでこれまでの異常な低金利の修正に過ぎない可能性が強い。
こうしてみてくると、日本の金利が上昇するかどうかの主要因は、日本の政府債務残高と国内民間部門の貯蓄のバランスの関係が最も大きくなりそうだ。恐らくすぐに懸念すべき事態が起こる可能性はないが、将来的には考えられるシナリオだ。
そしてもしも日本の長期金利が上昇すると、実は大きな円高を招く可能性がある。それは国内投資家がますますホームバイアスを強め、海外の資産を売却して国債に戻ることも考えられるし、海外の中央銀行が外貨準備のバランスのために日本国債に巨額の投資をすることも考えられる。そしてそれらは円高圧力となる。
次回は円高と介入について考えてみたい。
|
|
|
|
|
|
|
|
現場の外国為替! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
現場の外国為替!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人
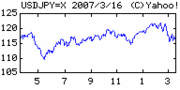














![[dir] FX](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/69/70/2046970_106s.jpg)








