前回の続きである。
前回のラストでは過去1年の為替相場の円高とドル高の理由について検討した。もう少し続けよう。
激しくドル高と円高が進んできた為替相場では、3月以降円高が反転し、ドル円相場では87円台から一時は100円台を回復した。クロス円も円安でユーロ円は113円台から130円台を回復している。
何が起こったのか?
これは以前テーマであげたが、日本は今回の金融危機の影響を最も受けていない安全な国だと思われ、逃避通貨として選好されてきたのだが、ここに暗雲が立ち込めたのである。すなわち、確かに金融機関の懸念度は欧米に比べれば小さいが、実態経済の影響は先進国の中で最も大きかったのである。先般発表された日本の1−3月期のGDPは年率で▲15.2%という激しいものだった。日本は再びデフレの恐怖に怯えているのである。
そうしたこともあり、円はこれまで一方的に買われ続けてきたのが、反転したのである。
それが最近は再びじりじりと円高が進行し、93円台に突入している。今回の為替相場の動きは明確だ。それは「ドルの全面安」だからだ。ドルは全ての通貨に対して弱含んでいる。ドルの全面安の地合いではクロス円は膠着する。
なぜドル安が進行しているのだろうか?
例の黄金の方程式=株安=円高が作用しているのだろうか?
ここが面白いのだが、確かに日々の中ではこの黄金の方程式はまだそれなりに有効に機能している。しかし以前に比べると、その有効度はかなり弱まっている。なにしろ株価は底値から30%以上も上昇しているのだ。
ドル安が進行している理由、これからもドル安が続くと思われる理由が主に3つある。
一つは前回のラストで書いたドル高の理由の一つが消滅していることである。それは金融危機に伴うドルの買い戻しである。今回の金融危機の震源地である米ドルが金融危機の真っただ中の買い戻された理由は、米国投資家、機関投資家などが採算などかえりみず、海外投資を引き揚げたことであった。しかし、その後の政府の強力なサポート等により、金融市場はとりあえず安定を取り戻し、株価等も大きく反転した。つまり危機に伴う後ろ向きなドル買い戻しは既に終了したのである。
2つ目は、今回の金融危機のダメージの後遺症である。米国の貿易赤字は景気後退の影響で急減している。金融危機前は毎月六百億ドル台の赤字を計上していたが、今では半減している。しかし、それでも赤字国であることに変わりはない。赤字国はその赤字を補填するために海外から資金を引き付ける必要があるが、これが難しくなっている。
それは金融危機のダメージにより世界中の投資家が静養中で、新たなリスクに慎重になっていること、米国の実質ゼロ金利政策により、魅力的な金利機会が望めないこと、更には財政赤字の急拡大の問題である。
米国の場合財政赤字はドル安材料となる。日本の場合は巨額の財政赤字があっても、日本の国債の保有はほとんどが日本国内の投資家であるため、通貨への影響は小さいが、米国債は海外投資家の保有率が非常に高いため、財政赤字はドル安に連動しやすいのである。
世界中の投資家が静養中であることは、我が国の機関投資家の動きでも顕著である。通常4月、5月は3月31日の決算を終えた機関投資家が、新たな外債投資に取り組む時期として有名だ。実際生保等は年間の外債投資の半分程度を4月、5月で終わらせる統計が出ている。ところが今年は、4月にほとんど投資が行われなかったという異例の結果が公表されている。投資に慎重なのだ。
最後の理由は、実はこれが本題であり、新しいテーマであるが、長期金利の動向である。昨年の金融危機への対処として各国の政府は異例の政策を次々に打ち出して、金融や経済を支えた。そしてこれからはいわゆるその「出口政策」が試されることになる。政府があれだけの異例な政策を実行すれば、必ず後遺症が出る。その後遺症を上手にコントロールできるかどうかというのが、今後の相場のテーマになると思料されるのだ。
そしてその判断は長期金利に現れる。ここ最近の動きとして、非常に注目されるのが、長期金利の値動きが非常に荒いという点がある。1日に10bp以上も変動する日がしばしばあるのだ。それだけ、このテーマが注目されている証であろう。
これからは出口政策への不安=長期金利上昇=通貨安という方程式が生まれそうだ。これまでは金利上昇=通貨高であったが、その反対の方程式である。
そうした観点で各国の金利を見ていくと、やはり危ないのが米国なのである。米国では長期金利がじりじり上昇しているほか、イールドカーブが急速にスティープ化している。イールドカーブのスティープ化とは、短期金利と長期金利の差が大きくなることだ。米ドルのlibor3か月が急低下しており、ついに円のliborとの差が15bpを割り込んだことが話題になっているが、こうしたliborの低下が長期金利の上昇とともに発生している点が危ないのである。
これからは株高=円安、株安=円高の黄金の方程式を横目に、悪い形での長期金利上昇=通貨安を正面から見ていく必要があるだろう。
前回のラストでは過去1年の為替相場の円高とドル高の理由について検討した。もう少し続けよう。
激しくドル高と円高が進んできた為替相場では、3月以降円高が反転し、ドル円相場では87円台から一時は100円台を回復した。クロス円も円安でユーロ円は113円台から130円台を回復している。
何が起こったのか?
これは以前テーマであげたが、日本は今回の金融危機の影響を最も受けていない安全な国だと思われ、逃避通貨として選好されてきたのだが、ここに暗雲が立ち込めたのである。すなわち、確かに金融機関の懸念度は欧米に比べれば小さいが、実態経済の影響は先進国の中で最も大きかったのである。先般発表された日本の1−3月期のGDPは年率で▲15.2%という激しいものだった。日本は再びデフレの恐怖に怯えているのである。
そうしたこともあり、円はこれまで一方的に買われ続けてきたのが、反転したのである。
それが最近は再びじりじりと円高が進行し、93円台に突入している。今回の為替相場の動きは明確だ。それは「ドルの全面安」だからだ。ドルは全ての通貨に対して弱含んでいる。ドルの全面安の地合いではクロス円は膠着する。
なぜドル安が進行しているのだろうか?
例の黄金の方程式=株安=円高が作用しているのだろうか?
ここが面白いのだが、確かに日々の中ではこの黄金の方程式はまだそれなりに有効に機能している。しかし以前に比べると、その有効度はかなり弱まっている。なにしろ株価は底値から30%以上も上昇しているのだ。
ドル安が進行している理由、これからもドル安が続くと思われる理由が主に3つある。
一つは前回のラストで書いたドル高の理由の一つが消滅していることである。それは金融危機に伴うドルの買い戻しである。今回の金融危機の震源地である米ドルが金融危機の真っただ中の買い戻された理由は、米国投資家、機関投資家などが採算などかえりみず、海外投資を引き揚げたことであった。しかし、その後の政府の強力なサポート等により、金融市場はとりあえず安定を取り戻し、株価等も大きく反転した。つまり危機に伴う後ろ向きなドル買い戻しは既に終了したのである。
2つ目は、今回の金融危機のダメージの後遺症である。米国の貿易赤字は景気後退の影響で急減している。金融危機前は毎月六百億ドル台の赤字を計上していたが、今では半減している。しかし、それでも赤字国であることに変わりはない。赤字国はその赤字を補填するために海外から資金を引き付ける必要があるが、これが難しくなっている。
それは金融危機のダメージにより世界中の投資家が静養中で、新たなリスクに慎重になっていること、米国の実質ゼロ金利政策により、魅力的な金利機会が望めないこと、更には財政赤字の急拡大の問題である。
米国の場合財政赤字はドル安材料となる。日本の場合は巨額の財政赤字があっても、日本の国債の保有はほとんどが日本国内の投資家であるため、通貨への影響は小さいが、米国債は海外投資家の保有率が非常に高いため、財政赤字はドル安に連動しやすいのである。
世界中の投資家が静養中であることは、我が国の機関投資家の動きでも顕著である。通常4月、5月は3月31日の決算を終えた機関投資家が、新たな外債投資に取り組む時期として有名だ。実際生保等は年間の外債投資の半分程度を4月、5月で終わらせる統計が出ている。ところが今年は、4月にほとんど投資が行われなかったという異例の結果が公表されている。投資に慎重なのだ。
最後の理由は、実はこれが本題であり、新しいテーマであるが、長期金利の動向である。昨年の金融危機への対処として各国の政府は異例の政策を次々に打ち出して、金融や経済を支えた。そしてこれからはいわゆるその「出口政策」が試されることになる。政府があれだけの異例な政策を実行すれば、必ず後遺症が出る。その後遺症を上手にコントロールできるかどうかというのが、今後の相場のテーマになると思料されるのだ。
そしてその判断は長期金利に現れる。ここ最近の動きとして、非常に注目されるのが、長期金利の値動きが非常に荒いという点がある。1日に10bp以上も変動する日がしばしばあるのだ。それだけ、このテーマが注目されている証であろう。
これからは出口政策への不安=長期金利上昇=通貨安という方程式が生まれそうだ。これまでは金利上昇=通貨高であったが、その反対の方程式である。
そうした観点で各国の金利を見ていくと、やはり危ないのが米国なのである。米国では長期金利がじりじり上昇しているほか、イールドカーブが急速にスティープ化している。イールドカーブのスティープ化とは、短期金利と長期金利の差が大きくなることだ。米ドルのlibor3か月が急低下しており、ついに円のliborとの差が15bpを割り込んだことが話題になっているが、こうしたliborの低下が長期金利の上昇とともに発生している点が危ないのである。
これからは株高=円安、株安=円高の黄金の方程式を横目に、悪い形での長期金利上昇=通貨安を正面から見ていく必要があるだろう。
|
|
|
|
|
|
|
|
現場の外国為替! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
現場の外国為替!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90018人
- 2位
- 酒好き
- 170665人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人
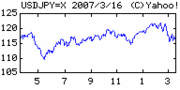














![[dir] FX](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/69/70/2046970_106s.jpg)








