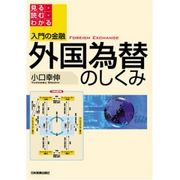☆ 外為取引はどこで、どのようにおこなわれるか
外為市場とは、コンピュータ端末や電話で結ばれた、「ネットワーク全体」の事を指している。
その市場は「銀行間市場」と「顧客市場」に分けることができる。
為替ディーラーには、以下の三種類がいる。
インターバンクディーラー
銀行間取引専門の人たち。
カスタマーディーラー
銀行以外の顧客を担当する。
プロプライアトリーディーラー
為替差益を狙ってポジションを専門に操作する。
外為市場は基本的に24時間市場である。
いつでも世界のどこかで市場が開いていて、我々はどこの市場でも外為を取り引きすることができる。
このようなことが可能なのも、外為市場の取引ルールや慣行が世界共通のものだからである。
外為市場とは、コンピュータ端末や電話で結ばれた、「ネットワーク全体」の事を指している。
その市場は「銀行間市場」と「顧客市場」に分けることができる。
為替ディーラーには、以下の三種類がいる。
インターバンクディーラー
銀行間取引専門の人たち。
カスタマーディーラー
銀行以外の顧客を担当する。
プロプライアトリーディーラー
為替差益を狙ってポジションを専門に操作する。
外為市場は基本的に24時間市場である。
いつでも世界のどこかで市場が開いていて、我々はどこの市場でも外為を取り引きすることができる。
このようなことが可能なのも、外為市場の取引ルールや慣行が世界共通のものだからである。
|
|
|
|
コメント(4)
☆ 拡大を続ける外為市場
その拡大の変遷を要約すると以下のようになる。
1973年、 変動相場制に移行してより拡大の一歩。
その背景には増大する貿易量があった。
80年代
資本取引の飛躍的増大
90年代
デリバティブの発展
2004年4月の調査では、一日あたりの平均取引高は2兆円近くになっていた。1994年4月平均の約二倍である。
銀行以外の金融機関、各種ファンド、さらにアジア通貨、東欧通貨などのの取引が増えてきたのがその背景にある。
一方でユーロの誕生により、通貨の数が減ったのはマイナス要因として働くだろう。
市場別ではロンドンがもっとも多く、全体の30%以上。ついでニューヨーク、東京、シンガポール、フランクフルト、香港市場と続く。
いずれの市場も、何時から何時まで、という時間的な決まりがあるわけではなく、朝に始まり、だいたい夕方に終わる、といったところ。
☆ 東京外為市場の特徴
NYやロンドンでは、銀行間取引が多いが、東京市場では顧客為替の比重が3割ほどもある。(NY、ロンドンでは1割程度)。
取り扱い通貨も、円に偏り、他の市場と比べローカル色が強い。
邦銀と外銀のシェアは、98年調査では 50:50 だったが、04年には 30:70 となっている。
90年代からの景気低迷により企業の為替取引が減少するとともに、市場全体の発展も遅れ気味となっている。
同時に日本の銀行の体力低下、東京の高コスト体質、税制上のデメリットなどもあり、アジア市場ではシンガポールが東京に肉薄している。
その拡大の変遷を要約すると以下のようになる。
1973年、 変動相場制に移行してより拡大の一歩。
その背景には増大する貿易量があった。
80年代
資本取引の飛躍的増大
90年代
デリバティブの発展
2004年4月の調査では、一日あたりの平均取引高は2兆円近くになっていた。1994年4月平均の約二倍である。
銀行以外の金融機関、各種ファンド、さらにアジア通貨、東欧通貨などのの取引が増えてきたのがその背景にある。
一方でユーロの誕生により、通貨の数が減ったのはマイナス要因として働くだろう。
市場別ではロンドンがもっとも多く、全体の30%以上。ついでニューヨーク、東京、シンガポール、フランクフルト、香港市場と続く。
いずれの市場も、何時から何時まで、という時間的な決まりがあるわけではなく、朝に始まり、だいたい夕方に終わる、といったところ。
☆ 東京外為市場の特徴
NYやロンドンでは、銀行間取引が多いが、東京市場では顧客為替の比重が3割ほどもある。(NY、ロンドンでは1割程度)。
取り扱い通貨も、円に偏り、他の市場と比べローカル色が強い。
邦銀と外銀のシェアは、98年調査では 50:50 だったが、04年には 30:70 となっている。
90年代からの景気低迷により企業の為替取引が減少するとともに、市場全体の発展も遅れ気味となっている。
同時に日本の銀行の体力低下、東京の高コスト体質、税制上のデメリットなどもあり、アジア市場ではシンガポールが東京に肉薄している。
☆ ロンドン外為市場の特徴
変動相場制開始以来、常に最大の市場。世界取引量の31%、東京市場の4倍弱。
英国経済が停滞しても、この地位は揺るぎない。それは、政策的に海外の金融機関が
自由に活動を保証され、英国の金融機関が取り立てて優遇されていないのが主たる理
由になっている。
さらに、アジアと米州との中間にあり、地理的にも恵まれている。
一日の始まりはシドニー、東京、シンガポールの順になり、最後は米国で終わるが、
その狭間にあるのが強みとなっている。
☆ NY市場の特徴
ロンドン市場が後場に入る頃、NY市場が開くため、特に午前中に売買が集中しやす
い。
午前には、世界中が注目する米国の経済指標の発表がしばしばおこなわれるので、値
動きも大きい。
さらにNY市場が世界の一日の終わりに開いているため、世界中のディーラーがポジ
ション調整のために売買をおこなうことが多く、出来高も増えやすい。
変動相場制開始以来、常に最大の市場。世界取引量の31%、東京市場の4倍弱。
英国経済が停滞しても、この地位は揺るぎない。それは、政策的に海外の金融機関が
自由に活動を保証され、英国の金融機関が取り立てて優遇されていないのが主たる理
由になっている。
さらに、アジアと米州との中間にあり、地理的にも恵まれている。
一日の始まりはシドニー、東京、シンガポールの順になり、最後は米国で終わるが、
その狭間にあるのが強みとなっている。
☆ NY市場の特徴
ロンドン市場が後場に入る頃、NY市場が開くため、特に午前中に売買が集中しやす
い。
午前には、世界中が注目する米国の経済指標の発表がしばしばおこなわれるので、値
動きも大きい。
さらにNY市場が世界の一日の終わりに開いているため、世界中のディーラーがポジ
ション調整のために売買をおこなうことが多く、出来高も増えやすい。
☆ 有力銀行の役割と市場への影響
銀行間市場では、ある銀行に為替レートを求めた場合、相手が求めてきたら自分も建値をしなければならないという相互主義がある。
つまり、売買の申し込みがあれば応じなければならない、ということ。
これには当然リスクも伴うため、為替取引に力を入れていない銀行、リスク許容量の小さな銀行では、直取引はしたがらない場合もある。そのような銀行はブローカーを利用するが、それでは完全に自分たちのペース(売買をしたいタイミングなど)では取引ができないため、有力銀行はブローカー取引と銀行間直取引の併用が多くなる。
東京市場の04年4月の調査では、10行ほどの有力銀行が銀行間市場の75%のシェアを持っているが、寡占が進むことは望ましくない。(98年度には55%程度だった)
以前はロンドン市場で、絶対的なシェアを持っていた数行が顧客に不当な取引価格を押しつけているとして、問題となったことがある。
☆ 影響力のある顧客の変遷
市場に影響力を与えるプレイヤーは時代とともに変わってきている。
・1970年代後半から80年代初め
旧西ドイツの自動車会社、ソ連の外国貿易銀行、中東の金融機関
・80年代半ば頃から
日本の生命保険会社等の機関投資家、アジアの中央銀行
・90年代
ヘッジファンド、アジアの中央銀行
・2000年代
ヘッジファンド、CTA(商品取引顧問業者)など
クォンタム・ファンドを率いるジョージ・ソロスが特に有名になったヘッジファンドであるが、その定義は曖昧のまま。
本来は投資した金融資産のリスクをヘッジするような取引に資金運用の特徴があったのでその名が付いた。
しかし現実には、運用方法も運用商品(株、債権、商品、各種のデリバティブ、不動産等々)も様々である。
2004年半ばの推計では、世界で約7000のヘッジファンドが、およそ8500億ドルの資金を運用されているとされる。
・ヘッジファンドの特色
私募形式といった限られたパートナー(富裕層、機関投資家、金融機関・・・)から資金を集める
国や市場から直接的な規制、監督をほとんど受けない
レバレッジを効かせて、少ない資金をもとに多額の資金を積極的に運用する
運用手数料(2%程度) にくわえて、運用成功報酬(20%程度) を取る
銀行間市場では、ある銀行に為替レートを求めた場合、相手が求めてきたら自分も建値をしなければならないという相互主義がある。
つまり、売買の申し込みがあれば応じなければならない、ということ。
これには当然リスクも伴うため、為替取引に力を入れていない銀行、リスク許容量の小さな銀行では、直取引はしたがらない場合もある。そのような銀行はブローカーを利用するが、それでは完全に自分たちのペース(売買をしたいタイミングなど)では取引ができないため、有力銀行はブローカー取引と銀行間直取引の併用が多くなる。
東京市場の04年4月の調査では、10行ほどの有力銀行が銀行間市場の75%のシェアを持っているが、寡占が進むことは望ましくない。(98年度には55%程度だった)
以前はロンドン市場で、絶対的なシェアを持っていた数行が顧客に不当な取引価格を押しつけているとして、問題となったことがある。
☆ 影響力のある顧客の変遷
市場に影響力を与えるプレイヤーは時代とともに変わってきている。
・1970年代後半から80年代初め
旧西ドイツの自動車会社、ソ連の外国貿易銀行、中東の金融機関
・80年代半ば頃から
日本の生命保険会社等の機関投資家、アジアの中央銀行
・90年代
ヘッジファンド、アジアの中央銀行
・2000年代
ヘッジファンド、CTA(商品取引顧問業者)など
クォンタム・ファンドを率いるジョージ・ソロスが特に有名になったヘッジファンドであるが、その定義は曖昧のまま。
本来は投資した金融資産のリスクをヘッジするような取引に資金運用の特徴があったのでその名が付いた。
しかし現実には、運用方法も運用商品(株、債権、商品、各種のデリバティブ、不動産等々)も様々である。
2004年半ばの推計では、世界で約7000のヘッジファンドが、およそ8500億ドルの資金を運用されているとされる。
・ヘッジファンドの特色
私募形式といった限られたパートナー(富裕層、機関投資家、金融機関・・・)から資金を集める
国や市場から直接的な規制、監督をほとんど受けない
レバレッジを効かせて、少ない資金をもとに多額の資金を積極的に運用する
運用手数料(2%程度) にくわえて、運用成功報酬(20%程度) を取る
☆ 外国為替ブローカーとその役割
銀行間の外為取引を仲介するのが外為ブローカーである。
様々な銀行が、売り・買いそれぞれの注文を寄せてくるのをつきあわせて、買値(ビッド・レート)と売値(オファー・レート)と、その量がつり合ったところで売買を成立させる。
かつて電話取り次ぎでおこなわれていた作業も今はコンピュータによる電子ブローキングが主流(9割ほど)となっている。その点は証券取引と似ている、というか、外為のほうが一歩先んじているようだ。
しかし、電話で注文を受ける取引も、システム障害にたいするリスク回避の観点から残されており、シェアも少し取り戻しつつある。
外為ブローカーはかつて、日本に8社あったが、今は3社だけとなっている。
☆ 新規参入と取引の拡大
日本の外為取引は、1980年に第一次外為法改正、98年に第二次改正があり、ほぼ完全自由化された。
これにより取引は、外為公認銀行を通じなくとも良くなり、誰とでもできるようになった。企業内部でも in と out を相殺できるようになり(ということは、昔はそれもできなかったのか・・!)、取引の絶対量が飛躍的に増大した。
これらの規制緩和措置によって、「外国為替保証金取引業者」が誕生した。
これは大別すると、以下の三者となる。
商品取引系業者
証券会社系
外為専業会社
これにくわえて、商社やインターネット系サービス会社も参入しつつある。
※ プライムブローキング
銀行はその信用力に応じて取引限度額が決まっている。
大手の有力銀行はその信用の余力を使い、取引枠を他の金融機関に貸すというサービスをおこなっている。
具体的には信用力の乏しい金融機関やヘッジファンド、CTAなどから、手数料や担保を取って、自分の名前で取り引きさせるというもの。
このサービスをプライムブローキングといい、おこなう主体(信用を貸す有力銀行)をプライムブローカーとよぶ。
このサービスが浸透して、外為取引はさらに量的に拡大し、また市場参加者も増加している。
銀行間の外為取引を仲介するのが外為ブローカーである。
様々な銀行が、売り・買いそれぞれの注文を寄せてくるのをつきあわせて、買値(ビッド・レート)と売値(オファー・レート)と、その量がつり合ったところで売買を成立させる。
かつて電話取り次ぎでおこなわれていた作業も今はコンピュータによる電子ブローキングが主流(9割ほど)となっている。その点は証券取引と似ている、というか、外為のほうが一歩先んじているようだ。
しかし、電話で注文を受ける取引も、システム障害にたいするリスク回避の観点から残されており、シェアも少し取り戻しつつある。
外為ブローカーはかつて、日本に8社あったが、今は3社だけとなっている。
☆ 新規参入と取引の拡大
日本の外為取引は、1980年に第一次外為法改正、98年に第二次改正があり、ほぼ完全自由化された。
これにより取引は、外為公認銀行を通じなくとも良くなり、誰とでもできるようになった。企業内部でも in と out を相殺できるようになり(ということは、昔はそれもできなかったのか・・!)、取引の絶対量が飛躍的に増大した。
これらの規制緩和措置によって、「外国為替保証金取引業者」が誕生した。
これは大別すると、以下の三者となる。
商品取引系業者
証券会社系
外為専業会社
これにくわえて、商社やインターネット系サービス会社も参入しつつある。
※ プライムブローキング
銀行はその信用力に応じて取引限度額が決まっている。
大手の有力銀行はその信用の余力を使い、取引枠を他の金融機関に貸すというサービスをおこなっている。
具体的には信用力の乏しい金融機関やヘッジファンド、CTAなどから、手数料や担保を取って、自分の名前で取り引きさせるというもの。
このサービスをプライムブローキングといい、おこなう主体(信用を貸す有力銀行)をプライムブローカーとよぶ。
このサービスが浸透して、外為取引はさらに量的に拡大し、また市場参加者も増加している。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
精読 外国為替のしくみ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-