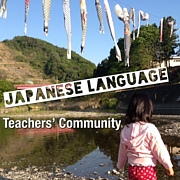言語教育公開講座
「多様化する教師、多様化する学習者 〜日本語教育の場合〜 」
ワークショップと講演会
主催:神田外語大学大学院言語科学研究科
対象者:主に日本語教育に関わるボランティア・養成講座受講生・教師・研究者・大学院生・大学生・一般
参加無料 詳細:http://
日時:9月17日(土)午前の部:10:00から 午後の部13:00から
場所:神田外語学院本館7階 講堂(東京都千代田区内神田2-13-13)
問い合わせ:岩本遠億(神田外語大学大学院教授)
iwamoto@kanda.kuis.ac.jp
+
テレビなどのメディアが日本語を自由に操る外国人を頻繁に登場させるようになり、日本語は日本人だけのものではないという事実が広く受け入れられるようになってきました。しかし、もう一方で、外国には片言の日本語で日本語を教える日本語教師がいるという現状や、体系的な日本語教育を受けることができない人々(労働力として日本に入って来た外国人やその子弟)に対する日本語の指導が社会的な課題となっていることは、あまり知られていません。
このような多様化の問題はかなり以前から存在していましたが、グローバル化の進む現在、日本語に関わるすべての人がそのことを意識すべき段階に入ったと言えるでしょう。多様化の進む日本語教育の現状はどのようなものであるのか、それにどのように対応することが求められるのか、実践報告から理論的考察まで、関連分野の最先端で働く専門家が分かりやすく話しをします。
+
また、日本語教育に関わる方々を対象にした音声と文法に関するワークショップを行い、共に問題を考えます。
・音声ワークショップ
音声は、どのような空気の流れを使うか、声を出すか出さないか、鼻に息が流れるか流れないかなど、いくつかの要素の組み合わせによって、その違いが作り出されます。このワークショップでは、実際に発音しながら、それぞれの要素を確認しつつ、日本語の音声の特徴を押さえ、学習者の日本語発音の問題点と解決法を考えるための基礎を作ります。
・文法ワークショップ
「ハとガは、学習者の誤用が多い学習項目の一つです。特に従属文を含む複雑な構造になると、誤用も増えます。このワークショップでは単文におけるハとガの用法と意味を確認したうえで、従属文を含む構造におけるハとガの使い分けがどのように行われているかを、主に動詞の語彙的特徴をもとに共に考えます。
+++
プログラム
【午前の部】 10時から12時
ワークショップ『日本語教育音声・文法再入門』
講師:木川 行央・岩本遠億
神田外語大学・大学院・言語科学研究科・教授
【午後の部】 13時から16時30分
基調講演『多様性から見た日本語教育の現状と展望』
講師:尾崎 明人 日本語教育学会会長
名古屋外国語大学・外国語学部・日本語学科・教授
講演�鵯『地域日本語教育における教育支援』
講師:伊藤 健人 群馬県立女子大学・文学部・国文学科・准教授
講演�鵺『外国人日本語教師の研修とその教育現場』
講師:木田 真理 国際交流基金・日本語国際センター・専任講師
講演�鶚『第二言語習得・教育研究の視点から』
講師:堀場 裕紀江 神田外語大学・大学院・言語科学研究科・教授
16時30分〜 懇親会・交流会
+++
講演要旨ならびに講師略歴
「多様性から見た日本語教育の現状と展望」
尾崎 明人
多様性の観点から日本語教育が抱える多様な課題とその将来について考えてみたい.国内では,日本語学習者の多様化にともないそのニーズに対応する多様な日本語教育が行われるようになった.しかし,教室の「学習者」が教室外では「使用者(学習者)」であるという事実に注目すると,従来の学習者のカテゴリー化では見えにくかった課題が見えてくる.日本語学習者の多様化は教師の多様化をもたらす.
一方で,ボランティア依存の地域日本語教育の現状を見ると,教師の専門性が改めて問われていると言えるだろう.教師とは資格要件が求められる職業であり,教師が教師であるためには,教育経験と自己研鑽をとおして学び続けねばならない.海外の日本語教育も多様であるが,それぞれが抱えるさまざまな課題に取り組むには世界の日本語教育関係者が連携することも大事である.
<略歴>
国際基督教大学教養学部語学科(日本語教育専攻)卒業.モナシュ大学にてPh.D取得.東海大学留学生別科,モナシュ大学文学部日本研究科,姫路獨協大学外国語学部,名古屋大学留学生センターを経て,2006年から名古屋外国語大学教授.日本語教育学会理事,副会長,国立国語研究所評議員,東海日本語ネットワーク協議員,日本語教育振興協会専門員などを歴任.2007年6月より(社)日本語教育学会会長.接触場面の会話分析,地域日本語教育の方法論を研究テーマとする.
主な業績:『日本語教育叢書つくる 会話教材を作る』(共著), スリーエーネットワーク,2010.「地域の日本語教育:成人の学習者を対象に」『講座日本語教育学第5巻 多文化間の教育と近接領域』(縫部義憲監修・倉地暁美編集), スリーエーネットワーク,2006.「地域日本語教育の方法論試案」『言語と教育−日本語を中心として』(小山悟他編), くろしお出版,2004.「日本語教師のエンカレッジメントとディスカレッジメント」『ことばと文化を結ぶ日本語教育』(細川英雄編), 凡人社,2002.『日本語教育学を学ぶ人のために』(共編),世界思想社,2001.
✾
「地域日本語教育における教育支援」
伊藤 健人
日本語を学んでいる外国人と聞くと,多くの人は,日本語学校や大学などで学んでいる留学生の姿を思い浮かべるのではないだろうか.しかし,日本国内の外国人登録者数に占める留学生の割合は8%程度でしかなく,留学生の何倍もの人々が生活のための日本語を必要としている.具体的には,日系ブラジル人・ペルー人などの定住者,フィリピンや中国などからの日本人の配偶者,ベトナムからの難民,そして中国,インドネシア,ベトナムなどからの研修生,さらにフィリピンやインドネシアからの看護師や介護福祉士など,多くの外国人が地域の日本語教育の場にいる.この講演では,地域日本語教育においてどのような日本語教育支援が行われているか,そして,今後どのような支援が望まれているかを中心に話をする.
<略歴>
群馬県立女子大学・文学部・准教授.博士(言語学)2005年3月,神田外語大学.日本学術振興会特別研究員,明海大学を経て,群馬県立女子大学へ.以来,群馬県国際課アドバイザーとして地域日本語教育に携わる.著書に『イメージ・スキーマに基づく格パターン構文』ひつじ書房,『日本語学習・生活ハンドブック』文化庁など.
✾
「外国人日本語教師の研修とその教育現場」
木田 真理
設立21年目を迎えた国際交流基金日本語国際センターでは,外国人日本語教師(以下NNT)研修を実施している.NNTが自国で取り組んでいる日本語教育は様々なものであり,NNT自身も,年齢,国籍,日本語教授歴,日本語学習歴,教授機関の教育段階など多様な背景を持っている.現在,海外で教える日本語教師の70%がNNTであるが,NNTは,外国語として日本語を学習した経験をもち,日本語教師という面だけでなく,日本語学習者としての面も兼ね備えているという特徴を持つ.本発表では,日本語を母語としない日本語教師の多様性,その背景にあるそれぞれの国の日本語教育の現場の多様性について,外国人日本語教師研修の観点から考察する.
<略歴>
国内日本語学校や大学非常勤講師をへて,1994年より国際交流基金日本語国際センター専任講師.外国人日本語教師研修のカリキュラム策定,教授法授業,文法授業を主に担当.専門分野は日本語教育,教師教育,日本語学.国際交流基金教授法シリーズ(ひつじ書房)では,『話すことを教える』『文法を教える』『文字・語彙を教える』の執筆を担当.
✾
「第二言語習得・教育研究の視点から」
堀場 裕紀江
日本語の学習者・教師・使用者における多様化・多様性の意味と課題について第二言語習得・教育研究の視点から考えるために,いくつかの代表的なモデル・理論的枠組みを使って基本的かつ重要な質問に対する答えを考えてみたい.取り上げる質問は(1)学習とはなにか.学習者とは誰か.(2)教師の役割は何か.(3)言語教育は何を目指すべきか.(4)言語教育の中で文化をどう扱うべきか.(5)学習者の意欲を引き出し自立性を育てるために教師は何をするべきか.そして(6)言語習得・教育の研究と実践の関係はどうあるべきか.関連する研究・教育分野に蓄積された知識から学び,新しい動向に目を向けることによって,これからの日本語教育に関わる我々(教師・研究者・教育関係者)に何が求められるか,何ができるかが見えてくるのではないか.
<略歴>
神田外語大学大学院・言語科学研究科,教授(応用言語学・言語教育学). 名古屋大学(教育学)卒業,オハイオ州立大学よりM.A. (英語教育学),ミネソタ大学よりPh.D.(第2言語文化教育学)を取得.マサチューセッツ大学・准教授(日本語・言語文化教育, 1990-1999)を経て,1999年より現職.主な研究関心は(日本語・英語)読解,語彙,評価,タスク・指導法,教師教育.
代表的な論文はDiscourse Processes, Language Learning, Modern Language Journal, Studies in Second Language Acquisition,第二言語としての日本語の習得研究や『英文読解のプロセスと指導』(津田塾大言文研読解研究グループ編, 大修館書店)などに掲載.
「多様化する教師、多様化する学習者 〜日本語教育の場合〜 」
ワークショップと講演会
主催:神田外語大学大学院言語科学研究科
対象者:主に日本語教育に関わるボランティア・養成講座受講生・教師・研究者・大学院生・大学生・一般
参加無料 詳細:http://
日時:9月17日(土)午前の部:10:00から 午後の部13:00から
場所:神田外語学院本館7階 講堂(東京都千代田区内神田2-13-13)
問い合わせ:岩本遠億(神田外語大学大学院教授)
iwamoto@kanda.kuis.ac.jp
+
テレビなどのメディアが日本語を自由に操る外国人を頻繁に登場させるようになり、日本語は日本人だけのものではないという事実が広く受け入れられるようになってきました。しかし、もう一方で、外国には片言の日本語で日本語を教える日本語教師がいるという現状や、体系的な日本語教育を受けることができない人々(労働力として日本に入って来た外国人やその子弟)に対する日本語の指導が社会的な課題となっていることは、あまり知られていません。
このような多様化の問題はかなり以前から存在していましたが、グローバル化の進む現在、日本語に関わるすべての人がそのことを意識すべき段階に入ったと言えるでしょう。多様化の進む日本語教育の現状はどのようなものであるのか、それにどのように対応することが求められるのか、実践報告から理論的考察まで、関連分野の最先端で働く専門家が分かりやすく話しをします。
+
また、日本語教育に関わる方々を対象にした音声と文法に関するワークショップを行い、共に問題を考えます。
・音声ワークショップ
音声は、どのような空気の流れを使うか、声を出すか出さないか、鼻に息が流れるか流れないかなど、いくつかの要素の組み合わせによって、その違いが作り出されます。このワークショップでは、実際に発音しながら、それぞれの要素を確認しつつ、日本語の音声の特徴を押さえ、学習者の日本語発音の問題点と解決法を考えるための基礎を作ります。
・文法ワークショップ
「ハとガは、学習者の誤用が多い学習項目の一つです。特に従属文を含む複雑な構造になると、誤用も増えます。このワークショップでは単文におけるハとガの用法と意味を確認したうえで、従属文を含む構造におけるハとガの使い分けがどのように行われているかを、主に動詞の語彙的特徴をもとに共に考えます。
+++
プログラム
【午前の部】 10時から12時
ワークショップ『日本語教育音声・文法再入門』
講師:木川 行央・岩本遠億
神田外語大学・大学院・言語科学研究科・教授
【午後の部】 13時から16時30分
基調講演『多様性から見た日本語教育の現状と展望』
講師:尾崎 明人 日本語教育学会会長
名古屋外国語大学・外国語学部・日本語学科・教授
講演�鵯『地域日本語教育における教育支援』
講師:伊藤 健人 群馬県立女子大学・文学部・国文学科・准教授
講演�鵺『外国人日本語教師の研修とその教育現場』
講師:木田 真理 国際交流基金・日本語国際センター・専任講師
講演�鶚『第二言語習得・教育研究の視点から』
講師:堀場 裕紀江 神田外語大学・大学院・言語科学研究科・教授
16時30分〜 懇親会・交流会
+++
講演要旨ならびに講師略歴
「多様性から見た日本語教育の現状と展望」
尾崎 明人
多様性の観点から日本語教育が抱える多様な課題とその将来について考えてみたい.国内では,日本語学習者の多様化にともないそのニーズに対応する多様な日本語教育が行われるようになった.しかし,教室の「学習者」が教室外では「使用者(学習者)」であるという事実に注目すると,従来の学習者のカテゴリー化では見えにくかった課題が見えてくる.日本語学習者の多様化は教師の多様化をもたらす.
一方で,ボランティア依存の地域日本語教育の現状を見ると,教師の専門性が改めて問われていると言えるだろう.教師とは資格要件が求められる職業であり,教師が教師であるためには,教育経験と自己研鑽をとおして学び続けねばならない.海外の日本語教育も多様であるが,それぞれが抱えるさまざまな課題に取り組むには世界の日本語教育関係者が連携することも大事である.
<略歴>
国際基督教大学教養学部語学科(日本語教育専攻)卒業.モナシュ大学にてPh.D取得.東海大学留学生別科,モナシュ大学文学部日本研究科,姫路獨協大学外国語学部,名古屋大学留学生センターを経て,2006年から名古屋外国語大学教授.日本語教育学会理事,副会長,国立国語研究所評議員,東海日本語ネットワーク協議員,日本語教育振興協会専門員などを歴任.2007年6月より(社)日本語教育学会会長.接触場面の会話分析,地域日本語教育の方法論を研究テーマとする.
主な業績:『日本語教育叢書つくる 会話教材を作る』(共著), スリーエーネットワーク,2010.「地域の日本語教育:成人の学習者を対象に」『講座日本語教育学第5巻 多文化間の教育と近接領域』(縫部義憲監修・倉地暁美編集), スリーエーネットワーク,2006.「地域日本語教育の方法論試案」『言語と教育−日本語を中心として』(小山悟他編), くろしお出版,2004.「日本語教師のエンカレッジメントとディスカレッジメント」『ことばと文化を結ぶ日本語教育』(細川英雄編), 凡人社,2002.『日本語教育学を学ぶ人のために』(共編),世界思想社,2001.
✾
「地域日本語教育における教育支援」
伊藤 健人
日本語を学んでいる外国人と聞くと,多くの人は,日本語学校や大学などで学んでいる留学生の姿を思い浮かべるのではないだろうか.しかし,日本国内の外国人登録者数に占める留学生の割合は8%程度でしかなく,留学生の何倍もの人々が生活のための日本語を必要としている.具体的には,日系ブラジル人・ペルー人などの定住者,フィリピンや中国などからの日本人の配偶者,ベトナムからの難民,そして中国,インドネシア,ベトナムなどからの研修生,さらにフィリピンやインドネシアからの看護師や介護福祉士など,多くの外国人が地域の日本語教育の場にいる.この講演では,地域日本語教育においてどのような日本語教育支援が行われているか,そして,今後どのような支援が望まれているかを中心に話をする.
<略歴>
群馬県立女子大学・文学部・准教授.博士(言語学)2005年3月,神田外語大学.日本学術振興会特別研究員,明海大学を経て,群馬県立女子大学へ.以来,群馬県国際課アドバイザーとして地域日本語教育に携わる.著書に『イメージ・スキーマに基づく格パターン構文』ひつじ書房,『日本語学習・生活ハンドブック』文化庁など.
✾
「外国人日本語教師の研修とその教育現場」
木田 真理
設立21年目を迎えた国際交流基金日本語国際センターでは,外国人日本語教師(以下NNT)研修を実施している.NNTが自国で取り組んでいる日本語教育は様々なものであり,NNT自身も,年齢,国籍,日本語教授歴,日本語学習歴,教授機関の教育段階など多様な背景を持っている.現在,海外で教える日本語教師の70%がNNTであるが,NNTは,外国語として日本語を学習した経験をもち,日本語教師という面だけでなく,日本語学習者としての面も兼ね備えているという特徴を持つ.本発表では,日本語を母語としない日本語教師の多様性,その背景にあるそれぞれの国の日本語教育の現場の多様性について,外国人日本語教師研修の観点から考察する.
<略歴>
国内日本語学校や大学非常勤講師をへて,1994年より国際交流基金日本語国際センター専任講師.外国人日本語教師研修のカリキュラム策定,教授法授業,文法授業を主に担当.専門分野は日本語教育,教師教育,日本語学.国際交流基金教授法シリーズ(ひつじ書房)では,『話すことを教える』『文法を教える』『文字・語彙を教える』の執筆を担当.
✾
「第二言語習得・教育研究の視点から」
堀場 裕紀江
日本語の学習者・教師・使用者における多様化・多様性の意味と課題について第二言語習得・教育研究の視点から考えるために,いくつかの代表的なモデル・理論的枠組みを使って基本的かつ重要な質問に対する答えを考えてみたい.取り上げる質問は(1)学習とはなにか.学習者とは誰か.(2)教師の役割は何か.(3)言語教育は何を目指すべきか.(4)言語教育の中で文化をどう扱うべきか.(5)学習者の意欲を引き出し自立性を育てるために教師は何をするべきか.そして(6)言語習得・教育の研究と実践の関係はどうあるべきか.関連する研究・教育分野に蓄積された知識から学び,新しい動向に目を向けることによって,これからの日本語教育に関わる我々(教師・研究者・教育関係者)に何が求められるか,何ができるかが見えてくるのではないか.
<略歴>
神田外語大学大学院・言語科学研究科,教授(応用言語学・言語教育学). 名古屋大学(教育学)卒業,オハイオ州立大学よりM.A. (英語教育学),ミネソタ大学よりPh.D.(第2言語文化教育学)を取得.マサチューセッツ大学・准教授(日本語・言語文化教育, 1990-1999)を経て,1999年より現職.主な研究関心は(日本語・英語)読解,語彙,評価,タスク・指導法,教師教育.
代表的な論文はDiscourse Processes, Language Learning, Modern Language Journal, Studies in Second Language Acquisition,第二言語としての日本語の習得研究や『英文読解のプロセスと指導』(津田塾大言文研読解研究グループ編, 大修館書店)などに掲載.
|
|
|
|
|
|
|
|
☆日本語教師☆ 更新情報
-
最新のアンケート