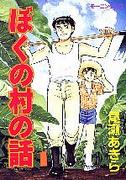|
|
|
|
コメント(23)
うわわ、こんな幽霊コミュに書き込みありがとうございます。
管理人の私は、既に最後に通して読んだのが8年位前。単行本持ってません。トホホ。
反対同盟が大きく二つに分裂したのは70年代の話で、連載当時はその一方(比較的穏健とされる)が、国と「シンポジウム」を行い、成田の歴史上初めて国が反対派と一応対等に交渉を行う、というようなことが進行していた頃です。このシンポジウムの評価自体は現在もさまざまですが。尾瀬あきらはシンポジウムの取材を通じて成田の人たちに話を聞いていたそうです。
連載が唐突に終わった印象があるのは、同盟が分裂する以前しか描いておらず、というか作者も書くことが出来ず、「僕はまだこの村に住んでいる」といきなり20年ほど時間が飛んでしまうからだと思います。少年の眼から見たファンタジックな描写(冒頭の白い馬やラストの蛍の群れ)を貫いていることもあって、反対する人々の分裂話が物語の素材として扱いにくい、またモデルとなる人々のそれぞれの立場に配慮すると描きにくいというのが大きな要因かな、と思っています。
この連載をはじめる前、「夏子の酒」(この取材で農業に興味を持ち成田闘争にたどりついたそうです)の大ヒットがあり、作者は「この話を描かせないなら「夏子」の単行本は出させない」と編集部と交渉した、と言われています。「夏子の酒」や「奈津の蔵」は何度も再版されるのに「ぼくの村の話」が出ないのは、やっぱり売れなかったんだろうな、単行本。
管理人の私は、既に最後に通して読んだのが8年位前。単行本持ってません。トホホ。
反対同盟が大きく二つに分裂したのは70年代の話で、連載当時はその一方(比較的穏健とされる)が、国と「シンポジウム」を行い、成田の歴史上初めて国が反対派と一応対等に交渉を行う、というようなことが進行していた頃です。このシンポジウムの評価自体は現在もさまざまですが。尾瀬あきらはシンポジウムの取材を通じて成田の人たちに話を聞いていたそうです。
連載が唐突に終わった印象があるのは、同盟が分裂する以前しか描いておらず、というか作者も書くことが出来ず、「僕はまだこの村に住んでいる」といきなり20年ほど時間が飛んでしまうからだと思います。少年の眼から見たファンタジックな描写(冒頭の白い馬やラストの蛍の群れ)を貫いていることもあって、反対する人々の分裂話が物語の素材として扱いにくい、またモデルとなる人々のそれぞれの立場に配慮すると描きにくいというのが大きな要因かな、と思っています。
この連載をはじめる前、「夏子の酒」(この取材で農業に興味を持ち成田闘争にたどりついたそうです)の大ヒットがあり、作者は「この話を描かせないなら「夏子」の単行本は出させない」と編集部と交渉した、と言われています。「夏子の酒」や「奈津の蔵」は何度も再版されるのに「ぼくの村の話」が出ないのは、やっぱり売れなかったんだろうな、単行本。
日本テレビ「ドキュメント06」で三里塚のドキュメンタリー番組「機影の下の闘い 終わらない成田闘争」(仮)が8月20日(日)24時25分〜55分(日本テレビ)に放送されるそうです。
※日本テレビ系は全部やっていると思いますが、放送時間は地域で違うかもしれないので確認してください。
日テレの番組サイト
http://www.ntv.co.jp/document/
---------------------------------------------------
機影の下の闘い 終わらない成田闘争(仮)
2006年8月20日(日)/30分枠
機影の下の闘い 終わらない成田闘争(仮)制作=日本テレビ
未買収地での田植え02年のW杯サッカーにあわせ成田空港の暫定滑走路がオープンした。
当初計画より320m短いのは移転を拒む地権者がいるからだ。反対派の最後の砦、東峰地区。1日の離発着155便。頭上40mを飛行機が飛ぶ度に家屋はきしみ騒音がとどろく。地権者の一人石井紀子さんは国に対する怒りの反面、次の世代にこの生活を続けさせるか迷い始めている。40年続く成田闘争は国際競争から取り残される空港と農民、双方を厳しい状況に追い込んでいるのだ。元空港公団の交渉人や支援学生など様々な立場から40年目の成田闘争をみつめる。
----------------------------------------------
※日本テレビ系は全部やっていると思いますが、放送時間は地域で違うかもしれないので確認してください。
日テレの番組サイト
http://www.ntv.co.jp/document/
---------------------------------------------------
機影の下の闘い 終わらない成田闘争(仮)
2006年8月20日(日)/30分枠
機影の下の闘い 終わらない成田闘争(仮)制作=日本テレビ
未買収地での田植え02年のW杯サッカーにあわせ成田空港の暫定滑走路がオープンした。
当初計画より320m短いのは移転を拒む地権者がいるからだ。反対派の最後の砦、東峰地区。1日の離発着155便。頭上40mを飛行機が飛ぶ度に家屋はきしみ騒音がとどろく。地権者の一人石井紀子さんは国に対する怒りの反面、次の世代にこの生活を続けさせるか迷い始めている。40年続く成田闘争は国際競争から取り残される空港と農民、双方を厳しい状況に追い込んでいるのだ。元空港公団の交渉人や支援学生など様々な立場から40年目の成田闘争をみつめる。
----------------------------------------------
ども。はじめまして。
連載中はいつ打ち切られてしまうか、あるいはどこまで(いつ頃までのエピソードを)描くのかと、ヒヤヒヤしながら見ていました。
リアルの「三里塚闘争入門」として見れば、ちんころくさんの書評通り、いろいろ物足りないものはあると思います。
しかし、この闘争にかかわった人々のメンタルな部分、どうして自分達にとってなんの得にもならないこの闘いに、多くの人が青春や人生を賭けて飛び込んでいったのか、そういう叙情的な部分が、プロパガンダくさくならずに、みごとに表現されていると思います。
反対派農家の少年(次男)の視点から描き、闘争の歴史につれて小学生だった主人公も思春期を迎えて成長していくという設定も成功していると思う。
これは私にとっては、自分の子供や妻、恋人など、近しい人に読んでほしいと思う作品です。自分がどんな思いで青春をすごしてきたのか、自分が愛する身近な人には、理屈ではなく、心情としてわかってほしい、知ってほしいから。
そう、プロパガンダ的な意味で「賛成してほしい」ではなく、愛するがゆえに「わかってほしい」人と共に読んで語り合いたい。それがこの作品です。
連載中はいつ打ち切られてしまうか、あるいはどこまで(いつ頃までのエピソードを)描くのかと、ヒヤヒヤしながら見ていました。
リアルの「三里塚闘争入門」として見れば、ちんころくさんの書評通り、いろいろ物足りないものはあると思います。
しかし、この闘争にかかわった人々のメンタルな部分、どうして自分達にとってなんの得にもならないこの闘いに、多くの人が青春や人生を賭けて飛び込んでいったのか、そういう叙情的な部分が、プロパガンダくさくならずに、みごとに表現されていると思います。
反対派農家の少年(次男)の視点から描き、闘争の歴史につれて小学生だった主人公も思春期を迎えて成長していくという設定も成功していると思う。
これは私にとっては、自分の子供や妻、恋人など、近しい人に読んでほしいと思う作品です。自分がどんな思いで青春をすごしてきたのか、自分が愛する身近な人には、理屈ではなく、心情としてわかってほしい、知ってほしいから。
そう、プロパガンダ的な意味で「賛成してほしい」ではなく、愛するがゆえに「わかってほしい」人と共に読んで語り合いたい。それがこの作品です。
はじめまして
この作品は、連載された時に、どうせたいした取材もしないで書くのだろと思って読んでませんでした、あるときに知り合いから千葉県土地収用委員会にもおいてあるって聞いて、最近取り寄せました。
主人公はおいらの1つ年下ですが、あのときに高校生のおいらは三里塚に行っていて、よねばぁちゃんの家に入り浸っていました、支援の団結小屋がすぐ上の一坪共有地にあったので。
反対同盟の農家の次男坊も同じ年で、そのお姉さんは、亡くなられた純さんのモデルの青年を好きだったそうです(最近聞きました)
機動隊が死んだ闘いで、おいらも青年行動隊と一緒に逮捕され、そのことが縁で今でも通っています。
綺麗に飾ってはいますが、ほとんど実在の話です。
初めて行ったときの、御料牧場のあとの山野は綺麗でした。
「なんでこんな綺麗なところに空港を造るのか?」それが印象です。
そのうち大地はブルトーザーやユンボで無残にも削り壊され、破壊されていきました。
あのころに食べたスイカと新米が一生忘れられない。
この作品は、連載された時に、どうせたいした取材もしないで書くのだろと思って読んでませんでした、あるときに知り合いから千葉県土地収用委員会にもおいてあるって聞いて、最近取り寄せました。
主人公はおいらの1つ年下ですが、あのときに高校生のおいらは三里塚に行っていて、よねばぁちゃんの家に入り浸っていました、支援の団結小屋がすぐ上の一坪共有地にあったので。
反対同盟の農家の次男坊も同じ年で、そのお姉さんは、亡くなられた純さんのモデルの青年を好きだったそうです(最近聞きました)
機動隊が死んだ闘いで、おいらも青年行動隊と一緒に逮捕され、そのことが縁で今でも通っています。
綺麗に飾ってはいますが、ほとんど実在の話です。
初めて行ったときの、御料牧場のあとの山野は綺麗でした。
「なんでこんな綺麗なところに空港を造るのか?」それが印象です。
そのうち大地はブルトーザーやユンボで無残にも削り壊され、破壊されていきました。
あのころに食べたスイカと新米が一生忘れられない。
はじめまして。最近、やっとこのコミュを知ちゃものです。
ある知人と台湾映画・「セデック・バレ」について話し合っている時、この作品の名が出て、20年ぶりくらいかな、思い出しました。
それで、映画「セデック・バレ」と重ねてこの作品を思い出し(全巻持っていません。事情によりKindle版はサンプルを最初数巻のみ)、思考し直しました。
この作品、尾瀬あきらの他の作品も、ヴァナキュラー(非近代的な土着的なもの)と産業的なもの、または伝統的なものと現代的なものとの葛藤・相克を見事に描いている。
その点に改めて気がつきました。
不登校を始めてから、元全共闘との付き合いが生じ、学校の持つ国家権力性に嫌気が指しました。
自分たちが闘っているものを充分に教えてはくれなかったものの、その萌芽は与えてもらったと思います。
立つ学校を唱える文明批評家・イリイチのヴァナキュラーなものが美しく描かれ、やがてそれは産業国家によって無残に破壊されていく様を連載当時はコンビニ立ち読みではよく分かりませんでした。
予備校は、イヤイヤ通っていましたが、市民活動を通じて元全共闘や元ヒッピー、元ウーマンリブや青い芝の会的な文化に触れました。
それの生じた時代と地域の風景を、尾瀬あきらさんの「ぼくの村の話」は上手に伝えてくれています。
ある知人と台湾映画・「セデック・バレ」について話し合っている時、この作品の名が出て、20年ぶりくらいかな、思い出しました。
それで、映画「セデック・バレ」と重ねてこの作品を思い出し(全巻持っていません。事情によりKindle版はサンプルを最初数巻のみ)、思考し直しました。
この作品、尾瀬あきらの他の作品も、ヴァナキュラー(非近代的な土着的なもの)と産業的なもの、または伝統的なものと現代的なものとの葛藤・相克を見事に描いている。
その点に改めて気がつきました。
不登校を始めてから、元全共闘との付き合いが生じ、学校の持つ国家権力性に嫌気が指しました。
自分たちが闘っているものを充分に教えてはくれなかったものの、その萌芽は与えてもらったと思います。
立つ学校を唱える文明批評家・イリイチのヴァナキュラーなものが美しく描かれ、やがてそれは産業国家によって無残に破壊されていく様を連載当時はコンビニ立ち読みではよく分かりませんでした。
予備校は、イヤイヤ通っていましたが、市民活動を通じて元全共闘や元ヒッピー、元ウーマンリブや青い芝の会的な文化に触れました。
それの生じた時代と地域の風景を、尾瀬あきらさんの「ぼくの村の話」は上手に伝えてくれています。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ぼくの村の話 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ぼくの村の話のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90004人
- 3位
- 酒好き
- 170654人