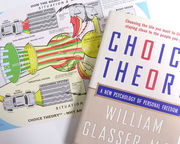私の一昨日の日記で、マイミクのマサさんが
ご自身のセミナーで扱っていらっしゃる内容を熱く語ってくださったので、
それを受けて、選択理論の基本的欲求の歴史(?)を
ちょっと書き留めておきたいと思います。
グラッサー先生の最初の著書『現実療法』では、基本的欲求について、
「愛し愛される欲求」と
「自分は自分自身と他人にとって価値あるものだと感じる欲求」として、
今で言う「愛・所属の欲求」と「力の欲求」の
二つの欲求だけを挙げていました。
そして「これら二つの欲求の充足で患者を手助けするのが、現実療法の基本である」
といわれていました。
やがて、これに「自由の欲求」と「楽しみの欲求」、
そして身体的な要素を司っている「生存の欲求」が加わって
いまでは、五つの基本的欲求として紹介されています。
そして、特に注目するのは、
2000年に発表された「新しい現実療法」以降、
「愛・所属の欲求」を【すべての欲求の中で、最も重要な欲求】とされたことです。
それまでのリアリティセラピーでは、
基本的欲求は「五つをバランスよく満たすことが重要」と教えられていましたが、
「新しい現実療法」の中で
「彼らが不幸なのは、現在、満足できる人間関係を持っていないからである」
と書かれていることがこれに反映していると思います。
※「新しい現実療法」についてはこちら↓
http://
また「力の欲求」(自己価値)については、
『現実療法』の次の著書である『同一性社会』の中で詳しく取り上げられています。
その後、グラッサー先生が「外的コントロール」という考え方を定義された際、
「外的コントロールは、力の落とし子、自由の敵」と表現されていましたが、
新しい冊子「メンタルヘルス」では、
「他の人とうまくいかなくなったときに、
外的コントロール心理学を使うことを身につけた。
それは、力の欲求があったからだ」と大胆に語っておられます。
昨年の来日講演では、力の欲求を【人間だけが持っている欲求】として、
他の四つの欲求とは分けて紹介されていたことも記憶に新しいところです。
「力のための力を使うのは人間だけだ」ということです。
(力の欲求は必ずしも悪いものではないということも書かれています。
力の欲求は遺伝子に組み込まれていますが、
外的コントロールは組み込まれていないわけで、
二つはイコールではありません)
これまでの選択理論の発達的な変遷を見ても
グラッサー先生は、「愛」と「自己価値」を重要に考えられていると感じます。
そんな私たちの欲求の核となる部分
「愛されたい」「認められたい」ことを扱うセミナーを
マサさんが担当されています。ご興味のある方はぜひどうぞ♪
http://
ご自身のセミナーで扱っていらっしゃる内容を熱く語ってくださったので、
それを受けて、選択理論の基本的欲求の歴史(?)を
ちょっと書き留めておきたいと思います。
グラッサー先生の最初の著書『現実療法』では、基本的欲求について、
「愛し愛される欲求」と
「自分は自分自身と他人にとって価値あるものだと感じる欲求」として、
今で言う「愛・所属の欲求」と「力の欲求」の
二つの欲求だけを挙げていました。
そして「これら二つの欲求の充足で患者を手助けするのが、現実療法の基本である」
といわれていました。
やがて、これに「自由の欲求」と「楽しみの欲求」、
そして身体的な要素を司っている「生存の欲求」が加わって
いまでは、五つの基本的欲求として紹介されています。
そして、特に注目するのは、
2000年に発表された「新しい現実療法」以降、
「愛・所属の欲求」を【すべての欲求の中で、最も重要な欲求】とされたことです。
それまでのリアリティセラピーでは、
基本的欲求は「五つをバランスよく満たすことが重要」と教えられていましたが、
「新しい現実療法」の中で
「彼らが不幸なのは、現在、満足できる人間関係を持っていないからである」
と書かれていることがこれに反映していると思います。
※「新しい現実療法」についてはこちら↓
http://
また「力の欲求」(自己価値)については、
『現実療法』の次の著書である『同一性社会』の中で詳しく取り上げられています。
その後、グラッサー先生が「外的コントロール」という考え方を定義された際、
「外的コントロールは、力の落とし子、自由の敵」と表現されていましたが、
新しい冊子「メンタルヘルス」では、
「他の人とうまくいかなくなったときに、
外的コントロール心理学を使うことを身につけた。
それは、力の欲求があったからだ」と大胆に語っておられます。
昨年の来日講演では、力の欲求を【人間だけが持っている欲求】として、
他の四つの欲求とは分けて紹介されていたことも記憶に新しいところです。
「力のための力を使うのは人間だけだ」ということです。
(力の欲求は必ずしも悪いものではないということも書かれています。
力の欲求は遺伝子に組み込まれていますが、
外的コントロールは組み込まれていないわけで、
二つはイコールではありません)
これまでの選択理論の発達的な変遷を見ても
グラッサー先生は、「愛」と「自己価値」を重要に考えられていると感じます。
そんな私たちの欲求の核となる部分
「愛されたい」「認められたい」ことを扱うセミナーを
マサさんが担当されています。ご興味のある方はぜひどうぞ♪
http://
|
|
|
|
コメント(8)
せっかくなので、もう少し・・・
この歴史の中で、今回グラッサー博士が力の欲求を特別視されたことで
「力のための力を使うのは人間だけだ」ということにより、
5つの欲求に必ず力が絡むと感じています。
生存の欲求にも力の欲求が絡み、愛所属、力、自由、楽しみにも力が絡んでいると伝えています。
そして、この力の欲求を外的コントロールとして使用するのではなく、自分らしく、他の人もその人らしくするために、創造性が必要です。
相手の力を出させないようにするために外的コントロールを使ったいるように感じています。
その恐れは、人が幸せになることであり、自分が幸せになることに恐れを抱いているように感じます。
コーチカーターを観ながら、輝きを解き放ちたいものです。
この歴史の中で、今回グラッサー博士が力の欲求を特別視されたことで
「力のための力を使うのは人間だけだ」ということにより、
5つの欲求に必ず力が絡むと感じています。
生存の欲求にも力の欲求が絡み、愛所属、力、自由、楽しみにも力が絡んでいると伝えています。
そして、この力の欲求を外的コントロールとして使用するのではなく、自分らしく、他の人もその人らしくするために、創造性が必要です。
相手の力を出させないようにするために外的コントロールを使ったいるように感じています。
その恐れは、人が幸せになることであり、自分が幸せになることに恐れを抱いているように感じます。
コーチカーターを観ながら、輝きを解き放ちたいものです。
久しぶりのトピに早速コメントいただけて嬉しく思います。
まつおっちさん
> しかし、どんなに他の欲求がみたされたとしても、
> 「愛」の欲求が満たされなければ、おそらく絶対に
> 幸福感を得ることはできないように思います。
・・・まったく同感です。
グラッサー博士は、現在では
「人々と大切な、親しい関係を維持することは、
すべての欲求を満たす必須条件です」と言っています。
マサさん
> 相手の力を出させないようにするために外的コントロールを使っている
・・・いまのマサさんの旬が「パワーロス」であることが
とても伝わってきます。
ティーローズさん
私は、「愛・所属の欲求が強い人」という表現をきくとき、
ティーローズさんのことをよく思い浮かべます。
ティーローズさんは、
子供たちと「信頼と尊敬」で結ばれている、
愛の溢れるカウンセラーだと思います♪
まつおっちさん
> しかし、どんなに他の欲求がみたされたとしても、
> 「愛」の欲求が満たされなければ、おそらく絶対に
> 幸福感を得ることはできないように思います。
・・・まったく同感です。
グラッサー博士は、現在では
「人々と大切な、親しい関係を維持することは、
すべての欲求を満たす必須条件です」と言っています。
マサさん
> 相手の力を出させないようにするために外的コントロールを使っている
・・・いまのマサさんの旬が「パワーロス」であることが
とても伝わってきます。
ティーローズさん
私は、「愛・所属の欲求が強い人」という表現をきくとき、
ティーローズさんのことをよく思い浮かべます。
ティーローズさんは、
子供たちと「信頼と尊敬」で結ばれている、
愛の溢れるカウンセラーだと思います♪
natsukoさん
>昨年の来日講演では、力の欲求を【人間だけが持っている欲求】として、
他の四つの欲求とは分けて紹介されていたことも記憶に新しいところです。
「力のための力を使うのは人間だけだ」ということです。
わたしも、グラッサー先生の話を聞いて、「力の欲求」を分けて紹介されていたのが印象的でした。そして、もしかしたら健全な形でこの「力の欲求」が満たされてないと不健全な形で満たそうとしてしまう人が多いのではないかと思っていました。
そして、マサさんの
>「力のための力を使うのは人間だけだ」ということにより、
5つの欲求に必ず力が絡むと感じています。
生存の欲求にも力の欲求が絡み、愛所属、力、自由、楽しみにも力が絡んでい ると伝えています。
を読み、「なるほど」っと思いました。
>昨年の来日講演では、力の欲求を【人間だけが持っている欲求】として、
他の四つの欲求とは分けて紹介されていたことも記憶に新しいところです。
「力のための力を使うのは人間だけだ」ということです。
わたしも、グラッサー先生の話を聞いて、「力の欲求」を分けて紹介されていたのが印象的でした。そして、もしかしたら健全な形でこの「力の欲求」が満たされてないと不健全な形で満たそうとしてしまう人が多いのではないかと思っていました。
そして、マサさんの
>「力のための力を使うのは人間だけだ」ということにより、
5つの欲求に必ず力が絡むと感じています。
生存の欲求にも力の欲求が絡み、愛所属、力、自由、楽しみにも力が絡んでい ると伝えています。
を読み、「なるほど」っと思いました。
他の人の「力」の欲求に注意を払うこと(欲求充足できているか、自分のかかわりがそれを削いでいないか)は人間関係を円満にする上では欠かせないことなんだなと感じました。
特に「尊敬する」、「信頼する」という行為はこの相手の力の欲求を自分が大切にしているというアピールかと思います。
そのためにも他者への関心を持つことが重要なのでしょうね。
今の人に欠けているものは「他者への関心」かもしれません。
門脇厚司先生の「親と子の社会力」という著書には、自分への「他者の取り込み」の多さ=心の豊かさと表現されていました。
「社会力の原基は他者への強い関心であり、愛着であり、信頼感である。(これらは)多様な他者との相互行為の繰り返しによって育まれる。」
よいとされる行いは「他者とのいい関係を持続させることを意図して行った行為であるということである。」
やはり欲求充足した生活を営む(社会力をもって生きる)ということに人間関係の充足というのは必要不可欠だなぁと感じ入る著書でした。
…ずれました?
特に「尊敬する」、「信頼する」という行為はこの相手の力の欲求を自分が大切にしているというアピールかと思います。
そのためにも他者への関心を持つことが重要なのでしょうね。
今の人に欠けているものは「他者への関心」かもしれません。
門脇厚司先生の「親と子の社会力」という著書には、自分への「他者の取り込み」の多さ=心の豊かさと表現されていました。
「社会力の原基は他者への強い関心であり、愛着であり、信頼感である。(これらは)多様な他者との相互行為の繰り返しによって育まれる。」
よいとされる行いは「他者とのいい関係を持続させることを意図して行った行為であるということである。」
やはり欲求充足した生活を営む(社会力をもって生きる)ということに人間関係の充足というのは必要不可欠だなぁと感じ入る著書でした。
…ずれました?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
選択理論★マニアの会 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
選択理論★マニアの会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90053人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208284人