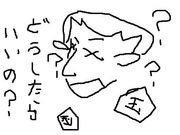いや〜、ひさびさにトピックたてます〜。
横歩取りはプロでも大流行の戦法です。左図がそのスタート局面ですが、プロの実戦ですと
ここで△3三角とするのが95%くらいの割合かと思われます。
しかし、ここから△8八角成▲同銀△2八歩▲同銀△4五角(中図)とする
「横歩取り4五角戦法」というのがあります。これはプロの対局ではほとんど出てきませんが、
アマチュアには根強い人気がある指し方です。
その魅力は何と言っても「相手が定跡を知らなければ一気に勝勢にできる可能性がある」
というところでしょう。要は「楽して勝てる!かも」というわけですな。プロではこんなのは
通用しないでしょうが、アマチュアなら十分通用するでしょう。
左図から中図までの手順で、△2八歩に▲同銀とせずに▲7七角(右図)とする変化もあり
ます。中図からの進行に自信が無ければ、先手としてはこちらを選択することもできる。
このトピックでは中図と左図の局面からの変化を掘り下げて、この戦法に詳しくなってもらい、
「後手をもってこの戦法を仕掛け、楽して勝てるようになる」
「先手を持ってやられたとき、間違えて敗勢にならないようになる」
の2つを目標にしようというわけ。研究手順に相手を嵌めて楽々と勝利する爽快感は何とも
言えませんからね〜。
私自身、24で初段前後の頃はコイツで随分と稼がせてもらいました。R1500〜R1800ぐらい
のときは全勝したと記憶してます。
横歩取りはプロでも大流行の戦法です。左図がそのスタート局面ですが、プロの実戦ですと
ここで△3三角とするのが95%くらいの割合かと思われます。
しかし、ここから△8八角成▲同銀△2八歩▲同銀△4五角(中図)とする
「横歩取り4五角戦法」というのがあります。これはプロの対局ではほとんど出てきませんが、
アマチュアには根強い人気がある指し方です。
その魅力は何と言っても「相手が定跡を知らなければ一気に勝勢にできる可能性がある」
というところでしょう。要は「楽して勝てる!かも」というわけですな。プロではこんなのは
通用しないでしょうが、アマチュアなら十分通用するでしょう。
左図から中図までの手順で、△2八歩に▲同銀とせずに▲7七角(右図)とする変化もあり
ます。中図からの進行に自信が無ければ、先手としてはこちらを選択することもできる。
このトピックでは中図と左図の局面からの変化を掘り下げて、この戦法に詳しくなってもらい、
「後手をもってこの戦法を仕掛け、楽して勝てるようになる」
「先手を持ってやられたとき、間違えて敗勢にならないようになる」
の2つを目標にしようというわけ。研究手順に相手を嵌めて楽々と勝利する爽快感は何とも
言えませんからね〜。
私自身、24で初段前後の頃はコイツで随分と稼がせてもらいました。R1500〜R1800ぐらい
のときは全勝したと記憶してます。
|
|
|
|
コメント(104)
先手に残された最後の受け、それが▲3九飛。見るからに苦し紛れの手だけどなかなかに
手強いようです。
当然の△6七飛成に▲5八銀△6八竜▲6九歩△7八竜▲5六角(左図)と懸命に竜を追う。
△7六竜のときに▲3三香成と待望の反撃ですが、その瞬間に△5六竜と竜をきってしまう。
これに▲同歩は、△6六角▲5七桂△3三角▲同馬△同金(中図)。
▲3二成香とするのも、△2六竜▲2七歩△3五竜(右図)。
どちらも後手指せる。
というわけで、△6九飛に対して▲5八銀、▲4九角、▲3九飛と3つの受けを検討しまし
たが、3つとも後手指せます。
であれば、この順で後手有望?と思わせますが、実は最後の難関
「受けない」
というのがあるのです。これを検証しなければいけません。
手強いようです。
当然の△6七飛成に▲5八銀△6八竜▲6九歩△7八竜▲5六角(左図)と懸命に竜を追う。
△7六竜のときに▲3三香成と待望の反撃ですが、その瞬間に△5六竜と竜をきってしまう。
これに▲同歩は、△6六角▲5七桂△3三角▲同馬△同金(中図)。
▲3二成香とするのも、△2六竜▲2七歩△3五竜(右図)。
どちらも後手指せる。
というわけで、△6九飛に対して▲5八銀、▲4九角、▲3九飛と3つの受けを検討しまし
たが、3つとも後手指せます。
であれば、この順で後手有望?と思わせますが、実は最後の難関
「受けない」
というのがあるのです。これを検証しなければいけません。
△6九飛に▲3三香成(左図)。実はこれが現在のところ最善と言われている。最善にして最強の順。
「両取り逃げる(受ける)べからず」古来から伝えられる格言はやっぱりタメになるもんですなあ。
以下△6七飛成▲3二成香と金を取り合う。ここで後手は△同銀といったん取っておくのが良い
とされている。これは香車を持つことで、△2五香の筋を狙っている。
これに対して先手は▲6二歩(中図)。この焦点の歩は、この戦型では再三出てくる手筋。
先手側の決め手になりうる一手なので、覚えておくべき手だと思う。
△同玉なら当然▲4二飛だ。△同銀は▲4二銀以下簡単に詰む。
なので取るとすれば△同金なのだが、すぐに取ると▲4二銀(右図)で、なんと即詰みなのだ。
というわけで、後手の正解はすぐには▲6二歩を取らずに、いったん△7八竜と王手して
合い駒を使わせる。ということになる。
「両取り逃げる(受ける)べからず」古来から伝えられる格言はやっぱりタメになるもんですなあ。
以下△6七飛成▲3二成香と金を取り合う。ここで後手は△同銀といったん取っておくのが良い
とされている。これは香車を持つことで、△2五香の筋を狙っている。
これに対して先手は▲6二歩(中図)。この焦点の歩は、この戦型では再三出てくる手筋。
先手側の決め手になりうる一手なので、覚えておくべき手だと思う。
△同玉なら当然▲4二飛だ。△同銀は▲4二銀以下簡単に詰む。
なので取るとすれば△同金なのだが、すぐに取ると▲4二銀(右図)で、なんと即詰みなのだ。
というわけで、後手の正解はすぐには▲6二歩を取らずに、いったん△7八竜と王手して
合い駒を使わせる。ということになる。
先手の駒台には▲4二銀から即詰みにするための駒が一通り揃っている状態だ。なので、
1枚でも合い駒で使わせれば詰み筋は消える。そこで△7八竜。これには色々合いごまが
あるけれど▲5八銀が最善とされる。こうして△6二金と後手が手を戻したときに、
▲6九金とさらに受ける狙いである。これには当然△8九竜だ。そこで▲2二馬(左図)。
これでほぼ互角、とされている。実はここまでの変化は全て、所司先生の「横歩取り
4五角戦法」に載っている。この本はところどころに穴があるとおもうが、やはり名著だ
と思う。しかし現在では入手困難だ。
そして入手が容易な飯島プロの本には書かれていないのだから、やはり裏技と言って良い
と思っている。
さて左図の形勢だけど、所司先生では互角とされているけど私見では先手がやや指しやすい
と思う。何よりも手番を握っているし、角と金の交換で若干の駒得でもある。
さてそこでオススメしたいのが、△3三香成のときに▲2九飛成(右図)と、金ではなく
桂を取る変化である。
1枚でも合い駒で使わせれば詰み筋は消える。そこで△7八竜。これには色々合いごまが
あるけれど▲5八銀が最善とされる。こうして△6二金と後手が手を戻したときに、
▲6九金とさらに受ける狙いである。これには当然△8九竜だ。そこで▲2二馬(左図)。
これでほぼ互角、とされている。実はここまでの変化は全て、所司先生の「横歩取り
4五角戦法」に載っている。この本はところどころに穴があるとおもうが、やはり名著だ
と思う。しかし現在では入手困難だ。
そして入手が容易な飯島プロの本には書かれていないのだから、やはり裏技と言って良い
と思っている。
さて左図の形勢だけど、所司先生では互角とされているけど私見では先手がやや指しやすい
と思う。何よりも手番を握っているし、角と金の交換で若干の駒得でもある。
さてそこでオススメしたいのが、△3三香成のときに▲2九飛成(右図)と、金ではなく
桂を取る変化である。
この△2九飛成の変化は、所司先生の本にも書かれていない。では、オイラのオリジナル
か?というとそうでもない。実はこの変化は、将棋倶楽部24でとある高段者が連採して
いた指し方なのである。
あれはもう何年前になるのか?R2700台の、とある高段者が4五角戦法を使いまくって
いたのだ。相手も当然2600〜2800クラスの猛者ばかりである。
その対局をオイラは追いかけていて、観戦していたのだが、オイラが見た限りでは、
▲3三香成に△2九飛成としたこの図は後手が2勝1敗だった。2600〜2800クラス
に2勝1敗である。これは有力な変化とみて間違いないだろう。
その3局の将棋では、△2九飛成以下▲3九銀打△3八歩▲1八角△3九歩成▲2九角
△同と(左図)と進んでいる。3局とも同じ進行である。これだけの高Rの対局で3局とも
同じ進行であれば、ほぼ常識的な手順だと言えると思う。
ここから▲3二成香△同銀▲6四歩と進んだ将棋は後手勝ち。▲3二成香△同銀▲1二飛
と進んだ将棋も後手勝ち。▲2一飛△4一金▲1二飛と進んだ将棋は先手勝ちとなった。
この変化は棋書にも載った事が無いから、結論がどうなのかはわからないけど有力な変化
なんだと思う。
次に△8八飛(右図)と打つ変化に行ってみたい。
か?というとそうでもない。実はこの変化は、将棋倶楽部24でとある高段者が連採して
いた指し方なのである。
あれはもう何年前になるのか?R2700台の、とある高段者が4五角戦法を使いまくって
いたのだ。相手も当然2600〜2800クラスの猛者ばかりである。
その対局をオイラは追いかけていて、観戦していたのだが、オイラが見た限りでは、
▲3三香成に△2九飛成としたこの図は後手が2勝1敗だった。2600〜2800クラス
に2勝1敗である。これは有力な変化とみて間違いないだろう。
その3局の将棋では、△2九飛成以下▲3九銀打△3八歩▲1八角△3九歩成▲2九角
△同と(左図)と進んでいる。3局とも同じ進行である。これだけの高Rの対局で3局とも
同じ進行であれば、ほぼ常識的な手順だと言えると思う。
ここから▲3二成香△同銀▲6四歩と進んだ将棋は後手勝ち。▲3二成香△同銀▲1二飛
と進んだ将棋も後手勝ち。▲2一飛△4一金▲1二飛と進んだ将棋は先手勝ちとなった。
この変化は棋書にも載った事が無いから、結論がどうなのかはわからないけど有力な変化
なんだと思う。
次に△8八飛(右図)と打つ変化に行ってみたい。
△6九飛の場合は、両取り逃げるべからずで▲3三香成が利いたけど、△8八飛の場合は
それはできません(笑)。
玉を逃げる手は無いので、何か合い駒をするしか無いところ。
一番普通に見えるのが▲6八歩。これには△8九飛成。先手は適当な受けが見当たらない
ので▲3三香成と攻め合うけど、△2九竜(左図)。
これは前に紹介した変化と似てるけど、それと比べても後手がだいぶ得をしている。
これは後手が良い。
というわけで▲6八歩はうまくない。
続けて考えられそうな手は▲5八銀だけど、これは△3八金(中図)がグッサリと突き刺さる。
▲5九玉△8九飛成▲6九歩に△4一桂(右図)と手堅く受けておいて後手良し。
普通に見える2通りの合い駒では、後手良しになるわけです。
ということで、最後に残された合い駒は・・・
それはできません(笑)。
玉を逃げる手は無いので、何か合い駒をするしか無いところ。
一番普通に見えるのが▲6八歩。これには△8九飛成。先手は適当な受けが見当たらない
ので▲3三香成と攻め合うけど、△2九竜(左図)。
これは前に紹介した変化と似てるけど、それと比べても後手がだいぶ得をしている。
これは後手が良い。
というわけで▲6八歩はうまくない。
続けて考えられそうな手は▲5八銀だけど、これは△3八金(中図)がグッサリと突き刺さる。
▲5九玉△8九飛成▲6九歩に△4一桂(右図)と手堅く受けておいて後手良し。
普通に見える2通りの合い駒では、後手良しになるわけです。
ということで、最後に残された合い駒は・・・
残された最後の合い駒は▲6八飛。飛車は敵陣に打ちたいところだけど、これ以外は悪く
なってしまうのだから仕方が無い。以下△8九飛成▲6九歩と徹底的に受けます。
ここまでされるとさすがに後手も急激に迫る手は無いので、△4一桂(左図)と受けに
回ります。
この局面、形勢はどうなのか?ですが、ほぼ互角とされています。
所司先生の本に書かれている進行は、まず1つ目が
▲5六金△9九竜▲3三香成△同桂▲5五桂△6二香▲3四銀△4二金打(中図)
というもの。
これは先手の攻めがやや息切れしている感があり、後手有望なんじゃないかと思ってます。
もう一つが▲6六角。これもなんか筋の良さそうな手です。
後手は△7八金(右図)と攻めますね。
なってしまうのだから仕方が無い。以下△8九飛成▲6九歩と徹底的に受けます。
ここまでされるとさすがに後手も急激に迫る手は無いので、△4一桂(左図)と受けに
回ります。
この局面、形勢はどうなのか?ですが、ほぼ互角とされています。
所司先生の本に書かれている進行は、まず1つ目が
▲5六金△9九竜▲3三香成△同桂▲5五桂△6二香▲3四銀△4二金打(中図)
というもの。
これは先手の攻めがやや息切れしている感があり、後手有望なんじゃないかと思ってます。
もう一つが▲6六角。これもなんか筋の良さそうな手です。
後手は△7八金(右図)と攻めますね。
△7八金に対し、「必死こいて受けに回る」が▲同飛△同竜▲7八金打△8七竜と進む。
そこで▲3三香成以下△同桂▲同角成△同金▲同馬と突撃する。
以下△4二銀▲3二馬に△6四香(左図)。
この分かれは後手十分。
△7八金に対し、「攻め合いに活路を見出す」は▲3三香成。
以下△6八金▲同金に△2六飛(中図)が炸裂!
これに対しては▲3八玉として△6六飛に▲4二成香で一応飛車を素抜くことはできる。
しかし△同玉▲6六馬に△6四香の追撃が厳しい。▲5六馬と竜に当てつつ逃げることは
できるが、△9九竜▲5八金△6九香成(右図)と進んでこれも後手十分。
このように△6六銀に▲5八金の変化は、強敵ではありますが、後手も十分にやれます。
では次に△6六銀に対する最後の敵、ボスキャラ▲3三香成に行ってみます。
そこで▲3三香成以下△同桂▲同角成△同金▲同馬と突撃する。
以下△4二銀▲3二馬に△6四香(左図)。
この分かれは後手十分。
△7八金に対し、「攻め合いに活路を見出す」は▲3三香成。
以下△6八金▲同金に△2六飛(中図)が炸裂!
これに対しては▲3八玉として△6六飛に▲4二成香で一応飛車を素抜くことはできる。
しかし△同玉▲6六馬に△6四香の追撃が厳しい。▲5六馬と竜に当てつつ逃げることは
できるが、△9九竜▲5八金△6九香成(右図)と進んでこれも後手十分。
このように△6六銀に▲5八金の変化は、強敵ではありますが、後手も十分にやれます。
では次に△6六銀に対する最後の敵、ボスキャラ▲3三香成に行ってみます。
△6六銀を無視して▲3三香成(左図)と攻め合う。とてもじゃないが研究の裏づけが無いと指せない
手です。しかし現在ではこれが先手の最善とされていて先手が良いとされています。
飯島プロの本には、先の▲5八金でも先手有望と書いていますが、本に書かれているのは
△6九飛と先着する順だけで、△6七銀成から清算して△8八飛と打つ変化など全く書かれて
いないです。まあ単純に「ページ数が足りなかった」んでしょう。
しかし▲5八金は後手有望です。これは自信がある。そこで最後の敵となるのが▲3三香成。
こいつをなんとかすれば4五角戦法は十分使える戦法になる。
▲3三香成の局面から後手の指し手は3通りです。
最も普通の△6七銀成
ちょっとひねって△6七銀不成
一番過激な△6七角成
というわけで、まずは最も普通の△6七銀成(右図)から行ってみます。
手です。しかし現在ではこれが先手の最善とされていて先手が良いとされています。
飯島プロの本には、先の▲5八金でも先手有望と書いていますが、本に書かれているのは
△6九飛と先着する順だけで、△6七銀成から清算して△8八飛と打つ変化など全く書かれて
いないです。まあ単純に「ページ数が足りなかった」んでしょう。
しかし▲5八金は後手有望です。これは自信がある。そこで最後の敵となるのが▲3三香成。
こいつをなんとかすれば4五角戦法は十分使える戦法になる。
▲3三香成の局面から後手の指し手は3通りです。
最も普通の△6七銀成
ちょっとひねって△6七銀不成
一番過激な△6七角成
というわけで、まずは最も普通の△6七銀成(右図)から行ってみます。
△6七銀成は最も普通な手ですが、金を取る手が敵玉から離れていってしまう点がやはり
ネックで攻め合いにおける迫力がちょっと不足します。
先手はそこにつけこんで一直線の攻め合いを挑んできます。
▲3二成香△7八成銀▲3一成香△6七角成▲3三馬△6二玉▲2二飛(左図)と、
「お前はお前、俺は俺」とばかりに一直線に攻め合う。この王手にどう受けるか?
△5二金打(安全第一路線)
△5二金(危険でも攻め合路線)
の2通りとなります。
△5二金打には、▲4八玉と早逃げして詰めろを消しておきます。そして△6八成銀に
▲7五桂(中図)これが▲5一銀以下の詰めろになっています。
これを受けるのに△7二銀では、▲5一金の俗手が厳しく受けが無くなります。このとき
に△7四歩と脱出路を開けても▲5二飛成で詰んでしまいますので確認してみてください。
ここは△7四歩と逃げ道を造るしかないですが、▲8三桂成がまた詰めろ。さらに△6四歩と
逃げ道を開ければ▲4一銀がまた詰めろ。△6三玉と早逃げして凌げば▲6五歩がまた詰めろ。
そこで△2五飛が詰めろ逃れの詰めろになりますが、▲5二銀不成△同金▲6四歩△同玉に
▲2四飛成(右図)が、ウイニングショット。
△同飛は▲5五金以下詰みです。△4四銀と受ければ▲2五竜で後手戦意喪失。
安全第一路線の△5二金打は、後手必敗とわかりました。
ネックで攻め合いにおける迫力がちょっと不足します。
先手はそこにつけこんで一直線の攻め合いを挑んできます。
▲3二成香△7八成銀▲3一成香△6七角成▲3三馬△6二玉▲2二飛(左図)と、
「お前はお前、俺は俺」とばかりに一直線に攻め合う。この王手にどう受けるか?
△5二金打(安全第一路線)
△5二金(危険でも攻め合路線)
の2通りとなります。
△5二金打には、▲4八玉と早逃げして詰めろを消しておきます。そして△6八成銀に
▲7五桂(中図)これが▲5一銀以下の詰めろになっています。
これを受けるのに△7二銀では、▲5一金の俗手が厳しく受けが無くなります。このとき
に△7四歩と脱出路を開けても▲5二飛成で詰んでしまいますので確認してみてください。
ここは△7四歩と逃げ道を造るしかないですが、▲8三桂成がまた詰めろ。さらに△6四歩と
逃げ道を開ければ▲4一銀がまた詰めろ。△6三玉と早逃げして凌げば▲6五歩がまた詰めろ。
そこで△2五飛が詰めろ逃れの詰めろになりますが、▲5二銀不成△同金▲6四歩△同玉に
▲2四飛成(右図)が、ウイニングショット。
△同飛は▲5五金以下詰みです。△4四銀と受ければ▲2五竜で後手戦意喪失。
安全第一路線の△5二金打は、後手必敗とわかりました。
では節約の△5二金です。先手玉は詰めろなので▲4八玉の早逃げ。後手△6八成銀と寄った
手が、今度は詰めろになっています。
そこで先手は▲3九金打とガッチリと受けるのが定跡。以下△7八飛も▲3八玉で逃れています。
「玉の早逃げ八手の得あり」とは良くぞ言ったものです。
以下△5八成銀▲同金△同馬▲4八桂としっかりと受けておけば、これ以上の追撃は無い。
△6一金と受けても▲4一銀(左図)で先手の攻めは切れない。ということでこれは先手勝勢。
ということで一番普通な△6七銀成は後手悪い。
次にちょっとひねった△6七銀不成です。これは△6七銀成と同じ手順で進んだときに
△6七角成の代わりに△6七銀成(中図)とできるようにした工夫です。こっちのほうが、
先手玉が狭い分迫力があります。
ここから▲3三馬△6二玉▲2二飛△5二金(右図)と同じように進みます。
手が、今度は詰めろになっています。
そこで先手は▲3九金打とガッチリと受けるのが定跡。以下△7八飛も▲3八玉で逃れています。
「玉の早逃げ八手の得あり」とは良くぞ言ったものです。
以下△5八成銀▲同金△同馬▲4八桂としっかりと受けておけば、これ以上の追撃は無い。
△6一金と受けても▲4一銀(左図)で先手の攻めは切れない。ということでこれは先手勝勢。
ということで一番普通な△6七銀成は後手悪い。
次にちょっとひねった△6七銀不成です。これは△6七銀成と同じ手順で進んだときに
△6七角成の代わりに△6七銀成(中図)とできるようにした工夫です。こっちのほうが、
先手玉が狭い分迫力があります。
ここから▲3三馬△6二玉▲2二飛△5二金(右図)と同じように進みます。
△5ニ金と受けたところでは、先手玉は詰めろになっています。これが△6七銀不成とした
効果です。一見後手有望のように見えますがしかし、ここで▲4八玉の早逃げがあります。
この早逃げには△7八飛で、以下▲5八桂△同成銀▲同金△3八金▲5九玉△6七桂
▲同金△同角成(左図)と進んで、先手玉に必死がかかります。ここで後手玉に詰みが
あるか?が勝負になります。
ではいきましょう。
▲7四桂△同歩▲5二飛成(中図)。
△同玉は▲4一銀△6二玉▲5一馬△7ニ玉▲8三銀△同玉▲8四金△9ニ玉▲8三金打まで。
△7三玉▲5五馬△6四桂▲8四銀△同玉▲8五歩△同玉▲9六金△9四玉▲8五金打
△8三玉▲8四銀まで。
というわけで、△6七銀不成の変化も先手の勝ち。
それにしても、この変化の定跡は、詰めろ逃れの詰めろがあったり、必死がかかった瞬間に
相手に長手数の詰みがあったりと、すごい定跡です。
というわけで後手の選択肢は、一番過激な△6七角成(右図)しかなくなりました。
効果です。一見後手有望のように見えますがしかし、ここで▲4八玉の早逃げがあります。
この早逃げには△7八飛で、以下▲5八桂△同成銀▲同金△3八金▲5九玉△6七桂
▲同金△同角成(左図)と進んで、先手玉に必死がかかります。ここで後手玉に詰みが
あるか?が勝負になります。
ではいきましょう。
▲7四桂△同歩▲5二飛成(中図)。
△同玉は▲4一銀△6二玉▲5一馬△7ニ玉▲8三銀△同玉▲8四金△9ニ玉▲8三金打まで。
△7三玉▲5五馬△6四桂▲8四銀△同玉▲8五歩△同玉▲9六金△9四玉▲8五金打
△8三玉▲8四銀まで。
というわけで、△6七銀不成の変化も先手の勝ち。
それにしても、この変化の定跡は、詰めろ逃れの詰めろがあったり、必死がかかった瞬間に
相手に長手数の詰みがあったりと、すごい定跡です。
というわけで後手の選択肢は、一番過激な△6七角成(右図)しかなくなりました。
▲6六馬に対しては、後手として考えられるのは△3ニ銀と成香を払っておく。と、
△6九飛から△6六飛成で馬を外す、の2つでしょう。前者は安全第一、後者は危険を
いとわず勝負、と言った感じでしょうか。
安全第一の△3二銀には▲6九金と受けに回るのが定跡。以下△8九馬▲7八銀(左図)
と馬を詰ませます。
これに対しては、△同馬▲同金としてから△2六飛の馬銀両取りが良さそうに思えますが、
▲3六飛(中図)の返し技があってうまくいきません。
▲7八銀には△6四香▲6五歩△同香▲同馬△9九馬(右図)と、香車を犠牲に馬を
救出するのが正解とされていて、右図の局面はほぼ互角だとされています。
△6九飛から△6六飛成で馬を外す、の2つでしょう。前者は安全第一、後者は危険を
いとわず勝負、と言った感じでしょうか。
安全第一の△3二銀には▲6九金と受けに回るのが定跡。以下△8九馬▲7八銀(左図)
と馬を詰ませます。
これに対しては、△同馬▲同金としてから△2六飛の馬銀両取りが良さそうに思えますが、
▲3六飛(中図)の返し技があってうまくいきません。
▲7八銀には△6四香▲6五歩△同香▲同馬△9九馬(右図)と、香車を犠牲に馬を
救出するのが正解とされていて、右図の局面はほぼ互角だとされています。
▲6六馬に△6九飛▲4八玉△6六飛成(左図)。
自玉の危険を顧みず馬をいただいてしまう。まあ、なんというか図々しい指し方ではある。
ここまで図々しくされると先手も怒るしかない。後手玉に迫る手はなにか?
考えられる手は3つだ。
▲4一飛
▲3一成香
▲5四桂
である。
まず▲5四桂から行ってみよう。これは△同歩に▲5三銀(中図)と後手玉に縛りをかけ
て一気に寄せてしまおうという手だ。この筋もこの戦型で良く出てくる筋。覚えておけば
勝率アップ間違いなし、ですぞ。
実は部分的にはこれで受けが無いのである。自玉の危険を顧みなかったツケである。
これで後手負けなのか?
ところがどっこい後手にも△3六桂(右図)の返し技があった。
▲同歩と取ればもちろん△2六角で銀を外して後手良しだ。
自玉の危険を顧みず馬をいただいてしまう。まあ、なんというか図々しい指し方ではある。
ここまで図々しくされると先手も怒るしかない。後手玉に迫る手はなにか?
考えられる手は3つだ。
▲4一飛
▲3一成香
▲5四桂
である。
まず▲5四桂から行ってみよう。これは△同歩に▲5三銀(中図)と後手玉に縛りをかけ
て一気に寄せてしまおうという手だ。この筋もこの戦型で良く出てくる筋。覚えておけば
勝率アップ間違いなし、ですぞ。
実は部分的にはこれで受けが無いのである。自玉の危険を顧みなかったツケである。
これで後手負けなのか?
ところがどっこい後手にも△3六桂(右図)の返し技があった。
▲同歩と取ればもちろん△2六角で銀を外して後手良しだ。
△3六桂は取れない。取れないから玉を逃げるしかない。逃げるしかないが、▲3九玉だ
と△4八金からバラして何と即詰みだ。ホントこの戦法の定跡は「即詰み」が多い。
実にスリリング。
なので▲3八玉。これに△4八金は▲2七玉で詰まないので後手が負ける。ここは
△6八竜(左図)と王手して合い駒請求するのが良いのである。
合い駒と言っても、金と飛しか無い。さてどちらが正解か?
結論から言うと、飛車合いは即詰みである。▲5八飛△同竜▲同金△4八金▲同金
△同桂成▲同玉△5八金(中図)以下の詰み。
というわけで金合いしかなく▲5八金打。竜が逃げれば▲4一飛まで。△同竜と
取っても先手玉に詰みは無い。さあどうするか?
△2八桂成▲同玉△5八竜▲同金△3ニ銀。
これで後手玉に詰みは無い。先手に金を使わせたことにより、必死がほどけたのである。
しかも後手に香車が入ったことにより、先手玉が詰めろになっている。
いわゆる必死逃れの詰めろである。
なので先手も▲1一飛と合い駒請求するしかない。これには△4一香(右図)で
間に合っている。スリリングな応酬となったが、右図では後手が有利だ。
というわけで▲5四桂は先手悪い。
と△4八金からバラして何と即詰みだ。ホントこの戦法の定跡は「即詰み」が多い。
実にスリリング。
なので▲3八玉。これに△4八金は▲2七玉で詰まないので後手が負ける。ここは
△6八竜(左図)と王手して合い駒請求するのが良いのである。
合い駒と言っても、金と飛しか無い。さてどちらが正解か?
結論から言うと、飛車合いは即詰みである。▲5八飛△同竜▲同金△4八金▲同金
△同桂成▲同玉△5八金(中図)以下の詰み。
というわけで金合いしかなく▲5八金打。竜が逃げれば▲4一飛まで。△同竜と
取っても先手玉に詰みは無い。さあどうするか?
△2八桂成▲同玉△5八竜▲同金△3ニ銀。
これで後手玉に詰みは無い。先手に金を使わせたことにより、必死がほどけたのである。
しかも後手に香車が入ったことにより、先手玉が詰めろになっている。
いわゆる必死逃れの詰めろである。
なので先手も▲1一飛と合い駒請求するしかない。これには△4一香(右図)で
間に合っている。スリリングな応酬となったが、右図では後手が有利だ。
というわけで▲5四桂は先手悪い。
▲5四桂は先手うまく行きませんでした。残るのは▲3一成香と▲4一飛です。
所司先生の本では双方共に難解な形勢、と結論付けられていますが、個人的には両方とも
後手が苦しいと思っています。なので後手は△6九飛から馬を取るのは危険で、
△3ニ銀と成香を払っておくべきだとおもっています。
その理由を述べましょう。
まず▲3一成香。所司先生の本では△8九馬▲3二飛(詰めろ)に、△6八竜と合い駒を
使わせる。これに▲5八金打とすると△8八竜で後手玉が詰まないため、先手不利と書かれて
います。しかし、▲3二飛でなく▲2二飛(左図)とすれば△6八竜に▲5八金打としても、
後手玉は詰めろです。なので後手は竜を逃げることができないので、先手有利だと思います。
続いては▲4一飛に行って見ます。△6ニ玉▲3一飛成△8九馬▲8三銀(中図)と進みます。
この▲8三銀は、▲4二竜以下の詰めろです。
後手は△7四歩と逃げ道を開けるのが最善の受けです。これには▲同銀成と取っておきます。
△4五馬が詰めろ逃れの詰めろになりますが、▲5八金打と投入して受けておき、△7三歩の
とき、▲6四桂(右図)が好手。これで先手良しだと思います。
なので、後手は6六の馬を取る欲張りな変化は危険であると思います。
所司先生の本では双方共に難解な形勢、と結論付けられていますが、個人的には両方とも
後手が苦しいと思っています。なので後手は△6九飛から馬を取るのは危険で、
△3ニ銀と成香を払っておくべきだとおもっています。
その理由を述べましょう。
まず▲3一成香。所司先生の本では△8九馬▲3二飛(詰めろ)に、△6八竜と合い駒を
使わせる。これに▲5八金打とすると△8八竜で後手玉が詰まないため、先手不利と書かれて
います。しかし、▲3二飛でなく▲2二飛(左図)とすれば△6八竜に▲5八金打としても、
後手玉は詰めろです。なので後手は竜を逃げることができないので、先手有利だと思います。
続いては▲4一飛に行って見ます。△6ニ玉▲3一飛成△8九馬▲8三銀(中図)と進みます。
この▲8三銀は、▲4二竜以下の詰めろです。
後手は△7四歩と逃げ道を開けるのが最善の受けです。これには▲同銀成と取っておきます。
△4五馬が詰めろ逃れの詰めろになりますが、▲5八金打と投入して受けておき、△7三歩の
とき、▲6四桂(右図)が好手。これで先手良しだと思います。
なので、後手は6六の馬を取る欲張りな変化は危険であると思います。
というわけで、△6七角成に▲3二成香と攻め合うのは、△7八馬▲6六馬△3二銀と
進めて形勢互角の分かれになるのが結論、とします。
市販の定跡本では△6七角成には▲同金と取ることになっています。前にも書いた通り、
4五角戦法は先手良しになるはず、というのがプロ間での暗黙の了解だからで、代表格と
して「羽生の頭脳」で△6七角成には▲同金として先手良し、と書かれているためです。
なので定跡を知っている人ほど、ここでは必ず▲同金としてくると思います。後手も当然
△同銀成(左図)としますね。
この図ではさすがに先手も受けに回るしかありません。▲3二成香と攻め合うのは、
△3八飛(中図)のスーパージャンピングダイレクトボレーシュートが決まります。
なので、どう受けるか?が問題。一見「玉の早逃げ八手の得」とばかりに▲4八玉が良さ
そうに見えます。
しかし、この場合は△8八飛▲5八桂△8九飛成▲3ニ成香に△5六桂▲同歩△5七金
▲3八玉△4九竜▲2七玉に△3ニ銀(右図)とされて先手不利。
格言が通用しないこの局面、さてどう受けますか。
進めて形勢互角の分かれになるのが結論、とします。
市販の定跡本では△6七角成には▲同金と取ることになっています。前にも書いた通り、
4五角戦法は先手良しになるはず、というのがプロ間での暗黙の了解だからで、代表格と
して「羽生の頭脳」で△6七角成には▲同金として先手良し、と書かれているためです。
なので定跡を知っている人ほど、ここでは必ず▲同金としてくると思います。後手も当然
△同銀成(左図)としますね。
この図ではさすがに先手も受けに回るしかありません。▲3二成香と攻め合うのは、
△3八飛(中図)のスーパージャンピングダイレクトボレーシュートが決まります。
なので、どう受けるか?が問題。一見「玉の早逃げ八手の得」とばかりに▲4八玉が良さ
そうに見えます。
しかし、この場合は△8八飛▲5八桂△8九飛成▲3ニ成香に△5六桂▲同歩△5七金
▲3八玉△4九竜▲2七玉に△3ニ銀(右図)とされて先手不利。
格言が通用しないこの局面、さてどう受けますか。
定跡におけるNo.86左図での先手の受けは、▲6八歩と▲6九歩の2つがあります。▲6八歩
のほうが優るとされていますが、先に▲6九歩から見ていきましょう。
▲6九歩の受けには、△7九飛か△7八飛かのどちらかの飛車打ちになります。それ以外、
例えば△3八飛は▲4八飛で受かってます。
△7八飛だと▲6八桂△5七成銀と進んで先手玉は詰めろになってしまいますが、そこで
▲4五角(左図)が攻防の名角。こんな良い手があっては後手はツライ。
△7九飛成と飛車を逃げるようでは、▲3ニ成香で攻め合い負け確実。
△6七金とへばりついても、▲同角△同成銀▲3ニ成香△同銀▲3一飛で後手不利。
というわけで▲6九歩に△7八飛はボツ。
ここは△7九飛の一手。次に△6九飛成殻先手玉は寄り筋。それを受けなければいけません。
ここでもまた角というわけで▲9六角(中図)が良い手。
しかし、今度は後手も△8九飛成▲3ニ成香△同銀で対抗できます。以下▲4八玉の早逃げに
△8五歩(右図)として、先手の角を召し取る楽しみがあって後手も指せます。
▲6九歩の受けはだいたいこんな感じになります。「羽生の頭脳」をはじめとする、プロ棋士
による定跡書では▲6八歩の受けが最善としています。次以降は▲6八歩の変化を調べて
みます。
のほうが優るとされていますが、先に▲6九歩から見ていきましょう。
▲6九歩の受けには、△7九飛か△7八飛かのどちらかの飛車打ちになります。それ以外、
例えば△3八飛は▲4八飛で受かってます。
△7八飛だと▲6八桂△5七成銀と進んで先手玉は詰めろになってしまいますが、そこで
▲4五角(左図)が攻防の名角。こんな良い手があっては後手はツライ。
△7九飛成と飛車を逃げるようでは、▲3ニ成香で攻め合い負け確実。
△6七金とへばりついても、▲同角△同成銀▲3ニ成香△同銀▲3一飛で後手不利。
というわけで▲6九歩に△7八飛はボツ。
ここは△7九飛の一手。次に△6九飛成殻先手玉は寄り筋。それを受けなければいけません。
ここでもまた角というわけで▲9六角(中図)が良い手。
しかし、今度は後手も△8九飛成▲3ニ成香△同銀で対抗できます。以下▲4八玉の早逃げに
△8五歩(右図)として、先手の角を召し取る楽しみがあって後手も指せます。
▲6九歩の受けはだいたいこんな感じになります。「羽生の頭脳」をはじめとする、プロ棋士
による定跡書では▲6八歩の受けが最善としています。次以降は▲6八歩の変化を調べて
みます。
このように詰みまで調べられた定跡により、▲6八歩に△7八飛は否定されたのですが、
昔ネットで次のような記述を見かけたことがあります。No.88の中図、▲3八銀に対して
△2七銀ではなく△3九金(左図)と打つ。
なにが違うか?というと、定跡手順と同じような攻め合い担った場合、つまり▲3ニ成香
△3八金▲同金△同竜(中図)になったときの先手の持ち駒が違う。つまり飛角金銀桂で
なく飛角金金桂となっている。なので、▲4一飛△6ニ玉▲6一飛成△同玉▲5ニ金では
詰まない。後手玉が詰まないのならば後手の攻め合い勝ちではないか?というものでした。
なんと!そんなことが!と思って私も調べたことがありました。ですが結局のところ、
やはり後手の負けです。中図から▲4一飛△6ニ玉▲6一飛成△同玉に▲8三角(右図)
とすればやはり詰みます。
この右図からの詰みはちょっと骨があるかもしれません。なのでここは「詰むや詰まざるや」
番外編(あっちのトピックもそのうち復活させなきゃ・・・)ということで、考えてみてく
ださい。
昔ネットで次のような記述を見かけたことがあります。No.88の中図、▲3八銀に対して
△2七銀ではなく△3九金(左図)と打つ。
なにが違うか?というと、定跡手順と同じような攻め合い担った場合、つまり▲3ニ成香
△3八金▲同金△同竜(中図)になったときの先手の持ち駒が違う。つまり飛角金銀桂で
なく飛角金金桂となっている。なので、▲4一飛△6ニ玉▲6一飛成△同玉▲5ニ金では
詰まない。後手玉が詰まないのならば後手の攻め合い勝ちではないか?というものでした。
なんと!そんなことが!と思って私も調べたことがありました。ですが結局のところ、
やはり後手の負けです。中図から▲4一飛△6ニ玉▲6一飛成△同玉に▲8三角(右図)
とすればやはり詰みます。
この右図からの詰みはちょっと骨があるかもしれません。なのでここは「詰むや詰まざるや」
番外編(あっちのトピックもそのうち復活させなきゃ・・・)ということで、考えてみてく
ださい。
ということで▲6八歩に△7八飛は敗退。なので△7九飛(左図)です。これに対して先手
は▲4八玉と▲6九桂があります。定跡では▲4八玉が正解とされています。しかし、その
手は定跡を知っていないと指せないのじゃないか?と思います。怖すぎる。▲6九桂のほう
が安全そうに思える。
しかし▲6九系だと後手の思うつぼにはまります。以下△7八飛成▲6七歩△2八竜▲3八銀
と、△7八飛のときの変化と同じように進みます。このとき△3九金(中図)と打てば、先手
は桂馬を使ってしまっているため、以下▲3二成香△3八金▲同金△同竜(右図)となった
とき、今度こそ後手玉が詰みません。
後手玉に詰みが無ければ先手不利です。▲5八金とか▲4八金とか受けるより無さそうです
が、ここで受けに回って受けきれるような状況じゃないでしょう。
というわけで、△7九飛に対しては怖かろうとも▲4八玉が正解ということになります。
は▲4八玉と▲6九桂があります。定跡では▲4八玉が正解とされています。しかし、その
手は定跡を知っていないと指せないのじゃないか?と思います。怖すぎる。▲6九桂のほう
が安全そうに思える。
しかし▲6九系だと後手の思うつぼにはまります。以下△7八飛成▲6七歩△2八竜▲3八銀
と、△7八飛のときの変化と同じように進みます。このとき△3九金(中図)と打てば、先手
は桂馬を使ってしまっているため、以下▲3二成香△3八金▲同金△同竜(右図)となった
とき、今度こそ後手玉が詰みません。
後手玉に詰みが無ければ先手不利です。▲5八金とか▲4八金とか受けるより無さそうです
が、ここで受けに回って受けきれるような状況じゃないでしょう。
というわけで、△7九飛に対しては怖かろうとも▲4八玉が正解ということになります。
先手の正解手▲4八玉には△5七成銀と△7八飛成の2通りがあります。定跡では前者が
正解とされていますが、△7八飛成はなぜダメなのか?この手も結構強力に思えます。
△7八飛成にまず考えられるのは「玉の早逃げ八手の得」、▲3八玉ですね。△6八竜
▲4八桂となってしのげそうに思えますが、ベタっと△5八金(左図)とされると、
▲3九金は△4八金▲同金△2六桂で先手不利。
ならばとばかりに▲3ニ成香と攻め合うのも△4九金とされてこれも先手不利。
▲4八玉がダメだとするとちょっと困ってしまいますが、定跡とは有難いものでして、
▲3六歩(中図)が好手で先手しのげているのです。
以下△6八竜▲3七玉△2六金▲同玉△2八竜▲2七歩と進む。
先手玉は風前の灯火のように見え、後手にうまい手があれば負けそうです。そして
△3四歩(右図)がそのうまい手。
先手は対応を間違えると負けになってしまいます。
正解とされていますが、△7八飛成はなぜダメなのか?この手も結構強力に思えます。
△7八飛成にまず考えられるのは「玉の早逃げ八手の得」、▲3八玉ですね。△6八竜
▲4八桂となってしのげそうに思えますが、ベタっと△5八金(左図)とされると、
▲3九金は△4八金▲同金△2六桂で先手不利。
ならばとばかりに▲3ニ成香と攻め合うのも△4九金とされてこれも先手不利。
▲4八玉がダメだとするとちょっと困ってしまいますが、定跡とは有難いものでして、
▲3六歩(中図)が好手で先手しのげているのです。
以下△6八竜▲3七玉△2六金▲同玉△2八竜▲2七歩と進む。
先手玉は風前の灯火のように見え、後手にうまい手があれば負けそうです。そして
△3四歩(右図)がそのうまい手。
先手は対応を間違えると負けになってしまいます。
△3四歩を▲同成香は、△2五銀▲3五玉△2七竜(左図)で先手受けなし。
ここは▲3七桂がこの一手の受けで後手の攻めを凌いでいます。
実はこの進行は、プロの実戦です。1989年▲森内−△屋敷戦です。
この時期は、羽生さん森内さん屋敷さんあたりが4五角戦法を使っていて、
第2次ブームという感じでした。ではその棋譜を。
開始日時:1989/10/17
棋戦:順位戦
戦型:横歩取り
持ち時間:6時間
場所:東京「将棋会館」
備考:△4五角
先手:森内俊之
後手:屋敷伸之
*棋戦詳細:第48期順位戦C級2組05回戦
▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩 △8四歩 ▲2五歩 △8五歩
▲7八金 △8六歩 ▲同 歩 △同 飛 ▲2四歩 △同 歩
▲同 飛 △3二金 ▲3四飛 △8八角成 ▲同 銀 △2八歩
▲同 銀 △4五角 ▲2四飛 △2三歩 ▲7七角 △8八飛成
▲同 角 △2四歩 ▲1一角成 △3三桂 ▲3六香 △6六銀
▲3三香成 △6七角成 ▲同 金 △同銀成 ▲6八歩 △7九飛
▲4八玉 △7八飛成 ▲3六歩 △6八龍 ▲3七玉 △2六金
▲同 玉 △2八龍 ▲2七歩 △3四歩 ▲3七桂 △1四歩
▲1六金 △5七成銀 ▲3二成香 △同 銀 ▲3一飛 △4一銀打
▲3三桂 △4七成銀 ▲4一桂成 △同 銀 ▲3三角 △6二玉
▲2四角成 △3二桂 ▲1四馬 △3七成銀 ▲1五玉 △5一金
▲5二歩 △同 玉 ▲4四歩 △2七成銀 ▲4三歩成 △同 玉
▲3二馬 △同 銀 ▲4四銀 △5二玉 ▲5三銀成 △6一玉
▲5一飛成 △7二玉 ▲7一龍 △同 玉 ▲6二金 △8二玉
▲8三歩 △同 玉 ▲8四歩 △9四玉 ▲8六桂 △9五玉
▲9六歩 △8六玉 ▲7七馬
まで93手で先手の勝ち
ということで△7八飛成は先手良し。しかし、いかにもギリギリ綱渡り的な
手順ではあります。
アマチュア2段〜3段ぐらいで、定跡を知らなかったら△7八飛成への対処を
間違って先手不利になる可能性高いんじゃないでしょうかね。
まあそれはともかく、次は△5七成銀です。これは▲同玉しかなくて
後手も△4九竜。そこで▲3ニ成香△同銀(右図)となる。
この局面はどちらが良いのか?また、ここで先手はどう指すのが良いのか?
というのが、第2次4五角戦法ブームにおける大きなテーマでした。
ここは▲3七桂がこの一手の受けで後手の攻めを凌いでいます。
実はこの進行は、プロの実戦です。1989年▲森内−△屋敷戦です。
この時期は、羽生さん森内さん屋敷さんあたりが4五角戦法を使っていて、
第2次ブームという感じでした。ではその棋譜を。
開始日時:1989/10/17
棋戦:順位戦
戦型:横歩取り
持ち時間:6時間
場所:東京「将棋会館」
備考:△4五角
先手:森内俊之
後手:屋敷伸之
*棋戦詳細:第48期順位戦C級2組05回戦
▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩 △8四歩 ▲2五歩 △8五歩
▲7八金 △8六歩 ▲同 歩 △同 飛 ▲2四歩 △同 歩
▲同 飛 △3二金 ▲3四飛 △8八角成 ▲同 銀 △2八歩
▲同 銀 △4五角 ▲2四飛 △2三歩 ▲7七角 △8八飛成
▲同 角 △2四歩 ▲1一角成 △3三桂 ▲3六香 △6六銀
▲3三香成 △6七角成 ▲同 金 △同銀成 ▲6八歩 △7九飛
▲4八玉 △7八飛成 ▲3六歩 △6八龍 ▲3七玉 △2六金
▲同 玉 △2八龍 ▲2七歩 △3四歩 ▲3七桂 △1四歩
▲1六金 △5七成銀 ▲3二成香 △同 銀 ▲3一飛 △4一銀打
▲3三桂 △4七成銀 ▲4一桂成 △同 銀 ▲3三角 △6二玉
▲2四角成 △3二桂 ▲1四馬 △3七成銀 ▲1五玉 △5一金
▲5二歩 △同 玉 ▲4四歩 △2七成銀 ▲4三歩成 △同 玉
▲3二馬 △同 銀 ▲4四銀 △5二玉 ▲5三銀成 △6一玉
▲5一飛成 △7二玉 ▲7一龍 △同 玉 ▲6二金 △8二玉
▲8三歩 △同 玉 ▲8四歩 △9四玉 ▲8六桂 △9五玉
▲9六歩 △8六玉 ▲7七馬
まで93手で先手の勝ち
ということで△7八飛成は先手良し。しかし、いかにもギリギリ綱渡り的な
手順ではあります。
アマチュア2段〜3段ぐらいで、定跡を知らなかったら△7八飛成への対処を
間違って先手不利になる可能性高いんじゃないでしょうかね。
まあそれはともかく、次は△5七成銀です。これは▲同玉しかなくて
後手も△4九竜。そこで▲3ニ成香△同銀(右図)となる。
この局面はどちらが良いのか?また、ここで先手はどう指すのが良いのか?
というのが、第2次4五角戦法ブームにおける大きなテーマでした。
No.93の右図。この図が自分的には4五角戦法のクライマックスだと思っています。この
図でどっちが良いのか?それがこの戦法の成否を握っている、と。
この局面で、定跡書などで取り上げられている先手の指し手は3つ。
▲2ニ馬・・・最も初期に定跡とされていた手
▲8三角・・・「羽生の頭脳」で最善手とされている手
▲5四歩・・・「横歩取り4五角戦法」で最善手とされている手
いちおう古い順に並べてあります。
ではまず▲2ニ馬から調べていきましょう。
▲2ニ馬には△5九竜と王手。▲5八歩の合い駒に△5四香とまた王手。これには▲5五桂
(左図)と受ける。
ここでの後手の攻め手は
△4五金と押さえつける。
△5五香とあっさり取る。
の2通りがあります。ちなみに、押さえつけでも△6五金としてしまうと、▲1一飛△6ニ玉
▲6一飛成△同玉▲8三角と、打ったばかりの金を引っこ抜かれて後手不利となりますので
ご注意を。
結論から書くと、△4五金でも△5五香でも後手十分やれます。ということでまずは△4五金
から行きましょう。△4五金には▲4六金(中図)がこの一手の受け。
以下△5五香▲同金△6五桂▲6七玉△5五金▲同馬△5七金▲6六玉△6八竜▲7五玉
△7四金▲8六玉△7八竜▲3一飛△4一銀▲同飛成△同玉▲2三角(右図)となって先手勝勢。
後手やれてねえじゃん!いえいえ、これは後手の攻め方がちょっとまずかったんです。正解の
攻めは次コメで。
図でどっちが良いのか?それがこの戦法の成否を握っている、と。
この局面で、定跡書などで取り上げられている先手の指し手は3つ。
▲2ニ馬・・・最も初期に定跡とされていた手
▲8三角・・・「羽生の頭脳」で最善手とされている手
▲5四歩・・・「横歩取り4五角戦法」で最善手とされている手
いちおう古い順に並べてあります。
ではまず▲2ニ馬から調べていきましょう。
▲2ニ馬には△5九竜と王手。▲5八歩の合い駒に△5四香とまた王手。これには▲5五桂
(左図)と受ける。
ここでの後手の攻め手は
△4五金と押さえつける。
△5五香とあっさり取る。
の2通りがあります。ちなみに、押さえつけでも△6五金としてしまうと、▲1一飛△6ニ玉
▲6一飛成△同玉▲8三角と、打ったばかりの金を引っこ抜かれて後手不利となりますので
ご注意を。
結論から書くと、△4五金でも△5五香でも後手十分やれます。ということでまずは△4五金
から行きましょう。△4五金には▲4六金(中図)がこの一手の受け。
以下△5五香▲同金△6五桂▲6七玉△5五金▲同馬△5七金▲6六玉△6八竜▲7五玉
△7四金▲8六玉△7八竜▲3一飛△4一銀▲同飛成△同玉▲2三角(右図)となって先手勝勢。
後手やれてねえじゃん!いえいえ、これは後手の攻め方がちょっとまずかったんです。正解の
攻めは次コメで。
▲4六金の受けには△5五香▲同金△4四桂(左図)と攻めるのが正解です。
う〜んこの△4四桂、実に良い手ですね〜。馬筋を止めつつ、金が取られるのを防ぎつつ
詰めろになっている。普通こんな良い手があれば勝負あり、となうところですが、この
戦法の定跡には随所に技があるのです。
▲1一飛△6ニ玉▲8三角(中図)これが詰めろ逃れの詰めろです。いやー4五角戦法
すごいなあ。定跡覚えるだけで終盤力がついていく感じがしますね〜。
これには△7二銀と受ける一手です。これに対し▲6五角成と逃げる手もありそうですが、
△5五金▲同馬に△5四歩(右図)と突き出す手が好手でうまくありません。
馬を一マス逃げるしかないですが、どこに行っても△5五金と押さえつけて後手良しです。
というわけで角は逃げられない。となると▲4五金と金を外すしか無いところ。
後手も当然△8三銀と角を取りますね。
う〜んこの△4四桂、実に良い手ですね〜。馬筋を止めつつ、金が取られるのを防ぎつつ
詰めろになっている。普通こんな良い手があれば勝負あり、となうところですが、この
戦法の定跡には随所に技があるのです。
▲1一飛△6ニ玉▲8三角(中図)これが詰めろ逃れの詰めろです。いやー4五角戦法
すごいなあ。定跡覚えるだけで終盤力がついていく感じがしますね〜。
これには△7二銀と受ける一手です。これに対し▲6五角成と逃げる手もありそうですが、
△5五金▲同馬に△5四歩(右図)と突き出す手が好手でうまくありません。
馬を一マス逃げるしかないですが、どこに行っても△5五金と押さえつけて後手良しです。
というわけで角は逃げられない。となると▲4五金と金を外すしか無いところ。
後手も当然△8三銀と角を取りますね。
さて前コメで触れたとおり、▲4五金△8三角と、金と角を取り合った局面が左図。
この局面の形勢がどうかというと、駒割りは先手の香得。しかし玉形がひどく、
しかも詰めろがかかっている。後手の玉形も威張れたものでは無いけれど先手よりは数段
マシ。ただし手番は先手が握っているので総合的にはほぼ互角というところでしょうか。
ただ個人的には実戦的に後手が勝ちやすいのでは無かろうか?と思っています。
続いてはもう一つの攻め方、△5五同香です。簡明さではこっちのほうが良いかもしれま
せん。▲同馬に△5四金。これに▲2ニ馬なら△6五桂▲6七玉△8九竜(中図)です。
▲4六馬なら△8九竜▲2四馬△3三歩(右図)。
どちらも互角以上に後手がやれると思います。というわけで、最も初期の定跡手▲2ニ馬は
後手十分ということがわかりました。次に「羽生の頭脳」推奨手▲8三角に行ってみます。
この局面の形勢がどうかというと、駒割りは先手の香得。しかし玉形がひどく、
しかも詰めろがかかっている。後手の玉形も威張れたものでは無いけれど先手よりは数段
マシ。ただし手番は先手が握っているので総合的にはほぼ互角というところでしょうか。
ただ個人的には実戦的に後手が勝ちやすいのでは無かろうか?と思っています。
続いてはもう一つの攻め方、△5五同香です。簡明さではこっちのほうが良いかもしれま
せん。▲同馬に△5四金。これに▲2ニ馬なら△6五桂▲6七玉△8九竜(中図)です。
▲4六馬なら△8九竜▲2四馬△3三歩(右図)。
どちらも互角以上に後手がやれると思います。というわけで、最も初期の定跡手▲2ニ馬は
後手十分ということがわかりました。次に「羽生の頭脳」推奨手▲8三角に行ってみます。
▲2二馬の次は▲8三角(左図)。「羽生の頭脳」において最善手とされ、先手良しとな
るとされている手。名にしおう羽生の頭脳ですから手強くないわけがありません。この難
敵▲8三角には△5九竜か△7二銀ですが、△5九竜だと▲5八金と弾かれ、△8九竜に
▲4二銀と打たれる手が厳しい。
以下、△6二玉▲5三銀成△同玉▲6一角成△5六歩▲同玉△6四桂▲4六玉△5六金
▲4五玉(中図)となってこの競り合いは先手の勝ち。さすがに羽生の頭脳です。
そこで△7二銀です。▲5六角成に△5九竜。ここで▲5八金は今度はもったいない感じ。
歩を打っちゃうと△5四香がある。ということで▲5八桂です。これには△4八金と俗手
で迫る。▲6七銀の補強に△6四香(右図)。
こう進めば後手が良いと思います。なので、やはりもったいなくても▲5八金しかないの
かもしえません。しかしそれには△2九竜で後手玉に対して寄せは無い局面ですから、
後手不満なしだと思います。
というわけで手強い羽生の頭脳▲8三角でしたが、なんとか対抗できそうです。
るとされている手。名にしおう羽生の頭脳ですから手強くないわけがありません。この難
敵▲8三角には△5九竜か△7二銀ですが、△5九竜だと▲5八金と弾かれ、△8九竜に
▲4二銀と打たれる手が厳しい。
以下、△6二玉▲5三銀成△同玉▲6一角成△5六歩▲同玉△6四桂▲4六玉△5六金
▲4五玉(中図)となってこの競り合いは先手の勝ち。さすがに羽生の頭脳です。
そこで△7二銀です。▲5六角成に△5九竜。ここで▲5八金は今度はもったいない感じ。
歩を打っちゃうと△5四香がある。ということで▲5八桂です。これには△4八金と俗手
で迫る。▲6七銀の補強に△6四香(右図)。
こう進めば後手が良いと思います。なので、やはりもったいなくても▲5八金しかないの
かもしえません。しかしそれには△2九竜で後手玉に対して寄せは無い局面ですから、
後手不満なしだと思います。
というわけで手強い羽生の頭脳▲8三角でしたが、なんとか対抗できそうです。
所司先生の「横歩取り4五角戦法」で、先手の最善とされているのが▲5四歩(左図)です。
これは最も強い手で、攻め合い一手勝ちを目指しています。△同歩と取れば▲5三銀でほぼ
受けなしですし、放っておいて▲5三歩成とされてもやはり受けなしです。
後手としてはその前に先手玉を寄せきらないと負けです。所司先生の本ではこの図では△5六香
の一手、と書かれており▲4六玉(中図)とかわして以下先手良し、というかほぼ勝ち、と
されているのです。ちなみに△5六香を▲同玉と取ってしまうと、△5八竜▲5七香に△5四歩
が詰めろとなり、後手良しになります。
ここからは独自の研究になります。後手悪いの定説を覆す候補手が左図で△4五金(右図)
と打つ手です。この手は市販の本にはどこにも載っていないハズです。
さあ果たしてどうなるでしょうか。
これは最も強い手で、攻め合い一手勝ちを目指しています。△同歩と取れば▲5三銀でほぼ
受けなしですし、放っておいて▲5三歩成とされてもやはり受けなしです。
後手としてはその前に先手玉を寄せきらないと負けです。所司先生の本ではこの図では△5六香
の一手、と書かれており▲4六玉(中図)とかわして以下先手良し、というかほぼ勝ち、と
されているのです。ちなみに△5六香を▲同玉と取ってしまうと、△5八竜▲5七香に△5四歩
が詰めろとなり、後手良しになります。
ここからは独自の研究になります。後手悪いの定説を覆す候補手が左図で△4五金(右図)
と打つ手です。この手は市販の本にはどこにも載っていないハズです。
さあ果たしてどうなるでしょうか。
前コメの手順の中で、△5九竜▲5八桂の2手が抜けておりました。お詫びして訂正
させていただきます。
さて詰めろの△4五金に対してどう受けるか?▲6七銀、▲5五金、▲8三角などが
考えられます。まずは▲6七銀。桂馬にもヒモをつけていて良さそうな手に見えます。
しかし△5五香がキビシク、▲6六玉△8九竜(左図)となればやはり先手玉が
詰めろで、これは後手が良しでしょう。
次に考えられるのは▲5五金。これには△5六香と王手。▲同金と取ってくれれば、
△同金▲同玉△5八竜で、▲5四歩△5九竜▲5八桂に△5六香▲同玉と進んだ変化
と同じ事になって後手良しになります。
そこで先手は▲6六玉とかわすわけですが、△6八竜▲6七歩に△5七香成(中図)
と空成りする手が詰めろになっています。実は私自身この変化は実戦例があります。
確かRが1700台だったときで、この中図から先手が▲4五金と金を取ったため、
△6七竜▲7五玉△7四金▲8六玉△8五歩▲9六玉△7六竜(右図)と進めて
勝利しました。
この一局は早指しでありながら、こちらは秒読みになる前、つまり最初の持ち時間
60秒の間で勝ちました。あらかじめ研究してあった手順のとおり進んで勝ったので
考える必要がありません。まさに「4五角戦法で楽して勝つ!」を地で行った勝利
だったと自負してます。
させていただきます。
さて詰めろの△4五金に対してどう受けるか?▲6七銀、▲5五金、▲8三角などが
考えられます。まずは▲6七銀。桂馬にもヒモをつけていて良さそうな手に見えます。
しかし△5五香がキビシク、▲6六玉△8九竜(左図)となればやはり先手玉が
詰めろで、これは後手が良しでしょう。
次に考えられるのは▲5五金。これには△5六香と王手。▲同金と取ってくれれば、
△同金▲同玉△5八竜で、▲5四歩△5九竜▲5八桂に△5六香▲同玉と進んだ変化
と同じ事になって後手良しになります。
そこで先手は▲6六玉とかわすわけですが、△6八竜▲6七歩に△5七香成(中図)
と空成りする手が詰めろになっています。実は私自身この変化は実戦例があります。
確かRが1700台だったときで、この中図から先手が▲4五金と金を取ったため、
△6七竜▲7五玉△7四金▲8六玉△8五歩▲9六玉△7六竜(右図)と進めて
勝利しました。
この一局は早指しでありながら、こちらは秒読みになる前、つまり最初の持ち時間
60秒の間で勝ちました。あらかじめ研究してあった手順のとおり進んで勝ったので
考える必要がありません。まさに「4五角戦法で楽して勝つ!」を地で行った勝利
だったと自負してます。
ニャン吉さん
△8八飛成を入れるのを忘れてしまいましたかー。
この戦法で先手の急所は▲7七角の一手ですね。必ずどこかでこの一手が入るわけです。
さて、私の研究の最後として
「じゃあオマエが4五角戦法を使われたときはどうすんのよ?」
という点について書きたいと思います。本当はコレは誰にも教えたくないのですが・・・
「4五角戦法に対し、先手は必ず▲7七角と打つ手が必要。ならば早ければ早いほど良い」
というのが私の中での理論です。
なので▲3四飛と横歩を取った局面から△8八角成▲同銀△2八歩の時点で▲7七角(左図)
と打ってしまうのが私にとっての「4五角戦法対策」になってます。
これに対しての後手の応手は、△8八飛成(中図)と斬り込む手と△7六飛(右図)と
飛車を逃げる手の2通りしかありません。
△8八飛成を入れるのを忘れてしまいましたかー。
この戦法で先手の急所は▲7七角の一手ですね。必ずどこかでこの一手が入るわけです。
さて、私の研究の最後として
「じゃあオマエが4五角戦法を使われたときはどうすんのよ?」
という点について書きたいと思います。本当はコレは誰にも教えたくないのですが・・・
「4五角戦法に対し、先手は必ず▲7七角と打つ手が必要。ならば早ければ早いほど良い」
というのが私の中での理論です。
なので▲3四飛と横歩を取った局面から△8八角成▲同銀△2八歩の時点で▲7七角(左図)
と打ってしまうのが私にとっての「4五角戦法対策」になってます。
これに対しての後手の応手は、△8八飛成(中図)と斬り込む手と△7六飛(右図)と
飛車を逃げる手の2通りしかありません。
前レスの続きですが、結論から書きます。
中図の△8八飛成と斬り込む順は、「後手不利」となります。私自身△8八飛成とされた
実戦は全勝です。これは先手必勝に近いと思っています。
なので左図△7六飛とするしかないのですが、私自身の実戦で△7六飛とされたことは
一度もありません。△8八飛成遭遇率100%なのです。これはやはり、4五角戦法を
仕掛けた側の心理として、超急戦、超乱戦を挑んでいる以上△7六飛のような緩やかな
手は選びづらいということもあるのだろうと思っています。
変化についても書いていこうと思ったのですが、飯島プロの「横歩取り超急戦のすべて」
にそっくり書かれてしまいました。何てことするんですか飯島さん!(笑)
まあでも、自分自身がひそかに研究していた順が正しいことがわかってちょっと鼻が
高いです。なので、詳細な変化については「横歩取り超急戦のすべて」を
買ってください(笑)。
市販の本に書いてあることを、丸ごとここに書いちゃマズイでしょうしねえ。
この本は、4五角戦法のほかに4四角戦法や、△8八角成▲同銀△3三角とする、
「3三角戦法」についても書かれていて非常に内容が充実しています。買って損はしな
い本だと思います。で、この本の頭には「アマ四段レベルなら十中八九、研究している
ほうが勝つ」とも書かれていますね。
中図の△8八飛成と斬り込む順は、「後手不利」となります。私自身△8八飛成とされた
実戦は全勝です。これは先手必勝に近いと思っています。
なので左図△7六飛とするしかないのですが、私自身の実戦で△7六飛とされたことは
一度もありません。△8八飛成遭遇率100%なのです。これはやはり、4五角戦法を
仕掛けた側の心理として、超急戦、超乱戦を挑んでいる以上△7六飛のような緩やかな
手は選びづらいということもあるのだろうと思っています。
変化についても書いていこうと思ったのですが、飯島プロの「横歩取り超急戦のすべて」
にそっくり書かれてしまいました。何てことするんですか飯島さん!(笑)
まあでも、自分自身がひそかに研究していた順が正しいことがわかってちょっと鼻が
高いです。なので、詳細な変化については「横歩取り超急戦のすべて」を
買ってください(笑)。
市販の本に書いてあることを、丸ごとここに書いちゃマズイでしょうしねえ。
この本は、4五角戦法のほかに4四角戦法や、△8八角成▲同銀△3三角とする、
「3三角戦法」についても書かれていて非常に内容が充実しています。買って損はしな
い本だと思います。で、この本の頭には「アマ四段レベルなら十中八九、研究している
ほうが勝つ」とも書かれていますね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
将棋、次の手どうしたらいいの? 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-