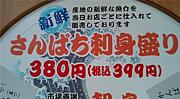うちらが子どものころからよく知ってるアンパンマン。
今のちっちゃいコたちにも大人気でしょ!?
それはなぜか!?
わたしの友達が書いた文章なんやけど、
おもしろかったから
こっそりここにも載せてみました。
くそ長いで覚悟して読んでね
でもかなり読む価値アリ
恥ずかしながら、
僕はこの年齢になりながらも、
ついつい見てしまうアニメがある。
それは、
やなせたかしが生み出した名作、
『それ行け!アンパンマン』(以下『アンパンマン』)
である。
一般的に、
それは幼児から小学校低学年までを対象にしたアニメであるとされる。
そして確かに、僕の脳内の一部はまだまだ幼児(乳児?)のままであるため(ぇ
このアニメが魅力的であるのは合点がいくわけである
が、
しかしながら、
やはり成人になってまでもこのアニメに魅力を感じるにはそれなりの理由が存在する。
そして、
その理由というものは、文章にする価値があると判断した。
故に、
以下にこの『アンパンマン』の魅力の秘密を、
個人的考察として、アダルトな視点から見てみようと思うのだ。
― アンパンマンを哲学する ―
『アンパンマン』に限らず、
長期に渡って支持されるアニメというのは、
そこに意識的にしろ無意識的にしろ、
何かしら我々に訴えかけてくる人類共通的なテーマが含まれているものである。
だからこそ教育的であり、地上波に乗せて放送するだけの価値があるのだ。
『ドラえもん』や『クレヨンしんちゃん』などもその点で同様であると言えよう。
表面だけを見ていてはならない。
アンパン頭のキャラクターにバイ菌の擬人化されたキャラクターがちょっかいをかけるアニメ。
弱虫主人公が毎回ガキ大将にいじめられ、猫型ロボットに助けを求めるアニメ。
破天荒な園児がお下劣全開で笑いを取ろうとするアニメ。
これだけの視点では味気ない。支持などされない。
時として『クレヨンしんちゃん』が教育的でないとして、
子どもに見せたくないアニメの代表とされるが、それは間違いである。
ものごとの本質を見ていない。
お下劣は事実であるが、教育的でないとまでは言い切れないはずだ。
あのくだらないまでのお下劣さは、巧みに「本当に言いたいこと」を隠しているのである。
「秀逸な小説は、本当に言いたいことを『隠して』書かれている」
というのが常識である。
村上春樹の作品は、まさにこの点において抜きん出ているため、
世界的に支持されているのだ。
言葉の並びが美しいというのはもちろんのこと、
その並べられた言葉と言葉の関係性、そこに含まれる意味が深く、
時として謎のままであるからこそ文学作品なのである。
これは、アニメにも同様のことが言えやしないか。
そこで、
『アンパンマン』なのである。
▼ 自己犠牲という美徳
「僕の顔をお食べ」
そう言ってアンパンマンは自分の顔を引き千切り、
空腹に喘ぐみんなを助けてまわる。
これが、アンパンマンが日常的に行っているパトロールの主な業務内容だ。
これは、このアンパンマン的世界の中で、ごく当たり前のこととして描かれている。
第三者である視聴者も、
「そうそう、アンパンって美味しいよね」
という程度の感動を引き出して、そこでお仕舞いである。
しかしながら、
この光景に「アンパンマンって優しいな」以上の、
何かしらの「美しさ」を感じるのも事実であろう。
まず、このシーンにおいて、
『アンパンマン』は人間をはじめとする生物共通の「食うか食われるか」の関係性を、
残酷な描写なしに描き出している点が素晴らしい。
「食うか食われるか」の食物連鎖が常識であるならば、
他人を助けるためには自己を犠牲にするしかない。
アンパンマンは、いとも簡単に
「僕の顔をお食べ」
と言ってみせる。
そして躊躇なく自分の顔をもぎ取って与えるのである。
「お腹が空いているなら僕を食べればいいじゃないか」
ややもすると、非常におぞましい光景になりかねない、
そんな究極的な自己犠牲をひょんとやってみせる、それが主人公アンパンマンなのだ。
自分が「食われる」というのはグロテスクとしか言いようがないはずであるが、
これが美しく描かれ、また微笑ましくも見えるのは、
やはりこの自己犠牲という行為が我々人間にとって特別な意味があり、
美徳とされるからなのであろう。
この自己犠牲の美徳と言うものは他のアニメにも描かれている。
例えば『ONE PIECE』の比較的序盤に登場する、
「海で王陸鮫(海洋モンスター)に襲われるルフィをシャンクスが助ける」というシーン。
ここでシャンクスは左腕を失う。
片腕を「食われる」ことによってルフィの命を救うのだ。
「安いもんだ 腕の一本ぐらい」と。
見事なまでの自己犠牲の描写。カッコ良すぎるだろう、シャンクスよ。
ここに感動したのは僕だけではないだろう。
はっきり言ってこれは推測でしかないが、
おそらくシャンクスは片腕を失う必要などなかった。
シャンクスの強さからすれば、あのレベルの怪物ぐらい、なんてことないはずだからだ。
事実、シャンクスはその眼力だけで王陸鮫を震いあがらせ、退散させている。
まさに自己犠牲の美徳を描き出すために、
そのためにシャンクスの左腕は失われることになったのではないか。
シャンクスは、作者が描きたい自己犠牲の犠牲になったのである。
『アンパンマン』の主題歌、
その歌詞は実に哲学的でありこれだけでいくらでも文章が書けるぐらいである。
その歌い出しはこうだ、
そうだ うれしいんだ
生きる よろこび
たとえ 胸の傷がいたんでも
なんのために 生まれて
なにをして 生きるのか
こたえられない なんて
そんなのは いやだ!
「なんのために生まれて、なにをして生きるのか」
その一つの答えが、他者のために生きるということなのであろう。
自分本位は虚しくなるだけであると。
誰か大切な人がいて、その人のために、
「たとえ 胸の傷がいたんでも」
つまり自己犠牲を払ってでも尽くそうと生きられることが、
「生きる よろこび」
なのではないか、と解釈出来よう。
▼ バタコさんの存在
バタコさんはジャムおじさんと一緒にパン工場で働いていおり、
アンパンマン的世界において珍しく人間(に近いキャラクター)として登場する。
一般的な感想としてはおそらく、
このバタコさんはあまりパッとしない脇役である。
だが、
このバタコさんは、
バタコさんこそは、
このアンパンマン的世界において必要不可欠な存在なのだ。
故に、
「アンパンマン ― バタコさん」という構図には、
またしても大きなテーマを読み取ることが出来よう。
アンパンマンは、自身でパンを焼くことができない。
この設定は実に興味深くないか。
アンパンマンが仮に自分で自分の顔を焼けたとすれば、
ジャムおじさんもバタコさんも必要ない。
手間だけを考えれば、自分で自分の顔を焼いてしまった方がはるかに効率が良い。
しかし、アンパンマンはそうはしない。
いや、もはや自分では焼くことが「できない」のだろう。
ここには、
生きていく上での他者の存在の必要性を見て取れる。
我々は助け合って生きているのだと。
いくら表面的に自立していても、精神的に他者に寄り掛かりながら生きている。
仮に「オレは完全に自立している」と豪語する存在があったにせよ、
それは他者の存在があるからこそ「自立」と言えるのであって、
他者がいなければそもそも「自立」の『自』すら必要のない概念かもしれない。
つまり、「自立」は他者によって「自立」させてもらっているのである。
故に、そういう意味において「自立」という言葉は、
元来自己矛盾を含んでいるとさえ言えるかもしれない。
このように、個人にとって他者の存在は必要不可欠なのである。
この世に生命を授かった以上、他者の存在は絶対なのであり、それは否定できない。
また、その他者の存在はこの上なくありがたいものであり、
他者によって生かしてもらっているのである。
これが「アンパンマン ― バタコさん」の関係性なのだ。
アンパンマンは顔が濡れると活動停止状態に陥る。
これは、生命の危機だ。
しかし、そこに毎回ベストタイミングで現れる救世主がいる。
それが、バタコさんだ!!
稀代のピッチャーとも言えるその抜群なコントロールで、
バタコさんは濡れたアンパンマンの顔を新品へと取り替える。
そして元気100倍になったアンパンマンはバイキンマンに打ち勝つことが出来るのだ。
バイ菌とアンパン。
我々世界の常識で考えれば、圧倒的にバイ菌の方が強いであろう。
しかしながら、アンパンマンはバタコさんによって通常の100倍もの元気を得て、
そして本来勝てるはずもないような強敵にも勝ってしまうのだ。
自分ひとりではどうにも出来ない。
そもそも自分ひとりでは新しいパンを焼けない=生きていけない、もしくは産まれてこれない、
のであり、
自分ひとりではバイキンマンに勝てない=他者の存在が必要、
なのである。
アンパンマンも愚かではない。
自分の顔が濡れれば危機に陥ることぐらい承知しているはずだ。
仮にバイキンマンに出会わなくても、急な雨にうたれてしまうだけでもいけない。
だから、アンパンマンは日常的に危険と隣りあわせであると言えよう。
ならば、自分でパンは焼けないにしても、
焼いてもらった顔を常にいくつか携帯して、
スペアとして持ち歩くことぐらいはしても良いはずだ。
自分の身のためを考えれば、それぐらい、当然の備えと言えよう。
しかし、彼はそれをしない。(もしくはこれもやはり「できない」)
おそらく、バタコさんへの並々ならぬ信頼があるのだろう。
バタコさんという他者の存在は絶対的であり、
ここを拠りどころとして主人公のアンパンマンは成立するのだ。
▼ 取替え可能な「顔」
さて、次は一段階抽象度を上げてみよう。
先ほどのバタコさんによる「顔ぶん投げシーン」であるが、
これも捉えようによっては面白い考察が可能だ。
アンパンマンは顔が濡れると活動停止状態へと向かう。
しかし、濡れたものはいずれ乾く。
普通ならば、ドライヤーを使ったりタオルで拭いてみるものだろう。
しかし、
バタコさんは顔ごと取り替えるという、とんでもない行動を取る。
これは暴挙としか言いようがない。
手術などの医療行為はゼロ。
ただ単に古い顔に新しい顔をぶん投げて弾き飛ばすのだ。
一般的に、
私たちは人間の本質は脳であり、
脳内の精神活動こそが生命であると考えている。
しかし、アンパンマンはそんな脳をそっくり取り替えてしまうのだ。
アイデンティティはいったいどうなるのか。あのイーガンも驚きである。
ここで、アンパンマンの脳は胴体に存在し、
顔は動力源にすぎないという仮説も立てられるが、もっと深い考察も可能だ。
つまり、
生命の本質は物質ではなく、同じ物質の状態を再構成しようとする流れである、
という寓意を導くことができるのである。
私たちは日々異物を食べ、消化し、排出している。
その過程で古くなった細胞は廃棄され、次々と新しい細胞へと入れ替わってく。
おそらく生まれた直後と今の自分では、
身体を構成する分子がほとんど入れ替わっているのではないか。
アイデンティティは物質ではない、
それ故に身体は取り替え可能なのだ、というメッセージを視覚的に表現したのが、
あのアンパンマン顔ぶん投げシーンであったわけだ。
臓器移植や精神の電子コピーなどの倫理的問題を豪快に解決する『アンパンマン』。
なんと高尚なアニメであろうか。
▼ 叶わぬ恋
人間の永遠のテーマ、「恋愛」。
これがしっかり描かれている点も、『アンパンマン』の抜け目ないところだ。
しかし、『アンパンマン』の中に描かれる恋愛はやや悲観的であり、
またそうであるが故にリアルで、テーマとしても大きくなる。
それが描かれているのが、
「食パンマン ― ドキンちゃん」の関係性である。
『アンパンマン』の世界では、パンのキャラクターはアンパンマンだけで本来必要十分だ。
しかし、食パンマンがわざわざ登場するのにはやはり意味があり、
彼が抱えているテーマが「恋愛」なのである。
ドキンちゃんは立場的に敵側の食パンマンに恋している。
この時点ですでにタブーを感じさせるが、
それ以上に深刻なのが彼らの性質の決定的な相違である。
食パンマンは「食品」であり、ドキンちゃんは「バイ菌」である。
食パンにとってバイ菌は言わずもがなの最大悪。
この関係性について作者のやなせたかし氏も、
「この恋が実ることはあり得ません。・・・絶対にあり得ません」
と断言し切っている。
アンパンマン的世界の創造主=神である作者がこれを許さないのであるから、
第三者がいくら気を揉もうが、この恋は実らないのである。
全てのことが上手くいくとは限らない、
自分がいくら願っても、どうしようもないことがある。
またそれは我々世界においても「恋愛」というフィールドによく現れる。
こちらがいくら相手を想っても、それが必ずしも叶うわけではない。
自分と相手の性質が違えば、絶対に交じり合えないのである。
それは定めとも言うべき決定的事項であるのだ。
諦めが必ずしも肝心と言うわけではない。
しかしながら、神をもってしてもどうしようもないことはいくらでもある。
それを受け入れられないためにストーカーなどの犯罪は起きるのであろう。
自己本位はあってはならないのである。
「アンパンマン ― バタコさん」の関係性で見たように、
他者の存在を無視してはならないのであるから。
▼ 仮説としての三角関係/恋愛対象としてのアンパンマン
もう少しアンパンマン的世界における「恋愛」に踏み込んでみよう。
そのための仮説、
「食パンマン ― ドキンちゃん ― バイキンマン」
の三角関係を見てみることにする。
既に述べたように、
食パンマンに対するドキンちゃんの気持ちは明白である。
しかし、バイキンマンのドキンちゃんに対する気持ちは不確実である。
そのために仮説止まりであるが、
「仮」にも「説」が立つということにはそれなりの根拠がある。
火のないところ煙は立たないのである。
バイキンマンの言動を見ていると、
ドキンちゃんの気を惹きたくて仕方ないように感じられることがよくある。
しかし、毎回のごとく軽くあしらわれてお仕舞いである。
だが逆に、ドキンちゃんからバイキンマンに何かお願いをすると、
それが無理難題であってもバイキンマンは必死にそのお願い事を叶えてあげようと努力する。
何だかんだ言っても、ドキンちゃんが可愛くて仕方ないのであろう。
我々世界でも、我儘な可愛い子の言うことについつい従ってしまう男性は多い。
むしろそのじゃじゃ馬っぷりが魅力的に感じてしまうのだ。
ちなみに、僕もそう思ってしまうダメ男の一人である。←どうでもいい。
仮にバイキンマンがドキンちゃんのことを好きでないにしても、
相手に好かれたいと思っているのはほぼ確実であろう。
なんとも微妙で純粋、そして可愛らしい男性心理が、
バイキンマンを通して描き出されている。
さて、
こうした枠組みに入ってこないのがアンパンマン。
アンパンマンはアンパンマン的世界のリーダー的存在である。
全体を統括するリーダーに恋愛は必要事項ではない。
恋愛に傾倒してしまっては、アンパンマン的世界の秩序は保たれないのである。
空腹に喘ぐみんなを目の前にしながら、
「あ、これからデートだからさすがに顔はあげられないよ」
と言ってしまうようでは絶対にダメなのだ。
そこはやはり、
「僕の顔をお食べ」
でないといけない。
故に、恋愛に走った時点で、アンパンマンは主人公から引き摺り下ろされるべきであろう。
これも私利私欲を第一に考えてはならないと言う、一つのリーダー論である。
しかしながら、
そうでなくとも、アンパンマンはそもそも他のキャラクターから恋愛対象として見られていないようだ。
これもリーダーの定めであろう。
アンパンマンのような民主主義的リーダーには、
全体を包み込む大らかさが必要である。
そこには距離的な近さと癒しがあり、父親的な温もりもある。
近親相姦はタブーであり、父親的リーダーは恋愛対象からごく自然に外れるのである。
人間的魅力が必ずしも性的魅力とはならない好例である。
その点において、アンパンマンは完璧なリーダーと言えよう。
異性からの人気を得るのは、やはり食パンマンのような少し距離感がってクールな、
いわゆる高嶺の花のような存在であるのだ。
しかし、食パンマンは主人公にはなれない。
ここがまた美しい。
現実世界の革命家、チェ・ゲバラは、
人間的(リーダー的)魅力と男性的魅力を兼ね備えている特例である。
特例であるからこそ、ここまでもてはやされるのだ。
現実でありながら非現実的である。
アンパンマン的世界の構図のほうが、
むしろ日常レベルではより現実的な描かれ方をされていると言えよう。
▼ アンパンマン vs バイキンマン
さて、
非常に大きなテーマがこのバイキンマンとアンパンマンの戦いの構図である。
これは実に様々な視点から見ることが可能である。
それをいくつかに分類して考えてみよう。
○ 何故バイキンマンはアンパンマンに勝てないのか
先程も少し触れたように、
「アンパン」と「バイ菌」では、「バイ菌」の方が明らかに強いであろう。
アンパンはバイ菌を汚染できないが、その逆は可能であるからだ。
しかし、何故バイキンマンは勝てないのか。
まず、「正義は常に正しいから」と考えられるだろう。
しかし「正義」とは何か。
どこを基準とした正義であるのか。
アンパンマンの視点からすればバイ菌を駆逐することが正義であるが、
バイキンマンの視点からすれば食品を汚染するのが正義であろう。
あくまでここで言う正義とは道徳的に正しいとされる側の「正義」を指している。
そしてそれはアンパンマン的世界においては当然、
アンパンマンが求める「正義」ということになる。
だから、バイキンマンは勝ってはならないのである。
秩序を守るために、勝てそうでも負けなければならない。
それがアンパンマン的世界においてのバイキンマンの宿命なのである。
○ 繰り返される戦い
だがしかし、バイキンマンは諦めない。
彼にも守るべき、貫くべき「正義」があるからだ。
負けることは分かっているが、そこでやめるわけにはいかないのだ。
おそらくバイキンマンは自分が正しいと言うことは疑っていないであろう。
まさに、
「アメリカ vs イスラム諸国」
のような構図であるとは言えないか。
お互いに、お互いの「正義」をぶつけ合う。
世界のリーダー(と言い張る?)アメリカ=アンパンマンと、
テロ攻撃で世界から恐れられるイスラム諸国=バイキンマン。
この世界の「正義」がややアメリカ寄りであるため、
どちらかというとアメリカが支持されるが、
これは僕らがアンパンマン的世界のアンパンマンを眺めているようなもので、
見方によってはバイキンマン=イスラム諸国の「正義」を完全には否定できないのである。
「アンパンマン=イスラム諸国、バイキンマン=アメリカ」
という世界観もあるのである。
現実的に、アメリカはアンパンマンより遥かに平和主義ではなく、
武力行使をも辞さないためにどちらが本当にアンパンマンなのか、
ということが言い難くなっている。
実際に起きているアメリカ批判は、
「我々はアメリカをアンパンマンと認めない」
と言っていると、
極端に要約すればそうなるのであろう。
○ 時に見られる友情とその可能性
だがしかし、
アンパンマン的世界において、
稀に見られる「理想」の描写がある。
それはバイキンマンがアンパンマンたちに友好的になるシーンだ。
僕個人として印象的であったのは、
「バイキンマンがバタコさんを助ける」という物語。
バイキンマンもさすがに露骨には協力しない。
しかし、ぎこちなくもバタコさんを助けようと行動するのだ。
直接的ではなく、間接的に。
とてもいじらしい物語であった。
バイキンマンはバタコさんの気持ちや状況を理解していた。
普段なら「分かり合えない仲」であるが、
ここでは「理解しあえる可能性」を示した。
共通の「正義」を見出したのである。
これをどう読み取るかは個人差がありそうであるが、
対立の解消不可能性を否定したように思える。
また、その先には理想的な結末が用意され、
互いが利益を得ている。
バタコさんは助かり、バイキンマンは照れくさいような心の充実感を得たのだ。
言ってみれば至極当たり前のことであるが、
それを貴重なシーンとして上手く描き出そうとするのが『アンパンマン』である。
現に、その次の回では、
またバイキンマンはアンパンマンに攻撃をしかけている。
ここで簡単に決着をつけさせない辺りが、
アンパンマン的世界の「リアリズム」と「永遠性」と言えるのであろう。
▼ アンパンマン的世界の多様性と理想郷
『アンパンマン』の世界は実に奇妙だ。
まず主人公がアンパンであり、
主人公がパンでありながら、登場してくるキャラクターはパンのみではない。
実に様々なキャラクターが存在する。
人間もいればカバもいる。
ウサギもいればおにぎりもいる。
天丼がいれば琴がいる。
ゴーヤがいれば妖精がいる。
この多様性は何かの象徴ではないか。
第一に、我々世界の人間的縮図ではないか。
マジョリティ・マイノリティ・白人・黒人・黄色人種・弱者・強者の混在。
第二に、我々世界の自然的縮図ではないか。
人間を含め、動物・植物・物・自然からの成り立ち。
二段階でリアルを突き詰めている。
そしてそれらが基本的に秩序立った平和が保たれた世界に収められており、
理想郷として現出している。
やなせたかしが目指した世界観は、
まさに「愛」と「勇気」だけで美しく回転する世界。
この世界で描き出されるストーリーに心惹かれるのは、
もはや仕方のないことであり、
良い意味で諦めるしかないものではないだろうか。
----------------------------------------------------------
どうだろう。
アンパンマンはあなたにとって哲学的であっただろうか。
その決断はさておいても、
このアニメの魅力が再確認されたことを願いたい。
身の回りのこと、
自分の感情の出所を探ってみることは、
ちょっと面白い試みであったりしますよ。
ではでは、
今回も長文・駄文失礼しました。
今のちっちゃいコたちにも大人気でしょ!?
それはなぜか!?
わたしの友達が書いた文章なんやけど、
おもしろかったから
こっそりここにも載せてみました。
くそ長いで覚悟して読んでね
でもかなり読む価値アリ
恥ずかしながら、
僕はこの年齢になりながらも、
ついつい見てしまうアニメがある。
それは、
やなせたかしが生み出した名作、
『それ行け!アンパンマン』(以下『アンパンマン』)
である。
一般的に、
それは幼児から小学校低学年までを対象にしたアニメであるとされる。
そして確かに、僕の脳内の一部はまだまだ幼児(乳児?)のままであるため(ぇ
このアニメが魅力的であるのは合点がいくわけである
が、
しかしながら、
やはり成人になってまでもこのアニメに魅力を感じるにはそれなりの理由が存在する。
そして、
その理由というものは、文章にする価値があると判断した。
故に、
以下にこの『アンパンマン』の魅力の秘密を、
個人的考察として、アダルトな視点から見てみようと思うのだ。
― アンパンマンを哲学する ―
『アンパンマン』に限らず、
長期に渡って支持されるアニメというのは、
そこに意識的にしろ無意識的にしろ、
何かしら我々に訴えかけてくる人類共通的なテーマが含まれているものである。
だからこそ教育的であり、地上波に乗せて放送するだけの価値があるのだ。
『ドラえもん』や『クレヨンしんちゃん』などもその点で同様であると言えよう。
表面だけを見ていてはならない。
アンパン頭のキャラクターにバイ菌の擬人化されたキャラクターがちょっかいをかけるアニメ。
弱虫主人公が毎回ガキ大将にいじめられ、猫型ロボットに助けを求めるアニメ。
破天荒な園児がお下劣全開で笑いを取ろうとするアニメ。
これだけの視点では味気ない。支持などされない。
時として『クレヨンしんちゃん』が教育的でないとして、
子どもに見せたくないアニメの代表とされるが、それは間違いである。
ものごとの本質を見ていない。
お下劣は事実であるが、教育的でないとまでは言い切れないはずだ。
あのくだらないまでのお下劣さは、巧みに「本当に言いたいこと」を隠しているのである。
「秀逸な小説は、本当に言いたいことを『隠して』書かれている」
というのが常識である。
村上春樹の作品は、まさにこの点において抜きん出ているため、
世界的に支持されているのだ。
言葉の並びが美しいというのはもちろんのこと、
その並べられた言葉と言葉の関係性、そこに含まれる意味が深く、
時として謎のままであるからこそ文学作品なのである。
これは、アニメにも同様のことが言えやしないか。
そこで、
『アンパンマン』なのである。
▼ 自己犠牲という美徳
「僕の顔をお食べ」
そう言ってアンパンマンは自分の顔を引き千切り、
空腹に喘ぐみんなを助けてまわる。
これが、アンパンマンが日常的に行っているパトロールの主な業務内容だ。
これは、このアンパンマン的世界の中で、ごく当たり前のこととして描かれている。
第三者である視聴者も、
「そうそう、アンパンって美味しいよね」
という程度の感動を引き出して、そこでお仕舞いである。
しかしながら、
この光景に「アンパンマンって優しいな」以上の、
何かしらの「美しさ」を感じるのも事実であろう。
まず、このシーンにおいて、
『アンパンマン』は人間をはじめとする生物共通の「食うか食われるか」の関係性を、
残酷な描写なしに描き出している点が素晴らしい。
「食うか食われるか」の食物連鎖が常識であるならば、
他人を助けるためには自己を犠牲にするしかない。
アンパンマンは、いとも簡単に
「僕の顔をお食べ」
と言ってみせる。
そして躊躇なく自分の顔をもぎ取って与えるのである。
「お腹が空いているなら僕を食べればいいじゃないか」
ややもすると、非常におぞましい光景になりかねない、
そんな究極的な自己犠牲をひょんとやってみせる、それが主人公アンパンマンなのだ。
自分が「食われる」というのはグロテスクとしか言いようがないはずであるが、
これが美しく描かれ、また微笑ましくも見えるのは、
やはりこの自己犠牲という行為が我々人間にとって特別な意味があり、
美徳とされるからなのであろう。
この自己犠牲の美徳と言うものは他のアニメにも描かれている。
例えば『ONE PIECE』の比較的序盤に登場する、
「海で王陸鮫(海洋モンスター)に襲われるルフィをシャンクスが助ける」というシーン。
ここでシャンクスは左腕を失う。
片腕を「食われる」ことによってルフィの命を救うのだ。
「安いもんだ 腕の一本ぐらい」と。
見事なまでの自己犠牲の描写。カッコ良すぎるだろう、シャンクスよ。
ここに感動したのは僕だけではないだろう。
はっきり言ってこれは推測でしかないが、
おそらくシャンクスは片腕を失う必要などなかった。
シャンクスの強さからすれば、あのレベルの怪物ぐらい、なんてことないはずだからだ。
事実、シャンクスはその眼力だけで王陸鮫を震いあがらせ、退散させている。
まさに自己犠牲の美徳を描き出すために、
そのためにシャンクスの左腕は失われることになったのではないか。
シャンクスは、作者が描きたい自己犠牲の犠牲になったのである。
『アンパンマン』の主題歌、
その歌詞は実に哲学的でありこれだけでいくらでも文章が書けるぐらいである。
その歌い出しはこうだ、
そうだ うれしいんだ
生きる よろこび
たとえ 胸の傷がいたんでも
なんのために 生まれて
なにをして 生きるのか
こたえられない なんて
そんなのは いやだ!
「なんのために生まれて、なにをして生きるのか」
その一つの答えが、他者のために生きるということなのであろう。
自分本位は虚しくなるだけであると。
誰か大切な人がいて、その人のために、
「たとえ 胸の傷がいたんでも」
つまり自己犠牲を払ってでも尽くそうと生きられることが、
「生きる よろこび」
なのではないか、と解釈出来よう。
▼ バタコさんの存在
バタコさんはジャムおじさんと一緒にパン工場で働いていおり、
アンパンマン的世界において珍しく人間(に近いキャラクター)として登場する。
一般的な感想としてはおそらく、
このバタコさんはあまりパッとしない脇役である。
だが、
このバタコさんは、
バタコさんこそは、
このアンパンマン的世界において必要不可欠な存在なのだ。
故に、
「アンパンマン ― バタコさん」という構図には、
またしても大きなテーマを読み取ることが出来よう。
アンパンマンは、自身でパンを焼くことができない。
この設定は実に興味深くないか。
アンパンマンが仮に自分で自分の顔を焼けたとすれば、
ジャムおじさんもバタコさんも必要ない。
手間だけを考えれば、自分で自分の顔を焼いてしまった方がはるかに効率が良い。
しかし、アンパンマンはそうはしない。
いや、もはや自分では焼くことが「できない」のだろう。
ここには、
生きていく上での他者の存在の必要性を見て取れる。
我々は助け合って生きているのだと。
いくら表面的に自立していても、精神的に他者に寄り掛かりながら生きている。
仮に「オレは完全に自立している」と豪語する存在があったにせよ、
それは他者の存在があるからこそ「自立」と言えるのであって、
他者がいなければそもそも「自立」の『自』すら必要のない概念かもしれない。
つまり、「自立」は他者によって「自立」させてもらっているのである。
故に、そういう意味において「自立」という言葉は、
元来自己矛盾を含んでいるとさえ言えるかもしれない。
このように、個人にとって他者の存在は必要不可欠なのである。
この世に生命を授かった以上、他者の存在は絶対なのであり、それは否定できない。
また、その他者の存在はこの上なくありがたいものであり、
他者によって生かしてもらっているのである。
これが「アンパンマン ― バタコさん」の関係性なのだ。
アンパンマンは顔が濡れると活動停止状態に陥る。
これは、生命の危機だ。
しかし、そこに毎回ベストタイミングで現れる救世主がいる。
それが、バタコさんだ!!
稀代のピッチャーとも言えるその抜群なコントロールで、
バタコさんは濡れたアンパンマンの顔を新品へと取り替える。
そして元気100倍になったアンパンマンはバイキンマンに打ち勝つことが出来るのだ。
バイ菌とアンパン。
我々世界の常識で考えれば、圧倒的にバイ菌の方が強いであろう。
しかしながら、アンパンマンはバタコさんによって通常の100倍もの元気を得て、
そして本来勝てるはずもないような強敵にも勝ってしまうのだ。
自分ひとりではどうにも出来ない。
そもそも自分ひとりでは新しいパンを焼けない=生きていけない、もしくは産まれてこれない、
のであり、
自分ひとりではバイキンマンに勝てない=他者の存在が必要、
なのである。
アンパンマンも愚かではない。
自分の顔が濡れれば危機に陥ることぐらい承知しているはずだ。
仮にバイキンマンに出会わなくても、急な雨にうたれてしまうだけでもいけない。
だから、アンパンマンは日常的に危険と隣りあわせであると言えよう。
ならば、自分でパンは焼けないにしても、
焼いてもらった顔を常にいくつか携帯して、
スペアとして持ち歩くことぐらいはしても良いはずだ。
自分の身のためを考えれば、それぐらい、当然の備えと言えよう。
しかし、彼はそれをしない。(もしくはこれもやはり「できない」)
おそらく、バタコさんへの並々ならぬ信頼があるのだろう。
バタコさんという他者の存在は絶対的であり、
ここを拠りどころとして主人公のアンパンマンは成立するのだ。
▼ 取替え可能な「顔」
さて、次は一段階抽象度を上げてみよう。
先ほどのバタコさんによる「顔ぶん投げシーン」であるが、
これも捉えようによっては面白い考察が可能だ。
アンパンマンは顔が濡れると活動停止状態へと向かう。
しかし、濡れたものはいずれ乾く。
普通ならば、ドライヤーを使ったりタオルで拭いてみるものだろう。
しかし、
バタコさんは顔ごと取り替えるという、とんでもない行動を取る。
これは暴挙としか言いようがない。
手術などの医療行為はゼロ。
ただ単に古い顔に新しい顔をぶん投げて弾き飛ばすのだ。
一般的に、
私たちは人間の本質は脳であり、
脳内の精神活動こそが生命であると考えている。
しかし、アンパンマンはそんな脳をそっくり取り替えてしまうのだ。
アイデンティティはいったいどうなるのか。あのイーガンも驚きである。
ここで、アンパンマンの脳は胴体に存在し、
顔は動力源にすぎないという仮説も立てられるが、もっと深い考察も可能だ。
つまり、
生命の本質は物質ではなく、同じ物質の状態を再構成しようとする流れである、
という寓意を導くことができるのである。
私たちは日々異物を食べ、消化し、排出している。
その過程で古くなった細胞は廃棄され、次々と新しい細胞へと入れ替わってく。
おそらく生まれた直後と今の自分では、
身体を構成する分子がほとんど入れ替わっているのではないか。
アイデンティティは物質ではない、
それ故に身体は取り替え可能なのだ、というメッセージを視覚的に表現したのが、
あのアンパンマン顔ぶん投げシーンであったわけだ。
臓器移植や精神の電子コピーなどの倫理的問題を豪快に解決する『アンパンマン』。
なんと高尚なアニメであろうか。
▼ 叶わぬ恋
人間の永遠のテーマ、「恋愛」。
これがしっかり描かれている点も、『アンパンマン』の抜け目ないところだ。
しかし、『アンパンマン』の中に描かれる恋愛はやや悲観的であり、
またそうであるが故にリアルで、テーマとしても大きくなる。
それが描かれているのが、
「食パンマン ― ドキンちゃん」の関係性である。
『アンパンマン』の世界では、パンのキャラクターはアンパンマンだけで本来必要十分だ。
しかし、食パンマンがわざわざ登場するのにはやはり意味があり、
彼が抱えているテーマが「恋愛」なのである。
ドキンちゃんは立場的に敵側の食パンマンに恋している。
この時点ですでにタブーを感じさせるが、
それ以上に深刻なのが彼らの性質の決定的な相違である。
食パンマンは「食品」であり、ドキンちゃんは「バイ菌」である。
食パンにとってバイ菌は言わずもがなの最大悪。
この関係性について作者のやなせたかし氏も、
「この恋が実ることはあり得ません。・・・絶対にあり得ません」
と断言し切っている。
アンパンマン的世界の創造主=神である作者がこれを許さないのであるから、
第三者がいくら気を揉もうが、この恋は実らないのである。
全てのことが上手くいくとは限らない、
自分がいくら願っても、どうしようもないことがある。
またそれは我々世界においても「恋愛」というフィールドによく現れる。
こちらがいくら相手を想っても、それが必ずしも叶うわけではない。
自分と相手の性質が違えば、絶対に交じり合えないのである。
それは定めとも言うべき決定的事項であるのだ。
諦めが必ずしも肝心と言うわけではない。
しかしながら、神をもってしてもどうしようもないことはいくらでもある。
それを受け入れられないためにストーカーなどの犯罪は起きるのであろう。
自己本位はあってはならないのである。
「アンパンマン ― バタコさん」の関係性で見たように、
他者の存在を無視してはならないのであるから。
▼ 仮説としての三角関係/恋愛対象としてのアンパンマン
もう少しアンパンマン的世界における「恋愛」に踏み込んでみよう。
そのための仮説、
「食パンマン ― ドキンちゃん ― バイキンマン」
の三角関係を見てみることにする。
既に述べたように、
食パンマンに対するドキンちゃんの気持ちは明白である。
しかし、バイキンマンのドキンちゃんに対する気持ちは不確実である。
そのために仮説止まりであるが、
「仮」にも「説」が立つということにはそれなりの根拠がある。
火のないところ煙は立たないのである。
バイキンマンの言動を見ていると、
ドキンちゃんの気を惹きたくて仕方ないように感じられることがよくある。
しかし、毎回のごとく軽くあしらわれてお仕舞いである。
だが逆に、ドキンちゃんからバイキンマンに何かお願いをすると、
それが無理難題であってもバイキンマンは必死にそのお願い事を叶えてあげようと努力する。
何だかんだ言っても、ドキンちゃんが可愛くて仕方ないのであろう。
我々世界でも、我儘な可愛い子の言うことについつい従ってしまう男性は多い。
むしろそのじゃじゃ馬っぷりが魅力的に感じてしまうのだ。
ちなみに、僕もそう思ってしまうダメ男の一人である。←どうでもいい。
仮にバイキンマンがドキンちゃんのことを好きでないにしても、
相手に好かれたいと思っているのはほぼ確実であろう。
なんとも微妙で純粋、そして可愛らしい男性心理が、
バイキンマンを通して描き出されている。
さて、
こうした枠組みに入ってこないのがアンパンマン。
アンパンマンはアンパンマン的世界のリーダー的存在である。
全体を統括するリーダーに恋愛は必要事項ではない。
恋愛に傾倒してしまっては、アンパンマン的世界の秩序は保たれないのである。
空腹に喘ぐみんなを目の前にしながら、
「あ、これからデートだからさすがに顔はあげられないよ」
と言ってしまうようでは絶対にダメなのだ。
そこはやはり、
「僕の顔をお食べ」
でないといけない。
故に、恋愛に走った時点で、アンパンマンは主人公から引き摺り下ろされるべきであろう。
これも私利私欲を第一に考えてはならないと言う、一つのリーダー論である。
しかしながら、
そうでなくとも、アンパンマンはそもそも他のキャラクターから恋愛対象として見られていないようだ。
これもリーダーの定めであろう。
アンパンマンのような民主主義的リーダーには、
全体を包み込む大らかさが必要である。
そこには距離的な近さと癒しがあり、父親的な温もりもある。
近親相姦はタブーであり、父親的リーダーは恋愛対象からごく自然に外れるのである。
人間的魅力が必ずしも性的魅力とはならない好例である。
その点において、アンパンマンは完璧なリーダーと言えよう。
異性からの人気を得るのは、やはり食パンマンのような少し距離感がってクールな、
いわゆる高嶺の花のような存在であるのだ。
しかし、食パンマンは主人公にはなれない。
ここがまた美しい。
現実世界の革命家、チェ・ゲバラは、
人間的(リーダー的)魅力と男性的魅力を兼ね備えている特例である。
特例であるからこそ、ここまでもてはやされるのだ。
現実でありながら非現実的である。
アンパンマン的世界の構図のほうが、
むしろ日常レベルではより現実的な描かれ方をされていると言えよう。
▼ アンパンマン vs バイキンマン
さて、
非常に大きなテーマがこのバイキンマンとアンパンマンの戦いの構図である。
これは実に様々な視点から見ることが可能である。
それをいくつかに分類して考えてみよう。
○ 何故バイキンマンはアンパンマンに勝てないのか
先程も少し触れたように、
「アンパン」と「バイ菌」では、「バイ菌」の方が明らかに強いであろう。
アンパンはバイ菌を汚染できないが、その逆は可能であるからだ。
しかし、何故バイキンマンは勝てないのか。
まず、「正義は常に正しいから」と考えられるだろう。
しかし「正義」とは何か。
どこを基準とした正義であるのか。
アンパンマンの視点からすればバイ菌を駆逐することが正義であるが、
バイキンマンの視点からすれば食品を汚染するのが正義であろう。
あくまでここで言う正義とは道徳的に正しいとされる側の「正義」を指している。
そしてそれはアンパンマン的世界においては当然、
アンパンマンが求める「正義」ということになる。
だから、バイキンマンは勝ってはならないのである。
秩序を守るために、勝てそうでも負けなければならない。
それがアンパンマン的世界においてのバイキンマンの宿命なのである。
○ 繰り返される戦い
だがしかし、バイキンマンは諦めない。
彼にも守るべき、貫くべき「正義」があるからだ。
負けることは分かっているが、そこでやめるわけにはいかないのだ。
おそらくバイキンマンは自分が正しいと言うことは疑っていないであろう。
まさに、
「アメリカ vs イスラム諸国」
のような構図であるとは言えないか。
お互いに、お互いの「正義」をぶつけ合う。
世界のリーダー(と言い張る?)アメリカ=アンパンマンと、
テロ攻撃で世界から恐れられるイスラム諸国=バイキンマン。
この世界の「正義」がややアメリカ寄りであるため、
どちらかというとアメリカが支持されるが、
これは僕らがアンパンマン的世界のアンパンマンを眺めているようなもので、
見方によってはバイキンマン=イスラム諸国の「正義」を完全には否定できないのである。
「アンパンマン=イスラム諸国、バイキンマン=アメリカ」
という世界観もあるのである。
現実的に、アメリカはアンパンマンより遥かに平和主義ではなく、
武力行使をも辞さないためにどちらが本当にアンパンマンなのか、
ということが言い難くなっている。
実際に起きているアメリカ批判は、
「我々はアメリカをアンパンマンと認めない」
と言っていると、
極端に要約すればそうなるのであろう。
○ 時に見られる友情とその可能性
だがしかし、
アンパンマン的世界において、
稀に見られる「理想」の描写がある。
それはバイキンマンがアンパンマンたちに友好的になるシーンだ。
僕個人として印象的であったのは、
「バイキンマンがバタコさんを助ける」という物語。
バイキンマンもさすがに露骨には協力しない。
しかし、ぎこちなくもバタコさんを助けようと行動するのだ。
直接的ではなく、間接的に。
とてもいじらしい物語であった。
バイキンマンはバタコさんの気持ちや状況を理解していた。
普段なら「分かり合えない仲」であるが、
ここでは「理解しあえる可能性」を示した。
共通の「正義」を見出したのである。
これをどう読み取るかは個人差がありそうであるが、
対立の解消不可能性を否定したように思える。
また、その先には理想的な結末が用意され、
互いが利益を得ている。
バタコさんは助かり、バイキンマンは照れくさいような心の充実感を得たのだ。
言ってみれば至極当たり前のことであるが、
それを貴重なシーンとして上手く描き出そうとするのが『アンパンマン』である。
現に、その次の回では、
またバイキンマンはアンパンマンに攻撃をしかけている。
ここで簡単に決着をつけさせない辺りが、
アンパンマン的世界の「リアリズム」と「永遠性」と言えるのであろう。
▼ アンパンマン的世界の多様性と理想郷
『アンパンマン』の世界は実に奇妙だ。
まず主人公がアンパンであり、
主人公がパンでありながら、登場してくるキャラクターはパンのみではない。
実に様々なキャラクターが存在する。
人間もいればカバもいる。
ウサギもいればおにぎりもいる。
天丼がいれば琴がいる。
ゴーヤがいれば妖精がいる。
この多様性は何かの象徴ではないか。
第一に、我々世界の人間的縮図ではないか。
マジョリティ・マイノリティ・白人・黒人・黄色人種・弱者・強者の混在。
第二に、我々世界の自然的縮図ではないか。
人間を含め、動物・植物・物・自然からの成り立ち。
二段階でリアルを突き詰めている。
そしてそれらが基本的に秩序立った平和が保たれた世界に収められており、
理想郷として現出している。
やなせたかしが目指した世界観は、
まさに「愛」と「勇気」だけで美しく回転する世界。
この世界で描き出されるストーリーに心惹かれるのは、
もはや仕方のないことであり、
良い意味で諦めるしかないものではないだろうか。
----------------------------------------------------------
どうだろう。
アンパンマンはあなたにとって哲学的であっただろうか。
その決断はさておいても、
このアニメの魅力が再確認されたことを願いたい。
身の回りのこと、
自分の感情の出所を探ってみることは、
ちょっと面白い試みであったりしますよ。
ではでは、
今回も長文・駄文失礼しました。
|
|
|
|
|
|
|
|
♡さんぱちッ♡ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
♡さんぱちッ♡のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75501人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196034人
- 3位
- 独り言
- 9045人