ハイデガーに挑むネット読書会 『存在と時間』 `本を手に街へ出よう!'
http://
が、事実上足踏み状態なので、Wikiをとりあえず参照していただきます。
存在と時間
PC:http://
CP:http://
#引用開始#
存在の哲学
ハイデガーの見地においては、行為に対する理論の伝統的優位が逆転される。
彼にとって理論的な見解というものは人工的なものであり、関わり合いを欠いたまま事物を見ることによってもたらされるものであり、そうした経験は「平板化」(Nivellierung)されたものである。
こうした態度は、ハイデッガーによって「客体的」(vorhanden=すでに手のうちにある)と呼ばれ、相互行為のより根源的なあり方である「用具的」(zuhanden=手の届くところにある)な態度に寄生的な欠如態とされる。
寄生的というのは、歴史のうちにおいてわれわれは、世界に対して科学的ないし中立的な態度をもちうるよりも前に、まず第一に世界に対する何らかの態度や心構えをもたなければならないという観念においてのことである。
客体的存在と用具的存在に加えて、現存在の第三の様態として「共同存在」(mitsein)があり、これが現存在の本質となる。
他者とは、孤立して存在する単一の主体「私」を除いたすべての人びとのことではなく、たいていの場合はひとが自分自身とは区別していない(ともにある)人びとのことである。
例えば、「私」が作物を踏み潰したり土を踏み固めてしまわないよう注意しながら畑の周りを歩くとき、この畑は「私」にとって道具的なものであるが、同時に「誰か」の所有地として、あるいは「誰か」に手入れされている(他の「誰か」にとっても道具的である)ものとしても現れる。
この「誰か」たる農夫は、「私」が思考のうちでその畑に付け加えたものではない。
なぜなら、畑が耕され手入れされているという事実を通してすでに農夫は自らを現しているからである。
このようにしてわれわれは世界内において他者と出会うのであり、またこうして現存在が他者と出会いともにある存在の仕方が「共同存在」であるとハイデッガーは述べる。
「共同存在」には好ましからぬ側面もあり、ハイデッガーは「世間」という語を用いてそれに言及する。
つまりニュースやゴシップでしばしば見られるように、「世間では〜といわれている」というとき、一般化して断定したり、一切のコンテクストを無視してそれをやり過ごそうとしたりする傾向があるということである。
何が信頼に値し、何が信頼に値しないのかという実存的概念が「世間」という考えに依拠して求められるのである。
たんに群集のあとを追って他の人々に習うだけでは何の妥当性も保証されないし、社会的・歴史的状況から完全にかけ離れたことが妥当なことだとみなすことなどできないにもかかわらず、「世間」がその平均性のみを妥当なものとして指示するのである(本書第1篇第4章第26 - 27節)。
#引用ここまで#
この論に衝撃を受けました。
(↑2010/02/10 02:33
added sentence & picture: w a r m a r t ;ID1098147↓
guidepost: 難解さ
http://
guidepost: 知識
http://
prologue & epilogue
http://
|
|
|
|
コメント(6)
> BETA@エポケーさん
はじめまして。このトピが気になっていたのですが、なかなか書き出せずにいました。
『存在と時間』
は僕も読んだ事があり、人という共同存在とか、道具的存在論とかが特に面白かったです。
僕は構造言語・構造主義の考えを基盤にする立場を取るので、結論部としては現象学を否定します。
でもハイデガーの手法と構造言語(構造主義)の考えに共通するものとかもあり面白かった事もあり、そういう観点で今コメントしてみようと思います。
だから必ずしも現象学と一致しないかも知れませんが、自分なりの理解です。
『予めある』ということ。
これがハイデガーの一つの根本的な根拠。
ハイデガーはそれを、世界・内・存在において存在するとする。
それは形而上学的実体のようなもの。
これをハイデガーのように「存在」とは呼ばずに「概念」とするなら、それはソシュールの構造言語と一致する。
ソシュールは言語をその言語が指し示す事物を指し示して意識させるための記号だとする。
記号は概念と結び付く事でその指し示す対象の内容や意味を表す。
概念は記号がなければ他の概念と区別がつかない。記号がなければ概念は産出されない。それらはア・プリオリではない。
予め概念があり、記号があるからこそ、諸表象を認識出来る。
目の前に在る実在以上の(以外の)意味内容を認識するのもそのため。
ハイデガーが言う共同存在として人がある場合、その人は自らを人という概念以上に認識する必要を持っていない。
そして、人という概念は人一般に共通する共通原因がら産出される共通概念。
ハンマー等の実在物はハンマーという概念と照らし会わされ認識され、その欠損も理解される。
ハンマーという概念とは、ハンマーの使用目的と密接に結び付く。
この場合、概念と道具という言葉は殆んど同じものになる。
大雑把ですがそんな感じで理解しています。
その上で、懐疑、「疑義」があるとされるその疑義の内容がちょっと解りません。
現象学の否定ということならたぶん同意出来ますが、例えば人が人を攻撃する事とか、いわゆる不幸というものとか、そういうのは現象学的な解釈も成り立つように思うのですが?
何を望まれているのかちょっと
亀レスになるかも知れませんが良ければ話をしましょう。
はじめまして。このトピが気になっていたのですが、なかなか書き出せずにいました。
『存在と時間』
は僕も読んだ事があり、人という共同存在とか、道具的存在論とかが特に面白かったです。
僕は構造言語・構造主義の考えを基盤にする立場を取るので、結論部としては現象学を否定します。
でもハイデガーの手法と構造言語(構造主義)の考えに共通するものとかもあり面白かった事もあり、そういう観点で今コメントしてみようと思います。
だから必ずしも現象学と一致しないかも知れませんが、自分なりの理解です。
『予めある』ということ。
これがハイデガーの一つの根本的な根拠。
ハイデガーはそれを、世界・内・存在において存在するとする。
それは形而上学的実体のようなもの。
これをハイデガーのように「存在」とは呼ばずに「概念」とするなら、それはソシュールの構造言語と一致する。
ソシュールは言語をその言語が指し示す事物を指し示して意識させるための記号だとする。
記号は概念と結び付く事でその指し示す対象の内容や意味を表す。
概念は記号がなければ他の概念と区別がつかない。記号がなければ概念は産出されない。それらはア・プリオリではない。
予め概念があり、記号があるからこそ、諸表象を認識出来る。
目の前に在る実在以上の(以外の)意味内容を認識するのもそのため。
ハイデガーが言う共同存在として人がある場合、その人は自らを人という概念以上に認識する必要を持っていない。
そして、人という概念は人一般に共通する共通原因がら産出される共通概念。
ハンマー等の実在物はハンマーという概念と照らし会わされ認識され、その欠損も理解される。
ハンマーという概念とは、ハンマーの使用目的と密接に結び付く。
この場合、概念と道具という言葉は殆んど同じものになる。
大雑把ですがそんな感じで理解しています。
その上で、懐疑、「疑義」があるとされるその疑義の内容がちょっと解りません。
現象学の否定ということならたぶん同意出来ますが、例えば人が人を攻撃する事とか、いわゆる不幸というものとか、そういうのは現象学的な解釈も成り立つように思うのですが?
何を望まれているのかちょっと
亀レスになるかも知れませんが良ければ話をしましょう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
spɐɯou ʇsol 考える旅人 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
spɐɯou ʇsol 考える旅人 のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90016人
- 2位
- 酒好き
- 170665人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37150人
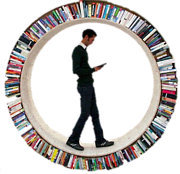

![[dir] 献血](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/19/76/3011976_247s.gif)





















