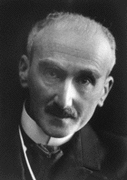第9回
こんにちは。先ほど気がつきましたが、本日このアンリ・ベルクソンのコミュは、202名で、僕がこの読書会の告知を出してから3ヶ月ほどたちますが、50名ほども増えたことになります。読書会をはじめて、どんどん人が抜けていくというのは悲しいですが、50人増えたというのはうれしい限りです。僕のCommentaireもどれだけの人が読んで下さっているかわかりませんが、コミュ作りに一役貢献していると前向きに考えたいです。それにしても、せっかくこれだけベルグソンに関心があるひとが集まっているのですから、もうすこしこの読書会以外にもトピックが活気付いて、情報交換の場になってもいいと思うのですが。みなさん、おとなしいのですね。
さて、今日は、最後にベルグソンの貴重な書簡を訳出してアップすることにします。とても興味深い資料で、ひょっとすると本邦初訳かもしれません。(笑) 最後までお読みくださいね。
(第17段落)さて、今までは、哲学体系の核心部分に直観があるということが述べられてきたわけですが、この段落から、ベルグソンは、哲学と科学の違いに述べていきます。そのことによって、哲学的な見かた即ち哲学的直観の独自性を示そうとするものです。
ベルグソンは1859年生まれでしたから、ベルグソンが育ったのは、まさしく19世紀後半の科学が飛躍的な進歩を遂げた時代だったわけです。この時代に至って、明確に科学は、従来の「自然学」ではなくなり、philosophieから切り離され、「自然科学」としての自己主張を始めるわけです。かつてはデカルトは自然学者であったし、ニュートンは自らの学説を哲学と名づけたように、哲学者が科学者を兼ねるということが出来なくなってきます。それだけではなく、自然科学自体がおのおのの分野で飛躍的な発展を遂げるため、自然科学者は、かつてのアリストテレスのように、すべての知に通じた総合的自然科学者たりうることが次第に不可能になってきます。
しかし、とベルグソンは言いますね。「それでも哲学者が普遍科学の人間であることに変わりありません。それは、たとえあらゆることを知ることが不可能であっても、哲学者が学んでならぬものは何もないという意味においてです。」(le philosophe reste l'homme de la science universelle, en ce sens que, s'il ne peut plus tout savoir, il n'y a rien qu'il ne doive s'être mis en état d'apprendre.) これはつまり、哲学者の真理追及の作業において、自然科学の成果を利用してもいいということを意味します。しかし、それでは、哲学的な見かたを保持したまま、自然科学と切り結ぶことは、どのようにして可能なのでしょう?この段落において、ベルグソンが批判しているように、個別科学(les sciences particulières)の成果を哲学がそっくり譲り受けて、それらを総合化することは、科学的な見かたの延長線上に哲学というものを考えていることにしかなりません。そのような知のあり方を否定するものではないが、それはあくまで科学にしかなりません。そのような知を備えた人間は、学者=物識り(un savant)であるかもしれないけれども、哲学者(philosophe)ではない。(on les dise philosophes, que d'ailleurs chaque science puisse et doive avoir sa philosophie ainsi comprise, je suis le premier à l'admettre. Mais cette philosophie-là est encore de la science, et celui qui la fait est encore un savant.)
この段落はベルグソンが親しんだというスペンサーの綜合哲学に対する批判となっているのかもしれませんね。
(第18段落)そのように、個別科学の諸成果をそっくり貰い受けてそれを総合化することのみを哲学の役割としてしまうことは、科学に対する侮辱となるだけではなく、哲学そのもにに大しても大変な侮辱となるわけです。なぜならが、科学の方法の延長線上に哲学を位置付けたところで、哲学の仕事の独自性にはなんらつながらないからです。個別科学の成果を見つけたところで、科学者の仕事が終わるならば、そこから先は、科学的な見地からはまったく不確実な世界なわけで、まったく同様の科学の方法でもって、そんな不確実な世界を相手にしていたら、いつまでたっても確実性は得られず、まさしく、「確実性の終わるところに哲学が始まる」( la philosophie commence là où la certitude finit)と言われる始末になるのです。それでは、学問とはいえなくなってくるわけです。これは哲学そのものを無意味化してしまうことになりかねない。だからこそ、哲学の役割は、科学的方法とはまったく別の方法によって、確実な確からしさが得られていなければ、意味がないのです。その別の方法が、哲学的直観なわけです。
ところで、ベルグソンとまったく同時期にベルグソンとは別の観点から、科学的方法と峻別して哲学の方法を打ち立てた人物がいます。フッサールです。フッサールは、科学知そのものがどうして可能なのか、科学知そのものを可能にしているわれわれの経験の地盤はどんなものなのかを根底から問い直すために「現象学」を提唱したわけです。厳密な学としての哲学の方法はこの現象学的方法でしかありえない。科学知というのは、一種の自然的態度なのであるから、これを判断停止し、現象学的見かたができる主観性の領野に還元(現象学的還元)するわけです。このような領野において、どのように知が形成され、確実性(明証性)が確立されるのかを問うたわけです。フッサールもその領野を調べるにあたって方法論的に「直観」を採用しますが、その「直観」はベルグソンとはまったく正反対です。フッサールが問題にしているのは、この領野における<本質>即ち形相をどうやって「直観」するかですから、その追求の行き着く先は、ある意味では、プラトン的なイデアリズムになってくるわけです。ベルグソンの直観は、これらの<本質>や形相の向こう側を見ているわけですから、この二人の求めているものはまったく違うわけです。
ところで、ベルグソン以降のフランスの思想界は、サルトルにせよ、メルロ・ポンティにせよ、あるいは、デリダなどのポスト構造主義にせよ、ベルグソンと現象学が複雑に絡み合って発展しているため、今日誰もそれを解きほぐすことに成功していないように見受けられます。それにしても、当のベルグソン自身は、フッサールの現象学をどのように見ていたのでしょうか?どこだか忘れましたが、ベルグソンが現象学に非常に注目していたということが書かれたものをどこかで読んだことがありますが、果たしてそうなのか?これは妖しいと思います。というのも、ベルグソンの百年記念版の著作集にも、メランジュにも、索引を見てもフッサールの名前は一度も出てこないからです。ところが、前にも取り上げた、Correspondances, PUF, 2002 には、ベルグソンのフッサール宛の書簡が一通だけ収録されています。僕の知っている限り、あとにも先にもベルグソンがフッサールに言及しているのはこれだけです。それをここに訳出しておきましょう。日付は1913年8月15日。ベルグソンのスイス滞在中にフッサール宛に送付したもののようです。フッサールがその主著『イデーン』をベルグソン宛に送付したことに対する返信です。
「ムッシュー、そして敬愛すべき同僚殿。
ご親切にも貴方の重要な著作である『イデーン』をお送りくださったことに、取り急ぎ感謝申し上げます。私は今これを読みたいと思っていますが、残念ながらそれが出来ません。いま滞在しているスイスの片隅で、自室に缶詰めになり、休みなく仕事をしなければいけない状態です。そして、しなければいけない仕事が終わるのかの検討もつかないのです。しかし、10月か11月にはもっと時間が取れる見込みですので、そのとき注意して拝読するつもりです。
私は貴方の仕事をとても高く評価しています。いくつかの点において私たちの視点はおそらく異なるでしょう。しかし、視点が容易に一致する点も多くあります。
敬具。
H.ベルグソン」
と、これ一通のみです。その後イデーンを読んだのかどうかも定かではありません。まあ、おそらく読んだのかもしれませんが、その後フッサールに対する言及がまったくないところを見ると重視していたとも思えない。第1回のときに、取り上げたハンス・ドリーシュの場合もそうでしたが、ウイリアム・ジェームズに邂逅したようには、親しみが沸かなかったのかもしれません。どうもベルグソンはドイツの哲学一般に対しては、あまり共感を抱かなかったようです。
【次回予習範囲】
第10回(10月2日(日))まで、以下のとおり読んでおいてください。
?Quadrige版:
始め:p136 25行目〜 La veriteから
終り:p138 19行目〜 une analyse.まで。
?世界の名著版:
始め:p128 上段 15行目〜
終り:p129 下段 08行目「働きなのであります。」まで
こんにちは。先ほど気がつきましたが、本日このアンリ・ベルクソンのコミュは、202名で、僕がこの読書会の告知を出してから3ヶ月ほどたちますが、50名ほども増えたことになります。読書会をはじめて、どんどん人が抜けていくというのは悲しいですが、50人増えたというのはうれしい限りです。僕のCommentaireもどれだけの人が読んで下さっているかわかりませんが、コミュ作りに一役貢献していると前向きに考えたいです。それにしても、せっかくこれだけベルグソンに関心があるひとが集まっているのですから、もうすこしこの読書会以外にもトピックが活気付いて、情報交換の場になってもいいと思うのですが。みなさん、おとなしいのですね。
さて、今日は、最後にベルグソンの貴重な書簡を訳出してアップすることにします。とても興味深い資料で、ひょっとすると本邦初訳かもしれません。(笑) 最後までお読みくださいね。
(第17段落)さて、今までは、哲学体系の核心部分に直観があるということが述べられてきたわけですが、この段落から、ベルグソンは、哲学と科学の違いに述べていきます。そのことによって、哲学的な見かた即ち哲学的直観の独自性を示そうとするものです。
ベルグソンは1859年生まれでしたから、ベルグソンが育ったのは、まさしく19世紀後半の科学が飛躍的な進歩を遂げた時代だったわけです。この時代に至って、明確に科学は、従来の「自然学」ではなくなり、philosophieから切り離され、「自然科学」としての自己主張を始めるわけです。かつてはデカルトは自然学者であったし、ニュートンは自らの学説を哲学と名づけたように、哲学者が科学者を兼ねるということが出来なくなってきます。それだけではなく、自然科学自体がおのおのの分野で飛躍的な発展を遂げるため、自然科学者は、かつてのアリストテレスのように、すべての知に通じた総合的自然科学者たりうることが次第に不可能になってきます。
しかし、とベルグソンは言いますね。「それでも哲学者が普遍科学の人間であることに変わりありません。それは、たとえあらゆることを知ることが不可能であっても、哲学者が学んでならぬものは何もないという意味においてです。」(le philosophe reste l'homme de la science universelle, en ce sens que, s'il ne peut plus tout savoir, il n'y a rien qu'il ne doive s'être mis en état d'apprendre.) これはつまり、哲学者の真理追及の作業において、自然科学の成果を利用してもいいということを意味します。しかし、それでは、哲学的な見かたを保持したまま、自然科学と切り結ぶことは、どのようにして可能なのでしょう?この段落において、ベルグソンが批判しているように、個別科学(les sciences particulières)の成果を哲学がそっくり譲り受けて、それらを総合化することは、科学的な見かたの延長線上に哲学というものを考えていることにしかなりません。そのような知のあり方を否定するものではないが、それはあくまで科学にしかなりません。そのような知を備えた人間は、学者=物識り(un savant)であるかもしれないけれども、哲学者(philosophe)ではない。(on les dise philosophes, que d'ailleurs chaque science puisse et doive avoir sa philosophie ainsi comprise, je suis le premier à l'admettre. Mais cette philosophie-là est encore de la science, et celui qui la fait est encore un savant.)
この段落はベルグソンが親しんだというスペンサーの綜合哲学に対する批判となっているのかもしれませんね。
(第18段落)そのように、個別科学の諸成果をそっくり貰い受けてそれを総合化することのみを哲学の役割としてしまうことは、科学に対する侮辱となるだけではなく、哲学そのもにに大しても大変な侮辱となるわけです。なぜならが、科学の方法の延長線上に哲学を位置付けたところで、哲学の仕事の独自性にはなんらつながらないからです。個別科学の成果を見つけたところで、科学者の仕事が終わるならば、そこから先は、科学的な見地からはまったく不確実な世界なわけで、まったく同様の科学の方法でもって、そんな不確実な世界を相手にしていたら、いつまでたっても確実性は得られず、まさしく、「確実性の終わるところに哲学が始まる」( la philosophie commence là où la certitude finit)と言われる始末になるのです。それでは、学問とはいえなくなってくるわけです。これは哲学そのものを無意味化してしまうことになりかねない。だからこそ、哲学の役割は、科学的方法とはまったく別の方法によって、確実な確からしさが得られていなければ、意味がないのです。その別の方法が、哲学的直観なわけです。
ところで、ベルグソンとまったく同時期にベルグソンとは別の観点から、科学的方法と峻別して哲学の方法を打ち立てた人物がいます。フッサールです。フッサールは、科学知そのものがどうして可能なのか、科学知そのものを可能にしているわれわれの経験の地盤はどんなものなのかを根底から問い直すために「現象学」を提唱したわけです。厳密な学としての哲学の方法はこの現象学的方法でしかありえない。科学知というのは、一種の自然的態度なのであるから、これを判断停止し、現象学的見かたができる主観性の領野に還元(現象学的還元)するわけです。このような領野において、どのように知が形成され、確実性(明証性)が確立されるのかを問うたわけです。フッサールもその領野を調べるにあたって方法論的に「直観」を採用しますが、その「直観」はベルグソンとはまったく正反対です。フッサールが問題にしているのは、この領野における<本質>即ち形相をどうやって「直観」するかですから、その追求の行き着く先は、ある意味では、プラトン的なイデアリズムになってくるわけです。ベルグソンの直観は、これらの<本質>や形相の向こう側を見ているわけですから、この二人の求めているものはまったく違うわけです。
ところで、ベルグソン以降のフランスの思想界は、サルトルにせよ、メルロ・ポンティにせよ、あるいは、デリダなどのポスト構造主義にせよ、ベルグソンと現象学が複雑に絡み合って発展しているため、今日誰もそれを解きほぐすことに成功していないように見受けられます。それにしても、当のベルグソン自身は、フッサールの現象学をどのように見ていたのでしょうか?どこだか忘れましたが、ベルグソンが現象学に非常に注目していたということが書かれたものをどこかで読んだことがありますが、果たしてそうなのか?これは妖しいと思います。というのも、ベルグソンの百年記念版の著作集にも、メランジュにも、索引を見てもフッサールの名前は一度も出てこないからです。ところが、前にも取り上げた、Correspondances, PUF, 2002 には、ベルグソンのフッサール宛の書簡が一通だけ収録されています。僕の知っている限り、あとにも先にもベルグソンがフッサールに言及しているのはこれだけです。それをここに訳出しておきましょう。日付は1913年8月15日。ベルグソンのスイス滞在中にフッサール宛に送付したもののようです。フッサールがその主著『イデーン』をベルグソン宛に送付したことに対する返信です。
「ムッシュー、そして敬愛すべき同僚殿。
ご親切にも貴方の重要な著作である『イデーン』をお送りくださったことに、取り急ぎ感謝申し上げます。私は今これを読みたいと思っていますが、残念ながらそれが出来ません。いま滞在しているスイスの片隅で、自室に缶詰めになり、休みなく仕事をしなければいけない状態です。そして、しなければいけない仕事が終わるのかの検討もつかないのです。しかし、10月か11月にはもっと時間が取れる見込みですので、そのとき注意して拝読するつもりです。
私は貴方の仕事をとても高く評価しています。いくつかの点において私たちの視点はおそらく異なるでしょう。しかし、視点が容易に一致する点も多くあります。
敬具。
H.ベルグソン」
と、これ一通のみです。その後イデーンを読んだのかどうかも定かではありません。まあ、おそらく読んだのかもしれませんが、その後フッサールに対する言及がまったくないところを見ると重視していたとも思えない。第1回のときに、取り上げたハンス・ドリーシュの場合もそうでしたが、ウイリアム・ジェームズに邂逅したようには、親しみが沸かなかったのかもしれません。どうもベルグソンはドイツの哲学一般に対しては、あまり共感を抱かなかったようです。
【次回予習範囲】
第10回(10月2日(日))まで、以下のとおり読んでおいてください。
?Quadrige版:
始め:p136 25行目〜 La veriteから
終り:p138 19行目〜 une analyse.まで。
?世界の名著版:
始め:p128 上段 15行目〜
終り:p129 下段 08行目「働きなのであります。」まで
|
|
|
|
コメント(10)
小雲さん
野良ガジラは空を飛ぶさん
こんにちは。
読んでくださる方が他にもいらしたようで、とてもうれしいです。
ぜひこの機会に「哲学的直観」をすみからすみまで、じっくり、そしてゆっくり読んでみてください。
さて、野良ガジラは空を飛ぶさんのおっしゃるドゥルーズの読書会というのは、都内国立大学TK大学のシネマかなにかをめぐるものではないですか?ぼくもうわさには聞いたことがあります。
僕は、ドゥルーズについては、あまり詳しくわかりませんが、もう何年も前ですが、例のドゥルーズ=ガタリの「ミル・プラトー」の序文のリゾームを友人達とフランス語で輪読したことがあります。
そのときの印象ですが、このリゾームという発想の核心部分にあるのは、間違いなくベルグソン哲学だなって実感しました。ドゥルーズ(それにガタリも!?)の哲学というのは、実は、かなりラディカルなvolontarisme、それも生の哲学ではないかなと確信いたしました。いずれにせよ、80年代に日本の紹介されたドゥルーズ像というのは実はかなり歪曲されたものでしかなかったのではないか?だからこそ根本的な読み直しが必要なのではないか?そんな気がしています。
以来ドゥルーズに興味を持って、主要な著作を手元にそろえているのですが、なかなか読む機会ももてずに今にいたっています。
今後もいろいろご教示いただければ幸いです。
野良ガジラは空を飛ぶさん
こんにちは。
読んでくださる方が他にもいらしたようで、とてもうれしいです。
ぜひこの機会に「哲学的直観」をすみからすみまで、じっくり、そしてゆっくり読んでみてください。
さて、野良ガジラは空を飛ぶさんのおっしゃるドゥルーズの読書会というのは、都内国立大学TK大学のシネマかなにかをめぐるものではないですか?ぼくもうわさには聞いたことがあります。
僕は、ドゥルーズについては、あまり詳しくわかりませんが、もう何年も前ですが、例のドゥルーズ=ガタリの「ミル・プラトー」の序文のリゾームを友人達とフランス語で輪読したことがあります。
そのときの印象ですが、このリゾームという発想の核心部分にあるのは、間違いなくベルグソン哲学だなって実感しました。ドゥルーズ(それにガタリも!?)の哲学というのは、実は、かなりラディカルなvolontarisme、それも生の哲学ではないかなと確信いたしました。いずれにせよ、80年代に日本の紹介されたドゥルーズ像というのは実はかなり歪曲されたものでしかなかったのではないか?だからこそ根本的な読み直しが必要なのではないか?そんな気がしています。
以来ドゥルーズに興味を持って、主要な著作を手元にそろえているのですが、なかなか読む機会ももてずに今にいたっています。
今後もいろいろご教示いただければ幸いです。
>小雪さん
書き込みありがとうございます。
>リゾームを視覚化したなら、
>雲の動きのようなことなんだろうか?
うーむ、雲のようにふわふわと捉えどころがないイメージよりも、かなり能動的なものをイメージします。
僕の理解を書きますね。
リゾームというのは、「ツリー」と対置させる概念です。
ツリーとはヨーロッパ的で通時的なモデルです。丸山真男の言葉を借りれば、「ササラ文化」。ひとつの出所から派生して、いろいろな枝に分かれていく。
だから、たとえばモデルとして社会を見てみても、昔からの因縁を引きずって、いろいろなものに分かれている。それを横切りしてみると、いろいろな輪切りの管がたくさん出来上がっているのが見えるでしょう。階級だの企業だの組織だの官僚だのがまさにそれです。
ところで、人間の意識を見てみると細胞みたいにぐつぐつといっている。これが多様体(la multiplicite)なわけです。まさしく、ベルグソンが『時間と自由』の第2章において、持続の特徴を質的多様性としたあれです。この人間の意識の多様体は、多様であるゆえに、必然的に分裂症的傾向をもっている。だから、たとえば、僕と小雪さんが出会うことによって、僕の意識の中に、小雪さん的要素(もしくはその反対要素)がぼわーっと広がってくる。その後、野良ガジラは空を飛ぶさんに会うことによって、こんどは、野良ガジラは空を飛ぶさん的なもの(もしくはその反対要素)がぼわーっと広がってくる。こういうふうに、意識のなかのいろいろな思考が人だのものだの事件だのに出会うことによって、それらに誘発されて、ぼわーっ、ぼわーっと絶えずぐつぐつしているのが、生命力のある細胞のような意識の状態なわけです。これを分裂的傾向とドゥルーズ=ガタリは言うらしい。
ところが、こういった本来分裂的傾向=多様体である人間が先ほどの、ツリー上のどこかの輪切りにされた中に入るとそこの価値観に洗脳されてしまって、すっかり思考が固定化し出られなくなってしまう。まさしく官僚だの会社だの大学だのといった組織に入り込んでそこの価値観に染まってしまって一歩も外に出られなくなってしまう。そうするとぐつぐついっていた細胞が固まってきてしまうんです。これを偏執的傾向(パラノイア)と呼ぶわけです。だからこんなことになったのでは、生命体のもつ生命力が奪われて身動きがとれなくなってしまう。
だからこそ、「点ではなく、線になれ」というのです。点というのがそのツリーの枝の輪切りです。そして線がリゾームです。いろいろなワッカを動き回って、いろいろな組織や人、事件に出会って自分の価値観を多様に保て、というわけです。
この線になる努力は相当なエネルギーを使います。80年代に言われたような感性のなんとかといった軽薄なものでは決してありえない。とても強い意志に基づかなければ、人間はリゾーム的運動体にはなれませんよね。だからそういう意味では、このリゾームを作り出すエネルギーこそはまさしく多様性を保ちつつ進化していくベルグソンのいうエランヴィタルみたいなものなのです。そういう意味で、僕はリゾームの中にベルグソン的な主意主義=生の哲学を読み取りました。
まあ、僕は、この「リゾーム」しか読んだことはないので、資本主義の分析だとか精神分析がどう関わるのか分かりませんが、こういった視点でもう一度読み直してみる必要があると思いますが、如何でしょう。
書き込みありがとうございます。
>リゾームを視覚化したなら、
>雲の動きのようなことなんだろうか?
うーむ、雲のようにふわふわと捉えどころがないイメージよりも、かなり能動的なものをイメージします。
僕の理解を書きますね。
リゾームというのは、「ツリー」と対置させる概念です。
ツリーとはヨーロッパ的で通時的なモデルです。丸山真男の言葉を借りれば、「ササラ文化」。ひとつの出所から派生して、いろいろな枝に分かれていく。
だから、たとえばモデルとして社会を見てみても、昔からの因縁を引きずって、いろいろなものに分かれている。それを横切りしてみると、いろいろな輪切りの管がたくさん出来上がっているのが見えるでしょう。階級だの企業だの組織だの官僚だのがまさにそれです。
ところで、人間の意識を見てみると細胞みたいにぐつぐつといっている。これが多様体(la multiplicite)なわけです。まさしく、ベルグソンが『時間と自由』の第2章において、持続の特徴を質的多様性としたあれです。この人間の意識の多様体は、多様であるゆえに、必然的に分裂症的傾向をもっている。だから、たとえば、僕と小雪さんが出会うことによって、僕の意識の中に、小雪さん的要素(もしくはその反対要素)がぼわーっと広がってくる。その後、野良ガジラは空を飛ぶさんに会うことによって、こんどは、野良ガジラは空を飛ぶさん的なもの(もしくはその反対要素)がぼわーっと広がってくる。こういうふうに、意識のなかのいろいろな思考が人だのものだの事件だのに出会うことによって、それらに誘発されて、ぼわーっ、ぼわーっと絶えずぐつぐつしているのが、生命力のある細胞のような意識の状態なわけです。これを分裂的傾向とドゥルーズ=ガタリは言うらしい。
ところが、こういった本来分裂的傾向=多様体である人間が先ほどの、ツリー上のどこかの輪切りにされた中に入るとそこの価値観に洗脳されてしまって、すっかり思考が固定化し出られなくなってしまう。まさしく官僚だの会社だの大学だのといった組織に入り込んでそこの価値観に染まってしまって一歩も外に出られなくなってしまう。そうするとぐつぐついっていた細胞が固まってきてしまうんです。これを偏執的傾向(パラノイア)と呼ぶわけです。だからこんなことになったのでは、生命体のもつ生命力が奪われて身動きがとれなくなってしまう。
だからこそ、「点ではなく、線になれ」というのです。点というのがそのツリーの枝の輪切りです。そして線がリゾームです。いろいろなワッカを動き回って、いろいろな組織や人、事件に出会って自分の価値観を多様に保て、というわけです。
この線になる努力は相当なエネルギーを使います。80年代に言われたような感性のなんとかといった軽薄なものでは決してありえない。とても強い意志に基づかなければ、人間はリゾーム的運動体にはなれませんよね。だからそういう意味では、このリゾームを作り出すエネルギーこそはまさしく多様性を保ちつつ進化していくベルグソンのいうエランヴィタルみたいなものなのです。そういう意味で、僕はリゾームの中にベルグソン的な主意主義=生の哲学を読み取りました。
まあ、僕は、この「リゾーム」しか読んだことはないので、資本主義の分析だとか精神分析がどう関わるのか分かりませんが、こういった視点でもう一度読み直してみる必要があると思いますが、如何でしょう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
アンリ・ベルクソン 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
アンリ・ベルクソンのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31947人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 3位
- 一行で笑わせろ!
- 82525人