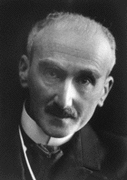第2回
(第4段落)ここは前の段落を受けて、相互浸透によって、諸要素が一点に統合してくるところに非常に単純なものが見て取れるというわけです。そして、この単純なものが、その哲学の核心なわけです。これは、概念や言語を越えたものであるので、その哲学者がこの核心を摑んで、概念や言語によって表現しようとすると、大変な困難を要し、表現自体も複雑化せざるを得なかったというわけです。ベルグソンは持続を表現するのに光のスペクトルの比喩を用いていますが、これを様々な色のタイルでできるだけ正確に再現しようとすると、もともとは連続的なものだから、タイルを可能な限り細かくして、多くのタイルを使おうとするでしょう。それと同じことを言っているわけです。そしてここで「直観」(intuition)という言葉が出てきますね。即ち直観とは、概念や言語を越えて、その向こう側にある単純なものを見ることなわけです。それにしても、quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire.(なにか単純なもの、無限に単純なもの、あまりにも単純なので、哲学者それを言い得ることが出来なかった。)とありますが、とても詩的な表現ですよね。ジャンケレヴィッチの美しい著書『仕事と日々・夢想と夜々』のある章名にそっくりこの言葉が採用されています。「そこで彼は生涯かたり続けたのだ・・・」という句も引用されます。そしてジャンケレヴィッチはこの無限に単純なものを薔薇に喩えて、次のように語ります。「約束されていた薔薇はここにある。やっと、ここにある。ところがこの薔薇は、私にとっては、同時に誠実な伴侶であり、私はこれを守り、隠し、そして、それにふさわしいものにならなければならない。絶え間なくそのとげを取り払う必要がある。その香りをかぐのを妨げ、その美しい色を妨げるものを絶え間なく取り除いてやらなければならないのだ。その度に、ふたたび始める必要がある。絶えず見つけ出し、絶えずまた見失う伴侶・・・・。」
(第5段落)さて、ここでまたとても重要なことばが出てきますね。即ちimageです。これは、「具体的な直観の単純性と抽象的複雑性の中間にある媒介的なあるイメージ」(une certaine image intermédiaire entre la simplicité de l'intuition concrète et la complexité des abstractions)です。この仏文は前にも出てきましたけど、la simplicitéとla complexitéがとても明確な対照をなしていますね。前者は、直観によって近づきえたという言語や概念を越えた何かですが、後者は、既に出来上がった概念や観念、もうすこし一般的に言うと言語のことです。我々が近づきえた単純なものは、imageとなって、我々の精神のなかに形成されるわけです。しかし、このimageは言語ではない。つまり単純性以下、言語以上のものですね。「それは捉えがたく消え去りやすいイメージですが、哲学者の心におそらくそれとは知られずに付きまとい、彼の思索の曲折を通して影のように従ってきたものです。」(image fuyante et évanouissante, qui hante, inaperçue peut-être, l'esprit du philosophe, qui le suit comme son ombre à travers les tours et détours de sa pensée)という表現も先ほどのジャンケレヴィッチの薔薇の喩えに対応した美しい表現ですね。
さて、ここでは、ふたつのことを指摘しておきましょう。?ここで言われている単純性の影のimageは、『物質と記憶』での「物質とはimageの総体である」と言ったときのいわゆる「イマージュ」とは違うものなのか?あるいはどのような関係にあるか?訳者の三輪氏はわざわざイメージという訳語を当てていますがこれは適切だと思います。実際に、ここでは心に思い浮かんだことといった意味合いに近いです。だがそれにしてもイマージュとは無関係ではない。僕もこの点について、今すぐにうまい説明ができないので、宿題ということにして、先を読みながら考えることにしておきましょう。?ここでいう、イメージの層というのは、僕達の知覚を構成している言語、概念、記号等(現象学の言葉を使うと「本質」)といった表面的な層のさらに下層のことを指しています。ベルグソンが、戦後フランスを中心にして流行した現代思想のように我々の意識や知覚のすべてを言語(langue)に還元する立場と鋭く対立していることがわかります。意識には言語や記号では汲み尽くせない何かがある、人間の発想の独創性はここから生じてくるのではないか、と言っているわけです。だから、記号や概念に頼るよりも、このイメージに頼れといっているわけです。
(第6段落)この段落はゆったり読めますね。先のイメージが否定の力を含んでおり、その源泉である直観をソクラテスのダイモニオンに喩えます。ソクラテスが行為をするときに、ダイモニオンの声は禁止という形で聞こえてきます。ベルグソンも直観をこのような内なる声としてとらえます。ある知識、命題、観念について、Impossible(ありえない)と否定的に判断するわけです。それにしてもなぜ否定なのか?これは、このイメージやそのもとである直観でとらえられるものというものが、既成の言語や観念の及ばない層に属するものだからです。だから哲学者は固形物である言語によって、もともとそういったものとは異質であるこのイメージを表わそうとするわけで、その際どうしてもこのイメージをゆがめてしまう。ただ、そうした概念や観念にしても、イメージに近いものと遠いものとがあるわけで、もとと似ても似つかないものは、きっぱりと拒絶されるわけです。これが否定の力なわけですね。だから、Plus tard, il pourra varier dans ce qu'il affirmera ; il ne variera guère dans ce qu'il nie. Et s'il varie dans ce qu'il affirme, ce sera encore en vertu de la puissance de négation immanente à l'intuition ou à son image.(肯定するものにおいては、意見を変えるかもしれないが、否定するものにおいてはほとんど意見を変えない。そして、肯定するものにおいて意見を変えるにしても、直観ないしはイメージに内在する否定の力によるものである。)と興味深いことを言っていますね。
さて、放談です。ベルグソンは、彼がここで言うとおり、その体系の中心は実に単純であり、生涯にわたって一つのことしか言わなかった哲学者であることは異論の余地がないでしょう。しかし、その他にベルグソンに匹敵するような哲学者がいたでしょうか?近代では、デカルトやルソーは明らかにこの類の天才ですね。またドイツではカントがそうです。しかし、少なくともベルグソンの時代についていえば、このようなひとつの単純な中心をもつ哲学を生んだ大物がもう一人います。即ちアランです。ベルグソンほど華麗な存在ではありませんし、その生き方もまったく対照的です。しかし、その哲学は、実に美しい体系をなしており、その中心に非常に明晰な単純性をもっています。しかもそこから多くの新しい発想が生じており、よく読んでみると、実存哲学だとか、記号論だとか、現代思想に通じるものがいろいろと出てくる。見ようによっては近代の哲学史をひっくり返すような革命性を確実にもっています。特に日本の思想界では、その著作の訳者も含めてそうなのですが、アランというと、人生論風な哲学者、モラリストでことさら独創的な体系をもっていないと評されていますが、とんでもない誤解で、ベルグソンとともに、フランスのみならずヨーロッパの同時代のどの哲学・思想をも凌駕しています。こうしたアランの思想の独創性、革命的側面は、アンドレ・モロアも言ったように、その主著Système des beaux-arts と Eléments de philosophieを調べればすぐにわかります。まさに、その哲学者の内側に身を置かない限り思想の正確な理解はできないというベルグソンの主張を見事に裏付けるよい例です。
【次回予習範囲】
第3回(8月14日(日))まで、以下のとおり読んでおいてください。
?Quadrige版:
始め:p121 16行目〜
終り:p123 21行目 la meme chose.まで。
?世界の名著版:
始め:p116 上段 19行目〜
終り:p118 上段 03行目「言ったはずです。」まで
(第4段落)ここは前の段落を受けて、相互浸透によって、諸要素が一点に統合してくるところに非常に単純なものが見て取れるというわけです。そして、この単純なものが、その哲学の核心なわけです。これは、概念や言語を越えたものであるので、その哲学者がこの核心を摑んで、概念や言語によって表現しようとすると、大変な困難を要し、表現自体も複雑化せざるを得なかったというわけです。ベルグソンは持続を表現するのに光のスペクトルの比喩を用いていますが、これを様々な色のタイルでできるだけ正確に再現しようとすると、もともとは連続的なものだから、タイルを可能な限り細かくして、多くのタイルを使おうとするでしょう。それと同じことを言っているわけです。そしてここで「直観」(intuition)という言葉が出てきますね。即ち直観とは、概念や言語を越えて、その向こう側にある単純なものを見ることなわけです。それにしても、quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire.(なにか単純なもの、無限に単純なもの、あまりにも単純なので、哲学者それを言い得ることが出来なかった。)とありますが、とても詩的な表現ですよね。ジャンケレヴィッチの美しい著書『仕事と日々・夢想と夜々』のある章名にそっくりこの言葉が採用されています。「そこで彼は生涯かたり続けたのだ・・・」という句も引用されます。そしてジャンケレヴィッチはこの無限に単純なものを薔薇に喩えて、次のように語ります。「約束されていた薔薇はここにある。やっと、ここにある。ところがこの薔薇は、私にとっては、同時に誠実な伴侶であり、私はこれを守り、隠し、そして、それにふさわしいものにならなければならない。絶え間なくそのとげを取り払う必要がある。その香りをかぐのを妨げ、その美しい色を妨げるものを絶え間なく取り除いてやらなければならないのだ。その度に、ふたたび始める必要がある。絶えず見つけ出し、絶えずまた見失う伴侶・・・・。」
(第5段落)さて、ここでまたとても重要なことばが出てきますね。即ちimageです。これは、「具体的な直観の単純性と抽象的複雑性の中間にある媒介的なあるイメージ」(une certaine image intermédiaire entre la simplicité de l'intuition concrète et la complexité des abstractions)です。この仏文は前にも出てきましたけど、la simplicitéとla complexitéがとても明確な対照をなしていますね。前者は、直観によって近づきえたという言語や概念を越えた何かですが、後者は、既に出来上がった概念や観念、もうすこし一般的に言うと言語のことです。我々が近づきえた単純なものは、imageとなって、我々の精神のなかに形成されるわけです。しかし、このimageは言語ではない。つまり単純性以下、言語以上のものですね。「それは捉えがたく消え去りやすいイメージですが、哲学者の心におそらくそれとは知られずに付きまとい、彼の思索の曲折を通して影のように従ってきたものです。」(image fuyante et évanouissante, qui hante, inaperçue peut-être, l'esprit du philosophe, qui le suit comme son ombre à travers les tours et détours de sa pensée)という表現も先ほどのジャンケレヴィッチの薔薇の喩えに対応した美しい表現ですね。
さて、ここでは、ふたつのことを指摘しておきましょう。?ここで言われている単純性の影のimageは、『物質と記憶』での「物質とはimageの総体である」と言ったときのいわゆる「イマージュ」とは違うものなのか?あるいはどのような関係にあるか?訳者の三輪氏はわざわざイメージという訳語を当てていますがこれは適切だと思います。実際に、ここでは心に思い浮かんだことといった意味合いに近いです。だがそれにしてもイマージュとは無関係ではない。僕もこの点について、今すぐにうまい説明ができないので、宿題ということにして、先を読みながら考えることにしておきましょう。?ここでいう、イメージの層というのは、僕達の知覚を構成している言語、概念、記号等(現象学の言葉を使うと「本質」)といった表面的な層のさらに下層のことを指しています。ベルグソンが、戦後フランスを中心にして流行した現代思想のように我々の意識や知覚のすべてを言語(langue)に還元する立場と鋭く対立していることがわかります。意識には言語や記号では汲み尽くせない何かがある、人間の発想の独創性はここから生じてくるのではないか、と言っているわけです。だから、記号や概念に頼るよりも、このイメージに頼れといっているわけです。
(第6段落)この段落はゆったり読めますね。先のイメージが否定の力を含んでおり、その源泉である直観をソクラテスのダイモニオンに喩えます。ソクラテスが行為をするときに、ダイモニオンの声は禁止という形で聞こえてきます。ベルグソンも直観をこのような内なる声としてとらえます。ある知識、命題、観念について、Impossible(ありえない)と否定的に判断するわけです。それにしてもなぜ否定なのか?これは、このイメージやそのもとである直観でとらえられるものというものが、既成の言語や観念の及ばない層に属するものだからです。だから哲学者は固形物である言語によって、もともとそういったものとは異質であるこのイメージを表わそうとするわけで、その際どうしてもこのイメージをゆがめてしまう。ただ、そうした概念や観念にしても、イメージに近いものと遠いものとがあるわけで、もとと似ても似つかないものは、きっぱりと拒絶されるわけです。これが否定の力なわけですね。だから、Plus tard, il pourra varier dans ce qu'il affirmera ; il ne variera guère dans ce qu'il nie. Et s'il varie dans ce qu'il affirme, ce sera encore en vertu de la puissance de négation immanente à l'intuition ou à son image.(肯定するものにおいては、意見を変えるかもしれないが、否定するものにおいてはほとんど意見を変えない。そして、肯定するものにおいて意見を変えるにしても、直観ないしはイメージに内在する否定の力によるものである。)と興味深いことを言っていますね。
さて、放談です。ベルグソンは、彼がここで言うとおり、その体系の中心は実に単純であり、生涯にわたって一つのことしか言わなかった哲学者であることは異論の余地がないでしょう。しかし、その他にベルグソンに匹敵するような哲学者がいたでしょうか?近代では、デカルトやルソーは明らかにこの類の天才ですね。またドイツではカントがそうです。しかし、少なくともベルグソンの時代についていえば、このようなひとつの単純な中心をもつ哲学を生んだ大物がもう一人います。即ちアランです。ベルグソンほど華麗な存在ではありませんし、その生き方もまったく対照的です。しかし、その哲学は、実に美しい体系をなしており、その中心に非常に明晰な単純性をもっています。しかもそこから多くの新しい発想が生じており、よく読んでみると、実存哲学だとか、記号論だとか、現代思想に通じるものがいろいろと出てくる。見ようによっては近代の哲学史をひっくり返すような革命性を確実にもっています。特に日本の思想界では、その著作の訳者も含めてそうなのですが、アランというと、人生論風な哲学者、モラリストでことさら独創的な体系をもっていないと評されていますが、とんでもない誤解で、ベルグソンとともに、フランスのみならずヨーロッパの同時代のどの哲学・思想をも凌駕しています。こうしたアランの思想の独創性、革命的側面は、アンドレ・モロアも言ったように、その主著Système des beaux-arts と Eléments de philosophieを調べればすぐにわかります。まさに、その哲学者の内側に身を置かない限り思想の正確な理解はできないというベルグソンの主張を見事に裏付けるよい例です。
【次回予習範囲】
第3回(8月14日(日))まで、以下のとおり読んでおいてください。
?Quadrige版:
始め:p121 16行目〜
終り:p123 21行目 la meme chose.まで。
?世界の名著版:
始め:p116 上段 19行目〜
終り:p118 上段 03行目「言ったはずです。」まで
|
|
|
|
コメント(7)
そらさん
ご旅行とのこと、どちらに行かれていましたか?僕は先月夏休みを消化してしまったので、もう休めません。(汗)
羨ましいです。
さて、ベルグソンはひとつのことしか語らなかった偉大な哲学者ですね。
それは、「時間と自由」(直接与件)で提示された「持続」が、カノンのような旋律を奏でて、「物質と記憶」、「創造的進化」、そして、「二源泉」へと引き継がれ壮大なシンフォニーへと発展しますね。最後になっても、持続の観念は失われることがありません。非常に単純なこの観念から多くの発想が引き出された観があります。
僕もこの哲学的直観を読みながら、ベルグソンの偉大さを再発見できたらと思っています。
よろしければ、そらさんがベルグソンのどんなところに関心をもっているかについてアップしてみてくださいね。
ご旅行とのこと、どちらに行かれていましたか?僕は先月夏休みを消化してしまったので、もう休めません。(汗)
羨ましいです。
さて、ベルグソンはひとつのことしか語らなかった偉大な哲学者ですね。
それは、「時間と自由」(直接与件)で提示された「持続」が、カノンのような旋律を奏でて、「物質と記憶」、「創造的進化」、そして、「二源泉」へと引き継がれ壮大なシンフォニーへと発展しますね。最後になっても、持続の観念は失われることがありません。非常に単純なこの観念から多くの発想が引き出された観があります。
僕もこの哲学的直観を読みながら、ベルグソンの偉大さを再発見できたらと思っています。
よろしければ、そらさんがベルグソンのどんなところに関心をもっているかについてアップしてみてくださいね。
青い鳥さん
ここでも調子にのって聞いてみたいことがいくつかあるのですが。
「否定の力」は、まずなにか強い確信のようなものがあるとき、あるいは常々、胎動のようなものとして己の奥深くになにかが宿っているようなとき、そのことを模して言い表わされた概念がはなはだ着心地が悪いような場合に「とんでもない」という言葉が口をついて出てくるのではないしょうか。
ようするに「そのようなものではないのだ」という強い否定は同時に確かなイメージをその人が持っていることの裏付けのようなものではないかと思うのですが、、、。
そういうことであれば誰にでもあるようなことだし、僕にもあるし、理解しやすいように思えるのですが、このように読むことは間違ってますか?
ここでも調子にのって聞いてみたいことがいくつかあるのですが。
「否定の力」は、まずなにか強い確信のようなものがあるとき、あるいは常々、胎動のようなものとして己の奥深くになにかが宿っているようなとき、そのことを模して言い表わされた概念がはなはだ着心地が悪いような場合に「とんでもない」という言葉が口をついて出てくるのではないしょうか。
ようするに「そのようなものではないのだ」という強い否定は同時に確かなイメージをその人が持っていることの裏付けのようなものではないかと思うのですが、、、。
そういうことであれば誰にでもあるようなことだし、僕にもあるし、理解しやすいように思えるのですが、このように読むことは間違ってますか?
soyogoさん
書き込みありがとうございます。
まずはこちらのほうから。
この文脈でベルグソンが言っている否定の力は、おっしゃるとおりだと思います。言葉や概念にならない、イメージを抱いていて、それをある固定化された概念や観念に置き換えるときの拒絶反応です。それが、Nonなんです。
ただ、この否定の力は、積極的なイメージを持たなくてもあるような気がします。このNonという声があがってくるのは、言語や記号、概念が及ばない分節化される以前の意識の層からです。だから、なんと表現していいか分からない心の状態のときがあると思う。それを言語化して、平板な言葉に当てはめられたときの拒絶反応なんかもこれに当たると思います。
書き込みありがとうございます。
まずはこちらのほうから。
この文脈でベルグソンが言っている否定の力は、おっしゃるとおりだと思います。言葉や概念にならない、イメージを抱いていて、それをある固定化された概念や観念に置き換えるときの拒絶反応です。それが、Nonなんです。
ただ、この否定の力は、積極的なイメージを持たなくてもあるような気がします。このNonという声があがってくるのは、言語や記号、概念が及ばない分節化される以前の意識の層からです。だから、なんと表現していいか分からない心の状態のときがあると思う。それを言語化して、平板な言葉に当てはめられたときの拒絶反応なんかもこれに当たると思います。
青い鳥さん
ありがとうございました。
僕はこの「否定の力」というものは、およそ人間が生き、なにかを探求するうえで誰でもがその内に宿すものではないのかなと思いました。
でも彼は「直観のこの否定の力は全く独特のものだ」と言っていますね。それでなにかもっと違う意味で使われている言葉なのかなと思って、聞いてみたのです。
青い鳥さんの考えを拝読し、よく考えてみれば、誰でもが直感的になにかを洞察することはあるのだろうから、この「独特さ」は直観というものの働きの一側面として捉えればいいわけですね。「独特さ」という言葉に意識過剰になって読み違えていたように思いました。
その後、この「独特さ」について考えていたのですが、
「何を肯定するかにおいて変節があっても、なにを否定するかにおいては変わらないし、肯定するものを変える場合もその源である直観やそのイメージに宿る否定の力による。」というところについて。
まず「何かを直観した」ということが最初にあるように思えます。そしてそれはある方向を指し示している。その方向に導かれてゆく過程で、否定の力がはたらき、そのはたらきによって彼は時に自身の外側に出ようとも、再び直観、即ち彼自身に帰ることが出来る。
ようするに、この「否定の力」は「導く力」でもあるような気がしましたし、そういう意味で「独特」なのかなと思いました。
でもまた的はずれなことを言ってるのかも、、、。
ありがとうございました。
僕はこの「否定の力」というものは、およそ人間が生き、なにかを探求するうえで誰でもがその内に宿すものではないのかなと思いました。
でも彼は「直観のこの否定の力は全く独特のものだ」と言っていますね。それでなにかもっと違う意味で使われている言葉なのかなと思って、聞いてみたのです。
青い鳥さんの考えを拝読し、よく考えてみれば、誰でもが直感的になにかを洞察することはあるのだろうから、この「独特さ」は直観というものの働きの一側面として捉えればいいわけですね。「独特さ」という言葉に意識過剰になって読み違えていたように思いました。
その後、この「独特さ」について考えていたのですが、
「何を肯定するかにおいて変節があっても、なにを否定するかにおいては変わらないし、肯定するものを変える場合もその源である直観やそのイメージに宿る否定の力による。」というところについて。
まず「何かを直観した」ということが最初にあるように思えます。そしてそれはある方向を指し示している。その方向に導かれてゆく過程で、否定の力がはたらき、そのはたらきによって彼は時に自身の外側に出ようとも、再び直観、即ち彼自身に帰ることが出来る。
ようするに、この「否定の力」は「導く力」でもあるような気がしましたし、そういう意味で「独特」なのかなと思いました。
でもまた的はずれなことを言ってるのかも、、、。
青いとりさん
ありがとうございました。「積極的ではないケースもある」という意味がよくわかりました。僕は「直観」というものをなにか特殊な状態として考えすぎていました。誰にでもそういった、確たるイメージを抱くことはあるわけですね。ただそのような直観を方法として積極的に活用するような哲学や宗教においてそれはもっと深められた状態へと向かうんですね。
哲人が直観したものの落とす影=媒介的イメージ、
このイメージは各々がこの哲人の直観に触れようと努めるときにその各々のなかに形成されるイメージととってもいいのでしょうか?それでそのイメージは同じ直観に触れようとしているのだからそれぞれ形は違っても共有されるイメージとなっているようなかんじです。
哲学者にそれとは知られずにつきまとうこの影は、本人ではなく我々から見てはじめて見えるようなもののように思えたのですが。
「この姿のまねようと努めるとき、この姿のなかに入ろうと努めるとき、哲人がなにを直観したかがわかってくる」
ここの表現はとても示唆に満ちているように感じたのですが、逆光の物体の投げかける影のなかにはいったとき、それまではシルエットとしてしか見えなかったものが、おぼろげにその物体のデイテールが見えてくるようなイメージを持ちました。
ありがとうございました。「積極的ではないケースもある」という意味がよくわかりました。僕は「直観」というものをなにか特殊な状態として考えすぎていました。誰にでもそういった、確たるイメージを抱くことはあるわけですね。ただそのような直観を方法として積極的に活用するような哲学や宗教においてそれはもっと深められた状態へと向かうんですね。
哲人が直観したものの落とす影=媒介的イメージ、
このイメージは各々がこの哲人の直観に触れようと努めるときにその各々のなかに形成されるイメージととってもいいのでしょうか?それでそのイメージは同じ直観に触れようとしているのだからそれぞれ形は違っても共有されるイメージとなっているようなかんじです。
哲学者にそれとは知られずにつきまとうこの影は、本人ではなく我々から見てはじめて見えるようなもののように思えたのですが。
「この姿のまねようと努めるとき、この姿のなかに入ろうと努めるとき、哲人がなにを直観したかがわかってくる」
ここの表現はとても示唆に満ちているように感じたのですが、逆光の物体の投げかける影のなかにはいったとき、それまではシルエットとしてしか見えなかったものが、おぼろげにその物体のデイテールが見えてくるようなイメージを持ちました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
アンリ・ベルクソン 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
アンリ・ベルクソンのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90059人
- 2位
- 酒好き
- 170694人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208291人