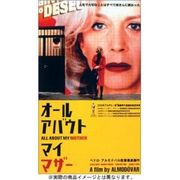人斬り (1969)
監督: 五社英雄
脚本: 橋本忍
撮影: 森田富士郎
音楽: 佐藤勝
出演:
勝新太郎 岡田以蔵
仲代達矢 武市半平太
石原裕次郎 坂本竜馬
三島由紀夫 田中新兵衛
倍賞美津子 おみの
新條多久美 姉小路綾姫
仲谷昇 姉小路公知
下元勉 松田治之助
山本圭 皆川一郎
伊藤孝雄 天野透
賀原夏子 おたき
田中邦衛 六角牢の役人
山内明 勝海舟
清水彰 井上佐一郎
滝田祐介 平松外記
東大二郎 両替屋の番頭
宮本曠二郎 渡辺金三郎
伊吹総太朗 本田精一郎
藤森達雄 北崎進
黒木現 工藤
中谷一郎 京都所司代与力
伊達岳志 京都市中見廻組役人
北村英三 横川帯刀
波多野憲 久坂玄瑞
福山錬 宮部鼎蔵
新田昌玄 伊地知三左衛門
萩本欽一 牢名主
坂上二郎 熊髭
辰巳柳太郎 吉田東洋
幕末時代に実在した土佐藩士の岡田以蔵を描く時代劇。橋本忍脚本、五社英雄監督。「人斬り以蔵」と呼ばれた彼の半生を、勝新太郎がダイナミックかつエネルギッシュに熱演。共演陣も仲代達矢、石原裕次郎、倍賞美津子と豪華な顔ぶれが集結。三島由紀夫が田中新兵衛役で出演し、緊迫感あふれる切腹シーンを披露した。
身分制のために出世が見込めない世の中で、くすぶった生活を続けていた青年岡田以蔵は、ある日、土佐勤王党首の武市半平太より吉田東洋暗殺視察の命を受ける。上洛後、半平太の手足となり数々の破壊・殺戮の実行役となった以蔵は坂本龍馬と出会う。龍馬は以蔵に人斬りをやめるよう忠告するのだが…。
以上が映画データベースの記述である。 You Tube を眺めていてひょんなことから本作が10分から15分ほどに分けられて幾つも載せられているのを順番に観た。 還暦を過ぎた年代にはチャンバラ、戦争、西部劇がテレビ勃興期の主なものだった。 その中でもそれまでの歌舞伎や演劇の舞台でみられたチャンバラからいくらか真に迫る殺陣を我々のまえに見せたのが「三匹の侍」シリーズで、そのなかでは刀の重み、振り回す様子、その音と刀と刀が合わさるときの火花までが「リアル」に表現され簡単にはバッサバサとこどもたちのチャンバラごっこのように人は斬られないというようなことが示され子供心に新しい殺陣を観て息をのんだことを覚えている。 そしてそのときの監督の名前が心に刻まれていてそれが本作でまた呼び起こされたのだった。 クリント・イーストウッドの銃器の取り扱いに対するこだわりのようなものが五社にはあるのだろうか。 岡田以蔵の野性的な剣法を強調するには大振りの刀の殺陣ではときにはチャンバラじみた動きがみられるものの、三島演じる田中新兵衛の動きには本人自身が「真」を追求するうるささが表れているようでその一挙手に見入った。 三島は自身、ボディービル、居合い、剣道を研鑽し、自身の軍隊を持ち、本作の翌年クーデターを画策し、そのなかでシナリオどおりの割腹自殺で果てるということを行っているから本作での割腹シーンには普通の役者以上の思いがあったにちがいないしそれが観るものにも伝わってくるようだ。
三島のこのような「予行演習」的なパーフォーマンスは本作にとどまらず、二二六事件の将校を題材にした、自身が制作した「憂国」での切腹シーンがその極まったものだろうが本作ではそれに加えて薩摩の野太い太刀捌きが襲撃の際の三島の頭巾姿、鍛えられた上腕から肩にかけての裸の上半身と共にきわめて印象的である。
制作当時から本作の名前は聞いていたもののどのような話か知らないまま今日に至り本作を観始め、そのキャストの豪華さに驚いた。 そして制作に勝プロダクションの名前があり、石原プロの名前が無いこととからもそうすると誰が主役であるのか想像がついた。 我々にはチャンバラの座頭市の勝新太郎である。 しかし本作では我々が観ていた勝に若さとギラギラするものを加えた真迫の演技に驚かされる。 例えば眼を大きく広げて前を見据える表情、煩悶する姿には本作の主役を張るに相応しいものと写るだろう。
新国劇の辰巳柳太郎は島田正吾とともに我々の年代より上のものたちが実際に体験し彼らの価値を充分認識しているのだろうが本作での辰巳の姿は舞台の要素を映画のリアルな実戦に昇華させ定着したものとしてその殺陣は忘れられないものとなる。 雨のなかでの襲撃シーンでまだ人を斬ったことのない岡田以蔵が初めて暗殺の場を観るシーンである。 これは本作中でも重要なものとなってとりわけ襲撃を受けるものに焦点をおいている例として辰巳柳太郎の名を後世に残すものである。
チャンバラや殺陣は人が人を殺し、殺されるという話をどう見せるか、というところに重点を置いていて、それはどれだけ観るものをその「真」に近づけようとするか、また様式の抽象性で話をうまく納得させようとするかとの違いがあるようで、それがそれぞれ「真」からの距離とベクトルを示しているように思われる。 歴史の「真」に近づくには数多の検証が必要となり、それをジャーナリズム「的」に文芸講談として成功したのが司馬遼太郎であり、本作は司馬の原作に則っていると示されている。 文芸講談であるから「講釈師見てきたような嘘をいい」というような要素も無くは無いにちがいない。 今の世の中、ネットの世界でここに登場する人物群、その時代のことを検索すると様々な「事実」が本作での「事実」と齟齬をきたしているのをみるようで、それは原作から半世紀以上も経っているからその間に明らかになった新事実との齟齬であるとすると一応の納得はするものの、それでも我々は本作の講談により親和性をみるようだ。 それが講談の講談たる所以だろうし映画というものだろう。
仲代達也は自分にとっては、五味川純平の原作を読みその後観た「人間の条件 (1959)」の梶である。 けれどその後の諸作の印象では悪を演じる時の表情とぬめりをおびた眼の輝きが不気味で素晴らしく、本作でもそれが遺憾なく表現され、仲代の鼻音を微かに含んだような声で台詞をゆっくり喋るときにはことさら本作に講談の凄みを醸しだす効果を作り出しているようにみえる。 新国劇の月形半平太が本作講談での武市半平太こと武市瑞山となりその違いには新国劇に親しんできたものたちはまるで振り子の両端をみるような驚きを感じるのに違いない。
これも制作時の時代を示すものなのだろうか、長閑なアメリカ西部劇のBGMがシリアスな勝の演技の後ろに流れるのと石原裕次郎演じる坂本竜馬の髪型にはその他の要素には満足をしていただけにいたく失望した。
監督: 五社英雄
脚本: 橋本忍
撮影: 森田富士郎
音楽: 佐藤勝
出演:
勝新太郎 岡田以蔵
仲代達矢 武市半平太
石原裕次郎 坂本竜馬
三島由紀夫 田中新兵衛
倍賞美津子 おみの
新條多久美 姉小路綾姫
仲谷昇 姉小路公知
下元勉 松田治之助
山本圭 皆川一郎
伊藤孝雄 天野透
賀原夏子 おたき
田中邦衛 六角牢の役人
山内明 勝海舟
清水彰 井上佐一郎
滝田祐介 平松外記
東大二郎 両替屋の番頭
宮本曠二郎 渡辺金三郎
伊吹総太朗 本田精一郎
藤森達雄 北崎進
黒木現 工藤
中谷一郎 京都所司代与力
伊達岳志 京都市中見廻組役人
北村英三 横川帯刀
波多野憲 久坂玄瑞
福山錬 宮部鼎蔵
新田昌玄 伊地知三左衛門
萩本欽一 牢名主
坂上二郎 熊髭
辰巳柳太郎 吉田東洋
幕末時代に実在した土佐藩士の岡田以蔵を描く時代劇。橋本忍脚本、五社英雄監督。「人斬り以蔵」と呼ばれた彼の半生を、勝新太郎がダイナミックかつエネルギッシュに熱演。共演陣も仲代達矢、石原裕次郎、倍賞美津子と豪華な顔ぶれが集結。三島由紀夫が田中新兵衛役で出演し、緊迫感あふれる切腹シーンを披露した。
身分制のために出世が見込めない世の中で、くすぶった生活を続けていた青年岡田以蔵は、ある日、土佐勤王党首の武市半平太より吉田東洋暗殺視察の命を受ける。上洛後、半平太の手足となり数々の破壊・殺戮の実行役となった以蔵は坂本龍馬と出会う。龍馬は以蔵に人斬りをやめるよう忠告するのだが…。
以上が映画データベースの記述である。 You Tube を眺めていてひょんなことから本作が10分から15分ほどに分けられて幾つも載せられているのを順番に観た。 還暦を過ぎた年代にはチャンバラ、戦争、西部劇がテレビ勃興期の主なものだった。 その中でもそれまでの歌舞伎や演劇の舞台でみられたチャンバラからいくらか真に迫る殺陣を我々のまえに見せたのが「三匹の侍」シリーズで、そのなかでは刀の重み、振り回す様子、その音と刀と刀が合わさるときの火花までが「リアル」に表現され簡単にはバッサバサとこどもたちのチャンバラごっこのように人は斬られないというようなことが示され子供心に新しい殺陣を観て息をのんだことを覚えている。 そしてそのときの監督の名前が心に刻まれていてそれが本作でまた呼び起こされたのだった。 クリント・イーストウッドの銃器の取り扱いに対するこだわりのようなものが五社にはあるのだろうか。 岡田以蔵の野性的な剣法を強調するには大振りの刀の殺陣ではときにはチャンバラじみた動きがみられるものの、三島演じる田中新兵衛の動きには本人自身が「真」を追求するうるささが表れているようでその一挙手に見入った。 三島は自身、ボディービル、居合い、剣道を研鑽し、自身の軍隊を持ち、本作の翌年クーデターを画策し、そのなかでシナリオどおりの割腹自殺で果てるということを行っているから本作での割腹シーンには普通の役者以上の思いがあったにちがいないしそれが観るものにも伝わってくるようだ。
三島のこのような「予行演習」的なパーフォーマンスは本作にとどまらず、二二六事件の将校を題材にした、自身が制作した「憂国」での切腹シーンがその極まったものだろうが本作ではそれに加えて薩摩の野太い太刀捌きが襲撃の際の三島の頭巾姿、鍛えられた上腕から肩にかけての裸の上半身と共にきわめて印象的である。
制作当時から本作の名前は聞いていたもののどのような話か知らないまま今日に至り本作を観始め、そのキャストの豪華さに驚いた。 そして制作に勝プロダクションの名前があり、石原プロの名前が無いこととからもそうすると誰が主役であるのか想像がついた。 我々にはチャンバラの座頭市の勝新太郎である。 しかし本作では我々が観ていた勝に若さとギラギラするものを加えた真迫の演技に驚かされる。 例えば眼を大きく広げて前を見据える表情、煩悶する姿には本作の主役を張るに相応しいものと写るだろう。
新国劇の辰巳柳太郎は島田正吾とともに我々の年代より上のものたちが実際に体験し彼らの価値を充分認識しているのだろうが本作での辰巳の姿は舞台の要素を映画のリアルな実戦に昇華させ定着したものとしてその殺陣は忘れられないものとなる。 雨のなかでの襲撃シーンでまだ人を斬ったことのない岡田以蔵が初めて暗殺の場を観るシーンである。 これは本作中でも重要なものとなってとりわけ襲撃を受けるものに焦点をおいている例として辰巳柳太郎の名を後世に残すものである。
チャンバラや殺陣は人が人を殺し、殺されるという話をどう見せるか、というところに重点を置いていて、それはどれだけ観るものをその「真」に近づけようとするか、また様式の抽象性で話をうまく納得させようとするかとの違いがあるようで、それがそれぞれ「真」からの距離とベクトルを示しているように思われる。 歴史の「真」に近づくには数多の検証が必要となり、それをジャーナリズム「的」に文芸講談として成功したのが司馬遼太郎であり、本作は司馬の原作に則っていると示されている。 文芸講談であるから「講釈師見てきたような嘘をいい」というような要素も無くは無いにちがいない。 今の世の中、ネットの世界でここに登場する人物群、その時代のことを検索すると様々な「事実」が本作での「事実」と齟齬をきたしているのをみるようで、それは原作から半世紀以上も経っているからその間に明らかになった新事実との齟齬であるとすると一応の納得はするものの、それでも我々は本作の講談により親和性をみるようだ。 それが講談の講談たる所以だろうし映画というものだろう。
仲代達也は自分にとっては、五味川純平の原作を読みその後観た「人間の条件 (1959)」の梶である。 けれどその後の諸作の印象では悪を演じる時の表情とぬめりをおびた眼の輝きが不気味で素晴らしく、本作でもそれが遺憾なく表現され、仲代の鼻音を微かに含んだような声で台詞をゆっくり喋るときにはことさら本作に講談の凄みを醸しだす効果を作り出しているようにみえる。 新国劇の月形半平太が本作講談での武市半平太こと武市瑞山となりその違いには新国劇に親しんできたものたちはまるで振り子の両端をみるような驚きを感じるのに違いない。
これも制作時の時代を示すものなのだろうか、長閑なアメリカ西部劇のBGMがシリアスな勝の演技の後ろに流れるのと石原裕次郎演じる坂本竜馬の髪型にはその他の要素には満足をしていただけにいたく失望した。
|
|
|
|
|
|
|
|
その映画&小説を見たくなる論評 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
その映画&小説を見たくなる論評のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90067人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208325人
- 3位
- 酒好き
- 170697人