「もしも正義それ自体というようなものが(中略)存在するとしたら、それを脱構築することはできない。同様に、脱構築それ自体というようなものが存在するとしたら、それを脱構築できない。脱構築は正義なのである。」(デリダ「法の力」)
驚くべきコメントですが、みなさんどう思われますか?
脱構築はXであるというタイプのあらゆる文は「アプリオリに適切でなく」「少なくとも偽である」(「プシケー」からの引用)
完全に矛盾する二つのコメント。
図式化すれば、脱構築=正義で、両方とも脱構築不可能!
私の感想は、デリダも人の子であり、脱構築を価値の高いものとして規定し、脱構築に批判的な論敵から身をまもる必要があったということ。
さらに脱構築は切れ味鋭いブーメランであり、脱構築それ自身も、脱構築によって傷をうける可能性があること。その両方を防ぐ必要があったのではないか?正義=脱構築の等置はまさに脱構築自身とデリダ本人を守る鎧であるということです。
ブーメランは別名「自己言及性」。
脱構築はエクリチュール一般を対象にしているため、自身の著作や主張も対象に入ってしまう。
さらにはデリダ本人が大事にしている価値観さえも。脱構築の守備範囲を限定し、自身の著作や「正義」は対象外としないと何も論じられない。
そのような状況にデリダ自身が追い込まれた証ではないかと思います。
上記のデリダのコメントは「冗談言うな」で済ますには惜しいとおもいます。さらに深い意味が汲み取れるとおもいます。みなさんのご意見お待ちしてます。
驚くべきコメントですが、みなさんどう思われますか?
脱構築はXであるというタイプのあらゆる文は「アプリオリに適切でなく」「少なくとも偽である」(「プシケー」からの引用)
完全に矛盾する二つのコメント。
図式化すれば、脱構築=正義で、両方とも脱構築不可能!
私の感想は、デリダも人の子であり、脱構築を価値の高いものとして規定し、脱構築に批判的な論敵から身をまもる必要があったということ。
さらに脱構築は切れ味鋭いブーメランであり、脱構築それ自身も、脱構築によって傷をうける可能性があること。その両方を防ぐ必要があったのではないか?正義=脱構築の等置はまさに脱構築自身とデリダ本人を守る鎧であるということです。
ブーメランは別名「自己言及性」。
脱構築はエクリチュール一般を対象にしているため、自身の著作や主張も対象に入ってしまう。
さらにはデリダ本人が大事にしている価値観さえも。脱構築の守備範囲を限定し、自身の著作や「正義」は対象外としないと何も論じられない。
そのような状況にデリダ自身が追い込まれた証ではないかと思います。
上記のデリダのコメントは「冗談言うな」で済ますには惜しいとおもいます。さらに深い意味が汲み取れるとおもいます。みなさんのご意見お待ちしてます。
|
|
|
|
コメント(18)
コメントが遅れてすいません。
誰?さん、コメントありがとうございます。
脱構築が我々にもたらす利益があるとすれば、次のようなものがあると思います。
それは社会正義実現のエンジンになるのかもしれません。
1、少数意見の尊重、議会制民主主義における野党の存在の保障
理由:同一の社会システムや法律から発生する<脱構築的意味の戯れ>が、多様な解釈と価値観を保障するから
2、被告人の冤罪被害の可能性を常に考慮すること
理由:決定不可能性や、証拠、動機に対する解釈の多様性から、裁判所の判決には<誤り>がつきものであり、常に冤罪被害がありうる。脱構築がその理論的基礎になる。
しかしながら、以下の領域には脱構築の適用に対し慎重になるべきだとおもいます。
1、数学領域。例:二進数の世界での1+1=2 脱構築理論ではこの等式は成立しないかもしれないが、哲学者はそのような領域の存在を示し、説明することができるのか?
2、物理学の領域。相対性理論の定数は定数でない(デリダ)。驚くべきコメントですが、ナンセンスと馬鹿にされないためには、時間とともに定数が変化するのか、異なる空間で定数に違いが生じるのか、そして定数を変数にして整合性のある理論構築が可能で、実験結果との整合性が確保できるのか?
そのような疑問に対しデリダに説明責任が発生しています。(おそら生前のデリダとっては回答不能でしょう)
3、日常生活の領域。「今から福島に行ってくる」(ハイパーレスキュー隊長の妻へのメール)
このメールは脱構築可能だが、その必要性を全く感じない。
どうでしょうか?皆さんの意見お待ちしてます。
誰?さん、コメントありがとうございます。
脱構築が我々にもたらす利益があるとすれば、次のようなものがあると思います。
それは社会正義実現のエンジンになるのかもしれません。
1、少数意見の尊重、議会制民主主義における野党の存在の保障
理由:同一の社会システムや法律から発生する<脱構築的意味の戯れ>が、多様な解釈と価値観を保障するから
2、被告人の冤罪被害の可能性を常に考慮すること
理由:決定不可能性や、証拠、動機に対する解釈の多様性から、裁判所の判決には<誤り>がつきものであり、常に冤罪被害がありうる。脱構築がその理論的基礎になる。
しかしながら、以下の領域には脱構築の適用に対し慎重になるべきだとおもいます。
1、数学領域。例:二進数の世界での1+1=2 脱構築理論ではこの等式は成立しないかもしれないが、哲学者はそのような領域の存在を示し、説明することができるのか?
2、物理学の領域。相対性理論の定数は定数でない(デリダ)。驚くべきコメントですが、ナンセンスと馬鹿にされないためには、時間とともに定数が変化するのか、異なる空間で定数に違いが生じるのか、そして定数を変数にして整合性のある理論構築が可能で、実験結果との整合性が確保できるのか?
そのような疑問に対しデリダに説明責任が発生しています。(おそら生前のデリダとっては回答不能でしょう)
3、日常生活の領域。「今から福島に行ってくる」(ハイパーレスキュー隊長の妻へのメール)
このメールは脱構築可能だが、その必要性を全く感じない。
どうでしょうか?皆さんの意見お待ちしてます。
スーダマさんコメントありがとうございます。
脱構築の正義宣言に対する、違和感には次の二つの側面があると思います。
1、論理的側面
これはエクリチュール一般を対象にしている脱構築が、もし適用に際し領域限定するのであれば、そしてそれが脱構築理論自体への適用時であるならば、その根拠が示される必要があると思います。
しかしデリダは唐突に正義宣言し、かつ脱構築理論は脱構築不可能とコメントするだけで、過去のデリダ自身のコメント(脱構築=Xは常に誤り)との整合性については無頓着です。
2、価値論的側面
こちらは分かりやすいとおもいます(笑)
つまり、自分自身に対する正義宣言の不自然さです。「俺は正義だ」に対する違和感。ウルトラマンは正義のヒーローですが、ウルトラマン自身が正義宣言してかっこいいでしょうか?
ただし、特定のイデオロギーに支配された国家や専制君主、さらにはスーパーパワーを持つ一部の国はしばしば自ら正義であることを主張したがります。
正義とは自らが宣言するものではなく、国民や市民の大多数が「正しい」と判断する何かであって、しかも長い歴史の積み重ねがあるものでなくてはならないでしょう。例えば生命や財産の尊重、基本的人権の尊重などです。
一般市民にとって難解で、歴史の浅い脱構築にその資格があるのでしょうか?
脱構築に辛口のコメントばかりで申し訳ないですが、みなさんのコメントお待ちしてます。
脱構築の正義宣言に対する、違和感には次の二つの側面があると思います。
1、論理的側面
これはエクリチュール一般を対象にしている脱構築が、もし適用に際し領域限定するのであれば、そしてそれが脱構築理論自体への適用時であるならば、その根拠が示される必要があると思います。
しかしデリダは唐突に正義宣言し、かつ脱構築理論は脱構築不可能とコメントするだけで、過去のデリダ自身のコメント(脱構築=Xは常に誤り)との整合性については無頓着です。
2、価値論的側面
こちらは分かりやすいとおもいます(笑)
つまり、自分自身に対する正義宣言の不自然さです。「俺は正義だ」に対する違和感。ウルトラマンは正義のヒーローですが、ウルトラマン自身が正義宣言してかっこいいでしょうか?
ただし、特定のイデオロギーに支配された国家や専制君主、さらにはスーパーパワーを持つ一部の国はしばしば自ら正義であることを主張したがります。
正義とは自らが宣言するものではなく、国民や市民の大多数が「正しい」と判断する何かであって、しかも長い歴史の積み重ねがあるものでなくてはならないでしょう。例えば生命や財産の尊重、基本的人権の尊重などです。
一般市民にとって難解で、歴史の浅い脱構築にその資格があるのでしょうか?
脱構築に辛口のコメントばかりで申し訳ないですが、みなさんのコメントお待ちしてます。
『脱構築理論自体』と書いてありますが、まず脱構築を「理論」と考えるのが不適切だと思われます。
脱構築は常に、何らかの形で基礎付けられた言説体系に対する、基礎の見直し(破壊と創造)の批評的作業であって、その「理論」なるものは存在しません。法体系には法体系の「脱構築」の仕方があるし、科学には科学の「脱構築」があります。その意味で、「脱構築理論」というもの、つまり『脱構築それ自体』なるものは存在しません。
「脱構築それ自体」は存在しませんが、その基礎の見直し作業の共通性を「脱構築」と名づけて、その営為それ自体の「基礎を見直す」というのは、論理的に不可能です。それは「批判的」作業であって、別の基礎に新たな体系を作るような試みではないからです。
理論体系として存在しないものを「脱構築」するのは不可能です。だから「脱構築はXである」という文が不適切である、という話になります。
全ての言説体系は言語の性格に依存して成立しており、その根本に「差異」への志向性を持っています。数学や科学のような厳密に思われる言説体系とて例外ではなく、それは言語によって構成された言説の集合です。その基礎性が見直される可能性を絶対的に秘めていること(これはその時点での言説体系が、かなり真実で思われる、という事とは別の問題です)は、科学や数学が『閉じた体系』として成立しえないとうゲーデルの証明によってなされました。また、言語体系の科学言説の変更可能性については、クワイン等の考察を参考にすべきだと思われます。
そもそも「法体系」というものが、その制定した国の想定する「人間」を基準に構成されてますが、概ねこれは「男」とか「白人」だとか、「妻帯者」「多数派」等の様々な性格を『隠して』前提にしていました。その隠れた前提を洗い出すのが「脱構築」だといえますが、このような「隠された一般性」はその背後に少数派を抑圧する契機を持ってます。
この隠れた抑圧性を洗い出しうる点で、『脱構築は正義である』という言葉が出てくるのではないでしょうか。言説のこのような「権力性」は、何も法体系に限った話ではありません。学問においてしかりです。
「脱構築」というものを「守る」必要はまったくありません。「脱構築理論」なるものは存在しないからです。あるのは、それぞれの領域にある隠れた抑圧性への批判、です。つまりデリダの言う「正義」とは、「正義=X」という風に定義されるものではなく、逆説的に「X=正当」と定義的に振舞う言説体系に対する、終わりなき批判作業である、という事だと思います。
脱構築は常に、何らかの形で基礎付けられた言説体系に対する、基礎の見直し(破壊と創造)の批評的作業であって、その「理論」なるものは存在しません。法体系には法体系の「脱構築」の仕方があるし、科学には科学の「脱構築」があります。その意味で、「脱構築理論」というもの、つまり『脱構築それ自体』なるものは存在しません。
「脱構築それ自体」は存在しませんが、その基礎の見直し作業の共通性を「脱構築」と名づけて、その営為それ自体の「基礎を見直す」というのは、論理的に不可能です。それは「批判的」作業であって、別の基礎に新たな体系を作るような試みではないからです。
理論体系として存在しないものを「脱構築」するのは不可能です。だから「脱構築はXである」という文が不適切である、という話になります。
全ての言説体系は言語の性格に依存して成立しており、その根本に「差異」への志向性を持っています。数学や科学のような厳密に思われる言説体系とて例外ではなく、それは言語によって構成された言説の集合です。その基礎性が見直される可能性を絶対的に秘めていること(これはその時点での言説体系が、かなり真実で思われる、という事とは別の問題です)は、科学や数学が『閉じた体系』として成立しえないとうゲーデルの証明によってなされました。また、言語体系の科学言説の変更可能性については、クワイン等の考察を参考にすべきだと思われます。
そもそも「法体系」というものが、その制定した国の想定する「人間」を基準に構成されてますが、概ねこれは「男」とか「白人」だとか、「妻帯者」「多数派」等の様々な性格を『隠して』前提にしていました。その隠れた前提を洗い出すのが「脱構築」だといえますが、このような「隠された一般性」はその背後に少数派を抑圧する契機を持ってます。
この隠れた抑圧性を洗い出しうる点で、『脱構築は正義である』という言葉が出てくるのではないでしょうか。言説のこのような「権力性」は、何も法体系に限った話ではありません。学問においてしかりです。
「脱構築」というものを「守る」必要はまったくありません。「脱構築理論」なるものは存在しないからです。あるのは、それぞれの領域にある隠れた抑圧性への批判、です。つまりデリダの言う「正義」とは、「正義=X」という風に定義されるものではなく、逆説的に「X=正当」と定義的に振舞う言説体系に対する、終わりなき批判作業である、という事だと思います。
ハルカさんコメントありがとうございます。
いくつかのテーマがあり、スペースの関係上全部には答えられないので最も重要なことのみコメントさせてください(笑)
それはゲーデルの「不完全性定理」です。
理由はデリダのみならず、ポストモダンの思想家のよりどころになっている可能性が高いからです。
ちょっと頑張って不完全性定理の論文(岩波文庫)にアタックしてみましょう。 不完全性定理は、数ページの導入部である第一部と、第一部の厳密な実行である第二部以降からなっています。導入部のみなら辛うじて読めますし、論文全体のエッセンスを汲み取れます。
非常に面白いのはゲーデルは超数学(数学基礎論)自体を表現している、論理記号(∀、≡など)を自然数に置換し、「論理式」(例えば証明式)自体を自然数の有限列にしてしまいます。そうすることで、超数学的な命題を、数学的命題に置き換えてしまう。
そして自己言及的(自己否定的)命題を一つ作り出し、決定不可能なことを証明しようとします。
つまりゲーデルが証明したのはあくまで「自己言及的」命題の決定不可能性のみであり、形式系内部の全ての命題が「決定不可能」であるとは言っていません。
(例えば、「クレタ人が「クレタ人は嘘つきだ」と言った」というような命題)
さらには、
「ゲーデルは絶対的決定不可能性になんら意味を認めていない、すなわち問題になるのは常に相対的決定不可能性に限定される」、
「ゲーデル命題はその命題が関わるシステムの中では決定不可能であるが、より強いシステムでなら決定可能である」(アナロジーの罠、ジャック・ブーブレス)
つまり、
ある形式系では決定不可能でも、新たに公理を追加すれば証明可能あるということ。 (ただしそのようなさらに強いシステムの中でも決定不能な命題が出てきてしまい、いたちごっこであるということ)
そして決定不可能なゲーデル命題とは具体的になんでしょうか?
またここで誤解がある気がします。数学的命題全体、日常言語で構成された言説全体を指しているのではありません。
それは実際のところ非常に限られていて、上記の自己言及的命題や、1977年以降に一部の研究者が発表した組み合わせ論の定理があるようです。(ゲーデル 不完全性定理、岩波文庫)
つまり現状の数学の領域では、ほとんど全ての命題に関して真偽の決定が可能である、ということになります。
もちろんクレイ研究所の発表したミレニアム問題のように未解決問題はたくさんありますが。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%A0%E6%87%B8%E8%B3%9E%E5%95%8F%E9%A1%8C
もし本当に数学領域に「脱構築」が適応可能なら、
フェルマーの最終定理が「フェルマー予想」に逆戻りする可能性があるということになります(笑)
そして「不完全性定理」も同じく定理でなくなる可能性があります。
さらに困ったことに、等式の羅列である数学証明図は、個々の等式のパラドキシカルな意味の複数性により 数学的証明自体が無効になる。そのような事態の発生が想定されます。
中途半端にゲーデルの解説書を読んでいた私も以前はかなり誤解していました(笑) 以上のことは実験結果に裏打ちされた物理にも言えることであると思いますが、長文になりすぎるのでここで筆を置きます。
みなさんのコメント期待してます。
いくつかのテーマがあり、スペースの関係上全部には答えられないので最も重要なことのみコメントさせてください(笑)
それはゲーデルの「不完全性定理」です。
理由はデリダのみならず、ポストモダンの思想家のよりどころになっている可能性が高いからです。
ちょっと頑張って不完全性定理の論文(岩波文庫)にアタックしてみましょう。 不完全性定理は、数ページの導入部である第一部と、第一部の厳密な実行である第二部以降からなっています。導入部のみなら辛うじて読めますし、論文全体のエッセンスを汲み取れます。
非常に面白いのはゲーデルは超数学(数学基礎論)自体を表現している、論理記号(∀、≡など)を自然数に置換し、「論理式」(例えば証明式)自体を自然数の有限列にしてしまいます。そうすることで、超数学的な命題を、数学的命題に置き換えてしまう。
そして自己言及的(自己否定的)命題を一つ作り出し、決定不可能なことを証明しようとします。
つまりゲーデルが証明したのはあくまで「自己言及的」命題の決定不可能性のみであり、形式系内部の全ての命題が「決定不可能」であるとは言っていません。
(例えば、「クレタ人が「クレタ人は嘘つきだ」と言った」というような命題)
さらには、
「ゲーデルは絶対的決定不可能性になんら意味を認めていない、すなわち問題になるのは常に相対的決定不可能性に限定される」、
「ゲーデル命題はその命題が関わるシステムの中では決定不可能であるが、より強いシステムでなら決定可能である」(アナロジーの罠、ジャック・ブーブレス)
つまり、
ある形式系では決定不可能でも、新たに公理を追加すれば証明可能あるということ。 (ただしそのようなさらに強いシステムの中でも決定不能な命題が出てきてしまい、いたちごっこであるということ)
そして決定不可能なゲーデル命題とは具体的になんでしょうか?
またここで誤解がある気がします。数学的命題全体、日常言語で構成された言説全体を指しているのではありません。
それは実際のところ非常に限られていて、上記の自己言及的命題や、1977年以降に一部の研究者が発表した組み合わせ論の定理があるようです。(ゲーデル 不完全性定理、岩波文庫)
つまり現状の数学の領域では、ほとんど全ての命題に関して真偽の決定が可能である、ということになります。
もちろんクレイ研究所の発表したミレニアム問題のように未解決問題はたくさんありますが。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%A0%E6%87%B8%E8%B3%9E%E5%95%8F%E9%A1%8C
もし本当に数学領域に「脱構築」が適応可能なら、
フェルマーの最終定理が「フェルマー予想」に逆戻りする可能性があるということになります(笑)
そして「不完全性定理」も同じく定理でなくなる可能性があります。
さらに困ったことに、等式の羅列である数学証明図は、個々の等式のパラドキシカルな意味の複数性により 数学的証明自体が無効になる。そのような事態の発生が想定されます。
中途半端にゲーデルの解説書を読んでいた私も以前はかなり誤解していました(笑) 以上のことは実験結果に裏打ちされた物理にも言えることであると思いますが、長文になりすぎるのでここで筆を置きます。
みなさんのコメント期待してます。
そもそもですが、日常言語を論理学に還元し、論理学を記号論理学に還元することで、数学的証明の明晰性を言語の体系に基礎付けようとしたラッセル等の試みが下敷きにあります。が、ある体系の無矛盾性を証明しようとして、自己言及的命題の決定不可能性(矛盾性)に行き当たり、ある「体系の無矛盾性」の証明が失敗します。
これを「階層を変える」ことで乗り越えようとするなどの様々な方策が分析哲学のなかで試みられました。しかしどんなに階層をかえて、下位の階層を基礎づけたとしても、その当の階層には「決定不可能な命題が存在しうる」という事を証明したのがゲーデルの証明だったと思います。ゲーデルが「問題」になった理由が、まずそこにあります。
ゲーデルのやったことそれ自体は数学的体系や言語体系全体の問題ではありませんが、その結果を哲学史的筋道を逆行して敷衍すると、それは数学体系や言語体系全体に影響を与えることになるワケです。
これが「自然を鏡のように写している」という言語体系像の完全性のイメージを覆します。人間が使用している「体系」は自然を地盤にピラミッドのように構築された『自然の模写』ではなく、むしろピラミッドを逆さにして、地面との僅かな接点だけで宙吊りされているような、不安定な体系である、ということになるからです。
数学の基礎理論のおいてもしかりで、フェルマーの最終定理やゲーデルの自体も、今までと全く別の基礎理論の上に数学それ自体が再定義された場合、それが「命題」に逆行する場合もありえるワケです。実際、非ユークリッド幾何学がそれまでのユークリッド幾何学においてなしたことが、そういう意味を持ってました。それまで「公理」とされていたものが、見直されたりしたわけです。
「現在の体系は完全(=真実)であり、現在の体系を越える上位の階層の出現はありえない」というのが、「体系の無矛盾性」を証明する本当の意味あいでした。もしこれが証明できれば、例えば相対性理論や現在の数学体系などが「最終的な理論」である、ということの証明になります。つまり「現在の体系は『真実』である」ことが証明できる。
けれど「体系が無矛盾である」という事を証明できない以上、「体系が不完全である」ことを逆説的に証明してしまう。というのが、論理の世界です。そして実際に物理学の理論構造や、証明手続き等の見直しが行われました。そこで重要になるのが、つまるところ「自然言語」の問題なのです。
…が、ゲーデル問題自体はそもそも、直接的に「脱構築」なのではなく、あくまでその批判的活動の裏づけになるだけなので、ちょっとトピずれな感じもしますが。ましてや「脱構築は正義か?」という命題には、あまりにも離れてる感じがあります。
これを「階層を変える」ことで乗り越えようとするなどの様々な方策が分析哲学のなかで試みられました。しかしどんなに階層をかえて、下位の階層を基礎づけたとしても、その当の階層には「決定不可能な命題が存在しうる」という事を証明したのがゲーデルの証明だったと思います。ゲーデルが「問題」になった理由が、まずそこにあります。
ゲーデルのやったことそれ自体は数学的体系や言語体系全体の問題ではありませんが、その結果を哲学史的筋道を逆行して敷衍すると、それは数学体系や言語体系全体に影響を与えることになるワケです。
これが「自然を鏡のように写している」という言語体系像の完全性のイメージを覆します。人間が使用している「体系」は自然を地盤にピラミッドのように構築された『自然の模写』ではなく、むしろピラミッドを逆さにして、地面との僅かな接点だけで宙吊りされているような、不安定な体系である、ということになるからです。
数学の基礎理論のおいてもしかりで、フェルマーの最終定理やゲーデルの自体も、今までと全く別の基礎理論の上に数学それ自体が再定義された場合、それが「命題」に逆行する場合もありえるワケです。実際、非ユークリッド幾何学がそれまでのユークリッド幾何学においてなしたことが、そういう意味を持ってました。それまで「公理」とされていたものが、見直されたりしたわけです。
「現在の体系は完全(=真実)であり、現在の体系を越える上位の階層の出現はありえない」というのが、「体系の無矛盾性」を証明する本当の意味あいでした。もしこれが証明できれば、例えば相対性理論や現在の数学体系などが「最終的な理論」である、ということの証明になります。つまり「現在の体系は『真実』である」ことが証明できる。
けれど「体系が無矛盾である」という事を証明できない以上、「体系が不完全である」ことを逆説的に証明してしまう。というのが、論理の世界です。そして実際に物理学の理論構造や、証明手続き等の見直しが行われました。そこで重要になるのが、つまるところ「自然言語」の問題なのです。
…が、ゲーデル問題自体はそもそも、直接的に「脱構築」なのではなく、あくまでその批判的活動の裏づけになるだけなので、ちょっとトピずれな感じもしますが。ましてや「脱構築は正義か?」という命題には、あまりにも離れてる感じがあります。
かなりトピからはなれてしまいましたね(笑)実は「ゲーデルと脱構築」といった別のトピを立てようかとも思ってました。ただし名称が地味でインパクトがないなと(笑)
脱構築は正義か?では、正義か否かで水掛け論になることに気づきました。
だからコメントも躊躇してました。
正義宣言に対しては、私はコメント4のスーダマさんに対するコメント以上の意見は、残念ながら持ち合わせていません。
さらに水掛け論の危険を承知で、前提条件の「脱構築自体が存在するか否か」の問いに対しても、私の立場からは「存在する」としかいいようが無いですね(笑)
理由をつければ
1、デリダのテクスト、その注釈書、あるいはこのコミュの存在自体が「脱構築」の存在理由になっていると思われる。
2、脱構築というシニフィアンに対し、なにがしかのシニフィエが想定されるから。
ただし理論ではなく、「概念」や「活動」、「運動」といった方が適切だとは感じます。
デリダ自身も自身の脱構築の標的になるような「理論」を構築しようと考えたことはないでしょう。
上記の理由2はひょっとしたら意見が分かれるかもしれませんね!
デリダは「意味の本質的不在を主張している」(「有限責任会社」の中でのサールの主張)からです。
みなさんのコメント期待してますね!!
脱構築は正義か?では、正義か否かで水掛け論になることに気づきました。
だからコメントも躊躇してました。
正義宣言に対しては、私はコメント4のスーダマさんに対するコメント以上の意見は、残念ながら持ち合わせていません。
さらに水掛け論の危険を承知で、前提条件の「脱構築自体が存在するか否か」の問いに対しても、私の立場からは「存在する」としかいいようが無いですね(笑)
理由をつければ
1、デリダのテクスト、その注釈書、あるいはこのコミュの存在自体が「脱構築」の存在理由になっていると思われる。
2、脱構築というシニフィアンに対し、なにがしかのシニフィエが想定されるから。
ただし理論ではなく、「概念」や「活動」、「運動」といった方が適切だとは感じます。
デリダ自身も自身の脱構築の標的になるような「理論」を構築しようと考えたことはないでしょう。
上記の理由2はひょっとしたら意見が分かれるかもしれませんね!
デリダは「意味の本質的不在を主張している」(「有限責任会社」の中でのサールの主張)からです。
みなさんのコメント期待してますね!!
>> 8 たっちゃんさん
>ただし理論ではなく、「概念」や「活動」、「運動」といった方が適切だとは感じます。
>デリダ自身も自身の脱構築の標的になるような「理論」を構築しようと考えたことはないでしょう。
勉強になります。
但し、脱構築はどのような「概念」「活動」「運動」になるのでしょうか。「概念」「活動」「運動」があるという事は、何らかの「理論」に裏打ちされているということにはならないのでしょうか。確かに、理論になった瞬間に、脱構築自体の射程圏内に入る可能性が高くなりますが、脱構築理論が、脱構築自体に標的にされても、自爆してしまうとも限らないと思います。
上で言及されているゲーデルの不完全性定理も、詳しいことは分かりませんが、同じ性質があるように思われます。結局、不完全性定理も、「体系が無矛盾である」という事が証明できないことが判明しただけで、体系が使えないという事にはならず、あくまでも完結していないということが言えるだけとも考えられます。すると、そのような矛盾を起爆剤として、新しい体系に更新していくプロセスが、脱構築ということになるのでしょうか。
>ただし理論ではなく、「概念」や「活動」、「運動」といった方が適切だとは感じます。
>デリダ自身も自身の脱構築の標的になるような「理論」を構築しようと考えたことはないでしょう。
勉強になります。
但し、脱構築はどのような「概念」「活動」「運動」になるのでしょうか。「概念」「活動」「運動」があるという事は、何らかの「理論」に裏打ちされているということにはならないのでしょうか。確かに、理論になった瞬間に、脱構築自体の射程圏内に入る可能性が高くなりますが、脱構築理論が、脱構築自体に標的にされても、自爆してしまうとも限らないと思います。
上で言及されているゲーデルの不完全性定理も、詳しいことは分かりませんが、同じ性質があるように思われます。結局、不完全性定理も、「体系が無矛盾である」という事が証明できないことが判明しただけで、体系が使えないという事にはならず、あくまでも完結していないということが言えるだけとも考えられます。すると、そのような矛盾を起爆剤として、新しい体系に更新していくプロセスが、脱構築ということになるのでしょうか。
なぜ理論と呼ぶのが適切でないのか?あいまいに考えてましたが、少し考えて自分なりに明確にしてみました。中途半端で終わった正義の問題を考えるいい機会になりました。長いのでまたまた二つに分けます。
1、運動・・・・脱構築的意味の戯れの言い換え。連続的に異なる意味を生産し続けるエクリチュールをイメージしました
2、活動・・・・ポール・ド・マンや柄谷行人の脱構築的批評活動をさして。
3、概念・・・差異、マーク、戯れなどの概念の集合体としての脱構築
理論の要件はウィキペディアに任せましょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%86%E8%AB%96
ウィキペディアではユークリッド幾何学を理論の代表例として挙げてますから、脱構築とユークリッド幾何学を比較しましょう。
二つの違いは以下の通りです。
1、価値中立性
ユークリッド幾何学は悪や正義といった価値観とは無関係です。
しかし脱構築は自らを正義と語り、価値中立ではありません。
デリダが冒頭で提出している「正義が存在するか否か」という問いはデリダの批判する二項対立的な問いであり、脱構築の存在問題と同じく水掛け論になりかねません。
もし存在しないとすれば、正義というシニフィアンに対応するシニフィエが存在しないことなります。正義という言葉の居所が無くなり、現実世界との齟齬が生じます。
正義が存在するとしても次のような問題が発生します。
一般論と経験則でまず語りましょう。
私が過去のコメントで指摘した基本的人権も専制国家においては正義ではなく、イスラエルの正義とパレスチナの正義は相矛盾しているでしょう。抑圧者はどちらなのでしょう(正義の相対性)
あるいは私の正義は他人に理解されないかもしれない(パーソナルな正義の存在)
アプリオリな議論では正義は脱構築不可能のようです。
しかし、正義に対する脱構築は不可能であることを宣言するには、各主体にとって同一で時空間で変化のない<絶対的正義>を定義しなくてはなりませんが、そんなことが可能なのでしょうか?(相対性理論の光速Cのような正義)
1、運動・・・・脱構築的意味の戯れの言い換え。連続的に異なる意味を生産し続けるエクリチュールをイメージしました
2、活動・・・・ポール・ド・マンや柄谷行人の脱構築的批評活動をさして。
3、概念・・・差異、マーク、戯れなどの概念の集合体としての脱構築
理論の要件はウィキペディアに任せましょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%86%E8%AB%96
ウィキペディアではユークリッド幾何学を理論の代表例として挙げてますから、脱構築とユークリッド幾何学を比較しましょう。
二つの違いは以下の通りです。
1、価値中立性
ユークリッド幾何学は悪や正義といった価値観とは無関係です。
しかし脱構築は自らを正義と語り、価値中立ではありません。
デリダが冒頭で提出している「正義が存在するか否か」という問いはデリダの批判する二項対立的な問いであり、脱構築の存在問題と同じく水掛け論になりかねません。
もし存在しないとすれば、正義というシニフィアンに対応するシニフィエが存在しないことなります。正義という言葉の居所が無くなり、現実世界との齟齬が生じます。
正義が存在するとしても次のような問題が発生します。
一般論と経験則でまず語りましょう。
私が過去のコメントで指摘した基本的人権も専制国家においては正義ではなく、イスラエルの正義とパレスチナの正義は相矛盾しているでしょう。抑圧者はどちらなのでしょう(正義の相対性)
あるいは私の正義は他人に理解されないかもしれない(パーソナルな正義の存在)
アプリオリな議論では正義は脱構築不可能のようです。
しかし、正義に対する脱構築は不可能であることを宣言するには、各主体にとって同一で時空間で変化のない<絶対的正義>を定義しなくてはなりませんが、そんなことが可能なのでしょうか?(相対性理論の光速Cのような正義)
2、適応範囲が明確か
ユークリッド幾何学は曲率0の空間(完全に平らな平面)において有効な理論です。そこでは問題の平行線公準も有効です。曲率が0以外の値をとれば非ユークリッド幾何学の出番になり,住み分けが明確です。
そして私とあなたの曲率0は同じでしょう。
ただし一般論では私とあなたの<正義>は同じとはいえません。
正義は脱構築不能なので、脱構築可能な領域は各人にとっての<正義>以外の領域です。すなわち、脱構築の適応範囲は各人で異なります。パレスチナの大義はある人にとって<脱構築可能>ですが、そうでない人もいます。
一方ユークリッド幾何学は曲率0の空間が適応範囲です。これは大多数の人にとって同じです。
<正義の脱構築不可能性>によって脱構築は各人にとって正しいかどうかというパーソナルな真偽しか問えません。理論に要求されるのは大多数の人にとってのパブリックな真偽です。
3、論証可能性
曲率が0以外の値をとる空間では平行線公準が成立ないことにより、ユークリド幾何学が適用不能であることは論証可能です。
仮に万人にとっての正義が定義できたとして、<光速Cの正義>が脱構築適応不能であることをどうやって論証するのでしょうか?
残念ながら、なぜ正義が脱構築不可能なのかをデリダは論証していません。
4、世界観の違い
理論はその真偽を問うことが可能な性質、つまり反証可能性を保持しなければならない。(ウィキペディア)
そもそも脱構築は真偽の二項対立を批判し、不確定な世界観を持ち込むものなので、真偽を問うこと自体がナンセンスかもしれません。
<理論>のもつ世界観<何が真で、何が偽か>は脱構築的世界観から遠いところにあります。
以上が理論とはいえない理由になります。
不完全性定理と脱構築の関係はかなりたくさん書きたいことがあります。。。。どうしましょう??
本当にきりがないので、すいませんが次回にします(笑)
ユークリッド幾何学は曲率0の空間(完全に平らな平面)において有効な理論です。そこでは問題の平行線公準も有効です。曲率が0以外の値をとれば非ユークリッド幾何学の出番になり,住み分けが明確です。
そして私とあなたの曲率0は同じでしょう。
ただし一般論では私とあなたの<正義>は同じとはいえません。
正義は脱構築不能なので、脱構築可能な領域は各人にとっての<正義>以外の領域です。すなわち、脱構築の適応範囲は各人で異なります。パレスチナの大義はある人にとって<脱構築可能>ですが、そうでない人もいます。
一方ユークリッド幾何学は曲率0の空間が適応範囲です。これは大多数の人にとって同じです。
<正義の脱構築不可能性>によって脱構築は各人にとって正しいかどうかというパーソナルな真偽しか問えません。理論に要求されるのは大多数の人にとってのパブリックな真偽です。
3、論証可能性
曲率が0以外の値をとる空間では平行線公準が成立ないことにより、ユークリド幾何学が適用不能であることは論証可能です。
仮に万人にとっての正義が定義できたとして、<光速Cの正義>が脱構築適応不能であることをどうやって論証するのでしょうか?
残念ながら、なぜ正義が脱構築不可能なのかをデリダは論証していません。
4、世界観の違い
理論はその真偽を問うことが可能な性質、つまり反証可能性を保持しなければならない。(ウィキペディア)
そもそも脱構築は真偽の二項対立を批判し、不確定な世界観を持ち込むものなので、真偽を問うこと自体がナンセンスかもしれません。
<理論>のもつ世界観<何が真で、何が偽か>は脱構築的世界観から遠いところにあります。
以上が理論とはいえない理由になります。
不完全性定理と脱構築の関係はかなりたくさん書きたいことがあります。。。。どうしましょう??
本当にきりがないので、すいませんが次回にします(笑)
9のあたりすさんの『矛盾を起爆剤として、新しい体系に更新していくプロセス』という理解で適切だと思われます。簡単にいえば脱構築とは「批評」です。その意味で、「理論」ではない、ということです。
大体、5で『『脱構築理論自体』と書いてありますが、まず脱構築を「理論」と考えるのが不適切だと思われます。』と書いた僕に対して、『 ただし理論ではなく、「概念」や「活動」、「運動」といった方が適切だとは感じます。』と書いたトピ主に話が通じてないことが判りましたのでコメントを避けてたんですが、少しだけコメントしておこうと思います。
そもそもデリダが批評の対象にしたのは、「ヨーロッパの伝統的観念」であり、そこに「基礎」として横たわっているドグマです。その意味でまず、「 ユークリッド幾何学は悪や正義といった価値観とは無関係」という理解自体が間違いです。
ユークリッド幾何学に代表されるヨーロッパの「超越論的観念」は、潜在意識の根深いところにまでヨーロッパの底流に流れており、それをこそ「脱構築」する必要があったのが、そもそもの始まりです。
フッサールが『幾何学の起源』を書いて、「ヨーロッパの危機」、つまり超越論的に基礎付けられた秩序概念の再構築を図ったのに対して、デリダはその訳書の序説のなかで、フッサールの意図それ自体を批判しています。
『じっさい、一方では、危機意識と理性の目的論の確認とは超越論的観念論を新しく正当化する方法的手段でしかない。他方では、西洋哲学の生成全体の展望、ヨーロッパ的形相と無限な任務を担った人間の定義、発見する所作そのものによってそのつど隠蔽されてしまう超越論的動機の冒険と受難を物語り、これらすべては、いかなる歴史的理性の批判もあからさまにかつ前もって正当化することができなかった信用状を、一覧標的回顧によって開設した』(『幾何学の起源』序説)
超越論的=つまり、非時間的に、超空間的に普遍妥当性を持つような先験的観念。この基礎付け作業は、生まれでた観念に対して、それが「常に」普遍的であったかのように振舞わせます。ここではその歴史的経緯や、文脈、文化的偏重等の諸条件が忘却され隠蔽されます。
しかし、ぶっちゃけた話ですが、カルチュラルスタディのような「あらゆる発言、言説には、その背景が影響している」というような分析方法が出てきた現在、わざわざデリダほど面倒な論理的手続きを踏む必要があるかはどうかは微妙です。
別トピでデリダ・サール論争が取り上げられてましたが、あそこで抜け落ちてるのは、ヨーロッパの伝統的な「言語・コミュニケーションの観念」です。それは「定義さえ明確であれば、言語だけの(つまりボディランゲージやコンセンサス等抜きでも)言語交通に誤解は生じない」というようなもので、伝統的なヨーロッパの言語概念です。サールはそれを固守しようとして、デリダはそれを批判したにすぎません。
しかし現在では大脳損傷例のようなケースから、人間は知性に欠陥がなくても「表情から感情を読み取る機能」なんかが欠落するだけで、コミュニケーションに大変な不適合が生ずることがわかってます。
いわばデリダの時代に居座っていたヨーロッパのドグマは、現在では別ルートでかなり解体してしまいました。それでもなお、現在デリダを読む意味が何処にあるか? を検討したほうが生産的だと思われます。
大体、5で『『脱構築理論自体』と書いてありますが、まず脱構築を「理論」と考えるのが不適切だと思われます。』と書いた僕に対して、『 ただし理論ではなく、「概念」や「活動」、「運動」といった方が適切だとは感じます。』と書いたトピ主に話が通じてないことが判りましたのでコメントを避けてたんですが、少しだけコメントしておこうと思います。
そもそもデリダが批評の対象にしたのは、「ヨーロッパの伝統的観念」であり、そこに「基礎」として横たわっているドグマです。その意味でまず、「 ユークリッド幾何学は悪や正義といった価値観とは無関係」という理解自体が間違いです。
ユークリッド幾何学に代表されるヨーロッパの「超越論的観念」は、潜在意識の根深いところにまでヨーロッパの底流に流れており、それをこそ「脱構築」する必要があったのが、そもそもの始まりです。
フッサールが『幾何学の起源』を書いて、「ヨーロッパの危機」、つまり超越論的に基礎付けられた秩序概念の再構築を図ったのに対して、デリダはその訳書の序説のなかで、フッサールの意図それ自体を批判しています。
『じっさい、一方では、危機意識と理性の目的論の確認とは超越論的観念論を新しく正当化する方法的手段でしかない。他方では、西洋哲学の生成全体の展望、ヨーロッパ的形相と無限な任務を担った人間の定義、発見する所作そのものによってそのつど隠蔽されてしまう超越論的動機の冒険と受難を物語り、これらすべては、いかなる歴史的理性の批判もあからさまにかつ前もって正当化することができなかった信用状を、一覧標的回顧によって開設した』(『幾何学の起源』序説)
超越論的=つまり、非時間的に、超空間的に普遍妥当性を持つような先験的観念。この基礎付け作業は、生まれでた観念に対して、それが「常に」普遍的であったかのように振舞わせます。ここではその歴史的経緯や、文脈、文化的偏重等の諸条件が忘却され隠蔽されます。
しかし、ぶっちゃけた話ですが、カルチュラルスタディのような「あらゆる発言、言説には、その背景が影響している」というような分析方法が出てきた現在、わざわざデリダほど面倒な論理的手続きを踏む必要があるかはどうかは微妙です。
別トピでデリダ・サール論争が取り上げられてましたが、あそこで抜け落ちてるのは、ヨーロッパの伝統的な「言語・コミュニケーションの観念」です。それは「定義さえ明確であれば、言語だけの(つまりボディランゲージやコンセンサス等抜きでも)言語交通に誤解は生じない」というようなもので、伝統的なヨーロッパの言語概念です。サールはそれを固守しようとして、デリダはそれを批判したにすぎません。
しかし現在では大脳損傷例のようなケースから、人間は知性に欠陥がなくても「表情から感情を読み取る機能」なんかが欠落するだけで、コミュニケーションに大変な不適合が生ずることがわかってます。
いわばデリダの時代に居座っていたヨーロッパのドグマは、現在では別ルートでかなり解体してしまいました。それでもなお、現在デリダを読む意味が何処にあるか? を検討したほうが生産的だと思われます。
今まで同様に脱構築に厳しいコメントになりますがご勘弁ください(笑)また前後半に分けます。
まずユークリッド幾何学の公準の一部をいくつか見ましょう。
・円周率は一定である(3.1415…..)
・三角形の内角の和は180度である
・すべての直角は互いに等しい
上記の文章は普遍的に振舞っているというより、まさに曲率0空間では「普遍的」といって差し支えないのでは?
理由は2300年以上に渡って反例が見つかっていないためです。
ましてや測量機械やGPSシステムは上記の公準なしに動作しないでしょう。実際に高精度で動いており、理論と現実が強く結びついている例です。
ただしデリダは幾何学の普遍性宣言に異議申し立てをし、隠れた価値観が存在していると主張しているわけですね。
デリダはそのような主張に伴い、数学者や工学者にも説得力のある形(証拠や裏づけアリ)での論証をしているのでしょうか?
例えば、円周率=πは決定不能な文章である(あるいは誤りの可能性あり)。なぜなら、、、、といった詳しい論証です。
歴史的経緯や文脈に関しても、ユークリッド本人に関してほとんど何も分かっていない(紀元前325年頃)ので調査が非常に困難です。(「ポワンカレ予想を解いた数学者」、オネル・ドシア)
誰かが意図的に文脈隠蔽を図っているというより、「わからなくなっている」
アプリオリな超越論も、現実世界の洗礼をうける必要があるでしょう。新たな概念や、実験データとの食い違いで修正されうる。
そのような意味でアカデミックなエクリチュールでも簡単に普遍性があるとは宣言できない。 それに関しては私も全く異論はありませんが、デリダ自身が具体的にどのテクストのどの点が問題なのかを具体的に提示する必要があったと思います。(実例の提示)
まずユークリッド幾何学の公準の一部をいくつか見ましょう。
・円周率は一定である(3.1415…..)
・三角形の内角の和は180度である
・すべての直角は互いに等しい
上記の文章は普遍的に振舞っているというより、まさに曲率0空間では「普遍的」といって差し支えないのでは?
理由は2300年以上に渡って反例が見つかっていないためです。
ましてや測量機械やGPSシステムは上記の公準なしに動作しないでしょう。実際に高精度で動いており、理論と現実が強く結びついている例です。
ただしデリダは幾何学の普遍性宣言に異議申し立てをし、隠れた価値観が存在していると主張しているわけですね。
デリダはそのような主張に伴い、数学者や工学者にも説得力のある形(証拠や裏づけアリ)での論証をしているのでしょうか?
例えば、円周率=πは決定不能な文章である(あるいは誤りの可能性あり)。なぜなら、、、、といった詳しい論証です。
歴史的経緯や文脈に関しても、ユークリッド本人に関してほとんど何も分かっていない(紀元前325年頃)ので調査が非常に困難です。(「ポワンカレ予想を解いた数学者」、オネル・ドシア)
誰かが意図的に文脈隠蔽を図っているというより、「わからなくなっている」
アプリオリな超越論も、現実世界の洗礼をうける必要があるでしょう。新たな概念や、実験データとの食い違いで修正されうる。
そのような意味でアカデミックなエクリチュールでも簡単に普遍性があるとは宣言できない。 それに関しては私も全く異論はありませんが、デリダ自身が具体的にどのテクストのどの点が問題なのかを具体的に提示する必要があったと思います。(実例の提示)
残念ながらカルチュラル・スタディーズに関しては手元の本が「「知」の欺瞞」(アラン・ソーカル、ジャン、ブリクモン)の為、良い印象を持っておりません(笑)
これは物理学者である著者が、アメリカの有名なカルチュラル・スタディーズ雑誌にでたらめなパロディー論文「境界を侵犯すること〜量子力学の変形解釈学に向けて」(1996年)を投稿し、見事掲載された事件に関係するものです。誤ってパロディ論文を掲載した編集者は「イグ・ノーベル賞」を受賞しました。 ソーカル事件と呼ばれる事件で、日本でも話題にされました。非常に面白い本なので、読んでいない方にはおすすめです。
以下は印象深い一文です。
「科学がポストモダンであるとみなされる簡単な基準は、それが客観的な真実という概念にいかなる意味でも依存しないことである」(境界を侵犯すること)
さらには、
「かつては定数であり普遍的とみなされたユークリッドのπやニュートンのGも、今やそれらが持つ避けがたい歴史性の文脈の中で捉えなおされることになる」
(境界を侵犯すること)
「アインシュタインの定数は定数ではなく、(中略)終局的にはゲームの概念なのです」(1970年のデリダのコメント、境界を侵犯することからの引用)
上記の二つのコメントは物理定数の否定という意味でよく似ています。
カルチュラル・スタディーズやポストモダン思想にとっては、いずれも妥当な考え方なのでしょうか?
ちなみに私の手元にある、「アナロジーの罠」(ジャック・ブーブレス)はこの事件に触発されて書かれた本です。不完全性定理を安易にアナロジーとして援用する危険を論じています。これは脱構築も例外ではありません。
ソーカルの「境界を侵犯すること」やブーブレスの本から発生する私の問題意識は、
・現代思想は(特にポストモダン)は根拠や証拠を否定し、現実から遊離することを自ら肯定し、説得力を急速に失い、さらには一般の人々の支持も失いつつあるのでは?
というものです。みなさんの感想をお聞かせください。
これは物理学者である著者が、アメリカの有名なカルチュラル・スタディーズ雑誌にでたらめなパロディー論文「境界を侵犯すること〜量子力学の変形解釈学に向けて」(1996年)を投稿し、見事掲載された事件に関係するものです。誤ってパロディ論文を掲載した編集者は「イグ・ノーベル賞」を受賞しました。 ソーカル事件と呼ばれる事件で、日本でも話題にされました。非常に面白い本なので、読んでいない方にはおすすめです。
以下は印象深い一文です。
「科学がポストモダンであるとみなされる簡単な基準は、それが客観的な真実という概念にいかなる意味でも依存しないことである」(境界を侵犯すること)
さらには、
「かつては定数であり普遍的とみなされたユークリッドのπやニュートンのGも、今やそれらが持つ避けがたい歴史性の文脈の中で捉えなおされることになる」
(境界を侵犯すること)
「アインシュタインの定数は定数ではなく、(中略)終局的にはゲームの概念なのです」(1970年のデリダのコメント、境界を侵犯することからの引用)
上記の二つのコメントは物理定数の否定という意味でよく似ています。
カルチュラル・スタディーズやポストモダン思想にとっては、いずれも妥当な考え方なのでしょうか?
ちなみに私の手元にある、「アナロジーの罠」(ジャック・ブーブレス)はこの事件に触発されて書かれた本です。不完全性定理を安易にアナロジーとして援用する危険を論じています。これは脱構築も例外ではありません。
ソーカルの「境界を侵犯すること」やブーブレスの本から発生する私の問題意識は、
・現代思想は(特にポストモダン)は根拠や証拠を否定し、現実から遊離することを自ら肯定し、説得力を急速に失い、さらには一般の人々の支持も失いつつあるのでは?
というものです。みなさんの感想をお聞かせください。
だから、ユークリッド幾何学のような「普遍的真実」として振舞ってきた第五公準のような例が、「曲率0空間では」という条件つきの「妥当性」でしかなかった、というような事がそもそもフッサールが「ヨーロッパの精神の危機」として基礎付けを図らなければならなかった要因です。
また、そもそも「普遍的」という言葉の意味を捉え違えています。例えば公理や定理によって、命題を「経験抜き」に証明できる、ということがヨーロッパ文化における「真実」=つまり「普遍性」です。経験的に誤謬が今のところない、という条件は、伝統的な「真理」概念ではそもそも「普遍的」ではないのです。
正直、デリダのことをゴチャゴチャ言う前に、デリダが対象にしたヨーロッパの精神それ自体を知る必要があるんじゃないでしょうか。
デリダ自身は科学における基礎条件の見直しは確かにしてませんが、クワイン等の研究があるのでその辺は充分だと思われます。というか、長い話になるので、以前に僕が書いた科学哲学に関する記事を貼っておきます。いわゆるソーカル事件も、そこでとりあげています。
・西欧的な認識 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1382179814&owner_id=16012523
・西欧における自然と知 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1386289034&owner_id=16012523
・東西の認識傾向 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1392142885&owner_id=16012523
・科学と真理 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1396632757&owner_id=16012523
・イマジナリーな科学 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1411009857&owner_id=16012523
・科学の危機 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1413542739&owner_id=16012523
・ホーリズムとパラダイム・シフト http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1418731278&owner_id=16012523
・サイエンス・ウォーズとソーカル事件 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1425340232&owner_id=16012523
・科学と技術 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1430884372&owner_id=16012523
ただ一つ言っておけば、もはやポストモダンは別に支持されてないのでは? 今、ポストモダン批判をする、ということが周期遅れな印象が否めないのです。
また、そもそも「普遍的」という言葉の意味を捉え違えています。例えば公理や定理によって、命題を「経験抜き」に証明できる、ということがヨーロッパ文化における「真実」=つまり「普遍性」です。経験的に誤謬が今のところない、という条件は、伝統的な「真理」概念ではそもそも「普遍的」ではないのです。
正直、デリダのことをゴチャゴチャ言う前に、デリダが対象にしたヨーロッパの精神それ自体を知る必要があるんじゃないでしょうか。
デリダ自身は科学における基礎条件の見直しは確かにしてませんが、クワイン等の研究があるのでその辺は充分だと思われます。というか、長い話になるので、以前に僕が書いた科学哲学に関する記事を貼っておきます。いわゆるソーカル事件も、そこでとりあげています。
・西欧的な認識 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1382179814&owner_id=16012523
・西欧における自然と知 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1386289034&owner_id=16012523
・東西の認識傾向 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1392142885&owner_id=16012523
・科学と真理 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1396632757&owner_id=16012523
・イマジナリーな科学 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1411009857&owner_id=16012523
・科学の危機 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1413542739&owner_id=16012523
・ホーリズムとパラダイム・シフト http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1418731278&owner_id=16012523
・サイエンス・ウォーズとソーカル事件 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1425340232&owner_id=16012523
・科学と技術 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1430884372&owner_id=16012523
ただ一つ言っておけば、もはやポストモダンは別に支持されてないのでは? 今、ポストモダン批判をする、ということが周期遅れな印象が否めないのです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ジャック・デリダ 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
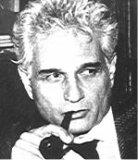













![[dir] 会津](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/93/42/729342_114s.jpg)






