仏の哲学者ジャック・デリダ氏、がんで死去
【パリ=島崎雅夫】9日のAFP通信によると、ポスト構造主義の代表的哲学者として著名なフランスのジャック・デリダ氏が8日深夜から9日未明にかけてパリ市内の病院で、すい臓がんのため死去した。74歳。
1930年7月、フランスの植民地だったアルジェリアでユダヤ系の家庭に生まれた。60年代、フッサールの現象学から出発、ニーチェやハイデッガーを批判的に発展させ、西欧哲学の解体を訴える「脱構築」の概念を確立した。
「散種」「差延」などの概念でも知られる。90年代からは政治、社会的な発言も積極的に行い、20世紀後半を代表する国際的な知識人でもあった。2003年、ドイツ人哲学者のユルゲン・ハーバーマス氏と共に、イラク戦争後の欧州の役割について共同声明を発表し、注目を集めた。代表作に「エクリチュールと差異」「グラマトロジーについて」「法の力」「死を与える」など。
【パリ=島崎雅夫】9日のAFP通信によると、ポスト構造主義の代表的哲学者として著名なフランスのジャック・デリダ氏が8日深夜から9日未明にかけてパリ市内の病院で、すい臓がんのため死去した。74歳。
1930年7月、フランスの植民地だったアルジェリアでユダヤ系の家庭に生まれた。60年代、フッサールの現象学から出発、ニーチェやハイデッガーを批判的に発展させ、西欧哲学の解体を訴える「脱構築」の概念を確立した。
「散種」「差延」などの概念でも知られる。90年代からは政治、社会的な発言も積極的に行い、20世紀後半を代表する国際的な知識人でもあった。2003年、ドイツ人哲学者のユルゲン・ハーバーマス氏と共に、イラク戦争後の欧州の役割について共同声明を発表し、注目を集めた。代表作に「エクリチュールと差異」「グラマトロジーについて」「法の力」「死を与える」など。
|
|
|
|
コメント(19)
『法の力』の訳者である堅田研一さんによる、以下のデリダ自身の本(『マルクスの亡霊たち』藤原書店より刊行予定)の紹介文がもっとも的確にデリダを追悼しているように思います。
/////以下引用///////////
〜それでは、この死者たちによって負わされる「負債」によって、相続人であるわれわれには何が命令されるのか。われわれは死者を哀悼しなければならない。つまり「喪の労働」をなさねばならない。それはつまり、遺産を相続するという決断をもって遺産を引き継ぐことであり、また遺産に労働を加えることである。そしてそれは、遺産を批判し選択しながら引き継ぐこと、遺産を解釈することである。そしてそれは、死者からの遺産、つまり古い言葉や衣装を借り受けて登場することである。
この登場こそが革命である。「革命revolution」とは、新しいものの定立という意味のほかに、「反動的」、つまり過去への回帰という意味も含む。フランス革命が古代ローマの服装をまとって現れたように、革命、つまり新しいものの定立とは常に古いものの反復のかたちをとる。古いものとはつまり、過去への遺物として表舞台から排除されていたものである。マルクスはこれを『ルイ・ボナパルトのブリュメール一八日』において語っていた。具体的な定立は、損得感情によって行なわれる。存在論的構造をもった法/権利は、この計算が作用する場である。けれどもその損得感情が始まるのは一つの決断によって、つまりある遺産の網のなかに責任をもって参加することに始まる決断によってである。遺産、つまり世界への刻みを置くこと、つまり定立作用とは約束することである。そしてこの約束とは、これまでにないもの、他者、つまり正義の到来の約束である。この正義は法/権利なしには現在しえないが、しかしそのかなたにある。
堅田研一「亡霊と正義(デリダとマルクス)」「アソシエ」2000.7より
/////以下引用///////////
〜それでは、この死者たちによって負わされる「負債」によって、相続人であるわれわれには何が命令されるのか。われわれは死者を哀悼しなければならない。つまり「喪の労働」をなさねばならない。それはつまり、遺産を相続するという決断をもって遺産を引き継ぐことであり、また遺産に労働を加えることである。そしてそれは、遺産を批判し選択しながら引き継ぐこと、遺産を解釈することである。そしてそれは、死者からの遺産、つまり古い言葉や衣装を借り受けて登場することである。
この登場こそが革命である。「革命revolution」とは、新しいものの定立という意味のほかに、「反動的」、つまり過去への回帰という意味も含む。フランス革命が古代ローマの服装をまとって現れたように、革命、つまり新しいものの定立とは常に古いものの反復のかたちをとる。古いものとはつまり、過去への遺物として表舞台から排除されていたものである。マルクスはこれを『ルイ・ボナパルトのブリュメール一八日』において語っていた。具体的な定立は、損得感情によって行なわれる。存在論的構造をもった法/権利は、この計算が作用する場である。けれどもその損得感情が始まるのは一つの決断によって、つまりある遺産の網のなかに責任をもって参加することに始まる決断によってである。遺産、つまり世界への刻みを置くこと、つまり定立作用とは約束することである。そしてこの約束とは、これまでにないもの、他者、つまり正義の到来の約束である。この正義は法/権利なしには現在しえないが、しかしそのかなたにある。
堅田研一「亡霊と正義(デリダとマルクス)」「アソシエ」2000.7より
晩年にフランスのアカデミズムでデリダが評価されたとすれば、それは功労者としてではないでしょうか。最近はもう、インターナショナルに活躍するフランスの大哲学者なんてほとんどいなくなっていたし、分析哲学に対抗できる独自の路線自体手詰まりでしたからね。
デリダの功績は、単に現象学の研究の中で独自の思想を打ち出しただけでなくて、その思想や概念で、文学理論、言語学、法思想、精神分析など、広範な周辺分野に自ら介入して貢献した点が大きいと思います。しかもそうした革新を、過去の哲学テクストを参照しながら行ったところがすごいですよね。コンディヤックやルソーに触れながら、アクチュアルなサール批判ができてしまうんですから。
ただ、偉人にはつきものですが、デリダがもたらした弊害というのもあると思います。それは、彼が過去のテクストの読み直しをあまりに見事にやってのけたので、周囲が歴史研究に期待を抱きすぎて、同時代の外国での哲学的動向から目を反らす免罪符を与えることになってしまったこととか、現象学やハイデガー主義(文体も含めて)を延命しすぎたことでしょうか。
話によると、とくにここ十年の間、フランスでは、英米哲学の受容が進んでいるそうです。セラーズやブランダムなんか、もっとずっと前から大陸で幅広く議論されてもよかったのにな、と思ってしまいますね。もちろんデリダだけのせいではないんでしょうけれども。
デリダ×磯崎×浅田の鼎談ですか・・・私も見たかったなぁ。
りんごさん、ときどきデリダの本を手にとって思索するだけでも、デリダに対する“応答”だと思いますよー^^
デリダの功績は、単に現象学の研究の中で独自の思想を打ち出しただけでなくて、その思想や概念で、文学理論、言語学、法思想、精神分析など、広範な周辺分野に自ら介入して貢献した点が大きいと思います。しかもそうした革新を、過去の哲学テクストを参照しながら行ったところがすごいですよね。コンディヤックやルソーに触れながら、アクチュアルなサール批判ができてしまうんですから。
ただ、偉人にはつきものですが、デリダがもたらした弊害というのもあると思います。それは、彼が過去のテクストの読み直しをあまりに見事にやってのけたので、周囲が歴史研究に期待を抱きすぎて、同時代の外国での哲学的動向から目を反らす免罪符を与えることになってしまったこととか、現象学やハイデガー主義(文体も含めて)を延命しすぎたことでしょうか。
話によると、とくにここ十年の間、フランスでは、英米哲学の受容が進んでいるそうです。セラーズやブランダムなんか、もっとずっと前から大陸で幅広く議論されてもよかったのにな、と思ってしまいますね。もちろんデリダだけのせいではないんでしょうけれども。
デリダ×磯崎×浅田の鼎談ですか・・・私も見たかったなぁ。
りんごさん、ときどきデリダの本を手にとって思索するだけでも、デリダに対する“応答”だと思いますよー^^
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ジャック・デリダ 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
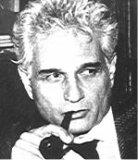













![[dir] 会津](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/93/42/729342_114s.jpg)






