朗読と講演
『塩狩峠』を読み、語る のご報告 その2です。
中村啓子さんたちの朗読ですっかり『塩狩峠』の世界に浸らせていただきました。
第二部は予定通り14:20から始まりました。
講師は佐藤優さん
「『塩狩峠』と私」という題で講演してくれました。
講演は4つに区切られます。
1.特別な作品であること
2.『塩狩峠』との出会い
3.再び『塩狩峠』と出会ったこと
4.神学的な観点からいくつか
【1.特別な作品であること 2.『塩狩峠』との出会い】
中学時代の塾の先生に勧められて『塩狩峠』を手にして、このような本が読みたかったと心から感動した。ずっと大事に読み継いでいた。
北海道に一人旅をした時に大勢の大学生にユースホステルで出会ったが、その8割が塩狩峠に足を運んだ時代だった。
その後同志社大学の神学部に進み、語学・哲学の習得に追われ、『塩狩峠』を忘れてしまう時期があった。また日本のプロテスタンティズムには「小説を遠ざける文化」があることも事実(『塩狩峠』中の待子の発言からも確認できる)
<戦後の戦中のこと>
戦後の社会の基本的な思想はというと
〇合理主義 であり
〇個人主義的であり
〇生命至上主義であったと言える
(一方)戦前・戦中はというと、飛行兵が飛行機がないので特攻のために切り込むようなことが行われた。モーターボートで突入したり人間魚雷もあった。(戦後とは大違い)
(佐藤さんの)母は14歳の時に沖縄戦に遭遇した。
若過ぎたが、実家に帰る手立てがないので軍属として雇用されて軍と行動を共にしていた。自決用に手りゅう弾が2発配られた。
兵隊たちは代わる代わる、「この戦は負け戦だ。死んだらあかん」と言ってくれたそうだ。
そうは言っても、ついにアメリカ兵に見つかった時に母は手りゅう弾の安全ピンを抜いて投げる用意をしたのだが、一緒にいた伍長が「死ぬのは捕虜になってからでも出来る」と降伏することになったので母は生きながらえることができた。
【3.再び『塩狩峠』と出会ったこと】
2011年3月11日に東日本大震災が起きて福島原発に被害が出た。
合理主義の極致で安全の極致であるはずの物だったではないですか。
でも・・・暴走したら専門家でも止めるのが困難。
この事態に対して、国も民間も専門家たちに「解決しろ」とは言えない。何故かというとそれは個人に無限責任を課すことになるから。
国のために死ぬことを良いことだという風潮が最近になってあるようだが、それは、まずいと思ってます。
フキシマの状況は『塩狩峠』のい事態と似ている。
近代技術の粋を集めたものが暴走して、専門家たちがその解決のために取り組む・・・
永野と三堀の二人だけが事故車両に乗り合わせた専門家。
永野は事務系だったが、それでも素人ではない。
永野が身を挺したのは、職業倫理に基づいて、社会のために無限責任を果たしたのだとみることができる。社会のための犠牲。
(補足。社会のために犠牲居なるというのは隣人愛を果たすことなのかもしれない と思わされました)
【4.神学的な観点からいくつか】
永野の最後の瞬間が二度にわたって描かれている。これは大変手法として巧いと思う。
一瞬の出来事。
信仰を決断と考えることもできるけど、いつの間にかこうなっているものともいうことができる。
神の声が聞こえるというか、そういった場に置かれる。
永野には神からの声が聞こえたと考えることもができる。
(その時の)他の人たちのために自分にしかできないことを果たすこと
今の時代にこのような信仰の生き方をしたのが後藤健二さん。
彼は日本基督教団の信徒だった。
中東の経験があり湯川春菜さんを助けに行った。
他の人のために自分にしかできないことを果たそうとした。
綾子さんにも時々神さまの声が聞こえていたと思う。
自分にしか書けない作品を書く。
最後に戦後のプロテスタンティズムの最高傑作を挙げろと言われたら躊躇いなく『塩狩峠』を挙げます。
ありがとうございました。
元サイト:https:/
『塩狩峠』を読み、語る のご報告 その2です。
中村啓子さんたちの朗読ですっかり『塩狩峠』の世界に浸らせていただきました。
第二部は予定通り14:20から始まりました。
講師は佐藤優さん
「『塩狩峠』と私」という題で講演してくれました。
講演は4つに区切られます。
1.特別な作品であること
2.『塩狩峠』との出会い
3.再び『塩狩峠』と出会ったこと
4.神学的な観点からいくつか
【1.特別な作品であること 2.『塩狩峠』との出会い】
中学時代の塾の先生に勧められて『塩狩峠』を手にして、このような本が読みたかったと心から感動した。ずっと大事に読み継いでいた。
北海道に一人旅をした時に大勢の大学生にユースホステルで出会ったが、その8割が塩狩峠に足を運んだ時代だった。
その後同志社大学の神学部に進み、語学・哲学の習得に追われ、『塩狩峠』を忘れてしまう時期があった。また日本のプロテスタンティズムには「小説を遠ざける文化」があることも事実(『塩狩峠』中の待子の発言からも確認できる)
<戦後の戦中のこと>
戦後の社会の基本的な思想はというと
〇合理主義 であり
〇個人主義的であり
〇生命至上主義であったと言える
(一方)戦前・戦中はというと、飛行兵が飛行機がないので特攻のために切り込むようなことが行われた。モーターボートで突入したり人間魚雷もあった。(戦後とは大違い)
(佐藤さんの)母は14歳の時に沖縄戦に遭遇した。
若過ぎたが、実家に帰る手立てがないので軍属として雇用されて軍と行動を共にしていた。自決用に手りゅう弾が2発配られた。
兵隊たちは代わる代わる、「この戦は負け戦だ。死んだらあかん」と言ってくれたそうだ。
そうは言っても、ついにアメリカ兵に見つかった時に母は手りゅう弾の安全ピンを抜いて投げる用意をしたのだが、一緒にいた伍長が「死ぬのは捕虜になってからでも出来る」と降伏することになったので母は生きながらえることができた。
【3.再び『塩狩峠』と出会ったこと】
2011年3月11日に東日本大震災が起きて福島原発に被害が出た。
合理主義の極致で安全の極致であるはずの物だったではないですか。
でも・・・暴走したら専門家でも止めるのが困難。
この事態に対して、国も民間も専門家たちに「解決しろ」とは言えない。何故かというとそれは個人に無限責任を課すことになるから。
国のために死ぬことを良いことだという風潮が最近になってあるようだが、それは、まずいと思ってます。
フキシマの状況は『塩狩峠』のい事態と似ている。
近代技術の粋を集めたものが暴走して、専門家たちがその解決のために取り組む・・・
永野と三堀の二人だけが事故車両に乗り合わせた専門家。
永野は事務系だったが、それでも素人ではない。
永野が身を挺したのは、職業倫理に基づいて、社会のために無限責任を果たしたのだとみることができる。社会のための犠牲。
(補足。社会のために犠牲居なるというのは隣人愛を果たすことなのかもしれない と思わされました)
【4.神学的な観点からいくつか】
永野の最後の瞬間が二度にわたって描かれている。これは大変手法として巧いと思う。
一瞬の出来事。
信仰を決断と考えることもできるけど、いつの間にかこうなっているものともいうことができる。
神の声が聞こえるというか、そういった場に置かれる。
永野には神からの声が聞こえたと考えることもができる。
(その時の)他の人たちのために自分にしかできないことを果たすこと
今の時代にこのような信仰の生き方をしたのが後藤健二さん。
彼は日本基督教団の信徒だった。
中東の経験があり湯川春菜さんを助けに行った。
他の人のために自分にしかできないことを果たそうとした。
綾子さんにも時々神さまの声が聞こえていたと思う。
自分にしか書けない作品を書く。
最後に戦後のプロテスタンティズムの最高傑作を挙げろと言われたら躊躇いなく『塩狩峠』を挙げます。
ありがとうございました。
元サイト:https:/
|
|
|
|
|
|
|
|
三浦綾子 更新情報
-
最新のアンケート
三浦綾子のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- マイミク募集はここで。
- 89578人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208274人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90042人
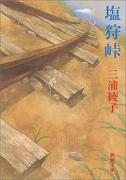


![[NHK]100分de名著](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/22/92/6082292_141s.jpg)




















