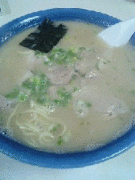■第1回
佐賀郡出身(現在は合併して佐賀市になっている)の私が通っていた小学校には、今では笑ってしまうような校則が存在していました。それは、「街に自分たちだけで出かけてはいけない」というもの。「街」というのは佐賀市の繁華街という意味です。どのくらいの田舎度かは容易に想像できますよね!?
周りの大人たちに「街さい行くけん、一緒にくっか?(来るか?)」と言われると、有頂天ものでした。今の自分に置き換えてみると、「沖縄に遊びに行かない?奢るから」てなレベルかなぁ。
といっても「街」ですることといえば、ゲームセンターでなけなしの小遣いを減らしたり、本屋で学校の図書館にはない本や雑誌を眺めたり(運がいいと買ってもらえた)ぐらいのものだったのです。しかし、それが至上の喜びだったわけで・・・。
そんな「街」行きでも、正月に家族で出かける初詣の際は格別でした。
というのも、佐賀神社と松原神社(二つの神社は隣接している)への初詣の後に、両神社の近くにある「一休軒本店」でラーメンを食べるという儀式があったからです。その当時の「一休軒本店」では、年末年始には店頭に行列が出来るくらい繁盛していました。行列の整理だけを担当する店員さんがいたくらいです。
酒を飲んで強気になってる私の親父が、店員に「はよ、食わせんかい(早く、食わせろよ)」と突っかかるのが、妙に恥ずかしかった記憶が残っています。
ラーメンの味には、いつもうっとりしていました。独特の甘味を内包しながら嫌味でなく、滑らかで優しい豚骨の風味は戸外の寒さを一瞬にして忘れさせてくれました。日常のラーメンといえば、当時は「カップヌードル」や「金ちゃんヌードル」や「カップスター」や「サンポー、マルタイの袋麺」だった(うまかっちゃんはまだ販売されていなかった)ので、一休軒本店のラーメンは異次元の食べ物のように思え、畏怖の念を抱きながら食べていたのです。
白濁豚骨ラーメンの発祥店とされる三九@久留米の創業者兄弟から暖簾を引継ぎ、玉名に支店を出して九州の白濁豚骨ラーメンの伝播に大きく貢献した四ケ所さん(現在は佐賀市の玉屋西で「三九中華そば専門店」を営業中)からラーメンの手法を伝授されたという一休軒本店。現在では、「佐賀ラーメン」と呼べる特異な進化を遂げたそのラーメンは、多くの佐賀人にとって、いつまでも「佐賀で一番うまかラーメン」であり続けることでしょう。
高校生の頃だったでしょうか、「狂い咲きサンダーロード」という映画を一人で見に出かけ、三本立ての中のその作品を二度見るために合計四本の映画を見おえて一休軒本店に食べに行ったことがありました。その時初めて食べた「特製ラーメン(チャーシューが多めで、生卵が入っている)」の衝撃は、ある意味ナニの喪失よりインパクトがあったかも(笑)
私が社会人になった当時、先輩たちに連れられて飲みに出た場合の〆は必ず一休軒本店のラーメンでした。その当時は午前2時まで営業していたのですが、今では22時頃までの営業となってしまいました。時代の趨勢とはいえ哀しい限りです。
今現在、一休軒系のお店として営業(本店あるいはその暖簾分け店で修行した)しているのは、成竜軒(佐賀市高木瀬町・佐賀市愛敬町に支店有)・一休軒さがラーメン(佐賀市若楠2丁目)・一休軒鍋島店(佐賀市鍋島町八戸)・幸陽軒(佐賀市大財1丁目)・いちばん星(佐賀市愛敬町)・いちげん(佐賀市川副町)です。
また、一休軒本店に過去におられた従業員の方が何らかの形で寄与されたお店として、駅前ラーメン ビッグワン(佐賀市駅前中央1丁目)・葉隠(横浜市神奈川区六角橋)・長崎街道ラーメン 太公房(小城市牛津町)があります。
なお、一休軒本店から暖簾分けされたお店が長崎と京都にあったのですが(屋号はいずれも一休軒)、今では両店とも閉店してしまい残念です。
佐賀郡出身(現在は合併して佐賀市になっている)の私が通っていた小学校には、今では笑ってしまうような校則が存在していました。それは、「街に自分たちだけで出かけてはいけない」というもの。「街」というのは佐賀市の繁華街という意味です。どのくらいの田舎度かは容易に想像できますよね!?
周りの大人たちに「街さい行くけん、一緒にくっか?(来るか?)」と言われると、有頂天ものでした。今の自分に置き換えてみると、「沖縄に遊びに行かない?奢るから」てなレベルかなぁ。
といっても「街」ですることといえば、ゲームセンターでなけなしの小遣いを減らしたり、本屋で学校の図書館にはない本や雑誌を眺めたり(運がいいと買ってもらえた)ぐらいのものだったのです。しかし、それが至上の喜びだったわけで・・・。
そんな「街」行きでも、正月に家族で出かける初詣の際は格別でした。
というのも、佐賀神社と松原神社(二つの神社は隣接している)への初詣の後に、両神社の近くにある「一休軒本店」でラーメンを食べるという儀式があったからです。その当時の「一休軒本店」では、年末年始には店頭に行列が出来るくらい繁盛していました。行列の整理だけを担当する店員さんがいたくらいです。
酒を飲んで強気になってる私の親父が、店員に「はよ、食わせんかい(早く、食わせろよ)」と突っかかるのが、妙に恥ずかしかった記憶が残っています。
ラーメンの味には、いつもうっとりしていました。独特の甘味を内包しながら嫌味でなく、滑らかで優しい豚骨の風味は戸外の寒さを一瞬にして忘れさせてくれました。日常のラーメンといえば、当時は「カップヌードル」や「金ちゃんヌードル」や「カップスター」や「サンポー、マルタイの袋麺」だった(うまかっちゃんはまだ販売されていなかった)ので、一休軒本店のラーメンは異次元の食べ物のように思え、畏怖の念を抱きながら食べていたのです。
白濁豚骨ラーメンの発祥店とされる三九@久留米の創業者兄弟から暖簾を引継ぎ、玉名に支店を出して九州の白濁豚骨ラーメンの伝播に大きく貢献した四ケ所さん(現在は佐賀市の玉屋西で「三九中華そば専門店」を営業中)からラーメンの手法を伝授されたという一休軒本店。現在では、「佐賀ラーメン」と呼べる特異な進化を遂げたそのラーメンは、多くの佐賀人にとって、いつまでも「佐賀で一番うまかラーメン」であり続けることでしょう。
高校生の頃だったでしょうか、「狂い咲きサンダーロード」という映画を一人で見に出かけ、三本立ての中のその作品を二度見るために合計四本の映画を見おえて一休軒本店に食べに行ったことがありました。その時初めて食べた「特製ラーメン(チャーシューが多めで、生卵が入っている)」の衝撃は、ある意味ナニの喪失よりインパクトがあったかも(笑)
私が社会人になった当時、先輩たちに連れられて飲みに出た場合の〆は必ず一休軒本店のラーメンでした。その当時は午前2時まで営業していたのですが、今では22時頃までの営業となってしまいました。時代の趨勢とはいえ哀しい限りです。
今現在、一休軒系のお店として営業(本店あるいはその暖簾分け店で修行した)しているのは、成竜軒(佐賀市高木瀬町・佐賀市愛敬町に支店有)・一休軒さがラーメン(佐賀市若楠2丁目)・一休軒鍋島店(佐賀市鍋島町八戸)・幸陽軒(佐賀市大財1丁目)・いちばん星(佐賀市愛敬町)・いちげん(佐賀市川副町)です。
また、一休軒本店に過去におられた従業員の方が何らかの形で寄与されたお店として、駅前ラーメン ビッグワン(佐賀市駅前中央1丁目)・葉隠(横浜市神奈川区六角橋)・長崎街道ラーメン 太公房(小城市牛津町)があります。
なお、一休軒本店から暖簾分けされたお店が長崎と京都にあったのですが(屋号はいずれも一休軒)、今では両店とも閉店してしまい残念です。
|
|
|
|
コメント(6)
■第二回
あれは何年前のことだろうか。
小学校の低学年の長女と幼稚園入園前の次女を連れて、つれあいとともに四人でそのラーメン店で昼食をとった時のことだ。
四人で三杯のラーメンをオーダーしたのだが、出来上がると同時に店主のおばちゃんは、カウンター越しにラーメンを私たちに差し出すと、「ちょっと留守番してて」と言い残し、入口の戸を開けて外に出て行ってしまったのである。一人でこの店を切り盛りしているおばちゃんがいなくなれば、店内にいるのは客の私たちだけなのである。
「なんなんだ」と、いぶかしげな心持ちのままラーメンを食べ進めていると、数分で店主のおばちゃんは帰ってきた。その手には包装された直方形の包みが握られていた。
おばちゃんは、「これ、お嬢ちゃんたちに」と言いつつ包みをつれあいに渡した。
「孫が十人いるんだけど、みんな男の子でねぇ。小さな女の子を見ると、なんか買ってあげたくなるのよ」
その包みは、二軒先の和菓子屋から買ってきたカステラだった。この店には私は何度も足を運んでいたが、つれあいと子供たちは初めてだった。それなのにラーメンの代金よりも高いと思われるものをもらってしまったのだから、恐縮してしまっていた。それでもその行為を素直に受け入れられたは、満面の笑顔を浮かべたおばちゃんが、至極幸せそうに見えたからである。
そのお店は再来軒という屋号だった。2005年の2月に45年の歴史に幕を閉じた店である。
来来軒(来々軒)と同様に、日本中に数多くの同名屋号がある再来軒だが、その再来軒は、佐賀市のどんどんどんの森の東南の交差点角にあった。旧紡績通りと言った方が気分か・・・。若い頃は電電公社の交換手だったおばちゃんは、自宅の道路に面したスペースをラーメン屋さんに貸していたのだが、そのラーメン屋さんが業種変更に伴い出て行ったので、厨房設備がもったいないからと、見よう見まねでラーメン店を引き継いだという。それも最初は、交換手の仕事も続けながら。
国道の拡張工事に伴い、周りの店舗や住宅が立退いたり曳家したりていく中で、ぎりぎりまでラーメン店の営業を続けていた。見るからにオンボロな建屋は、最初に入店するまでは、かなりの勇気が必要な佇まいであった。店内はL字型のカウンター席のみで、丸椅子が8個並べられていたが、6人で満席という雰囲気であった。
期待しないではじめて食べた時に、私は少なからずショックを受けた。
なんとも滋味深い旨みを持った豚骨スープの旨みは、じわじわと体中に浸潤していくようだった。尖った旨みではない。敢えて言えば、愚鈍な旨みである。それがスープを飲み進める過程で、少しずつではあるが確実に心と体の琴線に触れてくるのである。元ダレも化学調味料も必要最小限に抑えられて作られたそのラーメンは、滋味哀愁と呼べるものだった。
そして、不思議だったのが、紅しょうがとの相性が抜群だったことだ。大抵のラーメンのスープは紅しょうがの強力な個性に負けて台無しになってしまうのだが、ここのスープはなぜかそれと調和していたのである。
また、チャーシューは煮豚と呼ぶにふさわしい、弄り回さないプレーンな仕込み具合のものだった。今でもシンプルなチャーシューが好きなのは、あの潔い味を大脳が記憶し続けているからなのかもしれない。
閉店間近にはすでに78歳だと言っていたおばちゃんは、移転補償をもらってお店をやるにしても、一人では無理だからと閉店を覚悟していた。守られるべきものが消えていくのを見届けるのも生きている証かと自分に言い聞かせて、感傷的な心持を受け流すしか私の為す術はなかった。
初めて食べてから、閉店までは数年だったのだけど、日々の仕込み具合や仕入れた豚骨の具合で違う表情を見せるそのラーメンは、愛おしい存在までに私の中で昇華していた。現在まで数多くのラーメンを食べてきたのだが、あのラーメンを超えるラーメンを私はまだ食べてはいない。
あれは何年前のことだろうか。
小学校の低学年の長女と幼稚園入園前の次女を連れて、つれあいとともに四人でそのラーメン店で昼食をとった時のことだ。
四人で三杯のラーメンをオーダーしたのだが、出来上がると同時に店主のおばちゃんは、カウンター越しにラーメンを私たちに差し出すと、「ちょっと留守番してて」と言い残し、入口の戸を開けて外に出て行ってしまったのである。一人でこの店を切り盛りしているおばちゃんがいなくなれば、店内にいるのは客の私たちだけなのである。
「なんなんだ」と、いぶかしげな心持ちのままラーメンを食べ進めていると、数分で店主のおばちゃんは帰ってきた。その手には包装された直方形の包みが握られていた。
おばちゃんは、「これ、お嬢ちゃんたちに」と言いつつ包みをつれあいに渡した。
「孫が十人いるんだけど、みんな男の子でねぇ。小さな女の子を見ると、なんか買ってあげたくなるのよ」
その包みは、二軒先の和菓子屋から買ってきたカステラだった。この店には私は何度も足を運んでいたが、つれあいと子供たちは初めてだった。それなのにラーメンの代金よりも高いと思われるものをもらってしまったのだから、恐縮してしまっていた。それでもその行為を素直に受け入れられたは、満面の笑顔を浮かべたおばちゃんが、至極幸せそうに見えたからである。
そのお店は再来軒という屋号だった。2005年の2月に45年の歴史に幕を閉じた店である。
来来軒(来々軒)と同様に、日本中に数多くの同名屋号がある再来軒だが、その再来軒は、佐賀市のどんどんどんの森の東南の交差点角にあった。旧紡績通りと言った方が気分か・・・。若い頃は電電公社の交換手だったおばちゃんは、自宅の道路に面したスペースをラーメン屋さんに貸していたのだが、そのラーメン屋さんが業種変更に伴い出て行ったので、厨房設備がもったいないからと、見よう見まねでラーメン店を引き継いだという。それも最初は、交換手の仕事も続けながら。
国道の拡張工事に伴い、周りの店舗や住宅が立退いたり曳家したりていく中で、ぎりぎりまでラーメン店の営業を続けていた。見るからにオンボロな建屋は、最初に入店するまでは、かなりの勇気が必要な佇まいであった。店内はL字型のカウンター席のみで、丸椅子が8個並べられていたが、6人で満席という雰囲気であった。
期待しないではじめて食べた時に、私は少なからずショックを受けた。
なんとも滋味深い旨みを持った豚骨スープの旨みは、じわじわと体中に浸潤していくようだった。尖った旨みではない。敢えて言えば、愚鈍な旨みである。それがスープを飲み進める過程で、少しずつではあるが確実に心と体の琴線に触れてくるのである。元ダレも化学調味料も必要最小限に抑えられて作られたそのラーメンは、滋味哀愁と呼べるものだった。
そして、不思議だったのが、紅しょうがとの相性が抜群だったことだ。大抵のラーメンのスープは紅しょうがの強力な個性に負けて台無しになってしまうのだが、ここのスープはなぜかそれと調和していたのである。
また、チャーシューは煮豚と呼ぶにふさわしい、弄り回さないプレーンな仕込み具合のものだった。今でもシンプルなチャーシューが好きなのは、あの潔い味を大脳が記憶し続けているからなのかもしれない。
閉店間近にはすでに78歳だと言っていたおばちゃんは、移転補償をもらってお店をやるにしても、一人では無理だからと閉店を覚悟していた。守られるべきものが消えていくのを見届けるのも生きている証かと自分に言い聞かせて、感傷的な心持を受け流すしか私の為す術はなかった。
初めて食べてから、閉店までは数年だったのだけど、日々の仕込み具合や仕入れた豚骨の具合で違う表情を見せるそのラーメンは、愛おしい存在までに私の中で昇華していた。現在まで数多くのラーメンを食べてきたのだが、あのラーメンを超えるラーメンを私はまだ食べてはいない。
■第3回
昭和32年に開店したジャズーバー・ロンドは、現在は佐賀市水ケ江にあるのだが、平成元年の移転前は佐賀市松原で営業していた。
私が始めてロンドを訪れたのは、二十歳ぐらいのことだろうか。松原の方のお店は一度改装をされているのだが、初回訪問時は改装前で「アンダーグランドな泥臭いジャズ喫茶」的空気が漂っていた。床は土間と呼ぶにふさわしいようなカンジだったので、雰囲気的には地下の隠れ家のような店であった。
ロンドは佐賀の地でジャズと酒(カクテルを含むあらゆるジャンルの酒が楽しめる)で、佐賀の文化の一部を形作ってきたといっても過言ではないようなお店なのである。
そんなロンドで飲んだくれていたある夜のこと、なぜかマスターとの会話の中身がラーメンになったことがあった。その会話の中でマスターが言うには「一休軒本店がこの店より少し前に開店したんだけど、昔はよく店を閉めた後に食べていたなぁ。今、最もその当時の味を伝えているのは成竜軒ですよ。」とのこと。
創業当時の一休軒本店のラーメンのスープは、現在よりいい意味で泥臭く獣臭が強かったそうである。その時代に店員として働いていたのが、現在の成竜軒@佐賀市高木瀬町大字長瀬(パチンコ店・ゴールドラッシュ高木瀬店駐車場内)の大将なんだそうである。一休軒本店で働いた後、駅前ラーメン・ビッグワンでも腕を振るわれ、その後に成竜軒を開店したといういきさつらしい。
その話を聞いた数日後に、初めて成竜軒のラーメンを食べに行った。パチンコ屋の駐車場のお店なんてと、眼中になかったのだが、食べてみてぶっ飛んだ。超絶な荒々しい出汁具合であった。豚骨ラーメンの極みとでも呼べるような。現在の一休軒本店は、たおやかで優しい口当たりなのだけど、それを繊細化ではなく矮小化だろうとあざ笑うかのようなラーメンだった。一休軒系ではお約束の羽釜での平アミでの麺揚げでなく、テボでの麺揚げだったのので、ちと心配げにラーメンを待っていたのたが杞憂だった。
大将はかなりの高齢のようなのだが、かくしゃくとしてラーメンを作られていた。噂では一休軒系のお店の中では、この大将に頭が上がる人はいないらしい。ストイックな頑なさで創業当時の一休軒の味を守り続けていることの意味と素晴らしさは、パチンコの合間に食事を摂る人には伝わらないのかもしれない。しかし、それがラーメンという食べ物のあるべき姿なのだろう。「たかがラーメン」でいいのである。その「たかが」の貴重さは、別離の時を迎え初めて気付くのであるが・・・。
成竜軒はパチンコ屋御用達のお店であるから、ラーメン以外のメニューも豊富です。お昼の混雑時を終えると、大将はお店からあがられていたようだが、今も元気でラーメンを作っていらっしゃるのだろうか?最近は食べていないので近況が定かではないのだが。
そんなお店の条件具合だから、初回のラーメンの感動をひっくり返すような、乳化しすぎの出汁の日もありました。しかし、あの一休軒の源流の味を数度経験すると、何度裏切られようと距離的条件がよければハードローテしたくなるお店なのである。
ちなみに現在は、息子さんが佐賀市大財で支店も営業されている。深夜4時まで営業されている夜専の店なので、飲みの〆には重宝なのである。
昭和32年に開店したジャズーバー・ロンドは、現在は佐賀市水ケ江にあるのだが、平成元年の移転前は佐賀市松原で営業していた。
私が始めてロンドを訪れたのは、二十歳ぐらいのことだろうか。松原の方のお店は一度改装をされているのだが、初回訪問時は改装前で「アンダーグランドな泥臭いジャズ喫茶」的空気が漂っていた。床は土間と呼ぶにふさわしいようなカンジだったので、雰囲気的には地下の隠れ家のような店であった。
ロンドは佐賀の地でジャズと酒(カクテルを含むあらゆるジャンルの酒が楽しめる)で、佐賀の文化の一部を形作ってきたといっても過言ではないようなお店なのである。
そんなロンドで飲んだくれていたある夜のこと、なぜかマスターとの会話の中身がラーメンになったことがあった。その会話の中でマスターが言うには「一休軒本店がこの店より少し前に開店したんだけど、昔はよく店を閉めた後に食べていたなぁ。今、最もその当時の味を伝えているのは成竜軒ですよ。」とのこと。
創業当時の一休軒本店のラーメンのスープは、現在よりいい意味で泥臭く獣臭が強かったそうである。その時代に店員として働いていたのが、現在の成竜軒@佐賀市高木瀬町大字長瀬(パチンコ店・ゴールドラッシュ高木瀬店駐車場内)の大将なんだそうである。一休軒本店で働いた後、駅前ラーメン・ビッグワンでも腕を振るわれ、その後に成竜軒を開店したといういきさつらしい。
その話を聞いた数日後に、初めて成竜軒のラーメンを食べに行った。パチンコ屋の駐車場のお店なんてと、眼中になかったのだが、食べてみてぶっ飛んだ。超絶な荒々しい出汁具合であった。豚骨ラーメンの極みとでも呼べるような。現在の一休軒本店は、たおやかで優しい口当たりなのだけど、それを繊細化ではなく矮小化だろうとあざ笑うかのようなラーメンだった。一休軒系ではお約束の羽釜での平アミでの麺揚げでなく、テボでの麺揚げだったのので、ちと心配げにラーメンを待っていたのたが杞憂だった。
大将はかなりの高齢のようなのだが、かくしゃくとしてラーメンを作られていた。噂では一休軒系のお店の中では、この大将に頭が上がる人はいないらしい。ストイックな頑なさで創業当時の一休軒の味を守り続けていることの意味と素晴らしさは、パチンコの合間に食事を摂る人には伝わらないのかもしれない。しかし、それがラーメンという食べ物のあるべき姿なのだろう。「たかがラーメン」でいいのである。その「たかが」の貴重さは、別離の時を迎え初めて気付くのであるが・・・。
成竜軒はパチンコ屋御用達のお店であるから、ラーメン以外のメニューも豊富です。お昼の混雑時を終えると、大将はお店からあがられていたようだが、今も元気でラーメンを作っていらっしゃるのだろうか?最近は食べていないので近況が定かではないのだが。
そんなお店の条件具合だから、初回のラーメンの感動をひっくり返すような、乳化しすぎの出汁の日もありました。しかし、あの一休軒の源流の味を数度経験すると、何度裏切られようと距離的条件がよければハードローテしたくなるお店なのである。
ちなみに現在は、息子さんが佐賀市大財で支店も営業されている。深夜4時まで営業されている夜専の店なので、飲みの〆には重宝なのである。
■第4回
佐賀の街から屋台が消えてどのくらい経つのだろうか?
その昔、佐賀神社の近辺には数多くの屋台が営業していた。
その中でも私のお気に入りは「まこと」という屋号のお店だった。頻繁に通っていたのだが「まこと」が「真」だったのか「誠」だったのか記憶が混沌としていて思い出せない。あるいは、ひらがなの「まこと」だったのだろうか?
佐賀神社前の交番のある変形交差点の北東の隅、水路に架けられた橋の上で「まこと」は営業していた。近所の屋台では出していないラーメンを食べさせてくれるので必然的に選択していた屋台であった。友人たちと飲んでいて盛り上がってしまうと、スナック(懐かしい響きだw)の閉店はおおよそ2時なので、不完全燃焼だった場合は、、あとひと盛り上がりを求めてお酒も飲めてラーメンで〆られるという「まこと」に通っていたのだ。何度「まこと」で夜明けを迎えたことだろうか。
佐賀に家を作る前の島田洋七さんが、同窓会のために佐賀入りしてて友人たちと「まこと」におられる姿や、「まこと」のファンで新聞広告(酒造メーカーの広告)の素材として「まこと」を紹介されていた筒井ガンコ堂さんが「まこと」のおでんをつまんでいる姿もよく見かけたなぁ。
おでんを一年中やっていて、厚揚げや大根やスジや佐賀では珍しかったじゃがいもをツマミに冷酒をあおっていた。そのおでんには風味を加味するためか「剣菱」がなみなみと注がれていたのが強烈に印象に残っている。
ぐでんぐでんになった体に〆の「まこと」のラーメンは無性に旨かった。アルコールに浸潤されすぎた体をニュートラルな立ち位置に戻してくれるような錯覚さえ覚えたものだ。何が旨かったのか説明できないが、その時のその場所に嵌りすぎているラーメンだったのである。
一度だけ、素面の状態で「まこと」に行ったことがあった。数杯の冷酒を数種のおでんと共に体内に流し込んだあとにラーメンをオーダーした。大将がラーメンを作るプロセスを初めて目で追ってみた。大量の旨味調味料が丼に入れられていた。旨味調味料肯定派な私なのだが、目前でこれほどの量を投入されてはと、たじろぐものだった。
ラーメンを食べてみると、異常に尖がった味でピリピリと舌を刺激する。苦手なラーメンだった・・・。
「ラーメンとはなんなのだろう」そんな漠然とした疑問を頭に巡らせながら、そのラーメンを食べ進めた。この味は今日だけの不出来なのだろうか?旨味調味料の投入シーンを目撃し大脳がネガティプモードに移行していたから不味く感じるのだろうか?
その「事件」のあとも、何度も「まこと」のラーメンを食べた。もちろん、ヘベレケ状態限定ではあったが・・・。そして二度と「まこと」のラーメンは裏切ることはなかったのである。
絶対音感と同意議な絶対味覚は決して存在しえない。十人十色二十舌というフレーズを私は使っているけど、一個人にとっても、その置かれた環境で味覚は大きくゆらぐのだ。味覚をデータベース化しようとしても、そのコンプリートは永遠に成し遂げられないミッションなのだ。そう言った意味では、薀蓄やこだわりの情報で語られるラーメンは、決して半永久的に人の心を繋ぎとめる事ができないのではないだろうか?
あぁ、あの「まこと」のラーメンをもう一度たべてみたいなぁ。
(あぁ、あの「まこと」のラーメンを食べていた頃にもう一度戻ってみたいなぁ。)
佐賀の街から屋台が消えてどのくらい経つのだろうか?
その昔、佐賀神社の近辺には数多くの屋台が営業していた。
その中でも私のお気に入りは「まこと」という屋号のお店だった。頻繁に通っていたのだが「まこと」が「真」だったのか「誠」だったのか記憶が混沌としていて思い出せない。あるいは、ひらがなの「まこと」だったのだろうか?
佐賀神社前の交番のある変形交差点の北東の隅、水路に架けられた橋の上で「まこと」は営業していた。近所の屋台では出していないラーメンを食べさせてくれるので必然的に選択していた屋台であった。友人たちと飲んでいて盛り上がってしまうと、スナック(懐かしい響きだw)の閉店はおおよそ2時なので、不完全燃焼だった場合は、、あとひと盛り上がりを求めてお酒も飲めてラーメンで〆られるという「まこと」に通っていたのだ。何度「まこと」で夜明けを迎えたことだろうか。
佐賀に家を作る前の島田洋七さんが、同窓会のために佐賀入りしてて友人たちと「まこと」におられる姿や、「まこと」のファンで新聞広告(酒造メーカーの広告)の素材として「まこと」を紹介されていた筒井ガンコ堂さんが「まこと」のおでんをつまんでいる姿もよく見かけたなぁ。
おでんを一年中やっていて、厚揚げや大根やスジや佐賀では珍しかったじゃがいもをツマミに冷酒をあおっていた。そのおでんには風味を加味するためか「剣菱」がなみなみと注がれていたのが強烈に印象に残っている。
ぐでんぐでんになった体に〆の「まこと」のラーメンは無性に旨かった。アルコールに浸潤されすぎた体をニュートラルな立ち位置に戻してくれるような錯覚さえ覚えたものだ。何が旨かったのか説明できないが、その時のその場所に嵌りすぎているラーメンだったのである。
一度だけ、素面の状態で「まこと」に行ったことがあった。数杯の冷酒を数種のおでんと共に体内に流し込んだあとにラーメンをオーダーした。大将がラーメンを作るプロセスを初めて目で追ってみた。大量の旨味調味料が丼に入れられていた。旨味調味料肯定派な私なのだが、目前でこれほどの量を投入されてはと、たじろぐものだった。
ラーメンを食べてみると、異常に尖がった味でピリピリと舌を刺激する。苦手なラーメンだった・・・。
「ラーメンとはなんなのだろう」そんな漠然とした疑問を頭に巡らせながら、そのラーメンを食べ進めた。この味は今日だけの不出来なのだろうか?旨味調味料の投入シーンを目撃し大脳がネガティプモードに移行していたから不味く感じるのだろうか?
その「事件」のあとも、何度も「まこと」のラーメンを食べた。もちろん、ヘベレケ状態限定ではあったが・・・。そして二度と「まこと」のラーメンは裏切ることはなかったのである。
絶対音感と同意議な絶対味覚は決して存在しえない。十人十色二十舌というフレーズを私は使っているけど、一個人にとっても、その置かれた環境で味覚は大きくゆらぐのだ。味覚をデータベース化しようとしても、そのコンプリートは永遠に成し遂げられないミッションなのだ。そう言った意味では、薀蓄やこだわりの情報で語られるラーメンは、決して半永久的に人の心を繋ぎとめる事ができないのではないだろうか?
あぁ、あの「まこと」のラーメンをもう一度たべてみたいなぁ。
(あぁ、あの「まこと」のラーメンを食べていた頃にもう一度戻ってみたいなぁ。)
■第5回
今年の三月一杯で、幸陽軒は閉店してしまった。
現在、店主ご夫婦は、佐賀市下田町(西部環状線沿い・旧イエローパンプキンの店舗)で幸陽閣という焼肉店を営業されている。佐賀牛のみを使用されている、おいしく良心的な焼肉店なのだが、あのラーメンを食べることは出来ない。
あの力技で圧倒されるような、図太く逞しいラーメンとは二度と邂逅することは出来ないのである。
その昔、佐賀市の飲み屋街の中心は、ラサンビルと南国ビルだった。はしごをしていると、何度となく二つのビルの間を往復したものである。
その途上に幸陽軒は存在していた。
幸陽軒の道路対面には、皆から竜崎と呼ばれていたスキンヘッドの愛想の良い呼び込みのおっちゃんがいて、3時までの営業なのに麺切れのための早めの閉店に出くわすと、「残念だったね。さっき暖簾を下ろしていたよ」なんて教えてくれたりもした。
佐賀に住んでいて、東京に行くと一番びっくりするのは飲食店の行列の存在であった。なんともその成り立ちなり仕組みが理解できないのである。特にラーメン店の行列は。気に入ったラーメン店が複数あり、どのお店も長らく通いつづけているならば、行列して待つなんて概念は発生しないのである。
しかしながら、幸陽軒の行列だけは別であった。飲みの〆に幸陽軒というのは、ある意味、疑う余地が微塵もない公理みたいなものだったのである。佐賀では稀有な飲食店の行列に加わるというのは、至極、当たり前の行動だった。
幸陽軒店主の川上さんは、一休軒本店で修行したあと佐賀市神野の高架下でラーメン店を開店したという。そのお店は飲食店としては場所が良くなく、客入りは芳しくなかったとか。佐賀市の大財通り沿いに移転したら、タクシードライバーの口コミなどで評判になり繁盛したらしい。その後、手狭なキャパシティーの解消のため飲み屋街の愛敬通りに移転した(所在地の住所は佐賀市大財一丁目)という事情らしい。
一休軒系のお店でありながら、そのラーメンの趣は異端だった。一休軒系の滋味あっさりとは、一線を画すものだったのである。
平均的なラーメン店と比べると数倍の量の豚骨を長時間煮詰めて取られていた出汁は、他に比類すべきものがないような「こってり濃厚」なものだった。「こってり濃厚」という言葉が、安易に脂の量を示す概念として語られることがある。しかしながら幸陽軒のスープの味は、脂に頼らない真の「こってり濃厚」だったのである。
時としてそのスープは褐色に輝いていた。その味が愛しくて、丼を抱きしめたくなるようなことが何度もあった。店内が満席になると、かなりの人数前の麺揚げが一度に行われていた。出てきたラーメンの麺は超やわやわで、デンプンの一歩手前かと悶絶しそうなこともあった。しかし、極上スープの存在の前では、「まあ、いいか。仕方ない」と妥協できたほどであった。
本来ラーメンは、スープと麺が織り成す味覚と食感を楽しむ食べ物のはずなのであるが、幸陽軒のラーメンに関しては、完全に他には活用できないケーススタディみたいな一杯だったのだ。大体は酸化していて苦味があったチャーシューとユル度MAXの麺は、完全に添え物だったのである。
大量の豚骨を使用していたので、季節によるその質の変動によるものなのか、今日はハズレだなと思うこともあった。しかしそれでもなお、幸陽軒のラーメンの呪縛から解き放たれることはなかったのである。
年齢的に長時間の仕込みが難しくなってきた、というのが閉店の理由らしく、後継者もいないようである。
一子相伝どころか、全くの一代で途絶えようとしている幸陽軒。
白毛馬が突然変異で生まれる確率は数万頭に一頭らしい。一方、一年間に開店するラーメン店は全国で5千店ほどとのこと。佐賀県内で一年間に新規開店するラーメン店は、多めに考えてもニ、三十店というところだろう。
とすれば、突然変異的な味を持っていた幸陽軒と似たようなラーメン店が、佐賀に新規開店する確率は、どう考えても白毛馬が生まれてくる確率より、かなり低くそうである。
白毛馬が、日本ダービーとエプソムダービーと凱旋門賞を三連覇するぐらいの確率だろうか。その確率を表す分数の分母は、恒河沙とか阿僧祇とか那由他なんていう天文学的数字になるに違いない。
いずれにせよ、幸陽軒の行列に並んでいる間に酔いが若干醒めて、隣の甘栗屋で家族へのお土産を買うなんて夜は、二度と訪れることはないのである。
※久留米を発祥とする幸陽軒(丸幸ラーメンセンターもその系統)と、佐賀市に存在していた幸陽軒とは、何ら関係ありません。
今年の三月一杯で、幸陽軒は閉店してしまった。
現在、店主ご夫婦は、佐賀市下田町(西部環状線沿い・旧イエローパンプキンの店舗)で幸陽閣という焼肉店を営業されている。佐賀牛のみを使用されている、おいしく良心的な焼肉店なのだが、あのラーメンを食べることは出来ない。
あの力技で圧倒されるような、図太く逞しいラーメンとは二度と邂逅することは出来ないのである。
その昔、佐賀市の飲み屋街の中心は、ラサンビルと南国ビルだった。はしごをしていると、何度となく二つのビルの間を往復したものである。
その途上に幸陽軒は存在していた。
幸陽軒の道路対面には、皆から竜崎と呼ばれていたスキンヘッドの愛想の良い呼び込みのおっちゃんがいて、3時までの営業なのに麺切れのための早めの閉店に出くわすと、「残念だったね。さっき暖簾を下ろしていたよ」なんて教えてくれたりもした。
佐賀に住んでいて、東京に行くと一番びっくりするのは飲食店の行列の存在であった。なんともその成り立ちなり仕組みが理解できないのである。特にラーメン店の行列は。気に入ったラーメン店が複数あり、どのお店も長らく通いつづけているならば、行列して待つなんて概念は発生しないのである。
しかしながら、幸陽軒の行列だけは別であった。飲みの〆に幸陽軒というのは、ある意味、疑う余地が微塵もない公理みたいなものだったのである。佐賀では稀有な飲食店の行列に加わるというのは、至極、当たり前の行動だった。
幸陽軒店主の川上さんは、一休軒本店で修行したあと佐賀市神野の高架下でラーメン店を開店したという。そのお店は飲食店としては場所が良くなく、客入りは芳しくなかったとか。佐賀市の大財通り沿いに移転したら、タクシードライバーの口コミなどで評判になり繁盛したらしい。その後、手狭なキャパシティーの解消のため飲み屋街の愛敬通りに移転した(所在地の住所は佐賀市大財一丁目)という事情らしい。
一休軒系のお店でありながら、そのラーメンの趣は異端だった。一休軒系の滋味あっさりとは、一線を画すものだったのである。
平均的なラーメン店と比べると数倍の量の豚骨を長時間煮詰めて取られていた出汁は、他に比類すべきものがないような「こってり濃厚」なものだった。「こってり濃厚」という言葉が、安易に脂の量を示す概念として語られることがある。しかしながら幸陽軒のスープの味は、脂に頼らない真の「こってり濃厚」だったのである。
時としてそのスープは褐色に輝いていた。その味が愛しくて、丼を抱きしめたくなるようなことが何度もあった。店内が満席になると、かなりの人数前の麺揚げが一度に行われていた。出てきたラーメンの麺は超やわやわで、デンプンの一歩手前かと悶絶しそうなこともあった。しかし、極上スープの存在の前では、「まあ、いいか。仕方ない」と妥協できたほどであった。
本来ラーメンは、スープと麺が織り成す味覚と食感を楽しむ食べ物のはずなのであるが、幸陽軒のラーメンに関しては、完全に他には活用できないケーススタディみたいな一杯だったのだ。大体は酸化していて苦味があったチャーシューとユル度MAXの麺は、完全に添え物だったのである。
大量の豚骨を使用していたので、季節によるその質の変動によるものなのか、今日はハズレだなと思うこともあった。しかしそれでもなお、幸陽軒のラーメンの呪縛から解き放たれることはなかったのである。
年齢的に長時間の仕込みが難しくなってきた、というのが閉店の理由らしく、後継者もいないようである。
一子相伝どころか、全くの一代で途絶えようとしている幸陽軒。
白毛馬が突然変異で生まれる確率は数万頭に一頭らしい。一方、一年間に開店するラーメン店は全国で5千店ほどとのこと。佐賀県内で一年間に新規開店するラーメン店は、多めに考えてもニ、三十店というところだろう。
とすれば、突然変異的な味を持っていた幸陽軒と似たようなラーメン店が、佐賀に新規開店する確率は、どう考えても白毛馬が生まれてくる確率より、かなり低くそうである。
白毛馬が、日本ダービーとエプソムダービーと凱旋門賞を三連覇するぐらいの確率だろうか。その確率を表す分数の分母は、恒河沙とか阿僧祇とか那由他なんていう天文学的数字になるに違いない。
いずれにせよ、幸陽軒の行列に並んでいる間に酔いが若干醒めて、隣の甘栗屋で家族へのお土産を買うなんて夜は、二度と訪れることはないのである。
※久留米を発祥とする幸陽軒(丸幸ラーメンセンターもその系統)と、佐賀市に存在していた幸陽軒とは、何ら関係ありません。
■外伝1「佐賀ラーメン慕情」
「心のミシュラン」は前回までで5回書いていますが、今回は趣向をちょいと変えて「外伝」ということで。
すでに閉店してしまった、三九軒の回顧をしてみようというものです。実はそんなに数多く食べておらず、心のミシュランで取り上げるのは不適切なのですが、外伝ということならその歴史から書く価値はあります。
なお、その食べた時期もラーメンに開眼(笑)する前だったので、味の記憶も曖昧ですが、こってりと言うより滋味系の味だったように記憶しています。
佐賀市松原三丁目の楊柳亭の近くで営業していたのですが、白濁豚骨ラーメンの発祥店と言われている、久留米にあった屋台「三九」の創業者である杉野兄弟の弟さん・昌俊さんのお店でした。
なお、福岡にあった「三馬路」から影響を受けた「赤のれん」が白濁豚骨スープの起源だとする説もあるようですが、どうやらこちらはアイヌ料理からヒントを受けて白濁豚骨に辿り着いたのだとか。
「三九」を現「三九中華そば専門店」の店主・四ヶ所さんに譲ったあと、久留米で一時ラーメン店を開業されていたようですが、昭和三十年に佐賀で移転開業されたようです。くしくも翌年に、四ヶ所さんもその近く・玉屋西に開業されたのです。(二店と近い一休軒本店の開業はその後のようである。)
なお、四ヶ所さんによると、「三九」を譲り受けた時は、出汁やチャーシューの仕込み方を簡単に教わっただけで、味は別物だったようです。四ヶ所さんが作った「三九玉名店」の影響で九州各地に白濁豚骨ラーメンは伝播したのだとか。
また、兄の杉野勝見さんは、「三九」後は北九州で来々軒を立ち上げられています。
「三九軒」は私が「麺日記」を始める前の平成13年に廃業されたので、残念ながら私はその画像を持っていません。しかしながら、お客にいろいろと声をかけてくれていた奥さん語り口は、何故だかよく覚えています。私の友人であるあまちゃんの「あまおじさんのらーめん紀行♪」の「三九軒」の紹介ページが、そのへんの雰囲気をよく伝えています。
その奥さんが亡くなったのが閉店の理由だったようです。
実はその後、旧北方町で息子さんが「三九軒」の屋号を復活させて営業されたのですが、味は先代の「三九軒」とは異なっていました。「新三九軒」は武雄市内などで移転しながら営業されていたようでしたが、いつの間にか閉店されたようです。
そして、去年の夏に「えま」という屋号で、その息子さんが武雄市の県総合庁舎北、パチ屋のゴールデンラッキーの南側にラーメン店を開店されたようです。今年の四月に味納喜知を食べた後に寄ってみたのですが、営業していませんでした。店休日だったのでしょうか。
「三九」から「来々軒」「三九軒」「三九中華そば専門店」へとつながる系譜は、佐賀ラーメンファンにとっては、かなり興味深い歴史です。
「三九軒」のラーメンを今一度食べてみたいという願望は、もはや成し遂げられないものになってしまったようです。
「心のミシュラン」は前回までで5回書いていますが、今回は趣向をちょいと変えて「外伝」ということで。
すでに閉店してしまった、三九軒の回顧をしてみようというものです。実はそんなに数多く食べておらず、心のミシュランで取り上げるのは不適切なのですが、外伝ということならその歴史から書く価値はあります。
なお、その食べた時期もラーメンに開眼(笑)する前だったので、味の記憶も曖昧ですが、こってりと言うより滋味系の味だったように記憶しています。
佐賀市松原三丁目の楊柳亭の近くで営業していたのですが、白濁豚骨ラーメンの発祥店と言われている、久留米にあった屋台「三九」の創業者である杉野兄弟の弟さん・昌俊さんのお店でした。
なお、福岡にあった「三馬路」から影響を受けた「赤のれん」が白濁豚骨スープの起源だとする説もあるようですが、どうやらこちらはアイヌ料理からヒントを受けて白濁豚骨に辿り着いたのだとか。
「三九」を現「三九中華そば専門店」の店主・四ヶ所さんに譲ったあと、久留米で一時ラーメン店を開業されていたようですが、昭和三十年に佐賀で移転開業されたようです。くしくも翌年に、四ヶ所さんもその近く・玉屋西に開業されたのです。(二店と近い一休軒本店の開業はその後のようである。)
なお、四ヶ所さんによると、「三九」を譲り受けた時は、出汁やチャーシューの仕込み方を簡単に教わっただけで、味は別物だったようです。四ヶ所さんが作った「三九玉名店」の影響で九州各地に白濁豚骨ラーメンは伝播したのだとか。
また、兄の杉野勝見さんは、「三九」後は北九州で来々軒を立ち上げられています。
「三九軒」は私が「麺日記」を始める前の平成13年に廃業されたので、残念ながら私はその画像を持っていません。しかしながら、お客にいろいろと声をかけてくれていた奥さん語り口は、何故だかよく覚えています。私の友人であるあまちゃんの「あまおじさんのらーめん紀行♪」の「三九軒」の紹介ページが、そのへんの雰囲気をよく伝えています。
その奥さんが亡くなったのが閉店の理由だったようです。
実はその後、旧北方町で息子さんが「三九軒」の屋号を復活させて営業されたのですが、味は先代の「三九軒」とは異なっていました。「新三九軒」は武雄市内などで移転しながら営業されていたようでしたが、いつの間にか閉店されたようです。
そして、去年の夏に「えま」という屋号で、その息子さんが武雄市の県総合庁舎北、パチ屋のゴールデンラッキーの南側にラーメン店を開店されたようです。今年の四月に味納喜知を食べた後に寄ってみたのですが、営業していませんでした。店休日だったのでしょうか。
「三九」から「来々軒」「三九軒」「三九中華そば専門店」へとつながる系譜は、佐賀ラーメンファンにとっては、かなり興味深い歴史です。
「三九軒」のラーメンを今一度食べてみたいという願望は、もはや成し遂げられないものになってしまったようです。
■第6回
「佐賀ラーメンの代表と言えば一休軒だ」というのには、多くの佐賀人が同意できることだろう。
昭和三十年代前半に、久留米ラーメンを源流とすると思われる一休軒本店は創業した。現在の一休軒系の店を系統別に整理してみると、以下のようになる。
◆源流系
開店当初の一休軒本店の味に近い店。
・成竜軒(本店及び大財店)
・駅前ラーメン・ビッグワン(※1)
・葉隠(※2)
◆現本店系
現在の本店及びその味に近い店。
・一休軒本店(※3)
・一休軒さがラーメン
・一休軒本庄袋店
◆鍋一系
一休軒鍋島店とその弟子のお店。
・一休軒鍋島店
・いちばん星(※4)
・いちげん
◆独自発展系
現本店の味とはまったく違う、独自の発展を遂げた特異なお店。
・幸陽閣(旧幸陽軒)
一休軒鍋島店で三年間修行した「いちげん」店主が、自分の店を開店させたのは、1998年のことである。
開店から数年は、佐賀市川副町という飲食店としては悪条件である立地も重なってか、閑古鳥が鳴いていたという。
その後、師匠の教えのコアな部分は踏襲しつつ独自の工夫を重ね作り出した出汁の魅力は、そのラーメンを徐々に客を呼べるものへと進化させていった。
開店から満十年を経過し、その軽やかなのに奥深く濃厚なスープの風味は、こってりのレベルが脂の多寡で語られることの多いオサレなズージャ・バンダナ系ラーメンが、ものすごく陳腐なものに思えるほどに魅力的である。
そんな「いちげん」に、私は激しく通い倒している。様々な表現を駆使しても、ブログにアップするのに困るくらいの回数である。
いちげんのスープは、日々のブレや時間によるブレは大きいと感じる。
豚骨ラーメンは特にブレが大きいラーメンだと思う。ちょいとした客入りの変化で出汁が変わっていくのである。そういう意味ではリピーターとしてしか、より深くは楽しめないラーメンだと言えるのかもしれない。
元ダレ主導のケバいラーメンだったり、過剰な味の足算がされたラーメンでは、味の均一化は図れるだろうが、面白味はない。
あたかも四季の移り変わりを慈しむように、微妙な日々の変化を楽しめるのは、滋味哀愁な佐賀ラーメン全体に共通する特性なのだ。
遠方から駆けつけて、たまたまハズレを引いてしまうのも一期一会というものだろう。
漫画家でイラストレーターの江口寿史は、自身の好きなラーメン店である「たんたん亭(東京都杉並区)」を評して、「この店のカウンターに座ってラーメンを待つことは僕の小さな幸せのひとつだ。いつも開店する頃に行く。」「日によってブレもある。かなりある。でも平均値のとこでブレのまったくない店のどこがいいの?イマイチの時もまあまあの時もあるから、とびっきり旨い時の喜びが際立つじゃん。」と語っている。(※5)
豚骨ラーメンは、どんな名店であろうが、日々その表情を変える。同じ味を毎日提供出来てこそ一流の料理人なのであろうが、こと豚骨ラーメンについては、例外のように思う。
作り手にも食べ手にも絶対に予知できない、辿り着くまで見ることの許されないサンクチュアリが豚骨ラーメンにはあるのだ。
その違いを楽しむのはリピーターの特権であるのだ。あるリピート店の味が、決定的に許せないラインに堕ちたら、二度と行かないだけである。至極シンプル(ある意味残酷)。
「いちげん」は、ここ最近の一ヶ月は店主の入院加療のために休業していが、1月6日から、やっと営業を再開したのである。
冬季限定の佐賀海苔の一番摘みのものを使った「海苔ラーメン」を提供開始することなく休業に入っていたのだが、やっとあの味に邂逅できる時が来たことを純粋に嬉しく思い、ワクワク感が止まらない私である。
※1 本店で修行された成竜軒の店主が一時働いておられたが、現在は一休軒にゆかりのある方はいない。 しかし、ラーメンの味は現在も、一休軒の源流に近いと思われる。
※2 横浜市のお店。食べた事がないので正直自信がないが、一休軒本店で修行された方から手ほどきを受けたらしいので、多分、源流系ではないかと思う。
※3 現在は閉店してしまって営業していないが、京都市と長崎市に本店の暖簾分け店(屋号は二店とも「一休軒」)が存在していた。
※4 げんこつのみを使うのが鍋一の原則であるが、現在のいちばん星は他部位の豚骨も使っている。
※5 江口寿史・徳丸真人『ラーメン道場やぶり』集英社、2008年、228頁。
「佐賀ラーメンの代表と言えば一休軒だ」というのには、多くの佐賀人が同意できることだろう。
昭和三十年代前半に、久留米ラーメンを源流とすると思われる一休軒本店は創業した。現在の一休軒系の店を系統別に整理してみると、以下のようになる。
◆源流系
開店当初の一休軒本店の味に近い店。
・成竜軒(本店及び大財店)
・駅前ラーメン・ビッグワン(※1)
・葉隠(※2)
◆現本店系
現在の本店及びその味に近い店。
・一休軒本店(※3)
・一休軒さがラーメン
・一休軒本庄袋店
◆鍋一系
一休軒鍋島店とその弟子のお店。
・一休軒鍋島店
・いちばん星(※4)
・いちげん
◆独自発展系
現本店の味とはまったく違う、独自の発展を遂げた特異なお店。
・幸陽閣(旧幸陽軒)
一休軒鍋島店で三年間修行した「いちげん」店主が、自分の店を開店させたのは、1998年のことである。
開店から数年は、佐賀市川副町という飲食店としては悪条件である立地も重なってか、閑古鳥が鳴いていたという。
その後、師匠の教えのコアな部分は踏襲しつつ独自の工夫を重ね作り出した出汁の魅力は、そのラーメンを徐々に客を呼べるものへと進化させていった。
開店から満十年を経過し、その軽やかなのに奥深く濃厚なスープの風味は、こってりのレベルが脂の多寡で語られることの多いオサレなズージャ・バンダナ系ラーメンが、ものすごく陳腐なものに思えるほどに魅力的である。
そんな「いちげん」に、私は激しく通い倒している。様々な表現を駆使しても、ブログにアップするのに困るくらいの回数である。
いちげんのスープは、日々のブレや時間によるブレは大きいと感じる。
豚骨ラーメンは特にブレが大きいラーメンだと思う。ちょいとした客入りの変化で出汁が変わっていくのである。そういう意味ではリピーターとしてしか、より深くは楽しめないラーメンだと言えるのかもしれない。
元ダレ主導のケバいラーメンだったり、過剰な味の足算がされたラーメンでは、味の均一化は図れるだろうが、面白味はない。
あたかも四季の移り変わりを慈しむように、微妙な日々の変化を楽しめるのは、滋味哀愁な佐賀ラーメン全体に共通する特性なのだ。
遠方から駆けつけて、たまたまハズレを引いてしまうのも一期一会というものだろう。
漫画家でイラストレーターの江口寿史は、自身の好きなラーメン店である「たんたん亭(東京都杉並区)」を評して、「この店のカウンターに座ってラーメンを待つことは僕の小さな幸せのひとつだ。いつも開店する頃に行く。」「日によってブレもある。かなりある。でも平均値のとこでブレのまったくない店のどこがいいの?イマイチの時もまあまあの時もあるから、とびっきり旨い時の喜びが際立つじゃん。」と語っている。(※5)
豚骨ラーメンは、どんな名店であろうが、日々その表情を変える。同じ味を毎日提供出来てこそ一流の料理人なのであろうが、こと豚骨ラーメンについては、例外のように思う。
作り手にも食べ手にも絶対に予知できない、辿り着くまで見ることの許されないサンクチュアリが豚骨ラーメンにはあるのだ。
その違いを楽しむのはリピーターの特権であるのだ。あるリピート店の味が、決定的に許せないラインに堕ちたら、二度と行かないだけである。至極シンプル(ある意味残酷)。
「いちげん」は、ここ最近の一ヶ月は店主の入院加療のために休業していが、1月6日から、やっと営業を再開したのである。
冬季限定の佐賀海苔の一番摘みのものを使った「海苔ラーメン」を提供開始することなく休業に入っていたのだが、やっとあの味に邂逅できる時が来たことを純粋に嬉しく思い、ワクワク感が止まらない私である。
※1 本店で修行された成竜軒の店主が一時働いておられたが、現在は一休軒にゆかりのある方はいない。 しかし、ラーメンの味は現在も、一休軒の源流に近いと思われる。
※2 横浜市のお店。食べた事がないので正直自信がないが、一休軒本店で修行された方から手ほどきを受けたらしいので、多分、源流系ではないかと思う。
※3 現在は閉店してしまって営業していないが、京都市と長崎市に本店の暖簾分け店(屋号は二店とも「一休軒」)が存在していた。
※4 げんこつのみを使うのが鍋一の原則であるが、現在のいちばん星は他部位の豚骨も使っている。
※5 江口寿史・徳丸真人『ラーメン道場やぶり』集英社、2008年、228頁。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
佐賀ラーメンが好きだ。 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
佐賀ラーメンが好きだ。のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75488人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6448人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208289人