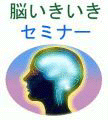第5回脳いきいきセミナー資料
(2007年6月の資料)
「在宅死」;看取りと癒し
藤・霽月 (ふじ・せいげつ)
1) はじめに
2)「在宅末期医療」で出来ること(その1)
3)「在宅末期医療」の出来ること(その2)
4)拒食ということ
5)より良く生かせ
6)呆けとは何か
7)「死の受容」とは
8)しげ子さんが笑った(その一)
9)しげ子さんが笑った (そに二)
10)ゆるやかな死(その一)
11)ゆるやかな死(その二)
12)ゆるやかな死(その三)
13)苦しみを和らげた上での死(その一)
14)苦しみを和らげた上での死(その二)
15)苦しみを和らげた上での死(その三)
1)はじめに
医者になって19年、癌や呼吸不全・難病を中心に650人程の「死」に立ち会ってきました。「死」は生あるものの「宿命」であり、「良い死に方」を得るには、その「宿命」であることを如何に受容するか、その前に自分が如何に生きてきたか、その後のこととして「死」を迎える家族や友人等周囲の条件が整っているかということが必要であることを患者さんから教わってきました。
現在は、ほとんど患者さんが病院で亡くなられる時代です。私が立ち会った内の550人程も、病院勤務時代の経験です。一般的な病院は、基本的に効率的に病気を治し延命を得るためのシステムで動いています。その中では医療者が一人の個人として少しでも「より良い死」を迎えさせてあげたいと考えたとしても、組織としての限界があります。私自身、1日100人の外来と50人の病棟廻診を行う中、3人の死亡診断書を書くという経験をしたことがあります。そこには「癒し」の時間を取る余裕はありませんでした。12年前、私の親友が亡くなる時、「最後の儀式」としての心臓マッサ−ジのために、家族と共に病室から出されるという経験もしました。
こんなこともあって、7年前に「在宅末期医療」のできる診療所を開設しました。やはり家族に見守られて、住み慣れた自宅で亡くなるのは、温かみがあって心地良いものがあります。まず驚いたのは、癌の痛みに対するモルヒネの量が「在宅死」の場合には格段に少なくなることです。これは癌が周りの臓器を食い散らす痛さだけでなく、心理的な影響も受けるものであり、自宅で家族に支えられることにより、和らげられるのだろうと考えます。こんな経験をすると、夜中や休日の往診の疲れも吹っ飛んでしまいます。
2)「在宅末期医療」で出来ること(その1)
癌の末期では、痛みを取ることだけが問題で、日本の医者はモルヒネの使い方が下手だから癌の患者が苦しむのだといった誤解を持たれている方が多くおられます。前号でお話しましたように、癌の痛みは心理的な影響を強く受けるものであり、不安感を持っておられると、痛みはより強いものとなります。またそういう方に限って、痛みの程度を家族を通して訴えられるため、対応に遅れが出て、痛みは耐えられないものとなってしまいます。医療者を信頼して、早めに直接訴えて頂くことが、まず必要だろうと思います。
また癌の末期の十中八、九はモルヒネだけで楽に死ねることは確かです。しかし、出血や呼吸困難、痙攣等それ以外の苦痛を取る処置が必要になる場合もあります。色々な処置が必要であったけれども、在宅で比較的「良い死に方」の出来た方のお話をします。
Aさん(80才、男性)は胆汁を通す管に出来た癌が肝臓と食道近くに転移している状態で公立病院に入院しておられました。胆汁を外に出すチュ−ブと、食べれないため心臓近くの太い静脈まで栄養補給のためのチュ−ブが入り、尿を取るチュ−ブを付けた状態でした。大変な風呂好きで、そんな状態でも毎日風呂に入りたいとして12月20日退院されてきました。それらチュ−ブの管理のため、1日に2、3回の往診が必要な状態でした。正月の間も続きました。家族の方々は大変心優しく、そして熱心に看病されておられました。携帯用の補液のポンプとモルヒネを用い、車椅子に乗ってではありましたが、梅の花見にも行けました。亡くなられる2、3日前は、少し呼吸困難も訴えられ、酸素も持ち込みました。3月29日、住み慣れた家で満足そうな顔をして息を引き取られました。
3)「在宅末期医療」の出来ること(その2)
致死的な病気あるいは「老衰」があって食べられなくなったら、そのまま何もせず亡くならせるのが良いという主張があります。尊厳死あるいは消極的安楽死の主張の中に、安易にこの考え方を取り入れられる方がおられます。しかし、これは個々の病状や置かれた状況を考慮しなければ、致死的な病気や重い「障害」を持った人間は早く死ねば良いという危険な考え方につながりかねません。
前号でお話しました末期的な癌で、中心静脈(心臓に近い所の太い静脈)と胆汁の管と尿への3本のチュ−ブを付けたAさんに、何故静脈からの栄養補給をしたのかといった御批判もあろうかと思います。その回答の一つは、末期的な癌と言えども、体力が残っている状態で突然餓死させられるのは、大変苦痛を伴うものであるということです。尊厳死あるいは消極的安楽死とは、体力が相当に弱って、余り苦痛を感じなくなった段階での餓死と考えるべきでしょう。
もう一つは、癌であり死が迫っているという「宿命」を受容し、単に臥して死を待つのでは無く、残り少ない命を最後まで精一杯楽しもう、出来るところまで仕事に、趣味に生き続けようとすることに、人間の生き様として価値があるように思います。前向きに生きるということは、少しでも長く生き続けようとすることでは無く、残り少ない命の中身を少しでも高めようとすることと考えます。そのための手段の一つとして中心静脈栄養が用いられるのです。「在宅死」を請け負うということは、そのような患者さんの姿勢に共感し、それを支えるということです。そこから「生きる」ということを教えられ、自分を磨かせて頂けるという感謝の気持ちで一杯の仕事であると思っています。
4)拒食ということ
病院に勤務していた頃は、「癒し」の時間が思うように取れなかったという反省から、開業医となってからは出来るだけカウンセリングを含め診察時間を長く取るようにしました。そんなこともあって、「心の病」で転々と医療機関を変わられてきた患者さんが相談に来られるようになってきました。最近は精神科通院中の方や拒食症の方も来られるようになりました。
Bさん(14才、女性)は、42キロあった体重が29キロまで減少して来院。料理店経営のお父さんを慕っておられ、自分は中学卒業後は調理師になる方向で進路を考えていたところ、学業でもスポ−ツでもかなり優秀であったため、お母さんや学校の先生からは進学を薦められていたようです。友人関係の悩みもあったようです。朝になると腹痛やめまいが起こることから学校になかなか行けなくなり、そこから成績も悪くなり、それがさらにストレスとなって、食べれば吐く、吐くから食べないという状態になったようでした。
このような患者さんには、時間をかけて話を聞き、「あなたこそ生きている価値があるのですよ。」ということを何度も何度も伝えていくことしか、我々に出来ることはないだろうと考えております。ある時、寝たきりで流動食しか食べられない患者さんでも、同じ味の物ばかり与えていると食欲が落ちてくるので、味を少し変えてやることも必要となるという話をしました。その後、1年浪人して体力を回復し、福祉系の高校へ入学されたようです。介護の解る調理師が生まれたら、面白いだろうなと考えています。
食べられなくなったら消極的安楽死をと単純に考えることは危険です。生活リハビリ研究所の三好春樹さんは寝たきりや痴呆の方の拒食を消極的自殺と呼んでおられます。次回はそんな話をします。
5)より良く生かせ
「『消極的自殺』は『より良く生かせ』の訴えです。」というのは、生活リハビリ研究所の三好春樹さんがよく言われる言葉です。寝たきりや痴呆の方が気分を害されると「異常行動」に出る場合と「消極的自殺」に向かう場合があります。
10月号の「いのちを見失うとき」を書かれた祖父江文宏先生の暁学園と「呆け老人をかかえる家族の会愛知支部」の事務局である尾之内直美さんの家が私の診療所の近くにあります。その二つが一緒になって、家族の虐待から保護されている子供と痴呆や寝たきりの要介護者との「ふれ合いの場」を設けておられます。そこに私も少しばかりのお手伝いに入っております。傷ついた者同士が互いに癒し合う不思議な空間が生まれております。
18年前から高血圧症で当院にかかっていたCさん(80才女性)は、3年前に軽い脳梗塞となり、息子さん達は介護の出来るようにと家を建て替えました。その頃から足腰も弱り、痴呆も始まりました。けがをさせないため、なるべく家に居させるようにとされたようです。そのため返って食が細り、粥も吐いてしまうようになりました。何か良い方法はないかと考え、暁学園デイサ−ビスを紹介しました。行く時は大変嫌がられ、抵抗されたとのことでしたが、子供達と遊んでいるうちに、笑顔も見られるようになってきました。昼食は、自分のために出された粥には手をつけられず、子供達のためのちらし寿司を希望され、お代わりまでして食べて帰られました。
痴呆というと「異常行動」ばかりが強調されているように思います。痴呆でも楽しければ笑いますし、思うようにやってもらえれば感謝もします。「呆けてもこころは生きている」は、「呆け老人をかかえる家族の会」の標語のようになっている言葉です。
6)呆けとは何か
「呆けてもこころは生きている」と書きました。このお話をすると、「では痴呆とは何か」という質問を受けることがあります。世間の多くは、まだこれを「心の病」あるいは「精神的な病気」と捉えているようです。15年程「痴呆」の要介護者の方々の診てきました経験から、現場の感覚で現在どう捉えているかをお話します。
高度の精神的な営みは脳の前の部分(大脳の前頭葉の一部)が司っています。古い記憶は脳の後ろの部分(後頭葉の一部)にあります。これは見ることの中枢の近くにあります。近い記憶は脳の横の部分(側頭葉の一部)にあります。これは聴覚の中枢の近くにあり、観念的な記憶にも強いところと思われます。この近い記憶の中枢が衰えてくるのが「痴呆」という状態と考えます。近い記憶が抜け落ち古い記憶が鮮明になることから、人間関係や生活に障害を来すというのが、特に「痴呆」の初期の実体です。但し観念的な記憶の弱りから理性も衰えていくこと、進行すれば幻覚・幻聴も現れることは否定できませんが、主体はこちらにあると考えます。
末期医療(ホスピスケア)の教科書的存在としてよく使われます本として、E・キュブラ−・ロスの「死ぬ瞬間」(読売新聞社発行)があります。死を前にして、あるいは重大な障害を得た時に人間はまず怒り(何故自分がこんな目に合わなければならないのか)、次に取引(もっと良い医者は居ないのか、あるいはもっと金を出せば何とかなるのではないか)を考え、そして抑うつ(やはり駄目か)となり、その後受容に至ると書かれています。「痴呆」では特に初期が最も厄介とされるのは、人間関系と生活の障害と、このことから来る本人・家族の「怒り」が合わさって、暴力あるいは異常行動が現れることにあるのだろうと思います。
7)「死の受容」とは
自己紹介を求められた時、「ボランティア歴二十六年という変わり者の医者です。」から始めることにしています。それに「結婚式も仏式で挙げたほどの仏教徒、真宗門徒です。」と加えることもあります。色々な宗教宗派の、特に国際的なボランティアとの交流が深くなるにつれ、自分の育てられた環境の中にあった信仰を、還って強く意識すると同時に、例え異なったものであっても他の人の信仰も尊重するようになってきました。この経験が在宅死の看取りでも役に立っています。しかし「自立と共生」をテ−マとするボランティアの信念と「共生と自律」の教えの間には合い通ずる部分と折り合いを着けなければならない部分とがあり、悩みもあるということは、また別の機会にお話したいと思います。
さて、そのようなボランティア同士の交流の中で、前号で触れましたE・キュブラ−・ロスの下、チャプレン(キリスト教的に「死の受容」を導く仕事)を経験されたニノミヤ・ヘンリ−・アキイエ関西学院大学教授と呑む機会がありました。しっかりした信仰のある方と完璧な無神論者は「死の受容」までの道のりが短く、苦しみも少ないが、中途半端な信仰を持つ人や知識人として宗教を哲学する人は苦しまれることも多いということで、意見が一致しました。
立派な宗教家が、死を目前にして狼狽えるといったことも何度となく経験してきました。やはり「死の受容」を導く力が無ければ信仰とは言えないだろうと思います。自分は神仏から、あるいは自然(宇宙)の中で生かされている、生かされてきたということを再確認し、ソクラテスの時代から言われてきた「求めるものは、ただ生きることではなく、良く生きることである。」ということを死の直前に実践できることが「死の受容」には求められていると思います。
8)しげ子さんが笑った(その一)
「いつ死んだっていいんだ。」と口癖のように言われる方がおられます。そういう方に限って、他人のちょっとした誤りや手順の違いに目鯨を立てられます。ただ生きる、生き長らえることに価値を見い出していることの裏返しの言葉だろうと思います。「死ぬって、そんな簡単な事ですか。」と聞くと黙ってしまわれます。
医療が高度化し、死に至る過程で種々の処置や治療への自己決定と自己責任が問われています。それは簡単な事ではありません。よく「お医者様にお任せして。」という話を聞きますが、医者は神仏ではありません。他力とは他の人間に対して求めるものでは無いはずです。医者は助言者であるに過ぎません。どのような時に、自己決定が必要となるのかというお話をして行きたいと思います。
Dさん(八十四歳、女性)は、一月号でお話しました「暁学園デイサ−ビス」に来られていた方です。入所していたの赤ん坊が上に登って、頬擦りをしたところ、突然Dさんが笑い出しました。これほど赤ん坊に癒しの力があるとはとスタッフは皆びっくりしました。その状況を詩にしてみました。家族の承諾を得て本名を使います。
しげ子さんが笑った
声を立てて笑った
お花見会に来て笑った
しげ子さんは八十四歳
脳梗塞から十二年
「呆け」て「寝たきり」となって五年
最近は、気分が良ければ
「こんにちは」というとニッと微笑む
マッサ−ジで痛いとカッと目を開いて怒る
ただそれだけの反応だった
しげ子さんが笑った
声を立てて笑った
赤ちゃんと頬擦りして笑った
「どじょうすくい」を見て笑った
しげ子さんが笑った
声を立てて笑った
「今日は楽しかったね」と言うと笑った
その笑い声につられて笑っているうち、「生きているんだ。」という実感も伴って、涙が出てきました。だからボランティアは辞められないのです。次号ではこの方の死の話をしたいと思います。
9)しげ子さんが笑った(その二)
声を出して笑われるようになってから半年後、Dさんは風邪から気管支炎となって食事が喉を通らなくなりました。七十五歳以上の方が気管支炎や肺炎となった場合、約半数の方は熱も出ず、ただ咳が出て食事が喉を通らなくなるだけで、なかなか気づかれないことも多いため、高齢者では呼吸器疾患の死亡率が高くなっています。Dさんの家族は、食事の量、水分の量をしっかり記録されておられ、早期に見つけることができました。入院を薦めましたが、Dさんの家族はキリスト教系のしっかりした信仰を持たれている方々で、神との対話の中で、在宅介護の継続を希望されました。抗生物質の点滴を7日間行って、呼吸音は改善しましたが、食事の量は一日九時間飲ませ続けて、七百ミリリットルまでしか改善しませんでした。
通常「寝たきり」でも、体重四十キロの方で千ミリリットル、六十キロで千三百ミリリットルの水分が必要とされています。そしてその三分の二以下に落ちると、発熱や幻覚といった脱水の苦しみが始まります。七百ミリリットルというのは、体重四十キロのDさんにとって、苦しまないための最低限の量でした。鼻からチュ−ブを入れるか、時間をかけた介護を続けるか聞きました。ご家族は後者を選ばれました。息子さん夫婦とお孫さんさらにボランティアも加わって四人で毎日九時間飲ませ続けました。さらに半年後、二時間の朝ご飯を終え、お孫さんが「洗い物に行くよ。」と話しかけると、ニッと笑われたのが最後だったとのことです。よく半年間頑張られたものだと頭の下がる想いがしました。これが本当の「消極的安楽死(尊厳死)」だろうと思います。
「安楽死」には三種類あります。次の「間接的安楽死」の話を次号からはしたいと思います。
10)ゆるやかな死(その一)
三年程前、「臨死体験」ということが話題となったことがありました。私も小学校二年の冬、はしかから肺炎となり四十二℃の発熱の中で、自分が自分の体から浮き、お花畑の向こうに川が流れ、その向こうに薄紫の山々が見えた記憶があります。その時は、母方の曽々祖父で、愛知医学校(名古屋大学医学部の前身)の設立に加わった中島三伯から伝えられていた犀角を飲んで回復したということですので、熱と血液中の酸素と血圧の低下にその薬剤も加わって、本当に三途の川を見たのではなく、幻覚だったのかもしれません。
医学部の法医学の中で縊死(首吊り)が定型(完全)か非定型(不完全)かという講義があります。脳への血流が低下すると同時に呼吸が止まった場合、苦しみが強くならず、呼吸だけ止められると非常に苦しんだ、まさに地獄を見た表情となります。これは柔道で絞めて落とされた時、通常はそれほど苦しくはないが、下手な相手で主に気道が絞められると大変苦しくなるということにも通ずると思います。
死後硬直などで表情が無くなった場合でも、解剖をさせていただくと、心臓を診れば、苦しんだかどうかの痕跡が残っています。これまで、死に立ち会った患者さんの三分の二の方に病気と死因の確認のための解剖(病理解剖)をさせていただきました。これは医学の発展のためというだけでなく、治療が正しかったのか、苦しませずに死なせることができたのか反省を迫るものとして行わせていただきました。御家族の方々には、死の悲しみの上に、さらに苦痛を与えるものであることは十分承知しております。多くの方々に御協力いただけたことを心から感謝しております。こんな経験から、できるだけ脳への血流が低下して、あるいはその他の要因で意識が薄れている中で呼吸が止まるようにしたいと考えるようになりました。
11)ゆるやかな死(その二)
Eさん(70歳、男性)は6年前から、パ−キンソン病という難病で病院の神経内科の専門医の所へ通院されておられました。当初は手がふるえる、歩き出しで突っかかるようなことがあるという程度で、特に日常生活で困るようなことはありませんでした。一般的には、この病気は進行がゆっくりで、十年、二十年という経過を取るものですが、この方の場合、進行が急速で、その状態を維持するために半年に一錠づつ薬を増やさざるを得ない状態でした。
二年前から投薬量は極量を越え、一年前からは薬の副作用も加わって、立ち眩み、頑固な便秘、そして時には幻覚も出現し、薄暗がりの中では痴呆のような症状も観られるようになって、ほとんど寝たきりとなってしまいました。病院への通院は困難となり、在宅ケア、在宅医療の相談に当院へ来られました。
Eさんは歌が好きで、奥様そして三人のお子さん達の仲も良く、お孫さん達も加わって、歌声の絶えない賑やかな在宅ケアが始まりました。整形外科医院からの訪問リハビリや訪問看護ステ−ションの看護婦さん、巡回入浴サ−ビスやボランティアによるデイサ−ビスも利用され、比較的落ち着いた状態が続いておりました。
亡くなられる三ヶ月前から喉の力が弱り、二ヶ月前から喉が落ち込んでの呼吸困難も現れました。喉の下に穴を開け、気管に管を入れますか、鼻からの人工呼吸を使用しますか、麻酔により息苦しさを感じなくする方法取りますかと訪ねました。本人家族は最後まで歌えるような状態にしておいて欲しいと希望されました。そこで第二の方法を使用することとしました。人工呼吸を受けながらも、歌を歌われていました。さらに徐々に病状は悪化して行きましたが、以後それ程の呼吸困難は訴えられず、静かに息を引き取られました。
12)ゆるやかな死(その三)
二十五年ほど前、車椅子での生活ながら、印刷会社を起こした脳性麻痺の方々と友達になりました。「障害者というのは、邪魔者とも読めるから嫌やや。」と言われました。「世の中に障害者はいない。障害を補う技術と支えるシステムの遅れがあるだけや。」という話も幾度となく聞かされてきました。
数年前、スティ−ブン・W・ホ−キング博士が「宇宙と理論物理」の講演のため、日本に来られました。筋萎縮性側索硬化症という神経の難病のため、人工呼吸器を車椅子に乗せ、そこに横たわった状態で、瞬きでパソコンを動かして講演をされる姿に、多くの方々が驚かれたことと思います。コンピュ−タ−の技術の進歩は目覚ましく、人工呼吸器もコンパクトで性能の良いものが開発されてきております。これを使っているからといって入院している必要はなく、海外旅行まで出来る時代になってきているのです。さらに最近は、鼻から行う簡易型の人工呼吸器もかなり安全に使えるようになり、睡眠時無呼吸症候群(寝ている時、かなり長い時間呼吸が止まり、睡眠が浅くなるため、日中の仕事の能率が落ちたり、交通事故を起こしたりする病気)や神経難病の本格的な人工呼吸に入る前の一時凌ぎとして用いられるようになってきました。
このような技術の進歩があったればこそ、パ−キンソン病という神経の難病のEさんも、家で歌いながら死に至るという希望を叶えることができたのだと思います。最後の段階で、首に穴を開け、気管にチュ−ブを入れ、本格的な人工呼吸に移っていれば、さらにもう少し生き延びられたという気もしますが、通夜に伺った時の家族の方々の晴れ晴れとしたお顔を拝見し、これで良かったのだろうと考えています。
13)苦しみを和らげた上での死(その一)
このようなお話をしてきますと、やはり多くの方が「こんなに難しいことは嫌だ。私はポックリ死にたい。」と言われます。しかし多くの在宅死に立ち会ってきますと、「ポックリ死」の方は僅か五%弱しかないと思われます。しかも「ポックリ死」の約半数は突然呼吸が止まったことによる、そして一気に来る苦痛から「地獄を見た表情」で亡くなられています。突然親しい方が亡くなられ、しかも苦痛の表情をしているのを見るのは家族や友人にとって、大変な苦痛や悲しみとなります。
このような状況を見ていると、「ポックリ死」信仰というものは、宝くじに当たるために神頼みするようなもので、本当の信仰ではないだろうと思います。やはり多くの方がそうであるように、緩やかに死に至る間にある徐々に来る苦痛を和らげるののとして、さらに「死の受容」に容易に向かわせるものとして信仰はあるのではないかと思います。
Fさん(79歳、男性)は胃癌が肝臓と肺に転移し、癌でリンパ管が詰まる状態や腰椎にも転移があって苦痛の強い状態でした。モルヒネ内服で痛みは管理されましたが、むくみや呼吸困難の管理はなかなか困難な状態でした。在宅死を希望され、病院からの紹介で当院に来られました。当初は週一回の往診のみで良かったものが、三ヶ月後には嘔吐や呼吸困難から一日に二回から五回の往診が必要となりました。酸素投与も行いましたが、さらに一週間後、呼吸困難が強くなり、本人や家族の「命が縮まっても良いから、薬で眠らせて欲しい。」という強い要望もあって、麻酔を軽くかけるような形の持続点滴開始しました。翌日家族が看守る中、静かに息を引き取られました。
14)苦しみを和らげた上での死(その二)
初めにお話しましたように、十中八、九は自然に、あるいは通常の医療の範囲内のモルヒネ使用などの苦痛を和らげる治療だけで、比較的楽に死に向かうことができます。そこに信仰があって、老いに対する和解や死の受容があれば、なおさら穏やかな死を迎えることができます。そして前回お話しましたように五%弱の方は「ポックリ死」です。残りは、通常の医療の範囲内であっても薬の副作用が出るため、苦痛を和らげる治療が十分に使えない方と、呼吸困難などの現在の医療的な処置の限界のある方ということになります。
マスコミの報道では、日本の医者は痛みに対するモルヒネなどの使い方に問題があるような記事をまだまだ見かけます。これは現在の医療現場では、ほとんど問題にならなくなっています。十分量のモルヒネが使えない方には、痛んでいる神経を直接に局所麻酔したり、遮断するブロックという方法もあります。しかしこの処置でも、逆に死の危険にさらすような副作用や合併症が起こることがあります。今回このシリ−ズをお受けするにあたって、まず死に向かう時の苦痛を和らげる治療に対して、どんなに十分に技量のある医者でも、どうにもならない事態が起こることがあるということをお伝えしなければという思いに駆られました。
神経ブロックや七月から九月号までお話してきました間接的安楽死は、逆に命を縮める可能性も十分にあるということを、医者は本人や家族に十分に説明し、本人の自己選択と納得の上で使われなければならないとされています。「安楽死」はこれまでタブ−とされてきました。そのために還って、あってはならない慈悲殺人や絶対的(積極的直接的)安楽死のような事件も起こってきました。間接的安楽死の理解を広める必要があるのではないかと考えています。
15)苦しみを和らげた上での死(その三)
8年程前に「東海大学安楽死事件」が起こりました。これは後に、本人の意志確認がない、使用薬剤が直接心臓を止めるものであって、苦痛を和らげるものではないということから、「慈悲殺人」であって、「安楽死」にも当たらないとされています。しかし、その4年後の横浜地裁判決は、「間接的安楽死」の要件を示した画期的判決とされています。
要件としては、「(1)患者に耐えがたい激しい肉体的苦痛が存在すること、(2)患者について死が避けられず(現代医学の知識と技術から見て不治の病で)、かつ死期が迫っていること、(3)患者の意思表示があること、(4)苦痛を除去・緩和するための措置を取るが、それが同時に死を早める可能性があり、それによって死に至ること。」が上げられています。その他、昭和37年の「名古屋高裁安楽死判決」から引き継ぐものして、「(5)医師の手によることを本則とし、こりにより得ない場合は、医師により得ないと認めるに足りる特別な事情があること、(6)その方法が倫理的にも妥当なものとして認容できるもの。」とされています。
その後にも、いくつかの「安楽死事件」が起こりました。多くの場合、本人の意志の確認が不十分であり、さらには「筋弛緩剤」で呼吸を止めるという方法が取られました。息したくても、息できないというのは、大変な苦痛となります。なぜこのような方法が選択されたのか理解に苦しむところです。また最近は、本人の意志確認の問題では、末期医療に入る(通常は亡くなられる一ヶ月から三ヶ月前の)段階で第一回目の確認を、そして「間接的安楽死」の処置に入る直前に、さらに二回の確認を二人の医師で行うこととされてきています。つまり自己決定権の尊重が強く求められているのです。
(2007年6月の資料)
「在宅死」;看取りと癒し
藤・霽月 (ふじ・せいげつ)
1) はじめに
2)「在宅末期医療」で出来ること(その1)
3)「在宅末期医療」の出来ること(その2)
4)拒食ということ
5)より良く生かせ
6)呆けとは何か
7)「死の受容」とは
8)しげ子さんが笑った(その一)
9)しげ子さんが笑った (そに二)
10)ゆるやかな死(その一)
11)ゆるやかな死(その二)
12)ゆるやかな死(その三)
13)苦しみを和らげた上での死(その一)
14)苦しみを和らげた上での死(その二)
15)苦しみを和らげた上での死(その三)
1)はじめに
医者になって19年、癌や呼吸不全・難病を中心に650人程の「死」に立ち会ってきました。「死」は生あるものの「宿命」であり、「良い死に方」を得るには、その「宿命」であることを如何に受容するか、その前に自分が如何に生きてきたか、その後のこととして「死」を迎える家族や友人等周囲の条件が整っているかということが必要であることを患者さんから教わってきました。
現在は、ほとんど患者さんが病院で亡くなられる時代です。私が立ち会った内の550人程も、病院勤務時代の経験です。一般的な病院は、基本的に効率的に病気を治し延命を得るためのシステムで動いています。その中では医療者が一人の個人として少しでも「より良い死」を迎えさせてあげたいと考えたとしても、組織としての限界があります。私自身、1日100人の外来と50人の病棟廻診を行う中、3人の死亡診断書を書くという経験をしたことがあります。そこには「癒し」の時間を取る余裕はありませんでした。12年前、私の親友が亡くなる時、「最後の儀式」としての心臓マッサ−ジのために、家族と共に病室から出されるという経験もしました。
こんなこともあって、7年前に「在宅末期医療」のできる診療所を開設しました。やはり家族に見守られて、住み慣れた自宅で亡くなるのは、温かみがあって心地良いものがあります。まず驚いたのは、癌の痛みに対するモルヒネの量が「在宅死」の場合には格段に少なくなることです。これは癌が周りの臓器を食い散らす痛さだけでなく、心理的な影響も受けるものであり、自宅で家族に支えられることにより、和らげられるのだろうと考えます。こんな経験をすると、夜中や休日の往診の疲れも吹っ飛んでしまいます。
2)「在宅末期医療」で出来ること(その1)
癌の末期では、痛みを取ることだけが問題で、日本の医者はモルヒネの使い方が下手だから癌の患者が苦しむのだといった誤解を持たれている方が多くおられます。前号でお話しましたように、癌の痛みは心理的な影響を強く受けるものであり、不安感を持っておられると、痛みはより強いものとなります。またそういう方に限って、痛みの程度を家族を通して訴えられるため、対応に遅れが出て、痛みは耐えられないものとなってしまいます。医療者を信頼して、早めに直接訴えて頂くことが、まず必要だろうと思います。
また癌の末期の十中八、九はモルヒネだけで楽に死ねることは確かです。しかし、出血や呼吸困難、痙攣等それ以外の苦痛を取る処置が必要になる場合もあります。色々な処置が必要であったけれども、在宅で比較的「良い死に方」の出来た方のお話をします。
Aさん(80才、男性)は胆汁を通す管に出来た癌が肝臓と食道近くに転移している状態で公立病院に入院しておられました。胆汁を外に出すチュ−ブと、食べれないため心臓近くの太い静脈まで栄養補給のためのチュ−ブが入り、尿を取るチュ−ブを付けた状態でした。大変な風呂好きで、そんな状態でも毎日風呂に入りたいとして12月20日退院されてきました。それらチュ−ブの管理のため、1日に2、3回の往診が必要な状態でした。正月の間も続きました。家族の方々は大変心優しく、そして熱心に看病されておられました。携帯用の補液のポンプとモルヒネを用い、車椅子に乗ってではありましたが、梅の花見にも行けました。亡くなられる2、3日前は、少し呼吸困難も訴えられ、酸素も持ち込みました。3月29日、住み慣れた家で満足そうな顔をして息を引き取られました。
3)「在宅末期医療」の出来ること(その2)
致死的な病気あるいは「老衰」があって食べられなくなったら、そのまま何もせず亡くならせるのが良いという主張があります。尊厳死あるいは消極的安楽死の主張の中に、安易にこの考え方を取り入れられる方がおられます。しかし、これは個々の病状や置かれた状況を考慮しなければ、致死的な病気や重い「障害」を持った人間は早く死ねば良いという危険な考え方につながりかねません。
前号でお話しました末期的な癌で、中心静脈(心臓に近い所の太い静脈)と胆汁の管と尿への3本のチュ−ブを付けたAさんに、何故静脈からの栄養補給をしたのかといった御批判もあろうかと思います。その回答の一つは、末期的な癌と言えども、体力が残っている状態で突然餓死させられるのは、大変苦痛を伴うものであるということです。尊厳死あるいは消極的安楽死とは、体力が相当に弱って、余り苦痛を感じなくなった段階での餓死と考えるべきでしょう。
もう一つは、癌であり死が迫っているという「宿命」を受容し、単に臥して死を待つのでは無く、残り少ない命を最後まで精一杯楽しもう、出来るところまで仕事に、趣味に生き続けようとすることに、人間の生き様として価値があるように思います。前向きに生きるということは、少しでも長く生き続けようとすることでは無く、残り少ない命の中身を少しでも高めようとすることと考えます。そのための手段の一つとして中心静脈栄養が用いられるのです。「在宅死」を請け負うということは、そのような患者さんの姿勢に共感し、それを支えるということです。そこから「生きる」ということを教えられ、自分を磨かせて頂けるという感謝の気持ちで一杯の仕事であると思っています。
4)拒食ということ
病院に勤務していた頃は、「癒し」の時間が思うように取れなかったという反省から、開業医となってからは出来るだけカウンセリングを含め診察時間を長く取るようにしました。そんなこともあって、「心の病」で転々と医療機関を変わられてきた患者さんが相談に来られるようになってきました。最近は精神科通院中の方や拒食症の方も来られるようになりました。
Bさん(14才、女性)は、42キロあった体重が29キロまで減少して来院。料理店経営のお父さんを慕っておられ、自分は中学卒業後は調理師になる方向で進路を考えていたところ、学業でもスポ−ツでもかなり優秀であったため、お母さんや学校の先生からは進学を薦められていたようです。友人関係の悩みもあったようです。朝になると腹痛やめまいが起こることから学校になかなか行けなくなり、そこから成績も悪くなり、それがさらにストレスとなって、食べれば吐く、吐くから食べないという状態になったようでした。
このような患者さんには、時間をかけて話を聞き、「あなたこそ生きている価値があるのですよ。」ということを何度も何度も伝えていくことしか、我々に出来ることはないだろうと考えております。ある時、寝たきりで流動食しか食べられない患者さんでも、同じ味の物ばかり与えていると食欲が落ちてくるので、味を少し変えてやることも必要となるという話をしました。その後、1年浪人して体力を回復し、福祉系の高校へ入学されたようです。介護の解る調理師が生まれたら、面白いだろうなと考えています。
食べられなくなったら消極的安楽死をと単純に考えることは危険です。生活リハビリ研究所の三好春樹さんは寝たきりや痴呆の方の拒食を消極的自殺と呼んでおられます。次回はそんな話をします。
5)より良く生かせ
「『消極的自殺』は『より良く生かせ』の訴えです。」というのは、生活リハビリ研究所の三好春樹さんがよく言われる言葉です。寝たきりや痴呆の方が気分を害されると「異常行動」に出る場合と「消極的自殺」に向かう場合があります。
10月号の「いのちを見失うとき」を書かれた祖父江文宏先生の暁学園と「呆け老人をかかえる家族の会愛知支部」の事務局である尾之内直美さんの家が私の診療所の近くにあります。その二つが一緒になって、家族の虐待から保護されている子供と痴呆や寝たきりの要介護者との「ふれ合いの場」を設けておられます。そこに私も少しばかりのお手伝いに入っております。傷ついた者同士が互いに癒し合う不思議な空間が生まれております。
18年前から高血圧症で当院にかかっていたCさん(80才女性)は、3年前に軽い脳梗塞となり、息子さん達は介護の出来るようにと家を建て替えました。その頃から足腰も弱り、痴呆も始まりました。けがをさせないため、なるべく家に居させるようにとされたようです。そのため返って食が細り、粥も吐いてしまうようになりました。何か良い方法はないかと考え、暁学園デイサ−ビスを紹介しました。行く時は大変嫌がられ、抵抗されたとのことでしたが、子供達と遊んでいるうちに、笑顔も見られるようになってきました。昼食は、自分のために出された粥には手をつけられず、子供達のためのちらし寿司を希望され、お代わりまでして食べて帰られました。
痴呆というと「異常行動」ばかりが強調されているように思います。痴呆でも楽しければ笑いますし、思うようにやってもらえれば感謝もします。「呆けてもこころは生きている」は、「呆け老人をかかえる家族の会」の標語のようになっている言葉です。
6)呆けとは何か
「呆けてもこころは生きている」と書きました。このお話をすると、「では痴呆とは何か」という質問を受けることがあります。世間の多くは、まだこれを「心の病」あるいは「精神的な病気」と捉えているようです。15年程「痴呆」の要介護者の方々の診てきました経験から、現場の感覚で現在どう捉えているかをお話します。
高度の精神的な営みは脳の前の部分(大脳の前頭葉の一部)が司っています。古い記憶は脳の後ろの部分(後頭葉の一部)にあります。これは見ることの中枢の近くにあります。近い記憶は脳の横の部分(側頭葉の一部)にあります。これは聴覚の中枢の近くにあり、観念的な記憶にも強いところと思われます。この近い記憶の中枢が衰えてくるのが「痴呆」という状態と考えます。近い記憶が抜け落ち古い記憶が鮮明になることから、人間関係や生活に障害を来すというのが、特に「痴呆」の初期の実体です。但し観念的な記憶の弱りから理性も衰えていくこと、進行すれば幻覚・幻聴も現れることは否定できませんが、主体はこちらにあると考えます。
末期医療(ホスピスケア)の教科書的存在としてよく使われます本として、E・キュブラ−・ロスの「死ぬ瞬間」(読売新聞社発行)があります。死を前にして、あるいは重大な障害を得た時に人間はまず怒り(何故自分がこんな目に合わなければならないのか)、次に取引(もっと良い医者は居ないのか、あるいはもっと金を出せば何とかなるのではないか)を考え、そして抑うつ(やはり駄目か)となり、その後受容に至ると書かれています。「痴呆」では特に初期が最も厄介とされるのは、人間関系と生活の障害と、このことから来る本人・家族の「怒り」が合わさって、暴力あるいは異常行動が現れることにあるのだろうと思います。
7)「死の受容」とは
自己紹介を求められた時、「ボランティア歴二十六年という変わり者の医者です。」から始めることにしています。それに「結婚式も仏式で挙げたほどの仏教徒、真宗門徒です。」と加えることもあります。色々な宗教宗派の、特に国際的なボランティアとの交流が深くなるにつれ、自分の育てられた環境の中にあった信仰を、還って強く意識すると同時に、例え異なったものであっても他の人の信仰も尊重するようになってきました。この経験が在宅死の看取りでも役に立っています。しかし「自立と共生」をテ−マとするボランティアの信念と「共生と自律」の教えの間には合い通ずる部分と折り合いを着けなければならない部分とがあり、悩みもあるということは、また別の機会にお話したいと思います。
さて、そのようなボランティア同士の交流の中で、前号で触れましたE・キュブラ−・ロスの下、チャプレン(キリスト教的に「死の受容」を導く仕事)を経験されたニノミヤ・ヘンリ−・アキイエ関西学院大学教授と呑む機会がありました。しっかりした信仰のある方と完璧な無神論者は「死の受容」までの道のりが短く、苦しみも少ないが、中途半端な信仰を持つ人や知識人として宗教を哲学する人は苦しまれることも多いということで、意見が一致しました。
立派な宗教家が、死を目前にして狼狽えるといったことも何度となく経験してきました。やはり「死の受容」を導く力が無ければ信仰とは言えないだろうと思います。自分は神仏から、あるいは自然(宇宙)の中で生かされている、生かされてきたということを再確認し、ソクラテスの時代から言われてきた「求めるものは、ただ生きることではなく、良く生きることである。」ということを死の直前に実践できることが「死の受容」には求められていると思います。
8)しげ子さんが笑った(その一)
「いつ死んだっていいんだ。」と口癖のように言われる方がおられます。そういう方に限って、他人のちょっとした誤りや手順の違いに目鯨を立てられます。ただ生きる、生き長らえることに価値を見い出していることの裏返しの言葉だろうと思います。「死ぬって、そんな簡単な事ですか。」と聞くと黙ってしまわれます。
医療が高度化し、死に至る過程で種々の処置や治療への自己決定と自己責任が問われています。それは簡単な事ではありません。よく「お医者様にお任せして。」という話を聞きますが、医者は神仏ではありません。他力とは他の人間に対して求めるものでは無いはずです。医者は助言者であるに過ぎません。どのような時に、自己決定が必要となるのかというお話をして行きたいと思います。
Dさん(八十四歳、女性)は、一月号でお話しました「暁学園デイサ−ビス」に来られていた方です。入所していたの赤ん坊が上に登って、頬擦りをしたところ、突然Dさんが笑い出しました。これほど赤ん坊に癒しの力があるとはとスタッフは皆びっくりしました。その状況を詩にしてみました。家族の承諾を得て本名を使います。
しげ子さんが笑った
声を立てて笑った
お花見会に来て笑った
しげ子さんは八十四歳
脳梗塞から十二年
「呆け」て「寝たきり」となって五年
最近は、気分が良ければ
「こんにちは」というとニッと微笑む
マッサ−ジで痛いとカッと目を開いて怒る
ただそれだけの反応だった
しげ子さんが笑った
声を立てて笑った
赤ちゃんと頬擦りして笑った
「どじょうすくい」を見て笑った
しげ子さんが笑った
声を立てて笑った
「今日は楽しかったね」と言うと笑った
その笑い声につられて笑っているうち、「生きているんだ。」という実感も伴って、涙が出てきました。だからボランティアは辞められないのです。次号ではこの方の死の話をしたいと思います。
9)しげ子さんが笑った(その二)
声を出して笑われるようになってから半年後、Dさんは風邪から気管支炎となって食事が喉を通らなくなりました。七十五歳以上の方が気管支炎や肺炎となった場合、約半数の方は熱も出ず、ただ咳が出て食事が喉を通らなくなるだけで、なかなか気づかれないことも多いため、高齢者では呼吸器疾患の死亡率が高くなっています。Dさんの家族は、食事の量、水分の量をしっかり記録されておられ、早期に見つけることができました。入院を薦めましたが、Dさんの家族はキリスト教系のしっかりした信仰を持たれている方々で、神との対話の中で、在宅介護の継続を希望されました。抗生物質の点滴を7日間行って、呼吸音は改善しましたが、食事の量は一日九時間飲ませ続けて、七百ミリリットルまでしか改善しませんでした。
通常「寝たきり」でも、体重四十キロの方で千ミリリットル、六十キロで千三百ミリリットルの水分が必要とされています。そしてその三分の二以下に落ちると、発熱や幻覚といった脱水の苦しみが始まります。七百ミリリットルというのは、体重四十キロのDさんにとって、苦しまないための最低限の量でした。鼻からチュ−ブを入れるか、時間をかけた介護を続けるか聞きました。ご家族は後者を選ばれました。息子さん夫婦とお孫さんさらにボランティアも加わって四人で毎日九時間飲ませ続けました。さらに半年後、二時間の朝ご飯を終え、お孫さんが「洗い物に行くよ。」と話しかけると、ニッと笑われたのが最後だったとのことです。よく半年間頑張られたものだと頭の下がる想いがしました。これが本当の「消極的安楽死(尊厳死)」だろうと思います。
「安楽死」には三種類あります。次の「間接的安楽死」の話を次号からはしたいと思います。
10)ゆるやかな死(その一)
三年程前、「臨死体験」ということが話題となったことがありました。私も小学校二年の冬、はしかから肺炎となり四十二℃の発熱の中で、自分が自分の体から浮き、お花畑の向こうに川が流れ、その向こうに薄紫の山々が見えた記憶があります。その時は、母方の曽々祖父で、愛知医学校(名古屋大学医学部の前身)の設立に加わった中島三伯から伝えられていた犀角を飲んで回復したということですので、熱と血液中の酸素と血圧の低下にその薬剤も加わって、本当に三途の川を見たのではなく、幻覚だったのかもしれません。
医学部の法医学の中で縊死(首吊り)が定型(完全)か非定型(不完全)かという講義があります。脳への血流が低下すると同時に呼吸が止まった場合、苦しみが強くならず、呼吸だけ止められると非常に苦しんだ、まさに地獄を見た表情となります。これは柔道で絞めて落とされた時、通常はそれほど苦しくはないが、下手な相手で主に気道が絞められると大変苦しくなるということにも通ずると思います。
死後硬直などで表情が無くなった場合でも、解剖をさせていただくと、心臓を診れば、苦しんだかどうかの痕跡が残っています。これまで、死に立ち会った患者さんの三分の二の方に病気と死因の確認のための解剖(病理解剖)をさせていただきました。これは医学の発展のためというだけでなく、治療が正しかったのか、苦しませずに死なせることができたのか反省を迫るものとして行わせていただきました。御家族の方々には、死の悲しみの上に、さらに苦痛を与えるものであることは十分承知しております。多くの方々に御協力いただけたことを心から感謝しております。こんな経験から、できるだけ脳への血流が低下して、あるいはその他の要因で意識が薄れている中で呼吸が止まるようにしたいと考えるようになりました。
11)ゆるやかな死(その二)
Eさん(70歳、男性)は6年前から、パ−キンソン病という難病で病院の神経内科の専門医の所へ通院されておられました。当初は手がふるえる、歩き出しで突っかかるようなことがあるという程度で、特に日常生活で困るようなことはありませんでした。一般的には、この病気は進行がゆっくりで、十年、二十年という経過を取るものですが、この方の場合、進行が急速で、その状態を維持するために半年に一錠づつ薬を増やさざるを得ない状態でした。
二年前から投薬量は極量を越え、一年前からは薬の副作用も加わって、立ち眩み、頑固な便秘、そして時には幻覚も出現し、薄暗がりの中では痴呆のような症状も観られるようになって、ほとんど寝たきりとなってしまいました。病院への通院は困難となり、在宅ケア、在宅医療の相談に当院へ来られました。
Eさんは歌が好きで、奥様そして三人のお子さん達の仲も良く、お孫さん達も加わって、歌声の絶えない賑やかな在宅ケアが始まりました。整形外科医院からの訪問リハビリや訪問看護ステ−ションの看護婦さん、巡回入浴サ−ビスやボランティアによるデイサ−ビスも利用され、比較的落ち着いた状態が続いておりました。
亡くなられる三ヶ月前から喉の力が弱り、二ヶ月前から喉が落ち込んでの呼吸困難も現れました。喉の下に穴を開け、気管に管を入れますか、鼻からの人工呼吸を使用しますか、麻酔により息苦しさを感じなくする方法取りますかと訪ねました。本人家族は最後まで歌えるような状態にしておいて欲しいと希望されました。そこで第二の方法を使用することとしました。人工呼吸を受けながらも、歌を歌われていました。さらに徐々に病状は悪化して行きましたが、以後それ程の呼吸困難は訴えられず、静かに息を引き取られました。
12)ゆるやかな死(その三)
二十五年ほど前、車椅子での生活ながら、印刷会社を起こした脳性麻痺の方々と友達になりました。「障害者というのは、邪魔者とも読めるから嫌やや。」と言われました。「世の中に障害者はいない。障害を補う技術と支えるシステムの遅れがあるだけや。」という話も幾度となく聞かされてきました。
数年前、スティ−ブン・W・ホ−キング博士が「宇宙と理論物理」の講演のため、日本に来られました。筋萎縮性側索硬化症という神経の難病のため、人工呼吸器を車椅子に乗せ、そこに横たわった状態で、瞬きでパソコンを動かして講演をされる姿に、多くの方々が驚かれたことと思います。コンピュ−タ−の技術の進歩は目覚ましく、人工呼吸器もコンパクトで性能の良いものが開発されてきております。これを使っているからといって入院している必要はなく、海外旅行まで出来る時代になってきているのです。さらに最近は、鼻から行う簡易型の人工呼吸器もかなり安全に使えるようになり、睡眠時無呼吸症候群(寝ている時、かなり長い時間呼吸が止まり、睡眠が浅くなるため、日中の仕事の能率が落ちたり、交通事故を起こしたりする病気)や神経難病の本格的な人工呼吸に入る前の一時凌ぎとして用いられるようになってきました。
このような技術の進歩があったればこそ、パ−キンソン病という神経の難病のEさんも、家で歌いながら死に至るという希望を叶えることができたのだと思います。最後の段階で、首に穴を開け、気管にチュ−ブを入れ、本格的な人工呼吸に移っていれば、さらにもう少し生き延びられたという気もしますが、通夜に伺った時の家族の方々の晴れ晴れとしたお顔を拝見し、これで良かったのだろうと考えています。
13)苦しみを和らげた上での死(その一)
このようなお話をしてきますと、やはり多くの方が「こんなに難しいことは嫌だ。私はポックリ死にたい。」と言われます。しかし多くの在宅死に立ち会ってきますと、「ポックリ死」の方は僅か五%弱しかないと思われます。しかも「ポックリ死」の約半数は突然呼吸が止まったことによる、そして一気に来る苦痛から「地獄を見た表情」で亡くなられています。突然親しい方が亡くなられ、しかも苦痛の表情をしているのを見るのは家族や友人にとって、大変な苦痛や悲しみとなります。
このような状況を見ていると、「ポックリ死」信仰というものは、宝くじに当たるために神頼みするようなもので、本当の信仰ではないだろうと思います。やはり多くの方がそうであるように、緩やかに死に至る間にある徐々に来る苦痛を和らげるののとして、さらに「死の受容」に容易に向かわせるものとして信仰はあるのではないかと思います。
Fさん(79歳、男性)は胃癌が肝臓と肺に転移し、癌でリンパ管が詰まる状態や腰椎にも転移があって苦痛の強い状態でした。モルヒネ内服で痛みは管理されましたが、むくみや呼吸困難の管理はなかなか困難な状態でした。在宅死を希望され、病院からの紹介で当院に来られました。当初は週一回の往診のみで良かったものが、三ヶ月後には嘔吐や呼吸困難から一日に二回から五回の往診が必要となりました。酸素投与も行いましたが、さらに一週間後、呼吸困難が強くなり、本人や家族の「命が縮まっても良いから、薬で眠らせて欲しい。」という強い要望もあって、麻酔を軽くかけるような形の持続点滴開始しました。翌日家族が看守る中、静かに息を引き取られました。
14)苦しみを和らげた上での死(その二)
初めにお話しましたように、十中八、九は自然に、あるいは通常の医療の範囲内のモルヒネ使用などの苦痛を和らげる治療だけで、比較的楽に死に向かうことができます。そこに信仰があって、老いに対する和解や死の受容があれば、なおさら穏やかな死を迎えることができます。そして前回お話しましたように五%弱の方は「ポックリ死」です。残りは、通常の医療の範囲内であっても薬の副作用が出るため、苦痛を和らげる治療が十分に使えない方と、呼吸困難などの現在の医療的な処置の限界のある方ということになります。
マスコミの報道では、日本の医者は痛みに対するモルヒネなどの使い方に問題があるような記事をまだまだ見かけます。これは現在の医療現場では、ほとんど問題にならなくなっています。十分量のモルヒネが使えない方には、痛んでいる神経を直接に局所麻酔したり、遮断するブロックという方法もあります。しかしこの処置でも、逆に死の危険にさらすような副作用や合併症が起こることがあります。今回このシリ−ズをお受けするにあたって、まず死に向かう時の苦痛を和らげる治療に対して、どんなに十分に技量のある医者でも、どうにもならない事態が起こることがあるということをお伝えしなければという思いに駆られました。
神経ブロックや七月から九月号までお話してきました間接的安楽死は、逆に命を縮める可能性も十分にあるということを、医者は本人や家族に十分に説明し、本人の自己選択と納得の上で使われなければならないとされています。「安楽死」はこれまでタブ−とされてきました。そのために還って、あってはならない慈悲殺人や絶対的(積極的直接的)安楽死のような事件も起こってきました。間接的安楽死の理解を広める必要があるのではないかと考えています。
15)苦しみを和らげた上での死(その三)
8年程前に「東海大学安楽死事件」が起こりました。これは後に、本人の意志確認がない、使用薬剤が直接心臓を止めるものであって、苦痛を和らげるものではないということから、「慈悲殺人」であって、「安楽死」にも当たらないとされています。しかし、その4年後の横浜地裁判決は、「間接的安楽死」の要件を示した画期的判決とされています。
要件としては、「(1)患者に耐えがたい激しい肉体的苦痛が存在すること、(2)患者について死が避けられず(現代医学の知識と技術から見て不治の病で)、かつ死期が迫っていること、(3)患者の意思表示があること、(4)苦痛を除去・緩和するための措置を取るが、それが同時に死を早める可能性があり、それによって死に至ること。」が上げられています。その他、昭和37年の「名古屋高裁安楽死判決」から引き継ぐものして、「(5)医師の手によることを本則とし、こりにより得ない場合は、医師により得ないと認めるに足りる特別な事情があること、(6)その方法が倫理的にも妥当なものとして認容できるもの。」とされています。
その後にも、いくつかの「安楽死事件」が起こりました。多くの場合、本人の意志の確認が不十分であり、さらには「筋弛緩剤」で呼吸を止めるという方法が取られました。息したくても、息できないというのは、大変な苦痛となります。なぜこのような方法が選択されたのか理解に苦しむところです。また最近は、本人の意志確認の問題では、末期医療に入る(通常は亡くなられる一ヶ月から三ヶ月前の)段階で第一回目の確認を、そして「間接的安楽死」の処置に入る直前に、さらに二回の確認を二人の医師で行うこととされてきています。つまり自己決定権の尊重が強く求められているのです。
|
|
|
|
コメント(2)
藤・霽月さんのお話しは、現場を数多く体験されたものだけに、とても考えさせられるものがたくさんあります。今回紹介されたものの中では、次の3点が特に印象に残りました。
*************************************************
『前向きに生きるということは、少しでも長く生き続けようとすることでは無く、残り少ない命の中身を少しでも高めようとすることと考えます。』
「『消極的自殺』は『より良く生かせ』の訴えです。」というのは、生活リハビリ研究所の三好春樹さんがよく言われる言葉です。寝たきりや痴呆の方が気分を害されると「異常行動」に出る場合と「消極的自殺」に向かう場合があります。
しっかりした信仰のある方と完璧な無神論者は「死の受容」までの道のりが短く、苦しみも少ないが、中途半端な信仰を持つ人や知識人として宗教を哲学する人は苦しまれることも多い
*************************************************
『前向きに生きるということは、少しでも長く生き続けようとすることでは無く、残り少ない命の中身を少しでも高めようとすることと考えます。』
「『消極的自殺』は『より良く生かせ』の訴えです。」というのは、生活リハビリ研究所の三好春樹さんがよく言われる言葉です。寝たきりや痴呆の方が気分を害されると「異常行動」に出る場合と「消極的自殺」に向かう場合があります。
しっかりした信仰のある方と完璧な無神論者は「死の受容」までの道のりが短く、苦しみも少ないが、中途半端な信仰を持つ人や知識人として宗教を哲学する人は苦しまれることも多い
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
脳いきいき セミナー 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
脳いきいき セミナーのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90065人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208324人
- 3位
- 酒好き
- 170697人