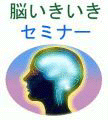第2回脳いきいきセミナー資料
3、セミナーの概略的な進行
セミナーは1ヵ月前にA−4版10ページの資料を配布いたします。セミナー当日多少の補足説明はありますが、基本的に資料を読んできてもらい、感想・意見を発表していただく形式でです。発表時間は1人10分以内です。脳いきいきために、発表内容の概要は事前に記述して持参してください。その発表内容を終了後に提出(任意の提出です)してください。その原稿はコミュニテイ「脳いきいきセミナー」に収録して配信します。意見の発表はミクシイの登録者にも呼びかけます。
4、セミナー資料
以下の通りです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第2回脳いきいきセミナー資料
セミナーの目次
1、脳いきいきセミナー2回以降の進行
(1)手の不思議
(2)記憶力
2、在宅で介護を担う人の4人に1人が、うつ病
3、使わなければ退化する
4、高齢者の13〜22%が「閉じこもり」
5、認知症の年代別の割合
6、凄い経歴の人がなぜ認知症になるのか
7、マンネリ化すれば脳は退化する。
8、廃用性症候群(1)
9、これが時代の流れだ (自分の死に場所)
10、砂糖健康学入門から 人間の脳細胞は70歳を超えても増える
1、脳いきいきセミナー2回以降の進行
2回目以降は参加している皆さんに多くの発言の機会を作るセミナーにします。セミナーの資料は1ヶ月以上前に配布し、参加する皆さんから理解した範囲を、自分の人生体験を加えてスピーチしてもらう形式のセミナーとします。発表する人は必ず発表原稿を記述することが条件です。心に刻みたい場所の朗読のみでも結構です。ただし、朗読する場所は自分で原稿を記述する。書く、話すという行為が脳を限りなくいきいきと活性させるのです。この概念を確認するために「手の不思議」「記憶力」のエッセイを引用します。
(1)手の不思議 (2004年1月7日の癒しの森から)
会社を退職してから1年6ヶ月が過ぎた。パソコンと縁がなかった人間がこれを覚え、インターネットをフル活用しているのであるから充実した時間を刻んでいるといえる。今日は1998年12月31日に書いた「手の不思議」の一部を引用しておきたい。
「今日で満2年730日、1日1枚「日々の映像」を記述した。振り返ってみると、『手は第2の頭脳である』という言葉がよく理解できる。誰が言ったのかは定かではないが西洋では『手は脳から飛び出した頭脳である』と表現するという。これらの言葉は、手を使うことがいかに重要であるかを示唆している。
手を動かして、文字を記述することによって、その内容が脳に刻まれることは確かである。どうもわれわれの脳は、書く、話す、というように肉体の一部を使わないと、記憶を預かる脳が作動しないようである。
手は脳から飛び出した頭脳であるとの表現の通り、手と脳は一体不可分なのである。くだいて言えば、手を動かすことと脳が活発に動くことは一体なのである。考えてみると、小説家・画家・音楽家・又は一流の経営者など、超一流の人で手を使わない人は誰もいないのである。私は2年間少々エッセイを書くために手を動かしたが、この手の不思議をしみじみ感じている」
(2)記憶力 (2004年1月8日の癒しの森から)
今日も昨日と同じく、講演の準備の一つとして2000年12月31日の日々の映像に書いた「記憶力」の大半を引用しておきたい。
・・・・私は昔から記憶の能力が弱いと自覚してきた。この弱さを証明する根拠は、人の名前がなかなか覚えられないという事実である。しかし、書くという行動があると、鈍い私の脳もかなりの情報を記憶する。今日で、1460回目の日々の映像となったが、手を動かすことがいかに重要なことであるかをヒシヒシと感じている。
脳と心の地形図(原書房・リタ・カータ著)という本を読んだ。『脳にある何10億というニューロンは、100兆もの結合を持っていて、その一つずつが記憶の一部になる可能性を秘めている。だから、人間の記憶能力は、正しいやり方で蓄えられれば無限なのである』(同書P259)・・・・
1998年12月31日にも書いたが、情報を得たら先ずメモをする(手を動かす)そして話す(口を動かす)という動きが加わると、完全に記憶として刻まれるのである。途中で手を動かす行動を省略しても、話すという動があればその情報・知識は脳に刻まれる。これらの「動」がいかに重要か、これを深く理解して行動すれば、脳は限りなく活性化していくように思う。ただ聞く、読むだけの「静」の状態では、脳の開発・活性化はありえないのである。
・人間の 脳と呼ばれる 小宇宙 無限に広がる ミクロの世界
3、在宅で介護を担う人の4人に1人が、うつ病
(2006年5月2日の高齢者福祉情報から)
以前日々の映像で書いたアメリカのデータである。娘が「認知症の母親の介護をした場合90%がうつ病になる」というものであった。それほど認知症の介護は厳しいのである。日本の場合に類似してデータの発表があった。厚生労働省の研究班による調査によると「在宅で介護を担う人の4人に1人が、うつ病の代表的な症状である『抑うつ』状態にある」(4月30日・毎日から)ことが分かったという。
高齢者が高齢者を介護する「老老介護」の場合、介護者の約3割が「死にたいと思ったことがある」と答えているのだ。調査は昨年6月、「介護者の健康実態に関するアンケート」として実施、8486人の回答を分析したもの。65歳以上の高齢介護者が約6割を占め、高齢化社会の進展の中で、老老介護の現実が浮かんでいる。
うつ病傾向を見る国際的な指標「自己評価抑うつ尺度」(SDS)を使ってさらに詳しく調べたところ、全体の23%が軽度から重度の「抑うつ状態」だったのだ。特に65〜74歳が最も高く「抑うつ状態」が27%に達している。特記すべき事項は75〜84歳で48%の人が「心が健康ではない」と感じていることである。昨日生涯青春の会の有力メンバーである70代の夫人を訪ねた。この人の兄の奥さんが78歳で認知症となり夫を認識できないのである。この段階になって、肉親が面倒を見ることはもはや不可能なのである。
3、使わなければ退化する(2006年7月30日高齢者福祉情報から)
なぜ痴呆になってしまうのか。いろいろな仮説があるが真実は単純な法則だ。使わなければ退化するだけなのである。少し前京都大学教授だった人が認知症になった事例を書いた。「使わなければ退化する」という法則に支配されただけのように思う。
NPO法人「亀田ボランテア」のまとう恵子さんと懇談する機会があった。「使わなければ退化する」に関連したことで次の話をしてくれた。「石田さん、使わないと本当に退化は早いのです。80歳以上の人で一人暮らし、ほとんど話す機会がない場合は30日で言葉を失うのです」詳しくは省略するが僅か30日で話すことが出来なくなってしまうという。まさに、真実は単純である。「使わなければ退化する」のである。これは高齢者だけのことでなく若い人も「脳は使わなければ退化する」という生物の法則を深く自覚しなければならない。
4、高齢者の13〜22%が「閉じこもり」
(2006年8月21日の高齢者福祉情報から)
高齢者福祉情報は3月25日から書き始めた。よって、スタート段階に書いた高齢者福祉情報を読んでいない人も多い。よって、今日から10日間余りは過去に記述して主要テーマを反復したいと思う。反復することによって、テーマがより明確になる効果があると思う。高齢者福祉情報を書き始めた2日目のテーマは高齢者の「閉じこもり」であった。
・・・健康に問題がないのに外出しない「閉じこもり」状態の高齢者が1〜2割に上ることが、厚生労働省の調査で分かった。これらの人は100%認知症の予備軍といっても過言でないと思う。生涯青春の会で、退職した夫を持っている60代の婦人数人との交流がある。彼女たちの嘆きはおおよそ「家ではなにもしない。毎日3合強のお酒を飲む。・・・このままだと健康が心配だ。何もしないで1日を過ごしてもったいないという気持ちが起らないのだろうか」というものである。
厚生労働省の調査でも高齢者の閉じこもりは「寝たきり」「認知症」につながるという前提で問題にしているのである。今回の調査は4市町村の65〜75歳以上の延べ2413人(男893人、女1520人)を対象に行ったデータである。調査の対象者は介護保険制度で「要支援」「要介護」とされる人以外で実施したものである。「閉じこもり」の定義を「週1回しか外出しない状態」として集計したものだ。最も高かったのは、三本木町の女性の22%。須賀川市の女性の21.5%が続き、最低は同市の男性(同)13%だった。「閉じこもり」と分類した人に外出する際の理由を聞いたところ、男女にかかわらず、最多は「通院」だったというから唖然とする。
介護保険の対象外の高齢者が、1週間に1回しか外出しないというのも異常である。その僅か1回の外出先が通院だというから社会から隔離した生活を送っているといわねばならない。これらの人には話をする友人が近所にいないのだろうか。貧弱な生活文化しかないので、友人がいない、少ないという結果を生むのではないだろうか。ともかく「閉じこもり」ではどうにもならないと声を大にして叫びたい思いだ。このような人達が認知症になって、国の保険財政を破綻させると言ったら言い過ぎだろうか。・・・・
1週間に1回しか外出しない高齢者が13%〜22%のいるというデータは驚愕に値する。現在で要介護人口は410万人である。1週間に一回しか外出しない高齢者の平均を17%とすると、おおよそ400万人が閉じこもっていることになる。
高齢者人口 2400万人×0.17=408万人
これでは、認知症が激増することは明らかである。生涯青春の会は微力ではあるがこのテーマに挑戦して行く決意である。今は多くの賛同者は出てくることを祈るのみである。
5、認知症の年代別の割合 (2006年8月23日高齢者福祉情報から)
生涯青春の会で12月から2月まで3回〜6回「脳いきいきセミナー」を開催することにした。その準備に以前熟読した認知症の専門医である金子満雄(金子クリニック)先生のページ開く。このホームページは、生涯青春の会を作って認知症の予防運動をしようとの決意を促がしてくれたのである。
金子クリニックホームページ http://
その中に認知症の年代的な割合が出ている。この記述を引用したい。
「私たちが全国数百ヶ所の保健師、医師や保健所の協力の元に実施してきた痴呆健診によって、以下のようなことが分かってきました。
早期痴呆を含めた年齢群ごとの全痴呆頻度は加齢とともに増加し、50歳代で5%、60歳代で12%、70歳代で30%となり、80歳代で初めて50%を越えます。90歳代ではほぼ75%に達し、そして100歳を越えると97%に達します」
再度確認しよう。認知症になる割合は
50代 5%・・・ 100人中5人
60代 12%・・・100人中12人
70代 30% 10人中3人
80代 50% 2人に1人
90代 75% 4人中3人
100歳以上 97%
生涯青春の会の発足直前までは「80代壮健の会」という名前で発足の準備をしていた。いうまでもなく、80代には約半数の人が痴呆になるが、その「50%の仲間に入るな!」がスローガンであった。
6、 凄い経歴の人がなぜ認知症になるのか
(2006年9月5日高齢者福祉情報から)
7月4日マイミクのシマさんの日記は「認知症」であった。ご本人の了解を得て日記の大半をそのまま引用させていただきました。
・・・認知症にはなりたくないなと思う。私の父も認知症だった。無くなったのが91才で80歳ごろからおかしくなってきた。自分の頭の中からいろいろなことか消えていくという自覚のあったときがあってすごい恐怖と戦っていた。
友人のご主人も京大の教授をされていたのだが退職後、症状がだいぶ進んできたときに「どうしたらいいのだろういっそ死んでしまおうか。でもそんな事はできないしなぁ」とおっしゃたそうである。その方も父も今は旅立ってしまったが、立派に活躍していた人が恥ずかしい有様になっていくのをみるのは本当に辛いものがある。・・・・
京大の教授までした人がなぜ認知症になるのか。生涯青春の会の主要メンバーでこのような例の意見交換をしてきたが、統一的な見解は次の通りである。
「過去のどんな経歴があっても、過去の常識(知識)のみで生きている人は認知症になる確率が高い。新しい情報を受け入れない人は、脳がどんどん退化しているのである」 生涯青春の会の主要メンバーで認知症の肉親を抱えている人が3人いる。この中に一人は元新聞記者である。バリバリの元新聞記者が考えられない姿に変わっていくのである。なぜ、凄い経歴の人が認知症になるのだろうか。・・・・
この記述に対して多くの書き込みを頂いた。ここで3つを引用したい
*ナース岩下さんの書き込み
「私が読んだ書物によれば、すごい人というよりは、人生において、なにかしら 解決しないままの課題がある方の場合に、認知症の症状が強くでるという説があります。高齢者ケアを実践していて、確かにそれを感じることがあります。すごい方というのは、たぶん、仕事などで成功を収めている方だと思うのですが、そういう方は、はやり人知れず、努力をされ、社会のいろいろな軋轢と戦い、そして、仕事の成功のために何かを犠牲にされている場合も多いと思うのです。そうすると、その何かを、自分自身の中できちんと解決せずに、時だけがたってしまい、脳の萎縮や障害が起きたときに、そのことが気になってしょうがないといった状況になるのではないかと思います。
徘徊といわれている、見た目には目的もなく、あてどなく歩き回る症状も、ご本人の中には、きちんと目的があるといわれており、どこかへ行きたいという気持ちがあるから、そのどこかを探して歩き回るといわれています。確かに、何かを一生懸命さがしておられるような印象を受けるのです。その何かが、たぶん、その方の人生の中で大切な気にかかることなんだろうな、と思うのです。
脳CTやMRIをとって、同じように脳萎縮があっても症状が穏やかな方もいれば、激しい方もいらっしゃいます。その差は、人生の課題をきちんと解決して生きてきた方と解決しないままになっている方の差ではないかと、私は思っています」
*ンチャさんの書き込み
「認知症になる大きな原因の一つは、脳に対する刺激が少なくなったり、弱くなったりすることにあります。人間の体は脳であろうと筋肉であろうと、使わずに刺激を与えないでおくと衰えていくものなのです。『凄い経歴の人』は、それまでの生活がいつも刺激的で、脳をよく使い、脳に対する刺激もとても強いものだったはずです。しかし退職すると、それまでの刺激の強かった生活があだとなり、仕事のない生活に何の刺激も感じなくなってしまうのです。悪いことに『凄い経歴の人』は、プライドも高いことが多いので、他の人の意見に耳を傾け、アドバイスに従おうともしないことが多いものです。『過去の栄光』にとらわれすぎて現実を直視することができず、受け入れることもできなくなって、認知症への道を歩むことになってしまうのではないかと思います。ただ、そういう人でも話を聞いてくれる人がいると、認知症になりにくいようです。「回想療法」というのがありますが、回想することによって、昔の興奮がよみがえったりするのだと思います」
*09月05日 ンチャさんの書き込み
脳も体も、働かせて刺激を与えないと退化してしまうのは同じなのですが、刺激の与え方に大きな違いがあります。例えば体は、1キロメートル歩けば、1キロメートル歩いた分確実に体に負荷を与えます。
しかし、脳はそう単純ではありません。ドラマを見て感動しても、同じドラマを2度目に見たときは、1度目ほどは感動しないことが多いということです。
なぞなぞやクイズなども、一度目はとても脳を使って、とても良い頭の体操になります。しかし当然のことですが、すでに答えを知ってしまってからは、同じ問題では、脳を鍛えることはできなくなってしまうのです。
沖縄戦当時の海兵隊員ユジーン・B.スレッジ氏の手記を翻訳した『泥と炎の沖縄戦』という本で彼は、戦争という極限状態では平和がとてもありがたく思えたそうです。しかし、戦争から引き上げてきたら、日常生活を送ることがとても難しくなっていたそうです。戦地に比べて日常生活の刺激のなさがあまりにも苦痛に感じられて、精神的に参るほどだったとのことです。
元ばりばりの新聞記者は、現役当時毎日のように血肉躍るようなニュースに接していたと思います。しかし、現役の時と比べると日常生活は、彼にとって全く刺激のない生活と同じなのではないでしょうか。そのため、脳に刺激が行かず、脳の萎縮が進んだとも考えられるのではないでしょうか。
7、マンネリ化すれば脳は退化する。(2006年9月19日の高齢者福祉情報から)
10月から「脳いきいきセミナー」を開始する。セミナーの主題は「認知症にならない生き方」の探求である。この主題に沿った情報を提供するのがセミナーの目的である。認知症になった後のことも情報として提供するが、このセミナーの目的の大半が「認知症にならない生き方」の探求なのである。9月18日このテーマに関して沖縄のンチャさんから次の書き込みを頂いた。セミナーで意見交換をする目的で全文を引用したい。
「どんなものでも、マンネリ化すれば、脳はあまり刺激を受けなくなり、退化していくようです。日本陸軍が採用した戦闘機「隼」の設計者糸川英夫氏は、日本ロケット開発の先駆者でもあり、数々の発明も行っています。その糸山氏は、一つだけの専門の世界に浸り続けると呆けてしまうと主張し、10年ごとに職業を変えたというのです。彼はその著書「独創力」の中で次のように述べています。
『同じ仕事を10年もしていれば地位も収入も安定してくるし、自分自身に気の緩みも出てくるだろう。あげくに独創力が止まる。だから私は安住を避けるために10年ごとにジャンルの異なる仕事に挑戦することになる。(中略)年を重ねた人ほど経験も豊富だし、知識や情報の量も多い。情報の量が豊かだから、ものに対する思考や判断を正確に、早く他の人に伝えることができる。(中略)年をとるにつれて金が貯まる。家や土地を持ち、家族も増える。世間的な名声も得るようになる。とりたてて不安もない。そういう安定感が能力を低下させ、独創力を低下させる基になる。
社会的な地位が安定すると、地位が高ければ高いほど、人にはその地位を守ろうとする気持ちが生じてくるものだ。失敗の可能性がありそうだと、すぐ避けようとする。つまり、ひたすら現状維持を図ろうと努めるわけだから、変化があってはならない。こういう人には独創的なプランを立てるとか、未知の世界を知るとか、困難な問題にたちむかおうとする積極的な姿勢はどこにもない。これでは年齢とかかわりなく、頭の回転が鈍くなるのはあたりまえである。』
糸川秀夫氏は、戦前は戦闘機の設計に携わったのだが、戦後は医学や音響学の研究をし、その後日本の宇宙開発の先駆者ともなっています。またその他に、占星術や、バレエ、チェロなどの研究もやっています」
8、廃用性症候群(1)(2006年10月10日の高齢者福祉情報から)
病気になる前の一定の知識は、病気そのものを避ける意味で不可欠のテーマであると思う。詳しくは後日に送るが、昨日新潟大学の阿保徹先生の講演会に参加して更にその感を深くした。
10月6日ンチャさんからコミ「要介護度改善ケア研究会準備室」の「廃用性症候群の予防改善」を読むよう薦められた。廃用性症候群の予備知識が明確であれば、そうならないための行動が自発的に生まれると思う。以下のナース岩下さんの説明を読むと、知らないことは悲惨を産む土壌のように思う。
http://
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2006年10月01日 ナース岩下
廃用性症候群の予防改善
「廃用性症候群」はいようせいしょうこうぐん と、読みます。 あんまりよい言語ではありませんが、意味としては、安静などのために心身の様々な機能を
動かさなかったこと、使わなかったことによっておこる 症状のことです。
例えば、
高齢者が、風邪をひいて、1週間くらい寝てばかりの生活を 送りました。食欲もまあまあではありましたので、入院はしなくてよいとのことで、ご家庭で様子をみました。そして、風邪は治ったのですが、今まで、自分ひとりでしっかりとトイレにいけたのに ふらふらしている。なんだか、ぼけたような、物忘れが強くなった。 心配なので、オムツを使用している。
こういった症状はすべてが廃用性症候群です。そして、このことをきっかけにどんどん体調は悪くなり 本当の認知症がひどくなり・・・・ 似たようなお話を聞いたことがありませんか? 現在の高齢者問題は、この廃用性症候群に対するケアを普及し、実践していくことが重要です。
特に病院やショートステイなどで同じような現象がおきています。 病院で、入院の原因である病気は治してくれても退院時には、そのほかの症状が追加されて退院する。ショートステイで、家族の介護疲れを緩和するために利用したのに、結果として、状態が悪くなって自宅に帰ってくる・・・ おかしいと思いませんか?
この研究会で、勉強していくテーマのひとつに この問題があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このテーマに関連して10月06日ンチャさんから次の書き込みを頂いた。〈中ほどを引用〉認知症になるメカニズムを明確に心に刻みたいものである。
・・・人間は、体でも脳でも、使わないと退化していく性質があります。
腕や脚を骨折したときギブスを巻きますが、一月後にギブスをはずした場合、ギブスをしてなかった腕や脚と比べるととても細くなっていることが分かります。これは年齢に関係なく、若者でもそうです。
脚を骨折したからと寝てばかりで体を動かさないでいると、骨折した脚だけでなく、もう片方の脚や腕など、体全体の筋肉が細くなってしまいます。筋肉ばかりでなく内臓も含めた体全体、そしてそれを司る脳まで衰えてしまうのです(廃用性萎縮)。
この廃用性萎縮は、生体だけでなく、社会的なことが原因でも起こりうるものです。人が退職し、社会から必要ないものとされてしまったとき、その人の存在は急速に萎縮していきます。その場合、筋肉などの体組織より、脳から萎縮するようです。つまり、認知症になりやすくなるのです。・・・・
10、この数字が時代の流れだ(自分の死に場所)
(2006年10月24日の高齢者福祉情報から)
10月15日医師の藤・霽月さんから以下のデータの書き込みがあった。藤さんが講演で使っているスライド原稿である。「死亡者数が1.7倍に増えるのに、病床は半減する。病院で死ねるなんて思わないほうが良いですよ」というアドバイスだ。現在は約80%の人が病院で亡くなっているが、これが難しくなってくるのだ。自分の死の場所を明確にする必要がある時代といえる。
死亡者数推計 一般病床数 療養型病床数 床数計
2003年 1067000人
2006年 96万床 38万床 134万床
2009年 1219000人
2012年 65万床 15万床 80万床
2015年 1376000人
2021年 1514000人
2027年 1615000人
2033年 1680000人
2039年 1699000人
11、砂糖健康学入門から 人間の脳細胞は70歳を超えても増える
1999年にアメリカでエリクソン博士が、「人間の脳細胞は70歳を超えても増える!」という画期的な研究結果を発表しました。しかも、海馬の細胞が、もっとも増えることがわかってきています。
脳細胞を増やし、脳の働きをよくするためには、常に脳を使って鍛えることが重要です。それには、脳に充分なエネルギーを供給しなくてはなりません。脳の唯一のエネルギー源は、ブドウ糖。ブドウ糖を摂取すると、脳の働きは格段に活性化します。
20歳の女性たちに、言語の記憶力や流暢さの実験を行うと、ブドウ糖を含む飲みものを摂取したグループのほうが、頭がすっきりして、はるかに多くの単語を思い出せたという結果も出ています。
しかも脳は、1日の摂取エネルギーの20%に当たる約500キロカロリーを消費する大食いの臓器。そして脳が蓄積できるブドウ糖はほんのわずかです。砂糖は、速効性のエネルギー源として素早くブドウ糖に分解され、脳の働きを活性化し、記憶力の向上を助ける重大な働きを持っています。
|
|
|
|
コメント(6)
「11、砂糖健康学入門から、、、、」へ補足情報です。
―――――――――――――――――――――――――
認知症?実は低血糖
低血糖の際になめるブドウ糖キャンデーを患者に手渡す板垣晃之さん(右)(浴風会病院で) 高齢者の場合、高血圧ばかりでなく、糖尿病の治療も、若い人と同じように行うと問題が起きる場合が少なくない。
糖尿病を患う東京都の男性(84)は、10年前から血糖値を下げるホルモン、インスリンの注射を毎日打っている。ところが、数年前から、口数が減って一日中ボーッとしている、家族と話したことを覚えていない、といった症状が現れた。好きだった碁も打たず、立って歩くことすら難しくなり、一昨年、東京都杉並区の浴風会病院を受診した。
朝食後の血糖値は200と、糖尿病と診断される下限の数値で、比較的良い水準だった。だが、診察した板垣晃之さん(現在さいたま市の大宮共立病院副院長)は「インスリンの量が多く、血糖値が下がり過ぎている」と判断し、インスリンの量を減らした。
男性の血糖値は以前より高くなったが、表情は明るくなって会話がスムーズになり、散歩も楽しめるようになった。家族も「話しかけても答えなかったが、今はとても活発に話すようになった」と喜ぶ。
血糖値の高い状態が続いて糖尿病が進行すると、失明に至る網膜症や、腎機能障害などの合併症につながり、高齢者でも糖尿病の治療は必要だ。
だが、高齢者は薬を分解する代謝機能が落ちていることなどから、薬の効果が強く出やすい。血糖値が下がりすぎ、低血糖症状が現れる恐れがある。
板垣さんは「脳の細胞はブドウ糖を栄養源としているので、低血糖でブドウ糖が足りない状態が続くと、考える力が落ち、認知症のような症状が出る場合もある。運動能力にも影響が出て、ふらついて転びやすくなる」と説明する。
そして「転倒し、骨折して寝たきりになったり、頭を強打したりする恐れもある。高齢者の低血糖は命にかかわる」と警告する。
ところが、ふらつく、思考力が落ちる、といった症状は「年のせい」「認知症」と、見過ごされることが少なくない。糖尿病の診断基準は、若い人も高齢者も同じであることから、画一的な治療が行われがちなことが背景にある。
東京都済生会渋谷診療所長の松岡健平さんも「糖尿病は心筋梗塞(こうそく)を引き起こす危険因子とされるが、高齢者の場合、血圧やコレステロールなどに比べると重要な因子とは言えない。血糖値を厳格に下げようとするあまり、低血糖で転倒事故などが起きては元も子もない」と話す。
高齢者の場合、数値だけにとらわれることなく、一人一人の体調に合わせた治療がとりわけ大切だ。(山口博弥、神宮聖、田中秀一)
低血糖 血糖値が下がり過ぎることで、脱力感、冷や汗、動悸(どうき)、震え、さらに意識障害、意識を失う昏睡(こんすい)、けいれんといった症状が急激に起きる。砂糖などを口にすると治まる。血糖降下剤やインスリンで治療している場合に起きる可能性がある。
(2006年1月14日 読売新聞)
★ 超寿宣言 認知症?実は低血糖
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/renai/20060114ik02.htm
―――――――――――――――――――――――――
認知症?実は低血糖
低血糖の際になめるブドウ糖キャンデーを患者に手渡す板垣晃之さん(右)(浴風会病院で) 高齢者の場合、高血圧ばかりでなく、糖尿病の治療も、若い人と同じように行うと問題が起きる場合が少なくない。
糖尿病を患う東京都の男性(84)は、10年前から血糖値を下げるホルモン、インスリンの注射を毎日打っている。ところが、数年前から、口数が減って一日中ボーッとしている、家族と話したことを覚えていない、といった症状が現れた。好きだった碁も打たず、立って歩くことすら難しくなり、一昨年、東京都杉並区の浴風会病院を受診した。
朝食後の血糖値は200と、糖尿病と診断される下限の数値で、比較的良い水準だった。だが、診察した板垣晃之さん(現在さいたま市の大宮共立病院副院長)は「インスリンの量が多く、血糖値が下がり過ぎている」と判断し、インスリンの量を減らした。
男性の血糖値は以前より高くなったが、表情は明るくなって会話がスムーズになり、散歩も楽しめるようになった。家族も「話しかけても答えなかったが、今はとても活発に話すようになった」と喜ぶ。
血糖値の高い状態が続いて糖尿病が進行すると、失明に至る網膜症や、腎機能障害などの合併症につながり、高齢者でも糖尿病の治療は必要だ。
だが、高齢者は薬を分解する代謝機能が落ちていることなどから、薬の効果が強く出やすい。血糖値が下がりすぎ、低血糖症状が現れる恐れがある。
板垣さんは「脳の細胞はブドウ糖を栄養源としているので、低血糖でブドウ糖が足りない状態が続くと、考える力が落ち、認知症のような症状が出る場合もある。運動能力にも影響が出て、ふらついて転びやすくなる」と説明する。
そして「転倒し、骨折して寝たきりになったり、頭を強打したりする恐れもある。高齢者の低血糖は命にかかわる」と警告する。
ところが、ふらつく、思考力が落ちる、といった症状は「年のせい」「認知症」と、見過ごされることが少なくない。糖尿病の診断基準は、若い人も高齢者も同じであることから、画一的な治療が行われがちなことが背景にある。
東京都済生会渋谷診療所長の松岡健平さんも「糖尿病は心筋梗塞(こうそく)を引き起こす危険因子とされるが、高齢者の場合、血圧やコレステロールなどに比べると重要な因子とは言えない。血糖値を厳格に下げようとするあまり、低血糖で転倒事故などが起きては元も子もない」と話す。
高齢者の場合、数値だけにとらわれることなく、一人一人の体調に合わせた治療がとりわけ大切だ。(山口博弥、神宮聖、田中秀一)
低血糖 血糖値が下がり過ぎることで、脱力感、冷や汗、動悸(どうき)、震え、さらに意識障害、意識を失う昏睡(こんすい)、けいれんといった症状が急激に起きる。砂糖などを口にすると治まる。血糖降下剤やインスリンで治療している場合に起きる可能性がある。
(2006年1月14日 読売新聞)
★ 超寿宣言 認知症?実は低血糖
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/renai/20060114ik02.htm
砂糖は悪いものと言う印象を持っている人が多い。砂糖健康学入門の補足説明になるが以下を引用しておきたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「砂糖の正しい知識を」から
http://sugar.lin.go.jp/japan/view/jv_9908a.htm
和洋女子大学 教授 坂本 元子
3.糖と脳の働き
我々の体の中で糖を必要としている臓器はどこだろう。最も多く糖を必要としているのは脳である。勿論、脳以外の臓器でも赤血球や腎臓の髄質、精巣などはブドウ糖しかエネルギーとして使っていない。また、筋肉もブドウ糖をエネルギー源として使っている。
昼夜の別なく働く脳のエネルギーをブドウ糖のみで賄っているとすれば、脳を正常に働かせるには常に脳が必要とするブドウ糖を補給しなければならない。脳へブドウ糖を運ぶ方法は我々の毎日の食事からである。脳のエネルギーを論じるには、まず1日の食事の在り方から入る方が理解しやすい。
先に述べたFAO/WHOの報告の中に、砂糖のもう1つの働きとして「ブドウ糖と記憶」について論評したものがある。ブドウ糖の投与によって人やラットの記憶力が増強するという実験結果があり、特にその効果は高齢者において強くみられるとするものであり、ブドウ糖投与と記憶過程の改善の関係が明らかにされている。
この上に立って、糖分の摂取と脳の働きとの関係について述べたい。
生理学的に明らかなことは、脳の活動には多くのエネルギーが必要であること、またその主要なエネルギー源はブドウ糖であることである。脳の重量は体重の約2%であるが、消費するエネルギーは体全体のエネルギー消費量の約20%で、大変なエネルギーを必要としている。人が生きるためのエネルギー源となる栄養素には、たんぱく質や糖質、脂質があり、エネルギー放出量は脂肪が最も多いが、残念ながら脳が必要とするエネルギー源はブドウ糖だけである。
最近では、ペプチドという分子量の小さいたんぱく質が脳のエネルギーを司っているという説もあるが、現在のところ脳の主要なエネルギー源はブドウ糖である。
脳が使うエネルギー源のブドウ糖は、1日当たり120gとされており、1gの糖のエネルギー放出量を4kcalとすると、脳は1日480kcal、約500kcalを使っていることになる。ブドウ糖を必要とする臓器は、他にも赤血球や腎臓の髄質、一部の筋肉があり、1日に必要なブドウ糖の量は約150gといわれている。これらのブドウ糖は食事から確保されるが、1回の食事で肝臓に貯蔵できるブドウ糖の量は約60といわれており、1日に必要なブドウ糖を得るためには、1日3回の食事で定期的にブドウ糖のもとになる食品を摂取する必要がある。
摂取された糖類は分解されてブドウ糖になり、吸収されて血液の中に入る。血液中のブドウ糖は全血液中に5g位であるが、5gのブドウ糖は約1時間で消費されてしまう。
一方、摂取したブドウ糖は、筋肉や肝臓でグリコーゲンという形で貯蔵される。血液中のブドウ糖は、血液が全身を回っているうちに消耗してくるので、貯蔵したグリコーゲンを分解してブドウ糖へ戻し、脳や全身に送らなければならない。しかし、グリコーゲンからブドウ糖への分解には時間がかかる上に、グリコーゲンから一度乳酸へ変わってから肝臓へ送られ、そこでブドウ糖へ変わるので効率が悪く、すぐに脳へ送ることはできない仕組みになっている。
したがって、脳を効果的に働かせるには、1日3回の食事を定期的に摂取し、血液中のブドウ糖濃度を一定に保ちながら脳へ運び、十分にエネルギーを与えることが大切である。
例えば、朝食を抜いたとしよう。前夜食べた食事から約60gのグリコーゲンが肝臓に蓄えられるが、翌朝はそのグリコーゲンはなくなる計算になる。また、血液中のブドウ糖濃度が減少して脳へ入りにくい状態になり、脳のエネルギー源がなくなって働かないことになる。食事を抜くことは、脳へのエネルギー補給ができないことになり、記憶の過程に影響を与えることにもなりかねない。
4.コーヒーと砂糖
格好良くコーヒーを飲む人やダイエットを試みる人の行動には、「コーヒーはブラックで。」という気持ちが強い。コーヒーは嗜好食品であるから個人の好みにあった飲み方で楽しむにこしたことはないが、「3時頃にややお腹も空いたし、頭休めにコーヒーでも」という場合には、是非砂糖を入れたコーヒーをお勧めしたい。
昼食後の血液には、十分なブドウ糖があり、脳や全身に運んでエネルギーを作っているが、3時間もすると血液中のブドウ糖の量は低下してくる。夜の食事までには時間があるので、補充が必要になる。そこで人は間食を摂ることになる。コーヒーにはカフェインが入っていて、血液を通して脳関門を通り、中脳を刺激する。そのために、疲労がとれたような気になったり、気分もやや高揚してくる。しかし、エネルギーのない状態では脳は働かないことになる。このような時に、ブドウ糖を体の中に入れると脳は働き始める。つまり、3時のお茶の時間にはコーヒーに砂糖を入れるか、甘いお菓子で糖分を補給するかが必要になってくる。
定期的に糖を補給することは、脳の発育や脳の働きに必要なことである。栄養状態が極度に悪い子どもでは知能の発育も遅れることが発展途上国で証明されている。このような子ども達には、療法として1日6回の食事が与えられる。朝6時、10時、12時の昼食、3時のおやつ、6時の夕食に10時の夜食と、6回の食事を与え、脳へのエネルギーの補給を怠らない。さもなければ、子ども達の知能の発達が遅れてくるからである。
糖をだらだらと間断なく摂取することにも問題があるが、補給が途絶えることにも問題があって、脳の働きに異常をきたす。食事は規則正しく、3時のおやつには糖分の摂取を、というのが人の健康を守る望ましい食べ方のようである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「砂糖の正しい知識を」から
http://sugar.lin.go.jp/japan/view/jv_9908a.htm
和洋女子大学 教授 坂本 元子
3.糖と脳の働き
我々の体の中で糖を必要としている臓器はどこだろう。最も多く糖を必要としているのは脳である。勿論、脳以外の臓器でも赤血球や腎臓の髄質、精巣などはブドウ糖しかエネルギーとして使っていない。また、筋肉もブドウ糖をエネルギー源として使っている。
昼夜の別なく働く脳のエネルギーをブドウ糖のみで賄っているとすれば、脳を正常に働かせるには常に脳が必要とするブドウ糖を補給しなければならない。脳へブドウ糖を運ぶ方法は我々の毎日の食事からである。脳のエネルギーを論じるには、まず1日の食事の在り方から入る方が理解しやすい。
先に述べたFAO/WHOの報告の中に、砂糖のもう1つの働きとして「ブドウ糖と記憶」について論評したものがある。ブドウ糖の投与によって人やラットの記憶力が増強するという実験結果があり、特にその効果は高齢者において強くみられるとするものであり、ブドウ糖投与と記憶過程の改善の関係が明らかにされている。
この上に立って、糖分の摂取と脳の働きとの関係について述べたい。
生理学的に明らかなことは、脳の活動には多くのエネルギーが必要であること、またその主要なエネルギー源はブドウ糖であることである。脳の重量は体重の約2%であるが、消費するエネルギーは体全体のエネルギー消費量の約20%で、大変なエネルギーを必要としている。人が生きるためのエネルギー源となる栄養素には、たんぱく質や糖質、脂質があり、エネルギー放出量は脂肪が最も多いが、残念ながら脳が必要とするエネルギー源はブドウ糖だけである。
最近では、ペプチドという分子量の小さいたんぱく質が脳のエネルギーを司っているという説もあるが、現在のところ脳の主要なエネルギー源はブドウ糖である。
脳が使うエネルギー源のブドウ糖は、1日当たり120gとされており、1gの糖のエネルギー放出量を4kcalとすると、脳は1日480kcal、約500kcalを使っていることになる。ブドウ糖を必要とする臓器は、他にも赤血球や腎臓の髄質、一部の筋肉があり、1日に必要なブドウ糖の量は約150gといわれている。これらのブドウ糖は食事から確保されるが、1回の食事で肝臓に貯蔵できるブドウ糖の量は約60といわれており、1日に必要なブドウ糖を得るためには、1日3回の食事で定期的にブドウ糖のもとになる食品を摂取する必要がある。
摂取された糖類は分解されてブドウ糖になり、吸収されて血液の中に入る。血液中のブドウ糖は全血液中に5g位であるが、5gのブドウ糖は約1時間で消費されてしまう。
一方、摂取したブドウ糖は、筋肉や肝臓でグリコーゲンという形で貯蔵される。血液中のブドウ糖は、血液が全身を回っているうちに消耗してくるので、貯蔵したグリコーゲンを分解してブドウ糖へ戻し、脳や全身に送らなければならない。しかし、グリコーゲンからブドウ糖への分解には時間がかかる上に、グリコーゲンから一度乳酸へ変わってから肝臓へ送られ、そこでブドウ糖へ変わるので効率が悪く、すぐに脳へ送ることはできない仕組みになっている。
したがって、脳を効果的に働かせるには、1日3回の食事を定期的に摂取し、血液中のブドウ糖濃度を一定に保ちながら脳へ運び、十分にエネルギーを与えることが大切である。
例えば、朝食を抜いたとしよう。前夜食べた食事から約60gのグリコーゲンが肝臓に蓄えられるが、翌朝はそのグリコーゲンはなくなる計算になる。また、血液中のブドウ糖濃度が減少して脳へ入りにくい状態になり、脳のエネルギー源がなくなって働かないことになる。食事を抜くことは、脳へのエネルギー補給ができないことになり、記憶の過程に影響を与えることにもなりかねない。
4.コーヒーと砂糖
格好良くコーヒーを飲む人やダイエットを試みる人の行動には、「コーヒーはブラックで。」という気持ちが強い。コーヒーは嗜好食品であるから個人の好みにあった飲み方で楽しむにこしたことはないが、「3時頃にややお腹も空いたし、頭休めにコーヒーでも」という場合には、是非砂糖を入れたコーヒーをお勧めしたい。
昼食後の血液には、十分なブドウ糖があり、脳や全身に運んでエネルギーを作っているが、3時間もすると血液中のブドウ糖の量は低下してくる。夜の食事までには時間があるので、補充が必要になる。そこで人は間食を摂ることになる。コーヒーにはカフェインが入っていて、血液を通して脳関門を通り、中脳を刺激する。そのために、疲労がとれたような気になったり、気分もやや高揚してくる。しかし、エネルギーのない状態では脳は働かないことになる。このような時に、ブドウ糖を体の中に入れると脳は働き始める。つまり、3時のお茶の時間にはコーヒーに砂糖を入れるか、甘いお菓子で糖分を補給するかが必要になってくる。
定期的に糖を補給することは、脳の発育や脳の働きに必要なことである。栄養状態が極度に悪い子どもでは知能の発育も遅れることが発展途上国で証明されている。このような子ども達には、療法として1日6回の食事が与えられる。朝6時、10時、12時の昼食、3時のおやつ、6時の夕食に10時の夜食と、6回の食事を与え、脳へのエネルギーの補給を怠らない。さもなければ、子ども達の知能の発達が遅れてくるからである。
糖をだらだらと間断なく摂取することにも問題があるが、補給が途絶えることにも問題があって、脳の働きに異常をきたす。食事は規則正しく、3時のおやつには糖分の摂取を、というのが人の健康を守る望ましい食べ方のようである。
「トレーニングの後はシャワーを浴びるよりも先にまず糖の摂取を」
グリコーゲンの再補充こそがハードな練習からの回復の鍵
臨床スポーツ医学1996年ワンポイントアドバイス
筋肉のグリコーゲンは運動を継続するための燃料であり、持久運動では特に重要である。多くのデータから、運動直前の筋肉グリコーゲンレベルが持久運動能力に直接的に影響することが明らかになっている。ハードな練習を行った直後では、筋肉のグリコーゲンは枯渇しているので、十分な補給をしないと翌日の練習に大きなハンデを背負うことになる。グリコーゲンの再補充には練習後に一刻も早く糖を摂取することが大切である。
グリコーゲンの原料となるグルコースは、グルコース輸送担体4型(Glut4)と呼ばれるキャリアータンパク質によって血液から筋肉へ吸収され、グリコーゲンに合成される。Glut4はインスリンが存在するときにだけ筋肉への糖の吸収を促進し、インスリンの作用がないときには働かない。この現象はインスリンによるGlut4のトランスロケーションとして知られている。しかし、運動直後に限っては、インスリンの作用が無くてもこのGlut4のトランスロケーションが起こっており、強力にグルコースを筋肉に吸収できるのである。このタイミングを逃してはいけない。糖の溶液を練習前に準備しておき、シャワーを浴びるよりも先に飲むことが重要である。グリコーゲンが枯渇した状態が長時間続くと、人間の身体は筋肉を分解してまで糖を合成しようとする。大切な筋肉を守るためにも糖の摂取は必要である。
摂取する糖は砂糖水が手軽ではあるが、砂糖はグルコースとフルクトースの化合物でありグルコースは半分しかないので効率が良くない。麦芽糖(グルコース2分子の化合物、マルトースシロップなどの名前で市販されている)やデキストリン(グルコースのつながったもの)が望ましい。腐敗を避けるために、作り置きをせず毎日調製する。長時間の激しい運動の後では体重1kgあたり1g程度(体重60kgの人ならば60g)の糖分、例えば20%糖溶液をゆっくり300ml飲めばよい。人によっては飲みやすいように味を付ける工夫も必要であろう。
運動直後は食欲が低下しており、糖の溶液を受けつけないこともある。特に、練習中に水分が枯渇すると吐き気を催すこともあり練習直後に糖溶液を飲むことは難しい。練習中にも十分な水の補給を心がける必要がある。グリコーゲン回復のためには練習中の水分摂取の時点から注意を払わなければならない。
★ 栄養化学
http://www.nutrchem.kais.kyoto-u.ac.jp/fushiki/AfterTraining/PostTraining.html
グリコーゲンの再補充こそがハードな練習からの回復の鍵
臨床スポーツ医学1996年ワンポイントアドバイス
筋肉のグリコーゲンは運動を継続するための燃料であり、持久運動では特に重要である。多くのデータから、運動直前の筋肉グリコーゲンレベルが持久運動能力に直接的に影響することが明らかになっている。ハードな練習を行った直後では、筋肉のグリコーゲンは枯渇しているので、十分な補給をしないと翌日の練習に大きなハンデを背負うことになる。グリコーゲンの再補充には練習後に一刻も早く糖を摂取することが大切である。
グリコーゲンの原料となるグルコースは、グルコース輸送担体4型(Glut4)と呼ばれるキャリアータンパク質によって血液から筋肉へ吸収され、グリコーゲンに合成される。Glut4はインスリンが存在するときにだけ筋肉への糖の吸収を促進し、インスリンの作用がないときには働かない。この現象はインスリンによるGlut4のトランスロケーションとして知られている。しかし、運動直後に限っては、インスリンの作用が無くてもこのGlut4のトランスロケーションが起こっており、強力にグルコースを筋肉に吸収できるのである。このタイミングを逃してはいけない。糖の溶液を練習前に準備しておき、シャワーを浴びるよりも先に飲むことが重要である。グリコーゲンが枯渇した状態が長時間続くと、人間の身体は筋肉を分解してまで糖を合成しようとする。大切な筋肉を守るためにも糖の摂取は必要である。
摂取する糖は砂糖水が手軽ではあるが、砂糖はグルコースとフルクトースの化合物でありグルコースは半分しかないので効率が良くない。麦芽糖(グルコース2分子の化合物、マルトースシロップなどの名前で市販されている)やデキストリン(グルコースのつながったもの)が望ましい。腐敗を避けるために、作り置きをせず毎日調製する。長時間の激しい運動の後では体重1kgあたり1g程度(体重60kgの人ならば60g)の糖分、例えば20%糖溶液をゆっくり300ml飲めばよい。人によっては飲みやすいように味を付ける工夫も必要であろう。
運動直後は食欲が低下しており、糖の溶液を受けつけないこともある。特に、練習中に水分が枯渇すると吐き気を催すこともあり練習直後に糖溶液を飲むことは難しい。練習中にも十分な水の補給を心がける必要がある。グリコーゲン回復のためには練習中の水分摂取の時点から注意を払わなければならない。
★ 栄養化学
http://www.nutrchem.kais.kyoto-u.ac.jp/fushiki/AfterTraining/PostTraining.html
糖は確かに体にとても大切な栄養素ですが、白糖の摂取には注意が必要です。白糖は精製され体に急速に吸収されやすくなっています。糖が体に急速に吸収されると血糖値が急に上がることになり、それが頻繁にあると健康に悪いのです。
普段の生活では、糖は炭水化物でとるのが、健康的な摂取法なのです。
――――――――――――――――――――――――――
白糖から黒糖へ
脳が生きていくためには「刺激」、「酸素」、「ブドウ糖」が必要です。
そうです、糖分(ブドウ糖)は脳や神経にとって非常に重要な栄養素です!!
その糖分も過剰摂取すると糖尿病なり、健康を害してしまいます。ですから糖の選択が必要になってきます。
一般的に黒糖は白糖よりも健康に良いとされています。黒糖には鉄分や亜鉛などミネラルがしっかりと含まれています。
次に吸収スピードにも大きな差があります。
これはインスリン分泌と関係がありますので重要です。
黒糖 先に脳にいく ゆっくり吸収される 1時間 効果が長く持続する
白糖 先にカラダにいく 短時間 10分 あっという間に体に50g脳に50gいく
なぜ吸収スピードにこんなにも差があるのでしょうか?
それは黒糖の黒い部分に砂糖の腸管吸収を阻止する物質がふくまれているからです。
ゆっくり吸収されるということはインスリン値もあんまり上昇しません。
★ 白糖から黒糖へ
http://www.geocities.jp/nagomi_chiro/kokutou.htm
普段の生活では、糖は炭水化物でとるのが、健康的な摂取法なのです。
――――――――――――――――――――――――――
白糖から黒糖へ
脳が生きていくためには「刺激」、「酸素」、「ブドウ糖」が必要です。
そうです、糖分(ブドウ糖)は脳や神経にとって非常に重要な栄養素です!!
その糖分も過剰摂取すると糖尿病なり、健康を害してしまいます。ですから糖の選択が必要になってきます。
一般的に黒糖は白糖よりも健康に良いとされています。黒糖には鉄分や亜鉛などミネラルがしっかりと含まれています。
次に吸収スピードにも大きな差があります。
これはインスリン分泌と関係がありますので重要です。
黒糖 先に脳にいく ゆっくり吸収される 1時間 効果が長く持続する
白糖 先にカラダにいく 短時間 10分 あっという間に体に50g脳に50gいく
なぜ吸収スピードにこんなにも差があるのでしょうか?
それは黒糖の黒い部分に砂糖の腸管吸収を阻止する物質がふくまれているからです。
ゆっくり吸収されるということはインスリン値もあんまり上昇しません。
★ 白糖から黒糖へ
http://www.geocities.jp/nagomi_chiro/kokutou.htm
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
脳いきいき セミナー 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
脳いきいき セミナーのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37860人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90055人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208307人