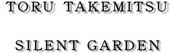|
|
|
|
コメント(27)
まず、若かりし武満徹にとってもっとも大事な音楽仲間であった鈴木博義と福島和夫との出会いについて。
亰華中学のときにわりに仲がよかった子がちょっとピアノが弾けたんですね。そいつの音楽仲間に、先だって亡くなった指揮者の浜田徳昭の弟がいたんです。そのころ浜田徳昭は玉川学園から武蔵高校に入ったところだったのかな、独自のコーラスグループを作っていたんです。そいつに、さそわれてそのグループに参加すると、鈴木博義、福島和夫がきていたわけです。
二人とも作曲に夢をもっていることがわかって、たちまち友達になるわけです。ぼくとちがって、彼らは子供のころから音楽をやってて、音符の書き方とか、具体的な楽譜の読み方とか、ボクはみんなこの二人に教わったんです。
ぼくがちょっと何か書くと、鈴木君なんかがよくきれいな譜面に書いてくれたものです。それで知らない間に、譜面の書き方を覚えたんです。
亰華中学のときにわりに仲がよかった子がちょっとピアノが弾けたんですね。そいつの音楽仲間に、先だって亡くなった指揮者の浜田徳昭の弟がいたんです。そのころ浜田徳昭は玉川学園から武蔵高校に入ったところだったのかな、独自のコーラスグループを作っていたんです。そいつに、さそわれてそのグループに参加すると、鈴木博義、福島和夫がきていたわけです。
二人とも作曲に夢をもっていることがわかって、たちまち友達になるわけです。ぼくとちがって、彼らは子供のころから音楽をやってて、音符の書き方とか、具体的な楽譜の読み方とか、ボクはみんなこの二人に教わったんです。
ぼくがちょっと何か書くと、鈴木君なんかがよくきれいな譜面に書いてくれたものです。それで知らない間に、譜面の書き方を覚えたんです。
古賀書店という神保町の音楽書専門の古本屋があるんですが、そこによく鈴木博義と行って、楽譜あさりをしました。知っている音楽の楽譜をを見つけ出して、ああ、あそこのところは楽譜の上ではこういう風に表現されるのか、と学んでいくわけです。ラジオで聞いて感激したフランクの「プレリュード、コラールとフーガ」の楽譜もここで見つけて、買いました。
それから、当時日比谷公会堂の前にアメリカのCIE図書館(後のアメリカ文化センター)というのがありまして、そこには、アメリカの音楽関係の雑誌もあれば、楽譜も沢山ありました。そして、毎週一回レコードコンサートが開かれて、アメリカから入ってきた最新のレコードを聞かせてくれたんです。そのときは、三人で必ず行ったものです。
さて、武満徹にとって初めの師となる清瀬保二との出会いは、1948年、武満が18歳の時で、偶然、目にした日米現代音楽祭というコンサートのポスターがきっかけになった。
その切符を買いに、そのころ日比谷映画のそばにあった東宝交響楽団の事務所にいったんです。そしたら、そこの人が親切そうだったので、『実は自分は音楽をやりたいと思っている。だれかいい先生につきたいんだけど、心当たりはないだろうか」というようなことを聞いたんですね。
そしたら、『いままでここに清瀬保二さんという人がいたんだけど、あの人はとてもいい人だから紹介してあげられたのに、いま帰られたところだ。今度聞いといてあげるから、また連絡してください』といわれたんです。それで何日後かに連絡したら、『清瀬さんが会ってもいいとおっしゃってる。よかったですね』といわれて、お宅までの簡単な地図を描いてくれた。それで祖師谷のお宅に会いに行くわけです。
その少し前に、清瀬さんの属していた新作曲家協会の発表会があって、そこでぼくは清瀬さんのヴァイオリン・ソナタを聞いて非常に感動していたこともあって、期待してうかがったら留守で、それから延々六時間も待つことになったわけです。
(清瀬保二は留守中の自宅に上がりこんでいる人間に出くわして、怪訝な顔をしたが、事情を説明すると了解してくれた。)
そのとき、清瀬さんのヴァイオリン・ソナタを聞いて、とても感動したという話をまずしたのが、よかったみたいですね。あの第二楽章で一ヵ所、ドッペルといって、二本の弦を同時に鳴らして二つの音を出して重ねる技法があるんですが、それを実に効果的に使っているところがあるんです。
清瀬さんの曲というのは、基本的にとてもシンプルで、技巧をこらしたり、大向こうの受けを狙ったりというところが全くない淡々とした曲がほとんどなんです。ほとんど俳句みたいなもんです。それだけに、そのドッペルを使った部分が実に効果的だったんですね。それを使ったがために一瞬にして曲全体が立体的になったような感じで、非常にインスピレーションを感じさせました。
清瀬さんとしても、そこは、ここはと思って作曲した部分だったらしく、これで画龍点晴になるんだよといってました。そこをほめられたことがとても嬉しかったみたいです。これからも遊びにきていいよと出入りを許されるのも、そのせいじゃなかったかと思います。
その切符を買いに、そのころ日比谷映画のそばにあった東宝交響楽団の事務所にいったんです。そしたら、そこの人が親切そうだったので、『実は自分は音楽をやりたいと思っている。だれかいい先生につきたいんだけど、心当たりはないだろうか」というようなことを聞いたんですね。
そしたら、『いままでここに清瀬保二さんという人がいたんだけど、あの人はとてもいい人だから紹介してあげられたのに、いま帰られたところだ。今度聞いといてあげるから、また連絡してください』といわれたんです。それで何日後かに連絡したら、『清瀬さんが会ってもいいとおっしゃってる。よかったですね』といわれて、お宅までの簡単な地図を描いてくれた。それで祖師谷のお宅に会いに行くわけです。
その少し前に、清瀬さんの属していた新作曲家協会の発表会があって、そこでぼくは清瀬さんのヴァイオリン・ソナタを聞いて非常に感動していたこともあって、期待してうかがったら留守で、それから延々六時間も待つことになったわけです。
(清瀬保二は留守中の自宅に上がりこんでいる人間に出くわして、怪訝な顔をしたが、事情を説明すると了解してくれた。)
そのとき、清瀬さんのヴァイオリン・ソナタを聞いて、とても感動したという話をまずしたのが、よかったみたいですね。あの第二楽章で一ヵ所、ドッペルといって、二本の弦を同時に鳴らして二つの音を出して重ねる技法があるんですが、それを実に効果的に使っているところがあるんです。
清瀬さんの曲というのは、基本的にとてもシンプルで、技巧をこらしたり、大向こうの受けを狙ったりというところが全くない淡々とした曲がほとんどなんです。ほとんど俳句みたいなもんです。それだけに、そのドッペルを使った部分が実に効果的だったんですね。それを使ったがために一瞬にして曲全体が立体的になったような感じで、非常にインスピレーションを感じさせました。
清瀬さんとしても、そこは、ここはと思って作曲した部分だったらしく、これで画龍点晴になるんだよといってました。そこをほめられたことがとても嬉しかったみたいです。これからも遊びにきていいよと出入りを許されるのも、そのせいじゃなかったかと思います。
清瀬保二は、のちに山根銀二との対談の中でそのときのことを次のように述べている。
いま僕のところに来る若い生徒がいるが、新作曲家の第二回作品発表会に来て、僕のヴァイオリン・ソナタを聴いて、その晩非常に興奮した。そこで自分は作曲に自信をもてないでやめようとで思ったが、あれを聴いてまたやりたくなったといってました。それで僕のところにやってきた。そういう話は僕も嬉しくて、面倒を見ているが、才能はありますね。第二楽章でドッペルを使った。そこで身震いしたというのだ。そんな細かいことを言われたのは初めてで、耳がいいと思って驚いたし、一音符の書き方に恐ろしくなった。(山根銀二「清瀬保二論----対談による」音楽芸術一九五〇年六月号)
(そのとき武満が持参した習作の楽譜を清瀬は丁寧に見て、とてもいいといって褒め、『君はもしかしたらこういう人の曲が好きかもしれませんね』と言って、積んである楽譜の中からある曲を選んでピアノで弾いてくれた。それはモンポウとセヴラックの曲だった。)
モンポウはスペインの現代の作曲家で、ドビュッシーの流れを汲む人です。ぼくの曲を聞いて、そういう好みを感じとったんでしょう。あと、きみならフォーレも好きになるにちがいないなんていってました。帰りにはモンポウやバルトークの楽譜を貸してくれて、それをかかえて、もう遅くなって電車もないので、祖師谷大蔵から、代田の家まで二時間以上もかけて線路沿いに歩いて帰りました。歩きながら『ああ、いい先生だな』と思いました。
いま僕のところに来る若い生徒がいるが、新作曲家の第二回作品発表会に来て、僕のヴァイオリン・ソナタを聴いて、その晩非常に興奮した。そこで自分は作曲に自信をもてないでやめようとで思ったが、あれを聴いてまたやりたくなったといってました。それで僕のところにやってきた。そういう話は僕も嬉しくて、面倒を見ているが、才能はありますね。第二楽章でドッペルを使った。そこで身震いしたというのだ。そんな細かいことを言われたのは初めてで、耳がいいと思って驚いたし、一音符の書き方に恐ろしくなった。(山根銀二「清瀬保二論----対談による」音楽芸術一九五〇年六月号)
(そのとき武満が持参した習作の楽譜を清瀬は丁寧に見て、とてもいいといって褒め、『君はもしかしたらこういう人の曲が好きかもしれませんね』と言って、積んである楽譜の中からある曲を選んでピアノで弾いてくれた。それはモンポウとセヴラックの曲だった。)
モンポウはスペインの現代の作曲家で、ドビュッシーの流れを汲む人です。ぼくの曲を聞いて、そういう好みを感じとったんでしょう。あと、きみならフォーレも好きになるにちがいないなんていってました。帰りにはモンポウやバルトークの楽譜を貸してくれて、それをかかえて、もう遅くなって電車もないので、祖師谷大蔵から、代田の家まで二時間以上もかけて線路沿いに歩いて帰りました。歩きながら『ああ、いい先生だな』と思いました。
清瀬保二について続けます。
こういう本を読むといいみたいな示唆はありましたが、和声学を教えてもらうとか、対位法を教えてもらうとか、そういうのは全然なかったです。作曲の仕方については、『きみの好きなようにやりなさい』といっていただけです。あとは、いろんな楽譜を見せたり貸してくれたり、『これは参考になりますよ』、とすすめてくれるとか、そういうことだったんですね。
生き方の上でとても教わることが多かったんです。清瀬さんという人は全く妥協しない人だった。芸術家として非常に純粋な生き方をした人です。いま思うと、音楽家としても偉い人だったと思うけれども、その当時は、正当に評価されず、日本の音楽家の中では傍系の作家と見られていた。ですから生活の上でも貧乏だったけれども、どんなことがあっても自分の音楽を曲げないというか、理想主義者だったと思います。
あのくらいの先生になると、年齢的にもいろんな誘いがあるんですよ。何とかの会長になってほしいとか、どこかの教職のいいポジションを提供されるとか。そういうものには、全く見向きもしなかった。常に一人の作家としてありたいということで。白樺派とかそういうものに代表される日本のあの時期の理想主義があるでしょう。あれを体現している人なんです。またそういうものを人にすすめるんですね。『ロダンの言葉』とか、岸田劉生の『美の本体』とか、そういうものを読めとすすめられました。音楽のことより、そういう話が多かったですね。
(しかし、武満は清瀬と4年後に袂を分かつ)
新作曲派は民族主義的音楽ということを標榜していて、すぐ『我々民族は・・・』みたいなことをいうんですね。ぼくは、日本の音楽、雅楽であるとか、尺八の音とかそういうものには関心を持っていたんですが、『民族主義』というものにはどうしてもなじめなかった。それと音楽的には、清瀬さんにしても、ペンタトニックを生で使ったりするんですね。それがどうしてもなじめなかった。
それであるとき、これは思い出すと恥ずかしいことなんですけど、清瀬さんのピアノ曲集の楽譜を、『僕だったらこうします』といって、赤インクで全部書きかえて持っていったことがあるんです。いま考えたら、ずいぶん無茶苦茶な恐ろしいことをしたもんだと思います。清瀬さんもさすがに激怒して、『きみっ、何てことをするんだ』と怒鳴りつけられました。結局、音楽的にはどうしても同じ方向に行けなかったですね。このままやっていたら清瀬さんと同じになってしまうと思って離れたわけです。
(それから十年以上あとに、武満は次のように語っている)
清瀬先生にはいろいろ作品を見ていただいたんですけれども、ぼくはたしかに不肖の弟子だし、先生もたぶんそう思っていらっしゃるだろう。しかし、ぼくはやっぱり清瀬さんから、一番影響されていますね。ぼくは清瀬さんのことを考えると、幸福な気持ちでいっぱいです。ほんとに。(音楽芸術一九六四年十月号 富樫康との対談)
こういう本を読むといいみたいな示唆はありましたが、和声学を教えてもらうとか、対位法を教えてもらうとか、そういうのは全然なかったです。作曲の仕方については、『きみの好きなようにやりなさい』といっていただけです。あとは、いろんな楽譜を見せたり貸してくれたり、『これは参考になりますよ』、とすすめてくれるとか、そういうことだったんですね。
生き方の上でとても教わることが多かったんです。清瀬さんという人は全く妥協しない人だった。芸術家として非常に純粋な生き方をした人です。いま思うと、音楽家としても偉い人だったと思うけれども、その当時は、正当に評価されず、日本の音楽家の中では傍系の作家と見られていた。ですから生活の上でも貧乏だったけれども、どんなことがあっても自分の音楽を曲げないというか、理想主義者だったと思います。
あのくらいの先生になると、年齢的にもいろんな誘いがあるんですよ。何とかの会長になってほしいとか、どこかの教職のいいポジションを提供されるとか。そういうものには、全く見向きもしなかった。常に一人の作家としてありたいということで。白樺派とかそういうものに代表される日本のあの時期の理想主義があるでしょう。あれを体現している人なんです。またそういうものを人にすすめるんですね。『ロダンの言葉』とか、岸田劉生の『美の本体』とか、そういうものを読めとすすめられました。音楽のことより、そういう話が多かったですね。
(しかし、武満は清瀬と4年後に袂を分かつ)
新作曲派は民族主義的音楽ということを標榜していて、すぐ『我々民族は・・・』みたいなことをいうんですね。ぼくは、日本の音楽、雅楽であるとか、尺八の音とかそういうものには関心を持っていたんですが、『民族主義』というものにはどうしてもなじめなかった。それと音楽的には、清瀬さんにしても、ペンタトニックを生で使ったりするんですね。それがどうしてもなじめなかった。
それであるとき、これは思い出すと恥ずかしいことなんですけど、清瀬さんのピアノ曲集の楽譜を、『僕だったらこうします』といって、赤インクで全部書きかえて持っていったことがあるんです。いま考えたら、ずいぶん無茶苦茶な恐ろしいことをしたもんだと思います。清瀬さんもさすがに激怒して、『きみっ、何てことをするんだ』と怒鳴りつけられました。結局、音楽的にはどうしても同じ方向に行けなかったですね。このままやっていたら清瀬さんと同じになってしまうと思って離れたわけです。
(それから十年以上あとに、武満は次のように語っている)
清瀬先生にはいろいろ作品を見ていただいたんですけれども、ぼくはたしかに不肖の弟子だし、先生もたぶんそう思っていらっしゃるだろう。しかし、ぼくはやっぱり清瀬さんから、一番影響されていますね。ぼくは清瀬さんのことを考えると、幸福な気持ちでいっぱいです。ほんとに。(音楽芸術一九六四年十月号 富樫康との対談)
清瀬保二とともに、武満が師と仰いだのは早坂文雄である。一般には黒澤明の傑作群の映画音楽を手掛けたことで著名であるが、当時、最も活動的に音楽作品を発表していた作曲家であり、清瀬と同じ新作曲家協会のメンバーだった。清瀬と早坂には濃密な交際があり、武満はその後まもなく、早坂の曲が演奏されたコンサートのあと、清瀬から早坂を紹介された。
たしかビアノコンツェルトをやったコンサートが終わってからだったと思います。清瀬さんが紹介してくれて、早坂さんが、『幾つですか』ときくので、『十七歳です』と答えると、『若いんだなあ。若いんだなあ』といわれたのを覚えています。
(ピアノコンツェルトは)実にいいものでしたよ。とてもロマンチックな曲で、ことに第一楽章の第一主題なんか、とても魅力的な旋律で、ぼくは今でも口ずさむことができるくらいです。ぼくは、早坂さんの映画音楽はもちろん高く評価しますけど、純粋音楽作品のほうも、ずっと評価してるんです。
ぼくは子供のときから映画狂いでしたからね。しょっちゅう映画を見ていたんです。そもそも母親が映画狂いなんで、その血を受けついだのかもしれない。年に二、三百本見るんです。昔から、それくらい映画を見ているわけですから、早坂文雄の名前は当然知っていました。
でも、ぼくは映画音楽をやりたくて、早坂さんのところに弟子入りしたというわけじゃないんです。そういうお弟子さんとしては、佐藤勝がいました。ぼくよりちょっと後に早坂さんのところに出入りするようになります。それから、純粋音楽のほうのお弟子さんとしては、ぼくの少し前から、佐藤慶次郎がいました。ぼくは一応、清瀬さんのお弟子さんという形だけど、しょっちゅう早坂さんのところに出入りするという形だったわけです。
(佐藤勝は、一九五一年に早坂に弟子入りし、「生きる」から本格的に手伝うようになる。以下は佐藤勝の話)
行ってすぐ武満君に紹介されたんですが、早坂さんが、『作曲家の武満君』といって紹介するんですよ。ぼくと同じくらいの年でもう作曲家と呼ばれてるなんてすごいなと思いましたよ。顔も当時からああいう神秘的な顔で、頭がでかくて脳味噌がいっぱい詰まっている感じで、何かぼくらとはレベルがちがう人間という感じでした。そういう時って、武者修行中の武芸者がすれちがったときみたいに、お互いに視線をパッパッと走らせて、相手の力量を測るわけですが、彼はなんだかすごい気迫がありました。その気迫だけで、彼の作った曲はまだ全然聞いてなかったんですが、この男はもしかしたら天才じゃないかと思いましたよ。
それから間もなく、読売ホールで新作曲家協会の発表会があり、彼の『妖精の距離』というヴァイオリンの曲が演奏されるというんで行ってみたんです。そうすると岡本太郎さんがきててね、休憩時間中に取りまき連中にかこまれてにぎやかにおしゃべりしてるんですね。何を話してるんだろうと思って近くで聞いてみると、武満君の曲がどうだこうだとやってるんです。へえー、こういう人とも知りあいなのか、やっぱのすげえ奴なんだとびっくりしました。だけどいっしょに仕事するようになって、雑談を交わすようになると、大谷友衛門の佐々木小次郎がどうのこうのと、その頃評判のチャンバラ映画の話を熱心にするのを聞いて、ああ、この人も普通の人なんだと思って安心したことを覚えています。
写真は清瀬保二 もう一枚は早坂文雄と佐藤勝(右)
たしかビアノコンツェルトをやったコンサートが終わってからだったと思います。清瀬さんが紹介してくれて、早坂さんが、『幾つですか』ときくので、『十七歳です』と答えると、『若いんだなあ。若いんだなあ』といわれたのを覚えています。
(ピアノコンツェルトは)実にいいものでしたよ。とてもロマンチックな曲で、ことに第一楽章の第一主題なんか、とても魅力的な旋律で、ぼくは今でも口ずさむことができるくらいです。ぼくは、早坂さんの映画音楽はもちろん高く評価しますけど、純粋音楽作品のほうも、ずっと評価してるんです。
ぼくは子供のときから映画狂いでしたからね。しょっちゅう映画を見ていたんです。そもそも母親が映画狂いなんで、その血を受けついだのかもしれない。年に二、三百本見るんです。昔から、それくらい映画を見ているわけですから、早坂文雄の名前は当然知っていました。
でも、ぼくは映画音楽をやりたくて、早坂さんのところに弟子入りしたというわけじゃないんです。そういうお弟子さんとしては、佐藤勝がいました。ぼくよりちょっと後に早坂さんのところに出入りするようになります。それから、純粋音楽のほうのお弟子さんとしては、ぼくの少し前から、佐藤慶次郎がいました。ぼくは一応、清瀬さんのお弟子さんという形だけど、しょっちゅう早坂さんのところに出入りするという形だったわけです。
(佐藤勝は、一九五一年に早坂に弟子入りし、「生きる」から本格的に手伝うようになる。以下は佐藤勝の話)
行ってすぐ武満君に紹介されたんですが、早坂さんが、『作曲家の武満君』といって紹介するんですよ。ぼくと同じくらいの年でもう作曲家と呼ばれてるなんてすごいなと思いましたよ。顔も当時からああいう神秘的な顔で、頭がでかくて脳味噌がいっぱい詰まっている感じで、何かぼくらとはレベルがちがう人間という感じでした。そういう時って、武者修行中の武芸者がすれちがったときみたいに、お互いに視線をパッパッと走らせて、相手の力量を測るわけですが、彼はなんだかすごい気迫がありました。その気迫だけで、彼の作った曲はまだ全然聞いてなかったんですが、この男はもしかしたら天才じゃないかと思いましたよ。
それから間もなく、読売ホールで新作曲家協会の発表会があり、彼の『妖精の距離』というヴァイオリンの曲が演奏されるというんで行ってみたんです。そうすると岡本太郎さんがきててね、休憩時間中に取りまき連中にかこまれてにぎやかにおしゃべりしてるんですね。何を話してるんだろうと思って近くで聞いてみると、武満君の曲がどうだこうだとやってるんです。へえー、こういう人とも知りあいなのか、やっぱのすげえ奴なんだとびっくりしました。だけどいっしょに仕事するようになって、雑談を交わすようになると、大谷友衛門の佐々木小次郎がどうのこうのと、その頃評判のチャンバラ映画の話を熱心にするのを聞いて、ああ、この人も普通の人なんだと思って安心したことを覚えています。
写真は清瀬保二 もう一枚は早坂文雄と佐藤勝(右)
早坂文雄との交際は師弟というよりも、ずっと親しいものになっていった。
早坂さんはそれから間もなく、清瀬さんの家のすぐ近くに引っ越してくるんです。清瀬さんの家のすぐ隣が東宝の撮影所でしたから、仕事に便利だったんでしょう。あの二人はもともと親しかった上に、家がそんなに近くなったんで、しょっちゅう行き来してたんです。それでぼくも清瀬さんのところに行けば早坂さんのところに一緒に行くようになり、そのうち、早坂さんのところにも自由に出入りするようになったんです。
早坂さんはいつもいろんな意見を言ってくれました。『二つのレント』にしても、早坂さんに見てもらったら、『これはいい。これはぼくらのところで発表してあげよう』といってくれて、それで正式に新作曲派協会のメンバーになるわけです。
早坂さんは、『ここ、きみはどう思う』なんて聞いたりするんです。それで、『このほうがいいと思う』なんていうと、早坂さんは平気でそれが気に入ると取り入れちゃう人なんですね。それだけでなく、早坂さんとは何でもしゃべりあう仲になっていました。清瀬さんはぼくの三十歳も年上ですから、文字通り"先生 "という感じでしたけど、早坂さんはまだ三十代半ばで、"兄貴 "という感じだったですね。気さくでやさしい人ですから、ぼくらとはいつも対等な感じで付きあってくれました。
ぼくらはわりに欧米の最新の音楽の動きに通じていたんですが、早坂さんはそういうことをすごく知りたがって、たとえば、ぼくらがメシアンの話をすると、すぐ自分でもメシアンを聞いたり、楽譜を買ってきたりしましたね。早坂さんのほうからは、雅楽や能、歌舞伎など伝統音楽に詳しいからそういう話もしてくれるし、もちろん、映画音楽についても話してくれる。
それから早坂さんという人は、幅の広い人で、思想書なんかもよく読んでるし、美術、ことに東洋美術には詳しいし、骨董なんかもやっていて、ぼくらの仲間がよく話題にしていた、西欧の前衛美術なんかにも旺盛な関心を示していました。だから会うと話がつきなくて、いつも夜遅くなりました。
(「ぼくら」というのは、実験工房グループのことである。早坂のところには、この実験工房の鈴木博義、福島和夫、秋山邦晴、湯浅譲二なども出入りするようになり、早坂の弟子であった佐藤慶次郎は、同グループのメンバーになってしまう)
武満の話を続ける
早坂さんは、孤独な人だったんです。早坂さんは、映画音楽の仕事を誇りをもってやってましたが、芸術音楽の世界の人は、どうしてもそういうものを一段低いものと見なして、秘かにさげすむみたいな風潮があったんですね。芸術音楽をやっている人たちはみんな貧乏でしたけど、映画音楽なんかやるとすごくお金が入るので、そういうやっかみもあったのでしょう。早坂さんはそんなの気にしないといってたけど、やっぱり心の奥ではかなり気にしていたんじゃないかと思うんですね。体にものすごい無理をしてまでも、純粋音楽作品を次々に発表しつづけたのは、やはり、自分は映画音楽だけじゃなくて、そっちのほうでもいい仕事をやってるんだぞということを示したいという気持ちがあったんじゃないでしょうか。
そういうわけで、楽壇の人たちとの親しい付き合いはあまりなかったわけです。それで、ぼくらみたいな純粋音楽やってる若い連中との付き合いが楽しかったんじゃないでしょうか。ぼくらが早坂さんの家を訪ねて帰ろうとすると、必ず、『まだ、いいじゃないか。メシでも食ってけよ』と遅くまで引きとめようとしました。早坂さんは当時、格段の作曲料を貰っていて、裕福な暮らしをしていました。食事はいつもご馳走でしたから、ぼくらは喜んでよばれてしまって、奥さんにいやな顔をされたものです。
早坂さんはそれから間もなく、清瀬さんの家のすぐ近くに引っ越してくるんです。清瀬さんの家のすぐ隣が東宝の撮影所でしたから、仕事に便利だったんでしょう。あの二人はもともと親しかった上に、家がそんなに近くなったんで、しょっちゅう行き来してたんです。それでぼくも清瀬さんのところに行けば早坂さんのところに一緒に行くようになり、そのうち、早坂さんのところにも自由に出入りするようになったんです。
早坂さんはいつもいろんな意見を言ってくれました。『二つのレント』にしても、早坂さんに見てもらったら、『これはいい。これはぼくらのところで発表してあげよう』といってくれて、それで正式に新作曲派協会のメンバーになるわけです。
早坂さんは、『ここ、きみはどう思う』なんて聞いたりするんです。それで、『このほうがいいと思う』なんていうと、早坂さんは平気でそれが気に入ると取り入れちゃう人なんですね。それだけでなく、早坂さんとは何でもしゃべりあう仲になっていました。清瀬さんはぼくの三十歳も年上ですから、文字通り"先生 "という感じでしたけど、早坂さんはまだ三十代半ばで、"兄貴 "という感じだったですね。気さくでやさしい人ですから、ぼくらとはいつも対等な感じで付きあってくれました。
ぼくらはわりに欧米の最新の音楽の動きに通じていたんですが、早坂さんはそういうことをすごく知りたがって、たとえば、ぼくらがメシアンの話をすると、すぐ自分でもメシアンを聞いたり、楽譜を買ってきたりしましたね。早坂さんのほうからは、雅楽や能、歌舞伎など伝統音楽に詳しいからそういう話もしてくれるし、もちろん、映画音楽についても話してくれる。
それから早坂さんという人は、幅の広い人で、思想書なんかもよく読んでるし、美術、ことに東洋美術には詳しいし、骨董なんかもやっていて、ぼくらの仲間がよく話題にしていた、西欧の前衛美術なんかにも旺盛な関心を示していました。だから会うと話がつきなくて、いつも夜遅くなりました。
(「ぼくら」というのは、実験工房グループのことである。早坂のところには、この実験工房の鈴木博義、福島和夫、秋山邦晴、湯浅譲二なども出入りするようになり、早坂の弟子であった佐藤慶次郎は、同グループのメンバーになってしまう)
武満の話を続ける
早坂さんは、孤独な人だったんです。早坂さんは、映画音楽の仕事を誇りをもってやってましたが、芸術音楽の世界の人は、どうしてもそういうものを一段低いものと見なして、秘かにさげすむみたいな風潮があったんですね。芸術音楽をやっている人たちはみんな貧乏でしたけど、映画音楽なんかやるとすごくお金が入るので、そういうやっかみもあったのでしょう。早坂さんはそんなの気にしないといってたけど、やっぱり心の奥ではかなり気にしていたんじゃないかと思うんですね。体にものすごい無理をしてまでも、純粋音楽作品を次々に発表しつづけたのは、やはり、自分は映画音楽だけじゃなくて、そっちのほうでもいい仕事をやってるんだぞということを示したいという気持ちがあったんじゃないでしょうか。
そういうわけで、楽壇の人たちとの親しい付き合いはあまりなかったわけです。それで、ぼくらみたいな純粋音楽やってる若い連中との付き合いが楽しかったんじゃないでしょうか。ぼくらが早坂さんの家を訪ねて帰ろうとすると、必ず、『まだ、いいじゃないか。メシでも食ってけよ』と遅くまで引きとめようとしました。早坂さんは当時、格段の作曲料を貰っていて、裕福な暮らしをしていました。食事はいつもご馳走でしたから、ぼくらは喜んでよばれてしまって、奥さんにいやな顔をされたものです。
次第に武満は早坂の映画音楽の仕事を手伝うようになる。
早坂さんが二段か三段の旋律を書くと、その下にぼくらがいろんな楽器を使って、オーケストレーションを付けていくわけです。どういう楽器をどう使うかといったラフな方針は早坂さんのほうから出ましたが、あとはぼくらにまかされました。ときどき早坂さんの指図に対して、『こうしてやったほうがいいと思う』なんていって勝手なことをやると、『いや、そんなことをすると、この楽器の音が聞えなくなってしまうから駄目だよ。でも、それがいいと思ったら、そうしておいてごらん。まずかったら、また現場で直せばいいんだから』なんていわれて、実際に、現場でオーケストラに音を出させてみると、早坂さんのいった通りで、現場で手直しするということが何度もありました。
そういうことを通して、早坂さんは、ぼくに、オーケストラの勉強をさせてくれたんですね。これは本当に貴重な経験でした。楽譜をオーケストラで音にするなんていう経験をもつことは、こういうこと以外では、全く不可能でした。ぼくはオーケストレーションの基礎をあれで勉強させてもらったと思っています。もちろん、それでお金が稼げるということも有り難いことでしたが、オーケストラの勉強ができたというのが何より有り難かったですね。
早坂さんのところに出入りしている間に、かれこれ二十本くらいは手伝いをしていると思いますね。その大部分、音入れの現場にも行っています。東宝だけじゃなくて、新東宝、松竹、東映、大映、みんな行ってますね。現場で手直しが必要なんてことになると、ぼくらがその場でパート譜をさっと書いて、楽団員に配ったりするわけです。
あんまり有名じゃない作品が多いですが、有名なところでは、『七人の侍』をやってます。あのときは、ぼくと、佐藤慶次郎、佐藤勝の三人で、早坂さんの十二畳の仕事場に、経机みたいのを三つならべて、スコアを書きまくりました。ぼくがやったシーンで有名なところというと、たとえば、勝四郎という木村功が扮する若侍と、志乃という津島恵子が扮する村娘のシーン、あそこなんかぼくがやってますね。
早坂さんはもうそのころから相当体が悪くて、お宅に行くとよく寝ていることがありました。生命を削って仕事をしているという感じでしたね。それだけ一生懸命仕事をしても、監督と意見が合わないとなると、せっかく書いたものを捨てられてしまうことがあるんですね。黒澤さんの場合、音楽の好き嫌いが激しいから、相当激しい衝突があるんです。『野良犬』のときも、バサッとボツにされて、ものすごく腹を立てて、『もう、あいつとは絶対一緒に仕事しないぞ』といって、昼間から雨戸を閉めて寝ちゃったこともありました。
病気がどんどんひどくなるのに、、映画の仕事を次々受ける一方、『ユーカラ』なんていう大作に取り組むわけです。あれは一時間もかかる大曲ですから、膨大なスコアの量で、書くだけでも大変なんです。そんなことやってたら死んじゃうからやめなさいって、ぼくなんか何度も忠告したんですがね。命を縮めると知りながらやめなかった。
『ユーカラ』を聞いて、ぼくは早坂さんの死を予感しました。早坂さんは死ぬ気だなと思いました。音楽の内容が死を予感させたということじゃなくて、自分の体がもう体力の限界まできていて、これを書いたら死ぬといことをう自分でも知っていて書いたということです。ぼくもそのころ結核が重くなって、病院に入院したり、家でも寝ていたりで、自分の死についてよく考えていましたから、感情の起伏が激しくなっていたかもしれません。日比谷公会堂で初演された『ユーカラ』を聞いて、思わず声を出して泣いてしまったんです。
早坂さんが二段か三段の旋律を書くと、その下にぼくらがいろんな楽器を使って、オーケストレーションを付けていくわけです。どういう楽器をどう使うかといったラフな方針は早坂さんのほうから出ましたが、あとはぼくらにまかされました。ときどき早坂さんの指図に対して、『こうしてやったほうがいいと思う』なんていって勝手なことをやると、『いや、そんなことをすると、この楽器の音が聞えなくなってしまうから駄目だよ。でも、それがいいと思ったら、そうしておいてごらん。まずかったら、また現場で直せばいいんだから』なんていわれて、実際に、現場でオーケストラに音を出させてみると、早坂さんのいった通りで、現場で手直しするということが何度もありました。
そういうことを通して、早坂さんは、ぼくに、オーケストラの勉強をさせてくれたんですね。これは本当に貴重な経験でした。楽譜をオーケストラで音にするなんていう経験をもつことは、こういうこと以外では、全く不可能でした。ぼくはオーケストレーションの基礎をあれで勉強させてもらったと思っています。もちろん、それでお金が稼げるということも有り難いことでしたが、オーケストラの勉強ができたというのが何より有り難かったですね。
早坂さんのところに出入りしている間に、かれこれ二十本くらいは手伝いをしていると思いますね。その大部分、音入れの現場にも行っています。東宝だけじゃなくて、新東宝、松竹、東映、大映、みんな行ってますね。現場で手直しが必要なんてことになると、ぼくらがその場でパート譜をさっと書いて、楽団員に配ったりするわけです。
あんまり有名じゃない作品が多いですが、有名なところでは、『七人の侍』をやってます。あのときは、ぼくと、佐藤慶次郎、佐藤勝の三人で、早坂さんの十二畳の仕事場に、経机みたいのを三つならべて、スコアを書きまくりました。ぼくがやったシーンで有名なところというと、たとえば、勝四郎という木村功が扮する若侍と、志乃という津島恵子が扮する村娘のシーン、あそこなんかぼくがやってますね。
早坂さんはもうそのころから相当体が悪くて、お宅に行くとよく寝ていることがありました。生命を削って仕事をしているという感じでしたね。それだけ一生懸命仕事をしても、監督と意見が合わないとなると、せっかく書いたものを捨てられてしまうことがあるんですね。黒澤さんの場合、音楽の好き嫌いが激しいから、相当激しい衝突があるんです。『野良犬』のときも、バサッとボツにされて、ものすごく腹を立てて、『もう、あいつとは絶対一緒に仕事しないぞ』といって、昼間から雨戸を閉めて寝ちゃったこともありました。
病気がどんどんひどくなるのに、、映画の仕事を次々受ける一方、『ユーカラ』なんていう大作に取り組むわけです。あれは一時間もかかる大曲ですから、膨大なスコアの量で、書くだけでも大変なんです。そんなことやってたら死んじゃうからやめなさいって、ぼくなんか何度も忠告したんですがね。命を縮めると知りながらやめなかった。
『ユーカラ』を聞いて、ぼくは早坂さんの死を予感しました。早坂さんは死ぬ気だなと思いました。音楽の内容が死を予感させたということじゃなくて、自分の体がもう体力の限界まできていて、これを書いたら死ぬといことをう自分でも知っていて書いたということです。ぼくもそのころ結核が重くなって、病院に入院したり、家でも寝ていたりで、自分の死についてよく考えていましたから、感情の起伏が激しくなっていたかもしれません。日比谷公会堂で初演された『ユーカラ』を聞いて、思わず声を出して泣いてしまったんです。
武満がはじめて自分の名前で引き受けた映画音楽は1956年の『狂った果実』だった。もともとは佐藤勝が受けた作品だったが、それが武満のところに回ってきたのだ。太陽族映画第一弾の石原慎太郎原作「太陽の季節」が大ヒットしたので、2匹目のドジョウを狙って大慌てで作られることになった作品だった。
あのころは、何しろ1週間に何本という割合でどんどん映画が作られていた時代で、映画音楽作曲家は数が少ないので、みんなかけ持ちで大変だったんです。佐藤さんも何かとぶつかってできなくなって(佐藤勝は黒澤明の「蜘蛛巣城」の仕事がはじまり、かけ持ちでやるのが困難になった)、ぼくのところに頼んできたわけです。
そのころぼくは鎌倉に住んでいて、『狂った果実』は、逗子とか葉山あたりでロケーションしていました。面白そうだし、撮影も見に行きやすいし、お金にもなる、ということで引き受けました。引き継ぎで佐藤さんと日活撮影所に行って中平監督や裕次郎にも会いました。見ると、裕次郎があの長い脚で歩きながら、ビールかなんか飲んで歌ってる。それがすごくうまいんですよ。それで佐藤さんに『あいつに歌わせたらいいんじゃないか』といったら、中平さんも、『それはいいや。そういうシーンもあるし、歌わせようか』ということになって、それで裕次郎は歌ったわけですよ。
ぼくはそういう歌が書けないので、他の音楽は全部やったんですけど、その歌だけは佐藤さんに書いてもらったんです。やっぱり、自分は純粋音楽の作曲家だというような意地があって、そういう流行歌みたいなのは書かないんだ、みたいなところがあったんですよね。だけど、中の音楽も評判は良くて、たまたまラジオを聞いてたら、江利チエミが、『最近、すごいすてきな音楽を聞いたわ。狂った果実という映画なの。あの映画音楽はいいわ』というのを聞いて、すごく嬉しくなったのを覚えています。後で知ったことですが、トリュフォーやフランスのヌーベル・ヴァーグの連中がみんなあの音楽をほめてくれていたんだそうです。
あのころは、何しろ1週間に何本という割合でどんどん映画が作られていた時代で、映画音楽作曲家は数が少ないので、みんなかけ持ちで大変だったんです。佐藤さんも何かとぶつかってできなくなって(佐藤勝は黒澤明の「蜘蛛巣城」の仕事がはじまり、かけ持ちでやるのが困難になった)、ぼくのところに頼んできたわけです。
そのころぼくは鎌倉に住んでいて、『狂った果実』は、逗子とか葉山あたりでロケーションしていました。面白そうだし、撮影も見に行きやすいし、お金にもなる、ということで引き受けました。引き継ぎで佐藤さんと日活撮影所に行って中平監督や裕次郎にも会いました。見ると、裕次郎があの長い脚で歩きながら、ビールかなんか飲んで歌ってる。それがすごくうまいんですよ。それで佐藤さんに『あいつに歌わせたらいいんじゃないか』といったら、中平さんも、『それはいいや。そういうシーンもあるし、歌わせようか』ということになって、それで裕次郎は歌ったわけですよ。
ぼくはそういう歌が書けないので、他の音楽は全部やったんですけど、その歌だけは佐藤さんに書いてもらったんです。やっぱり、自分は純粋音楽の作曲家だというような意地があって、そういう流行歌みたいなのは書かないんだ、みたいなところがあったんですよね。だけど、中の音楽も評判は良くて、たまたまラジオを聞いてたら、江利チエミが、『最近、すごいすてきな音楽を聞いたわ。狂った果実という映画なの。あの映画音楽はいいわ』というのを聞いて、すごく嬉しくなったのを覚えています。後で知ったことですが、トリュフォーやフランスのヌーベル・ヴァーグの連中がみんなあの音楽をほめてくれていたんだそうです。
その後、数多くの映画音楽を担当することになる武満だが、「太陽の季節」の同年にもう一本手掛けたあと体をこわし、五年の休養を経て一九六一年に毎日映画コンクールの音楽賞を受賞した羽仁進監督の「不良少年」が映画音楽への本格的復帰となった。
最初に書いた音楽は別にあったんです。それを羽仁さんが『書き直してください。この音楽は、私の映画が意図していることとまるで違う』と言うので、それでぼくもカッとなって、『あんたみたいな自由学園出のわがままなおぼっちゃんとはもう一緒に仕事をしたくないから、やめる』といって、大ゲンカになった。そうしたら助監督が、まあまあといって間に入って、その助監督は土本典昭というなかなかの人物なんですが、その人が、『羽仁さんという人はああいう人なんだから、まあそう怒らないでください。今日は新宿のトトヤでひと晩飲んで、ゆっくり話をしましょう』といって、三人でその日は飲み明かして、最後、どっかの旅館かなんかで川の字になって寝て、いろんな話をしたわけです。
その間、羽仁さんがいろんなことをしゃべって、それを聞いているうちに、羽仁さんがいっていることも当たっていることがあるなと思うようになって、それで、もう一度だけ書き直してみようと思って、あれができたわけです。前に書いた音楽と、書き直した音楽を聞きくらべてみたら、これはもう完全に羽仁さんのほうが正しかった。書き直したほうの音楽は、ふだんの自分からは、全然出てこないような音楽なんです。羽仁さんというそれまでぼくが全く知らなかったタイプの個性とぼくがぶつかることで、ぼくから引きだされた、自分でも知らなかった一面なんですね。
こういうことがあるから映画の仕事は面白いんです。映画というのは、一人でコツコツやっていく純粋音楽の作曲とちがって、いろんな制約の下にいろんな個性がぶつかり合う共同作業ですから、そういうぶつかり合いの中で、自分でも思いがけないものが、自分の中から生まれてきたりするんです。
最初に書いた音楽は別にあったんです。それを羽仁さんが『書き直してください。この音楽は、私の映画が意図していることとまるで違う』と言うので、それでぼくもカッとなって、『あんたみたいな自由学園出のわがままなおぼっちゃんとはもう一緒に仕事をしたくないから、やめる』といって、大ゲンカになった。そうしたら助監督が、まあまあといって間に入って、その助監督は土本典昭というなかなかの人物なんですが、その人が、『羽仁さんという人はああいう人なんだから、まあそう怒らないでください。今日は新宿のトトヤでひと晩飲んで、ゆっくり話をしましょう』といって、三人でその日は飲み明かして、最後、どっかの旅館かなんかで川の字になって寝て、いろんな話をしたわけです。
その間、羽仁さんがいろんなことをしゃべって、それを聞いているうちに、羽仁さんがいっていることも当たっていることがあるなと思うようになって、それで、もう一度だけ書き直してみようと思って、あれができたわけです。前に書いた音楽と、書き直した音楽を聞きくらべてみたら、これはもう完全に羽仁さんのほうが正しかった。書き直したほうの音楽は、ふだんの自分からは、全然出てこないような音楽なんです。羽仁さんというそれまでぼくが全く知らなかったタイプの個性とぼくがぶつかることで、ぼくから引きだされた、自分でも知らなかった一面なんですね。
こういうことがあるから映画の仕事は面白いんです。映画というのは、一人でコツコツやっていく純粋音楽の作曲とちがって、いろんな制約の下にいろんな個性がぶつかり合う共同作業ですから、そういうぶつかり合いの中で、自分でも思いがけないものが、自分の中から生まれてきたりするんです。
そんな武満も、あらかじめ名曲をイメージして撮影し編集する黒澤明との作業には困った。
あの人はいつでも、映画を作る前から音楽のイメージができちゃってるんです。『乱』はマーラーの『大地の歌』や『巨人』、影武者はグリーグの『ペール・ギュント』やスッペの『軽騎兵序曲』だし、『赤ひげ』はベートーヴェンの第九やハイドンの『驚愕』だし、そのイメージをスタッフにも徹底させる。ときには撮影現場でもその音楽を聞きながら撮っている。編集もそれに合わせてやってしまう。ラッシュではマーラーをつけてみせる。音楽に合わせて編集するんですから、見事にピッタリと合っている。
ぼくがやったのは『どですかでん』と『乱』ですが、『どですかでん』はビゼーの『アルルの女』なんです。あのときも、こんなに合ってるんだから、そのまま使ったほうがいいといったんですが、『きみ、バカいっちゃいけないよ』といわれた。『ぼくはこれを超えてもらいたいんだ』って。
『羅生門』はラヴェルの『ボレロ』ですよね。だから、あの音楽がボレロそっくりだとだいぶ問題になったでしょう。だけどあれはそっくりにならざるを得ませんよ。絵がボレロのあの独特のリズムにのせて編集されているんですもの。あれは早坂さんもだいぶ苦労したと思います。そうやって出てくるのはみんな、いわゆる世界の名曲ですよね。多分、昔、黒澤さんの家に、世界の名曲アルバムみたいなのがあって、それが頭にこびりついてしまったんじゃないかな。
だいたい、ぼくと黒澤さんでは音の感じ方が本質的に違うんですよ。あの人は、ティンパニーが大好きなんです。ところがぼくはティンパニーがどうしても駄目なんです。ぼくのオーケストラ曲でティンパニー使ったのは一曲もないんです。使ったのは、黒澤さんの『乱』だけです。黒澤さんがどうしてもティンパニーを使ってもらわなきゃ困るというから、仕方がなくて使った。あれは岩城宏之が振ってくれたんですけど、彼はぼくのいろんな曲をやっているから、それでびっくりしちゃって、『武満さん、ティンパニーちゃんと使えるじゃない』なんていってた。
『乱』ではずいぶん激しいケンカをしました。ぼくは なんでも平気でズバズバいうほうだけど、黒澤さんは気が弱いほうだから、面と向かってはあんまりいえないんですね。それで、朝、ホテルの部屋のドアの下から、ズズズッと紙が入ってくるの。それに、『ぼくはきみの音楽が大きらいです。黒澤明』なんて書いてあるわけ。ぼくはずいぶん持ってますよ、そういう手紙を。
ぼくは話したほうが早いと思うから、食事のときに、『じゃあ、ちゃんと話し合う時間を作ってください』というと、『うん、いや、きみの音楽、悪くはないんだけど・・・』とか何とかいうだけなので、じゃあいいのか、と思っていると、次の朝またドアの下から紙が入ってくるわけ。そういうことが何回もつづく。しつこいんですよ。それでぼくも怒って、『もう、やめた』といって家に帰ってしまうと、プロデューサーと助監督が迎えにくる。
あの人はいつでも、映画を作る前から音楽のイメージができちゃってるんです。『乱』はマーラーの『大地の歌』や『巨人』、影武者はグリーグの『ペール・ギュント』やスッペの『軽騎兵序曲』だし、『赤ひげ』はベートーヴェンの第九やハイドンの『驚愕』だし、そのイメージをスタッフにも徹底させる。ときには撮影現場でもその音楽を聞きながら撮っている。編集もそれに合わせてやってしまう。ラッシュではマーラーをつけてみせる。音楽に合わせて編集するんですから、見事にピッタリと合っている。
ぼくがやったのは『どですかでん』と『乱』ですが、『どですかでん』はビゼーの『アルルの女』なんです。あのときも、こんなに合ってるんだから、そのまま使ったほうがいいといったんですが、『きみ、バカいっちゃいけないよ』といわれた。『ぼくはこれを超えてもらいたいんだ』って。
『羅生門』はラヴェルの『ボレロ』ですよね。だから、あの音楽がボレロそっくりだとだいぶ問題になったでしょう。だけどあれはそっくりにならざるを得ませんよ。絵がボレロのあの独特のリズムにのせて編集されているんですもの。あれは早坂さんもだいぶ苦労したと思います。そうやって出てくるのはみんな、いわゆる世界の名曲ですよね。多分、昔、黒澤さんの家に、世界の名曲アルバムみたいなのがあって、それが頭にこびりついてしまったんじゃないかな。
だいたい、ぼくと黒澤さんでは音の感じ方が本質的に違うんですよ。あの人は、ティンパニーが大好きなんです。ところがぼくはティンパニーがどうしても駄目なんです。ぼくのオーケストラ曲でティンパニー使ったのは一曲もないんです。使ったのは、黒澤さんの『乱』だけです。黒澤さんがどうしてもティンパニーを使ってもらわなきゃ困るというから、仕方がなくて使った。あれは岩城宏之が振ってくれたんですけど、彼はぼくのいろんな曲をやっているから、それでびっくりしちゃって、『武満さん、ティンパニーちゃんと使えるじゃない』なんていってた。
『乱』ではずいぶん激しいケンカをしました。ぼくは なんでも平気でズバズバいうほうだけど、黒澤さんは気が弱いほうだから、面と向かってはあんまりいえないんですね。それで、朝、ホテルの部屋のドアの下から、ズズズッと紙が入ってくるの。それに、『ぼくはきみの音楽が大きらいです。黒澤明』なんて書いてあるわけ。ぼくはずいぶん持ってますよ、そういう手紙を。
ぼくは話したほうが早いと思うから、食事のときに、『じゃあ、ちゃんと話し合う時間を作ってください』というと、『うん、いや、きみの音楽、悪くはないんだけど・・・』とか何とかいうだけなので、じゃあいいのか、と思っていると、次の朝またドアの下から紙が入ってくるわけ。そういうことが何回もつづく。しつこいんですよ。それでぼくも怒って、『もう、やめた』といって家に帰ってしまうと、プロデューサーと助監督が迎えにくる。
武満に大きな影響を与えた作曲家にオリヴィエ・メシアンがいるが、メシアンとの出会いには、当時まだ少年の一柳慧との出会いがあった。一九四九年、武満が一九歳、一柳が一六歳のときだった。
ぼくが下宿していた家の前の通りを、ぼくよりも若いくらいの男の子が、チェロをかかえたお父さんらしい人とよく歩いていくのを見かけたんです。ある日、その男の子がひとりでいるところに、『きみ、音楽やってるの』みたいな感じで声をかけてみたら、それが一柳慧だったわけです。一柳のお父さんはチェリストで、お母さんはピアニストだったんですが、当時は生活のために、お父さんが進駐軍のキャンプでチェロを弾き、息子がそのピアノ伴奏をやっていたわけです。
家が近くだったので、『一度遊びに来ませんか』の誘いにのっていってみたら、素晴らしいグランドピアノがあって、彼がラヴェルかなんかをバァーッと弾くんです。原智恵子さん仕込みで、何しろうまい。これはとてもかなわないと思った。話を聞いてみると、彼はもう作曲をやっていて、毎日音楽コンクールで一等賞をとっている。音楽の話なんかすると、向こうは何でも知っている。音楽ではとても太刀打ちできないわけです。そしたら、一柳さんが『将棋でもやりますか』というから、やりましょうといって、それから始終将棋をやる仲になりました。
彼のお父さんはフランスで音楽教育を受けた人で、作曲をやる息子のために、フランスの音楽出版社から始終最新の楽譜を取り寄せていたんです。その中にメシアンの『プレリュード』というピアノ曲があったわけです。チラと見たら、何か面白そうなんです。一柳さんはそれにあんまり関心がないらしくて、頼むとすぐに貸してくれた。家に帰って、自分のピアノで少しずつ弾いてみると、といってもサッとは弾けませんから、少しずつ触ってみるといったほうがいいですが、素晴らしい音がするわけです。たちまち魅了されてしまいました。
(そのころメシアンのことは)ほとんど誰も知らないといっていいくらいですよ。日本ではじめてメシアンに注目したのは、ぼくら実験工房のグループなんです。五二年に実験工房の第二回発表会『現代作品演奏会』で、メシアンの『プレリュード』と『世の終わりのための四重奏曲』をやるんですが、それがメシアンの日本初演になるんです。そのとき、音楽評論家の山根銀二が会場の近くに住んでいたので、ぜひおいでくださいと誘ったら、『メシアン?そんな名前は聞いたこともない。そいつがもう少し大成したら聞きに行くよ』と断ったくらいですからね。
メシアンの官能的な音、音の響きの色彩の豊かさ、ああ、これが自分の探し求めていた音だと思いました。感覚的に自分にピッタリだったんです。それまで最初のレントをまとめるのに、ものすごく悩み、いろんな模索をつづけていたけど、何か同じようなところを堂々めぐりするばかりという感じだったんですよ。それがメシアンを聞いたとたん、自分の感性のいままで閉じられていたドアがパッと開かれたという感じだったですね。それまで長いこと一人で苦闘していた問題点をメシアンが魅惑的な音そのものを提示してくれることで、きれいに解決してくれているんですね。それに惹かれて二つ目のレントを書くわけです。一つ目のレントは延々苦労したけど、二つ目は早かったですよ。一つ目のレントを書くのにかけた時間の十分の一も使わないで書きあげてしまいました。
ぼくが下宿していた家の前の通りを、ぼくよりも若いくらいの男の子が、チェロをかかえたお父さんらしい人とよく歩いていくのを見かけたんです。ある日、その男の子がひとりでいるところに、『きみ、音楽やってるの』みたいな感じで声をかけてみたら、それが一柳慧だったわけです。一柳のお父さんはチェリストで、お母さんはピアニストだったんですが、当時は生活のために、お父さんが進駐軍のキャンプでチェロを弾き、息子がそのピアノ伴奏をやっていたわけです。
家が近くだったので、『一度遊びに来ませんか』の誘いにのっていってみたら、素晴らしいグランドピアノがあって、彼がラヴェルかなんかをバァーッと弾くんです。原智恵子さん仕込みで、何しろうまい。これはとてもかなわないと思った。話を聞いてみると、彼はもう作曲をやっていて、毎日音楽コンクールで一等賞をとっている。音楽の話なんかすると、向こうは何でも知っている。音楽ではとても太刀打ちできないわけです。そしたら、一柳さんが『将棋でもやりますか』というから、やりましょうといって、それから始終将棋をやる仲になりました。
彼のお父さんはフランスで音楽教育を受けた人で、作曲をやる息子のために、フランスの音楽出版社から始終最新の楽譜を取り寄せていたんです。その中にメシアンの『プレリュード』というピアノ曲があったわけです。チラと見たら、何か面白そうなんです。一柳さんはそれにあんまり関心がないらしくて、頼むとすぐに貸してくれた。家に帰って、自分のピアノで少しずつ弾いてみると、といってもサッとは弾けませんから、少しずつ触ってみるといったほうがいいですが、素晴らしい音がするわけです。たちまち魅了されてしまいました。
(そのころメシアンのことは)ほとんど誰も知らないといっていいくらいですよ。日本ではじめてメシアンに注目したのは、ぼくら実験工房のグループなんです。五二年に実験工房の第二回発表会『現代作品演奏会』で、メシアンの『プレリュード』と『世の終わりのための四重奏曲』をやるんですが、それがメシアンの日本初演になるんです。そのとき、音楽評論家の山根銀二が会場の近くに住んでいたので、ぜひおいでくださいと誘ったら、『メシアン?そんな名前は聞いたこともない。そいつがもう少し大成したら聞きに行くよ』と断ったくらいですからね。
メシアンの官能的な音、音の響きの色彩の豊かさ、ああ、これが自分の探し求めていた音だと思いました。感覚的に自分にピッタリだったんです。それまで最初のレントをまとめるのに、ものすごく悩み、いろんな模索をつづけていたけど、何か同じようなところを堂々めぐりするばかりという感じだったんですよ。それがメシアンを聞いたとたん、自分の感性のいままで閉じられていたドアがパッと開かれたという感じだったですね。それまで長いこと一人で苦闘していた問題点をメシアンが魅惑的な音そのものを提示してくれることで、きれいに解決してくれているんですね。それに惹かれて二つ目のレントを書くわけです。一つ目のレントは延々苦労したけど、二つ目は早かったですよ。一つ目のレントを書くのにかけた時間の十分の一も使わないで書きあげてしまいました。
こうして書きあげた「二つのレント」が早坂に認められて、新作曲家協会の第七回発表会で演奏されたことは前に書いたとおり。この演奏会で武満は特別に親しくなる二人の友人を得る。
(自分の作品がはじめて演奏されることは)なんだか恐いというか、不安な気持ちもありましたね。演奏会の聴衆はほぼ満員だったという記憶ですが、聴衆の反応は全然覚えていないです。覚えているのは、終わってから楽屋に秋山邦晴と湯浅譲二がたずねてきて、『とてもよかった。感動した』といってくれたことです。秋山はレインコートを着て、湯浅は慶応の帽子をかぶっていたな。
(秋山は当時早稲田の学生、湯浅は慶応の学生だったが、二人は何をそんなに感激したのか)
秋山邦晴
そういっちゃ何だけど、他の人たちはみんなお年寄りで、まあ、こんなもんだろうという程度のものなんですよね。その中にあって、まだ十九か二十歳の武満の曲はものすごく斬新に聞えましたね。特に二曲目のレントは、はじめて聞くような新鮮な響きでした。湯浅と隣り同士で聞いていて、これはすごいじゃないかといって、終わってすぐ楽屋に飛んでいったんです。
湯浅譲二
音楽の表現そのものが、そのころ日本で芸大系統の人が『作曲というのはこうやるものだ』みたいな感じでヨーロッパを模倣してやっているのと全然ちがったわけです。それで、この人は何かきっと深く考えて作っているにちがいないと思って、その人に会いたくなったんですね。
(この二人の絶賛に比べ、評論家による批評はさんざんなものだった)
翌日の東京新聞で、山根銀二が、いろんな人の作品についてあれこれ書いたあと、ぼくについては、最後にたった一言、『武満徹は音楽以前である』と切り捨ててるんです。そのときちょうど、その新聞を買って映画館に入ったところだったんですが、もう映画なんか全然目に入らなくて、それは『また逢う日まで』という岡田英次と久我美子がガラス越しのキスをするという有名なシーンがある映画だったんですが、もう何を見たか全然覚えていません。
映画を見ながら、頭の中では、こんなに酷評されるほどにオレは才能がないんだろうか、作曲家になるなんて望みはきっぱり捨てたほうがいいんじゃないかなんて考えていたんです。そのあと秋山たちに会ったら、『こんな批評は名誉だと思えよ。こういう連中にこういう批判を受けることこそ、オレたちが本当の前衛なんだという証明なんだから』と励ましてくれて勇気づけられました。
(この演奏会には評論家の吉田秀和も来ていた。一六年後、、日本ビクターから「武満徹の音楽」全集という四枚組のレコードが出たときに吉田によって書かれた解説が非常に興味深いものなので次に載せる)
戦後間もないころ、第何回目かの新作曲派の作品発表会があった。そこで、私たちはすでに幾つかの曲で馴染みになっていた当時の日本を代表する作曲家の作品とならんで、はじめて武満のピアノ曲にふれたのだった。それは実に奇妙な曲だった。たしか《二つのレント》と題されていたと思うが、ややフランス印象派風の音の装いの中で、孤独狷介で人を寄せつけない厳しさをもった音楽であった。
そこには音の優しさと、孤独への指向とが、今まで、どんな音楽でも経験したことがないような具合に、とけあったり、矛盾し対立しあったりしていた。しかもその曲は、あらゆる音楽の法則に背して、レントに重なるにもう一つのレントをもっており、対立と歩みよりは、外的な構造に全くよりかからず、まるで自分を表現するのを恥じるかのように、ひたすら内部へ内部へと沈潜し、音楽は前に向かって歩むというよりも、ますます身を隠していくような出来具合をしていた。
あまり盛大ともいえぬ拍手に応えて、舞台の上に頭ばかり大きくて、痩せて小さな体を運んでゆく青年の姿を見ながら、私は 〈蟹は自分に似せて穴を掘るというが、その穴を続けて掘るとは何たる蟹だろう?〉 と誰にいうともなく呟いたことを思いだす。私は、あの時、自分が武満徹という音楽家を理解したとは言わない。残念ながら、私はそんなに俊敏な批評家ではなかったわけである。しかし、そんな私にも、これは何という奇妙な若者だろうという印象は残った。そうして私は、あの時に演奏されたほかの曲はほとんど忘れてしまったのに、あの曲のことだけは、未だに覚えているのである。
そのあと、私は、武満という青年を、音楽会で時々見かけた。私たちはお互いに口もきかず、挨拶さえかわさなかったけれども、あの舞台でみた時は頭ばかり大きく見えた若者は、近くでみると、広い額と大きな目を、その頭部にもっていることがよくわかった。私は、その眼の光をみるたびに、雄弁な沈黙 という言葉のあったことを思いだすのが常だった。
(自分の作品がはじめて演奏されることは)なんだか恐いというか、不安な気持ちもありましたね。演奏会の聴衆はほぼ満員だったという記憶ですが、聴衆の反応は全然覚えていないです。覚えているのは、終わってから楽屋に秋山邦晴と湯浅譲二がたずねてきて、『とてもよかった。感動した』といってくれたことです。秋山はレインコートを着て、湯浅は慶応の帽子をかぶっていたな。
(秋山は当時早稲田の学生、湯浅は慶応の学生だったが、二人は何をそんなに感激したのか)
秋山邦晴
そういっちゃ何だけど、他の人たちはみんなお年寄りで、まあ、こんなもんだろうという程度のものなんですよね。その中にあって、まだ十九か二十歳の武満の曲はものすごく斬新に聞えましたね。特に二曲目のレントは、はじめて聞くような新鮮な響きでした。湯浅と隣り同士で聞いていて、これはすごいじゃないかといって、終わってすぐ楽屋に飛んでいったんです。
湯浅譲二
音楽の表現そのものが、そのころ日本で芸大系統の人が『作曲というのはこうやるものだ』みたいな感じでヨーロッパを模倣してやっているのと全然ちがったわけです。それで、この人は何かきっと深く考えて作っているにちがいないと思って、その人に会いたくなったんですね。
(この二人の絶賛に比べ、評論家による批評はさんざんなものだった)
翌日の東京新聞で、山根銀二が、いろんな人の作品についてあれこれ書いたあと、ぼくについては、最後にたった一言、『武満徹は音楽以前である』と切り捨ててるんです。そのときちょうど、その新聞を買って映画館に入ったところだったんですが、もう映画なんか全然目に入らなくて、それは『また逢う日まで』という岡田英次と久我美子がガラス越しのキスをするという有名なシーンがある映画だったんですが、もう何を見たか全然覚えていません。
映画を見ながら、頭の中では、こんなに酷評されるほどにオレは才能がないんだろうか、作曲家になるなんて望みはきっぱり捨てたほうがいいんじゃないかなんて考えていたんです。そのあと秋山たちに会ったら、『こんな批評は名誉だと思えよ。こういう連中にこういう批判を受けることこそ、オレたちが本当の前衛なんだという証明なんだから』と励ましてくれて勇気づけられました。
(この演奏会には評論家の吉田秀和も来ていた。一六年後、、日本ビクターから「武満徹の音楽」全集という四枚組のレコードが出たときに吉田によって書かれた解説が非常に興味深いものなので次に載せる)
戦後間もないころ、第何回目かの新作曲派の作品発表会があった。そこで、私たちはすでに幾つかの曲で馴染みになっていた当時の日本を代表する作曲家の作品とならんで、はじめて武満のピアノ曲にふれたのだった。それは実に奇妙な曲だった。たしか《二つのレント》と題されていたと思うが、ややフランス印象派風の音の装いの中で、孤独狷介で人を寄せつけない厳しさをもった音楽であった。
そこには音の優しさと、孤独への指向とが、今まで、どんな音楽でも経験したことがないような具合に、とけあったり、矛盾し対立しあったりしていた。しかもその曲は、あらゆる音楽の法則に背して、レントに重なるにもう一つのレントをもっており、対立と歩みよりは、外的な構造に全くよりかからず、まるで自分を表現するのを恥じるかのように、ひたすら内部へ内部へと沈潜し、音楽は前に向かって歩むというよりも、ますます身を隠していくような出来具合をしていた。
あまり盛大ともいえぬ拍手に応えて、舞台の上に頭ばかり大きくて、痩せて小さな体を運んでゆく青年の姿を見ながら、私は 〈蟹は自分に似せて穴を掘るというが、その穴を続けて掘るとは何たる蟹だろう?〉 と誰にいうともなく呟いたことを思いだす。私は、あの時、自分が武満徹という音楽家を理解したとは言わない。残念ながら、私はそんなに俊敏な批評家ではなかったわけである。しかし、そんな私にも、これは何という奇妙な若者だろうという印象は残った。そうして私は、あの時に演奏されたほかの曲はほとんど忘れてしまったのに、あの曲のことだけは、未だに覚えているのである。
そのあと、私は、武満という青年を、音楽会で時々見かけた。私たちはお互いに口もきかず、挨拶さえかわさなかったけれども、あの舞台でみた時は頭ばかり大きく見えた若者は、近くでみると、広い額と大きな目を、その頭部にもっていることがよくわかった。私は、その眼の光をみるたびに、雄弁な沈黙 という言葉のあったことを思いだすのが常だった。
演奏会の楽屋を訪ねてきた秋山は次のように語る。
秋山邦晴
楽屋では、人がたくさんいて、ほとんど話らしい話ができなかったんですが、家はどこだというので、住所を教えておいたら、すぐ翌日、武満が家に訪ねてきたんです。彼は世田谷代田で、ぼくは明大前ですから、歩いていける距離なんです。会った最初から話がはずんで、その日は昼ごろ来て、そのまま真夜中まで二人で話しつづけました。音楽のことだけじゃなくて、文学から美術までいろんなことをしゃべりました。
ぼくはずっとシュールレアリスムの研究をしていて、それで卒論も書くつもりだったのに、早稲田の仏文には、シュールレアリスムがわかる先生が一人もいなくて、それも大学を中退する理由の一つになったんですが、武満は、その関係の文学も絵画も実によく知っているのでびっくりしました。普通音楽家というのは、音楽の世界にだけ閉じこもっていて、他の世界のことはほとんど知らないという人が多いんです。武満の場合は、ぼくが興味を持っているようなことはだいたい彼のほうでも知っていて、最初から本当に気があったという感じでした。
その日は一二月の寒い日で、当時のこととて暖房もなくて、彼はレインコートを羽織ったまま火鉢に足をのせて、ポケットから煙草を出しちゃ、次から次へ吸っていました。だけど、あんまり長くいたので、そのうち煙草が一本もなくなり、火鉢の灰に突きさしてあった吸殻をもう一度拾いあげて、楊枝でそれを突きさして本当にぎりぎり吸えなくなるまで吸っていた姿をいまでも覚えています。
その翌日だったか、それから二、三日してだったか、今度はぼくが彼の家を訪ねたんです。四畳半くらいの狭い部屋に、ピアノが置いてあったけど、ピアノの椅子がなくて、代わりにみかん箱が重ねて置いてあって、その上に座布団がしいてあった。その椅子にしているみかん箱の中に楽譜がいっぱい入っていて、それはみんな習作時代の作品なんです。『ぼくはもうこういうのは書かないんだ』といいながら全部見せてくれたんですが、その中にあった『筧(かけひ)』なんて曲は、いまでも思いだすくらいにいい曲だったですね。
それからしょっちゅうお互いに行ったり来たりがはじまりました。ある時は湯浅がいっしょだったり、鈴木がいっしょだったり、みんないっしょだったり、とにかくよく会ってました。彼はいつも作曲をしていて、一区切りつくと、深夜の一時でも二時でも、ぼくの家まで下駄で歩いてきて、聞いてくれというんですよ。だけどぼくの家には小さなオルガンしかなくて、弾いているうちに音が足りなくなって、二人でまた武満の家まで歩いてピアノで弾いてみるとか、そういうことがよくありましたね。
秋山邦晴
楽屋では、人がたくさんいて、ほとんど話らしい話ができなかったんですが、家はどこだというので、住所を教えておいたら、すぐ翌日、武満が家に訪ねてきたんです。彼は世田谷代田で、ぼくは明大前ですから、歩いていける距離なんです。会った最初から話がはずんで、その日は昼ごろ来て、そのまま真夜中まで二人で話しつづけました。音楽のことだけじゃなくて、文学から美術までいろんなことをしゃべりました。
ぼくはずっとシュールレアリスムの研究をしていて、それで卒論も書くつもりだったのに、早稲田の仏文には、シュールレアリスムがわかる先生が一人もいなくて、それも大学を中退する理由の一つになったんですが、武満は、その関係の文学も絵画も実によく知っているのでびっくりしました。普通音楽家というのは、音楽の世界にだけ閉じこもっていて、他の世界のことはほとんど知らないという人が多いんです。武満の場合は、ぼくが興味を持っているようなことはだいたい彼のほうでも知っていて、最初から本当に気があったという感じでした。
その日は一二月の寒い日で、当時のこととて暖房もなくて、彼はレインコートを羽織ったまま火鉢に足をのせて、ポケットから煙草を出しちゃ、次から次へ吸っていました。だけど、あんまり長くいたので、そのうち煙草が一本もなくなり、火鉢の灰に突きさしてあった吸殻をもう一度拾いあげて、楊枝でそれを突きさして本当にぎりぎり吸えなくなるまで吸っていた姿をいまでも覚えています。
その翌日だったか、それから二、三日してだったか、今度はぼくが彼の家を訪ねたんです。四畳半くらいの狭い部屋に、ピアノが置いてあったけど、ピアノの椅子がなくて、代わりにみかん箱が重ねて置いてあって、その上に座布団がしいてあった。その椅子にしているみかん箱の中に楽譜がいっぱい入っていて、それはみんな習作時代の作品なんです。『ぼくはもうこういうのは書かないんだ』といいながら全部見せてくれたんですが、その中にあった『筧(かけひ)』なんて曲は、いまでも思いだすくらいにいい曲だったですね。
それからしょっちゅうお互いに行ったり来たりがはじまりました。ある時は湯浅がいっしょだったり、鈴木がいっしょだったり、みんないっしょだったり、とにかくよく会ってました。彼はいつも作曲をしていて、一区切りつくと、深夜の一時でも二時でも、ぼくの家まで下駄で歩いてきて、聞いてくれというんですよ。だけどぼくの家には小さなオルガンしかなくて、弾いているうちに音が足りなくなって、二人でまた武満の家まで歩いてピアノで弾いてみるとか、そういうことがよくありましたね。
湯浅も初対面のときから、武満とは気があったという。湯浅はいまカリフォルニア大学サンディエゴ校の教授をしているが、アメリカに渡る前の十年間は、武満とずっと隣同士の家に住むというほど親しいつきあいをしていた。
実験工房の仲間たちというのは、しょっちゅう会っていろんな話をしてましたね。音楽の話なんか五分の一くらいで、あとは映画の話とか、文学、哲学の話、そういう話題で語り明かして、武満のところの四畳半とか、他の家とかで、みんなで雑魚寝してしまうということがよくありました。それだけしゃべり合っていると、切磋琢磨というか芋洗いみたいな形で相互に影響されあって、お互いの考えが近くなってしまうんですね。しかし、そういう相互影響だけでなくて、その根底に、この音楽はいいとか悪いとかいう音楽的感性の原点みたいなところの美的判断で、みんな話し合う前から一致していたということがあったんです。
それがあの仲間の結びつきの原点だったという気がしますね。思想的にはみんな少しずつズレがあるんですが、あんなのはダメだのバカだのという判断はほとんど完全に一致してましたね。世評とは反対の評価の場合でもそうなんです。武満とはいまでもそうですよ。最近はアメリカと日本にわかれてしまったので、なかなか会う機会がないんですが、久しぶりに会って、『あれはどうだった』といろんな作品についての感想をいいあうと、どれがよかった、つまらなかったというのが、ほとんど一致しますね。
それから、そのころ始終話し合っていたのは、音楽の新しい構造がどうあるべきかということです。ソナタ形式なんて全然つまらないとか、曲のはじめ方終わり方にしても、いかにもという定形はつまらない、ベートーヴェンみたいに、『さあ、終るぞ、終るぞ!』といって終るみたいな音楽はバカげているとか、そういう話はよくやっていました。
(一方で激しい相互批判もあった)
秋山は言う。
みんなよくできかけの作品を他の人たちに見せて、意見を求めたりするわけです。そうすると、歯に衣着せない相当激しい批判がとびかいましたね。『ここは全然だめだ』『ここは頭で書いているだけだ』とか。それに対して、批判されたほうもへこたれずに反論して、お互いの主張をぶつけ合うという場面がよくありました。あれがお互いの刺激になり、栄養になり、お互いの成長にすごく役立っていると思いますよ。一人でやってたら、どうしたって独善的になりますからね。あのころ、ああいう相互批判の中で、これはダメだと思って机の中にしまいこんじゃって、ついに発表されなかった作品というのが、みんな相当あるんじゃないかな。
実験工房の仲間たちというのは、しょっちゅう会っていろんな話をしてましたね。音楽の話なんか五分の一くらいで、あとは映画の話とか、文学、哲学の話、そういう話題で語り明かして、武満のところの四畳半とか、他の家とかで、みんなで雑魚寝してしまうということがよくありました。それだけしゃべり合っていると、切磋琢磨というか芋洗いみたいな形で相互に影響されあって、お互いの考えが近くなってしまうんですね。しかし、そういう相互影響だけでなくて、その根底に、この音楽はいいとか悪いとかいう音楽的感性の原点みたいなところの美的判断で、みんな話し合う前から一致していたということがあったんです。
それがあの仲間の結びつきの原点だったという気がしますね。思想的にはみんな少しずつズレがあるんですが、あんなのはダメだのバカだのという判断はほとんど完全に一致してましたね。世評とは反対の評価の場合でもそうなんです。武満とはいまでもそうですよ。最近はアメリカと日本にわかれてしまったので、なかなか会う機会がないんですが、久しぶりに会って、『あれはどうだった』といろんな作品についての感想をいいあうと、どれがよかった、つまらなかったというのが、ほとんど一致しますね。
それから、そのころ始終話し合っていたのは、音楽の新しい構造がどうあるべきかということです。ソナタ形式なんて全然つまらないとか、曲のはじめ方終わり方にしても、いかにもという定形はつまらない、ベートーヴェンみたいに、『さあ、終るぞ、終るぞ!』といって終るみたいな音楽はバカげているとか、そういう話はよくやっていました。
(一方で激しい相互批判もあった)
秋山は言う。
みんなよくできかけの作品を他の人たちに見せて、意見を求めたりするわけです。そうすると、歯に衣着せない相当激しい批判がとびかいましたね。『ここは全然だめだ』『ここは頭で書いているだけだ』とか。それに対して、批判されたほうもへこたれずに反論して、お互いの主張をぶつけ合うという場面がよくありました。あれがお互いの刺激になり、栄養になり、お互いの成長にすごく役立っていると思いますよ。一人でやってたら、どうしたって独善的になりますからね。あのころ、ああいう相互批判の中で、これはダメだと思って机の中にしまいこんじゃって、ついに発表されなかった作品というのが、みんな相当あるんじゃないかな。
美術家の北代省三は武満の九歳年上。グループの中でも一人だけ年がはなれていた。北代はつぎのように回想する。
第一回のアンデパンダン展に『カストールとボルックス』という作品を出したら、それが瀧口さんの目にとまって、読売新聞の評ですごくほめてくれたんです。その翌年、第二回のアンデパンダン展の準備をしてるころ、主催の読売新聞がその景気づけの紙面を作るために、瀧口さんに、有望新人の制作風景をルポして書かせたんです。それでぼくのところに来てくれた。それからですね、瀧口さんと急速に親しくなって、日米通信に会いにいって話しこんだりするようになるのは。ちょうどそのころ武満とも知り合うようになって、何かの機会に、これから瀧口さんのところに行くといったら、ぼくも連れていってくださいということで連れていったんだろうと思います。
(これが、武満の生涯において最も影響を受けた人物と言っていい瀧口修造との出会いだった。武満の記憶によると、武満はこのとき下駄ばき、瀧口は上下つなぎの飛行服を着ていたという。終戦直後で、みんなひどいかっこうをしていたのである。武満は語る。)
たしか日米通信は、有楽町の駅前の毎日新聞社の中にあった。瀧口さんは外に出てきてくれて、近くのスバル座という映画館の脇の喫茶店で会ったんです。
第一回のアンデパンダン展に『カストールとボルックス』という作品を出したら、それが瀧口さんの目にとまって、読売新聞の評ですごくほめてくれたんです。その翌年、第二回のアンデパンダン展の準備をしてるころ、主催の読売新聞がその景気づけの紙面を作るために、瀧口さんに、有望新人の制作風景をルポして書かせたんです。それでぼくのところに来てくれた。それからですね、瀧口さんと急速に親しくなって、日米通信に会いにいって話しこんだりするようになるのは。ちょうどそのころ武満とも知り合うようになって、何かの機会に、これから瀧口さんのところに行くといったら、ぼくも連れていってくださいということで連れていったんだろうと思います。
(これが、武満の生涯において最も影響を受けた人物と言っていい瀧口修造との出会いだった。武満の記憶によると、武満はこのとき下駄ばき、瀧口は上下つなぎの飛行服を着ていたという。終戦直後で、みんなひどいかっこうをしていたのである。武満は語る。)
たしか日米通信は、有楽町の駅前の毎日新聞社の中にあった。瀧口さんは外に出てきてくれて、近くのスバル座という映画館の脇の喫茶店で会ったんです。
実験工房という日本において特記すべき芸術集団の父親的存在であり、また日本の前衛芸術の世界に大きな影響を与えた瀧口修造と、武満はここで初めて相見えた。
ぼくはすごく緊張していて、ほとんど瀧口さんと北代さんが話しているのをそばで聞いていたという感じです。
なんか不思議な人だと思いましたね、新聞社とか通信社とか、そういう仕事をしている人には全然見えなかった。話を聞いていると、とにかく何でも知っているし、何でも興味を持っている。そして、話すことがいつでも本質を衝いている。なにか非常に奥の深い人だなと思いました。
名前とどういう人かは、一応知っていたんです。詩人ということも知っていました。だけど、会う前から詩をちゃんと詠んでいたということはなかったと思います。だいたい、瀧口さんの詩は、読もうと思っても、そう簡単に読めなかったんです。読もうと思ったら、「詩と詩論」とか、昔の雑誌を見つけなければならないわけです。
あとで秋山と知り合ってからは、秋山がそういうのを全部集めて持っていたので、片端から借りて読みました。秋山と知り合う前に読んだのは、戦前一冊だけ瀧口さんが書いた詩集『妖精の距離』なんです。これは阿部展也さんの絵が入った詩画集で、わずか百部限定の豪華本です。普通では絶対に手に入らない本なんですが、幸いなことに、福島の家にあったんです。福島の姉の福島秀子さんが、阿部展也と親しかったからだと思います。
それを読んだときは、相当ショックでしたね。その衝撃はものすごく大きかったわけです。そのとき、これで音楽を書きたいと思ったんです。それで瀧口さんにこれで書いていいですかといったら、はにかみながら、どうぞと言ってくれました。それで書いたのが『妖精の距離』なわけです。
(「ふたつのレント」の発表が終わると、武満は早々と「妖精の距離」の作曲に着手した。ヴァイオリンの曲にしたのは、前がピアノ曲だから今度はヴァイオリンをやってみようかくらいの軽い気持ちだったという。この曲を初演した諏訪晶子は秋山邦晴の小学校の先輩で、諏訪根自子の妹であり、当時、美貌の天才姉妹として有名だった。そのときのことを諏訪晶子はよく記憶している。)
一見ひ弱な坊やみたいなんだけど、相当に頑固な人だなと思いました。何度でも、『そこんとこちがうんだよな』といって絶対にゆずらないんです。曲はとても澄んだきれいな音の曲で、白い柳の木のようだと思ったのを覚えています。ストレートで一見単調なんだけど、お能みたいな頑強さがその底にあるという感じでしたね。
武満さんという人は、なんというのか本当に妥協しない頑固な人だなと思ったのは、当日の朝になって、わたしをつかまえて、どうしても直したいところがあるといって楽譜を直そうとしたことなんです。わたしはせっかく練習を重ねて覚えた曲だから、ここで直されたら大変だと思って、譜面をかかえて『いやだ、いやだ』といって逃げまわったんですが、武満さんは鉛筆を持って追いかけてきて、『一音だけ。一音だけでいいから』といって、とうとう一音直されてしまいました。
ぼくはすごく緊張していて、ほとんど瀧口さんと北代さんが話しているのをそばで聞いていたという感じです。
なんか不思議な人だと思いましたね、新聞社とか通信社とか、そういう仕事をしている人には全然見えなかった。話を聞いていると、とにかく何でも知っているし、何でも興味を持っている。そして、話すことがいつでも本質を衝いている。なにか非常に奥の深い人だなと思いました。
名前とどういう人かは、一応知っていたんです。詩人ということも知っていました。だけど、会う前から詩をちゃんと詠んでいたということはなかったと思います。だいたい、瀧口さんの詩は、読もうと思っても、そう簡単に読めなかったんです。読もうと思ったら、「詩と詩論」とか、昔の雑誌を見つけなければならないわけです。
あとで秋山と知り合ってからは、秋山がそういうのを全部集めて持っていたので、片端から借りて読みました。秋山と知り合う前に読んだのは、戦前一冊だけ瀧口さんが書いた詩集『妖精の距離』なんです。これは阿部展也さんの絵が入った詩画集で、わずか百部限定の豪華本です。普通では絶対に手に入らない本なんですが、幸いなことに、福島の家にあったんです。福島の姉の福島秀子さんが、阿部展也と親しかったからだと思います。
それを読んだときは、相当ショックでしたね。その衝撃はものすごく大きかったわけです。そのとき、これで音楽を書きたいと思ったんです。それで瀧口さんにこれで書いていいですかといったら、はにかみながら、どうぞと言ってくれました。それで書いたのが『妖精の距離』なわけです。
(「ふたつのレント」の発表が終わると、武満は早々と「妖精の距離」の作曲に着手した。ヴァイオリンの曲にしたのは、前がピアノ曲だから今度はヴァイオリンをやってみようかくらいの軽い気持ちだったという。この曲を初演した諏訪晶子は秋山邦晴の小学校の先輩で、諏訪根自子の妹であり、当時、美貌の天才姉妹として有名だった。そのときのことを諏訪晶子はよく記憶している。)
一見ひ弱な坊やみたいなんだけど、相当に頑固な人だなと思いました。何度でも、『そこんとこちがうんだよな』といって絶対にゆずらないんです。曲はとても澄んだきれいな音の曲で、白い柳の木のようだと思ったのを覚えています。ストレートで一見単調なんだけど、お能みたいな頑強さがその底にあるという感じでしたね。
武満さんという人は、なんというのか本当に妥協しない頑固な人だなと思ったのは、当日の朝になって、わたしをつかまえて、どうしても直したいところがあるといって楽譜を直そうとしたことなんです。わたしはせっかく練習を重ねて覚えた曲だから、ここで直されたら大変だと思って、譜面をかかえて『いやだ、いやだ』といって逃げまわったんですが、武満さんは鉛筆を持って追いかけてきて、『一音だけ。一音だけでいいから』といって、とうとう一音直されてしまいました。
瀧口修造とのかかわりについて続ける。
当時ぼくは音楽でなければ美術評論をやりたいなんて思っていて、クレーやルドンなんかが好きでしたが、『クレー論を書くんなら一つ書いてごらんなさい』と瀧口さんに言われて、短い文章を書いたことがあるんです。それを瀧口さんに見てもらったら、原稿の始めから終いまで、本当に朱筆がこと細かに入ってたんでぼくはびっくりしちゃって。瀧口さんはその文章を『アトリエ』という雑誌に発表してくれたんです。美術のことを書いて、というより、仕事をしてお金を貰ったのは、それが初めてでした。
(瀧口は物心両面にわたって武満を励ましつづけた。当時武満はひどい貧乏暮らしをしていて、食べるものにこと欠くことすらあった。そんな武満に、瀧口はしばしば金銭的援助をしていたのである。)
瀧口さんはすごい照れ屋だから、正面切って資金援助するというんじゃなくて、ぼくの下宿に寄って、帰られたあと蒲団の下にお金が入った封筒がしのばせてあったりとか、そういうやりかたでしたね。お土産を持ってこようと思ったけど忘れたなんていって、封筒をわたされたこともあります。中を見ると、一万とか二万とか入っている。瀧口さんもかなり貧乏していたはずです。そんなに仕事をしていませんでしたからね。生活も質素だったし。
そのころのぼくは、ほんとに何も知らなくて、文学や芸術に関して何の知識もない男です。ところが瀧口さんはそんなことはおかまいなしに、瀧口さんが知っていることはこっちも当然知っているという前提で、まったく対等に話をするわけです。トリスタン・ツァラはこういってるとか、ピカビアはこういったとか。そんなこといわれたって、こっちはチンプンカンプンですよ。それでも瀧口さんは話のレベルを落とさない。シュールレアリストでも、絵描きでも、知らない人の名前がポンポン出てくる。それで仕方ないから帰ってから調べるわけです。
あの話題はどういうことなんだろう。いろんな本を読んで少しでも瀧口さんのレベルに近づこうとするわけです。それで次に行くとまた新しい名前や、新しい概念がどんどん出てくる。そこでまた帰って勉強する。それを繰り返すうちに、だんだんわかってきて、瀧口さんと中身のある話ができるようになっていったんです。瀧口さんの書斎がぼくの大学だったわけです。行くたんびに講義を受けて、宿題を出されて帰るという感じだったんですね。それなのに、月謝を払わないで、逆に奨学金を貰っていたみたいなもんです。
瀧口さんのところにはそれはもういろんな人が来ていました。絵描きが多かったですけど、いろんな美術関係者、詩人、文学者ですね。佐藤朔とか、詩人では西脇順三郎の系統の人が多かった。しばらくすると、若手の大岡信とか、飯島耕一なんかが出入りするようになった。そういう人たちの話を聞くことがまた刺激的だったですね。みんなよく喋って、本当に賑やかだった。だけど瀧口さんはいつも静かにニコニコ笑っていた。
そこからまた知り合いの輪が広がっていくんです。たとえば、瀧口修造さんを通じて版画の駒井哲郎さんと知りあいになる。駒井さんの知りあいになるとその友人の安東次男さんと知りあいになる。それから、画家の岡鹿之助さんとも知りあいになる。駒井さんは音楽好きで、『岡さんのところにすごくいいレコードがある。エドガー・ヴァレーズのレコードなんだけど、岡さんのところにしかないから、聞きにいこう』なんていって岡さんのアトリエに連れていってくれるわけですね。岡さんのところは素晴らしい再生装置があって、喜んでそのレコードを聞かせてくれるとか、瀧口さんのおかげで広がった交友関係というのは、ぼくの場合すごく沢山あるんですね。
ぼくは瀧口さんをお父さんみたいに思っていたし、瀧口さんはぼくを息子みたいに思っておられたんだと思います。ちょうど親子くらい年が開いていて、ぼくは早く父を亡くしていたし、瀧口さんは子供がいなかったということもあって、始終お宅に入りびたっている間に、お互いに父子的な感情を持つようになっていったんですすね。
それで、実をいうと、本邦初公開で、ほとんど誰も知らない話なんですが、瀧口さんから養子にならないかという話がきたことがあるんです。瀧口さんはぼくの母に会って正式に申しいれてるんです。母は母子のべったりとした関係は全然ない人ですから、『どうぞ、どうぞ』という感じだったんですが、ぼくのほうがずいぶん悩みました。結局一人でいろいろ考えた末に、自分の意思で断ることにしたんです。それは瀧口さんへの甘えになると思ったんです。ぼくは甘えというのがきらいなんです。それと、ぼくにとって瀧口さんというのは、とても尊敬する、とても大事な人だったんですね。それを身近な存在にして日常化してしまいたくないという気持ちがあったんです。
当時ぼくは音楽でなければ美術評論をやりたいなんて思っていて、クレーやルドンなんかが好きでしたが、『クレー論を書くんなら一つ書いてごらんなさい』と瀧口さんに言われて、短い文章を書いたことがあるんです。それを瀧口さんに見てもらったら、原稿の始めから終いまで、本当に朱筆がこと細かに入ってたんでぼくはびっくりしちゃって。瀧口さんはその文章を『アトリエ』という雑誌に発表してくれたんです。美術のことを書いて、というより、仕事をしてお金を貰ったのは、それが初めてでした。
(瀧口は物心両面にわたって武満を励ましつづけた。当時武満はひどい貧乏暮らしをしていて、食べるものにこと欠くことすらあった。そんな武満に、瀧口はしばしば金銭的援助をしていたのである。)
瀧口さんはすごい照れ屋だから、正面切って資金援助するというんじゃなくて、ぼくの下宿に寄って、帰られたあと蒲団の下にお金が入った封筒がしのばせてあったりとか、そういうやりかたでしたね。お土産を持ってこようと思ったけど忘れたなんていって、封筒をわたされたこともあります。中を見ると、一万とか二万とか入っている。瀧口さんもかなり貧乏していたはずです。そんなに仕事をしていませんでしたからね。生活も質素だったし。
そのころのぼくは、ほんとに何も知らなくて、文学や芸術に関して何の知識もない男です。ところが瀧口さんはそんなことはおかまいなしに、瀧口さんが知っていることはこっちも当然知っているという前提で、まったく対等に話をするわけです。トリスタン・ツァラはこういってるとか、ピカビアはこういったとか。そんなこといわれたって、こっちはチンプンカンプンですよ。それでも瀧口さんは話のレベルを落とさない。シュールレアリストでも、絵描きでも、知らない人の名前がポンポン出てくる。それで仕方ないから帰ってから調べるわけです。
あの話題はどういうことなんだろう。いろんな本を読んで少しでも瀧口さんのレベルに近づこうとするわけです。それで次に行くとまた新しい名前や、新しい概念がどんどん出てくる。そこでまた帰って勉強する。それを繰り返すうちに、だんだんわかってきて、瀧口さんと中身のある話ができるようになっていったんです。瀧口さんの書斎がぼくの大学だったわけです。行くたんびに講義を受けて、宿題を出されて帰るという感じだったんですね。それなのに、月謝を払わないで、逆に奨学金を貰っていたみたいなもんです。
瀧口さんのところにはそれはもういろんな人が来ていました。絵描きが多かったですけど、いろんな美術関係者、詩人、文学者ですね。佐藤朔とか、詩人では西脇順三郎の系統の人が多かった。しばらくすると、若手の大岡信とか、飯島耕一なんかが出入りするようになった。そういう人たちの話を聞くことがまた刺激的だったですね。みんなよく喋って、本当に賑やかだった。だけど瀧口さんはいつも静かにニコニコ笑っていた。
そこからまた知り合いの輪が広がっていくんです。たとえば、瀧口修造さんを通じて版画の駒井哲郎さんと知りあいになる。駒井さんの知りあいになるとその友人の安東次男さんと知りあいになる。それから、画家の岡鹿之助さんとも知りあいになる。駒井さんは音楽好きで、『岡さんのところにすごくいいレコードがある。エドガー・ヴァレーズのレコードなんだけど、岡さんのところにしかないから、聞きにいこう』なんていって岡さんのアトリエに連れていってくれるわけですね。岡さんのところは素晴らしい再生装置があって、喜んでそのレコードを聞かせてくれるとか、瀧口さんのおかげで広がった交友関係というのは、ぼくの場合すごく沢山あるんですね。
ぼくは瀧口さんをお父さんみたいに思っていたし、瀧口さんはぼくを息子みたいに思っておられたんだと思います。ちょうど親子くらい年が開いていて、ぼくは早く父を亡くしていたし、瀧口さんは子供がいなかったということもあって、始終お宅に入りびたっている間に、お互いに父子的な感情を持つようになっていったんですすね。
それで、実をいうと、本邦初公開で、ほとんど誰も知らない話なんですが、瀧口さんから養子にならないかという話がきたことがあるんです。瀧口さんはぼくの母に会って正式に申しいれてるんです。母は母子のべったりとした関係は全然ない人ですから、『どうぞ、どうぞ』という感じだったんですが、ぼくのほうがずいぶん悩みました。結局一人でいろいろ考えた末に、自分の意思で断ることにしたんです。それは瀧口さんへの甘えになると思ったんです。ぼくは甘えというのがきらいなんです。それと、ぼくにとって瀧口さんというのは、とても尊敬する、とても大事な人だったんですね。それを身近な存在にして日常化してしまいたくないという気持ちがあったんです。
このようなエピソードを聞いて、「なるほど、やっぱりそうだったんですか」というのは、大岡信である。
あの二人が一緒にいると、いつも独特の濃密な空間がそこにできて、他の人がちょっと近寄れないような感じになることがありました。瀧口さんは沢山の若い芸術家をいろんな形で支援して親しい付きあいをしていたんですが、武満に対しては特別なものがありました。やっぱり可愛かったんでしょうね。武満が成城の家に下駄ばきであらわれたころはまだ少年といっていいころでしょう。本当にお父さんと息子という精神的関係になってしまったんじゃないかしら。瀧口さんのことを、武満が自分の口から、『いってみれば、ぼくの親爺みたいなもんです』というのを、ぼくは何度か聞いたことがあります。それでぼくの頭の中では、瀧口さんに "武満徹のお父さん " というラベルが貼ってありました。
瀧口からの養子の申し出を断った武満の話を続ける。
あんまり瀧口さんの影響を受け過ぎると、小さい瀧口修造になって自分は終りになってしまうだろう、それは瀧口さんも望むことではないだろうということなんです。自分には自分なりの生き方があるはずだ。そのためには、瀧口さんから自分を心理的に引き離す必要があるということですね。それと、瀧口さんは、人格的に丸すぎるところがありましたね、どんな人にも理解を示し、やさしくするところがあった。ぼくなんか、こんなくだらない奴、つき合わなければいいのにと思うような人にまで親切だったですね。
そういうところは本気で反撥したところですけど、大半は反撥、反抗といっても、要するに自分の生き方を求めていたということです。そして考えてみると、自分の生き方で生きろということそれ自体は、瀧口さんの教えなんですね。そういう風に、生きるにあたっての基本的態度みたいなものは、ぼくは結局、瀧口さんに学んだんです。徹底的な自由人でいることとか、いやなものには断固としていやというとか、潔癖さとか、反権威主義とか、そういうところは、ずっと瀧口さんを範としてきました。
さて、最初の作品「二つのレント」、二番目の作品「妖精の距離」に続いて、一九五一年に上演されたバレエ「生きる悦び」の音楽が、武満の三番目の作品(鈴木博義と共作)となる。このバレエは読売新聞社が主催していたピカソ展の前夜祭の演し物として企画されたもので、その文化部にいた海藤日出男から相談を受けた瀧口の提案によって武満らのまだ名もなきグループが製作全般を引き受けることになった。
このグループを見守っていた瀧口の引立てによって、この大仕事がまかされることになったのである。グループの名前『実験工房』はここに瀧口修造によって命名された。
ほぼ素人集団によるバレエ「生きる悦び」はテンヤワンヤの末になんとか上演なった。この音楽についての印象をメンバーに聞いてみる。
秋山邦晴
ぼくの記憶だと、幕が開く前にまずプレリュードがあるんですね。その最初のところがすごくよかった。聞いたとたん、こんなオーケストラの曲はいままで聞いたことがないぞ、と思って、背筋がゾクッとしたのを覚えています。なんといったらいいんだろう。ある意味でメシアン的な響きなんですけどね。
湯浅譲二
武満が書いたところと鈴木が書いたところがあって、かなりちがうんです。武満はドビュッシー的なところがあって、鈴木にはバルトーク的なところがあった。武満の音は、マスクを掛けたみたいにこもった、独特な、誰も出せないように音を出していた。いまから思うと稚拙な部分もあったけど、非常にユニークだった。
山口勝弘
リリックというか、とてもきれいなか音楽でした。どんな音楽になるのか、それまでぼくらもぜんぜん知らなかったわけで、へえー、こんなきれいな音楽を書いていたのかと思った。
武満自身は
多分、結核のため肺か肋膜が癒着を起こして、指揮していても手が上がらず全く余裕がなくて、この曲はほとんど記憶してないです。あのときはくたくたになって、エネルギーを使いつくしてしまって、音楽だけでなく、舞台も、踊りもぜんぜん覚えてないです。プレリュードのはじめの出だしがよかったといわれると、そこは確かにぼくが棒を振ったときに、自分でも、ああ、いい響きだなと思ったところです。メシアン的な響きがあったといわれればそうかもしれない。あのころはメシアンに傾倒していましたから。ただそれまで聞いていたのはピアノ曲だけで、オーケストラ曲はまだ日本に紹介されてなかった。ドビュッシー風だったといわれると、それもそうかもしれないという気がします。ピカソの絵に牧神が出てきて、それが踊るわけですから、ドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』の連想が働いたということがあるかもしれません。だけど、その辺のことはぜんぜん覚えてないんですよ。
あの二人が一緒にいると、いつも独特の濃密な空間がそこにできて、他の人がちょっと近寄れないような感じになることがありました。瀧口さんは沢山の若い芸術家をいろんな形で支援して親しい付きあいをしていたんですが、武満に対しては特別なものがありました。やっぱり可愛かったんでしょうね。武満が成城の家に下駄ばきであらわれたころはまだ少年といっていいころでしょう。本当にお父さんと息子という精神的関係になってしまったんじゃないかしら。瀧口さんのことを、武満が自分の口から、『いってみれば、ぼくの親爺みたいなもんです』というのを、ぼくは何度か聞いたことがあります。それでぼくの頭の中では、瀧口さんに "武満徹のお父さん " というラベルが貼ってありました。
瀧口からの養子の申し出を断った武満の話を続ける。
あんまり瀧口さんの影響を受け過ぎると、小さい瀧口修造になって自分は終りになってしまうだろう、それは瀧口さんも望むことではないだろうということなんです。自分には自分なりの生き方があるはずだ。そのためには、瀧口さんから自分を心理的に引き離す必要があるということですね。それと、瀧口さんは、人格的に丸すぎるところがありましたね、どんな人にも理解を示し、やさしくするところがあった。ぼくなんか、こんなくだらない奴、つき合わなければいいのにと思うような人にまで親切だったですね。
そういうところは本気で反撥したところですけど、大半は反撥、反抗といっても、要するに自分の生き方を求めていたということです。そして考えてみると、自分の生き方で生きろということそれ自体は、瀧口さんの教えなんですね。そういう風に、生きるにあたっての基本的態度みたいなものは、ぼくは結局、瀧口さんに学んだんです。徹底的な自由人でいることとか、いやなものには断固としていやというとか、潔癖さとか、反権威主義とか、そういうところは、ずっと瀧口さんを範としてきました。
さて、最初の作品「二つのレント」、二番目の作品「妖精の距離」に続いて、一九五一年に上演されたバレエ「生きる悦び」の音楽が、武満の三番目の作品(鈴木博義と共作)となる。このバレエは読売新聞社が主催していたピカソ展の前夜祭の演し物として企画されたもので、その文化部にいた海藤日出男から相談を受けた瀧口の提案によって武満らのまだ名もなきグループが製作全般を引き受けることになった。
このグループを見守っていた瀧口の引立てによって、この大仕事がまかされることになったのである。グループの名前『実験工房』はここに瀧口修造によって命名された。
ほぼ素人集団によるバレエ「生きる悦び」はテンヤワンヤの末になんとか上演なった。この音楽についての印象をメンバーに聞いてみる。
秋山邦晴
ぼくの記憶だと、幕が開く前にまずプレリュードがあるんですね。その最初のところがすごくよかった。聞いたとたん、こんなオーケストラの曲はいままで聞いたことがないぞ、と思って、背筋がゾクッとしたのを覚えています。なんといったらいいんだろう。ある意味でメシアン的な響きなんですけどね。
湯浅譲二
武満が書いたところと鈴木が書いたところがあって、かなりちがうんです。武満はドビュッシー的なところがあって、鈴木にはバルトーク的なところがあった。武満の音は、マスクを掛けたみたいにこもった、独特な、誰も出せないように音を出していた。いまから思うと稚拙な部分もあったけど、非常にユニークだった。
山口勝弘
リリックというか、とてもきれいなか音楽でした。どんな音楽になるのか、それまでぼくらもぜんぜん知らなかったわけで、へえー、こんなきれいな音楽を書いていたのかと思った。
武満自身は
多分、結核のため肺か肋膜が癒着を起こして、指揮していても手が上がらず全く余裕がなくて、この曲はほとんど記憶してないです。あのときはくたくたになって、エネルギーを使いつくしてしまって、音楽だけでなく、舞台も、踊りもぜんぜん覚えてないです。プレリュードのはじめの出だしがよかったといわれると、そこは確かにぼくが棒を振ったときに、自分でも、ああ、いい響きだなと思ったところです。メシアン的な響きがあったといわれればそうかもしれない。あのころはメシアンに傾倒していましたから。ただそれまで聞いていたのはピアノ曲だけで、オーケストラ曲はまだ日本に紹介されてなかった。ドビュッシー風だったといわれると、それもそうかもしれないという気がします。ピカソの絵に牧神が出てきて、それが踊るわけですから、ドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』の連想が働いたということがあるかもしれません。だけど、その辺のことはぜんぜん覚えてないんですよ。
実験工房は、様々なジャンルの人々が集まったインターメディア的集団だった。秋山邦晴は語る。
実験工房では、ひとりひとりがインターメディア的な考え方を持っていたんですね。音楽のことを美術家もしゃべる。新しい曲ができればみんなで論じる。美術作品についてもみんなで論じる。海外のいろんな画家や音楽家についても、みんな同じように論じる。そういうことが、はじめからごく自然に行われていて、専門の垣根みたいなものが、全然なかった。だから、世界的にも珍しいインターメディアグループが生まれた。
それは瀧口さんの存在が大きいでしょうね。あれだけ間口が広い人って、なかなかいません。詩、文学、美術、写真、音楽、なんでも同じように論じられる人でしたからね。あの人自身がインターメディア的存在だったんです。その瀧口さんにみんな影響されていたから、インターメディアが当然と考えていたということがありますね。だからコンサートをやるときでも、それは音楽グループのともの考えないで、みんな一緒に何かやりたがって、実際、必ず何かやるわけです。
はじめは、会場にオブジェをかざとしったる程度の脇役だったんですけど、そのうち、一九五六年だったかな、実験工房主催で、日本ではじめてのテープ音楽のコンサートをやったんですよ。そのときなんか、会場はヤマハホールだったんですが、天井から、いっぱいのひもをちょうど天の川みたいにパーッと広げて、それにライトを当てて、会場全体をなんとも不思議な空間に変えてしまうといった大仕掛けなことをやったりするようになっていくんです。
一方、ぼくらのほうも、展覧会なんかのときに、美術家の制作を手伝ったり、搬入を手伝ったりという程度だったのが、ついには対等な関係で、グループ全員が共同製作した巨大なオブジェをアンデパンダン展に出すといったこともやったりしたんです。そしてそのうち、内容的にもっと音楽と美術が密接に結びついたものをやりたいということで、映画をやったり、オート・インスライド作品というものを作ったり、バレエ、演劇などの世界に入って行ったりするんです。
実験工房では、ひとりひとりがインターメディア的な考え方を持っていたんですね。音楽のことを美術家もしゃべる。新しい曲ができればみんなで論じる。美術作品についてもみんなで論じる。海外のいろんな画家や音楽家についても、みんな同じように論じる。そういうことが、はじめからごく自然に行われていて、専門の垣根みたいなものが、全然なかった。だから、世界的にも珍しいインターメディアグループが生まれた。
それは瀧口さんの存在が大きいでしょうね。あれだけ間口が広い人って、なかなかいません。詩、文学、美術、写真、音楽、なんでも同じように論じられる人でしたからね。あの人自身がインターメディア的存在だったんです。その瀧口さんにみんな影響されていたから、インターメディアが当然と考えていたということがありますね。だからコンサートをやるときでも、それは音楽グループのともの考えないで、みんな一緒に何かやりたがって、実際、必ず何かやるわけです。
はじめは、会場にオブジェをかざとしったる程度の脇役だったんですけど、そのうち、一九五六年だったかな、実験工房主催で、日本ではじめてのテープ音楽のコンサートをやったんですよ。そのときなんか、会場はヤマハホールだったんですが、天井から、いっぱいのひもをちょうど天の川みたいにパーッと広げて、それにライトを当てて、会場全体をなんとも不思議な空間に変えてしまうといった大仕掛けなことをやったりするようになっていくんです。
一方、ぼくらのほうも、展覧会なんかのときに、美術家の制作を手伝ったり、搬入を手伝ったりという程度だったのが、ついには対等な関係で、グループ全員が共同製作した巨大なオブジェをアンデパンダン展に出すといったこともやったりしたんです。そしてそのうち、内容的にもっと音楽と美術が密接に結びついたものをやりたいということで、映画をやったり、オート・インスライド作品というものを作ったり、バレエ、演劇などの世界に入って行ったりするんです。
実験工房の活動は活発化していったが、一方、武満の病状は悪化の一途を辿るようになっていった。入退院を繰り返し、治療もはかばかしくなく、もう自分は間もなく死ぬだろうと覚悟する程に症状も悪く、その絶望感から実験工房を脱退すると仲間に宣言したりした。
しかし、そんな日々の中、幸運なことに、新しく開発された薬と従来の薬の併用で、医者も奇跡というほどの回復をすることになった。武満は九死に一生を得た。ちょうどそのころ、武満はその後最も親しい友人となる男とめぐりあう。詩人の谷川俊太郎である。谷川を病院に連れていったのは、福島和夫だった。福島は駒井哲郎経由で谷川と知りあって意気投合していた。
福島が、『すげえやつがいるんだ。ぜひ会わせたい』といって引っぱっていった。やっぱり武満は当時から周囲の人間に、『すげえやつ』と思わせるものを持っていたんですね。最初に会ったとき、どんな話をしたかは忘れてしまいましたけど、とにかくパッと気が合って、すぐに友だちになりました。ぼくの最初の妻の岸田衿子が、浅香さんと立教女学院でいっしょだったという縁もあったんです。といっても、ちょうどその頃、ぼくは岸田と別れて、二度目の結婚をするところで、武満も浅香さんと結婚する前で、四人いっしょにあったというわけではないんですが。
武満は、谷川に会う前から、『二十億光年の孤独』を読んでいた。
ぼくはその頃瀧口さんの詩のようなシュールレアリスティックなものにひかれていたので、谷川の詩はあまりにナイーブすぎるような気がしたけど、でもあの独特の叙情性と透明性にとてもひかれるものがありました。詩から受けた印象では、谷川という男は、よれよれの洋服を着た苦学生で、働きながらコツコツ詩を書いている青年というイメーじだったんですが、会ってみたら、都会的なスマートな青年で、屈折したところがまるでなく、とても素直で、とてもまともで、いい意味のお坊ちゃん育ちという感じだったですね。ぼくなんかとまるでタイプがちがう未知の世界の人間という感じでした。友達になったのも、そういうところにひかれたということがあります。
別のタイプの人間ということは、谷川のほうでも感じていた。谷川は武満に、「秘められた激情」「ある危険な感じ」「一種の暗さ」「ドラマチックな性格」「自分の中に抱え込んだ大きな矛盾」を感じとっていたのである。
その隠された激情がたまに爆発する。それが暴力的に爆発することがある。そのとき彼は何をしでかすかわからないというところがあるわけです。若いころヤクザみたいのと殴り合いのケンカをしたことがあるなんていうのもそのあらわれでしょうね。ぼくの目の前で起きた例をひとつあげると、これはもう少しあとの話になりますが、彼が文学座の『国姓爺』の音楽を担当したときのことなんです。大阪で公演があったので、我われ夫婦もそっちにいってその芝居を見たんです。ところがその芝居がちっとも面白くなかった。
それでたしか途中で出てきちゃって、こっちは友だちだからいい気になって、こんなひでえ芝居はどうとかこうとかいったんですね。浅香さんもいっしょになって、これはよくないとか何とかいったんです。そしたらいきなり武満が浅香さんを足蹴にしてひっぱたいたんです。劇場のロビーですよ。ぼくは蒼ざめちゃって、彼の腕をおさえこんで、ぼくらが悪かった、いいすぎたと平謝りに謝って彼をなだめたことがある。
武満はどんな仕事でもものすごく一生懸命やる人だから、その仕事も幾晩も幾晩も徹夜してやったにちがいないわけです。それをぼくらがチョロッと見て酷評するなんて、耐えられなかったにちがいない。もちろんぼくらは、芝居の悪口をいっただけで、音楽の悪口をいったわけじゃないんですが、武満にとってはやはり自分を否定するものに聞えたんでしょう。ぼく自身はそういうふうに激情を爆発させるということは絶対にない人間だから、そのときは相当驚いた。
実際にそれを爆発させることは滅多にないけれど、彼の内部には、いつでもああいう爆発に導かれかねない内的矛盾のようなものがある、内的苛立ちがある。若いときは、通常は、もの静かな青年だったけど、そういう危険な激情を内部に秘めている感じが表にも出ていた。いまは外見からはそういう感じが消えているけど、でも、やっぱりそういうものは依然として根っこのところに持っている。いつだったか彼は、自分の作品の初演の公演を聞きにきた聴衆について、『おれはときどき、ああいう着飾ってスノッブづらして座っている聴衆を、舞台の上から機銃掃射して全部殺したいと思うことがある』といったことがある。
彼はあそこまで成功し、作曲家として認められ、みんなにほめそやされながら、どこかでそういう自分自身の現在に対して、これは違うと思ってるんじゃないか。
しかし、そんな日々の中、幸運なことに、新しく開発された薬と従来の薬の併用で、医者も奇跡というほどの回復をすることになった。武満は九死に一生を得た。ちょうどそのころ、武満はその後最も親しい友人となる男とめぐりあう。詩人の谷川俊太郎である。谷川を病院に連れていったのは、福島和夫だった。福島は駒井哲郎経由で谷川と知りあって意気投合していた。
福島が、『すげえやつがいるんだ。ぜひ会わせたい』といって引っぱっていった。やっぱり武満は当時から周囲の人間に、『すげえやつ』と思わせるものを持っていたんですね。最初に会ったとき、どんな話をしたかは忘れてしまいましたけど、とにかくパッと気が合って、すぐに友だちになりました。ぼくの最初の妻の岸田衿子が、浅香さんと立教女学院でいっしょだったという縁もあったんです。といっても、ちょうどその頃、ぼくは岸田と別れて、二度目の結婚をするところで、武満も浅香さんと結婚する前で、四人いっしょにあったというわけではないんですが。
武満は、谷川に会う前から、『二十億光年の孤独』を読んでいた。
ぼくはその頃瀧口さんの詩のようなシュールレアリスティックなものにひかれていたので、谷川の詩はあまりにナイーブすぎるような気がしたけど、でもあの独特の叙情性と透明性にとてもひかれるものがありました。詩から受けた印象では、谷川という男は、よれよれの洋服を着た苦学生で、働きながらコツコツ詩を書いている青年というイメーじだったんですが、会ってみたら、都会的なスマートな青年で、屈折したところがまるでなく、とても素直で、とてもまともで、いい意味のお坊ちゃん育ちという感じだったですね。ぼくなんかとまるでタイプがちがう未知の世界の人間という感じでした。友達になったのも、そういうところにひかれたということがあります。
別のタイプの人間ということは、谷川のほうでも感じていた。谷川は武満に、「秘められた激情」「ある危険な感じ」「一種の暗さ」「ドラマチックな性格」「自分の中に抱え込んだ大きな矛盾」を感じとっていたのである。
その隠された激情がたまに爆発する。それが暴力的に爆発することがある。そのとき彼は何をしでかすかわからないというところがあるわけです。若いころヤクザみたいのと殴り合いのケンカをしたことがあるなんていうのもそのあらわれでしょうね。ぼくの目の前で起きた例をひとつあげると、これはもう少しあとの話になりますが、彼が文学座の『国姓爺』の音楽を担当したときのことなんです。大阪で公演があったので、我われ夫婦もそっちにいってその芝居を見たんです。ところがその芝居がちっとも面白くなかった。
それでたしか途中で出てきちゃって、こっちは友だちだからいい気になって、こんなひでえ芝居はどうとかこうとかいったんですね。浅香さんもいっしょになって、これはよくないとか何とかいったんです。そしたらいきなり武満が浅香さんを足蹴にしてひっぱたいたんです。劇場のロビーですよ。ぼくは蒼ざめちゃって、彼の腕をおさえこんで、ぼくらが悪かった、いいすぎたと平謝りに謝って彼をなだめたことがある。
武満はどんな仕事でもものすごく一生懸命やる人だから、その仕事も幾晩も幾晩も徹夜してやったにちがいないわけです。それをぼくらがチョロッと見て酷評するなんて、耐えられなかったにちがいない。もちろんぼくらは、芝居の悪口をいっただけで、音楽の悪口をいったわけじゃないんですが、武満にとってはやはり自分を否定するものに聞えたんでしょう。ぼく自身はそういうふうに激情を爆発させるということは絶対にない人間だから、そのときは相当驚いた。
実際にそれを爆発させることは滅多にないけれど、彼の内部には、いつでもああいう爆発に導かれかねない内的矛盾のようなものがある、内的苛立ちがある。若いときは、通常は、もの静かな青年だったけど、そういう危険な激情を内部に秘めている感じが表にも出ていた。いまは外見からはそういう感じが消えているけど、でも、やっぱりそういうものは依然として根っこのところに持っている。いつだったか彼は、自分の作品の初演の公演を聞きにきた聴衆について、『おれはときどき、ああいう着飾ってスノッブづらして座っている聴衆を、舞台の上から機銃掃射して全部殺したいと思うことがある』といったことがある。
彼はあそこまで成功し、作曲家として認められ、みんなにほめそやされながら、どこかでそういう自分自身の現在に対して、これは違うと思ってるんじゃないか。
谷川と武満、二人はとにかく仲がよかった。詩人仲間で谷川俊太郎と親しくしていた大岡信は、こんなことを語る。
谷川と話していると、武満が、武満がっていうんですよ。それでぼくは、はじめて武満という人間の存在を知ったわけです。武満がこう言った、ああ言った。武満とこんなことをした、あんなことをした。まるで兄弟のことをいっているみたいだった。あんまり武満の話が出てくるもんで、何だこの武満という野郎は、と少し不愉快になるくらいだった。そして、その武満という奴に早く会ってみたいもんだと思うようになった。
谷川の話を続ける。
はじめのうちは、二人はいろんなことでピッタリ息が合うと思っていた。実際、西部劇の好みなんてよく一致していた。それから、ちょうどあの頃はじまった007シリーズはどちらも好きで、新しいのがくると、いつも二人で連れだって見に行きました。しかし、付き合いが深まるにつれ、だんだんお互いの違う面が見えてきた。だからといって、仲が遠のいていったことはなかった。
また当時の「シンフォニー」誌に武満について谷川は次のようなことを書いている。
彼の尊敬する人物。大塩平八郎、佐倉惣五郎、佐久間艇長、瀧口修造、および彼自身の女房、浅香さん。
彼の好きな文学。ホフマン、ポー、ピアース、秋成、馬琴、エリュアール。
最近感心した映画。ワイラアの『友情ある説得』。音楽としては、『居酒屋』。
彼は生活には比較的ノンシャランだが、作曲する時は、極度に神経質になる。机の上をきれいに掃除し、見事にけずられた各種の鉛筆を並べ、チューインガム、ミンツ、ドロップ等のキャンディを多量に用意する。それらをしゃぶりながら、顕微鏡的な細密さで譜を書いてゆく。丹念なレース編みのような美しさ。
武満の文学の好みは、谷川のそれと全く異質のものだという。さらに谷川の話を続ける。
彼はいわゆる自然主義的なリアリズムの小説とか、私小説とか、生の現実に近いものには関心がないんです。ここにあげられたような、幻想小説、怪奇物、ゴシック小説なんかが好きなんですね。それから、推理小説、SF小説といったイマジナリーな作品が一貫して好きなんですよ。そういうものの読書量はものすごいですよ。ぼくなんか聞いたこともないような日本人作家の幻想小説なんか大量に持っている。『これ面白いから読んでみろよ』なんて薦められるんだけど、ぼくは全然食指が動かない。
ぼくは日常的な現実な世界のリアリティというものにこだわる人間なんです。一本のくぎとか、一個のコップとか、そういうものがすごく気になるタイプなんです。しかし彼は、そういう日常性の世界にリアリティを感じないで、イマジナリーな世界のほうにリアリティを感じるタイプの人間なんですね。彼が日常生活に全然関心がないというのも、おそらくそこから来てるんじゃないかと思うんです。
それがまた詩に対する好みにもつながってくる。彼はやっぱり、シュールレアリスムが好きなんです。日常的な現実を超えた超現実主義がいいわけです。しかしぼくのほうは、シュールレアリスムをほとんど理解できない。だから、瀧口さんの詩なんかもそんなにいいとは思わない。もちろん瀧口さんという人はとてもいい人で、ぼくも人間的には大好きだったんだけど、その作品に共感するということはなかったし、まして大岡や武満のように、瀧口さんに師事しようと思ったことなんてないわけです。
武満とぼくは何度か一緒に仕事をしているけど、彼の音楽との親和性からいったら、ぼくよりシュールレアリスムの洗礼を受けてきた大岡のほうがずっといいわけです。だから、『環礁』とか、『揺れる鏡の夜明け』とか、大岡の詩に武満が音楽をつけたり、大岡の詩のタイトルそのまま武満の音楽のタイトルにするといったことが何度かあります。ぼくの詩とはそういうことはほとんどないんです。
谷川は子供のころから西洋音楽に親しみ、ピアノも習得していた。二人が知りあったころ、ピアノは谷川のほうが武満よりずっとうまかったという。
ぼくはベートーヴェンに目を開かれて夢中になって聞いていました。そのあと、ロマン派くらいまでは熱心に聞いていたけど、現代音楽というと、ラヴェル、ドビュッシー、ガーシュインくらいまでで、同時代の現代音楽を聞くようになるのは、武満と知りあってからです。武満の音楽を最初に聞いたのは、『遮られない休息』だったと思うんですが、聞いた印象を率直にいうと、『なんて血の気がない音楽だろう』という感じでしたね。頭でっかちで、蒼白くて、ひ弱という印象。現代音楽を聞いてベートーヴェンから受けたような感動を受けるといったことはなかったわけです。しかし、同時代的同志愛みたいなのがあって、武満と知りあってからは、メシアン、ジョリヴェ、ケージとか聞くようになりました。
谷川と話していると、武満が、武満がっていうんですよ。それでぼくは、はじめて武満という人間の存在を知ったわけです。武満がこう言った、ああ言った。武満とこんなことをした、あんなことをした。まるで兄弟のことをいっているみたいだった。あんまり武満の話が出てくるもんで、何だこの武満という野郎は、と少し不愉快になるくらいだった。そして、その武満という奴に早く会ってみたいもんだと思うようになった。
谷川の話を続ける。
はじめのうちは、二人はいろんなことでピッタリ息が合うと思っていた。実際、西部劇の好みなんてよく一致していた。それから、ちょうどあの頃はじまった007シリーズはどちらも好きで、新しいのがくると、いつも二人で連れだって見に行きました。しかし、付き合いが深まるにつれ、だんだんお互いの違う面が見えてきた。だからといって、仲が遠のいていったことはなかった。
また当時の「シンフォニー」誌に武満について谷川は次のようなことを書いている。
彼の尊敬する人物。大塩平八郎、佐倉惣五郎、佐久間艇長、瀧口修造、および彼自身の女房、浅香さん。
彼の好きな文学。ホフマン、ポー、ピアース、秋成、馬琴、エリュアール。
最近感心した映画。ワイラアの『友情ある説得』。音楽としては、『居酒屋』。
彼は生活には比較的ノンシャランだが、作曲する時は、極度に神経質になる。机の上をきれいに掃除し、見事にけずられた各種の鉛筆を並べ、チューインガム、ミンツ、ドロップ等のキャンディを多量に用意する。それらをしゃぶりながら、顕微鏡的な細密さで譜を書いてゆく。丹念なレース編みのような美しさ。
武満の文学の好みは、谷川のそれと全く異質のものだという。さらに谷川の話を続ける。
彼はいわゆる自然主義的なリアリズムの小説とか、私小説とか、生の現実に近いものには関心がないんです。ここにあげられたような、幻想小説、怪奇物、ゴシック小説なんかが好きなんですね。それから、推理小説、SF小説といったイマジナリーな作品が一貫して好きなんですよ。そういうものの読書量はものすごいですよ。ぼくなんか聞いたこともないような日本人作家の幻想小説なんか大量に持っている。『これ面白いから読んでみろよ』なんて薦められるんだけど、ぼくは全然食指が動かない。
ぼくは日常的な現実な世界のリアリティというものにこだわる人間なんです。一本のくぎとか、一個のコップとか、そういうものがすごく気になるタイプなんです。しかし彼は、そういう日常性の世界にリアリティを感じないで、イマジナリーな世界のほうにリアリティを感じるタイプの人間なんですね。彼が日常生活に全然関心がないというのも、おそらくそこから来てるんじゃないかと思うんです。
それがまた詩に対する好みにもつながってくる。彼はやっぱり、シュールレアリスムが好きなんです。日常的な現実を超えた超現実主義がいいわけです。しかしぼくのほうは、シュールレアリスムをほとんど理解できない。だから、瀧口さんの詩なんかもそんなにいいとは思わない。もちろん瀧口さんという人はとてもいい人で、ぼくも人間的には大好きだったんだけど、その作品に共感するということはなかったし、まして大岡や武満のように、瀧口さんに師事しようと思ったことなんてないわけです。
武満とぼくは何度か一緒に仕事をしているけど、彼の音楽との親和性からいったら、ぼくよりシュールレアリスムの洗礼を受けてきた大岡のほうがずっといいわけです。だから、『環礁』とか、『揺れる鏡の夜明け』とか、大岡の詩に武満が音楽をつけたり、大岡の詩のタイトルそのまま武満の音楽のタイトルにするといったことが何度かあります。ぼくの詩とはそういうことはほとんどないんです。
谷川は子供のころから西洋音楽に親しみ、ピアノも習得していた。二人が知りあったころ、ピアノは谷川のほうが武満よりずっとうまかったという。
ぼくはベートーヴェンに目を開かれて夢中になって聞いていました。そのあと、ロマン派くらいまでは熱心に聞いていたけど、現代音楽というと、ラヴェル、ドビュッシー、ガーシュインくらいまでで、同時代の現代音楽を聞くようになるのは、武満と知りあってからです。武満の音楽を最初に聞いたのは、『遮られない休息』だったと思うんですが、聞いた印象を率直にいうと、『なんて血の気がない音楽だろう』という感じでしたね。頭でっかちで、蒼白くて、ひ弱という印象。現代音楽を聞いてベートーヴェンから受けたような感動を受けるといったことはなかったわけです。しかし、同時代的同志愛みたいなのがあって、武満と知りあってからは、メシアン、ジョリヴェ、ケージとか聞くようになりました。
絵描きの芥川紗織は実験工房の美術グループと親しい関係にあったが、そういう縁を通じて、武満は芥川紗織と親しくなり、芥川家に出入りするようになった。芥川紗織の夫は作曲家の芥川也寸志である。
芥川也寸志さんにも紹介されて、自然に音楽のことを、いろいろ語り合うようになった。ぼくは若くて生意気ざかりだったから、平気で芥川さんの音楽を、ここがよくない、あそこがどうのとズケズケ批判したんですね。あの頃ぼくは、清瀬さんにも、早坂さんにも平気でそういうことをやっていたわけです。芥川さんはやさしい人だから、はじめは黙ってきいていたけど、そのうちたまりかねたのか、ちょっと怒りをあらわにして、ピシャリと、『武満くん、口で批判するのは簡単だよ。何とでもいえる。でも、くやしかったら、一曲でもいいから書いてごらんよ』といわれたんです。これはこたえましたね。確かあのときは『二つのレント』の前で、ぼくはまだ人に見せられるような作品を何も書いていなかったんです。
こういうやりとりははじめのころあったものの、その後、幾つかの作品を発表するうちに、芥川は武満の才能を高く評価してくれるようになった。そして、武満の経済状態を心配して、ときどき映画音楽を書くときのアシスタントに使ってくれたのである。
早坂さんのところでやったように、芥川さんの指示を受けてオーケストレーションをするとか、スコアを清書するとかするわけです。かれこれ十本くらいはやったと思います。忘れられないのは『目白三平』(千葉泰樹監督)の仕事で、あれは結婚直後にやった仕事だと思うんですが、終るとすぐに、芥川さんがステュードベーカーに乗ってぼくらの新居を訪ねてきてくれて、『武満くん、なにかとお金がいるだろう』といって、『目白三平』の仕事の報酬という形をとって、相当のお金をくださったことです。
そのお金で、はじめて電気洗濯機を買ったことを覚えています。そのあとも、何度か洗足池の家をたずねてくれて、仕事を頼むという形で経済援助してくれました。録音の現場なんかにもよく連れていってくれて、作曲された作品が具体的にどういう風に音になっていくかを教えてくれました。
芥川の追悼文集の中で、武満は次のように書いている。
特に忘れられない仕事は、一九六三年に製作された、市川崑監督の『太平洋ひとりぼっち』である。この映画では、共作という形で、芥川也寸志が音楽監督を務め、私が作曲に当たった。この経験から作曲家として得たものは大きく、また、芥川也寸志の人格から受けた影響も少なくない。
私自身は、未だ、映画音楽の経験に乏しかったので、教えられることばかりだった。場面(シーン)とそれにフィットするオーケストラのサイズ。また、遠景(ロングショット)であるか近景(アップ)であるかによって、作曲への指示は同じ旋律動機を用いても、かなり異なった。それに応えるのは未熟な私には難しかった。幾夜も徹夜が続いた。
芥川氏もその私につきあって、音楽録音の際に必要な、楽器編成表や、ロール表を、丹念に色分けして作ったりしていた。作曲された音楽が、芥川氏のオーケストレーションで生きた響きをえ、映像(イメージ)と合わせられて、私はやっと、芥川氏の意図を、実際に、理解できたのだった。
『太平洋ひとりぼっち』では、石原裕次郎扮する堀江青年が、孤独と疲労の果てに、妄想に悩まされる場面(シーン)がある。具体音楽(ミュージック・コンクレート)の手法で作曲すべきだろうと提案したのは芥川也寸志だった。その当時、私は、具体音楽を主に仕事にしていたので、事情を識ったひとは、当然、それが私のアイディアだと思ったようだ。だが実際には、そこで使われた具体的な音響、鋏や鎖(チェーン)の音等の素材(ソース)は、すべて芥川の示唆によった。
さて、貧乏していた時に武満徹が黛敏郎からピアノを贈られたというのは有名な話だが、この話には芥川が大きく関わっていた。贈られたことは事実に間違いないものの、武満と黛両者の話は食い違いを見せて興味深い。その話は次回。
芥川也寸志さんにも紹介されて、自然に音楽のことを、いろいろ語り合うようになった。ぼくは若くて生意気ざかりだったから、平気で芥川さんの音楽を、ここがよくない、あそこがどうのとズケズケ批判したんですね。あの頃ぼくは、清瀬さんにも、早坂さんにも平気でそういうことをやっていたわけです。芥川さんはやさしい人だから、はじめは黙ってきいていたけど、そのうちたまりかねたのか、ちょっと怒りをあらわにして、ピシャリと、『武満くん、口で批判するのは簡単だよ。何とでもいえる。でも、くやしかったら、一曲でもいいから書いてごらんよ』といわれたんです。これはこたえましたね。確かあのときは『二つのレント』の前で、ぼくはまだ人に見せられるような作品を何も書いていなかったんです。
こういうやりとりははじめのころあったものの、その後、幾つかの作品を発表するうちに、芥川は武満の才能を高く評価してくれるようになった。そして、武満の経済状態を心配して、ときどき映画音楽を書くときのアシスタントに使ってくれたのである。
早坂さんのところでやったように、芥川さんの指示を受けてオーケストレーションをするとか、スコアを清書するとかするわけです。かれこれ十本くらいはやったと思います。忘れられないのは『目白三平』(千葉泰樹監督)の仕事で、あれは結婚直後にやった仕事だと思うんですが、終るとすぐに、芥川さんがステュードベーカーに乗ってぼくらの新居を訪ねてきてくれて、『武満くん、なにかとお金がいるだろう』といって、『目白三平』の仕事の報酬という形をとって、相当のお金をくださったことです。
そのお金で、はじめて電気洗濯機を買ったことを覚えています。そのあとも、何度か洗足池の家をたずねてくれて、仕事を頼むという形で経済援助してくれました。録音の現場なんかにもよく連れていってくれて、作曲された作品が具体的にどういう風に音になっていくかを教えてくれました。
芥川の追悼文集の中で、武満は次のように書いている。
特に忘れられない仕事は、一九六三年に製作された、市川崑監督の『太平洋ひとりぼっち』である。この映画では、共作という形で、芥川也寸志が音楽監督を務め、私が作曲に当たった。この経験から作曲家として得たものは大きく、また、芥川也寸志の人格から受けた影響も少なくない。
私自身は、未だ、映画音楽の経験に乏しかったので、教えられることばかりだった。場面(シーン)とそれにフィットするオーケストラのサイズ。また、遠景(ロングショット)であるか近景(アップ)であるかによって、作曲への指示は同じ旋律動機を用いても、かなり異なった。それに応えるのは未熟な私には難しかった。幾夜も徹夜が続いた。
芥川氏もその私につきあって、音楽録音の際に必要な、楽器編成表や、ロール表を、丹念に色分けして作ったりしていた。作曲された音楽が、芥川氏のオーケストレーションで生きた響きをえ、映像(イメージ)と合わせられて、私はやっと、芥川氏の意図を、実際に、理解できたのだった。
『太平洋ひとりぼっち』では、石原裕次郎扮する堀江青年が、孤独と疲労の果てに、妄想に悩まされる場面(シーン)がある。具体音楽(ミュージック・コンクレート)の手法で作曲すべきだろうと提案したのは芥川也寸志だった。その当時、私は、具体音楽を主に仕事にしていたので、事情を識ったひとは、当然、それが私のアイディアだと思ったようだ。だが実際には、そこで使われた具体的な音響、鋏や鎖(チェーン)の音等の素材(ソース)は、すべて芥川の示唆によった。
さて、貧乏していた時に武満徹が黛敏郎からピアノを贈られたというのは有名な話だが、この話には芥川が大きく関わっていた。贈られたことは事実に間違いないものの、武満と黛両者の話は食い違いを見せて興味深い。その話は次回。
武満に立花が尋ねる。
作曲家にとってピアノがないというのはつらいでしょうね。万年筆がないもの書きみたいなものですね。
いやね、本当にそうですね。作曲家によっては、いちいちピアノを使わないという人もいるんだけど、ぼくの場合は、ヴァイオリンの曲でもなんでも、ピアノで音を確かめながら書いていくんです。
そうすると、ピアノがないとどうなるんですか。
友だちのピアノを借りたりして仕事をするわけです。そうやって小さい曲をいくつか書いたことは書いたんです。だけど、ろくなのが書けなかったなあ。
そんなときいきなり、黛敏郎からピアノが送られてきた。
ある日、新婚家庭に突然ピアノが来たんです。運送屋の人が、『黛さんという方から届けるように言われた』ってことで。青天の霹靂ですよね。(座談会「題名のない音楽談義」「週刊朝日」一九八二年十月二十九日号)
芥川さんが黛さんにいったんですね。こういう男がいて、ピアノがないんだと。だからぼくは黛さんという人とは全く面識がなかったんだけど・・・・。暑い夏の日にいきなりピアノがやってきちゃったんですよ。予告なしに。これは信じられないような話でしょう。それですぐに住所を調べて黛さんに会いに行ったんですよ。黛さんは当時、桂木洋子さんというきれいな女優さんと結婚したばかりで、奥さんもピアノを持っていたので、あれは女房のですって言うの。家に二台あっても仕方ないので使ってくださいって。それじゃあ貸してくださいということで。(「武満徹、音楽生活を語る」「マリー・クレール」一九九〇年十一月号)
結局武満は、このピアノを十三年間使い、「ノヴェンバー・ステップス」までの全作品をこのピアノで作曲することになる。
ピアノが送られてきたのは武満によれば、芥川也寸志が武満の窮状を黛に話してくれたからだろうという。武満の生活をいつも気づかっていた芥川が、ピアノがないという窮状を黛に話してくれて、それでピアノが送られてきたというのだ。しかし、この点について、黛の記憶はすこし食い違っている。黛は、その前に、武満に会っていたという。
いきなり送ったというのは伝説でしてね、実はその少し前に武満くんに会っているんです。芥川さんが、若くて優秀な作曲家で、きみに会いたがっていると紹介してくれて、会ったんです。
その経緯を黛は雑誌「ポリフォーン」第八号に書いている。
武満徹と初めて会ったときのことは忘れられない。芥川也寸志から『病身で貧乏しているが凄く才能のある作曲家で、きみに是非会いたいと言っているから』と紹介されて、彼が代々木の拙宅に現われたのは確か一九五三年のことだった。
痩せて顔色の悪い青年で、友人の鈴木博義と一緒だった。ソファに座るなり一言『武満です』と言ったきり、あとは二人とも全く無言である。私は些か困って、いろいろ話を向けるのだが、『ハイ』とか『イイエ』とか短い答えが返ってくるだけで、すぐに途切れてしまう。
一体、何で私に会いに来たのかよく理解できぬまま時が流れ、最初の出会いはギコチなく終った。でも〈遮られない休息〉の楽譜を見せて貰い、既存の美学では稚拙といえるような独自性を持った世界に、驚嘆したことは鮮烈に憶えている。
彼はピアノを持っていなかった。道を歩いていてピアノの音が聞こえると、その家に飛び込んで弾かせて貰い、作曲をするという話は、同じように以前、ピアノを持っていなかった私の身につまされた。さいわい私のところには、家内が使ったガルブランセンというアメリカのスピネット・ピアノが一台空いていたので、よかったら使ってくださいと彼に上げたことが、後日美談みたいに伝えられたが、同じ悩みを分け合った人間の、ささやかな贈り物に過ぎなかったのだ。
そのあたりについて黛に確認すると、
いずれにしても、ピアノを送る前に会っているんです。譜面を見たこともよく覚えています。「稚拙」と書いたのは、当時の風潮からすると、あまりに寡黙であまりに音の数が少なすぎるために、プリミティブな印象を与えたということです。我々の仲間は、もっと音の多い饒舌な音楽を作ってしまうものなんです。そうじゃないと、プロの作品と見なされないようなところがある。それが山根銀二の「音楽以前」という批評にもつながったんだと思います。
そういうわけで、音楽のエクリチュールという書法からするとプリミティブなんですが、我々の仲間にはない音の真実性といいますか、純粋ないい音楽性を持っているなと評価したわけです。そういうありきたりな音楽でない音楽を作る才能を評価したからこそ、ピアノをさしあげたわけです。見ず知らずの人に闇雲にピアノを上げたわけではなくて、やっぱりこれだけの才能ある人がピアノがないのは気の毒だと思ったんです。
さらに食い違う話は次回に。
作曲家にとってピアノがないというのはつらいでしょうね。万年筆がないもの書きみたいなものですね。
いやね、本当にそうですね。作曲家によっては、いちいちピアノを使わないという人もいるんだけど、ぼくの場合は、ヴァイオリンの曲でもなんでも、ピアノで音を確かめながら書いていくんです。
そうすると、ピアノがないとどうなるんですか。
友だちのピアノを借りたりして仕事をするわけです。そうやって小さい曲をいくつか書いたことは書いたんです。だけど、ろくなのが書けなかったなあ。
そんなときいきなり、黛敏郎からピアノが送られてきた。
ある日、新婚家庭に突然ピアノが来たんです。運送屋の人が、『黛さんという方から届けるように言われた』ってことで。青天の霹靂ですよね。(座談会「題名のない音楽談義」「週刊朝日」一九八二年十月二十九日号)
芥川さんが黛さんにいったんですね。こういう男がいて、ピアノがないんだと。だからぼくは黛さんという人とは全く面識がなかったんだけど・・・・。暑い夏の日にいきなりピアノがやってきちゃったんですよ。予告なしに。これは信じられないような話でしょう。それですぐに住所を調べて黛さんに会いに行ったんですよ。黛さんは当時、桂木洋子さんというきれいな女優さんと結婚したばかりで、奥さんもピアノを持っていたので、あれは女房のですって言うの。家に二台あっても仕方ないので使ってくださいって。それじゃあ貸してくださいということで。(「武満徹、音楽生活を語る」「マリー・クレール」一九九〇年十一月号)
結局武満は、このピアノを十三年間使い、「ノヴェンバー・ステップス」までの全作品をこのピアノで作曲することになる。
ピアノが送られてきたのは武満によれば、芥川也寸志が武満の窮状を黛に話してくれたからだろうという。武満の生活をいつも気づかっていた芥川が、ピアノがないという窮状を黛に話してくれて、それでピアノが送られてきたというのだ。しかし、この点について、黛の記憶はすこし食い違っている。黛は、その前に、武満に会っていたという。
いきなり送ったというのは伝説でしてね、実はその少し前に武満くんに会っているんです。芥川さんが、若くて優秀な作曲家で、きみに会いたがっていると紹介してくれて、会ったんです。
その経緯を黛は雑誌「ポリフォーン」第八号に書いている。
武満徹と初めて会ったときのことは忘れられない。芥川也寸志から『病身で貧乏しているが凄く才能のある作曲家で、きみに是非会いたいと言っているから』と紹介されて、彼が代々木の拙宅に現われたのは確か一九五三年のことだった。
痩せて顔色の悪い青年で、友人の鈴木博義と一緒だった。ソファに座るなり一言『武満です』と言ったきり、あとは二人とも全く無言である。私は些か困って、いろいろ話を向けるのだが、『ハイ』とか『イイエ』とか短い答えが返ってくるだけで、すぐに途切れてしまう。
一体、何で私に会いに来たのかよく理解できぬまま時が流れ、最初の出会いはギコチなく終った。でも〈遮られない休息〉の楽譜を見せて貰い、既存の美学では稚拙といえるような独自性を持った世界に、驚嘆したことは鮮烈に憶えている。
彼はピアノを持っていなかった。道を歩いていてピアノの音が聞こえると、その家に飛び込んで弾かせて貰い、作曲をするという話は、同じように以前、ピアノを持っていなかった私の身につまされた。さいわい私のところには、家内が使ったガルブランセンというアメリカのスピネット・ピアノが一台空いていたので、よかったら使ってくださいと彼に上げたことが、後日美談みたいに伝えられたが、同じ悩みを分け合った人間の、ささやかな贈り物に過ぎなかったのだ。
そのあたりについて黛に確認すると、
いずれにしても、ピアノを送る前に会っているんです。譜面を見たこともよく覚えています。「稚拙」と書いたのは、当時の風潮からすると、あまりに寡黙であまりに音の数が少なすぎるために、プリミティブな印象を与えたということです。我々の仲間は、もっと音の多い饒舌な音楽を作ってしまうものなんです。そうじゃないと、プロの作品と見なされないようなところがある。それが山根銀二の「音楽以前」という批評にもつながったんだと思います。
そういうわけで、音楽のエクリチュールという書法からするとプリミティブなんですが、我々の仲間にはない音の真実性といいますか、純粋ないい音楽性を持っているなと評価したわけです。そういうありきたりな音楽でない音楽を作る才能を評価したからこそ、ピアノをさしあげたわけです。見ず知らずの人に闇雲にピアノを上げたわけではなくて、やっぱりこれだけの才能ある人がピアノがないのは気の毒だと思ったんです。
さらに食い違う話は次回に。
黛敏郎の話をつづける。
ただ、これがあんまり美談化されているので、念のために申しあげておきますが、ぼくはあれはただで差し上げるつもりだったんですが、武満くんはすっかり恐縮してしまって、あのあと、ちゃんとお金をもってきたんです。そういうものをいただいているので、あんまり美談美談といわれると恥ずかしくなってしまうのです。
黛はそう言うが、武満はそれについて首をひねる。
お金なんかあげたかなあ、何しろお金がないから貸しピアノも借りられなかったんですから。もし持っていったとしても、雀の涙のような金額だったと思いますよ。ただ、貰いっぱなしというのは、あまりに心苦しいので、その頃大事にしていたインド音楽のレコードと天台声明のレコード、それに声明の楽譜を持っていって、これをお礼代わりに貰ってくださいと推しつけてきたことを覚えています。黛さんが後に『涅槃交響曲』を書くようになったのは、あのレコードと楽譜の影響もあったんじゃないかと秘かに思ってるんですけど。
ともかく、これを契機に、二人は親しく交際するようになり、武満は黛の映画音楽などの仕事を手伝うことになった。
あのころの映画音楽というのは、想像を絶するようなスピードで書くことが要求されたんです。武満くんには、うちに泊まってもらって、私が書くそばからオーケストレーションをしてもらったり、あるいは、場合によっては、二曲、三曲くらい代作してもらうとか、そういうことをやってもらっていたんです。
その頃の思い出を武満はこう語る。
二人でふすま一枚へだてて仕事をするわけです。黛さんは、『武満君、じゃこれを清書してください』とか、『これをオーケストレーションしてください』と指示すると、向こうに行って自分の仕事をはじめるわけです。そうすると、鉛筆の音が休みなしにコンスタントに聞こえてくるわけです。ツツツツ・・・・・と。その速いのなんの。ぼくは驚きましたね。音楽というものはこんなに速く書くことができるものなんだろうかと思った。
ぼくなんか書いてる時間より、消しゴムで消している時間のほうが長いくらいなんです。しかし黛さんは消しゴムなんか使わず、休みなく書いているから、仕事も早い。ぼくが半分もいかないうちに、ふすまを開けて、『武満君、ぼくはもう終わったから、先に失礼して休ませてもらいます』といって寝てしまう。それからぼくはえんえんと一人で徹夜するわけです。
あれには参ったなあ。こんなにもちがうのかと、コンプレックスを感じました。これは本当に天才だなと思いました。ぼくは今でも彼を天才だと思っているんです。黛さんという人は、本気を出さないでも、仕事をパッパッパッと片づけていける人なんですね。だいたいふだんは自分の持っている能力の六〇%からせいぜい八〇%くらいまでしか使っていないんじゃないかしら。
だから、とてももったいない生き方をしていると思うんです。一〇〇%とはいわないでも、せめて九〇%でも使ってくれたら、余人をよせつけない、ものすごい作品を作れる人です。
いっぽう、黛はこう見ていた。
彼はアルバイトの仕事でも、自分の作品づくりと同じように、丁寧にいい仕事をする人なんです。だから、丸々代作を頼んだところなんか、代作として手離すにはもったいないくらい素晴らしい曲を書いてくれて、前後の私の書きとばした部分とのちがいが目立ってしまって困ったくらいです。
彼は大変な映画狂で、年に三百本も映画を見る人ですから、下らないプログラム・ピクチャーなんかも全部見ていて、どういうシーンにはどういう音楽をつければよいかというカン所を心得た人だったですから、アシスタントとしては最適でしたね。
武満にこの褒め言葉を聞かせると、
いやあ、とんでもない。黛さんがぼくに頼んだところなんか、ほんとは全部黛さんが自分で簡単にやってのけられるところなんです。一人でやったほうが早いし、上手くできるにきまっている。実際、ぼくは毎日黛さんの仕事をはたから見ていて、いやあ速いなあ、いやううまいなあと感心するばかりでした。ぼくは足手まといになっていただけなんです。それでもぼくに仕事を頼んでくれたのは、ぼくにお金をくれる口実だったんだと思います。芥川さんにしてもそうだったけど、ただじゃ本人も貰いにくいだろうと、気をつかってくれてたんですよ。
(写真 黛敏郎・桂木洋子夫妻)
ただ、これがあんまり美談化されているので、念のために申しあげておきますが、ぼくはあれはただで差し上げるつもりだったんですが、武満くんはすっかり恐縮してしまって、あのあと、ちゃんとお金をもってきたんです。そういうものをいただいているので、あんまり美談美談といわれると恥ずかしくなってしまうのです。
黛はそう言うが、武満はそれについて首をひねる。
お金なんかあげたかなあ、何しろお金がないから貸しピアノも借りられなかったんですから。もし持っていったとしても、雀の涙のような金額だったと思いますよ。ただ、貰いっぱなしというのは、あまりに心苦しいので、その頃大事にしていたインド音楽のレコードと天台声明のレコード、それに声明の楽譜を持っていって、これをお礼代わりに貰ってくださいと推しつけてきたことを覚えています。黛さんが後に『涅槃交響曲』を書くようになったのは、あのレコードと楽譜の影響もあったんじゃないかと秘かに思ってるんですけど。
ともかく、これを契機に、二人は親しく交際するようになり、武満は黛の映画音楽などの仕事を手伝うことになった。
あのころの映画音楽というのは、想像を絶するようなスピードで書くことが要求されたんです。武満くんには、うちに泊まってもらって、私が書くそばからオーケストレーションをしてもらったり、あるいは、場合によっては、二曲、三曲くらい代作してもらうとか、そういうことをやってもらっていたんです。
その頃の思い出を武満はこう語る。
二人でふすま一枚へだてて仕事をするわけです。黛さんは、『武満君、じゃこれを清書してください』とか、『これをオーケストレーションしてください』と指示すると、向こうに行って自分の仕事をはじめるわけです。そうすると、鉛筆の音が休みなしにコンスタントに聞こえてくるわけです。ツツツツ・・・・・と。その速いのなんの。ぼくは驚きましたね。音楽というものはこんなに速く書くことができるものなんだろうかと思った。
ぼくなんか書いてる時間より、消しゴムで消している時間のほうが長いくらいなんです。しかし黛さんは消しゴムなんか使わず、休みなく書いているから、仕事も早い。ぼくが半分もいかないうちに、ふすまを開けて、『武満君、ぼくはもう終わったから、先に失礼して休ませてもらいます』といって寝てしまう。それからぼくはえんえんと一人で徹夜するわけです。
あれには参ったなあ。こんなにもちがうのかと、コンプレックスを感じました。これは本当に天才だなと思いました。ぼくは今でも彼を天才だと思っているんです。黛さんという人は、本気を出さないでも、仕事をパッパッパッと片づけていける人なんですね。だいたいふだんは自分の持っている能力の六〇%からせいぜい八〇%くらいまでしか使っていないんじゃないかしら。
だから、とてももったいない生き方をしていると思うんです。一〇〇%とはいわないでも、せめて九〇%でも使ってくれたら、余人をよせつけない、ものすごい作品を作れる人です。
いっぽう、黛はこう見ていた。
彼はアルバイトの仕事でも、自分の作品づくりと同じように、丁寧にいい仕事をする人なんです。だから、丸々代作を頼んだところなんか、代作として手離すにはもったいないくらい素晴らしい曲を書いてくれて、前後の私の書きとばした部分とのちがいが目立ってしまって困ったくらいです。
彼は大変な映画狂で、年に三百本も映画を見る人ですから、下らないプログラム・ピクチャーなんかも全部見ていて、どういうシーンにはどういう音楽をつければよいかというカン所を心得た人だったですから、アシスタントとしては最適でしたね。
武満にこの褒め言葉を聞かせると、
いやあ、とんでもない。黛さんがぼくに頼んだところなんか、ほんとは全部黛さんが自分で簡単にやってのけられるところなんです。一人でやったほうが早いし、上手くできるにきまっている。実際、ぼくは毎日黛さんの仕事をはたから見ていて、いやあ速いなあ、いやううまいなあと感心するばかりでした。ぼくは足手まといになっていただけなんです。それでもぼくに仕事を頼んでくれたのは、ぼくにお金をくれる口実だったんだと思います。芥川さんにしてもそうだったけど、ただじゃ本人も貰いにくいだろうと、気をつかってくれてたんですよ。
(写真 黛敏郎・桂木洋子夫妻)
そういう一面もあったことは否定できないだろう。そのころ黛は若い貧しい芸術家に、進んでチャンスを与え、財政的な支援をしていた。
涅槃交響曲の初演のオーケストラはN響だった。当時、岩城宏之はN響の研究生で副指揮者という立場にあった。月給は手取り四千五百円という本当の駆け出しだった。まだフル編成のN響を指揮したことは一度しかなかった。
その岩城を、涅槃交響曲の指揮者として黛が指名してきた。N響では、指揮をすると月給のほかに特別手当がつくことになっていたが、涅槃交響曲の場合、それはわずか六百円だった。そういうことを知っていた黛は、『ありがとう』といって、二万円だか三万円だかが入った封筒を渡してくれたという。
しかし黛が武満の音楽的感性を高く買っていたことも、偽りのない事実である。黛が語る次のエピソードでもそれが分かる。
涅槃交響曲を書いていたとき、ぼくはずいぶん悩み、迷ったところがあるんです。第四楽章で、まったく同じハーモニーが、オーケストレーションを変えるだけで、延々と繰り返されるところがあるんです。スコアにしても十ページ近くもつづく。いくらオーケストレーションを変えても、同じハーモニーをこんなにつづけたら単調で退屈でどうにもならないんじゃないかと不安になって、武満君に家にきてもらって、スコアを見てもらったんです。
やめようかどうしようか迷っているというと、武満君が、『黛さん、これは絶対大丈夫です。絶対このままがいいです』と、非常に強くいってくれたんです。それで迷いがてふっ切れそのままやったんですが、やはりそれがいちばんよかったと思って、今でも武満君のあの強い助言に感謝しているんです。
周囲の友人たちはみな、なんとか武満が食えるようにしてやろうと気をつかっていた。秋山邦晴は語る。
たとえば、新日本放送、いまの毎日放送ですけど、そこの音楽プロデューサーをやっていた藁科雅美さんに頼んで、『朝の歌』という番組をやらせてもらったりしました。これは毎朝同じ歌を一か月間にわたって放送するというもので、結構いい報酬をもらいました。
詩はお前が書いてくれといわれて、ぼくが書いたんですけど、『さようなら』という、とても甘いリリカルな曲になりました。武満は、実はそういう叙情的な曲もうまいんです。ぼくの作詞料が一万何千円かで、こんなに貰えるのかと驚いた記憶があるんですが、武満も相当貰ったはずです。
これが機縁になって、一連のラジオドラマの仕事とか、ミュージック・コンクレートの仕事を新日本放送でやるようになるんです。いまでは想像もできないことですが、シェーンベルクの『期待』という音楽ドラマをやっぱり藁科さんのプロデュースでやったことがあります。台詞と音楽が交錯していくドラマなんですが、音楽はレコードを使って、出演は浅香さんで、日本語の台詞はぼくが書いて、譜面を見ながらキューを出すのが武満でと、ぼくらだけでやってしまったんです。
涅槃交響曲の初演のオーケストラはN響だった。当時、岩城宏之はN響の研究生で副指揮者という立場にあった。月給は手取り四千五百円という本当の駆け出しだった。まだフル編成のN響を指揮したことは一度しかなかった。
その岩城を、涅槃交響曲の指揮者として黛が指名してきた。N響では、指揮をすると月給のほかに特別手当がつくことになっていたが、涅槃交響曲の場合、それはわずか六百円だった。そういうことを知っていた黛は、『ありがとう』といって、二万円だか三万円だかが入った封筒を渡してくれたという。
しかし黛が武満の音楽的感性を高く買っていたことも、偽りのない事実である。黛が語る次のエピソードでもそれが分かる。
涅槃交響曲を書いていたとき、ぼくはずいぶん悩み、迷ったところがあるんです。第四楽章で、まったく同じハーモニーが、オーケストレーションを変えるだけで、延々と繰り返されるところがあるんです。スコアにしても十ページ近くもつづく。いくらオーケストレーションを変えても、同じハーモニーをこんなにつづけたら単調で退屈でどうにもならないんじゃないかと不安になって、武満君に家にきてもらって、スコアを見てもらったんです。
やめようかどうしようか迷っているというと、武満君が、『黛さん、これは絶対大丈夫です。絶対このままがいいです』と、非常に強くいってくれたんです。それで迷いがてふっ切れそのままやったんですが、やはりそれがいちばんよかったと思って、今でも武満君のあの強い助言に感謝しているんです。
周囲の友人たちはみな、なんとか武満が食えるようにしてやろうと気をつかっていた。秋山邦晴は語る。
たとえば、新日本放送、いまの毎日放送ですけど、そこの音楽プロデューサーをやっていた藁科雅美さんに頼んで、『朝の歌』という番組をやらせてもらったりしました。これは毎朝同じ歌を一か月間にわたって放送するというもので、結構いい報酬をもらいました。
詩はお前が書いてくれといわれて、ぼくが書いたんですけど、『さようなら』という、とても甘いリリカルな曲になりました。武満は、実はそういう叙情的な曲もうまいんです。ぼくの作詞料が一万何千円かで、こんなに貰えるのかと驚いた記憶があるんですが、武満も相当貰ったはずです。
これが機縁になって、一連のラジオドラマの仕事とか、ミュージック・コンクレートの仕事を新日本放送でやるようになるんです。いまでは想像もできないことですが、シェーンベルクの『期待』という音楽ドラマをやっぱり藁科さんのプロデュースでやったことがあります。台詞と音楽が交錯していくドラマなんですが、音楽はレコードを使って、出演は浅香さんで、日本語の台詞はぼくが書いて、譜面を見ながらキューを出すのが武満でと、ぼくらだけでやってしまったんです。
そういう仕事もあったかと思うと、早坂さんのところに、北海道の美幌町から町歌を作ってくれと依頼があって、早坂さんが、きみやったらどうだといって、武満にまわしてきたことがありました。美幌町が武満徹作曲の町歌をもつなんて名誉をになうことになったのも、武満のあのころの貧乏のおかげなんです。
このころなんでもやっていた仕事の一部として、鈴木章治とリズムエースとの仕事なんていうのもある。武満はこう語る。
秋山が紹介してくれたTBSラジオの『こだまが歌う』という番組があって、一連のポップスやジャズのスタンダードを編曲してオーケストラに演奏させるんです。そのときピアノを弾いたのが、鈴木章治のお兄さんなんです。その関係で鈴木章治さんとも親しくなり、リズム・エースのアレンジをやったり、ジャズの曲を書いたりもしました。
秋山がもうひとつエピソードを語る。
武満にもう少し継続的な仕事はないかと、武満と鈴木と三人で大映の多摩川撮影所をたずねたことがあるんです。そこの所長とぼくのおやじが親しかったもんで、仕事を頼みに行ったんです。それでいろいろ話を聞いてもらったら、その人が、『ところでどこの音楽大学出られたんですか』と聞くわけね。『いや、ぼくは中学しか出ていません』と武満が答えると、『それは無理かもしれません』と言われて、三人ショボンとして撮影所の中を歩いていると、そのころやっぱり早坂さんのアシスタントをゃっていた斎藤さんという作曲家に会った。
『いま困ってるんですよ』。木村恵吾監督で京マチ子主演の『牝犬』という映画の音楽の録音で、オケもそろって録音が始められる状態なのに、頼んでいたピアニストの藤田弓子さんがこないというんです。それで、『武満さん、代わりにやってくれない』というわけです。
だけど、武満のピアノといったら、ぼくらみんな知っていたけど、自分の曲をゆっくり弾く程度で、藤田さんに頼むような曲を初見で弾くなんてできるはずないんですよ。そのとき一緒にいた鈴木なら、井口愛子の門下生だから、それくらい簡単にできたと思うんだけど、彼はそういうことをしない人なんですね。
結局、武満が、『じゃあ、やってみるか』といって、ピアノの前に座ったんです。まずリハーサルで、映画を映しながらオーケストラの演奏がはじまったら、武満は譜面と画面を見ているきりで、全然手が動かないんですよ。これは大丈夫なんだろうかと本当に心配になりました。
ところが武満は、斎藤さんが、『武満さん、大丈夫ですか。本番いっていいですか』と声をかけると、『ハイ』なんていってるんです。それで、本番になったら、本当に弾いちゃったんです。あれを見てて、武満のガッツというか、とにかくどんな仕事でも引き受ければやりとげちゃうというところはほんとにすごいと思いましたね。
しかし、本当にうまくいったのか、ぼくは心配になって、封切日に朝から下北沢の映画館に行って第一回目の上映を見ましたよ。そしたら、ほんとに大オーケストラをバックにちゃんと弾いてるんでビックリしました。彼がオーケストラをバックにピアノを弾いたなんて、後にも先にもあれ一回きりのはずです。
このころなんでもやっていた仕事の一部として、鈴木章治とリズムエースとの仕事なんていうのもある。武満はこう語る。
秋山が紹介してくれたTBSラジオの『こだまが歌う』という番組があって、一連のポップスやジャズのスタンダードを編曲してオーケストラに演奏させるんです。そのときピアノを弾いたのが、鈴木章治のお兄さんなんです。その関係で鈴木章治さんとも親しくなり、リズム・エースのアレンジをやったり、ジャズの曲を書いたりもしました。
秋山がもうひとつエピソードを語る。
武満にもう少し継続的な仕事はないかと、武満と鈴木と三人で大映の多摩川撮影所をたずねたことがあるんです。そこの所長とぼくのおやじが親しかったもんで、仕事を頼みに行ったんです。それでいろいろ話を聞いてもらったら、その人が、『ところでどこの音楽大学出られたんですか』と聞くわけね。『いや、ぼくは中学しか出ていません』と武満が答えると、『それは無理かもしれません』と言われて、三人ショボンとして撮影所の中を歩いていると、そのころやっぱり早坂さんのアシスタントをゃっていた斎藤さんという作曲家に会った。
『いま困ってるんですよ』。木村恵吾監督で京マチ子主演の『牝犬』という映画の音楽の録音で、オケもそろって録音が始められる状態なのに、頼んでいたピアニストの藤田弓子さんがこないというんです。それで、『武満さん、代わりにやってくれない』というわけです。
だけど、武満のピアノといったら、ぼくらみんな知っていたけど、自分の曲をゆっくり弾く程度で、藤田さんに頼むような曲を初見で弾くなんてできるはずないんですよ。そのとき一緒にいた鈴木なら、井口愛子の門下生だから、それくらい簡単にできたと思うんだけど、彼はそういうことをしない人なんですね。
結局、武満が、『じゃあ、やってみるか』といって、ピアノの前に座ったんです。まずリハーサルで、映画を映しながらオーケストラの演奏がはじまったら、武満は譜面と画面を見ているきりで、全然手が動かないんですよ。これは大丈夫なんだろうかと本当に心配になりました。
ところが武満は、斎藤さんが、『武満さん、大丈夫ですか。本番いっていいですか』と声をかけると、『ハイ』なんていってるんです。それで、本番になったら、本当に弾いちゃったんです。あれを見てて、武満のガッツというか、とにかくどんな仕事でも引き受ければやりとげちゃうというところはほんとにすごいと思いましたね。
しかし、本当にうまくいったのか、ぼくは心配になって、封切日に朝から下北沢の映画館に行って第一回目の上映を見ましたよ。そしたら、ほんとに大オーケストラをバックにちゃんと弾いてるんでビックリしました。彼がオーケストラをバックにピアノを弾いたなんて、後にも先にもあれ一回きりのはずです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
SILENT GARDEN 武満徹 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
SILENT GARDEN 武満徹 のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37865人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90065人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人