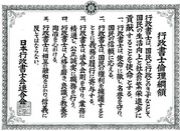【情報トピックス<本部用>】2011.1.11 付 (政策)
※ 周辺分野も含む。一部項目に過日情報と重複可能性あり。
◆内閣府 行政救済制度検討チーム(第4回) (12月14日開催)
・内山政務官「そうしましたら、各省庁に対しまして、本調査票(下記アドレス参照。)の作成を依頼し、不服申立前置(不服申立前置とは、行政上の不服申立てを出訴前に義務付けることをいうものとします。)の全面的見直しに向け、実態調査、把握を行いたいと思います。
なお、不服申立前置の全面的見直しは行政不服申立制度改革方針に基づき、ワーキンググループを開催して行うこととしておりますが、ワーキンググループの詳細については後日、別途チームにお諮りをいたします。
それでは、最後に次回日程について、事務方から説明をいたします。」
・小峯室長「次回の日程ですが、第5回の会合です。日時は平成23 年1月26 日水曜日になります。時間は18〜20 時となります。会場は官邸2階の小ホールになります。議題は本日御議論いただいた以外の審議の迅速化、地方公共団体における措置、代理人制度などについてでございます。以上です。」
・不服申立前置の全面的見直しに関する調査票(案)
http://
・第4回(12月14日開催)議事録
http://
・行政求愛制度検討チーム「全部資料、議事録」サイト
http://
【参考】11月1日会議提出資料
・行政不服審査法の改正に関する「国民・職員の声」
http://
・「行政不服審査法の改正の方向性について」に対する各省庁の意見(PDF:544KB)
http://
・「行政不服審査法の改正の方向性について」に対する参集者の意見(PDF:489KB)
http://
◆経済産業省 「新成長戦略の実現に向けた経済産業省の取組(進捗と今後の課題)」 1月5日
「新成長戦略」実現に向けて これまでの進展と今後の課題
1.国際競争を勝ち抜く事業活動の拠点としての飛躍的な魅力向上
2.新たに成長を主導する戦略分野
−高機能・単品売り型産業から、システム売り/課題解決型/文化付加価値型、の産業へ−
3.地域経済・中小企業の活性化
−多様性に対応した支援策の展開−
4.「国を開く」内外一体の経済産業政策の展開
5.「技術で勝って、事業でも勝つ」事業戦略への転換
−「技術を価値につなげる」研究開発と国際標準戦略の推進−
6.事業仕分け・行政事業レビューの徹底・横展開を通じた事業の選択と集中
http://
◆日本中古自動車販売協会連合会、2013年めど一般社団法人化 将来の公益法人化も視野 (1月5日)
・日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連、澤田稔会長)は2013年をめどに一般社団法人への移行を目指す。すでに、JU中販連と中古車オークション(AA)事業を手がける日本中古自動車販売商工組合連合会(JU中商連、澤田稔理事長)などグループ各事業の公益性を精査、移行申請へのガイドライン作りに乗り出した。また一方で、公益法人への移行も検討する。方針として、現組織とは別に一般社団法人を設立し法人格を取得、さらにその後に公益社団法人へ移行することを模索していく。
08年12月に施行された新公益法人制度では、その5年後の13年11月末までに公益社団法人の認定、もしくは一般社団法人への移行認可を受けなければ自動的に解散と見なされる。このことから、JU中販連では一般社団法人への移行申請を早い段階で行う。
すでにコンサルタント機関とともに、移行申請に向け各事業の公益性の調査を開始した。グループの事業活動としてはAA事業のほか、小売り事業での消費者保護、共済事業を始めとした会員販売店を対象とする事業など共益性の高い事業がすでに多くの割合を占めていると判断。また今後、「中古自動車販売士制度」などさらに公益性の高い事業展開を計画している。
JU中販連では、一般社団法人化を目指す新組織を設立し、まず、その組織での法人格取得を目指す。その後、その組織の公益社団法人への移行可能性を探る。
澤田会長は「JU組織は約40年にわたり消費者保護を基調とした純粋な公益事業を行ってきたと自負している。新たに公益事業に特化した一般社団法人を設立するが、このままでは公益社団法人に認定されることは難しい。しかし、先になるだろうが将来的に公益社団法人に移行することを引き続き検討し、我々に課せられた責務を果たしていきたい」としている。
http://
≪「建設産業戦略の基本方針」について≫
◆馬淵国交相、「建設産業戦略の基本方針」をきょう7日に発表 (1月7日)
地域建設業の再生方策など盛る
・馬淵澄夫国土交通相はきょう7日、地域建設業の再生方策などを盛り込んだ建設業再生戦略の基本方針を発表する。6日に開いた「建設産業戦略会議」(座長・大森文彦東洋大学教授)の提言を踏まえたもので、建設産業の構造改革に踏み込んだ内容になるとみられる。戦略会議は入札契約制度改革を主体とした中間報告を3月にまとめた上で、6月に「建設業再生戦略」として全体像を提示する方針だ。
馬淵国交相は戦略会議の冒頭、「公共投資が減少し地域の疲弊が進む中、建設産業を所管する役所として取り組まなければならない課題にわれわれは目を背けていなかったか。不作為による無責任の連鎖は最も恥ずべきことであり、それを断ち切らなければならない」と強調した。
その上で「産業保護やバラマキの発想ではなく、低成長時代の建設産業をどのような方向に進めるべきか、強制はせずにしっかりと道筋を示すことが重要だ」と訴えた。
非公開で行われた会合では、事務局が示した基本方針案に対して、委員から「市場競争と公平性のバランスを確保することが重要」「人材確保・育成の観点でもっと踏み込んだ議論が必要」といった声が上がったが、最終的には大筋で了承されたという。基本方針はきょう7日の定例会見で馬淵国交相が正式に発表する見込みだ。
建設産業戦略会議は、地域の担い手となっている建設業の再生を軸としつつ、建設産業全体の在り方を検討する場として、馬淵国交相の肝いりで2010年12月に設置された。過去2回の会合で、馬淵国交相は「地方の建設産業に対して国が一定程度関与していかなければならない」「(公共投資が)地域の末端に行き渡る形でどのように再分配機能を果たしていくかが重要」などと発言している。
http://
◆国交省 「建設産業の再生と発展のための方策に関する当面の基本方針について」 (1月7日)
・ 国土交通省より、『建設産業の再生と発展のための方策に関する当面の基本 方針について』が公表されました。
http://
◆「建設産業の再生と発展のための方策に関する当面の基本方針」に対するコメントを発表
・ 1月7日、国土交通省建設産業戦略会議において取りまとめられた「建設産業の再生と発展のための方策に関する当面の基本方針」が公表されました。これに対して、当協会は、(社)日本建設業団体連合会・(社)日本土木工業協会とともに、コメントを発表しました。
http://
◆国の規制「仕分け」3月実施…薬ネット販売など
政府の行政刷新会議(議長・菅首相)は、国の規制や制度の是非を公開の場で議論する「規制仕分け」を3月にも実施する方針を固めた。
医療、農業分野などで市民生活や経済活動の妨げとなっている規制などを対象とする予定だ。
同会議の規制・制度改革分科会は、「環境」「医療」「農林・地域活性化」の3分野の作業部会で、計約150項目の規制見直しを進めている。月内に報告書をまとめ、省庁側との調整を経て3月中に閣議決定する予定だ。
これに対し、省庁側の抵抗が予想されるため、「規制仕分け」の構想が浮上してきた。同会議では、行政の無駄遣いを洗い出すために実施した「事業仕分け」の手法を使って規制撤廃に慎重な各省庁の抵抗を抑え込み、閣議決定につなげる考えだ。
対象として想定されているのは、市販薬のインターネット販売に関する規制などだ。厚生労働省は「対面販売のように副作用の説明ができない」とし、2009年6月から市販薬のネット販売を原則的に禁止したが、同分科会は報告書でネット販売を認める方向だ。この問題では、蓮舫行政刷新相も「安全性を確保して答えを出すことは、規制・制度改革の大きな意味合いがある」としている。(2011年1月7日 読売新聞)
http://
◆政府は28日、情報公開法の改正案を次期通常国会に提出する方針を固めた。(12月29日)
改正案は、開示までの期間短縮や開示範囲の拡大などが柱だ。情報公開制度の抜本的見直しは、2001年4月の同法施行後、初めてとなる。菅首相は28日の閣議で改正案の取りまとめを指示。内閣官房は同日、法案作成を担当する「情報公開法改正準備室」を設置した。
改正案には、〈1〉請求から開示までの期間を「原則30日以内」から「土日祝日を除き14日以内」に短縮〈2〉請求に必要な手数料(1件300円)を原則廃止〈3〉政府系公益法人も公開対象に追加〈4〉役職名だけ開示していた公務員の氏名の原則公開――などを盛り込む。同法について、「国民の『知る権利』を保障するためのもの」であるとの理念も明記する。
http://
◆近畿経済産業局「知的資産経営報告書の評価・認証手法に関する調査研究 報告書」(平成22年12月)
・知的資産
特許やノウハウなどの「知的財産」だけでなく、組織力、人材、顧客とのネットワークなど企業の「強み」となる目に見えない資産の総称。
・知的資産経営
企業に固有の知的資産を「認識」し、有効に組み合わせたバリューチェーンを認識し、それを意識的に「管理・活用」し、持続的な利益を確保する経営。
<図表 I-1 知的資産経営の考え方>
http://
≪ブログ拾い読み≫
【[刑事判例】弁護士資格等がない者らが、ビルの所有者から委託を受けて、そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行った行為について、弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例。
・最高裁第一小法廷平成22年7月20日決定ですが、判例時報2093号161頁以下に掲載されていました。
弁護士法72条における「その他一般の法律事件」については、判例時報のコメントでも紹介されているように、「事件性」を要するかどうかに争いがあり、従来の刑事裁判例では、事件性を必要としつつも緩やかに解していたところ、法務省が平成15年に示した見解で、争いや疑義が具体化または顕在化していることが必要という、事件性について厳格に解するかのような立場が示されたことから、グレー感が強まっていたような状況にはあったと言えると思われます。そこで示されたのが本決定における判断で、最高裁は、本件の事案に即しつつ、「交渉において解決しなければならない法的紛議が生じることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らか」として、その他一般の法律事件に該当するという判断を示しています。
判例時報のコメントでは、本決定について、
「本決定のこのような判示は、事件性のような要件を全く必要としないとする立場には立っておらず、争いや疑義が具体化または顕在化していることまでは要しないとしても、事件性必要説に親和的な立場と理解できるように思われる。」
と評価していますが、事件性を要するとしつつも上記のような法務省見解ほど厳格な事件性は要しないと見ていることは明らかで、今後、事件性についてどこで線引されるかについては、事案の集積の中で徐々に明らかにされるべきものと考えられているのではないかという印象を受けます。グレー感はなかなか払拭できませんね。
72条の問題は、例えば、企業で働く法務部員が、有償サービスとして、子会社や関連会社に関する法務をどこまで担当できるかといったことを考える上で、その解釈の影響は小さくなく、今後の議論の中で、この決定が参考にされる機会が出てくるのではないかと思われます。
http://
≪ブログ拾い読み≫
・昨今、行書の試験は、法科大学院の生徒さんが、新司法の予備試験のすべり止め対策で、受けていて、彼らが択一のみで180点オーバーをされて合格されてるのを耳にしてます。
・またボク自身が業界に精通する親友から耳にするに新司法試験や弁護士試験あるいは司法書士試験を受ける方々が行政書士試験を腕試し的に受験されているようですので、主催者側も合格率調整の観点から民法や行政法は司法書士レベル以上になってきていると聞きます。
(以上)
※ 周辺分野も含む。一部項目に過日情報と重複可能性あり。
◆内閣府 行政救済制度検討チーム(第4回) (12月14日開催)
・内山政務官「そうしましたら、各省庁に対しまして、本調査票(下記アドレス参照。)の作成を依頼し、不服申立前置(不服申立前置とは、行政上の不服申立てを出訴前に義務付けることをいうものとします。)の全面的見直しに向け、実態調査、把握を行いたいと思います。
なお、不服申立前置の全面的見直しは行政不服申立制度改革方針に基づき、ワーキンググループを開催して行うこととしておりますが、ワーキンググループの詳細については後日、別途チームにお諮りをいたします。
それでは、最後に次回日程について、事務方から説明をいたします。」
・小峯室長「次回の日程ですが、第5回の会合です。日時は平成23 年1月26 日水曜日になります。時間は18〜20 時となります。会場は官邸2階の小ホールになります。議題は本日御議論いただいた以外の審議の迅速化、地方公共団体における措置、代理人制度などについてでございます。以上です。」
・不服申立前置の全面的見直しに関する調査票(案)
http://
・第4回(12月14日開催)議事録
http://
・行政求愛制度検討チーム「全部資料、議事録」サイト
http://
【参考】11月1日会議提出資料
・行政不服審査法の改正に関する「国民・職員の声」
http://
・「行政不服審査法の改正の方向性について」に対する各省庁の意見(PDF:544KB)
http://
・「行政不服審査法の改正の方向性について」に対する参集者の意見(PDF:489KB)
http://
◆経済産業省 「新成長戦略の実現に向けた経済産業省の取組(進捗と今後の課題)」 1月5日
「新成長戦略」実現に向けて これまでの進展と今後の課題
1.国際競争を勝ち抜く事業活動の拠点としての飛躍的な魅力向上
2.新たに成長を主導する戦略分野
−高機能・単品売り型産業から、システム売り/課題解決型/文化付加価値型、の産業へ−
3.地域経済・中小企業の活性化
−多様性に対応した支援策の展開−
4.「国を開く」内外一体の経済産業政策の展開
5.「技術で勝って、事業でも勝つ」事業戦略への転換
−「技術を価値につなげる」研究開発と国際標準戦略の推進−
6.事業仕分け・行政事業レビューの徹底・横展開を通じた事業の選択と集中
http://
◆日本中古自動車販売協会連合会、2013年めど一般社団法人化 将来の公益法人化も視野 (1月5日)
・日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連、澤田稔会長)は2013年をめどに一般社団法人への移行を目指す。すでに、JU中販連と中古車オークション(AA)事業を手がける日本中古自動車販売商工組合連合会(JU中商連、澤田稔理事長)などグループ各事業の公益性を精査、移行申請へのガイドライン作りに乗り出した。また一方で、公益法人への移行も検討する。方針として、現組織とは別に一般社団法人を設立し法人格を取得、さらにその後に公益社団法人へ移行することを模索していく。
08年12月に施行された新公益法人制度では、その5年後の13年11月末までに公益社団法人の認定、もしくは一般社団法人への移行認可を受けなければ自動的に解散と見なされる。このことから、JU中販連では一般社団法人への移行申請を早い段階で行う。
すでにコンサルタント機関とともに、移行申請に向け各事業の公益性の調査を開始した。グループの事業活動としてはAA事業のほか、小売り事業での消費者保護、共済事業を始めとした会員販売店を対象とする事業など共益性の高い事業がすでに多くの割合を占めていると判断。また今後、「中古自動車販売士制度」などさらに公益性の高い事業展開を計画している。
JU中販連では、一般社団法人化を目指す新組織を設立し、まず、その組織での法人格取得を目指す。その後、その組織の公益社団法人への移行可能性を探る。
澤田会長は「JU組織は約40年にわたり消費者保護を基調とした純粋な公益事業を行ってきたと自負している。新たに公益事業に特化した一般社団法人を設立するが、このままでは公益社団法人に認定されることは難しい。しかし、先になるだろうが将来的に公益社団法人に移行することを引き続き検討し、我々に課せられた責務を果たしていきたい」としている。
http://
≪「建設産業戦略の基本方針」について≫
◆馬淵国交相、「建設産業戦略の基本方針」をきょう7日に発表 (1月7日)
地域建設業の再生方策など盛る
・馬淵澄夫国土交通相はきょう7日、地域建設業の再生方策などを盛り込んだ建設業再生戦略の基本方針を発表する。6日に開いた「建設産業戦略会議」(座長・大森文彦東洋大学教授)の提言を踏まえたもので、建設産業の構造改革に踏み込んだ内容になるとみられる。戦略会議は入札契約制度改革を主体とした中間報告を3月にまとめた上で、6月に「建設業再生戦略」として全体像を提示する方針だ。
馬淵国交相は戦略会議の冒頭、「公共投資が減少し地域の疲弊が進む中、建設産業を所管する役所として取り組まなければならない課題にわれわれは目を背けていなかったか。不作為による無責任の連鎖は最も恥ずべきことであり、それを断ち切らなければならない」と強調した。
その上で「産業保護やバラマキの発想ではなく、低成長時代の建設産業をどのような方向に進めるべきか、強制はせずにしっかりと道筋を示すことが重要だ」と訴えた。
非公開で行われた会合では、事務局が示した基本方針案に対して、委員から「市場競争と公平性のバランスを確保することが重要」「人材確保・育成の観点でもっと踏み込んだ議論が必要」といった声が上がったが、最終的には大筋で了承されたという。基本方針はきょう7日の定例会見で馬淵国交相が正式に発表する見込みだ。
建設産業戦略会議は、地域の担い手となっている建設業の再生を軸としつつ、建設産業全体の在り方を検討する場として、馬淵国交相の肝いりで2010年12月に設置された。過去2回の会合で、馬淵国交相は「地方の建設産業に対して国が一定程度関与していかなければならない」「(公共投資が)地域の末端に行き渡る形でどのように再分配機能を果たしていくかが重要」などと発言している。
http://
◆国交省 「建設産業の再生と発展のための方策に関する当面の基本方針について」 (1月7日)
・ 国土交通省より、『建設産業の再生と発展のための方策に関する当面の基本 方針について』が公表されました。
http://
◆「建設産業の再生と発展のための方策に関する当面の基本方針」に対するコメントを発表
・ 1月7日、国土交通省建設産業戦略会議において取りまとめられた「建設産業の再生と発展のための方策に関する当面の基本方針」が公表されました。これに対して、当協会は、(社)日本建設業団体連合会・(社)日本土木工業協会とともに、コメントを発表しました。
http://
◆国の規制「仕分け」3月実施…薬ネット販売など
政府の行政刷新会議(議長・菅首相)は、国の規制や制度の是非を公開の場で議論する「規制仕分け」を3月にも実施する方針を固めた。
医療、農業分野などで市民生活や経済活動の妨げとなっている規制などを対象とする予定だ。
同会議の規制・制度改革分科会は、「環境」「医療」「農林・地域活性化」の3分野の作業部会で、計約150項目の規制見直しを進めている。月内に報告書をまとめ、省庁側との調整を経て3月中に閣議決定する予定だ。
これに対し、省庁側の抵抗が予想されるため、「規制仕分け」の構想が浮上してきた。同会議では、行政の無駄遣いを洗い出すために実施した「事業仕分け」の手法を使って規制撤廃に慎重な各省庁の抵抗を抑え込み、閣議決定につなげる考えだ。
対象として想定されているのは、市販薬のインターネット販売に関する規制などだ。厚生労働省は「対面販売のように副作用の説明ができない」とし、2009年6月から市販薬のネット販売を原則的に禁止したが、同分科会は報告書でネット販売を認める方向だ。この問題では、蓮舫行政刷新相も「安全性を確保して答えを出すことは、規制・制度改革の大きな意味合いがある」としている。(2011年1月7日 読売新聞)
http://
◆政府は28日、情報公開法の改正案を次期通常国会に提出する方針を固めた。(12月29日)
改正案は、開示までの期間短縮や開示範囲の拡大などが柱だ。情報公開制度の抜本的見直しは、2001年4月の同法施行後、初めてとなる。菅首相は28日の閣議で改正案の取りまとめを指示。内閣官房は同日、法案作成を担当する「情報公開法改正準備室」を設置した。
改正案には、〈1〉請求から開示までの期間を「原則30日以内」から「土日祝日を除き14日以内」に短縮〈2〉請求に必要な手数料(1件300円)を原則廃止〈3〉政府系公益法人も公開対象に追加〈4〉役職名だけ開示していた公務員の氏名の原則公開――などを盛り込む。同法について、「国民の『知る権利』を保障するためのもの」であるとの理念も明記する。
http://
◆近畿経済産業局「知的資産経営報告書の評価・認証手法に関する調査研究 報告書」(平成22年12月)
・知的資産
特許やノウハウなどの「知的財産」だけでなく、組織力、人材、顧客とのネットワークなど企業の「強み」となる目に見えない資産の総称。
・知的資産経営
企業に固有の知的資産を「認識」し、有効に組み合わせたバリューチェーンを認識し、それを意識的に「管理・活用」し、持続的な利益を確保する経営。
<図表 I-1 知的資産経営の考え方>
http://
≪ブログ拾い読み≫
【[刑事判例】弁護士資格等がない者らが、ビルの所有者から委託を受けて、そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行った行為について、弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例。
・最高裁第一小法廷平成22年7月20日決定ですが、判例時報2093号161頁以下に掲載されていました。
弁護士法72条における「その他一般の法律事件」については、判例時報のコメントでも紹介されているように、「事件性」を要するかどうかに争いがあり、従来の刑事裁判例では、事件性を必要としつつも緩やかに解していたところ、法務省が平成15年に示した見解で、争いや疑義が具体化または顕在化していることが必要という、事件性について厳格に解するかのような立場が示されたことから、グレー感が強まっていたような状況にはあったと言えると思われます。そこで示されたのが本決定における判断で、最高裁は、本件の事案に即しつつ、「交渉において解決しなければならない法的紛議が生じることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らか」として、その他一般の法律事件に該当するという判断を示しています。
判例時報のコメントでは、本決定について、
「本決定のこのような判示は、事件性のような要件を全く必要としないとする立場には立っておらず、争いや疑義が具体化または顕在化していることまでは要しないとしても、事件性必要説に親和的な立場と理解できるように思われる。」
と評価していますが、事件性を要するとしつつも上記のような法務省見解ほど厳格な事件性は要しないと見ていることは明らかで、今後、事件性についてどこで線引されるかについては、事案の集積の中で徐々に明らかにされるべきものと考えられているのではないかという印象を受けます。グレー感はなかなか払拭できませんね。
72条の問題は、例えば、企業で働く法務部員が、有償サービスとして、子会社や関連会社に関する法務をどこまで担当できるかといったことを考える上で、その解釈の影響は小さくなく、今後の議論の中で、この決定が参考にされる機会が出てくるのではないかと思われます。
http://
≪ブログ拾い読み≫
・昨今、行書の試験は、法科大学院の生徒さんが、新司法の予備試験のすべり止め対策で、受けていて、彼らが択一のみで180点オーバーをされて合格されてるのを耳にしてます。
・またボク自身が業界に精通する親友から耳にするに新司法試験や弁護士試験あるいは司法書士試験を受ける方々が行政書士試験を腕試し的に受験されているようですので、主催者側も合格率調整の観点から民法や行政法は司法書士レベル以上になってきていると聞きます。
(以上)
|
|
|
|
|
|
|
|
MIXI 行政書士連合会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-