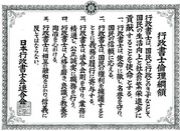さる1月22日開催の日本行政書士会連合会理事会において
協議事項として提案された平成21年度 事業計画基本方針(案)です。
議案ではないため、今後各方面の意見を取り付けながら
修正も行われることでしょうが、ここでは読みやすいように
段落等を手直しして掲載しております。
??????????????????????????????????????????????????
平成21年度 事業計画基本方針(案)
ー国民の信頼を基盤に、国民の利便に資する制度構築に向けてー
米国経済の減速、世界的な為替市場、金融市場の混乱が日本経済を直撃し、
景況の悪化、雇用不安と行政書士のクライアントである国民、事業者が
かつてない試練の時代を迎えております。
「行政と国民のパイプ役」、「まちの法律家」である行政書士を擁する
行政書士会(以下「単位会」という。)、日本行政書士会連合会
(以下「日行連」という。)にとっても、昨今の激変への対応が
求められております。
司法制度改革については、法科大学院による法曹養成を重ね、
さらに平成21年5月から裁判員制度が導入されるに及んで、
諸整備の状況が一般国民の視野に入ってきました。
司法制度改革審議会意見書(平成13年)に示された一連の司法制度改革
(隣接法律専門職種を含む)の完成期に入ってきたと言っても
過言ではありません。
内閣府規制改革会議から三次にわたり答申が行われ、「法務・資格分野」
に関する提言には、行政書士を含む隣接法律専門職種に、サービスを
利用する国民の視点にたち、利便性や提供されるサービスの向上に
対する期待が重ねて記されております。
以上を踏まえ、法1条に掲げる国民の利便に資する行政書士の育成、
行政書士制度の構築が急務です。また、「国民の利便」のためには、
「国民の信頼」が基盤をなすことは言を待ちません。
このような視点から、本年度は総花的に重点項目を示すことなく、
大きく次の3点に紋り、限りある会の資源を「選択と集中」の
もと投下し、ゆるぎない行政書士制度の地歩を固めるべく
邁進してまいります。
1.行政不服申立て代理の実現に向けて
平成20年12月に内閣府規制改革会議が発表した
「規制改革推進のための第三次答申」で、
「行政機関に提出する許認可等の申請書類の作成・提出を行い申請
内容を熟知する行政書士が、依頼者の意向に基づきそれらに関わる
行政不服審査申立も含め一貫して取り扱えるようになれば、
行政不服審査制度の活用が促進され、国民の利便性の向上が図られる
との見解もある。」と答申されています。
昨年の法改正で明確化された許認可等における聴聞・弁明の機会の
付与手続代理の延長線上に行政不服申立て代理業務があり、
十分な能力担保を伴って当該業務に参入することを、
依頼者である国民、事業者は期待するところです。
そのためには行政書士法の創設的改正が必要となり、
その実現を目指します。
2.長期会費未納会員に対する登録抹消の実現に向けて
国民の信頼を獲得するためには、業務能力とともに、
そのコンプライアンスが
極めて重要です。厳格な登録入会・抹消退会制度に関与する単位会、
日行連が行う自律、自助の事業活動が個々の会員のコンプライアンスの
確立に寄与し、行政書士への信頼の基盤づくりに深く関わっています。
これら団体の財政を脅かす長期会費未納は、行政書士制度にとって
脅威であり、積年の問題でした。「みなし退会」を求める声はあったものの、
現行の行政書士法制にあっては、長期会費未納者を「みなし退会」
とする根拠に欠けているので、登録入会・抹消退会制度を堅持しつつ、
会費滞納を登録抹消事由とするなどの法改正を目指します。
3.社会貢献活動への取り組みについて
社会環境の変化とともに、高齢化問題に代表される社会問題が
次々と顕在化しています。
その中で法定業務以外にも行政書士が担うに相応しい業務分野が
拡大しています。これらの業務に対して積極的に取り組んでいくことが、
社会に貢献するとともに、今後の行政書士業務の拡大にも資するところです。
従前から取り組んでいる次の事業を日行連は単位会と連携して
引き続き推進します。
1)行政書士ADRセンターの事業推進について
平成20年3月に日本弁護士連合会と交わした行政書士ADRセンターに
関する基本合意を堅持しつつ、各地の行政書士ADRセンターの稼働を
積極的に支援していきます。その後、平成20年12月に内閣府規制改革会議が
発表した「規制改革推進のための第三次答申」における
ADR事業に関する提言も参考としつつ、業容を発展的に拡大し、
ADR手続実施者としての実績を重ねてまいります。
2)成年後見(特に法定後見)業務の推進について
核家族化が常態化している今日、親族以外の第三者を法定後見人とする
ケースが増加しています。行政書士の法定業務にはなり得ないが、
「まちの法律家」として諸手続に精通し、コンプライアンス遵守が
義務づけられている行政書士が、その業務を担う社会的妥当性は大いに
認められてしかるべきです。関係業務に対する会員の研錬、関係組織づくり、
外部PRを重ね、家庭裁判所における任用事例を拡大すべく、
諸施策を講じていきます。
本年度はこれらを重点項目とし、各部・委員会事業の連携を図り、
課題の達成に向けて取り組んでまいります。当然、従来からの継続事業、
各部・委員会の課
題事業にも果敢に取り組んでまいる所存であります。
協議事項として提案された平成21年度 事業計画基本方針(案)です。
議案ではないため、今後各方面の意見を取り付けながら
修正も行われることでしょうが、ここでは読みやすいように
段落等を手直しして掲載しております。
??????????????????????????????????????????????????
平成21年度 事業計画基本方針(案)
ー国民の信頼を基盤に、国民の利便に資する制度構築に向けてー
米国経済の減速、世界的な為替市場、金融市場の混乱が日本経済を直撃し、
景況の悪化、雇用不安と行政書士のクライアントである国民、事業者が
かつてない試練の時代を迎えております。
「行政と国民のパイプ役」、「まちの法律家」である行政書士を擁する
行政書士会(以下「単位会」という。)、日本行政書士会連合会
(以下「日行連」という。)にとっても、昨今の激変への対応が
求められております。
司法制度改革については、法科大学院による法曹養成を重ね、
さらに平成21年5月から裁判員制度が導入されるに及んで、
諸整備の状況が一般国民の視野に入ってきました。
司法制度改革審議会意見書(平成13年)に示された一連の司法制度改革
(隣接法律専門職種を含む)の完成期に入ってきたと言っても
過言ではありません。
内閣府規制改革会議から三次にわたり答申が行われ、「法務・資格分野」
に関する提言には、行政書士を含む隣接法律専門職種に、サービスを
利用する国民の視点にたち、利便性や提供されるサービスの向上に
対する期待が重ねて記されております。
以上を踏まえ、法1条に掲げる国民の利便に資する行政書士の育成、
行政書士制度の構築が急務です。また、「国民の利便」のためには、
「国民の信頼」が基盤をなすことは言を待ちません。
このような視点から、本年度は総花的に重点項目を示すことなく、
大きく次の3点に紋り、限りある会の資源を「選択と集中」の
もと投下し、ゆるぎない行政書士制度の地歩を固めるべく
邁進してまいります。
1.行政不服申立て代理の実現に向けて
平成20年12月に内閣府規制改革会議が発表した
「規制改革推進のための第三次答申」で、
「行政機関に提出する許認可等の申請書類の作成・提出を行い申請
内容を熟知する行政書士が、依頼者の意向に基づきそれらに関わる
行政不服審査申立も含め一貫して取り扱えるようになれば、
行政不服審査制度の活用が促進され、国民の利便性の向上が図られる
との見解もある。」と答申されています。
昨年の法改正で明確化された許認可等における聴聞・弁明の機会の
付与手続代理の延長線上に行政不服申立て代理業務があり、
十分な能力担保を伴って当該業務に参入することを、
依頼者である国民、事業者は期待するところです。
そのためには行政書士法の創設的改正が必要となり、
その実現を目指します。
2.長期会費未納会員に対する登録抹消の実現に向けて
国民の信頼を獲得するためには、業務能力とともに、
そのコンプライアンスが
極めて重要です。厳格な登録入会・抹消退会制度に関与する単位会、
日行連が行う自律、自助の事業活動が個々の会員のコンプライアンスの
確立に寄与し、行政書士への信頼の基盤づくりに深く関わっています。
これら団体の財政を脅かす長期会費未納は、行政書士制度にとって
脅威であり、積年の問題でした。「みなし退会」を求める声はあったものの、
現行の行政書士法制にあっては、長期会費未納者を「みなし退会」
とする根拠に欠けているので、登録入会・抹消退会制度を堅持しつつ、
会費滞納を登録抹消事由とするなどの法改正を目指します。
3.社会貢献活動への取り組みについて
社会環境の変化とともに、高齢化問題に代表される社会問題が
次々と顕在化しています。
その中で法定業務以外にも行政書士が担うに相応しい業務分野が
拡大しています。これらの業務に対して積極的に取り組んでいくことが、
社会に貢献するとともに、今後の行政書士業務の拡大にも資するところです。
従前から取り組んでいる次の事業を日行連は単位会と連携して
引き続き推進します。
1)行政書士ADRセンターの事業推進について
平成20年3月に日本弁護士連合会と交わした行政書士ADRセンターに
関する基本合意を堅持しつつ、各地の行政書士ADRセンターの稼働を
積極的に支援していきます。その後、平成20年12月に内閣府規制改革会議が
発表した「規制改革推進のための第三次答申」における
ADR事業に関する提言も参考としつつ、業容を発展的に拡大し、
ADR手続実施者としての実績を重ねてまいります。
2)成年後見(特に法定後見)業務の推進について
核家族化が常態化している今日、親族以外の第三者を法定後見人とする
ケースが増加しています。行政書士の法定業務にはなり得ないが、
「まちの法律家」として諸手続に精通し、コンプライアンス遵守が
義務づけられている行政書士が、その業務を担う社会的妥当性は大いに
認められてしかるべきです。関係業務に対する会員の研錬、関係組織づくり、
外部PRを重ね、家庭裁判所における任用事例を拡大すべく、
諸施策を講じていきます。
本年度はこれらを重点項目とし、各部・委員会事業の連携を図り、
課題の達成に向けて取り組んでまいります。当然、従来からの継続事業、
各部・委員会の課
題事業にも果敢に取り組んでまいる所存であります。
|
|
|
|
コメント(30)
>積極的に支援していきます。その後、平成20年12月に内閣府規制改革会議が
>発表した「規制改革推進のための第三次答申」における
>ADR事業に関する提言も参考としつつ、業容を発展的に拡大し、
なんとも不思議な表現です。
「ADR事業に関する提言」が規制改革会議の第3次答申にありましたか?
提言は、みあたらないけどなぁ。どこをどう読んでも。
474ページに、「具体的施策」と明記し、平成20年度実施とは記載されています。
これは提言でもなんでもないのだ。
また、 この具体的施策に関連して法務省が先日、再回答を寄せている。
「規制改革会議の「規制改革推進のための第3次答申」(平成20年12月22日)に示された「具体的施策」を尊重し,民間紛争解決手続の業務の認証に関する事務を適正に実施してまいりたい。」と。
いったいどこにあるのか? 「第3次答申の提言」なる部分は。
つまりは、3次答申中の表現は{認証に関する事務の適正実施}をさしているわけであって、
一切「提言」なるものではないのだ。
「ADR事業に関する提言も参考としつつ、業容を発展的に拡大し、」って、全く意味不明である。
業容を発展的に拡大? なんなんだ? 業容って。
ようは、規制改革会議の第3次答申など全く読んでいないのではないか。
>発表した「規制改革推進のための第三次答申」における
>ADR事業に関する提言も参考としつつ、業容を発展的に拡大し、
なんとも不思議な表現です。
「ADR事業に関する提言」が規制改革会議の第3次答申にありましたか?
提言は、みあたらないけどなぁ。どこをどう読んでも。
474ページに、「具体的施策」と明記し、平成20年度実施とは記載されています。
これは提言でもなんでもないのだ。
また、 この具体的施策に関連して法務省が先日、再回答を寄せている。
「規制改革会議の「規制改革推進のための第3次答申」(平成20年12月22日)に示された「具体的施策」を尊重し,民間紛争解決手続の業務の認証に関する事務を適正に実施してまいりたい。」と。
いったいどこにあるのか? 「第3次答申の提言」なる部分は。
つまりは、3次答申中の表現は{認証に関する事務の適正実施}をさしているわけであって、
一切「提言」なるものではないのだ。
「ADR事業に関する提言も参考としつつ、業容を発展的に拡大し、」って、全く意味不明である。
業容を発展的に拡大? なんなんだ? 業容って。
ようは、規制改革会議の第3次答申など全く読んでいないのではないか。
>平成20年3月に日本弁護士連合会と交わした行政書士ADRセンターに
>関する基本合意を堅持しつつ、各地の行政書士ADRセンターの稼働を
>積極的に支援していきます。その後、平成20年12月に内閣府規制改革会議が
>発表した「規制改革推進のための第三次答申」における
>ADR事業に関する提言も参考としつつ、業容を発展的に拡大し、
>ADR手続実施者としての実績を重ねてまいります。
この文書の裏読みしなければならない、つらさ(笑)
ようするに、日弁連との合意書について批判が多いも、今後とも合意書を堅持するとの意思表明なのだ。
規制改革会議の福井委員からの「提言」については、参照にするも、日弁連との合意書の堅持が前提であって、
認証取得後に、委員の提言(メモ)に沿った形式で、取り扱う紛争範囲(業容)を拡大していく、と。これは今後の課題とする。発展的に拡大とする。
発展的解消とは、聞くが。発展的に拡大する、とはあまり聞かないな。ということで、福井メモについては歯牙にもかけないとのことですね。
以下、参考までに。
福井委員の”メモ”、「行政書士の役割の強化とADR 08.10.03」
・行政書士がADRに関わる場合には、広く、国民ニーズに応える分野を網羅すべき
・ペット、外国人就労就学、自転車事故、敷金の4分野での限定は、あくまでも単位弁護士会からの協力を受けたい場合に限られる。個別弁護士の協力が前提なら、あらゆる分野が対象になりうる。
・単位弁護士会との間での協定は、他の分野のADRを行わないことを前提とするのであれば、行政書士会にとって百害あって一利なし。
・法務省のADR認証は、個別弁護士の助言を受けうることで問題ないことは、司法法制部に確認済み。
・弁護士会には、行政書士の専門性等の判断権がないことも、法務省に確認済み。
>関する基本合意を堅持しつつ、各地の行政書士ADRセンターの稼働を
>積極的に支援していきます。その後、平成20年12月に内閣府規制改革会議が
>発表した「規制改革推進のための第三次答申」における
>ADR事業に関する提言も参考としつつ、業容を発展的に拡大し、
>ADR手続実施者としての実績を重ねてまいります。
この文書の裏読みしなければならない、つらさ(笑)
ようするに、日弁連との合意書について批判が多いも、今後とも合意書を堅持するとの意思表明なのだ。
規制改革会議の福井委員からの「提言」については、参照にするも、日弁連との合意書の堅持が前提であって、
認証取得後に、委員の提言(メモ)に沿った形式で、取り扱う紛争範囲(業容)を拡大していく、と。これは今後の課題とする。発展的に拡大とする。
発展的解消とは、聞くが。発展的に拡大する、とはあまり聞かないな。ということで、福井メモについては歯牙にもかけないとのことですね。
以下、参考までに。
福井委員の”メモ”、「行政書士の役割の強化とADR 08.10.03」
・行政書士がADRに関わる場合には、広く、国民ニーズに応える分野を網羅すべき
・ペット、外国人就労就学、自転車事故、敷金の4分野での限定は、あくまでも単位弁護士会からの協力を受けたい場合に限られる。個別弁護士の協力が前提なら、あらゆる分野が対象になりうる。
・単位弁護士会との間での協定は、他の分野のADRを行わないことを前提とするのであれば、行政書士会にとって百害あって一利なし。
・法務省のADR認証は、個別弁護士の助言を受けうることで問題ないことは、司法法制部に確認済み。
・弁護士会には、行政書士の専門性等の判断権がないことも、法務省に確認済み。
>(財)入管協会理事役員一覧に行政書士が名を連ねています。
http://www.disclo-koeki.org/03b/00639/2.pdf
この一覧表が古いか?
そんなことはありません。当該協会の専務理事である佐藤氏は、元大阪入管局長であり、
昨年3月退職、その後6月に専務理事に就任です。
次の法務省情報から、
http://www.moj.go.jp/PRESS/081225-1.html
平成20年 再就職状況の公表について 法務省
ということで、一覧表は全く新しい。
なお、ニセ行政書士のことですが、5年前に退会されているようです。元行政書士です。
私としては、このニセ行政書士を問題にしたいのではなく、
これが5年間も放置され、連合会会長が当該協会の理事として同席しているという点です。
ましてや、日行連、行政書士会と入管協会の間には、切っても切れない関係にもあるのですから。
http://www.disclo-koeki.org/03b/00639/2.pdf
この一覧表が古いか?
そんなことはありません。当該協会の専務理事である佐藤氏は、元大阪入管局長であり、
昨年3月退職、その後6月に専務理事に就任です。
次の法務省情報から、
http://www.moj.go.jp/PRESS/081225-1.html
平成20年 再就職状況の公表について 法務省
ということで、一覧表は全く新しい。
なお、ニセ行政書士のことですが、5年前に退会されているようです。元行政書士です。
私としては、このニセ行政書士を問題にしたいのではなく、
これが5年間も放置され、連合会会長が当該協会の理事として同席しているという点です。
ましてや、日行連、行政書士会と入管協会の間には、切っても切れない関係にもあるのですから。
motakinさんの、
>質問?
> 許認可等における聴聞・弁明の機会の付与手続代理の延長線上に
> 行政不服申立て代理業務があるのでしょうか。
私の解釈では「延長線上に」というのは正しいと思っています。
ただなぁ、「聴聞・弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述」の代理手続としてくれるともっと分かり易いのだが。改正行政書士法のメインは、「その他の意見陳述の手続」の代理にあるのだし。
ようするに、この背景には弁護士法72条規制の突破という点があるのではないか。
だからこそ、「創設的行政書士法の改正」をも主張しているのであろう。
行政不服申立の代理手続においても、弁護士法のしばりを外せという主張です。
つまり、延長線上にあるのだ。
聴聞等の機会での代理”作業”の延長線上に不服申立の代理”作業”がある、と読込、理解されませんように。
>質問?
> 許認可等における聴聞・弁明の機会の付与手続代理の延長線上に
> 行政不服申立て代理業務があるのでしょうか。
私の解釈では「延長線上に」というのは正しいと思っています。
ただなぁ、「聴聞・弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述」の代理手続としてくれるともっと分かり易いのだが。改正行政書士法のメインは、「その他の意見陳述の手続」の代理にあるのだし。
ようするに、この背景には弁護士法72条規制の突破という点があるのではないか。
だからこそ、「創設的行政書士法の改正」をも主張しているのであろう。
行政不服申立の代理手続においても、弁護士法のしばりを外せという主張です。
つまり、延長線上にあるのだ。
聴聞等の機会での代理”作業”の延長線上に不服申立の代理”作業”がある、と読込、理解されませんように。
コメント12の、
>法務省所管の入管協会(特例民法法人)も、新公益法人制度施行により、公益法人の認定を目指すも>のと思われ、その法人に日行連会長が理事職を勤めるという、極めて今日的話題なのです。
今日的話題の関連で、
毎日新聞から、
http://mainichi.jp/enta/sports/general/sumo/news/20090130k0000m050027000c.html
日本相撲協会:公益財団認定申請へ
に、外部委員に弁護士と中馬国会議員がいます。中馬氏は、ご存じの自民党行政書士制度推進議連の会長ではありませんか。
そこで、日本相撲協会が公益法人認定取得にあたって、外部理事に、日行連から理事職を派遣するように手を打っておくとか。(爆) 外部理事に行政書士もいるのだ、と。日行連会長でなくても、副会長でもよろしい。公益財団法人の認定をえれば文科省の所管から外れますし、ちょうど時期的によろしいかと。所管庁からの天下りの阻止もあって・・・・
夢物語か?
>法務省所管の入管協会(特例民法法人)も、新公益法人制度施行により、公益法人の認定を目指すも>のと思われ、その法人に日行連会長が理事職を勤めるという、極めて今日的話題なのです。
今日的話題の関連で、
毎日新聞から、
http://mainichi.jp/enta/sports/general/sumo/news/20090130k0000m050027000c.html
日本相撲協会:公益財団認定申請へ
に、外部委員に弁護士と中馬国会議員がいます。中馬氏は、ご存じの自民党行政書士制度推進議連の会長ではありませんか。
そこで、日本相撲協会が公益法人認定取得にあたって、外部理事に、日行連から理事職を派遣するように手を打っておくとか。(爆) 外部理事に行政書士もいるのだ、と。日行連会長でなくても、副会長でもよろしい。公益財団法人の認定をえれば文科省の所管から外れますし、ちょうど時期的によろしいかと。所管庁からの天下りの阻止もあって・・・・
夢物語か?
>政治的力学において 勝ち越しの可能性はなきにしもあらず
はい、星が八個とれば十分です。(笑)
それ以上を望むべくもない。
相撲と行政書士の関係は因縁浅からぬ、と。20年前かなぁ、会報「日本行政」に外国人力士の高見山が
行政書士会館を表敬訪問した写真が掲載されていた。
日本国籍取得・帰化手続に行政書士が関与したこともあって、そのお礼かたがたとの記事であったように
思う。当時の会長と会談していた。
当時、外国人力士は珍しかったが、今は外国人力士数も多くあり、
これら力士の国籍取得手続、あるいは在留資格関連の手続に関与する行政書士も多数となっているものと思われる。
という時代背景もあって、相撲協会の外部理事に行政書士がともなれば、社会への影響が大きいのだがなぁ。他の士業では、なり得ない部分だし。
日本文化の相撲と、日本文化の行政書士制度のコラボ。
特例民法法人たる相撲協会の現在の外部理事の3名の方々は、齢も75を超えられ、そうそう長期間の役職は無理だとも思われるし・・・・・
夢物語で終わるか?
はい、星が八個とれば十分です。(笑)
それ以上を望むべくもない。
相撲と行政書士の関係は因縁浅からぬ、と。20年前かなぁ、会報「日本行政」に外国人力士の高見山が
行政書士会館を表敬訪問した写真が掲載されていた。
日本国籍取得・帰化手続に行政書士が関与したこともあって、そのお礼かたがたとの記事であったように
思う。当時の会長と会談していた。
当時、外国人力士は珍しかったが、今は外国人力士数も多くあり、
これら力士の国籍取得手続、あるいは在留資格関連の手続に関与する行政書士も多数となっているものと思われる。
という時代背景もあって、相撲協会の外部理事に行政書士がともなれば、社会への影響が大きいのだがなぁ。他の士業では、なり得ない部分だし。
日本文化の相撲と、日本文化の行政書士制度のコラボ。
特例民法法人たる相撲協会の現在の外部理事の3名の方々は、齢も75を超えられ、そうそう長期間の役職は無理だとも思われるし・・・・・
夢物語で終わるか?
>gyolawyerさん解説をお願いします。
とほ。
私は素直ではないので、基本方針案の連合会起案者に聞いた方がよろしいかと。
基本方針に、単に「改正」と表現するより、より積極的な意味を持たせた「創設的」としているのを、個人的には評価しているのですけどね。
ただなぁ、この基本方針案の作成者が練りに練って、時間をかけて文書を創り上げたとの読み応えがないのが、残念ですけどね。
はっきり限定すればよろしいのだ。
1,行政不服審査の代理権の付与に関する創設的改正を目指す
行政不服審査法の大改正もあって、(今国会で審議中)
これが施行される暁には、行政書士への代理権について行政書士法にて規定されることに
なる。規定させるべく行動したい、ということ。
とほ。
私は素直ではないので、基本方針案の連合会起案者に聞いた方がよろしいかと。
基本方針に、単に「改正」と表現するより、より積極的な意味を持たせた「創設的」としているのを、個人的には評価しているのですけどね。
ただなぁ、この基本方針案の作成者が練りに練って、時間をかけて文書を創り上げたとの読み応えがないのが、残念ですけどね。
はっきり限定すればよろしいのだ。
1,行政不服審査の代理権の付与に関する創設的改正を目指す
行政不服審査法の大改正もあって、(今国会で審議中)
これが施行される暁には、行政書士への代理権について行政書士法にて規定されることに
なる。規定させるべく行動したい、ということ。
ちょい面白い意見聴取会の案内があるので、
本日の官報から、
「行政不服審査法に基づく異議申立てに係る意見聴取会について(経済産業省)」
http://kanpou.npb.go.jp/20090203/20090203h05003/20090203h050030010f.html
特に注目点としては、
「異議申立てに係る処分
平成二十年十一月二十一日付けドイツ短機関銃MPe38のレプリカの輸入承認申請の不受理処分」にて
「不受理処分」としている部分です。
改正行政書士法の次の箇所、
「許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)」における「受理」とはいかなる定義なのかが、話題となっていましたね。日行連のガイドラインでは、この受理定義について・・・・・。?
さて、今回の承認申請での受理、不受理などを指すと言えるのではないかと思っているところです。
異議申立人の代理人として意見陳述の手続が今後は可能であり、かつこうした聴取会にて代理人として意見を述べることも想定できますね。
で、結論:
改正行政書士法の趣旨について、「許認可等における聴聞・弁明の機会の付与手続代理」と表現すると大いなる誤解を生むと思っています。
やはり、「意見陳述(聴聞・弁明等含む)手続の代理」と包括的表現が望ましい、と。
本日の官報から、
「行政不服審査法に基づく異議申立てに係る意見聴取会について(経済産業省)」
http://kanpou.npb.go.jp/20090203/20090203h05003/20090203h050030010f.html
特に注目点としては、
「異議申立てに係る処分
平成二十年十一月二十一日付けドイツ短機関銃MPe38のレプリカの輸入承認申請の不受理処分」にて
「不受理処分」としている部分です。
改正行政書士法の次の箇所、
「許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)」における「受理」とはいかなる定義なのかが、話題となっていましたね。日行連のガイドラインでは、この受理定義について・・・・・。?
さて、今回の承認申請での受理、不受理などを指すと言えるのではないかと思っているところです。
異議申立人の代理人として意見陳述の手続が今後は可能であり、かつこうした聴取会にて代理人として意見を述べることも想定できますね。
で、結論:
改正行政書士法の趣旨について、「許認可等における聴聞・弁明の機会の付与手続代理」と表現すると大いなる誤解を生むと思っています。
やはり、「意見陳述(聴聞・弁明等含む)手続の代理」と包括的表現が望ましい、と。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
MIXI 行政書士連合会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
MIXI 行政書士連合会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
困ったときには