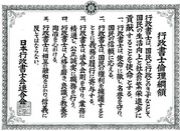○車庫証明業務における行政書士とユーザーとの関係について
みだしのことにつき
当会会員と自動車販売店との係争事件に関して
裁判官が判決文に下記の通り記載したことに対して
事実誤認があるとして
行政書士会として意見書を提出することにしました。
これは日行連と自販連との合意確認書と
行政書士に対する依頼書の取扱に関して
両業界に十分理解されないまま業務が遂行されていること
ならびに
弁護士を除いて隣接法律職には仲介制限がないため
「他人の依頼を受けて」の他人には
申請人だけでなく仲介者も含まれています。
このように車庫証明業務だけでなく
仲介者を介して受託した業務に関して
申請人に行政書士が面談等
?出来るか
2出来ないか
に関わる問題だと認識すべきではないでしょうか。
各位に当該事案の研究意見を
お聞かせ下さるようお願い申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁判官の意見記述の部分
?「行政書士が自動車販売店の顧客
(行政書士に対する車庫証明業務の依頼者ではあるが、
あくまで自動車販売店の顧客であることが前提である)を
自動車販売店に無断で訪問した」
?顧客はあくまで自動車販売店から自動車を買うことを目的とする顧客であり、
行政書士への依頼は顧客にとって副次的・間接的なものであるから、
顧客や自動車販売店の承諾を得ることなく
顧客方を訪問することが委託契約の内容に含まれ、
あるいは独自の判断で依頼者方を訪問することが
委託契約に根拠を有するとは言えない。」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
意見書は以下の通り
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行政書士法及び車庫証明業務に関する意見書
滋賀県行政書士会 会長 盛武 隆
? 行政書士法
行政書士法第一条の二は、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成
する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。
)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含
む。)を作成することを業とする。」と定めている。
また行政書士法 第一条の三は、「行政書士は、前条に規定する業務のほか、
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただ
し、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、
この限りでない。」
さらに第一条の三の一及び二は、「前条の規定により行政書士が作成することが
できる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する
書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に
規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明
の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対して
する行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法
律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。」、
及び「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する
書類を代理人として作成すること。」と定めている。
これにより、
1 官公署に提出する書類のうち
?道路運送車両法に基づく自動車保有関係手続及びこれにともなう自動車
税法、自動車重量税法、自動車取得税法、地方税法による自動車税等の
申請書・申告書等及び申請書に代えて作成する電磁的記録の作成は行政
書士の独占業務である。
この場合官公署とは国土交通省、都道府県税事務所である。
?自動車の保管場所の確保に関する法律に基づく自動車保管場所証明書等
の申請書及び申請書に代えて作成する電磁的記録の作成は行政書士の独
占業務である。
この場合官公署とは警察署である。
2 実地調査に基づく図面の作成
?自動車の保管場所の確保に関する法律に基づく、自動車保管場所証明書
の申請書に添付する自動車保管場所の配置図の作成は、行政書士法に定
める「その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図
面類を含む。)」であり、その作成は行政書士の独占業務である。
?同じく上記申請書に添付する「保管場所使用権原疎明書(自認書)」及
び「保管場所使用承諾証明書」の作成は、「行政書士法に定めるその他
権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含
む。)」であり、その作成は行政書士の独占業務である。
3 代理行為
上記行政書士法第一条の三の一に基づき、行政書士は申請人の委任を得
て、代理人として行政書士が申請人となり申請書の作成及び申請代理を業
として行うことができる。(添付資料1)
4 確認行為
自動車の保管場所の確保に関する法律にあっては、申請人が自動車の保管
場所として「確保した場所」とは、保管するのに「適当な広さ」をいうの
ではなく、保管するのに必要な広さと共に、その場所が物置やその他の者
が常時使用できないように「申請自動車の保管のために確保した保管場
所」をいうのであり、実際には、警察署の確認調査の際に何も置かれてお
らず他の目的にも使用されていない「確保した保管場所」であることを確
認したうえで証明書を発行することとされている。
?行政書士は、申請書等の作成にあたっては、当該申請がユーザー自身の
依頼であることを依頼書により業務委託契約が成立したことを確認の
上、業務を遂行することとしている。(添付資料2)
?また自動車販売店のセールスマン等は、車庫証明申請を依頼書記載の行
政書士に委任することを説明し同意を得た上で、預かり行政書士料を含
む諸費用の徴収とともに、依頼書にユーザーの署名または記名押印を求
め、販売店が行政書士に依頼の仲介を行っている。
?これにより行政書士は、車庫証明申請書に添付する保管場所の配置図の
作成に当たり、当該申請自動車の専用場所として「確保されているこ
と」の確認が必要であり、他の自動車等が置かれている場合は、ユーザ
ーに確認のうえ、当該自動車が下取りされること等を警察に対して申し
出る必要が生じる。
?加えて、ユーザー自身の作成する「保管場所使用権原疎明書(自認
書)」及び第三者である保管場所の所有者が発行する「保管場所使用承
諾証明書」については、警察署に提出する前又は提出後において、その
内容について疑義が生じた場合は当該書類発行者に対して連絡し、内容
の確認、警察署への連絡等の依頼等の事務が行政書士に生じる。(添付
資料3、4)
?実地調査に基づく図面の作成とは、保管場所の配置図の作成に必要なガ
レージ等における駐車区画の位置についてユーザーへの確認行為を指し
ているのである。
また、車庫証明申請手続きについては、自動車の保管場所の確保に関
する法律及び行政手続法に基づき申請するものであるが、申請者等に対
して当該法令の趣旨、申請要件、許可要件、標準処理期間、不許可とな
る条件等の説明が必要であり、さらに消費者契約法により業務の依頼人
である自動車販売店、ユーザーに対する説明義務が課されている。(添
付資料5)
5.職務上請求書の使用
車庫証明業務の遂行に際しては、ユーザーの本人確認、住所地を住民票等
で確認して正確を期すため、住民票等の交付申請が付随している。これら
の個人情報の取扱に関して依頼書により、本人の同意を得ておく必要があ
る。これにより行政書士は戸籍法・住民基本台帳法に定める特定事務受任
者として職務上請求書を使用して住民票等の請求を行っている。
6 事件簿の保存期間
行政書士法第九条は、「行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これ
に事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府
県知事の定める事項を記載しなければならない。」 と定めており、行政書
士法第九条2は「行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿
閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなったとき
も、また同様とする。」と定めている。
? 自動車登録及び車庫証明業務に関する行政指導等
自動車業界の「自動車保有関係手続」に関する不正事件による行政秩序の
混乱およびこれを原因とするユーザー被害防止策は、たびたび国会等で取り
上げられたため、関係行政機関は自動車関係団体に対して下記の行政指導等
を行っている。
1 自動車保有関係手続の費用徴収に係る行政指導
自動車保有関係手続の費用徴収に係る行政指導として通産省通達がある。
これにより車庫証明業務を行政書士に依頼した場合に行政書士に支払わ
れる手数料は、自動車販売店が「預かり行政書士料」としてユーザーから
預かるよう指導されており、自動車販売契約書等にその表示がされてい
る。
当然に「預かり行政書士料」であるから、これを自動車販売店等がピン
ハネして行政書士に手数料を支払うような場合は、「詐欺罪」に該当する
場合があることが、法務省刑事局長の国会答弁されている。万一ユーザー
からの徴収額と行政書士への支払額との差額が生じた場合は、当然にユー
ザーに還付されなければならない。そうしなければ不当利得となるからで
ある。(添付資料6)
2 自動車流通の適正化に係る業界指導
自動車販売における流通の適正化については、業界団体から傘下の会員に
対して指導が行われている。(添付資料7)
3 車庫証明に係る行政指導
車庫証明に係る行政指導としては昭和45.3.9警察庁丙規発第22号 警察庁交
通局長から運輸省自動車局長宛「自動車の保管場所の確保の適正化に関する
要望について」に基づく昭和45.5.22自管第3号 自動車局長発各陸運局長宛
「自動車の保管場所の確保の適正化に関する要望について」があり、運輸省
はこれに基づき自動車業界に対して行政指導を行っている。(添付資料8、
9)
? 業界協議
自動車業界に対する上記行政指導及び関係法令の遵守等による自動車流通
の適正化が社会的に求められたことから、行政書士法違反行為の是正とあわ
せて、行政書士会と自動車業界は下記の通り合意確認書を交わしている。
1 日本行政書士会連合会と日本自動車販売店連合会の覚え書き
(添付資料10,)
2 滋賀県行政書士会と滋賀県自動車販売協会の覚え書き(添付資料11)
3 滋賀県行政書士会と滋賀県自動車販売協会の協定書(添付資料12)
? 業務委託契約
行政書士と自動車販売店は上記合意確認書に基づき、自動車保管場所証明
書の申請手続きに関して下記のとおり業務委託を行っている。
1 業務委託の方法
「セールスマン等は、ユーザーが車庫証明申請書を作成しない場合は、
行政書士に作成を依頼するものとする。」との車庫証明業務取扱基本要項
に基づき、滋賀県行政書士会は会員及び自動車販売店に対して「車庫証明
依頼書(委任書)」(三者間契約書)により業務の取扱を行うよう指導・
要請し、これは両者間に定着している。
2 業務委託契約
車庫証明業務は、申請書、権利義務又は事実証明に関する書類、実地調査
に基づく図面類を作成する事を自動車ユーザー、自動車販売店、行政書士
が「車庫証明依頼書(委任書)」により三者間契約書を交わすことにより
行われている。
3 申請手続代理
車庫証明申請手続に関してユーザーが行政書士に委任状を発行した場合
は、行政書士が申請代理人として申請手続きを行っている。
4 預かり行政書士料
自動車登録・車庫証明業務申請書類の作成を行政書士に依頼するとして、
自動車販売店はユーザーから「預かり行政書士料」を徴収し、預かり金と
して保管し、業務委託が完了した時点で、行政書士の請求により車庫証明
業務費用が支払われている。
? 個人情報保護
1 個人情報保護契約
滋賀県行政書士会は、行政書士及び自動車販売店との間に「個人情報保護
契約」を交わすよう指導している。これは行政書士法には罰則のある「行
政書士の守秘義務」が定められているが、自動車販売店に守秘義務が課さ
れていないため、ユーザーのプライバシー侵害防止のため、個人情報保護
法により双方が協力し責任を分担して法令遵守を図ることを目的としてい
るためである。
2 事件簿(名簿)
行政書士は、車庫証明を受託した場合は、行政書士法により罰則付きで事
件簿に事件名・住所・氏名等を記録して保存することが定められている。
この事件簿は、まさに個人情報の記録であるため、自動車販売店との業
務委託契約が解約された場合でも、個人情報保護契約の特約として、行政
書士法に定めのある「事件簿を閉じてから二年間の保管期間」が満了しな
ければ返還できない旨の規定を挿入して行政書士の法令遵守の徹底を図っ
ている。
? 消費者契約法
1 消費者契約法
行政書士及び自動車販売店は、消費者契約法において事業者として定義
されているため、自動車の販売に際して取り交わす契約書及びその約款な
らびに車庫証明業務依頼書について、ユーザーに対して説明責任と情報提
供が義務づけられており、セールスマン等は、当然にその説明を行ってい
る。
2 依頼書と費用徴収
自動車販売店は、車庫証明業務についてユーザーから依頼書を貰い受
け、行政書士に業務を委託しない場合、あるいは行政書士に依頼したと
しても徴収した預かり行政書士費用と実際の支払額との間に差額が生
じる場合は、当然にユーザーに返還しなければならない。
このように依頼書及び契約書等は、自動車の保管場所の確保の適正化に
貢献し、交通安全の一助に資することにとどまらず、適正申請の遂行によ
りユーザー被害の防止や自動車流通の適正化など自動車業界の法令遵守に
貢献している。
? 行政書士と申請者(顧客)の接点
以上縷々述べてきたごとく、行政書士は、ユーザーが行政書士に依頼する
意志を明示した、ユーザーと自動車販売店と行政書士との三者間業務委託契
約である「依頼書」により車庫証明業務を推進しているのであり、この業務
に係る行政の円滑な推進のために関係法令を遵守するためには、販売店との
連絡のみならずユーザーとの面談、意思確認、質疑応答等は必然的な行政書
士の代理業務としてユーザーとの契約に基づき委任されているのである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
なお添付資料については
以下に掲載しております。
http://
閲覧キーは210111です。
ご参考
今月号「月刊日本行政」に個人情報保護法の契約モデルが掲載されているが
行政書士の事件簿の保存期間に関する注意が欠けており、あのモデルで契約を
交わした場合には行政書士が行政書士法違反を問われることになる。
(日本行政モデルには下記の条項はない)
(例 契約解除した場合はただちに個人情報を返還する・・・などの条項)
また一般的モデルには
立ち入り調査を依頼者に認める条項が規定されていることが多いが
(日本行政モデルにはこの条項はない)
これも守秘義務を課されている行政書士事務所への立ち入りを容易に認める契約としないよう注意が必要であろうと考える。
みだしのことにつき
当会会員と自動車販売店との係争事件に関して
裁判官が判決文に下記の通り記載したことに対して
事実誤認があるとして
行政書士会として意見書を提出することにしました。
これは日行連と自販連との合意確認書と
行政書士に対する依頼書の取扱に関して
両業界に十分理解されないまま業務が遂行されていること
ならびに
弁護士を除いて隣接法律職には仲介制限がないため
「他人の依頼を受けて」の他人には
申請人だけでなく仲介者も含まれています。
このように車庫証明業務だけでなく
仲介者を介して受託した業務に関して
申請人に行政書士が面談等
?出来るか
2出来ないか
に関わる問題だと認識すべきではないでしょうか。
各位に当該事案の研究意見を
お聞かせ下さるようお願い申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁判官の意見記述の部分
?「行政書士が自動車販売店の顧客
(行政書士に対する車庫証明業務の依頼者ではあるが、
あくまで自動車販売店の顧客であることが前提である)を
自動車販売店に無断で訪問した」
?顧客はあくまで自動車販売店から自動車を買うことを目的とする顧客であり、
行政書士への依頼は顧客にとって副次的・間接的なものであるから、
顧客や自動車販売店の承諾を得ることなく
顧客方を訪問することが委託契約の内容に含まれ、
あるいは独自の判断で依頼者方を訪問することが
委託契約に根拠を有するとは言えない。」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
意見書は以下の通り
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行政書士法及び車庫証明業務に関する意見書
滋賀県行政書士会 会長 盛武 隆
? 行政書士法
行政書士法第一条の二は、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成
する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。
)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含
む。)を作成することを業とする。」と定めている。
また行政書士法 第一条の三は、「行政書士は、前条に規定する業務のほか、
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただ
し、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、
この限りでない。」
さらに第一条の三の一及び二は、「前条の規定により行政書士が作成することが
できる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する
書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に
規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明
の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対して
する行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法
律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。」、
及び「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する
書類を代理人として作成すること。」と定めている。
これにより、
1 官公署に提出する書類のうち
?道路運送車両法に基づく自動車保有関係手続及びこれにともなう自動車
税法、自動車重量税法、自動車取得税法、地方税法による自動車税等の
申請書・申告書等及び申請書に代えて作成する電磁的記録の作成は行政
書士の独占業務である。
この場合官公署とは国土交通省、都道府県税事務所である。
?自動車の保管場所の確保に関する法律に基づく自動車保管場所証明書等
の申請書及び申請書に代えて作成する電磁的記録の作成は行政書士の独
占業務である。
この場合官公署とは警察署である。
2 実地調査に基づく図面の作成
?自動車の保管場所の確保に関する法律に基づく、自動車保管場所証明書
の申請書に添付する自動車保管場所の配置図の作成は、行政書士法に定
める「その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図
面類を含む。)」であり、その作成は行政書士の独占業務である。
?同じく上記申請書に添付する「保管場所使用権原疎明書(自認書)」及
び「保管場所使用承諾証明書」の作成は、「行政書士法に定めるその他
権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含
む。)」であり、その作成は行政書士の独占業務である。
3 代理行為
上記行政書士法第一条の三の一に基づき、行政書士は申請人の委任を得
て、代理人として行政書士が申請人となり申請書の作成及び申請代理を業
として行うことができる。(添付資料1)
4 確認行為
自動車の保管場所の確保に関する法律にあっては、申請人が自動車の保管
場所として「確保した場所」とは、保管するのに「適当な広さ」をいうの
ではなく、保管するのに必要な広さと共に、その場所が物置やその他の者
が常時使用できないように「申請自動車の保管のために確保した保管場
所」をいうのであり、実際には、警察署の確認調査の際に何も置かれてお
らず他の目的にも使用されていない「確保した保管場所」であることを確
認したうえで証明書を発行することとされている。
?行政書士は、申請書等の作成にあたっては、当該申請がユーザー自身の
依頼であることを依頼書により業務委託契約が成立したことを確認の
上、業務を遂行することとしている。(添付資料2)
?また自動車販売店のセールスマン等は、車庫証明申請を依頼書記載の行
政書士に委任することを説明し同意を得た上で、預かり行政書士料を含
む諸費用の徴収とともに、依頼書にユーザーの署名または記名押印を求
め、販売店が行政書士に依頼の仲介を行っている。
?これにより行政書士は、車庫証明申請書に添付する保管場所の配置図の
作成に当たり、当該申請自動車の専用場所として「確保されているこ
と」の確認が必要であり、他の自動車等が置かれている場合は、ユーザ
ーに確認のうえ、当該自動車が下取りされること等を警察に対して申し
出る必要が生じる。
?加えて、ユーザー自身の作成する「保管場所使用権原疎明書(自認
書)」及び第三者である保管場所の所有者が発行する「保管場所使用承
諾証明書」については、警察署に提出する前又は提出後において、その
内容について疑義が生じた場合は当該書類発行者に対して連絡し、内容
の確認、警察署への連絡等の依頼等の事務が行政書士に生じる。(添付
資料3、4)
?実地調査に基づく図面の作成とは、保管場所の配置図の作成に必要なガ
レージ等における駐車区画の位置についてユーザーへの確認行為を指し
ているのである。
また、車庫証明申請手続きについては、自動車の保管場所の確保に関
する法律及び行政手続法に基づき申請するものであるが、申請者等に対
して当該法令の趣旨、申請要件、許可要件、標準処理期間、不許可とな
る条件等の説明が必要であり、さらに消費者契約法により業務の依頼人
である自動車販売店、ユーザーに対する説明義務が課されている。(添
付資料5)
5.職務上請求書の使用
車庫証明業務の遂行に際しては、ユーザーの本人確認、住所地を住民票等
で確認して正確を期すため、住民票等の交付申請が付随している。これら
の個人情報の取扱に関して依頼書により、本人の同意を得ておく必要があ
る。これにより行政書士は戸籍法・住民基本台帳法に定める特定事務受任
者として職務上請求書を使用して住民票等の請求を行っている。
6 事件簿の保存期間
行政書士法第九条は、「行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これ
に事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府
県知事の定める事項を記載しなければならない。」 と定めており、行政書
士法第九条2は「行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿
閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなったとき
も、また同様とする。」と定めている。
? 自動車登録及び車庫証明業務に関する行政指導等
自動車業界の「自動車保有関係手続」に関する不正事件による行政秩序の
混乱およびこれを原因とするユーザー被害防止策は、たびたび国会等で取り
上げられたため、関係行政機関は自動車関係団体に対して下記の行政指導等
を行っている。
1 自動車保有関係手続の費用徴収に係る行政指導
自動車保有関係手続の費用徴収に係る行政指導として通産省通達がある。
これにより車庫証明業務を行政書士に依頼した場合に行政書士に支払わ
れる手数料は、自動車販売店が「預かり行政書士料」としてユーザーから
預かるよう指導されており、自動車販売契約書等にその表示がされてい
る。
当然に「預かり行政書士料」であるから、これを自動車販売店等がピン
ハネして行政書士に手数料を支払うような場合は、「詐欺罪」に該当する
場合があることが、法務省刑事局長の国会答弁されている。万一ユーザー
からの徴収額と行政書士への支払額との差額が生じた場合は、当然にユー
ザーに還付されなければならない。そうしなければ不当利得となるからで
ある。(添付資料6)
2 自動車流通の適正化に係る業界指導
自動車販売における流通の適正化については、業界団体から傘下の会員に
対して指導が行われている。(添付資料7)
3 車庫証明に係る行政指導
車庫証明に係る行政指導としては昭和45.3.9警察庁丙規発第22号 警察庁交
通局長から運輸省自動車局長宛「自動車の保管場所の確保の適正化に関する
要望について」に基づく昭和45.5.22自管第3号 自動車局長発各陸運局長宛
「自動車の保管場所の確保の適正化に関する要望について」があり、運輸省
はこれに基づき自動車業界に対して行政指導を行っている。(添付資料8、
9)
? 業界協議
自動車業界に対する上記行政指導及び関係法令の遵守等による自動車流通
の適正化が社会的に求められたことから、行政書士法違反行為の是正とあわ
せて、行政書士会と自動車業界は下記の通り合意確認書を交わしている。
1 日本行政書士会連合会と日本自動車販売店連合会の覚え書き
(添付資料10,)
2 滋賀県行政書士会と滋賀県自動車販売協会の覚え書き(添付資料11)
3 滋賀県行政書士会と滋賀県自動車販売協会の協定書(添付資料12)
? 業務委託契約
行政書士と自動車販売店は上記合意確認書に基づき、自動車保管場所証明
書の申請手続きに関して下記のとおり業務委託を行っている。
1 業務委託の方法
「セールスマン等は、ユーザーが車庫証明申請書を作成しない場合は、
行政書士に作成を依頼するものとする。」との車庫証明業務取扱基本要項
に基づき、滋賀県行政書士会は会員及び自動車販売店に対して「車庫証明
依頼書(委任書)」(三者間契約書)により業務の取扱を行うよう指導・
要請し、これは両者間に定着している。
2 業務委託契約
車庫証明業務は、申請書、権利義務又は事実証明に関する書類、実地調査
に基づく図面類を作成する事を自動車ユーザー、自動車販売店、行政書士
が「車庫証明依頼書(委任書)」により三者間契約書を交わすことにより
行われている。
3 申請手続代理
車庫証明申請手続に関してユーザーが行政書士に委任状を発行した場合
は、行政書士が申請代理人として申請手続きを行っている。
4 預かり行政書士料
自動車登録・車庫証明業務申請書類の作成を行政書士に依頼するとして、
自動車販売店はユーザーから「預かり行政書士料」を徴収し、預かり金と
して保管し、業務委託が完了した時点で、行政書士の請求により車庫証明
業務費用が支払われている。
? 個人情報保護
1 個人情報保護契約
滋賀県行政書士会は、行政書士及び自動車販売店との間に「個人情報保護
契約」を交わすよう指導している。これは行政書士法には罰則のある「行
政書士の守秘義務」が定められているが、自動車販売店に守秘義務が課さ
れていないため、ユーザーのプライバシー侵害防止のため、個人情報保護
法により双方が協力し責任を分担して法令遵守を図ることを目的としてい
るためである。
2 事件簿(名簿)
行政書士は、車庫証明を受託した場合は、行政書士法により罰則付きで事
件簿に事件名・住所・氏名等を記録して保存することが定められている。
この事件簿は、まさに個人情報の記録であるため、自動車販売店との業
務委託契約が解約された場合でも、個人情報保護契約の特約として、行政
書士法に定めのある「事件簿を閉じてから二年間の保管期間」が満了しな
ければ返還できない旨の規定を挿入して行政書士の法令遵守の徹底を図っ
ている。
? 消費者契約法
1 消費者契約法
行政書士及び自動車販売店は、消費者契約法において事業者として定義
されているため、自動車の販売に際して取り交わす契約書及びその約款な
らびに車庫証明業務依頼書について、ユーザーに対して説明責任と情報提
供が義務づけられており、セールスマン等は、当然にその説明を行ってい
る。
2 依頼書と費用徴収
自動車販売店は、車庫証明業務についてユーザーから依頼書を貰い受
け、行政書士に業務を委託しない場合、あるいは行政書士に依頼したと
しても徴収した預かり行政書士費用と実際の支払額との間に差額が生
じる場合は、当然にユーザーに返還しなければならない。
このように依頼書及び契約書等は、自動車の保管場所の確保の適正化に
貢献し、交通安全の一助に資することにとどまらず、適正申請の遂行によ
りユーザー被害の防止や自動車流通の適正化など自動車業界の法令遵守に
貢献している。
? 行政書士と申請者(顧客)の接点
以上縷々述べてきたごとく、行政書士は、ユーザーが行政書士に依頼する
意志を明示した、ユーザーと自動車販売店と行政書士との三者間業務委託契
約である「依頼書」により車庫証明業務を推進しているのであり、この業務
に係る行政の円滑な推進のために関係法令を遵守するためには、販売店との
連絡のみならずユーザーとの面談、意思確認、質疑応答等は必然的な行政書
士の代理業務としてユーザーとの契約に基づき委任されているのである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
なお添付資料については
以下に掲載しております。
http://
閲覧キーは210111です。
ご参考
今月号「月刊日本行政」に個人情報保護法の契約モデルが掲載されているが
行政書士の事件簿の保存期間に関する注意が欠けており、あのモデルで契約を
交わした場合には行政書士が行政書士法違反を問われることになる。
(日本行政モデルには下記の条項はない)
(例 契約解除した場合はただちに個人情報を返還する・・・などの条項)
また一般的モデルには
立ち入り調査を依頼者に認める条項が規定されていることが多いが
(日本行政モデルにはこの条項はない)
これも守秘義務を課されている行政書士事務所への立ち入りを容易に認める契約としないよう注意が必要であろうと考える。
|
|
|
|
|
|
|
|
MIXI 行政書士連合会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
MIXI 行政書士連合会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
困ったときには