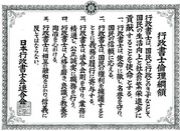士業団体の強制入会に対する規制緩和要求に対する参考判決文
ジュリスト 2006.12.1 NO 1324 p125より引用
(著作権許諾無しにつき近日中に削除予定)
事実
社団法人Y保証協会(被告・被控訴人・上告人)は,訴外社団法人都道府県A業協会(以下,単に「A業協会」という)に加入する宅建業者が中心となって設立された団体であり,宅建業法の指定を受け営業保証金相当額の弁済等の業務を行っていた。A業協会及び全国A業協会連合会(以下,単に「連合会」という)は,宅建業の適正な運営を確保し健全な発達を図るため,会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とした団体であり,国土交通大臣ないし都道府県知事が,連合会ないしA業協会に対し,必要な事項に関して報告を求め,必要な指導,助言及び勧告をすることができるとされていた(宅建業74条3項・4項)。また,Y保証協会が地方に独自の組織,施設を有しないことから,取引主任者等に対する研修業務を連合会及びA業協会と共同で行っており,顧客からの苦情の解決業務等についても連合会ないしA業協会に委託するなど,両者の間には密接な業務上の関係があった。
Y保証協会の定款(以下「本件定款」という)は,会員の入会につき,「本会の会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を得なければならない」と規定し(5条・6条1項),実施細目として,「この定款の施行について必要な事項は,会長が理事会の議決を得て別に定める」と規定していた(42条)。そして,この規定に基づく定款施行規則(以下「本件規則」という)3条1項は,入会資格要件として,Y保証協会の会員は,連合会会員の所属構成員,すなわち各都道府県A業協会の会員でなければならない旨が規定されていた(以下「本件入会資格要件」という)。
宅建業者である?(原告・控訴人・被上告人)は,A業協会の会員となることなくY保証協会に対し入会の申込みをしたところ,Y保証協会は,?が本件入会資格要件を満たさないことを理由に,入会申込みを拒否する旨の決定をした。なお,保証協会の会員となった宅建業者は,宅建業法で定められた営業保証金(主たる事務所につき1000万円,その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額)の供託義務を免除され,主たる事務所につき60万円,その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額の弁済業務保証金分担金をY保証協会に納付すれば足りるとされている(宅建業25条・64条の13・64条の9第1項,宅建業令2条の4・7条)。
本件は,?がY保証協会に対し,本件入会資格要件を定めた本件規則3条1項は宅建業法及び本件定款に違反して無効であり,Y保証協会が?の入会申込みを拒否したことは不法行為を構成すると主張して,?がY保証協会の会員たる資格を有する地位にあることの確認を求めると共に,損害賠償(慰謝料)300万円の支払を求めた事案である。
第1審(東京地判平成14・5・14平成13年20551号判例MASTER2002−05−14−0011)は,?会員である資格を有する地位にあることの確認請求については,直ちに会員であることの地位に直結しないから,法律上の利益がない,として却下し,(塾損害賠償請求についても,入会拒否が?に対する不法行為を構成するのは,基本的人権の保障に照らして著しく不合理であるなどの特段の事情がある場合に限られるが,本件ではそのような事情はなく,かえって,Y保証協会とA業協会とは研修等を通じた密接な業務上の関係があり,A 平成16年度5法令上の優遇措置のある社団法人の入会費格安件の合理性最高裁平成16年11月26日第=小法廷判決会の入会をY保証協会への入会資格とすることには合理性がある,と判示して棄却した。
これに対して原審(東京高判平成15・7・31判時1845号68頁)は,次のように判示し,害賠償請求を一部認容した。すなわち,?社員が法令上の優遇措置を受けるような社団法人については,目的及び事業の性質との関係で具体的に合理性のある社員資格を定められるに過ぎず,それに反した社員資格の定めは,法の下の平等を定める憲法の下の私法秩序に反することから,公序良俗に反して無効となる。そして,?Y保証協会の目的及び事業の性質からして,顧客への損害発生の危険性の有無,業者としての知識,能力,性行等を社員資格とすることは具体的な合理性が認められ盲が,A業協会の会員であることを社員資格とすることについては,Y保証協会とA業協会が別法人である以上,研修の実施や苦情処理業務の委託等は,本件入会資格要件の有無に関わらず生じうるものであるから,具体的合理性があるとは認められない。また,?社団法人の社員資格は,最重要事項として定款により定められるべきものであり,定款と実質的に異なる資格を定款施行規則等の下位規範で定めたとしても効力はない。
この原審に対してY保証協会は,公益社団法人の自律性を主張し,公序良俗違反の解釈を争って上告した。
判旨
原判決破棄,控訴棄却。
1
「保証協会の社員と宅地建物取引業に閲し取引をした者との間の取引により生じた債権については,保証協会及びその社員の負担において,上記債権の支払が担保される仕組みとなっている」から,「保証協会としては,入会を申し込む個々の宅地建物取引者の信用性,その者が関係法令を遵守する業者であるか否か等について重大な利害関係を有するものであり,上記弁済業務に係る制度を適切に運営……するために,保証協会が,その入会資格につき,上記の入会者の関係法令の遵守等の観点からの一定の資格要件を定めることには十分な合理性があるというべきである。」
2
IY保証協会とA業協会及び連合会との業務上の関係や,A業協会の会員に対する指導監督の状況からすると,「Y保証協会としては,このような関係にあるA業協会の会員であって,その指導,監督の下にある宅地建物取引業者であれば,上記研修の実施等により,入会者の関係法令の遵守等が相当程度期待し得るものとして,本件入会資格要件を定めたことが明らかである」から,「本件入会資格要件は,入会者の関係法令の遵守等の観点から定められた合理的なものというべきであり,公序良俗に違反するものとはいえない。」
3
「本件規則3条1項所定の本件入会資格要件は,本件定款所定の上記の入会の要件である『理事会の承認』を得るために不可欠な条件を,本件定款の施行について必要な事項の1つとして定めたものと解することができ,本件定款に違反するものということはできない。」
判旨賛成。
1
本判決は,社団法人の定款及び定款施行規則による社員資格の定めが,公序良俗に反しないとした初の最高裁判決であり,業務上の関係を有する他の団体への入会を要件とすることの可否に関する解釈を具体的に示した事例判決として,実務に大きな影響を与える可能性を持つものである。
2
社団法人の会員資格に関する従来の裁判例では,要件の設定や具体的審査結果について,社団法人の自律性からある程度の裁量権が認められるとされつつ,実際には,当該団体の目的,事業との関連性が個別に検討され,入会拒否や除名の合法違法が判断されてきたということができる(除名や入会拒否が合法とされたものとして,東京高判昭和25・12・28下民集1巻12号2092頁〔計理士会〕東京地判平成11・7・26判タ1029号243頁〔区医師会〕,違法とされたものとして,長野地判昭和35・10・8下民集11巻10号2086頁〔郡歯科医師会〕,広島地判昭和50・6・18判時811号87頁〔県歯科医師会〕,東京地判平成5・6・24判タ838号234頁〔アマチュア無線連盟〕,東京地八王子支判平成13・9・6判タ1116号273頁〔不動産鑑定士協会〕。
各判決については,白鳥・後掲参照)。本件入会資格要件については,定款の下位規範である定款施行規則で定められたことも原審で問題とされているが,原審の判示においても「具体的合理性」を有する審査基準が宅建業者であることに加えて定められることは公序良俗に反しないわけであるから,結局,「A業協会の会員であること」との要件自体に合理性が認められるか否かが,本件の判断を実質的に決することとなると考えてよい。
3
本件で,Y保証協会は,定款施行規則で本件入会資格要件を定めるほか,「入会審査基準」として入会申込みをしてきた者の業者としての知識,能力,性行等について実質審査を行うこととしており具体的には「入会審査基準運用に関する指針」に基づいて,行政罰,無免許営業,顧客とのトラブル違法行為,詐欺強迫等の有無等を考慮していたと主張している。Y保証協会の業務の性質上,これらの事項に係る実質的審査が公序良俗に反しないことは異論がないものと思われるが,問題は,この実質的審査の前段階として,「A業協会の会員であること」との形式的審査を行う必要があるか否かである。
実務上,宅建業の免許を受けた業者がY保証協会に入会しようとする時期は,A業協会の入会手続と同時であることが少なくないようであるから,業者としての知識,能力,性行等については,A業協会に入会しているか否かのみでは,事実上判断が困難である。したがって,本件入会資格要件は,むしろ宅建業者がY保証協会に入会した後における各種の研修や指導,さらには顧客等からの苦情処理に関して,Y保証協会がA業協会との業務上の委託,提携ないし連携関係に期待していることを,端的に示すものと考えられる。
このような観点からすれば,原審と最高裁との結論の違いは,正にこのY保証協会とA業協会との業務上の関係に対する評価が分かれたことに主要な理由があると言って差し支えないであろう。
すなわち,原審は,Y保証協会とA業協会とが「別法人」であることを強調し,あくまで保証協会が(A業協会に現実に事務を委託するか否かを問わず),.入会審査から会員に対する研修指導等を独自に実施すべきである以上,A業協会への入会の有無をもって形式的審査基準とすることは不合理であると判断しているのに対し,最高裁は,むしろY保証協会とA業協会との間に従来から業務上の密接な関係があることを前提として,Y保証協会がA業協会に,会員である宅建業者に対する指導監督等を行うことを通じて業者としての資質の向上維持を図ることを期待することに,十分な合理性があると判断しているものと考えられる。
4
したがって,原審と最高裁とのどちらに与するべきかは,要するにY保証協会の業務における「自律性」をどのように捉えるかによることとなるが,Y保証協会の業務内容が,会員業者のトラブル等における弁済業務を主とするものであり,会員業者の資質の判断に慎重を期するべきであることからすると,Y保証協会とA業協会とが別法人であるとの前提に立ったとしても,Y保証協会自身による実質的審査に加え,「第三者」からの評価としてのA業協会の入会審査を経ていることを要求することは,一概に不合理とは言えないように思われる。
また,Y保証協会に入会した後における業者としての資質の向上維持を図ることをA業協会の指導等に期待することも,業界団体に対して準公的な立場が一般に期待され,公的な規制に実質的な差が法律上設けられている業種もある ことからすれば(証取61条参照○平成18年改正により成立した金融商品取引法56条の4も同旨),必ずしも合理性を欠く判断とは言えないものと考えられる。
もっとも,A業協会の目的ないし事業内容が公的ないし準公的なものに限られていない場合には,特定の思想信条ないし目的に賛同した者に対してのみ,Y保証協会に入会することによる業法上の利益を受けることとなって不当である,との批判が生ずる可能性は否定できない0このような問題は,特定政党への政治献金に対する賛否等に関して,典型的に争われることとなる(税理士会に関する最判平成8・3・19民集50巻3号615貢参照)0
しかしながら,Y保証協会に入会することによる宅建業法上の優遇措置は,確かに宅建業者に事実上経済的利益をもたらすものではあるが,かかる優遇措置の本来の目的は,トラブルが生じた場合にぉける顧客に対する賠償金等の支払を業界全体で確実なものとすることにあると理解すべきであろから,A業協会の目的及び事業内容が完全に公的ないし準公的なものばかりでなかったとしても,これをもって「憲法の下における私法秩序に反する」ほどの不公平が生ずるとまでは言えないように思われる。 ジ1リスト(No.1324)2006・12・1
5
本件は,Y保証協会における本件定款及び本件規則に関する個別的な判断であり,かつ,前述のとおり,原審と最高裁との結論の違いも,Y保証協会とA業協会との業務上の関係に対する評価の違いに起因するものと言うことができるから,本件の一般論がどこまで他の事例に適用されるかは,本件の結論に対する評価とは別に考える必要があるであろう。
すなわち,原審も最高裁も,社団法人における入会審査基準に関しては,当該団体が一定の裁量を持つことを前提に,当該団体の目的及び事業内容との関係で合理性を有する基準を要求していることに変わりはなく,かつ,このような考え方は,前述した過去の裁判例でも一貫して維持されているものと考えられる0その意味では,本件に関して,社団法人の入会資格に関する従来からの一般的観点を確認した最高裁判決と評価することも,差し支えないように思われる。
* 本件に関する判例評釈としては,後藤元伸・民商132巻4・5号624頁,中村肇・法の支配138号90貢がある。また,原審判批として,後藤元伸・判評549号(判時1867号)11頁,白鳥公子・ジュリ1306号180貢がある。
(ほしの・ゆたか)
ジュリスト 2006.12.1 NO 1324 p125より引用
(著作権許諾無しにつき近日中に削除予定)
事実
社団法人Y保証協会(被告・被控訴人・上告人)は,訴外社団法人都道府県A業協会(以下,単に「A業協会」という)に加入する宅建業者が中心となって設立された団体であり,宅建業法の指定を受け営業保証金相当額の弁済等の業務を行っていた。A業協会及び全国A業協会連合会(以下,単に「連合会」という)は,宅建業の適正な運営を確保し健全な発達を図るため,会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とした団体であり,国土交通大臣ないし都道府県知事が,連合会ないしA業協会に対し,必要な事項に関して報告を求め,必要な指導,助言及び勧告をすることができるとされていた(宅建業74条3項・4項)。また,Y保証協会が地方に独自の組織,施設を有しないことから,取引主任者等に対する研修業務を連合会及びA業協会と共同で行っており,顧客からの苦情の解決業務等についても連合会ないしA業協会に委託するなど,両者の間には密接な業務上の関係があった。
Y保証協会の定款(以下「本件定款」という)は,会員の入会につき,「本会の会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を得なければならない」と規定し(5条・6条1項),実施細目として,「この定款の施行について必要な事項は,会長が理事会の議決を得て別に定める」と規定していた(42条)。そして,この規定に基づく定款施行規則(以下「本件規則」という)3条1項は,入会資格要件として,Y保証協会の会員は,連合会会員の所属構成員,すなわち各都道府県A業協会の会員でなければならない旨が規定されていた(以下「本件入会資格要件」という)。
宅建業者である?(原告・控訴人・被上告人)は,A業協会の会員となることなくY保証協会に対し入会の申込みをしたところ,Y保証協会は,?が本件入会資格要件を満たさないことを理由に,入会申込みを拒否する旨の決定をした。なお,保証協会の会員となった宅建業者は,宅建業法で定められた営業保証金(主たる事務所につき1000万円,その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額)の供託義務を免除され,主たる事務所につき60万円,その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額の弁済業務保証金分担金をY保証協会に納付すれば足りるとされている(宅建業25条・64条の13・64条の9第1項,宅建業令2条の4・7条)。
本件は,?がY保証協会に対し,本件入会資格要件を定めた本件規則3条1項は宅建業法及び本件定款に違反して無効であり,Y保証協会が?の入会申込みを拒否したことは不法行為を構成すると主張して,?がY保証協会の会員たる資格を有する地位にあることの確認を求めると共に,損害賠償(慰謝料)300万円の支払を求めた事案である。
第1審(東京地判平成14・5・14平成13年20551号判例MASTER2002−05−14−0011)は,?会員である資格を有する地位にあることの確認請求については,直ちに会員であることの地位に直結しないから,法律上の利益がない,として却下し,(塾損害賠償請求についても,入会拒否が?に対する不法行為を構成するのは,基本的人権の保障に照らして著しく不合理であるなどの特段の事情がある場合に限られるが,本件ではそのような事情はなく,かえって,Y保証協会とA業協会とは研修等を通じた密接な業務上の関係があり,A 平成16年度5法令上の優遇措置のある社団法人の入会費格安件の合理性最高裁平成16年11月26日第=小法廷判決会の入会をY保証協会への入会資格とすることには合理性がある,と判示して棄却した。
これに対して原審(東京高判平成15・7・31判時1845号68頁)は,次のように判示し,害賠償請求を一部認容した。すなわち,?社員が法令上の優遇措置を受けるような社団法人については,目的及び事業の性質との関係で具体的に合理性のある社員資格を定められるに過ぎず,それに反した社員資格の定めは,法の下の平等を定める憲法の下の私法秩序に反することから,公序良俗に反して無効となる。そして,?Y保証協会の目的及び事業の性質からして,顧客への損害発生の危険性の有無,業者としての知識,能力,性行等を社員資格とすることは具体的な合理性が認められ盲が,A業協会の会員であることを社員資格とすることについては,Y保証協会とA業協会が別法人である以上,研修の実施や苦情処理業務の委託等は,本件入会資格要件の有無に関わらず生じうるものであるから,具体的合理性があるとは認められない。また,?社団法人の社員資格は,最重要事項として定款により定められるべきものであり,定款と実質的に異なる資格を定款施行規則等の下位規範で定めたとしても効力はない。
この原審に対してY保証協会は,公益社団法人の自律性を主張し,公序良俗違反の解釈を争って上告した。
判旨
原判決破棄,控訴棄却。
1
「保証協会の社員と宅地建物取引業に閲し取引をした者との間の取引により生じた債権については,保証協会及びその社員の負担において,上記債権の支払が担保される仕組みとなっている」から,「保証協会としては,入会を申し込む個々の宅地建物取引者の信用性,その者が関係法令を遵守する業者であるか否か等について重大な利害関係を有するものであり,上記弁済業務に係る制度を適切に運営……するために,保証協会が,その入会資格につき,上記の入会者の関係法令の遵守等の観点からの一定の資格要件を定めることには十分な合理性があるというべきである。」
2
IY保証協会とA業協会及び連合会との業務上の関係や,A業協会の会員に対する指導監督の状況からすると,「Y保証協会としては,このような関係にあるA業協会の会員であって,その指導,監督の下にある宅地建物取引業者であれば,上記研修の実施等により,入会者の関係法令の遵守等が相当程度期待し得るものとして,本件入会資格要件を定めたことが明らかである」から,「本件入会資格要件は,入会者の関係法令の遵守等の観点から定められた合理的なものというべきであり,公序良俗に違反するものとはいえない。」
3
「本件規則3条1項所定の本件入会資格要件は,本件定款所定の上記の入会の要件である『理事会の承認』を得るために不可欠な条件を,本件定款の施行について必要な事項の1つとして定めたものと解することができ,本件定款に違反するものということはできない。」
判旨賛成。
1
本判決は,社団法人の定款及び定款施行規則による社員資格の定めが,公序良俗に反しないとした初の最高裁判決であり,業務上の関係を有する他の団体への入会を要件とすることの可否に関する解釈を具体的に示した事例判決として,実務に大きな影響を与える可能性を持つものである。
2
社団法人の会員資格に関する従来の裁判例では,要件の設定や具体的審査結果について,社団法人の自律性からある程度の裁量権が認められるとされつつ,実際には,当該団体の目的,事業との関連性が個別に検討され,入会拒否や除名の合法違法が判断されてきたということができる(除名や入会拒否が合法とされたものとして,東京高判昭和25・12・28下民集1巻12号2092頁〔計理士会〕東京地判平成11・7・26判タ1029号243頁〔区医師会〕,違法とされたものとして,長野地判昭和35・10・8下民集11巻10号2086頁〔郡歯科医師会〕,広島地判昭和50・6・18判時811号87頁〔県歯科医師会〕,東京地判平成5・6・24判タ838号234頁〔アマチュア無線連盟〕,東京地八王子支判平成13・9・6判タ1116号273頁〔不動産鑑定士協会〕。
各判決については,白鳥・後掲参照)。本件入会資格要件については,定款の下位規範である定款施行規則で定められたことも原審で問題とされているが,原審の判示においても「具体的合理性」を有する審査基準が宅建業者であることに加えて定められることは公序良俗に反しないわけであるから,結局,「A業協会の会員であること」との要件自体に合理性が認められるか否かが,本件の判断を実質的に決することとなると考えてよい。
3
本件で,Y保証協会は,定款施行規則で本件入会資格要件を定めるほか,「入会審査基準」として入会申込みをしてきた者の業者としての知識,能力,性行等について実質審査を行うこととしており具体的には「入会審査基準運用に関する指針」に基づいて,行政罰,無免許営業,顧客とのトラブル違法行為,詐欺強迫等の有無等を考慮していたと主張している。Y保証協会の業務の性質上,これらの事項に係る実質的審査が公序良俗に反しないことは異論がないものと思われるが,問題は,この実質的審査の前段階として,「A業協会の会員であること」との形式的審査を行う必要があるか否かである。
実務上,宅建業の免許を受けた業者がY保証協会に入会しようとする時期は,A業協会の入会手続と同時であることが少なくないようであるから,業者としての知識,能力,性行等については,A業協会に入会しているか否かのみでは,事実上判断が困難である。したがって,本件入会資格要件は,むしろ宅建業者がY保証協会に入会した後における各種の研修や指導,さらには顧客等からの苦情処理に関して,Y保証協会がA業協会との業務上の委託,提携ないし連携関係に期待していることを,端的に示すものと考えられる。
このような観点からすれば,原審と最高裁との結論の違いは,正にこのY保証協会とA業協会との業務上の関係に対する評価が分かれたことに主要な理由があると言って差し支えないであろう。
すなわち,原審は,Y保証協会とA業協会とが「別法人」であることを強調し,あくまで保証協会が(A業協会に現実に事務を委託するか否かを問わず),.入会審査から会員に対する研修指導等を独自に実施すべきである以上,A業協会への入会の有無をもって形式的審査基準とすることは不合理であると判断しているのに対し,最高裁は,むしろY保証協会とA業協会との間に従来から業務上の密接な関係があることを前提として,Y保証協会がA業協会に,会員である宅建業者に対する指導監督等を行うことを通じて業者としての資質の向上維持を図ることを期待することに,十分な合理性があると判断しているものと考えられる。
4
したがって,原審と最高裁とのどちらに与するべきかは,要するにY保証協会の業務における「自律性」をどのように捉えるかによることとなるが,Y保証協会の業務内容が,会員業者のトラブル等における弁済業務を主とするものであり,会員業者の資質の判断に慎重を期するべきであることからすると,Y保証協会とA業協会とが別法人であるとの前提に立ったとしても,Y保証協会自身による実質的審査に加え,「第三者」からの評価としてのA業協会の入会審査を経ていることを要求することは,一概に不合理とは言えないように思われる。
また,Y保証協会に入会した後における業者としての資質の向上維持を図ることをA業協会の指導等に期待することも,業界団体に対して準公的な立場が一般に期待され,公的な規制に実質的な差が法律上設けられている業種もある ことからすれば(証取61条参照○平成18年改正により成立した金融商品取引法56条の4も同旨),必ずしも合理性を欠く判断とは言えないものと考えられる。
もっとも,A業協会の目的ないし事業内容が公的ないし準公的なものに限られていない場合には,特定の思想信条ないし目的に賛同した者に対してのみ,Y保証協会に入会することによる業法上の利益を受けることとなって不当である,との批判が生ずる可能性は否定できない0このような問題は,特定政党への政治献金に対する賛否等に関して,典型的に争われることとなる(税理士会に関する最判平成8・3・19民集50巻3号615貢参照)0
しかしながら,Y保証協会に入会することによる宅建業法上の優遇措置は,確かに宅建業者に事実上経済的利益をもたらすものではあるが,かかる優遇措置の本来の目的は,トラブルが生じた場合にぉける顧客に対する賠償金等の支払を業界全体で確実なものとすることにあると理解すべきであろから,A業協会の目的及び事業内容が完全に公的ないし準公的なものばかりでなかったとしても,これをもって「憲法の下における私法秩序に反する」ほどの不公平が生ずるとまでは言えないように思われる。 ジ1リスト(No.1324)2006・12・1
5
本件は,Y保証協会における本件定款及び本件規則に関する個別的な判断であり,かつ,前述のとおり,原審と最高裁との結論の違いも,Y保証協会とA業協会との業務上の関係に対する評価の違いに起因するものと言うことができるから,本件の一般論がどこまで他の事例に適用されるかは,本件の結論に対する評価とは別に考える必要があるであろう。
すなわち,原審も最高裁も,社団法人における入会審査基準に関しては,当該団体が一定の裁量を持つことを前提に,当該団体の目的及び事業内容との関係で合理性を有する基準を要求していることに変わりはなく,かつ,このような考え方は,前述した過去の裁判例でも一貫して維持されているものと考えられる0その意味では,本件に関して,社団法人の入会資格に関する従来からの一般的観点を確認した最高裁判決と評価することも,差し支えないように思われる。
* 本件に関する判例評釈としては,後藤元伸・民商132巻4・5号624頁,中村肇・法の支配138号90貢がある。また,原審判批として,後藤元伸・判評549号(判時1867号)11頁,白鳥公子・ジュリ1306号180貢がある。
(ほしの・ゆたか)
|
|
|
|
コメント(1)
長い....
判決は理解できるけど、実際問題としては、いずれも天下り団体になって、組織の理事とかがたいした仕事をしないで莫大な報酬と退職金をもらっているとしたら、会員でなくても疑問を感じる人は出ると思います。
本当に、国民と業者のための組織か、一部の既得権を維持するためだけの組織か、国民や弱いものを搾取するための組織か、法廷では裁かれない裏の現実があると思います。
たとえば、アマチュア無線。技術基準適合のシールを貼るだけで、某法人にお金が転がり込む。しかし、国民として考えるべきなのは、そもそも、そのような制度が必要なのかということです。設計図を見ただけで、その無線機から有害な電波が出ているかどうかを判断することは不可能です。しかし、現実は、書類の審査だけで手数料が取られています。なくせないのは、その手数料で潤っている人がいるからです。
この判決の事例でも、問題提起した人は、単なるゴネ屋ではなく、組織的な利権構造に納得できなかったのかもしれません。だとしたら、表向きは形式的に間違っていない利権構造に対して、司法は何もできないことになります。残念です。
もちろん、宅建業者のことについては、私も知りませんから、このコメントが的外れになっていたら申し訳ございません。
判決は理解できるけど、実際問題としては、いずれも天下り団体になって、組織の理事とかがたいした仕事をしないで莫大な報酬と退職金をもらっているとしたら、会員でなくても疑問を感じる人は出ると思います。
本当に、国民と業者のための組織か、一部の既得権を維持するためだけの組織か、国民や弱いものを搾取するための組織か、法廷では裁かれない裏の現実があると思います。
たとえば、アマチュア無線。技術基準適合のシールを貼るだけで、某法人にお金が転がり込む。しかし、国民として考えるべきなのは、そもそも、そのような制度が必要なのかということです。設計図を見ただけで、その無線機から有害な電波が出ているかどうかを判断することは不可能です。しかし、現実は、書類の審査だけで手数料が取られています。なくせないのは、その手数料で潤っている人がいるからです。
この判決の事例でも、問題提起した人は、単なるゴネ屋ではなく、組織的な利権構造に納得できなかったのかもしれません。だとしたら、表向きは形式的に間違っていない利権構造に対して、司法は何もできないことになります。残念です。
もちろん、宅建業者のことについては、私も知りませんから、このコメントが的外れになっていたら申し訳ございません。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
MIXI 行政書士連合会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
MIXI 行政書士連合会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
困ったときには