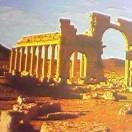ユング心理学研究会からのお知らせです。
==========
【参加無料・オンライン開催】
ユングスタディ忘年会企画
「S.シュピールライン『生成の原因としての破壊』を読む」
.
.
本年度ユングスタディの忘年会企画では、前半はシュピールラインの論文「生成の原因としての破壊」を読み、後半では質疑応答を含めた交流会を行いたいと思います。
.
ザビーナ・シュピールライン(1885-1942)はロシア系ユダヤ人の女性で、1904年にヒステリー状態で、ユングが医長代理を務めていたチューリッヒ近郊ブルクヘルツリ精神病院に緊急入院しました。そこで、ユング自身において初となる精神分析的治療を施した最初の患者となります。そこから二人は、医者と患者との関係を超えた愛人関係へと至ります。関係が表沙汰となって、愛と苦しみに満ちた二人の関係が解消した後、シュピールラインはフロイト門下で精神分析家となります。最後はロシアへと戻りますが、そこでヒトラーによるホロコーストの犠牲となって命を落とします。
ユングの愛人としてばかり語られてきた彼女ですが、近年では研究が進み、その先駆的な業績の再評価や、女性としての生き方への注目がされています。クローネンバーグ監督による映画『危険なメソッド』(2011)など、様々な小説や戯曲でも取り上げられてきています。
.
ザビーナ・シュピールラインの論文「生成の原因としての破壊」は、ユングとの関係が解消した頃に書かれた論文です。フロイトは後期において「生の欲動と死の欲動」という概念を導入しますが、この概念を先取りしていたのが、まさにこの「生成の原因としての破壊」でありました。
この論文は、ユングとの破滅的な性愛関係の苦しみから生まれた、ザビーナ自身の自己受容の過程が反映されていると言われます。また、かつての愛人ユングへのラブレターであるとともに、ユングに対する決別の宣言でもある、とも言われたりします。
愛の喜びの中で、私たちはなぜ不安に苛まれるのか。愛はなぜ私たち自身を破壊してくのか。その破壊を通して、私たちには何が生まれるのか。ザビーナの問いかけの生々しさと洞察の深さが、読む者の心を強く掴む、まさに珠玉の論文と言えるでしょう。
.
今期のユングスタディでは、ユングによる『分析心理学セミナー』を読み進めてきましたが、そこでの大きなテーマのひとつは、無意識の中にある生成と破壊の両側面の存在でした。「生成の原因としての破壊」は、まさにそこに対応する内容になっています。シュピールラインの側からユングを見ることで、ユング自身が語らなかったユングの姿も見ることができるように思います。
.
.
今回の忘年会企画は、zoomオンラインのみでの開催となります。参加費は無料ですので、お気楽にご参加頂ければと思います。参加申し込み方法は、右の無料チケットを取得していただくか、事務局宛にメールで申し込みをするか、になります。
開始時間はいつもより一時間遅い20時からとなりますので、ご注意ください。
■ 主催:ユング心理学研究会 http://
■ スタディ参加申し込みURL https:/
■参加申し込み用のメールアドレス:
研究会事務局 jungtokyo_info@yahoo.co.jp
※セミナー時に撮影した写真を当研究会のホームページやFacebook等のソーシャルメディアに公開する場合があります。あらかじめご了承ください。
※当会Facebookコミュニティ(詳細はこちらをご覧ください):
https:/
==========
【参加無料・オンライン開催】
ユングスタディ忘年会企画
「S.シュピールライン『生成の原因としての破壊』を読む」
.
.
本年度ユングスタディの忘年会企画では、前半はシュピールラインの論文「生成の原因としての破壊」を読み、後半では質疑応答を含めた交流会を行いたいと思います。
.
ザビーナ・シュピールライン(1885-1942)はロシア系ユダヤ人の女性で、1904年にヒステリー状態で、ユングが医長代理を務めていたチューリッヒ近郊ブルクヘルツリ精神病院に緊急入院しました。そこで、ユング自身において初となる精神分析的治療を施した最初の患者となります。そこから二人は、医者と患者との関係を超えた愛人関係へと至ります。関係が表沙汰となって、愛と苦しみに満ちた二人の関係が解消した後、シュピールラインはフロイト門下で精神分析家となります。最後はロシアへと戻りますが、そこでヒトラーによるホロコーストの犠牲となって命を落とします。
ユングの愛人としてばかり語られてきた彼女ですが、近年では研究が進み、その先駆的な業績の再評価や、女性としての生き方への注目がされています。クローネンバーグ監督による映画『危険なメソッド』(2011)など、様々な小説や戯曲でも取り上げられてきています。
.
ザビーナ・シュピールラインの論文「生成の原因としての破壊」は、ユングとの関係が解消した頃に書かれた論文です。フロイトは後期において「生の欲動と死の欲動」という概念を導入しますが、この概念を先取りしていたのが、まさにこの「生成の原因としての破壊」でありました。
この論文は、ユングとの破滅的な性愛関係の苦しみから生まれた、ザビーナ自身の自己受容の過程が反映されていると言われます。また、かつての愛人ユングへのラブレターであるとともに、ユングに対する決別の宣言でもある、とも言われたりします。
愛の喜びの中で、私たちはなぜ不安に苛まれるのか。愛はなぜ私たち自身を破壊してくのか。その破壊を通して、私たちには何が生まれるのか。ザビーナの問いかけの生々しさと洞察の深さが、読む者の心を強く掴む、まさに珠玉の論文と言えるでしょう。
.
今期のユングスタディでは、ユングによる『分析心理学セミナー』を読み進めてきましたが、そこでの大きなテーマのひとつは、無意識の中にある生成と破壊の両側面の存在でした。「生成の原因としての破壊」は、まさにそこに対応する内容になっています。シュピールラインの側からユングを見ることで、ユング自身が語らなかったユングの姿も見ることができるように思います。
.
.
今回の忘年会企画は、zoomオンラインのみでの開催となります。参加費は無料ですので、お気楽にご参加頂ければと思います。参加申し込み方法は、右の無料チケットを取得していただくか、事務局宛にメールで申し込みをするか、になります。
開始時間はいつもより一時間遅い20時からとなりますので、ご注意ください。
■ 主催:ユング心理学研究会 http://
■ スタディ参加申し込みURL https:/
■参加申し込み用のメールアドレス:
研究会事務局 jungtokyo_info@yahoo.co.jp
※セミナー時に撮影した写真を当研究会のホームページやFacebook等のソーシャルメディアに公開する場合があります。あらかじめご了承ください。
※当会Facebookコミュニティ(詳細はこちらをご覧ください):
https:/
|
|
|
|
コメント(2)
ユング心理学研究会から、忘年会企画のご報告です。
今年も宜しくお願い申し上げます。
**********
12月17日【忘年会企画】「S.シュピールライン『生成の原因としての破壊』を読む」
.
すでに昨年の話ではありますが、忘年会企画として行った「S.シュピールライン『生成の原因としての破壊』を読む」のご報告です。
.
令和2年度の忘年会企画では、前半にシュピールラインの「生成の原因としての破壊」を読み、後半では質疑応答を含めた交流会を行いました。今期スタディでの大きなテーマのひとつは、無意識の中にある生成と破壊の両側面の存在でしたが、「生成の原因としての破壊」は、まさにそこと呼応する内容になっています。
.
ザビーナ・シュピールライン(1885-1942)はロシア系ユダヤ人の女性で、1904年、ユングが医長代理を務めていたチューリッヒ近郊ブルクヘルツリ精神病院に、ヒステリー状態で緊急入院しました。ザビーナはそこで、ユング自身が初めて精神分析的治療を施した最初の患者となります。そこから二人は、医者と患者との関係を超えた愛人関係へと至ります。この関係はユングにとって、アニマや影といった概念についての大きな示唆となったと言われています。
関係が表沙汰となって、愛と苦しみに満ちた二人の関係が解消した後、シュピールラインはフロイト門下で精神分析家となります。その後はジュネーブでのピアジェとの児童心理研究などを経て、最後はロシア革命後のソ連へと戻りますが、そこでヒトラー侵攻の犠牲となり命を落とします。
ユングの愛人としてばかり語られてきた彼女ですが、近年では研究が進み、その先駆的な業績の再評価や、女性としての生き方への注目がされています。クローネンバーグ監督による映画『危険なメソッド』(2011)など、様々な創作でも取り上げられてきています。
.
ザビーナ・シュピールラインの「生成の原因としての破壊」(1912)は、ユングとの関係が解消した頃に書かれた論文で、後期フロイトにおける「生の欲動と死の欲動」概念を先取りしていたとされます。この論文には、ユングとの破滅的な性愛関係の苦しみから生まれた、ザビーナ自身の自己受容の過程が反映されていると言われます。
愛の喜びの中で、私たちはなぜ不安に苛まれるのか。愛はなぜ私たち自身を破壊してくのか。その破壊を通して、私たちには何が生まれるのか。ザビーナの問いかけの生々しさと洞察の深さが、読む者の心を強く掴みます。
.
ザビーナはこの問いに、自己保存欲動と種族保存欲動との関係を軸に考察を行っていきます。自己保存欲動は、人間が個人へと分化する衝動で、個人としての自分を維持するように働きます。これに対し、種族保存欲動は性行動を通して子孫を残していくとともに、個体としての死を迎えて次世代につないでいく衝動です。
種族保存欲動の現れは、分化した個人を再び種族の集合的レベルに戻すものなので、個人はそれを死の観念として、不安や脅威に受け取ります。しかし「愛」の中で個人が溶解されるとき、それは死や破壊であると同時に、新たな分化としての自己肯定、自己生命となる、とザビーナは言います。これは単なる自我の死ではなくて、自我の新しいあり方に至るための自己破壊です。
ザビーナはこの論文を通して、かつての愛人ユングに対し、「二人の愛の中で私は死に、新たな私になったのだ」と伝えたかったのかもしれません。
.
またザビーナは、「私」の体験が「私たち」の体験へと変わる際に、祖先から受け継いだ象徴的イメージが重要な役割を果たすことも指摘しています。この祖先から受け継いだイメージとは、要するに元型的イメージのことになりますが、この論文の時点ではまだ「元型」という用語をユングは使っていません。自我のモードの変化への元型的象徴が果たす機能については、改めて注目してよいかと思います。
.
ザビーナとの一連の事柄の中でのユングの言動には、正直なところ幻滅させられる部分もあります。とはいえ、コンプレックスや劣等機能が働くところ、誰であってもそのようなものかもしれない、ということは考える必要はあるでしょう。
また、今回のセミナーの中では、従姉妹の霊媒ヘリーに関連する経緯についてと同様、ザビーナとの関係に関わっていたはずの部分で語られていないことも多いです。プライベートなことなので話ができないのは理解できるとしても、今日においては、ユングが多かれ少なかれ「信頼できない語り手」であることを念頭に置く必要もあるでしょう。
今年も宜しくお願い申し上げます。
**********
12月17日【忘年会企画】「S.シュピールライン『生成の原因としての破壊』を読む」
.
すでに昨年の話ではありますが、忘年会企画として行った「S.シュピールライン『生成の原因としての破壊』を読む」のご報告です。
.
令和2年度の忘年会企画では、前半にシュピールラインの「生成の原因としての破壊」を読み、後半では質疑応答を含めた交流会を行いました。今期スタディでの大きなテーマのひとつは、無意識の中にある生成と破壊の両側面の存在でしたが、「生成の原因としての破壊」は、まさにそこと呼応する内容になっています。
.
ザビーナ・シュピールライン(1885-1942)はロシア系ユダヤ人の女性で、1904年、ユングが医長代理を務めていたチューリッヒ近郊ブルクヘルツリ精神病院に、ヒステリー状態で緊急入院しました。ザビーナはそこで、ユング自身が初めて精神分析的治療を施した最初の患者となります。そこから二人は、医者と患者との関係を超えた愛人関係へと至ります。この関係はユングにとって、アニマや影といった概念についての大きな示唆となったと言われています。
関係が表沙汰となって、愛と苦しみに満ちた二人の関係が解消した後、シュピールラインはフロイト門下で精神分析家となります。その後はジュネーブでのピアジェとの児童心理研究などを経て、最後はロシア革命後のソ連へと戻りますが、そこでヒトラー侵攻の犠牲となり命を落とします。
ユングの愛人としてばかり語られてきた彼女ですが、近年では研究が進み、その先駆的な業績の再評価や、女性としての生き方への注目がされています。クローネンバーグ監督による映画『危険なメソッド』(2011)など、様々な創作でも取り上げられてきています。
.
ザビーナ・シュピールラインの「生成の原因としての破壊」(1912)は、ユングとの関係が解消した頃に書かれた論文で、後期フロイトにおける「生の欲動と死の欲動」概念を先取りしていたとされます。この論文には、ユングとの破滅的な性愛関係の苦しみから生まれた、ザビーナ自身の自己受容の過程が反映されていると言われます。
愛の喜びの中で、私たちはなぜ不安に苛まれるのか。愛はなぜ私たち自身を破壊してくのか。その破壊を通して、私たちには何が生まれるのか。ザビーナの問いかけの生々しさと洞察の深さが、読む者の心を強く掴みます。
.
ザビーナはこの問いに、自己保存欲動と種族保存欲動との関係を軸に考察を行っていきます。自己保存欲動は、人間が個人へと分化する衝動で、個人としての自分を維持するように働きます。これに対し、種族保存欲動は性行動を通して子孫を残していくとともに、個体としての死を迎えて次世代につないでいく衝動です。
種族保存欲動の現れは、分化した個人を再び種族の集合的レベルに戻すものなので、個人はそれを死の観念として、不安や脅威に受け取ります。しかし「愛」の中で個人が溶解されるとき、それは死や破壊であると同時に、新たな分化としての自己肯定、自己生命となる、とザビーナは言います。これは単なる自我の死ではなくて、自我の新しいあり方に至るための自己破壊です。
ザビーナはこの論文を通して、かつての愛人ユングに対し、「二人の愛の中で私は死に、新たな私になったのだ」と伝えたかったのかもしれません。
.
またザビーナは、「私」の体験が「私たち」の体験へと変わる際に、祖先から受け継いだ象徴的イメージが重要な役割を果たすことも指摘しています。この祖先から受け継いだイメージとは、要するに元型的イメージのことになりますが、この論文の時点ではまだ「元型」という用語をユングは使っていません。自我のモードの変化への元型的象徴が果たす機能については、改めて注目してよいかと思います。
.
ザビーナとの一連の事柄の中でのユングの言動には、正直なところ幻滅させられる部分もあります。とはいえ、コンプレックスや劣等機能が働くところ、誰であってもそのようなものかもしれない、ということは考える必要はあるでしょう。
また、今回のセミナーの中では、従姉妹の霊媒ヘリーに関連する経緯についてと同様、ザビーナとの関係に関わっていたはずの部分で語られていないことも多いです。プライベートなことなので話ができないのは理解できるとしても、今日においては、ユングが多かれ少なかれ「信頼できない語り手」であることを念頭に置く必要もあるでしょう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ユング心理学研究会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ユング心理学研究会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82539人
- 2位
- 酒好き
- 170702人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90062人