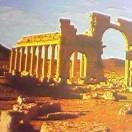震災以降ご無沙汰しております。
今期のテーマ「芸術と言葉」に関係するコラムを数々の国際コンクールで上位入賞をされたピアニストでピアノ講師の辰巳京子さんとともに書きました(私は文章を補ったり、接続詞を変えたくらいですが)。
ご参考までに。
1.芸術の最大の楽しみ
“何がおこるかわからない”
これが芸術の最大の楽しみなのではないでしょうか。
だから「どうなってもいい」のです。
もちろん、努力をせずに曲を弾いていいというわけでも、好き勝手に弾いていいというわけでもありません。投げやりになってよいはずもありません。
そうではなくて、自分にできること、すべてをやりつくした上で「すべてを手放す」ことで自分の想像以上の結果を得られることができるのです。
舞台が怖いのは、自然なことなのです。なぜなら、想像もつかない自分を発見するかもしれないのですから。
ところが、私たちはどうしてもどうにかして「安心」を手に入れようとしてしまいます。
だから、曲がうまく破綻なく弾けるように練習します。そして練習すればするほど心配になって「さらに完璧に」弾けるように長時間練習を重ねます。
有機的な練習であれば、いくら時間をかけても問題はないと思います。
ただ、たいていの練習の場合はからだが疲労して、思うようにからだが動かなくなってしまいます。心もやっぱり疲労して、「新しい何か」を追及する元気がなくなってしまうのです。
「なんとか無事に弾きとおせますように」 このことは誰もが1度は思った事があるのではないでしょうか。
私自身もつい練習をしすぎて、本番時に疲労困憊な状態になってしまうことも何度かありました。
2.有機的な練習
では有機的な練習とはなんでしょうか?
まず次のような先入観を捨て去りましょう。
曲を「このような曲だ」とか
「この速さで弾かなければならない」とか
「このように解釈すべきだ」
これらの固定的な考えをいちど手放してください。
自分の小さな世界の中だけで曲を判断して弾いても、新しい発見はありません。
また 自分の小さな世界から出ていくために、先生の下で習うことは、必要不可欠ですし、重要です。しかし、先生の「言いなり」になってはいけません。
そうではなくて、練習すべきことは、すべて自分の出す「音」を聴いて、どのように反応するのかをすべての瞬間瞬間に選択し続けることなのです。
共演者が居るときは、その場で発生した音にどのように反応するかが大切です。
また、「どのように弾きたいのか」という自分の考えがはっきりしている場合には、そのように「反応したくなる音」をどのようにしてを出すのかを考えるべきです。
普通に人と会話をするときだって、「面白い会話」は相手の反応と自分の反応が呼応したときに「楽しい」と感じるでしょう?
台詞のあるお芝居も「棒読み」だったり、いかにも「台詞をしゃべっている」ようで、相手とまったく意志の疎通がないような話し方では、「面白かった」とは言い難いお芝居ですよね。
それは演奏家であっても、同じはずです。特にピアニストはどうしても他の楽器よりも「独りよがり」になってしまいがちです。自己完結しすぎてしまう傾向にあるように思います。
だからこそ、自分が相手と会話するように、楽器と対話し、今そこにある音と対話をする練習を心掛けましょう。
テクニックがあるから曲が弾けるようになるのではなく、自分が曲に反応するからテクニックがついていくのです。
演奏家にとって、アレクサンダーテクニークやボディマッピングが役に立つのも、自分が曲や音に反応できるようになれるからです。 そして、少し大げさに言えば、失敗することが悪いと思わなくなれるからです。
だから、どんなときも指が動くことだけを目的に練習をするべきではないのです。
たとえ指が動くようになったとしても、そこに指を動かす「根拠」がなければ、感動的な音楽はけっして生まれません。私たちが曲や音にどのくらい反応できるか、そのことこそが指を動かす「根拠」になるのです。
こんなことは当たり前なことなのに、私たちは舞台を怖れるあまり、あるいは本番で物理的な破綻を怖れるあまり、普段の練習の時から、そして本番の時に、その時その場で曲や音に反応することを放棄して、いつ聞いても、まるで版を押したような、ワンパターンな演奏に逃げる誘惑に駆られがちです。
しかし、そこには、演奏家にとっても、聴衆にとっても、もはや芸術の本当の楽しみはありません。
ここであなたに問います。あなたが本当にやりたいのはなんでしょうか? 生身の血の通った人間の”演奏”ですか? それともCDの真似(まね)ですか?
いつでも版を押したような演奏には、安心さや冷静さは不可欠でしょう。でも、それはあなたが本当にやりたいことですか?
音楽を追求するわくわく感、表現する喜び、それこそがあなたのやりたいことではありませんか?
3.本番当日にできること
私たちは、いつも理想的な環境で演奏できるわけではありません。天候によって楽器の状態は変わるし、聴衆が入っているときといないときとでは音の響き方もまったく違います。ですので、繰り返しになりますが、反応できることがとても重要になります。
そのためにも、本番当日は次のことをしましょう。
(1)早めに会場に入る
演奏をするときは、その場所とピアノ、環境と自分がうまく対話できるように早目に会場に入って慣れておく必要があります。控え室から舞台までの距離とか、ライトをつけたとき客席がどのように見えるかとか・・・その空間が自分とできるだけ近しい存在になるようにしておきましょう。
(2)リハーサルをしすぎない
さて、ここで注意することがあります。
会場入りから本番までにかなり余裕があり、リハーサルがたくさんできるときには、どうしても時間いっぱいいっぱい弾いて、「安心」しようとしてしまいます。
そんなときこそ、本番のその時まで体力をとっておくことにどうぞ注意してください。
自分の思っている以上に本番の日は神経が細かくなっていて、いつも以上に体力を消耗しやすくなることが多いのです。
(3)じゅうぶんな食事と、じゅうぶんな休息
きちんと食事をとり、疲れすぎないように気をつけましょう。
(4)手放すこと
やることはやった。だから「もうどうなってもいい」のです。
自分を許すことで、予想以上の結果を得られることがあるのです。
4.結び
本番で緊張すること、怖いことは当然です。
ですから恐れず緊張しましょう。そして堂々と舞台に出てください。
そして本当にその曲に、その音に反応して。オーケストラと共演するときには、オケの音を聞いて調和するように。
曲に、音に反応する練習を積んだあなたは、本番では練習とはまるで違うことをやりだしたり、やりたくなったりするかもしれません。
さあ、楽しい音楽の時間の始まりです。
執筆:ピアニスト・ピアノ演奏教師 辰巳京子 アレクサンダーテクニーク教師 かわかみひろひこ
下記より引用
http://
今期のテーマ「芸術と言葉」に関係するコラムを数々の国際コンクールで上位入賞をされたピアニストでピアノ講師の辰巳京子さんとともに書きました(私は文章を補ったり、接続詞を変えたくらいですが)。
ご参考までに。
1.芸術の最大の楽しみ
“何がおこるかわからない”
これが芸術の最大の楽しみなのではないでしょうか。
だから「どうなってもいい」のです。
もちろん、努力をせずに曲を弾いていいというわけでも、好き勝手に弾いていいというわけでもありません。投げやりになってよいはずもありません。
そうではなくて、自分にできること、すべてをやりつくした上で「すべてを手放す」ことで自分の想像以上の結果を得られることができるのです。
舞台が怖いのは、自然なことなのです。なぜなら、想像もつかない自分を発見するかもしれないのですから。
ところが、私たちはどうしてもどうにかして「安心」を手に入れようとしてしまいます。
だから、曲がうまく破綻なく弾けるように練習します。そして練習すればするほど心配になって「さらに完璧に」弾けるように長時間練習を重ねます。
有機的な練習であれば、いくら時間をかけても問題はないと思います。
ただ、たいていの練習の場合はからだが疲労して、思うようにからだが動かなくなってしまいます。心もやっぱり疲労して、「新しい何か」を追及する元気がなくなってしまうのです。
「なんとか無事に弾きとおせますように」 このことは誰もが1度は思った事があるのではないでしょうか。
私自身もつい練習をしすぎて、本番時に疲労困憊な状態になってしまうことも何度かありました。
2.有機的な練習
では有機的な練習とはなんでしょうか?
まず次のような先入観を捨て去りましょう。
曲を「このような曲だ」とか
「この速さで弾かなければならない」とか
「このように解釈すべきだ」
これらの固定的な考えをいちど手放してください。
自分の小さな世界の中だけで曲を判断して弾いても、新しい発見はありません。
また 自分の小さな世界から出ていくために、先生の下で習うことは、必要不可欠ですし、重要です。しかし、先生の「言いなり」になってはいけません。
そうではなくて、練習すべきことは、すべて自分の出す「音」を聴いて、どのように反応するのかをすべての瞬間瞬間に選択し続けることなのです。
共演者が居るときは、その場で発生した音にどのように反応するかが大切です。
また、「どのように弾きたいのか」という自分の考えがはっきりしている場合には、そのように「反応したくなる音」をどのようにしてを出すのかを考えるべきです。
普通に人と会話をするときだって、「面白い会話」は相手の反応と自分の反応が呼応したときに「楽しい」と感じるでしょう?
台詞のあるお芝居も「棒読み」だったり、いかにも「台詞をしゃべっている」ようで、相手とまったく意志の疎通がないような話し方では、「面白かった」とは言い難いお芝居ですよね。
それは演奏家であっても、同じはずです。特にピアニストはどうしても他の楽器よりも「独りよがり」になってしまいがちです。自己完結しすぎてしまう傾向にあるように思います。
だからこそ、自分が相手と会話するように、楽器と対話し、今そこにある音と対話をする練習を心掛けましょう。
テクニックがあるから曲が弾けるようになるのではなく、自分が曲に反応するからテクニックがついていくのです。
演奏家にとって、アレクサンダーテクニークやボディマッピングが役に立つのも、自分が曲や音に反応できるようになれるからです。 そして、少し大げさに言えば、失敗することが悪いと思わなくなれるからです。
だから、どんなときも指が動くことだけを目的に練習をするべきではないのです。
たとえ指が動くようになったとしても、そこに指を動かす「根拠」がなければ、感動的な音楽はけっして生まれません。私たちが曲や音にどのくらい反応できるか、そのことこそが指を動かす「根拠」になるのです。
こんなことは当たり前なことなのに、私たちは舞台を怖れるあまり、あるいは本番で物理的な破綻を怖れるあまり、普段の練習の時から、そして本番の時に、その時その場で曲や音に反応することを放棄して、いつ聞いても、まるで版を押したような、ワンパターンな演奏に逃げる誘惑に駆られがちです。
しかし、そこには、演奏家にとっても、聴衆にとっても、もはや芸術の本当の楽しみはありません。
ここであなたに問います。あなたが本当にやりたいのはなんでしょうか? 生身の血の通った人間の”演奏”ですか? それともCDの真似(まね)ですか?
いつでも版を押したような演奏には、安心さや冷静さは不可欠でしょう。でも、それはあなたが本当にやりたいことですか?
音楽を追求するわくわく感、表現する喜び、それこそがあなたのやりたいことではありませんか?
3.本番当日にできること
私たちは、いつも理想的な環境で演奏できるわけではありません。天候によって楽器の状態は変わるし、聴衆が入っているときといないときとでは音の響き方もまったく違います。ですので、繰り返しになりますが、反応できることがとても重要になります。
そのためにも、本番当日は次のことをしましょう。
(1)早めに会場に入る
演奏をするときは、その場所とピアノ、環境と自分がうまく対話できるように早目に会場に入って慣れておく必要があります。控え室から舞台までの距離とか、ライトをつけたとき客席がどのように見えるかとか・・・その空間が自分とできるだけ近しい存在になるようにしておきましょう。
(2)リハーサルをしすぎない
さて、ここで注意することがあります。
会場入りから本番までにかなり余裕があり、リハーサルがたくさんできるときには、どうしても時間いっぱいいっぱい弾いて、「安心」しようとしてしまいます。
そんなときこそ、本番のその時まで体力をとっておくことにどうぞ注意してください。
自分の思っている以上に本番の日は神経が細かくなっていて、いつも以上に体力を消耗しやすくなることが多いのです。
(3)じゅうぶんな食事と、じゅうぶんな休息
きちんと食事をとり、疲れすぎないように気をつけましょう。
(4)手放すこと
やることはやった。だから「もうどうなってもいい」のです。
自分を許すことで、予想以上の結果を得られることがあるのです。
4.結び
本番で緊張すること、怖いことは当然です。
ですから恐れず緊張しましょう。そして堂々と舞台に出てください。
そして本当にその曲に、その音に反応して。オーケストラと共演するときには、オケの音を聞いて調和するように。
曲に、音に反応する練習を積んだあなたは、本番では練習とはまるで違うことをやりだしたり、やりたくなったりするかもしれません。
さあ、楽しい音楽の時間の始まりです。
執筆:ピアニスト・ピアノ演奏教師 辰巳京子 アレクサンダーテクニーク教師 かわかみひろひこ
下記より引用
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
ユング心理学研究会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ユング心理学研究会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82541人
- 2位
- 酒好き
- 170694人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90064人