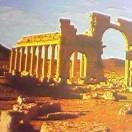ユング心理学の理論(2)元型論その1/4編
http://
ユング心理学の理論(2)元型論その2/4
http://
ユング心理学の理論(2)元型論その3/4
http://
6.ウィルバー『万物の歴史』のユング評について
最近再版された
ユングの元型は、大部分、人間の意識の魔術的および神話的次元にある基本的な、集合的に引き継がれてきたイメージや形象であり、そしてこれらは心霊および微細領域における発達とけっして混同されるべきない。集合的であることは必ずしもトランスパーソナルではない。元型の大部分は意識における退行的な引き手であり、より高い発達のまわりの鉛の錘りであって、たんに包含されるべきではなく、まさに克服されるべき当のものである。ほとんどのユング的元型は前パーソナル的、若干はパーソナル(エゴ、ペルソナ)、若干は漠然とトランスパーソナル的(老賢者、セルフ、マンダラ)。トランスパーソナル的な元型にしても、トランスパーソナルな次元について知っているものに比べて決定的に貧血気味である。チベット仏教のマハームードラ―に詳しく記述されているようなトランスパーソナルな意識の進化段階のどれ一つも、世界の古典的神話のどれにも現れていない。ユングは集合的に引き継がれている三つの次元の差異化を怠っている。「真の」元型とは、原初的な<空>から現れる最初の形態のことであり、それは深遠な存在論的リアリティ、微細世界空間から出てくるものである。(P.318-326)
万物との歴史 再版されました。
後期の元型論について、ウィルバーは理解していないのではないかなと。ウィルバーが言っていることって、逆にウィルバーが後期に言っているのではないかと。
言っていることはある程度分かる。例えばトランスパーソナルであることと元型的であることをごっちゃにするなと。その通りなのです。元型の中にもいろいろあって、前合理的・前トランスパーソナル的な元型もあれば、パーソナルレベルの元型もあれば、トランスパーソナルレベルの元型もある。今言った発達過程にぴったり合っている。自我の形成過程は自我の確立の前の話。ぺルソナ・影はパーソナルレベルで。それ以降がトランスパーソナルレベルに関係するのだと。
確かに全部元型という言葉に入っているんですよ。これは確かにウィルバーの言っていることは合っているのですよ。
ウィルバーの言っていることで面白いことが1つありまして、これは正しいのですが、例えばチベット仏教の例を挙げますが、トランスパーソナル的な過程が事細かに書いてある。ところが、世界中のどこの神話見たって、そんなことは書いてないではないか。だから世界中の神話をユングは調べているけれど、そんなことをいくらやってもスピリチュアルなレベルには行かないだろう。これは極論ではありけれどちょっと正しいなという気がします。
例えば神話とかおとぎ話の心理は通常に人間の心理です。臨床的には重要です。けれどトランスパーソナルなレベルに行って、それより先に行くにはどうしたらよいかという話になったときに、それでは役が足りないというのは事実なんです。
それでウィルバーはそういうレベルはユングにはないと言っているのですが、ちょっと待ってください。ユングの前期は神話研究をしていましたが、ユングの後期になったら、ヨガの研究はやるは、錬金術の研究はやるは、キリスト教の研究はやるはで、言ってみればトランスパーソナルレベルの研究に切り替えているんです。内容を。自己の元型の様々な表れについてということで、『アイオーン』という本を1冊書いているほどです。
そういう研究をユングはしているのに、ユングのそのあたりの研究は貧弱であまりやっていないというのはちょっと変ではないか。これは明らかに後期の研究を読んでいないのではないかと思う、もしくはユングを判断するに当たって、ユンギアンの実際を見すぎている。ユンギアンが実際にやっていることを見て、ユング批判をしているという面がどうも強いなという印象を受けました。するどくてビシッと正しいことを言っているところと、ちょっと違うんじゃないというのが混じっていて、ちょっと気持ち悪いのですよ。
今日それこそ尾崎さんがいればね、たっぷり聞いてやろうかと思ったのですが。」
大橋さん「尾崎さんは2次会に出てこられると思います」
白田さん「そうなのですか? 逃げようかな、なんて。」
大橋さん「なにしろ本人ユング嫌いだって言っているからね」
白田さん「檜垣さんはいかがですかね? この辺りは?」
檜垣さん「白田さんの言う通りではないですか? ユングを批判していても、ユンギアンのことを言っている。」
白田さん「と私も思います。ユンギアンのことを批判するあまり、それがユングへの批判にすり替わっているのではないかという感じがする。
こうやってユングやユンギアンが発達過程について詳細に分けて研究しているのにも関わらず、こういうのを混同していると言うのはおかしいなと。明らかに分けているだろうと」
檜垣さん「僕の疑問は、このレジメに左に書いてある自我の形成過程と個性化過程のこの段階が、いわゆる発達心理学とウィルバーが言っているものと同じなのかなあと思いながら見ていた。
白田さん「だれだったかな? スガワヒロシ(講義録作成人:?)だったかな? のブログにあったのですが、ウィルバーは発達心理学にこだわりすぎているという言い方をしている。特にノイマン的な枠組みに囚われ過ぎているという言い方をしている。
鋭いと思いました。実はノイマン的なものとウィルバー的なものは似ているのです。」
檜垣さん「ほとんどいっしょだなと」
白田さん「その通りなのですよ。だから逆にウィルバーに対するユング派の批判は、発達過程に対する批判に重なることが多いのですよ。魂を大事にしろとか、精神ばかりとか。この批判とウィリバー批判は重なって来るのですよ。そういう意味で面白いと。
ウィルバーから引用したところで『前トランスパーソナル的な部分は克服されるべきだ』と。3行目からのところ。個の元型は統合するのではなく、克服されるべきだと言っているのです。この第一段階辺りに関しては。
そういうところはちょっと西洋的というか、ノイマン的というか、父殺しとか母殺しとか強いコンプレックスではないかという批判に重なって来るんです。こういうところが気になるのです。
檜垣さん「これってこのままの通りを抜いてきていらっしゃいます?」
白田さん「このへんは確かそのままです。」
檜垣さん「ウィルバーの言っている元型批判の時のこのシャドウとか神話的要素で、トランスパーソナルではない元型のところの話については、発達段階でじゃまになっているから克服しなければないというのはそういう意味で、純粋に元型についてはそういう言い方をしていない。」
白田さん「克服っていうのはどういう意味なのでしょうかね。この場合は」
檜垣さん「なんというのかな」
白田さん「私はこの辺、禅的なものを感じるんですね。」
檜垣さん「元型と元型イメージを分けなければならないと言う話ですよね。純粋な元型はイメージではないですよね」
白田さん「そうそう。」
檜垣さん「ユングは臨床心理学者だから、患者さんから聞いた話はすべて元型から得られたイメージですよね」
白田さん「はい」
檜垣さん「そういうものはその時代とかその人の持っているものとか汚れたものがいっぱいついていますよね。そういうものがいっぱい混ざっているということをウィルバーは言っている。だから克服されるべきだとウィルバーは言っている。」
白田さん「確かに本当の元型とは。。。とウィルバーも書いていますよね。けれどユングの後期の元型的イメージと元型論とをはっきり分けて論ずるような論文が出てくるのですよね。
それとウィルバーの言っていることは同じだという気がして。それなのになぜわざわざユングとは違うと言い出すのかなと。ちょっと不思議な感じがするのですよね。やはり前期の元型論のイメージが強いような気がするのです。ウィルバーにとっては。特に生物学的な意味での元型論を抜けきっていないような。元型そのものはむしろ宇宙的原理であって、そこから派生してくるものがいろいろあるのだと。そういう宇宙観をユング派示しているから、ウィルバーの結論とどこが違うのかと。
ここどうですかね? ウィルバーの研究会では議論があるのかしら? 」
檜垣さん「研究会では見たことがないですね。」
白田さん「ちょっとね。ウィルバーの考えを逆の意味で焙り出す意味でも。ちょっとこの辺は時間かけて議論する方が面白いのですけれどね。
檜垣さん「文献についてはそんなに注意していないと思いますよ。スピリチュアリティ―という意味では混乱しているからきれいに整理して議論しているのだけれど、元型についてはそんなにきれいに分析して整理はしていない。だいたいそんなにたくさん書いてはいないですよ。」
白田さん「鋭いところはあるのですよね。ユンギアンが使っているのはスピリチュアルなレベルではないとか。確かにそれはその通りなのですよ。実を言うと。私もそう思うのですよ。でも臨床家ですからね。それで正しいのですよ。」
檜垣さん「自我の形成過程の元型イメージは何歳くらいで出るかということは書いているのですかね?
白田さん「特に書いていないですね。」
檜垣さん「シュタイナーは7歳ごとに区切るではないですか? それを当てはめて見ていると、ちょうど竜殺しは思春期の時だなあと思いながら。」
白田さん「まあそうでしょうねえ。だから反抗期とかね、竜に当たるのかなと。グレートマザーなんて最初の反抗期に当たるのかなとか。そういう対応関係はある程度あるかも。
ただ人生の後半になって、課題がね。ある面では出てくることもありうるので、何歳という言い方はですね。子どもの発達過程の繰り返しがまたある。ちょっとロマン主義的な枠になってきますけれど。個体発生は系統発生を繰り返すみたいな。そういうような何かがちょっと。逆に言うとロマン主義的な思想の系統に入ることを如実に表しているということでもあるのですが。元型論のいちばんおもしろいところは発達過程論なのですよね。元型の定義なんていくらやったって、分からないですよ。」
大橋さん「石川さん。わざわざ東北は仙台からいらしたのだからなにかございませんか?」
石川さん「考えていたのですけれど。う〜ん」
白田さん「石川さん。ネットだとばんばん出てくるのに、不思議だなあ。ペルソナか?」
石川さん「どっちがペルソナか? 」
白田さん「どっちがペルソナ?」
石川さん「後期の元型がもしあるとすれば、進化はないことになると思う。初めから完成しているので。」
白田さん「ああ、よい視点ですよね」
石川さん「でも、ウィルバーなんかは、宇宙は進化すると言っています。善に向って進化するという立場ですよね。そこに違和感があるのですよね。」
白田さん「よい質問ですよね。わざとやっているかのようなよい質問。結局そこなのですよね。それがユングの後期のテーマなのです。まさにそれが。言ってみれば、死後論にも関わる。
石川さん「シェリング、ヘーゲル、ウォーロビントン(講義録作成人メモ:聞き取れず)の進化みたいな言い方をウィルバーは言っているのだけれど、生物が進化するときも、より劣ったものから優れたものに進化しているとウィルバーは言っているのだけれど、生物学的な進化論は劣ったものから進化したわけではなくて、生成変化しているだけ。」
白田さん「そうですね。」
石川さん「そこの進化という考え方も、ウィルバーは混同しているかなと。」
白田さん「仮に今の進化論を基準に考えるならば、ただ単に変化しているだけ。偶然によって。ただその時の条件によって残ったものは残って言っているだけの話だから。別に発達ではない。人間の体だって最初から設計するのであれば欠陥だらけという話も。後付けでどんどんやっているからこんなふうになる。」
(尾崎さん登場)
白田さん「逃げる算段を・・・」
大橋さん「今尾崎さんの話を。意見を聞きたいと」
黒田さん「仮に低次元から高次元に進化しても、以前のものは捨象されずに蓄積されて、含まれているのではないか?」
白田さん「何が高いか低いかという問題はありますが、なにか前段階のものがあったとして、それがユング的な発想だと消えてなくなることはない。もちろん含んでいる。けれど以前のような働き方はしない。その機能は変わる。実は次の錬金術の発達論に出て来るのですよ。精神と肉体が、○○○○(講義録作成人:聞き取れず)、一なる世界になっていくというプロセスがそれなのですよ。」
檜垣さん「発達論と価値について。積み上がってきたものに価値があるかという視点は相対論。」
黒田さん「それは考えたくない。疑問持っていないから。希望持ちたいから」
檜垣さん「発達論には価値は関係ないのですよ」
大橋さん「2次会でやってください」
白田さん「実は今の話は実在論と構造主義と関わって来るので。本当は違い自身が議論できると面白いのですけれど。
石川さんのご質問に戻るのですけれど、確かに根源的なものは変わらないのですけれど、根源的なものが現れる現れ方が微細で繊細なものになって来るのです。そういうプロセスはあると言っているのです。ユングは」
石川さん「ああ!」
白田さん「元型というものはずっとあったとしても、例えばその人の人格が発達することで、昔のアニマの働き方と今のアニマの働き方とは全然違うものになって行くとかね。世界もそうで、人が死んで歴史が進んでいく中で、今までの歴史の中でのある問題に対する課題を次なる段階ではもっと繊細に扱えるようになって、その代わり別の新しい問題も出て来て。。。神と人間との関係で、古代のヨブ記で出てきた問題がどんどん分化して、最後現代のキリスト教のマリアの被昇天に至るという、そういうプロセスなのですよね。
元型そのものは変わらないのですけれど、元型と人間との関係が変わって来るのです。より繊細に現れる。」
檜垣さん「僕の言った価値が相対的だから変わるっていうこと。発達論て価値で見ちゃうから、相対論だから、年代によって変わるよということ。それと同じ。」(講義録作成人メモ:間違えていたらゴメンナサイ。檜垣さん)
白田さん「今のは分からないのだけれどね」
石川さん「たとえばルソンの焼き物(生活雑器)が茶室に置くと価値が出て来るような。」
白田さん「そうかもしれませんね」
檜垣さん「例えばさっきの成長のある段階で、必要な元型が現れて、それによって引っ張られて、成長したら価値がなくなって、その原型は現れなくなるでしょ?」
白田さん「現れなくなると言うか、最終的には自己の統制下に入るということでしょうね。」
檜垣さん「だから現れなくなる訳だよ。」
白田さん「そういう形で現れなくなるだけで、あることはあるのですよ。別の形で現れる可能性がある」
檜垣さん「だからその人の発達段階において現れるものが変わると言う話をしたの」
白田さん「なるほど。例えばアニマにしても最初は肉体的なアニマだとしても、それが発達していくのにしたがって、智慧のアニマに変わるとかね。智慧を持った深い女性に変わるとかね。変化が出て着るとかそういうことを言っているのです」
檜垣さん「それは個人的な発達の段階によって変わるでしょ? それがさらに集合的になったら、人類と言う発達段階において、現れるものの現れ方が変わるっていうことを言いたくて」
白田さん「ああああ。そうですね。歴史のある段階になれば、言ってみれば起点そのものが違うのですものね」
檜垣さん「そうそう。」
白田さん「シンボルだって、すでに持っているわけで。」
河上素子さん「進化するとしたら、どうして歴史が繰り返すのだろうと。いろいろな音楽家がいても、現れ方が違っても、どうして似たようなことが起こるのだろうと。」
石川さん「それが元型なのですよね?」
白田さん「と言うか。現れ方の話ですよね。歴史の。」
尾崎さん「なんかそれって。らせん状になっているからじゃないかな?って気がするのですよね。一回同じようなところを通っても、1つずつ違っているような気がして。少しずつ上にあがって質が変わっているのではないですかねえ」
河上素子さん「だとしたら、目に見えて変わって来るのに本当に時間がかかる。キリストが生まれたのが2000年前ですよね。」
白田さん「幅は広がっていると思うのですよ。どんな時代でも争いはある一方で、その中から積み重ねられた精神性はある。上がっているとは思うのですよ。
そこで大きく何か変わるかどうかなんですが、ユングなんかはおそらく将来的には何か意識も世界に合わせて変わって行くのではないかとちょっと考えていると思える節があるのです。そういうのは基本的にオカルト的な思考の典型的な発想なのです。これは高橋巌さんが言ったのですけどね。このように世界そのものが変わって行くという発想は、オカルト的な発想の典型だと。」
尾崎さん「もしかしたら、本質はあまり変わらないのだけど、複雑性が増すとか、システマティックになるとかが発達の考え方みたいなのですけれど、そういうことじゃないかと思うのですよね。本質が変わらないから、同じことを繰り返しているように見えるのだけれど、私たちの意識は100年前の人たちとはちょっと違うのではないかと。より複雑になって。音楽なんかもそうでしょ?」
檜垣さん「スパイラル・ダイナミクス」
尾崎さん「そうそう。」
黒田さん「今の話って、2012年アセンションみたいのとは無縁の話と思ってよいのでしょうか?」
白田さん「私はね。ちょっと関係あると思っているのですよ。あるかというとあまり信じていないのですが、ユングの発想の中には多少なり宇宙は変わって行くという発想があるように思っています。」
黒田さん「よい方にでしょう? 今の話の文脈では?」
白田さん「ユングの価値的にはよい方でしょうね。意識と無意識との関係が変わって行くと、宇宙も変わって行くだろうという発想。
例えば子どもの虐待は今も昔もあるとして、虐待を救うシステムは今の方が発達しているではないですか? そういう意味では進んでいるのではないかと。」
尾崎さん「確かに問題も大きく見えて来ていると同時に、救い方のバリエーションも増えている。前見えなかったものが表面に見えている感じなのかなと。」
白田さん「ここら辺の話し始めるとおもしろいでしょ? ユングのスケールの話はとても面白いですよ。」
黒田さん「意識が拡張するというのもあってよいのかなと思うようになりました。完全に肯定ではないですけれど、ウィルバーの克服という文言に反発しちゃう。」
檜垣さん「今まで自分が自身だと思ってきたものと自分自身の自己を1歩引いて見て、それを自分で必要なときに取り扱い可能な機能にする。Iをmeに変えるということを含んでいる。」
白田さん「そうすると、ユングとウィルバーってあまり変わらないのではないですか?」
檜垣さん「変わらない」
白田さん「なんで批判するのだよ? なにか単純なユングに関する知識のことで、ウィルバーが間違えているのではないですかね?」
檜垣さん「そこは白田さんがさっき言った通りで、ユングではなくてユンギアンのやっていることをユングと取り違えて批判しているのだと」
大橋さん「カウンセラーの江川洋子さん。創立以来のメンバーで3年ぶり。」
江川さん「自己の成長過程の前段階で問題が大きくて、年齢年齢で出てきたものでその時向き合えなかったものが大人になってから出て来て問題が大きくなることがあって、系統立てて聞けて、私にとってすごくよかったです。ありがとうございます。」
次回予告
後期のユングのものの考え方はなんだったか? ここでは基礎的な見解を多く変えてしまったと。ここからは自己の元型というテーマに絞って行く。それはキリスト教の半面の歴史でもあって、ユングにとってのキリスト教の再生の試みでもあるし、宇宙の一元的な原理について考えるというものでもあったし、死んだ後の話にも関わって来る。ある意味オカルティックという言い方をしてもよいし。もっとも研究が進んでいないところなのですよね。私も分からないことがあるのだけれど。前期も中期も面白いのですけれど、本当は後期こそ面白い。いちばん面白いところのとっかかりのようなところを紹介できればと。
大橋さんより トランスパーソナルな課題ともいちばんかみ合う話になって来ると思うのですよね。
白田さん ユングのトランスパーソナル研究です。要するにね。
7.白田さんと尾崎さんとの対話
ウィルバーの言っていることは、後期のユングの言っていること。
あるいはユンギアンが実際にやっていることを批判している。
この点について、交流会にて白田さんがアンナさんに確認したところ、ウィルバーは後期のユングの言っていること(錬金術の研究)を理解しつつ、神秘主義と距離を置きたいので、このようにユングを批判しているのではないかという趣旨の示唆があった。
以前にウィルバーはアカデミズムの世界からは疎んじられているというお話をアンナさんから伺っていたので、講義録作成人は個人的には奇妙な思いに駆られた。
8.講義録作成人の結び
講義録作成がたいへん遅くなり、申し訳ございませんでした。
質問で議論が深くなるのはたいへん聞き応えがありました。個人的には大橋さんと檜垣さんと石川さんの発言がすごいなあと。
当日は石川さん(けろりんさん)のモヒカンが格好良かったと。特に女性たちのあいだで好評でした。今回は石川さんの新章スタートか?
以上
前へ http://
http://
ユング心理学の理論(2)元型論その2/4
http://
ユング心理学の理論(2)元型論その3/4
http://
6.ウィルバー『万物の歴史』のユング評について
最近再版された
ユングの元型は、大部分、人間の意識の魔術的および神話的次元にある基本的な、集合的に引き継がれてきたイメージや形象であり、そしてこれらは心霊および微細領域における発達とけっして混同されるべきない。集合的であることは必ずしもトランスパーソナルではない。元型の大部分は意識における退行的な引き手であり、より高い発達のまわりの鉛の錘りであって、たんに包含されるべきではなく、まさに克服されるべき当のものである。ほとんどのユング的元型は前パーソナル的、若干はパーソナル(エゴ、ペルソナ)、若干は漠然とトランスパーソナル的(老賢者、セルフ、マンダラ)。トランスパーソナル的な元型にしても、トランスパーソナルな次元について知っているものに比べて決定的に貧血気味である。チベット仏教のマハームードラ―に詳しく記述されているようなトランスパーソナルな意識の進化段階のどれ一つも、世界の古典的神話のどれにも現れていない。ユングは集合的に引き継がれている三つの次元の差異化を怠っている。「真の」元型とは、原初的な<空>から現れる最初の形態のことであり、それは深遠な存在論的リアリティ、微細世界空間から出てくるものである。(P.318-326)
万物との歴史 再版されました。
後期の元型論について、ウィルバーは理解していないのではないかなと。ウィルバーが言っていることって、逆にウィルバーが後期に言っているのではないかと。
言っていることはある程度分かる。例えばトランスパーソナルであることと元型的であることをごっちゃにするなと。その通りなのです。元型の中にもいろいろあって、前合理的・前トランスパーソナル的な元型もあれば、パーソナルレベルの元型もあれば、トランスパーソナルレベルの元型もある。今言った発達過程にぴったり合っている。自我の形成過程は自我の確立の前の話。ぺルソナ・影はパーソナルレベルで。それ以降がトランスパーソナルレベルに関係するのだと。
確かに全部元型という言葉に入っているんですよ。これは確かにウィルバーの言っていることは合っているのですよ。
ウィルバーの言っていることで面白いことが1つありまして、これは正しいのですが、例えばチベット仏教の例を挙げますが、トランスパーソナル的な過程が事細かに書いてある。ところが、世界中のどこの神話見たって、そんなことは書いてないではないか。だから世界中の神話をユングは調べているけれど、そんなことをいくらやってもスピリチュアルなレベルには行かないだろう。これは極論ではありけれどちょっと正しいなという気がします。
例えば神話とかおとぎ話の心理は通常に人間の心理です。臨床的には重要です。けれどトランスパーソナルなレベルに行って、それより先に行くにはどうしたらよいかという話になったときに、それでは役が足りないというのは事実なんです。
それでウィルバーはそういうレベルはユングにはないと言っているのですが、ちょっと待ってください。ユングの前期は神話研究をしていましたが、ユングの後期になったら、ヨガの研究はやるは、錬金術の研究はやるは、キリスト教の研究はやるはで、言ってみればトランスパーソナルレベルの研究に切り替えているんです。内容を。自己の元型の様々な表れについてということで、『アイオーン』という本を1冊書いているほどです。
そういう研究をユングはしているのに、ユングのそのあたりの研究は貧弱であまりやっていないというのはちょっと変ではないか。これは明らかに後期の研究を読んでいないのではないかと思う、もしくはユングを判断するに当たって、ユンギアンの実際を見すぎている。ユンギアンが実際にやっていることを見て、ユング批判をしているという面がどうも強いなという印象を受けました。するどくてビシッと正しいことを言っているところと、ちょっと違うんじゃないというのが混じっていて、ちょっと気持ち悪いのですよ。
今日それこそ尾崎さんがいればね、たっぷり聞いてやろうかと思ったのですが。」
大橋さん「尾崎さんは2次会に出てこられると思います」
白田さん「そうなのですか? 逃げようかな、なんて。」
大橋さん「なにしろ本人ユング嫌いだって言っているからね」
白田さん「檜垣さんはいかがですかね? この辺りは?」
檜垣さん「白田さんの言う通りではないですか? ユングを批判していても、ユンギアンのことを言っている。」
白田さん「と私も思います。ユンギアンのことを批判するあまり、それがユングへの批判にすり替わっているのではないかという感じがする。
こうやってユングやユンギアンが発達過程について詳細に分けて研究しているのにも関わらず、こういうのを混同していると言うのはおかしいなと。明らかに分けているだろうと」
檜垣さん「僕の疑問は、このレジメに左に書いてある自我の形成過程と個性化過程のこの段階が、いわゆる発達心理学とウィルバーが言っているものと同じなのかなあと思いながら見ていた。
白田さん「だれだったかな? スガワヒロシ(講義録作成人:?)だったかな? のブログにあったのですが、ウィルバーは発達心理学にこだわりすぎているという言い方をしている。特にノイマン的な枠組みに囚われ過ぎているという言い方をしている。
鋭いと思いました。実はノイマン的なものとウィルバー的なものは似ているのです。」
檜垣さん「ほとんどいっしょだなと」
白田さん「その通りなのですよ。だから逆にウィルバーに対するユング派の批判は、発達過程に対する批判に重なることが多いのですよ。魂を大事にしろとか、精神ばかりとか。この批判とウィリバー批判は重なって来るのですよ。そういう意味で面白いと。
ウィルバーから引用したところで『前トランスパーソナル的な部分は克服されるべきだ』と。3行目からのところ。個の元型は統合するのではなく、克服されるべきだと言っているのです。この第一段階辺りに関しては。
そういうところはちょっと西洋的というか、ノイマン的というか、父殺しとか母殺しとか強いコンプレックスではないかという批判に重なって来るんです。こういうところが気になるのです。
檜垣さん「これってこのままの通りを抜いてきていらっしゃいます?」
白田さん「このへんは確かそのままです。」
檜垣さん「ウィルバーの言っている元型批判の時のこのシャドウとか神話的要素で、トランスパーソナルではない元型のところの話については、発達段階でじゃまになっているから克服しなければないというのはそういう意味で、純粋に元型についてはそういう言い方をしていない。」
白田さん「克服っていうのはどういう意味なのでしょうかね。この場合は」
檜垣さん「なんというのかな」
白田さん「私はこの辺、禅的なものを感じるんですね。」
檜垣さん「元型と元型イメージを分けなければならないと言う話ですよね。純粋な元型はイメージではないですよね」
白田さん「そうそう。」
檜垣さん「ユングは臨床心理学者だから、患者さんから聞いた話はすべて元型から得られたイメージですよね」
白田さん「はい」
檜垣さん「そういうものはその時代とかその人の持っているものとか汚れたものがいっぱいついていますよね。そういうものがいっぱい混ざっているということをウィルバーは言っている。だから克服されるべきだとウィルバーは言っている。」
白田さん「確かに本当の元型とは。。。とウィルバーも書いていますよね。けれどユングの後期の元型的イメージと元型論とをはっきり分けて論ずるような論文が出てくるのですよね。
それとウィルバーの言っていることは同じだという気がして。それなのになぜわざわざユングとは違うと言い出すのかなと。ちょっと不思議な感じがするのですよね。やはり前期の元型論のイメージが強いような気がするのです。ウィルバーにとっては。特に生物学的な意味での元型論を抜けきっていないような。元型そのものはむしろ宇宙的原理であって、そこから派生してくるものがいろいろあるのだと。そういう宇宙観をユング派示しているから、ウィルバーの結論とどこが違うのかと。
ここどうですかね? ウィルバーの研究会では議論があるのかしら? 」
檜垣さん「研究会では見たことがないですね。」
白田さん「ちょっとね。ウィルバーの考えを逆の意味で焙り出す意味でも。ちょっとこの辺は時間かけて議論する方が面白いのですけれどね。
檜垣さん「文献についてはそんなに注意していないと思いますよ。スピリチュアリティ―という意味では混乱しているからきれいに整理して議論しているのだけれど、元型についてはそんなにきれいに分析して整理はしていない。だいたいそんなにたくさん書いてはいないですよ。」
白田さん「鋭いところはあるのですよね。ユンギアンが使っているのはスピリチュアルなレベルではないとか。確かにそれはその通りなのですよ。実を言うと。私もそう思うのですよ。でも臨床家ですからね。それで正しいのですよ。」
檜垣さん「自我の形成過程の元型イメージは何歳くらいで出るかということは書いているのですかね?
白田さん「特に書いていないですね。」
檜垣さん「シュタイナーは7歳ごとに区切るではないですか? それを当てはめて見ていると、ちょうど竜殺しは思春期の時だなあと思いながら。」
白田さん「まあそうでしょうねえ。だから反抗期とかね、竜に当たるのかなと。グレートマザーなんて最初の反抗期に当たるのかなとか。そういう対応関係はある程度あるかも。
ただ人生の後半になって、課題がね。ある面では出てくることもありうるので、何歳という言い方はですね。子どもの発達過程の繰り返しがまたある。ちょっとロマン主義的な枠になってきますけれど。個体発生は系統発生を繰り返すみたいな。そういうような何かがちょっと。逆に言うとロマン主義的な思想の系統に入ることを如実に表しているということでもあるのですが。元型論のいちばんおもしろいところは発達過程論なのですよね。元型の定義なんていくらやったって、分からないですよ。」
大橋さん「石川さん。わざわざ東北は仙台からいらしたのだからなにかございませんか?」
石川さん「考えていたのですけれど。う〜ん」
白田さん「石川さん。ネットだとばんばん出てくるのに、不思議だなあ。ペルソナか?」
石川さん「どっちがペルソナか? 」
白田さん「どっちがペルソナ?」
石川さん「後期の元型がもしあるとすれば、進化はないことになると思う。初めから完成しているので。」
白田さん「ああ、よい視点ですよね」
石川さん「でも、ウィルバーなんかは、宇宙は進化すると言っています。善に向って進化するという立場ですよね。そこに違和感があるのですよね。」
白田さん「よい質問ですよね。わざとやっているかのようなよい質問。結局そこなのですよね。それがユングの後期のテーマなのです。まさにそれが。言ってみれば、死後論にも関わる。
石川さん「シェリング、ヘーゲル、ウォーロビントン(講義録作成人メモ:聞き取れず)の進化みたいな言い方をウィルバーは言っているのだけれど、生物が進化するときも、より劣ったものから優れたものに進化しているとウィルバーは言っているのだけれど、生物学的な進化論は劣ったものから進化したわけではなくて、生成変化しているだけ。」
白田さん「そうですね。」
石川さん「そこの進化という考え方も、ウィルバーは混同しているかなと。」
白田さん「仮に今の進化論を基準に考えるならば、ただ単に変化しているだけ。偶然によって。ただその時の条件によって残ったものは残って言っているだけの話だから。別に発達ではない。人間の体だって最初から設計するのであれば欠陥だらけという話も。後付けでどんどんやっているからこんなふうになる。」
(尾崎さん登場)
白田さん「逃げる算段を・・・」
大橋さん「今尾崎さんの話を。意見を聞きたいと」
黒田さん「仮に低次元から高次元に進化しても、以前のものは捨象されずに蓄積されて、含まれているのではないか?」
白田さん「何が高いか低いかという問題はありますが、なにか前段階のものがあったとして、それがユング的な発想だと消えてなくなることはない。もちろん含んでいる。けれど以前のような働き方はしない。その機能は変わる。実は次の錬金術の発達論に出て来るのですよ。精神と肉体が、○○○○(講義録作成人:聞き取れず)、一なる世界になっていくというプロセスがそれなのですよ。」
檜垣さん「発達論と価値について。積み上がってきたものに価値があるかという視点は相対論。」
黒田さん「それは考えたくない。疑問持っていないから。希望持ちたいから」
檜垣さん「発達論には価値は関係ないのですよ」
大橋さん「2次会でやってください」
白田さん「実は今の話は実在論と構造主義と関わって来るので。本当は違い自身が議論できると面白いのですけれど。
石川さんのご質問に戻るのですけれど、確かに根源的なものは変わらないのですけれど、根源的なものが現れる現れ方が微細で繊細なものになって来るのです。そういうプロセスはあると言っているのです。ユングは」
石川さん「ああ!」
白田さん「元型というものはずっとあったとしても、例えばその人の人格が発達することで、昔のアニマの働き方と今のアニマの働き方とは全然違うものになって行くとかね。世界もそうで、人が死んで歴史が進んでいく中で、今までの歴史の中でのある問題に対する課題を次なる段階ではもっと繊細に扱えるようになって、その代わり別の新しい問題も出て来て。。。神と人間との関係で、古代のヨブ記で出てきた問題がどんどん分化して、最後現代のキリスト教のマリアの被昇天に至るという、そういうプロセスなのですよね。
元型そのものは変わらないのですけれど、元型と人間との関係が変わって来るのです。より繊細に現れる。」
檜垣さん「僕の言った価値が相対的だから変わるっていうこと。発達論て価値で見ちゃうから、相対論だから、年代によって変わるよということ。それと同じ。」(講義録作成人メモ:間違えていたらゴメンナサイ。檜垣さん)
白田さん「今のは分からないのだけれどね」
石川さん「たとえばルソンの焼き物(生活雑器)が茶室に置くと価値が出て来るような。」
白田さん「そうかもしれませんね」
檜垣さん「例えばさっきの成長のある段階で、必要な元型が現れて、それによって引っ張られて、成長したら価値がなくなって、その原型は現れなくなるでしょ?」
白田さん「現れなくなると言うか、最終的には自己の統制下に入るということでしょうね。」
檜垣さん「だから現れなくなる訳だよ。」
白田さん「そういう形で現れなくなるだけで、あることはあるのですよ。別の形で現れる可能性がある」
檜垣さん「だからその人の発達段階において現れるものが変わると言う話をしたの」
白田さん「なるほど。例えばアニマにしても最初は肉体的なアニマだとしても、それが発達していくのにしたがって、智慧のアニマに変わるとかね。智慧を持った深い女性に変わるとかね。変化が出て着るとかそういうことを言っているのです」
檜垣さん「それは個人的な発達の段階によって変わるでしょ? それがさらに集合的になったら、人類と言う発達段階において、現れるものの現れ方が変わるっていうことを言いたくて」
白田さん「ああああ。そうですね。歴史のある段階になれば、言ってみれば起点そのものが違うのですものね」
檜垣さん「そうそう。」
白田さん「シンボルだって、すでに持っているわけで。」
河上素子さん「進化するとしたら、どうして歴史が繰り返すのだろうと。いろいろな音楽家がいても、現れ方が違っても、どうして似たようなことが起こるのだろうと。」
石川さん「それが元型なのですよね?」
白田さん「と言うか。現れ方の話ですよね。歴史の。」
尾崎さん「なんかそれって。らせん状になっているからじゃないかな?って気がするのですよね。一回同じようなところを通っても、1つずつ違っているような気がして。少しずつ上にあがって質が変わっているのではないですかねえ」
河上素子さん「だとしたら、目に見えて変わって来るのに本当に時間がかかる。キリストが生まれたのが2000年前ですよね。」
白田さん「幅は広がっていると思うのですよ。どんな時代でも争いはある一方で、その中から積み重ねられた精神性はある。上がっているとは思うのですよ。
そこで大きく何か変わるかどうかなんですが、ユングなんかはおそらく将来的には何か意識も世界に合わせて変わって行くのではないかとちょっと考えていると思える節があるのです。そういうのは基本的にオカルト的な思考の典型的な発想なのです。これは高橋巌さんが言ったのですけどね。このように世界そのものが変わって行くという発想は、オカルト的な発想の典型だと。」
尾崎さん「もしかしたら、本質はあまり変わらないのだけど、複雑性が増すとか、システマティックになるとかが発達の考え方みたいなのですけれど、そういうことじゃないかと思うのですよね。本質が変わらないから、同じことを繰り返しているように見えるのだけれど、私たちの意識は100年前の人たちとはちょっと違うのではないかと。より複雑になって。音楽なんかもそうでしょ?」
檜垣さん「スパイラル・ダイナミクス」
尾崎さん「そうそう。」
黒田さん「今の話って、2012年アセンションみたいのとは無縁の話と思ってよいのでしょうか?」
白田さん「私はね。ちょっと関係あると思っているのですよ。あるかというとあまり信じていないのですが、ユングの発想の中には多少なり宇宙は変わって行くという発想があるように思っています。」
黒田さん「よい方にでしょう? 今の話の文脈では?」
白田さん「ユングの価値的にはよい方でしょうね。意識と無意識との関係が変わって行くと、宇宙も変わって行くだろうという発想。
例えば子どもの虐待は今も昔もあるとして、虐待を救うシステムは今の方が発達しているではないですか? そういう意味では進んでいるのではないかと。」
尾崎さん「確かに問題も大きく見えて来ていると同時に、救い方のバリエーションも増えている。前見えなかったものが表面に見えている感じなのかなと。」
白田さん「ここら辺の話し始めるとおもしろいでしょ? ユングのスケールの話はとても面白いですよ。」
黒田さん「意識が拡張するというのもあってよいのかなと思うようになりました。完全に肯定ではないですけれど、ウィルバーの克服という文言に反発しちゃう。」
檜垣さん「今まで自分が自身だと思ってきたものと自分自身の自己を1歩引いて見て、それを自分で必要なときに取り扱い可能な機能にする。Iをmeに変えるということを含んでいる。」
白田さん「そうすると、ユングとウィルバーってあまり変わらないのではないですか?」
檜垣さん「変わらない」
白田さん「なんで批判するのだよ? なにか単純なユングに関する知識のことで、ウィルバーが間違えているのではないですかね?」
檜垣さん「そこは白田さんがさっき言った通りで、ユングではなくてユンギアンのやっていることをユングと取り違えて批判しているのだと」
大橋さん「カウンセラーの江川洋子さん。創立以来のメンバーで3年ぶり。」
江川さん「自己の成長過程の前段階で問題が大きくて、年齢年齢で出てきたものでその時向き合えなかったものが大人になってから出て来て問題が大きくなることがあって、系統立てて聞けて、私にとってすごくよかったです。ありがとうございます。」
次回予告
後期のユングのものの考え方はなんだったか? ここでは基礎的な見解を多く変えてしまったと。ここからは自己の元型というテーマに絞って行く。それはキリスト教の半面の歴史でもあって、ユングにとってのキリスト教の再生の試みでもあるし、宇宙の一元的な原理について考えるというものでもあったし、死んだ後の話にも関わって来る。ある意味オカルティックという言い方をしてもよいし。もっとも研究が進んでいないところなのですよね。私も分からないことがあるのだけれど。前期も中期も面白いのですけれど、本当は後期こそ面白い。いちばん面白いところのとっかかりのようなところを紹介できればと。
大橋さんより トランスパーソナルな課題ともいちばんかみ合う話になって来ると思うのですよね。
白田さん ユングのトランスパーソナル研究です。要するにね。
7.白田さんと尾崎さんとの対話
ウィルバーの言っていることは、後期のユングの言っていること。
あるいはユンギアンが実際にやっていることを批判している。
この点について、交流会にて白田さんがアンナさんに確認したところ、ウィルバーは後期のユングの言っていること(錬金術の研究)を理解しつつ、神秘主義と距離を置きたいので、このようにユングを批判しているのではないかという趣旨の示唆があった。
以前にウィルバーはアカデミズムの世界からは疎んじられているというお話をアンナさんから伺っていたので、講義録作成人は個人的には奇妙な思いに駆られた。
8.講義録作成人の結び
講義録作成がたいへん遅くなり、申し訳ございませんでした。
質問で議論が深くなるのはたいへん聞き応えがありました。個人的には大橋さんと檜垣さんと石川さんの発言がすごいなあと。
当日は石川さん(けろりんさん)のモヒカンが格好良かったと。特に女性たちのあいだで好評でした。今回は石川さんの新章スタートか?
以上
前へ http://
|
|
|
|
コメント(4)
ああ、面白かった〜っ
ひろひこ@(^-^)ノ さん、ありがとうございます
読んでいる途中から、私も実際にご講義に参加してる気分になりました
ところで最近、『アイオーン』を読んだのですが、その時、私は自然に(必然的に?)プレ・パーソナル、パーソナル、トランス・パーソナルの発達過程を、イメージしてましたよ。
(キリスト教以前の)異教世界(おひつじ座の時代)から、キリスト教時代(魚座の時代)を経て、ポスト・キリスト教の時代(=インテグラルの時代=みずがめ座の時代?)へと移っていく何千年もの歴史が、西洋における壮大な発達過程であり、まさに精神変容の大実験であったように思えたのですよね。
それは、
混沌の時代(異教の時代:全てが共存し交じり合った世界)
↓
意識の時代(キリスト教の時代:善と悪、光と闇、美と醜など相反するものに区別し識別して、目の前にある混沌の世界がどんなものから成り立っているのかを細分化し見極めていこうとする時代)
↓
ポスト・キリスト教の時代=キリスト教が急速に力をなくした科学の時代=現代あるいは未来(統合(インテグラル)の時代;意識の時代に細分化され識別されたものをもう一度全体から見てみる時代)
というものです。
そして、混沌の時代に見ている風景とインテグラルの時代に見ている風景は、一見、同じ風景に見えるけれども、見ている視点の意識(ステージ)は違う、というところに、精神の発達がある・・・と。
つまり、同じ世界を見ているのでも、“わからずに見ている(混沌)”のと“わかって見ている(統合)”のとでは、意識のステージが違う・・・ということです。
そんな流れを『アイオーン』という書物の中に感じたのです。
そしてそれを、ウィルバー的な発達過程で言えば、プレ・パーソナル→パーソナル→トランス・パーソナルの流れになるのかな・・・と。
それから、また話は変わりますが、ご講義録を読みながら、私は、“元型と対決してこそ、精神の変容と人格の向上が獲得できる”のだったわよね・・・と考えていました。
元型にとり憑かれてしまったり飲み込まれてしまっては、精神の良き変容も人格の向上も得られなかったのではないかしら・・・と。
(アニマだったかな?)元型と“対決した人にだけ、繰り返される無意味さの後ろに、秩序や何かしらの意図を見つけられる”・・・みたいな文章もどこかで読んだ記憶もあるのですが・・・。
だから私は、ウィルバーの使う「克服」という言葉は、「対決」と同義なのかなぁ・・・なんて思いながら読んでいました。
(だとすれば、ウィルバーとユングは同じことを言っている・・・という考え方に賛成! ということになるかな? )
)
ひろひこ@(^-^)ノ さん、ありがとうございます
読んでいる途中から、私も実際にご講義に参加してる気分になりました
ところで最近、『アイオーン』を読んだのですが、その時、私は自然に(必然的に?)プレ・パーソナル、パーソナル、トランス・パーソナルの発達過程を、イメージしてましたよ。
(キリスト教以前の)異教世界(おひつじ座の時代)から、キリスト教時代(魚座の時代)を経て、ポスト・キリスト教の時代(=インテグラルの時代=みずがめ座の時代?)へと移っていく何千年もの歴史が、西洋における壮大な発達過程であり、まさに精神変容の大実験であったように思えたのですよね。
それは、
混沌の時代(異教の時代:全てが共存し交じり合った世界)
↓
意識の時代(キリスト教の時代:善と悪、光と闇、美と醜など相反するものに区別し識別して、目の前にある混沌の世界がどんなものから成り立っているのかを細分化し見極めていこうとする時代)
↓
ポスト・キリスト教の時代=キリスト教が急速に力をなくした科学の時代=現代あるいは未来(統合(インテグラル)の時代;意識の時代に細分化され識別されたものをもう一度全体から見てみる時代)
というものです。
そして、混沌の時代に見ている風景とインテグラルの時代に見ている風景は、一見、同じ風景に見えるけれども、見ている視点の意識(ステージ)は違う、というところに、精神の発達がある・・・と。
つまり、同じ世界を見ているのでも、“わからずに見ている(混沌)”のと“わかって見ている(統合)”のとでは、意識のステージが違う・・・ということです。
そんな流れを『アイオーン』という書物の中に感じたのです。
そしてそれを、ウィルバー的な発達過程で言えば、プレ・パーソナル→パーソナル→トランス・パーソナルの流れになるのかな・・・と。
それから、また話は変わりますが、ご講義録を読みながら、私は、“元型と対決してこそ、精神の変容と人格の向上が獲得できる”のだったわよね・・・と考えていました。
元型にとり憑かれてしまったり飲み込まれてしまっては、精神の良き変容も人格の向上も得られなかったのではないかしら・・・と。
(アニマだったかな?)元型と“対決した人にだけ、繰り返される無意味さの後ろに、秩序や何かしらの意図を見つけられる”・・・みたいな文章もどこかで読んだ記憶もあるのですが・・・。
だから私は、ウィルバーの使う「克服」という言葉は、「対決」と同義なのかなぁ・・・なんて思いながら読んでいました。
(だとすれば、ウィルバーとユングは同じことを言っている・・・という考え方に賛成! ということになるかな?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ユング心理学研究会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ユング心理学研究会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170675人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90053人