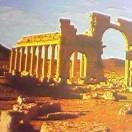三木さんから送られたレポートを投稿させていただきます。
ここから下は三木さんから送られたままの原文です。
-----------------------------------------------------------------------------
'King of Pop' Michael Jackson is dead.
突然の訃報に驚いておりますが、果たしてマイケルはどこに行ったのでしょうか?
HEAL THE WORLD
MAKE IT A BETTER PLACE
FOR YOU AND FOR ME
AND THE ENTIRE HUMAN RACE
THERE ARE PEOPLE DYING
IF YOU CARE ENOUGH FOR THE LIVING
MAKE A BETTER PLACE
FOR YOU AND ME
(from [HEAL THE WORLD] written by Michael Jackson)
さて、2009年前期のユングセミナーは、『私』のライフサイクル−死んだらどこへ行くの?」をテーマに、いよいよ今回シリーズ最終回を迎えることとなりました。シリーズラストを飾るのは、志賀くにみつさんによる『シュタイナーの死後体験論』です。
『死とイメージのユング思想』(白田重信さん)に始まり、『ウィルバーモデルで考える『あの世』(檜垣清志さん)』、『『あの世』はどこへ行った?―『死後』から『死』後へ−』(甲田烈さん)、『『死後再生の原理と他世界』−現世解脱と来世往生の道−』(網代裕康さん)、と、それぞれの立場から『私』のライフサイクルについてみてきた訳です。中々糸口が見えないと思っていたテーマですが、個人的には何となく腑に落ちるポイントが見えてきたように思います。
2007年に没した文筆家・池田晶子さんの最後の新刊(死後出版)3冊も今回のテーマと中々繋がりがあるように感じるので、ご紹介しておきます。
『私とは何か さて死んだのは誰なのか』、『魂とは何か さて死んだのは誰なのか』、『死とは何か さて死んだのは誰なのか』
つまり池田さんも切り口はどうあれ今期テーマの究極の落し処、
? 死んだら私はどうなるの?
? 人間は何のために生きて死ぬのか?即ち、どういう目的で生まれ死んだら何を残すのか?
? 生死のプロセスの最後に何があるのか?
を思索していたように思うのです。
前置きはこれくらいにして、そろそろ本題に入りたいと思いますが、個人的に興味を持った点や疑問などを五月雨式に連ねて行こうと思います。異論や捉え方の違い、はたまた連想ゲーム的で意味不明な点も多々あるかと思いますがご容赦いただき、最後までお付き合い頂ければ幸いです。
2009年6月18日(木)「シュタイナーの死後体験論」(志賀くにみつ氏)
1. 臨死体験、2.誕生前記憶
志賀さんが何度もおっしゃっていたように「信じるか信じないかは自由」である。
個人的には志賀さんの話しを聞いていて、臨死体験の中の「愛に満ちている光を見る、光の存在に包まれる」という箇所で、「風の谷のナウシカ」でナウシカがオウムの黄金(!?)の触覚(!?)に包まれるシーン(かなり記憶が曖昧ですが…)が「ラーンランララランランラン♪」という歌声と共に甦ってきた。不思議なことにパブロフの犬かの如くこのシーンは、ことあるごとに甦ってくる。来期のテーマに『宮崎アニメ作品にみるユング的世界』があるが、宮崎ワールドには様々なヒントが散りばめられていると改めて勝手に感ず。
◆ 「“死後”体験論」に、「“臨死”体験」と「“誕生前”記憶」が説明されたのは如何なる理由か?(甲田さんのセミナー時に出てきた話題、「生前はお世話になりました」あるいは「後ろの正面だ、あ、れ」と関係がありそうな…)
◆ 臨死体験や誕生前記憶が本当だとしたならば人間の脳(視覚等々)を介さない知覚がある。これらのことはどのように解釈できるのか?
3.共時性の3つのタイプ
志賀さん流に解釈すると人間の心が関与しているか否かで「心と心」、「心と非心」、「非心と非心」タイプ分けされる。中でも、共時性3タイプの中で個人的に気になったのは「非心と非心」。
(※芋洗いサル(100匹目のサルが出現するとき)は、ライアル・ワトソンの名著『生命潮流』をご参照)
◆ 「非心と非心」が信頼できれば人間とは関係なくあの世とこの世の共時性に繋がるという話しがあったが、あの世とこの世の共時性って一体全体何だろう?
◆ アボリジニー(オーストラリア)のドリーミング(ユング心理学研究会でもアボリジニー画家エミリー・ングワレさんが一時期話題になった)は、「心と非心」に該当するのか?それとも通過儀礼なのか?両者一体なのか?若しくは全く別ものなのか?
4.通過儀礼の本質
シュタイナー的解釈によると、通過儀礼とは意識的に「エーテル体をはずし、仮死状態(すなわち臨死体験)に陥ることにより、個人の人生を超えて誕生前、その部族の記憶(全知全能)、はては過去性、人類の歴史、宇宙の歴史、宇宙の未来まで体験する(ことが可能)ことという。
(※エーテル体については、志賀くにみつさん著『はじめてのシュタイナー(小学館スクウェア)ご参照』)
モーツアルトの「魔笛」に関する、志賀さんの解釈は非常に興味深い。個人的には、このテーマのセミナーを是非リクエストしたい。
(※「魔笛」に関するユング的解釈は、林道義さん著『ユングと学ぶ名画と名曲』の“モーツアルト「魔笛」に見る成熟と個性化”をご参照)
◆ モーツアルトは「魔笛」という作品を通し、何を伝えたかったのか?
◆ 昨年ネパールの生神クマリに3歳の少女が新しく就任した訳だが、果たしてクマリまでの道のりをここでいう通過儀礼とみなす事が出来るのだろうか?(32の身体的条件をクリアし、真っ暗な恐ろしいうめき声や音、血のしたたる水牛の生首が置いてある小部屋で、一日を過ごし、恐怖に耐える最後の試練を通過したものが選ばれるという)
5.死後体験
6.死後の世界のとらえ方
7.死後の道程
死後の道程を考えると、自分ひとりの問題ではないような気に囚われる(というよりも正にそうである)。私たちは生死を通し何かをバケツリレーのように運び、次の段階にバトンタッチしているのだろう。自分(どこからどこまでが自分なのか不明)の与えられた区間(生と死に関係なく)に時間というものが伴うのは不思議な感覚である。(例えば、3日間のパノラマ期間、人生の1/3の月領域 等々。林道義さん著『ユングと学ぶ名画と名曲』によると「3」はダイナミックで、ある意味不安定でありそれ故に動きが出てダイナミックになる。)
コメンテーター黒川さんが、シュタイナーは科学と宗教を交差させたとおっしゃっていましたが、改めてシュタイナーの偉大さを教えてもらったセミナーでした。また、近代科学は人類の破滅を導いているとのお言葉もありましたが、正に現代を生きる私たちが次の段階のために『私』のライフサイクルをどう意識し、どうこの世に存在(生きて)するのかが問われているような気がします。
最後に故・アンリ・カルティエ=ブレッソン(写真家)の言葉を結びとし、終了いたします;
「科学技術が鳴らす警笛の破壊的な音につつまれ、グローバリゼーションという新たな奴隷制度と貪欲な権力争いに侵略され、収益優先の重圧の下に崩壊する世界であっても、友情と愛情は存在する」(1998年5月15日)
ここから下は三木さんから送られたままの原文です。
-----------------------------------------------------------------------------
'King of Pop' Michael Jackson is dead.
突然の訃報に驚いておりますが、果たしてマイケルはどこに行ったのでしょうか?
HEAL THE WORLD
MAKE IT A BETTER PLACE
FOR YOU AND FOR ME
AND THE ENTIRE HUMAN RACE
THERE ARE PEOPLE DYING
IF YOU CARE ENOUGH FOR THE LIVING
MAKE A BETTER PLACE
FOR YOU AND ME
(from [HEAL THE WORLD] written by Michael Jackson)
さて、2009年前期のユングセミナーは、『私』のライフサイクル−死んだらどこへ行くの?」をテーマに、いよいよ今回シリーズ最終回を迎えることとなりました。シリーズラストを飾るのは、志賀くにみつさんによる『シュタイナーの死後体験論』です。
『死とイメージのユング思想』(白田重信さん)に始まり、『ウィルバーモデルで考える『あの世』(檜垣清志さん)』、『『あの世』はどこへ行った?―『死後』から『死』後へ−』(甲田烈さん)、『『死後再生の原理と他世界』−現世解脱と来世往生の道−』(網代裕康さん)、と、それぞれの立場から『私』のライフサイクルについてみてきた訳です。中々糸口が見えないと思っていたテーマですが、個人的には何となく腑に落ちるポイントが見えてきたように思います。
2007年に没した文筆家・池田晶子さんの最後の新刊(死後出版)3冊も今回のテーマと中々繋がりがあるように感じるので、ご紹介しておきます。
『私とは何か さて死んだのは誰なのか』、『魂とは何か さて死んだのは誰なのか』、『死とは何か さて死んだのは誰なのか』
つまり池田さんも切り口はどうあれ今期テーマの究極の落し処、
? 死んだら私はどうなるの?
? 人間は何のために生きて死ぬのか?即ち、どういう目的で生まれ死んだら何を残すのか?
? 生死のプロセスの最後に何があるのか?
を思索していたように思うのです。
前置きはこれくらいにして、そろそろ本題に入りたいと思いますが、個人的に興味を持った点や疑問などを五月雨式に連ねて行こうと思います。異論や捉え方の違い、はたまた連想ゲーム的で意味不明な点も多々あるかと思いますがご容赦いただき、最後までお付き合い頂ければ幸いです。
2009年6月18日(木)「シュタイナーの死後体験論」(志賀くにみつ氏)
1. 臨死体験、2.誕生前記憶
志賀さんが何度もおっしゃっていたように「信じるか信じないかは自由」である。
個人的には志賀さんの話しを聞いていて、臨死体験の中の「愛に満ちている光を見る、光の存在に包まれる」という箇所で、「風の谷のナウシカ」でナウシカがオウムの黄金(!?)の触覚(!?)に包まれるシーン(かなり記憶が曖昧ですが…)が「ラーンランララランランラン♪」という歌声と共に甦ってきた。不思議なことにパブロフの犬かの如くこのシーンは、ことあるごとに甦ってくる。来期のテーマに『宮崎アニメ作品にみるユング的世界』があるが、宮崎ワールドには様々なヒントが散りばめられていると改めて勝手に感ず。
◆ 「“死後”体験論」に、「“臨死”体験」と「“誕生前”記憶」が説明されたのは如何なる理由か?(甲田さんのセミナー時に出てきた話題、「生前はお世話になりました」あるいは「後ろの正面だ、あ、れ」と関係がありそうな…)
◆ 臨死体験や誕生前記憶が本当だとしたならば人間の脳(視覚等々)を介さない知覚がある。これらのことはどのように解釈できるのか?
3.共時性の3つのタイプ
志賀さん流に解釈すると人間の心が関与しているか否かで「心と心」、「心と非心」、「非心と非心」タイプ分けされる。中でも、共時性3タイプの中で個人的に気になったのは「非心と非心」。
(※芋洗いサル(100匹目のサルが出現するとき)は、ライアル・ワトソンの名著『生命潮流』をご参照)
◆ 「非心と非心」が信頼できれば人間とは関係なくあの世とこの世の共時性に繋がるという話しがあったが、あの世とこの世の共時性って一体全体何だろう?
◆ アボリジニー(オーストラリア)のドリーミング(ユング心理学研究会でもアボリジニー画家エミリー・ングワレさんが一時期話題になった)は、「心と非心」に該当するのか?それとも通過儀礼なのか?両者一体なのか?若しくは全く別ものなのか?
4.通過儀礼の本質
シュタイナー的解釈によると、通過儀礼とは意識的に「エーテル体をはずし、仮死状態(すなわち臨死体験)に陥ることにより、個人の人生を超えて誕生前、その部族の記憶(全知全能)、はては過去性、人類の歴史、宇宙の歴史、宇宙の未来まで体験する(ことが可能)ことという。
(※エーテル体については、志賀くにみつさん著『はじめてのシュタイナー(小学館スクウェア)ご参照』)
モーツアルトの「魔笛」に関する、志賀さんの解釈は非常に興味深い。個人的には、このテーマのセミナーを是非リクエストしたい。
(※「魔笛」に関するユング的解釈は、林道義さん著『ユングと学ぶ名画と名曲』の“モーツアルト「魔笛」に見る成熟と個性化”をご参照)
◆ モーツアルトは「魔笛」という作品を通し、何を伝えたかったのか?
◆ 昨年ネパールの生神クマリに3歳の少女が新しく就任した訳だが、果たしてクマリまでの道のりをここでいう通過儀礼とみなす事が出来るのだろうか?(32の身体的条件をクリアし、真っ暗な恐ろしいうめき声や音、血のしたたる水牛の生首が置いてある小部屋で、一日を過ごし、恐怖に耐える最後の試練を通過したものが選ばれるという)
5.死後体験
6.死後の世界のとらえ方
7.死後の道程
死後の道程を考えると、自分ひとりの問題ではないような気に囚われる(というよりも正にそうである)。私たちは生死を通し何かをバケツリレーのように運び、次の段階にバトンタッチしているのだろう。自分(どこからどこまでが自分なのか不明)の与えられた区間(生と死に関係なく)に時間というものが伴うのは不思議な感覚である。(例えば、3日間のパノラマ期間、人生の1/3の月領域 等々。林道義さん著『ユングと学ぶ名画と名曲』によると「3」はダイナミックで、ある意味不安定でありそれ故に動きが出てダイナミックになる。)
コメンテーター黒川さんが、シュタイナーは科学と宗教を交差させたとおっしゃっていましたが、改めてシュタイナーの偉大さを教えてもらったセミナーでした。また、近代科学は人類の破滅を導いているとのお言葉もありましたが、正に現代を生きる私たちが次の段階のために『私』のライフサイクルをどう意識し、どうこの世に存在(生きて)するのかが問われているような気がします。
最後に故・アンリ・カルティエ=ブレッソン(写真家)の言葉を結びとし、終了いたします;
「科学技術が鳴らす警笛の破壊的な音につつまれ、グローバリゼーションという新たな奴隷制度と貪欲な権力争いに侵略され、収益優先の重圧の下に崩壊する世界であっても、友情と愛情は存在する」(1998年5月15日)
|
|
|
|
コメント(58)
ミネルバさん
>清志朗さんの聞き取りって、すごいですね!!
いや〜。ただのメモ魔です。
>エーテル体には人生の記憶が逐一刻まれていると言われますが(肉体はそこまで性能が良くないの
>で忘却が生じますけれど、肉体を脱ぎ去るとエーテル体の機能が100%現れて)死んだ後は、人生の
>大パノラマ体験がなされるのだ、ということでした。
そうでしたね。なるほど。その結果が、
とら有無さんが、12 で説明している
>1は空間を超え、
>2は時間を超えて
>次元を高めるのです。
>1はアストラル体、2はエーテル体がより多くかかわっています。
と関係するんでしょうね。
しかし、そうすると、エーテル体が消えると、記憶が全部なくなってしまいますね。
これだと、記憶の継承がどうなっているのか上手く説明できないですね。
どういう仕組みに、なるんでしょう。
あ、でも
>エーテル体は、表象を形作る働きを担っていて、記憶が刻まれているわけではないのでしたっけ・・・?
ということですね。
では、記憶はどこに、どういう形で残るのでしょうか。
>とら有無さん
>清志朗さんの聞き取りって、すごいですね!!
いや〜。ただのメモ魔です。
>エーテル体には人生の記憶が逐一刻まれていると言われますが(肉体はそこまで性能が良くないの
>で忘却が生じますけれど、肉体を脱ぎ去るとエーテル体の機能が100%現れて)死んだ後は、人生の
>大パノラマ体験がなされるのだ、ということでした。
そうでしたね。なるほど。その結果が、
とら有無さんが、12 で説明している
>1は空間を超え、
>2は時間を超えて
>次元を高めるのです。
>1はアストラル体、2はエーテル体がより多くかかわっています。
と関係するんでしょうね。
しかし、そうすると、エーテル体が消えると、記憶が全部なくなってしまいますね。
これだと、記憶の継承がどうなっているのか上手く説明できないですね。
どういう仕組みに、なるんでしょう。
あ、でも
>エーテル体は、表象を形作る働きを担っていて、記憶が刻まれているわけではないのでしたっけ・・・?
ということですね。
では、記憶はどこに、どういう形で残るのでしょうか。
>とら有無さん
けろりんさん
私が主人と結婚したのは、まさに23歳のときでしたよ
18歳で出会って23歳で結婚って、私は主人にとって“魔性”だったかもしれませんね・・・( できれば、聞いてみたいものです
できれば、聞いてみたいものです )
)
そういえば、中野の新井薬師で“不吉な数”の話、チラッとしましたよね
6といえば堕天使(ルシフェル)を思う・・・、とお話したように思います。
実は、シュタイナーもルツィフェルについていろいろ書いてるんですよ。
例えば『神秘学概論』の中では・・
“月紀における人間は、太陽から分離することによって、独立し、太陽存在から直接得た意識よりももっと自由な意識を獲得することができた。”(P254)そして、地球紀における
“彼ら(ルツィフェル的な霊)の月紀の性質の中には、月紀において太陽霊に反抗したときの衝動が生き続けていた。
月紀の当時には、この衝動は、人間を自由な独立した意識状態に導いた点で、祝福でさえあった。しかし、地球紀になって、この存在たちが独自の進化の過程を辿るようになると(中略)人類の妨害者とならざるをえなくなった。”(P255)
“月紀の性質を保った存在たちが人間に近づいて、人間を「誘惑」しようとした・・・”(P256)
“ルツィフェル的な霊たちは、人間の意識の中に自由な活動を呼び起こしたが、それと同時に誤謬と悪の可能性をも人間に与えたのである”(P257)
セミナー当日の2次会席で、「ルツィフェルって、他の星から来た霊なんですか?」と、的外れた質問をとら有無先生にしましたら、先生は「進化に取り残された霊です。でも、最後には彼らも救われます」(実際、このような言葉ではなかったかもしれませんが、そのような意味のことだったと思います)と、お話していただきました。
私が主人と結婚したのは、まさに23歳のときでしたよ
18歳で出会って23歳で結婚って、私は主人にとって“魔性”だったかもしれませんね・・・(
そういえば、中野の新井薬師で“不吉な数”の話、チラッとしましたよね
6といえば堕天使(ルシフェル)を思う・・・、とお話したように思います。
実は、シュタイナーもルツィフェルについていろいろ書いてるんですよ。
例えば『神秘学概論』の中では・・
“月紀における人間は、太陽から分離することによって、独立し、太陽存在から直接得た意識よりももっと自由な意識を獲得することができた。”(P254)そして、地球紀における
“彼ら(ルツィフェル的な霊)の月紀の性質の中には、月紀において太陽霊に反抗したときの衝動が生き続けていた。
月紀の当時には、この衝動は、人間を自由な独立した意識状態に導いた点で、祝福でさえあった。しかし、地球紀になって、この存在たちが独自の進化の過程を辿るようになると(中略)人類の妨害者とならざるをえなくなった。”(P255)
“月紀の性質を保った存在たちが人間に近づいて、人間を「誘惑」しようとした・・・”(P256)
“ルツィフェル的な霊たちは、人間の意識の中に自由な活動を呼び起こしたが、それと同時に誤謬と悪の可能性をも人間に与えたのである”(P257)
セミナー当日の2次会席で、「ルツィフェルって、他の星から来た霊なんですか?」と、的外れた質問をとら有無先生にしましたら、先生は「進化に取り残された霊です。でも、最後には彼らも救われます」(実際、このような言葉ではなかったかもしれませんが、そのような意味のことだったと思います)と、お話していただきました。
で、けろりんさん
このお話には、続きがあって、そのお話を(『神秘学概論』の中で)読んだとき、私は内心ぜひともけろりんさんにお話したいと思ったんですよ!!
(けろりんさんは、以前、ユダヤの神は人間に嫉妬して、自分もこの世に生まれおち、イエス・キリストの人生という遊びを体験した・・・みたいなこと書かれてましたでしょ
そのイエス・キリストの誕生とその人生の意味について、シュタイナーはものすごく感動的な(私にとってだけ?)解釈をしているのです。
ルツィフェルとアーリマン(この霊は、この世の感覚的=物質的な存在を唯一の存在とみなすように強制し、霊界への展望をさえぎろうとするらしく、死後もアーリマンの支配を受けると利己主義者となって生まれ変わってくるそうです《『神秘学概論』P297より》)によって、地上の人々は霊界から疎外され、死んだ魂たちは死後の生活を影の国の生活だと感じるようになって、「影の国で王になるよりは、むしろこの世で乞食になる方が好ましい」と語るほど霊界は曇らされてしまったというのですが、キリスト出現によって、その事態が激変したというのです。
“「キリスト」こそは、崇高な太陽存在が人間の手本となるように準備してきた偉大な存在なのである”(『神秘学概論』P301〜302)
“この世におけるキリスト・イエスのアストラル体が、ルツィフェルの干渉によって覆い隠されていたすべてを、自分の中で体験できるようになった瞬間に、キリストは人類の師となった。この瞬間から、地球紀の人類の進化の中に、一つの可能性が植えつけられた。それは、地球紀の地上での目標が次第に成就していくために必要な叡智を獲得する可能性であった”(『神秘学概論』P302)
“ゴルゴダの秘儀が成就した瞬間に、もうひとつの可能性が人類に植えつけられた。それはアーリマンの影響を善なるものに変えることのできる可能性である”(『神秘学概論』P302)
“「ゴルゴダの秘蹟」が成就し、「十字架の死」が遂げられたとき、キリストは、人間の魂が死後滞在するあの世に現れた。そしてアーリマンの力に限界のあることを示した”(『神秘学概論』P302〜303)
“この瞬間から、ギリシァ人が「影の国」と呼んだあの死後の領域が、霊光につらぬかれ、再びキリストの光がやがてその世界にも生ずるであろうということを、そこに住む存在たちに知らせた”(『神秘学概論』P303)
以上のお話、私は、
太陽心霊であるキリスト(その神的部分は、仏性のようなものとして私たち一人一人の霊の中にも流れ込んでいる・・・と私はイメージしています)は、地上に生まれ、ルシフェルとアーリマンの試みに傷つけられずにあの世に帰った。そうすることによって、私たちの魂の中の仏性(神性)にも、キリストの経験(自分の心の中に叡智を獲得する可能性と悪(アーリマンの影響)を善に変える可能性)を獲得した。
そして、この世にいる人々と共にあの世にいる(仏性・神性を持つ全ての)霊たちの中にも可能性の光が輝いた・・・
という風に受け取りました。
イエス・キリストは、そんな形で救済に来た・・・と。
で、再び“6”の問題に立ち返れば、いろいろ(お互いに)“魔性”が存在するとしても、そのことで“何で自分だけにこんな白羽の矢が当たったんだよ〜・・・”と嘆くよりも(いや、実際に嘆きまくるのが普通だとは思いますけど、それでも、その冬の心にどっぷり浸かった後は)、そうした貴重な体験を、“叡智を獲得する可能性”と“悪を善に変えていく力”に変えていきたいと思うのですよね。
シュタイナーは、私に、そんな“物語”を提供してくれます
このお話には、続きがあって、そのお話を(『神秘学概論』の中で)読んだとき、私は内心ぜひともけろりんさんにお話したいと思ったんですよ!!
(けろりんさんは、以前、ユダヤの神は人間に嫉妬して、自分もこの世に生まれおち、イエス・キリストの人生という遊びを体験した・・・みたいなこと書かれてましたでしょ
そのイエス・キリストの誕生とその人生の意味について、シュタイナーはものすごく感動的な(私にとってだけ?)解釈をしているのです。
ルツィフェルとアーリマン(この霊は、この世の感覚的=物質的な存在を唯一の存在とみなすように強制し、霊界への展望をさえぎろうとするらしく、死後もアーリマンの支配を受けると利己主義者となって生まれ変わってくるそうです《『神秘学概論』P297より》)によって、地上の人々は霊界から疎外され、死んだ魂たちは死後の生活を影の国の生活だと感じるようになって、「影の国で王になるよりは、むしろこの世で乞食になる方が好ましい」と語るほど霊界は曇らされてしまったというのですが、キリスト出現によって、その事態が激変したというのです。
“「キリスト」こそは、崇高な太陽存在が人間の手本となるように準備してきた偉大な存在なのである”(『神秘学概論』P301〜302)
“この世におけるキリスト・イエスのアストラル体が、ルツィフェルの干渉によって覆い隠されていたすべてを、自分の中で体験できるようになった瞬間に、キリストは人類の師となった。この瞬間から、地球紀の人類の進化の中に、一つの可能性が植えつけられた。それは、地球紀の地上での目標が次第に成就していくために必要な叡智を獲得する可能性であった”(『神秘学概論』P302)
“ゴルゴダの秘儀が成就した瞬間に、もうひとつの可能性が人類に植えつけられた。それはアーリマンの影響を善なるものに変えることのできる可能性である”(『神秘学概論』P302)
“「ゴルゴダの秘蹟」が成就し、「十字架の死」が遂げられたとき、キリストは、人間の魂が死後滞在するあの世に現れた。そしてアーリマンの力に限界のあることを示した”(『神秘学概論』P302〜303)
“この瞬間から、ギリシァ人が「影の国」と呼んだあの死後の領域が、霊光につらぬかれ、再びキリストの光がやがてその世界にも生ずるであろうということを、そこに住む存在たちに知らせた”(『神秘学概論』P303)
以上のお話、私は、
太陽心霊であるキリスト(その神的部分は、仏性のようなものとして私たち一人一人の霊の中にも流れ込んでいる・・・と私はイメージしています)は、地上に生まれ、ルシフェルとアーリマンの試みに傷つけられずにあの世に帰った。そうすることによって、私たちの魂の中の仏性(神性)にも、キリストの経験(自分の心の中に叡智を獲得する可能性と悪(アーリマンの影響)を善に変える可能性)を獲得した。
そして、この世にいる人々と共にあの世にいる(仏性・神性を持つ全ての)霊たちの中にも可能性の光が輝いた・・・
という風に受け取りました。
イエス・キリストは、そんな形で救済に来た・・・と。
で、再び“6”の問題に立ち返れば、いろいろ(お互いに)“魔性”が存在するとしても、そのことで“何で自分だけにこんな白羽の矢が当たったんだよ〜・・・”と嘆くよりも(いや、実際に嘆きまくるのが普通だとは思いますけど、それでも、その冬の心にどっぷり浸かった後は)、そうした貴重な体験を、“叡智を獲得する可能性”と“悪を善に変えていく力”に変えていきたいと思うのですよね。
シュタイナーは、私に、そんな“物語”を提供してくれます
そして、けろりんさん
2次会でも喋りまくっていたことなんですけど、『神秘学概論』の中にこんな文章を見つけて、私はとても嬉しかったんです。
“地球紀は、月紀のあとを受けて生じた。月紀に属するすべてをもって、地球はみずからを「叡智の宇宙」に作り上げた。地球紀は、この叡智に「新しい働き」を組み込むという課題を背負っているが、その進化はまだはじまったばかりである。
地球紀は、自分を霊界の独立した一員であると感じることができる人間を育てる。(中略)「自我」が人間の中に形成されることによる。(中略)
この自我は、今後、未来において、地球紀の間に「叡智」に組み込まれるべきもう一つの「働き」を通して、地球紀、木星紀、金星紀、ヴルカン紀の諸存在と調和していくであろう。そのような「働き」とは、愛の力のことである。地球紀の人間こそが、愛の力を初めて行使しなければならない。それによって、「叡智の宇宙」は「愛の宇宙」にまで進化を遂げなければならない”(『神秘学概論』P425〜426)
“叡智は内面化されると、愛の萌芽になる。叡智は愛の前提条件なのだ。愛とは、「自我」の中で再び甦った叡智のことなのである”(『神秘学概論』P427)
いつかけろりんさんが教えてくださったエーリッヒ・フロムのHAVEの価値とBEの価値を思い出します。
土星紀・太陽紀・月紀・地球紀・木星紀、金星紀、ヴルカン紀と7つのビッグ・バンを経て、進化していく地球(宇宙)と私たちですけれど、シュタイナーに言わせると、地球紀の今、私たちがこの世に生まれ生きていくのは、まさにこの“叡智という愛”を表現するためのようですね。
この考え方は、仏教の悟りを愛へ転化させていくための思想のように、私には思えます。
2次会でも喋りまくっていたことなんですけど、『神秘学概論』の中にこんな文章を見つけて、私はとても嬉しかったんです。
“地球紀は、月紀のあとを受けて生じた。月紀に属するすべてをもって、地球はみずからを「叡智の宇宙」に作り上げた。地球紀は、この叡智に「新しい働き」を組み込むという課題を背負っているが、その進化はまだはじまったばかりである。
地球紀は、自分を霊界の独立した一員であると感じることができる人間を育てる。(中略)「自我」が人間の中に形成されることによる。(中略)
この自我は、今後、未来において、地球紀の間に「叡智」に組み込まれるべきもう一つの「働き」を通して、地球紀、木星紀、金星紀、ヴルカン紀の諸存在と調和していくであろう。そのような「働き」とは、愛の力のことである。地球紀の人間こそが、愛の力を初めて行使しなければならない。それによって、「叡智の宇宙」は「愛の宇宙」にまで進化を遂げなければならない”(『神秘学概論』P425〜426)
“叡智は内面化されると、愛の萌芽になる。叡智は愛の前提条件なのだ。愛とは、「自我」の中で再び甦った叡智のことなのである”(『神秘学概論』P427)
いつかけろりんさんが教えてくださったエーリッヒ・フロムのHAVEの価値とBEの価値を思い出します。
土星紀・太陽紀・月紀・地球紀・木星紀、金星紀、ヴルカン紀と7つのビッグ・バンを経て、進化していく地球(宇宙)と私たちですけれど、シュタイナーに言わせると、地球紀の今、私たちがこの世に生まれ生きていくのは、まさにこの“叡智という愛”を表現するためのようですね。
この考え方は、仏教の悟りを愛へ転化させていくための思想のように、私には思えます。
19の
「エーテル体が消えると記憶が全部なくなってしまう」について
私たち一人一人が独自に持っている記憶装置が
エーテル【体】です。・・(体に下線を引いているつもりです)
いわば自分用のパソコン、USB,SDカードのようなものです。
一方宇宙には宇宙エーテルがあり、これはいわば
プロバイダーにある巨大コンピューターのようなものです。
死後、月領域で自分のパソコンにある記憶を巨大コンピュータに
移して、自分のパソコンはいったん空にするのです。
その後次の人生のために再び月領域を通過するときに
巨大コンピュータにある自分の記憶を閲覧するのです。
そのようにして記憶は継承されるのです。
なぜいったん空にするかというと、他にやることがあるからです。
今回は時間の関係で省略しましたが、
月以上の次元である水星、金星、太陽領域・・・
で自分のパソコンを使うためです。
また巨大コンピュータに移し替えると、
そのコンピュータがいわば記憶の整理してくれて次の
人生に使いやすいようにしてくれるのです。
その巨大コンピュータには自分だけでなく、同じく死んだ家族、友人ら・・・
すべての人生が記憶されていて、
次の人生で出会えるように整理してくれるのです。
「エーテル体が消えると記憶が全部なくなってしまう」について
私たち一人一人が独自に持っている記憶装置が
エーテル【体】です。・・(体に下線を引いているつもりです)
いわば自分用のパソコン、USB,SDカードのようなものです。
一方宇宙には宇宙エーテルがあり、これはいわば
プロバイダーにある巨大コンピューターのようなものです。
死後、月領域で自分のパソコンにある記憶を巨大コンピュータに
移して、自分のパソコンはいったん空にするのです。
その後次の人生のために再び月領域を通過するときに
巨大コンピュータにある自分の記憶を閲覧するのです。
そのようにして記憶は継承されるのです。
なぜいったん空にするかというと、他にやることがあるからです。
今回は時間の関係で省略しましたが、
月以上の次元である水星、金星、太陽領域・・・
で自分のパソコンを使うためです。
また巨大コンピュータに移し替えると、
そのコンピュータがいわば記憶の整理してくれて次の
人生に使いやすいようにしてくれるのです。
その巨大コンピュータには自分だけでなく、同じく死んだ家族、友人ら・・・
すべての人生が記憶されていて、
次の人生で出会えるように整理してくれるのです。
10
の五行説との関連について。
それぞれお互い独自なものです。
ただ結果として共通点があります。
それはあちらの世界が客観的にあるからです。
あちらの世界を富士山だとすると、
いつどの地点から各々が見ても富士山は富士山に
かわりありません。
ただあの世も少しずつですが変化(メタモルフォーゼ)を
遂げているので、昔見た富士山と今の富士山とでは
ちょっと違いがあります。
シュタイナーが独自だと判断する基準は、
たとえばシュタイナーは太陽とゴルゴダの秘儀についての密接な
関連性を述べていますが、おそらく五行説には存在しないでしょう。
(一方シュタイナーにはないものが五行説にはあるでしょう。)
他にもシュタイナーしか述べていないことが多々あります。
そういった点からオリジナリティーの判断ができると思います。
の五行説との関連について。
それぞれお互い独自なものです。
ただ結果として共通点があります。
それはあちらの世界が客観的にあるからです。
あちらの世界を富士山だとすると、
いつどの地点から各々が見ても富士山は富士山に
かわりありません。
ただあの世も少しずつですが変化(メタモルフォーゼ)を
遂げているので、昔見た富士山と今の富士山とでは
ちょっと違いがあります。
シュタイナーが独自だと判断する基準は、
たとえばシュタイナーは太陽とゴルゴダの秘儀についての密接な
関連性を述べていますが、おそらく五行説には存在しないでしょう。
(一方シュタイナーにはないものが五行説にはあるでしょう。)
他にもシュタイナーしか述べていないことが多々あります。
そういった点からオリジナリティーの判断ができると思います。
14のミネルヴァの戦士さん、
死後最終的に「自我だけの存在になる」のですか?
その通りです。
外惑星についても述べたかったのですが、時間的に不可能でした。
私の勉強会でしている『死後体験論』は20数回の連続講座です。
(ちなみに『カルマ論』はさらに20数回かかります。)
今回はそれの前半をかいつまんだダイジェスト版としてお話しました。
1時間でできるだけ大事なことをつたえうようとベストを
つくしたつもりですが、細かい点は言えず、いろいろと
疑問も増えたのではないかと思います。
金星と水星の入れ替えについてもそうです。これはすでに
コペルニクス以前に替っているのです。
コペルニクス以前の人々は明けの明星をメルクアと呼んでいました。
自縛霊状態も時間がなくて説明不足でした。
自縛霊状態は小屋を作る「前」のことです。あいまいにして失礼しました。
しかも自縛状態は死後全員体験するのではなく、一部の人間だけです。
あまりにも物質にこだわっている人はあちらに行ったらあちらの世界を
認識できず、念が一時的にこちらにとどまってしまうのです。
死後最終的に「自我だけの存在になる」のですか?
その通りです。
外惑星についても述べたかったのですが、時間的に不可能でした。
私の勉強会でしている『死後体験論』は20数回の連続講座です。
(ちなみに『カルマ論』はさらに20数回かかります。)
今回はそれの前半をかいつまんだダイジェスト版としてお話しました。
1時間でできるだけ大事なことをつたえうようとベストを
つくしたつもりですが、細かい点は言えず、いろいろと
疑問も増えたのではないかと思います。
金星と水星の入れ替えについてもそうです。これはすでに
コペルニクス以前に替っているのです。
コペルニクス以前の人々は明けの明星をメルクアと呼んでいました。
自縛霊状態も時間がなくて説明不足でした。
自縛霊状態は小屋を作る「前」のことです。あいまいにして失礼しました。
しかも自縛状態は死後全員体験するのではなく、一部の人間だけです。
あまりにも物質にこだわっている人はあちらに行ったらあちらの世界を
認識できず、念が一時的にこちらにとどまってしまうのです。
26:とら有無さん
五行説との類似性。西洋占星術と東洋のも似ているし、グルジェフの言っていることも似ているし、結局こういったものは、そういった意識に達して、ビジョンを見た人達が、語るから同じようなものになるんでしょうね。
その少しの違いが、結局解釈の違い、その人が生きた文化、文明、時代からの影響による違いということなんでしょうね。
つまりAQALの全象限の影響、中でも左下象限(間主観領域)の影響によって、いろいろな風に表現されるけど、分類整理していけば、本質的に同じダイナミズが見えてくるということだと思ってます。
絶対的にそういった存在や構造が、永遠不滅に存在するというより、そういった存在構造が、現われるダイナミズムこそが宇宙の本質なのだなという理解です。
五行説との類似性。西洋占星術と東洋のも似ているし、グルジェフの言っていることも似ているし、結局こういったものは、そういった意識に達して、ビジョンを見た人達が、語るから同じようなものになるんでしょうね。
その少しの違いが、結局解釈の違い、その人が生きた文化、文明、時代からの影響による違いということなんでしょうね。
つまりAQALの全象限の影響、中でも左下象限(間主観領域)の影響によって、いろいろな風に表現されるけど、分類整理していけば、本質的に同じダイナミズが見えてくるということだと思ってます。
絶対的にそういった存在や構造が、永遠不滅に存在するというより、そういった存在構造が、現われるダイナミズムこそが宇宙の本質なのだなという理解です。
あやぼんさん
心理学系学科の卒論で、エミリー・ウングワレーをどのように取り上げられたのか大変興味があります。
ところで今回のセミナーは、死後の世界テーマの最終回でしたので、シリーズの整理の意味で、この世(生)とあの世(死)の境がない民俗学の例として千の風〜とアボリジニーのドリーミングに触れたといういきさつです。
ちなみにその対極にあるのが、この世とあの世(天国〜)が明確に分けられ行き来できないのが、キリスト教など一神教的な考え方だと思います。
それはさておき、エミリーの終盤ころの抽象画と、ワシリー・カンディンスキーの抽象画と似ていると思われませんか?
ボディペインティングや砂の絵を描いていて、80歳近くになってはじめてキャンバスを手にした彼女の作品が、西洋で注目されたのはそうした類似性もあるのではないかと思っています。
しかし、カンディンスキーとエミリーが基本的に違うのは、カンディンスキーが外界の事象をそのまま描いた具象画からスタートし、それからフォルムと色彩をデフォルム・記号化した作品とみられるのに対して、エミリーは最初に自身と先祖・部族と同一化しているヤムイモの蔓を図案化し、そこから同じく自分自身でもあるトーテムである動植物などを抽象化したと思われます。
心理学的に比較すると、同じ抽象画でも、西洋文明の自我意識の視点で対象化された作品と、未開社会の自我と無意識が未分化で、ドリーミングした作品の決定的な違いがあるような気がしますが、あやぼんさんはどう考えられますか?
心理学系学科の卒論で、エミリー・ウングワレーをどのように取り上げられたのか大変興味があります。
ところで今回のセミナーは、死後の世界テーマの最終回でしたので、シリーズの整理の意味で、この世(生)とあの世(死)の境がない民俗学の例として千の風〜とアボリジニーのドリーミングに触れたといういきさつです。
ちなみにその対極にあるのが、この世とあの世(天国〜)が明確に分けられ行き来できないのが、キリスト教など一神教的な考え方だと思います。
それはさておき、エミリーの終盤ころの抽象画と、ワシリー・カンディンスキーの抽象画と似ていると思われませんか?
ボディペインティングや砂の絵を描いていて、80歳近くになってはじめてキャンバスを手にした彼女の作品が、西洋で注目されたのはそうした類似性もあるのではないかと思っています。
しかし、カンディンスキーとエミリーが基本的に違うのは、カンディンスキーが外界の事象をそのまま描いた具象画からスタートし、それからフォルムと色彩をデフォルム・記号化した作品とみられるのに対して、エミリーは最初に自身と先祖・部族と同一化しているヤムイモの蔓を図案化し、そこから同じく自分自身でもあるトーテムである動植物などを抽象化したと思われます。
心理学的に比較すると、同じ抽象画でも、西洋文明の自我意識の視点で対象化された作品と、未開社会の自我と無意識が未分化で、ドリーミングした作品の決定的な違いがあるような気がしますが、あやぼんさんはどう考えられますか?
研究会に参加している大学一年生、さわらです。
>13のミネルヴァの戦士さん
魔笛の「通過儀礼」のシーンで、興味深い映像があります。
(苦難に満ちてこの道をさすらい来るものは、火、水、大気、そして大地によって清められる)
20世紀を代表する映画監督イングマール・ベルイマンが演出をしているオペラ映画のラストシーンです。ちょっと長い動画なので試練のシーンだけ観たい方は2分30秒あたりからどうぞ。
この「火と水の試練」のかなり異色な演出は、四大存在との接触でありながら、むしろ(特に火の試練は)月領域段階のカマロカを見ているような気がしませんか?身ぐるみ剥がされた人間が欲を焼き、相手に与えた感情を何倍もの感覚にして体験しているようです。色んなイミで直視しづらい映像ですね。そして皆男か女か判断がつきません。
シュタイナーが実際にいう月領域とは随分違うかもしれないし、勝手に結びつけてしまうのもどうかとも思ったのですが、何らかのイメージを感化させる助けになればと思い引用してみました。
洞窟に入る前の決意のシーンで、
ここには恐怖の門があり、苦しみと死が私をおびやかしている(冒頭の王子)
私たちは(汝達は)音の力によって進んでいく、死の暗い夜を突き抜けて楽しく!(四重唱)
と歌っています。当人達がどこか死後の世界の通過を意識しているのがわかります。
実際にはモーツァルト自身が約二か月後に死の世界へ旅立ってしまうのですが。
魔笛という作品に鑑賞なり演奏なりで触れることは、私達に通過儀礼や死後の道程をある意味で想像体験させますね。
魔笛の音楽を聴いていると、モーツァルトはこの作品を作曲することそれ自体を、自らの通過儀礼にさせられたのではないかと思わせます。一人の人間が死をもってそういった相位を通過し、顕された芸術の恩恵を受け取れる私達はとても恵まれていますね。
フリーメーソンの型を使って、モーツァルトのやったことはそういうことでもあるかな、と思います。
>13のミネルヴァの戦士さん
魔笛の「通過儀礼」のシーンで、興味深い映像があります。
(苦難に満ちてこの道をさすらい来るものは、火、水、大気、そして大地によって清められる)
20世紀を代表する映画監督イングマール・ベルイマンが演出をしているオペラ映画のラストシーンです。ちょっと長い動画なので試練のシーンだけ観たい方は2分30秒あたりからどうぞ。
この「火と水の試練」のかなり異色な演出は、四大存在との接触でありながら、むしろ(特に火の試練は)月領域段階のカマロカを見ているような気がしませんか?身ぐるみ剥がされた人間が欲を焼き、相手に与えた感情を何倍もの感覚にして体験しているようです。色んなイミで直視しづらい映像ですね。そして皆男か女か判断がつきません。
シュタイナーが実際にいう月領域とは随分違うかもしれないし、勝手に結びつけてしまうのもどうかとも思ったのですが、何らかのイメージを感化させる助けになればと思い引用してみました。
洞窟に入る前の決意のシーンで、
ここには恐怖の門があり、苦しみと死が私をおびやかしている(冒頭の王子)
私たちは(汝達は)音の力によって進んでいく、死の暗い夜を突き抜けて楽しく!(四重唱)
と歌っています。当人達がどこか死後の世界の通過を意識しているのがわかります。
実際にはモーツァルト自身が約二か月後に死の世界へ旅立ってしまうのですが。
魔笛という作品に鑑賞なり演奏なりで触れることは、私達に通過儀礼や死後の道程をある意味で想像体験させますね。
魔笛の音楽を聴いていると、モーツァルトはこの作品を作曲することそれ自体を、自らの通過儀礼にさせられたのではないかと思わせます。一人の人間が死をもってそういった相位を通過し、顕された芸術の恩恵を受け取れる私達はとても恵まれていますね。
フリーメーソンの型を使って、モーツァルトのやったことはそういうことでもあるかな、と思います。
ご紹介の巨匠の映画オペラで観る映像は、実際舞台で観る魔笛のメルフェン的イメージとは違い、かなり重い秘教的雰囲気を感じました。
モーツァルトの魔笛の試練についてのユング的解釈では、王子タミーノはギリシャ神話のメドゥーサを退治してアンドロメダを得たペルセウス、日本神話のスサノオからスセリヒメを得たオオクニヌシなどに見られる英雄元型であり、夜の女王の娘パミーナはギリシャ神話のデメテルの娘ペルペソネと同じようにグレートマザーから自立する母娘元型で、いずれも人類に普遍的な個性化の枠に含まれるイメージと考えています。
あくまでこの世において、全体性(自己)へ至る個性化段階のイニシエーションで、あの世への通過儀式とは考えていません。
インテリ秘密結社フリーメーソンの会員でもあったモーツァルトは、世界の神話あるいはメルフェンにみられる集合的無意識のストーリーに、(集合意識である)秘教イメージのフリーメーソン的男性原理を入れたために、複雑なストーリーになったのではないでしょうか?
たとえば、夜の女王がタミーノに渡した魔笛が、実は娘タミーナの父親が作ったもので、その父親は大祭司ザラストロの親友だったこと、そのザラストロがタミーナとタミーノに試練を与え結婚を許し、そのご夜の女王を滅ぼし地獄に落とすといったわけですね。
本来自然に語り継がれてきた集合的無意識(元型)のメルフェンを、時代の集合意識で修正したケースは、初版版のグリム童話が当時のキリスト教的禁欲的要請で、現在の童話になっていることとも関係しているように思えてなりません。
これは今回シリーズの3回目のセミナーのタイトルになります。
モーツァルトの魔笛の試練についてのユング的解釈では、王子タミーノはギリシャ神話のメドゥーサを退治してアンドロメダを得たペルセウス、日本神話のスサノオからスセリヒメを得たオオクニヌシなどに見られる英雄元型であり、夜の女王の娘パミーナはギリシャ神話のデメテルの娘ペルペソネと同じようにグレートマザーから自立する母娘元型で、いずれも人類に普遍的な個性化の枠に含まれるイメージと考えています。
あくまでこの世において、全体性(自己)へ至る個性化段階のイニシエーションで、あの世への通過儀式とは考えていません。
インテリ秘密結社フリーメーソンの会員でもあったモーツァルトは、世界の神話あるいはメルフェンにみられる集合的無意識のストーリーに、(集合意識である)秘教イメージのフリーメーソン的男性原理を入れたために、複雑なストーリーになったのではないでしょうか?
たとえば、夜の女王がタミーノに渡した魔笛が、実は娘タミーナの父親が作ったもので、その父親は大祭司ザラストロの親友だったこと、そのザラストロがタミーナとタミーノに試練を与え結婚を許し、そのご夜の女王を滅ぼし地獄に落とすといったわけですね。
本来自然に語り継がれてきた集合的無意識(元型)のメルフェンを、時代の集合意識で修正したケースは、初版版のグリム童話が当時のキリスト教的禁欲的要請で、現在の童話になっていることとも関係しているように思えてなりません。
これは今回シリーズの3回目のセミナーのタイトルになります。
みっくんさん
実はまだ、林道義先生の『ユングと学ぶ名画と名曲』を読んでいなくて、どんなお話が展開されているのか、とても興味深々でした。
林先生は、『魔笛』の物語を、タミーノの“英雄神話的な個性化”、タミーナの“グレートマザーから自立”の物語と、とらえられていたのですね。
確かに、イニシエーション(例えば“死と再生”のイニシエーション)についても、ユングとシュタイナーとでは、そのとらえ方がずいぶん違うように思います。
ユングはあくまでも“この世を生きる人々の心のステージが変わるサインとしてイニシエーション”を語り、シュタイナーは“次元(この世からあの世へ、あるいはあの世でのステージ)が変わる際のイニシエーション”を語っているように思えます。
ところで、エミリー・ウングワレーのヤムイモについて、みっくんさんが以前、日記を書かれていたことを思い出しました
実はまだ、林道義先生の『ユングと学ぶ名画と名曲』を読んでいなくて、どんなお話が展開されているのか、とても興味深々でした。
林先生は、『魔笛』の物語を、タミーノの“英雄神話的な個性化”、タミーナの“グレートマザーから自立”の物語と、とらえられていたのですね。
確かに、イニシエーション(例えば“死と再生”のイニシエーション)についても、ユングとシュタイナーとでは、そのとらえ方がずいぶん違うように思います。
ユングはあくまでも“この世を生きる人々の心のステージが変わるサインとしてイニシエーション”を語り、シュタイナーは“次元(この世からあの世へ、あるいはあの世でのステージ)が変わる際のイニシエーション”を語っているように思えます。
ところで、エミリー・ウングワレーのヤムイモについて、みっくんさんが以前、日記を書かれていたことを思い出しました
さわらさんが紹介してくださった映像の感想、書きます
・まず“洞窟”というのが象徴的ですよね。
これから(死ぬほどの)苦難や恐怖が待っている世界へ繋がる門を連想します。
ユング的に見れば、意識が無意識の世界へ入っていく象徴のような・・・ (そういえば、宮崎駿監督のアニメでも異世界へ通じる門の象徴としてトンネルがよく使われていましたよね)
(そういえば、宮崎駿監督のアニメでも異世界へ通じる門の象徴としてトンネルがよく使われていましたよね)
・『魔笛』では、火の試練と水の試練の前に“沈黙の試練”というのがありました。そして、その“沈黙の試練”とは“感情を沈黙させる”ことにあたるのだと、ご講義の中で教えていただきました。で、私は連想したのです。感情を沈黙させる=平静心を養う=瞑想・・・と。
この試練では、嘘をつきたがるパパゲーノが失格しますが、もしかしたら、『魔笛』は、瞑想を成功させる秘訣は、日常生活から逃避することなく、自分の心と自分を取り巻く世界とを正直に誠実に見ることだよ・・・と暗示してくれていたのかもしれませんね。
・で、“火の試練”に入るわけですが、これについてシュタイナーは『いかにして・・・』の中でも記述していたように思います(P79〜80)。
そこで彼が言いたかったことは、
“「霊的燃焼過程」によって、存在を覆い隠しているヴェールを焼き、その存在に直接向かい合うということが、「火の試練」と象徴的に呼ばれていることであり、
「自己信頼、勇気、不撓不屈の精神を健全に育成する努力を重ね、苦悩、幻滅、失敗を魂の偉大さ、特に内的平静と忍耐力とをもって耐え抜く」ことを日常生活から深く学んでいくことが「火の試練」でもある”
ということだったみたいです。
これは、ユング的に言うなら、“英雄神話による自我確立の戦い”とも言えそうだな・・・と思いましたよ。
・“水の試練”についても、シュタイナーは『いかにして・・・』の中に記述しています。(P84〜85) そこでは、
“気まぐれや思いつきや自分勝手な考えではなく、崇高な理想や根源的な命題に従うこと。個人的な好みや性向が義務を忘れさせようとする場合にも、常にその義務を遂行できるような在り方を、日々の生活のなかで実践できることが、「水の試練」を通して獲得する力=自制心なのだ”
と言われていたように思います。
シュタイナーは霊的世界を叙述しますが、『いかにして・・・』などを読むと、その霊的世界(死後の世界)が、この世を生きる私たちの心の中にも同じように展開されているのだ、と伝えてくれているようにも思えます。
なので私は、たとえば月世界のカマロカなんかも、実はこの世でも体験できる世界なんじゃないか・・・と思ったりもするんですよ。
月世界は、“出合った人との関係をどうするか”を問う世界だと教えていただきましたが、私たちは“反省”によって、その月世界を味わうことができると思うのです。
自分の言動によって他者がどう感じたか・・・を他人の立場になって振り返ってみるとき、(肉体があるのでカマロカほどの過激な痛みはないとしても)良心の呵責を感じたり、他者の痛みを想像することはできるからです。そうして味わった“痛み”によって、私たちはある意味浄化され、思いやりや愛や智慧を身につけていくのかもしれませんね。
そんなことを思いました
・まず“洞窟”というのが象徴的ですよね。
これから(死ぬほどの)苦難や恐怖が待っている世界へ繋がる門を連想します。
ユング的に見れば、意識が無意識の世界へ入っていく象徴のような・・・
・『魔笛』では、火の試練と水の試練の前に“沈黙の試練”というのがありました。そして、その“沈黙の試練”とは“感情を沈黙させる”ことにあたるのだと、ご講義の中で教えていただきました。で、私は連想したのです。感情を沈黙させる=平静心を養う=瞑想・・・と。
この試練では、嘘をつきたがるパパゲーノが失格しますが、もしかしたら、『魔笛』は、瞑想を成功させる秘訣は、日常生活から逃避することなく、自分の心と自分を取り巻く世界とを正直に誠実に見ることだよ・・・と暗示してくれていたのかもしれませんね。
・で、“火の試練”に入るわけですが、これについてシュタイナーは『いかにして・・・』の中でも記述していたように思います(P79〜80)。
そこで彼が言いたかったことは、
“「霊的燃焼過程」によって、存在を覆い隠しているヴェールを焼き、その存在に直接向かい合うということが、「火の試練」と象徴的に呼ばれていることであり、
「自己信頼、勇気、不撓不屈の精神を健全に育成する努力を重ね、苦悩、幻滅、失敗を魂の偉大さ、特に内的平静と忍耐力とをもって耐え抜く」ことを日常生活から深く学んでいくことが「火の試練」でもある”
ということだったみたいです。
これは、ユング的に言うなら、“英雄神話による自我確立の戦い”とも言えそうだな・・・と思いましたよ。
・“水の試練”についても、シュタイナーは『いかにして・・・』の中に記述しています。(P84〜85) そこでは、
“気まぐれや思いつきや自分勝手な考えではなく、崇高な理想や根源的な命題に従うこと。個人的な好みや性向が義務を忘れさせようとする場合にも、常にその義務を遂行できるような在り方を、日々の生活のなかで実践できることが、「水の試練」を通して獲得する力=自制心なのだ”
と言われていたように思います。
シュタイナーは霊的世界を叙述しますが、『いかにして・・・』などを読むと、その霊的世界(死後の世界)が、この世を生きる私たちの心の中にも同じように展開されているのだ、と伝えてくれているようにも思えます。
なので私は、たとえば月世界のカマロカなんかも、実はこの世でも体験できる世界なんじゃないか・・・と思ったりもするんですよ。
月世界は、“出合った人との関係をどうするか”を問う世界だと教えていただきましたが、私たちは“反省”によって、その月世界を味わうことができると思うのです。
自分の言動によって他者がどう感じたか・・・を他人の立場になって振り返ってみるとき、(肉体があるのでカマロカほどの過激な痛みはないとしても)良心の呵責を感じたり、他者の痛みを想像することはできるからです。そうして味わった“痛み”によって、私たちはある意味浄化され、思いやりや愛や智慧を身につけていくのかもしれませんね。
そんなことを思いました
そうしてまた思うのです(う〜、我ながら長い! )
)
もし、シュタイナーの言う霊的世界や霊的宇宙が、そのまま丸ごと私たちの“心”におさまっているのだとしたら・・・
ユングとシュタイナーとでは、いろいろ理論の違うところもあると思うのですが、シュタイナーが霊的感覚を持って一足飛びに霊的世界を感知し、その世界を主(あるいは原因)としてこの世の成り立ちと仕組みを説明したのに対して、ユングはこの世に生きる人間の立場から霊的世界を探っていったように私には思えるのです。
シュタイナーは言います。人は、体と魂と霊によって成り立っている・・・と。
身体を治すのは、医者の領域です。
そして、シュタイナーに言わせれば、身体は地上にある鉱物(元素)から成り立っており、その構成体が崩壊しないように機能しているのが生命体(エーテル体)なのだ、ということでした。
魂は心理学の領域である、と、またシュタイナーは語ります。
それは、シュタイナー理論から言うと、エーテル体の一部(感覚魂;快・不快・衝動・本能・情欲が結びついている)とアストラル体(=悟性魂;思考能力を持った、感覚魂よりも高次の魂の部分。例えば、思考によって自分の衝動や本能・情欲に盲目的に従うことはしないで、それらを満足させる適当な機会を自分の手で作り出そうとする。人間の文化を作り出すもの + 意思魂;真なるもの・善なるもの(=神の光?)が浸透している部分)を扱う領域だ、ということになると思います(カウンセリングなんかは、まさにそうだと、私には思えます)。
ところで、ユングは、まず医者として患者に関わり、また心理学者として患者の心(=魂;エーテル体の一部+アストラル体)を探求していきました。
また、アニマ(アニムス)はラテン語で、“魂”を意味するとも言われます。
シュタイナーも“男性のエーテル体は女性的で、女性のエーテル体は男性的である”と言いますが、ユングも魂を探る時点(心理学)では、男性性・女性性の別があることを語っているのが面白いと思いました。
またユングは、アニマやアニムスは無意識との仲介人になる・・・みたいなことも言っていましたよね・・・。
そして再びシュタイナーにもどるのですが、この間のご講義では、“霊=ガイスト”には“性別がない”と教えていただきました。
私は、このお話を聞いて、ユング晩年の錬金術による考察を思い出さずにはいられなかったのす。
つまり、アニマ(あるいはアニムス)によって無意識に導かれ、ぶじ個性化を成し遂げる(錬金術でいうなら、“男女の結合”)ということは、実は、シュタイナーの言う“霊=ガイスト”の発見ではなかったのか・・・と思ったわけなのです。
オペラ『魔笛』も最後は、タミーノとパミーナの結婚(男性性と女性性の結合)によって締めくくられます。
これは、シュタイナーでいうと、人が死後、3つの試練を乗り越えて“霊=ガイスト”に至る秘儀なのだ・・・ということでした。
しかし、その過程を、この世でなぞろうとしたとき、もしかしたらユングの言う個性化過程が現れてくるのかもしれません。
ご講義の終わりに、のぶさんが、ユングの晩年(=錬金術を研究し始めた頃から)は、実はシュタイナーと同じところを目指していたのではないか・・・と言われたお話が印象的でした。
実は私も、以上のような形で、同じことを思っていたんです
もし、シュタイナーの言う霊的世界や霊的宇宙が、そのまま丸ごと私たちの“心”におさまっているのだとしたら・・・
ユングとシュタイナーとでは、いろいろ理論の違うところもあると思うのですが、シュタイナーが霊的感覚を持って一足飛びに霊的世界を感知し、その世界を主(あるいは原因)としてこの世の成り立ちと仕組みを説明したのに対して、ユングはこの世に生きる人間の立場から霊的世界を探っていったように私には思えるのです。
シュタイナーは言います。人は、体と魂と霊によって成り立っている・・・と。
身体を治すのは、医者の領域です。
そして、シュタイナーに言わせれば、身体は地上にある鉱物(元素)から成り立っており、その構成体が崩壊しないように機能しているのが生命体(エーテル体)なのだ、ということでした。
魂は心理学の領域である、と、またシュタイナーは語ります。
それは、シュタイナー理論から言うと、エーテル体の一部(感覚魂;快・不快・衝動・本能・情欲が結びついている)とアストラル体(=悟性魂;思考能力を持った、感覚魂よりも高次の魂の部分。例えば、思考によって自分の衝動や本能・情欲に盲目的に従うことはしないで、それらを満足させる適当な機会を自分の手で作り出そうとする。人間の文化を作り出すもの + 意思魂;真なるもの・善なるもの(=神の光?)が浸透している部分)を扱う領域だ、ということになると思います(カウンセリングなんかは、まさにそうだと、私には思えます)。
ところで、ユングは、まず医者として患者に関わり、また心理学者として患者の心(=魂;エーテル体の一部+アストラル体)を探求していきました。
また、アニマ(アニムス)はラテン語で、“魂”を意味するとも言われます。
シュタイナーも“男性のエーテル体は女性的で、女性のエーテル体は男性的である”と言いますが、ユングも魂を探る時点(心理学)では、男性性・女性性の別があることを語っているのが面白いと思いました。
またユングは、アニマやアニムスは無意識との仲介人になる・・・みたいなことも言っていましたよね・・・。
そして再びシュタイナーにもどるのですが、この間のご講義では、“霊=ガイスト”には“性別がない”と教えていただきました。
私は、このお話を聞いて、ユング晩年の錬金術による考察を思い出さずにはいられなかったのす。
つまり、アニマ(あるいはアニムス)によって無意識に導かれ、ぶじ個性化を成し遂げる(錬金術でいうなら、“男女の結合”)ということは、実は、シュタイナーの言う“霊=ガイスト”の発見ではなかったのか・・・と思ったわけなのです。
オペラ『魔笛』も最後は、タミーノとパミーナの結婚(男性性と女性性の結合)によって締めくくられます。
これは、シュタイナーでいうと、人が死後、3つの試練を乗り越えて“霊=ガイスト”に至る秘儀なのだ・・・ということでした。
しかし、その過程を、この世でなぞろうとしたとき、もしかしたらユングの言う個性化過程が現れてくるのかもしれません。
ご講義の終わりに、のぶさんが、ユングの晩年(=錬金術を研究し始めた頃から)は、実はシュタイナーと同じところを目指していたのではないか・・・と言われたお話が印象的でした。
実は私も、以上のような形で、同じことを思っていたんです
さわらさん
いつの間にか自分の考えを述べることに夢中になりすぎて、さわらさんからの
>この「火と水の試練」のかなり異色な演出は、四大存在との接触でありながら、むしろ(特に火の試練は)月領域段階のカマロカを見ているような気がしませんか?
の問いからズレていました ごめんなさい。
ごめんなさい。
はい、私も連想します。
シュタイナーの文章は難しいので、“映像があったらいいのになぁ・・・”といつも思っていました(土星紀や太陽紀・月紀の映像、誰か作ってくれないでしょうか・・・ )
)
ところで、もしかしたらカマロカでの痛み、次の転生前に再び月世界を通るとき、“もう2度と同じ過ちは繰り返さない”という決意で、次の人生で生きる運命を準備する種みたいなものになるのかもしれませんね
いつの間にか自分の考えを述べることに夢中になりすぎて、さわらさんからの
>この「火と水の試練」のかなり異色な演出は、四大存在との接触でありながら、むしろ(特に火の試練は)月領域段階のカマロカを見ているような気がしませんか?
の問いからズレていました
はい、私も連想します。
シュタイナーの文章は難しいので、“映像があったらいいのになぁ・・・”といつも思っていました(土星紀や太陽紀・月紀の映像、誰か作ってくれないでしょうか・・・
ところで、もしかしたらカマロカでの痛み、次の転生前に再び月世界を通るとき、“もう2度と同じ過ちは繰り返さない”という決意で、次の人生で生きる運命を準備する種みたいなものになるのかもしれませんね
そんなことないですよ、けろりんさん。
だた暇なだけです
先日の上京が嬉しくて楽しくって、何度も思い返しているうちに、思いが膨れあがっちゃったんでしょうね。単純な私です
その思いを吐き出したくて(ごめんなさい )夢中で書いちゃったので、エラそうな文章になってますけど、シュタイナーの書いていることをキチンと自分が理解できているかどうかはまた別の話です。とら有無先生に検閲を入れていただかないといけないと思ってます
)夢中で書いちゃったので、エラそうな文章になってますけど、シュタイナーの書いていることをキチンと自分が理解できているかどうかはまた別の話です。とら有無先生に検閲を入れていただかないといけないと思ってます
ユング心理学的にも、何か修正すべきところやポイントがあったらご指摘ください。考える時間だけは、毎日たっぷりあるので よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
でも、家に帰ってくると、ここ最近PCにかじりついてばかりいるので、
「母親らしいこと、ちょっとはちゃんとやんなさい 」
」
とおばあちゃん(私の母)に叱られているんですよ
(これは、きっと“水の試練”に違いない )
)
だた暇なだけです
先日の上京が嬉しくて楽しくって、何度も思い返しているうちに、思いが膨れあがっちゃったんでしょうね。単純な私です
その思いを吐き出したくて(ごめんなさい
ユング心理学的にも、何か修正すべきところやポイントがあったらご指摘ください。考える時間だけは、毎日たっぷりあるので
でも、家に帰ってくると、ここ最近PCにかじりついてばかりいるので、
「母親らしいこと、ちょっとはちゃんとやんなさい
とおばあちゃん(私の母)に叱られているんですよ
(これは、きっと“水の試練”に違いない
ユングについてですが、
発表時にご紹介した「自伝」後半を信頼するかぎり、
あちらの世界の客観的存在を信じていたように思います。
・孫の水難をヴィジョンで見た
・元患者のピストル自殺時にユング自身もこめかみに激痛を覚えた
・知人の死の際、ユングは彼の部屋まで辿って行った。
・「フィレモンは独立した存在である(すなわちユングの心が作り出した
ものではない)」とユングは主張している
・「心がUFOを投影しているのではなく、UFOがカール・グスタフ・
ユングを作り出しているのである」
他にももっとあからさまな発言をユングは自伝で書いたのですが、
出版社や家族の都合で書き換えられました(湯浅泰雄「ユング超心理学
書簡」247ページ)
これらのユングの発言を真に受けとめるならば
「あちらの世界が客観的に存在し、しかもあちらが「主」で
その反映としてこちらの世界が存在する」
と晩年のユングは考えていたことになります。
そうするとシュタイナーと考える方向は同じといえます。
晩年のユングはその方向をさらに進もうとしたのではないか、
その際のよりどころが錬金術であったのではないか(特に
ドルネウスの錬金術)、と思います。
発表時にご紹介した「自伝」後半を信頼するかぎり、
あちらの世界の客観的存在を信じていたように思います。
・孫の水難をヴィジョンで見た
・元患者のピストル自殺時にユング自身もこめかみに激痛を覚えた
・知人の死の際、ユングは彼の部屋まで辿って行った。
・「フィレモンは独立した存在である(すなわちユングの心が作り出した
ものではない)」とユングは主張している
・「心がUFOを投影しているのではなく、UFOがカール・グスタフ・
ユングを作り出しているのである」
他にももっとあからさまな発言をユングは自伝で書いたのですが、
出版社や家族の都合で書き換えられました(湯浅泰雄「ユング超心理学
書簡」247ページ)
これらのユングの発言を真に受けとめるならば
「あちらの世界が客観的に存在し、しかもあちらが「主」で
その反映としてこちらの世界が存在する」
と晩年のユングは考えていたことになります。
そうするとシュタイナーと考える方向は同じといえます。
晩年のユングはその方向をさらに進もうとしたのではないか、
その際のよりどころが錬金術であったのではないか(特に
ドルネウスの錬金術)、と思います。
海外にいるためここ数日インターネットが使えませんでした。
けろりんさん、
なるほどペルソナと自己の違いなのですね。
晩年のユングは生物や人間の心以外にも、それらから独立した
「存在」があると確信していた様がうかがえます。
しかしそう確信するとユング「心理学」は成り立ちにくくなります。
あらゆる心理現象は人間の心が作り出したものであるというのが
心理学の基本です。つまり心が出発点ですが、その出発点以前に
心とは独立した存在があり、心に影響を与えていた(フィレモン)
のですから、晩年のユングを受け入れるには価値観の逆転を
する必要があります。
(家族や出版社にはそれができなかったのでしょう。だから
「自伝」を勝手に書き換えたのでしょう。)
晩年のユングを研究するには、価値観を変える勇気が必要だと
思います。
勇気あるユンギアンが登場することを願っています。
けろりんさん、
なるほどペルソナと自己の違いなのですね。
晩年のユングは生物や人間の心以外にも、それらから独立した
「存在」があると確信していた様がうかがえます。
しかしそう確信するとユング「心理学」は成り立ちにくくなります。
あらゆる心理現象は人間の心が作り出したものであるというのが
心理学の基本です。つまり心が出発点ですが、その出発点以前に
心とは独立した存在があり、心に影響を与えていた(フィレモン)
のですから、晩年のユングを受け入れるには価値観の逆転を
する必要があります。
(家族や出版社にはそれができなかったのでしょう。だから
「自伝」を勝手に書き換えたのでしょう。)
晩年のユングを研究するには、価値観を変える勇気が必要だと
思います。
勇気あるユンギアンが登場することを願っています。
晩年のユングの考えの萌芽は、ユングの幼少期〜青年期にすでにあります。
ですから、ユングの晩年の思想はむしろ、
もともとのユングの資質に回帰したもの、
あるいはユング心理学の底流にある思想が表面化したもの、
と考えることができると思います。
臨床心理学としてのユング心理学と、広い意味でのユングの思想とは、
おそらくは入れ子のような関係、後者が前者を含む関係で、
前者をある観点・ある特殊な領域に特化したものとすれば矛盾なくつながります。
例えるならば、
ニュートン力学と相対性理論との関係のようなものかもしれません。
ユングの思想の発展は、外側から見れば価値観の転換になるし、
時にはユング自身がペルソナを使い分けていたところもあるわけですが、
ユングの内部では、実は価値観の転換というようなものはなくて、
ひとつの基盤が自然に展開し成長していっただけ、みたいな面があると思います。
ユンギアンは、言ってみればその職業柄から
神秘思想家ではなくて臨床心理学者に留まらざるをえない。
いろいろ葛藤はあると思いますよ。
こうやってお気楽にユングを読める自分なんかとは違う苦労があるのかな、と。
ですから、ユングの晩年の思想はむしろ、
もともとのユングの資質に回帰したもの、
あるいはユング心理学の底流にある思想が表面化したもの、
と考えることができると思います。
臨床心理学としてのユング心理学と、広い意味でのユングの思想とは、
おそらくは入れ子のような関係、後者が前者を含む関係で、
前者をある観点・ある特殊な領域に特化したものとすれば矛盾なくつながります。
例えるならば、
ニュートン力学と相対性理論との関係のようなものかもしれません。
ユングの思想の発展は、外側から見れば価値観の転換になるし、
時にはユング自身がペルソナを使い分けていたところもあるわけですが、
ユングの内部では、実は価値観の転換というようなものはなくて、
ひとつの基盤が自然に展開し成長していっただけ、みたいな面があると思います。
ユンギアンは、言ってみればその職業柄から
神秘思想家ではなくて臨床心理学者に留まらざるをえない。
いろいろ葛藤はあると思いますよ。
こうやってお気楽にユングを読める自分なんかとは違う苦労があるのかな、と。
素人の気楽さで 単刀直入に言ってしまえば、「ユングは、幽霊(←と書くと化けて出る方をイメージしますが、私が思う“霊”は天使をも含んだ死後の一般的な霊のイメージです)の存在を認めていたのか」という疑問があります。
単刀直入に言ってしまえば、「ユングは、幽霊(←と書くと化けて出る方をイメージしますが、私が思う“霊”は天使をも含んだ死後の一般的な霊のイメージです)の存在を認めていたのか」という疑問があります。
・幽霊(一般の霊)は、心が作り出したイメージや幻なのか? それとも、
・霊とは、心が形作るイメージや幻とは全く別の、客観的に存在するものなのか・・・
実は私は、ユングは客観的な幽霊(一般的な霊)の存在を認めていたのではないか・・・と勝手に思いこんでいるのです
(幼い頃のユングや青・壮年の彼がどう思っていたかは判りませんが、晩年のユングはそう思っていたように感じます)
セミナーで紹介していただいた文章を読んでも、フィレモンは、ユングの心が作り出したものではなく、客観的に存在している霊のように読めますよね。
そういえば、ユングは夢分析に際しても、“分析対象としての夢”と“実際に亡くなった人からのメッセージ的な夢”とを区別していたようなお話を読んだ覚えがあります。
シュタイナーは『神智学』の中で、
魂は、肉体と霊とを仲介するもので、肉体からも霊からも双方の作用(影響)をうける・・・、
肉体には肉体の法則があり、魂には魂の法則がある・・・、
とも書いていましたが、ユングはその辺のところをどう考えていたのでしょうか・・・。
ユングは、「霊」というものを知って(認めて)いて、敢えて「魂の法則」を構築していったのか・・・。それとも、知らずに自分の理論を構築していったのか・・・。
いづれにしても、霊的世界が隠されたこの世において、心の事象を辿って、ここまで理論構築したユングの直感には脱帽しますね
・幽霊(一般の霊)は、心が作り出したイメージや幻なのか? それとも、
・霊とは、心が形作るイメージや幻とは全く別の、客観的に存在するものなのか・・・
実は私は、ユングは客観的な幽霊(一般的な霊)の存在を認めていたのではないか・・・と勝手に思いこんでいるのです
(幼い頃のユングや青・壮年の彼がどう思っていたかは判りませんが、晩年のユングはそう思っていたように感じます)
セミナーで紹介していただいた文章を読んでも、フィレモンは、ユングの心が作り出したものではなく、客観的に存在している霊のように読めますよね。
そういえば、ユングは夢分析に際しても、“分析対象としての夢”と“実際に亡くなった人からのメッセージ的な夢”とを区別していたようなお話を読んだ覚えがあります。
シュタイナーは『神智学』の中で、
魂は、肉体と霊とを仲介するもので、肉体からも霊からも双方の作用(影響)をうける・・・、
肉体には肉体の法則があり、魂には魂の法則がある・・・、
とも書いていましたが、ユングはその辺のところをどう考えていたのでしょうか・・・。
ユングは、「霊」というものを知って(認めて)いて、敢えて「魂の法則」を構築していったのか・・・。それとも、知らずに自分の理論を構築していったのか・・・。
いづれにしても、霊的世界が隠されたこの世において、心の事象を辿って、ここまで理論構築したユングの直感には脱帽しますね
53ののぶさん、
52で述べた私の価値観の転換もユング自身のことではなく、
家族や出版社の人に代表される人たちについて言ったものです。
彼らが「晩年のユング(思想)を受け入れるには価値観の逆転を・・・」
と書きました。
もし受け入れていたら書き換えはしなかったでしょう。
ユング自身はおっしゃる通り、若い時から「あちらの世界の客観性」
を想定せざるを得ない数々の体験をしていると思います。
ではユングはその「客観性」について若い時から確信や自信が
あったのでしょうか。
それとも研究をしながら徐々に身につけていったのでしょうか。
私は後者のような気がします。
●それとあくまでも外側から見た場合ですが、
中年期までのユング心理学はやはり「心」(魂)の領域にとどまって
いたように見えます。
●シュタイナーを学んでいる人の中にユングをも読んでいる人たち
が少なからずいます。(あくまで私の友人、知人の範囲のことですが。)
ちなみに友人で一方がユング分析家、もう一方がシュタイナー派の夫婦が
います。
シュタイナーを学んでいる人たちの知りたいことを、
54のミネルヴァの戦士さんがとても愛情をもった言葉で
説明してくれています。
ユングとシュタイナーの懸け橋にふさわしい内容です。
52で述べた私の価値観の転換もユング自身のことではなく、
家族や出版社の人に代表される人たちについて言ったものです。
彼らが「晩年のユング(思想)を受け入れるには価値観の逆転を・・・」
と書きました。
もし受け入れていたら書き換えはしなかったでしょう。
ユング自身はおっしゃる通り、若い時から「あちらの世界の客観性」
を想定せざるを得ない数々の体験をしていると思います。
ではユングはその「客観性」について若い時から確信や自信が
あったのでしょうか。
それとも研究をしながら徐々に身につけていったのでしょうか。
私は後者のような気がします。
●それとあくまでも外側から見た場合ですが、
中年期までのユング心理学はやはり「心」(魂)の領域にとどまって
いたように見えます。
●シュタイナーを学んでいる人の中にユングをも読んでいる人たち
が少なからずいます。(あくまで私の友人、知人の範囲のことですが。)
ちなみに友人で一方がユング分析家、もう一方がシュタイナー派の夫婦が
います。
シュタイナーを学んでいる人たちの知りたいことを、
54のミネルヴァの戦士さんがとても愛情をもった言葉で
説明してくれています。
ユングとシュタイナーの懸け橋にふさわしい内容です。
>54・ミネルヴァの戦士さん
お返事遅くなりました。
>実は私は、ユングは客観的な幽霊(一般的な霊)の存在を認めていたのではないか・・・と勝手に思いこんでいるのです
おそらくユングは、若い時から霊の実在を確信し、生涯信じていたでしょう。
ただ、カントや精神医学の影響を受けて、その実在性を懐疑的に見る観点を持ち、
晩年には超心理学や量子力学の知見も参照して、
ただ素朴に信じるだけとは異なる「信じ方」をしていたと思います。
その「信じ方」の変遷こそがユング思想の成立過程そのものだと思います。
>ユングは、「霊」というものを知って(認めて)いて、敢えて「魂の法則」を構築していったのか・・・。それとも、知らずに自分の理論を構築していったのか・・・。
「霊」の実在を信じていた上で、その実在について留保し、
敢えて「魂」の領域に言説を限定して理論構築をした、というところだと思います。
とら有無さんへのコメントの中で、もう少し詳しく説明します。
お返事遅くなりました。
>実は私は、ユングは客観的な幽霊(一般的な霊)の存在を認めていたのではないか・・・と勝手に思いこんでいるのです
おそらくユングは、若い時から霊の実在を確信し、生涯信じていたでしょう。
ただ、カントや精神医学の影響を受けて、その実在性を懐疑的に見る観点を持ち、
晩年には超心理学や量子力学の知見も参照して、
ただ素朴に信じるだけとは異なる「信じ方」をしていたと思います。
その「信じ方」の変遷こそがユング思想の成立過程そのものだと思います。
>ユングは、「霊」というものを知って(認めて)いて、敢えて「魂の法則」を構築していったのか・・・。それとも、知らずに自分の理論を構築していったのか・・・。
「霊」の実在を信じていた上で、その実在について留保し、
敢えて「魂」の領域に言説を限定して理論構築をした、というところだと思います。
とら有無さんへのコメントの中で、もう少し詳しく説明します。
>55・とら有無さん
>ではユングはその「客観性」について若い時から確信や自信が
>あったのでしょうか。
>それとも研究をしながら徐々に身につけていったのでしょうか。
>私は後者のような気がします。
これは、なにをもって「確信や自信」とするかで異なってくると思います。
霊が存在するという確信は、自らの体験を通して、若い頃からずっと持っていたと思うのですが、
それを理論的に整理して裏付けたのは、長い研究の後になります。
晩年のユングは、超心理学の成果などを参照して、
「霊的なもの」が実在するとしか説明できない事柄が
魂(心)や肉体(物質的世界)のレベルにおいて実際起きている、と認識していました。
>中年期までのユング心理学はやはり「心」(魂)の領域にとどまって いたように見えます。
この点は、やはり事実ではないかと私は思います。
ただ、「魂」の領域に言説をとどめることと、
「魂の学」であることとは、微妙に違いがあると思います。
背後において「魂の外」の領域と「魂」との関係を常に考えている点で、
ユング心理学は前者ではあるが後者ではない、と私は思っています。
「霊的なもの」の実在を括弧に入れるということは、
要するに、肯定も否定もしないことを確信犯的にやっていることになります。
ユングはそうした措置をもって、アカデミックな学問領域の中に
「霊的なもの」の現れとされている「現象」を持ち込むことに成功した。
霊の実在性を留保しつつ、実在性への確信を温存する、
このトリッキーさが中期までのユング心理学の特徴になるでしょう。
「中年期」というのをどこで区切るかという問題もあるのですが、
そこは煩雑なので敢えてサラリと流します。
簡単に触れておくと、
ユング心理学の一応の成立となる1921年『タイプ論』と、
共時性の概念を始めて言葉にした1930年との間に、
なにかひとつ転機があると私は考えています。
>シュタイナーを学んでいる人たちの知りたいことを、
>54のミネルヴァの戦士さんがとても愛情をもった言葉で
>説明してくれています。
「シュタイナーを学んでいる人たちの知りたいこと」に対して、
おそらくユングの立場では、
「答えているような、答えていないような」回答にならざるを得ないところがあります。
ユングとシュタイナーとの関係を考えるとき、
このつかず離れずの関係を、強引に割り切ることなく上手に捉えることが
大事なのではないかと思います。
>ではユングはその「客観性」について若い時から確信や自信が
>あったのでしょうか。
>それとも研究をしながら徐々に身につけていったのでしょうか。
>私は後者のような気がします。
これは、なにをもって「確信や自信」とするかで異なってくると思います。
霊が存在するという確信は、自らの体験を通して、若い頃からずっと持っていたと思うのですが、
それを理論的に整理して裏付けたのは、長い研究の後になります。
晩年のユングは、超心理学の成果などを参照して、
「霊的なもの」が実在するとしか説明できない事柄が
魂(心)や肉体(物質的世界)のレベルにおいて実際起きている、と認識していました。
>中年期までのユング心理学はやはり「心」(魂)の領域にとどまって いたように見えます。
この点は、やはり事実ではないかと私は思います。
ただ、「魂」の領域に言説をとどめることと、
「魂の学」であることとは、微妙に違いがあると思います。
背後において「魂の外」の領域と「魂」との関係を常に考えている点で、
ユング心理学は前者ではあるが後者ではない、と私は思っています。
「霊的なもの」の実在を括弧に入れるということは、
要するに、肯定も否定もしないことを確信犯的にやっていることになります。
ユングはそうした措置をもって、アカデミックな学問領域の中に
「霊的なもの」の現れとされている「現象」を持ち込むことに成功した。
霊の実在性を留保しつつ、実在性への確信を温存する、
このトリッキーさが中期までのユング心理学の特徴になるでしょう。
「中年期」というのをどこで区切るかという問題もあるのですが、
そこは煩雑なので敢えてサラリと流します。
簡単に触れておくと、
ユング心理学の一応の成立となる1921年『タイプ論』と、
共時性の概念を始めて言葉にした1930年との間に、
なにかひとつ転機があると私は考えています。
>シュタイナーを学んでいる人たちの知りたいことを、
>54のミネルヴァの戦士さんがとても愛情をもった言葉で
>説明してくれています。
「シュタイナーを学んでいる人たちの知りたいこと」に対して、
おそらくユングの立場では、
「答えているような、答えていないような」回答にならざるを得ないところがあります。
ユングとシュタイナーとの関係を考えるとき、
このつかず離れずの関係を、強引に割り切ることなく上手に捉えることが
大事なのではないかと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ユング心理学研究会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ユング心理学研究会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人