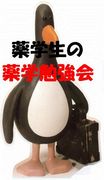『臨床分析化学』
★血液学検査の標準値
赤血球:成人男子→500万/μl
成人女子→430万/μl
白血球:4000〜8000/μl
血小板:24万/μl
ヘモグロビン:男子→16g/dl
女子→14g/dl
ヘマクリット値:男子→45%
女子→40%
赤血球沈降速度:男子→2〜10mm
(一時間値) 女子→3〜15mm
体液=体重×60/100 *体重の60%が体液。
★約40L:体液
?10〜15L:細胞外液の内、7〜10Lは組織間液、3〜5Lは血漿である。
?25〜30L:細胞内液。
★血液
血球成分を除いたものを血漿、血液凝固因子のフィブリノーゲンを除いたものを血清という。
→血漿:採血時に抗凝固剤を加えて直ちに遠心分離。
例 EDTA:Ca2+とキレート形成。
ヘパリン:抗プロトロンビン作用。
赤血球と血漿中の化学成分の違い
?赤血球中に多い成分:K1+、Mg2+、Fe3+
?血漿中に多い成分:Na+、Ca2+(カルシウムは遊離型)
★水分摂取
1日2.5〜3.0Lである(飲水、固形成分、燃焼水)。排他量も同じくらいで、尿は1日1.2〜1.8Lである。
腎糸球体ろ過量:血液1200〜1700L
血漿量700〜1000L
ろ液として120ml/min
*基本的に99%が再吸収され、1%が尿として排出される。
尿量:男子1.5L、女子1.2L。
*昼に尿量が多く、夜は普通少ない。
外観:黄色、透明、比重は1.015。
*アンモニア臭は放置することで生じ、直後は芳香臭。
アセトン臭→糖尿病、腐敗臭→膀胱炎、メープルシロップ臭→アミノ酸代謝異常、ネズミ尿→フェニルケトン尿症。
*Phは4.6〜7.8(健康な人はPh6付近)
酸性尿→糖尿病、アルカリ尿→膀胱炎
1.尿検査
採取が簡単で、多量で繰り返し変化が可能。防腐剤としてトルエン、キシレンを得られる。正常成分や異常成分の量的変化を得られる。尿中のクレアチニン量によって尿量に関係なく検査できる。
?ドライケミストリー:支持体に数種の試薬を乾燥状態で保持させたものに、資料を接触させ資料中の測定成分を分析する方法。
試験紙法:尿成分の簡易検査法、Dip and read方式をとる。
Dip and read方式:短冊形プラスチックの一端に試薬類をしみ込ませた試験紙が貼ってあり、これを尿につけて色の変化を見る方法。
A、ビリルビン:黄疸、胆道閉塞の疑い
→ビリルビンに2,4−ジクロロベンゼンジアゾニウム四フッ化ホウ素酸をジアゾカップリングさせて色を確認する。
B、ウロビリノーゲン:溶血性黄疸
→ジアゾカップリングによって4−メトキシベンゼンジアゾニウム四フッ化ホウ素酸塩とウロビリノーゲンが反応し色を示す。
C、潜血、血尿:結石、膀胱炎、糸球体腎炎
→ヘモグロビン、ミオグロビンが有するペルオキシダーゼ作用によって、クメンヒドロペルオキシド存在下O-トリジンが酸化され色を示す。(O-トリジンが試薬)
D、ブドウ糖:糖尿病
→ブドウ糖は空気中でグルコースオキシダーゼによって過酸化水素を生じ、ペルオキシダーゼによってO-トリジンが酸化されて色を示す。
E、アスコルビン酸:還元作用チェック
→アスコルビン酸は還元作用を持つため過酸化水素を還元してしまう。そのため潜血やブドウ糖の検出ができなくなる。2,6−ジクロロフェノールナトリウムによってアスコルビン酸の量が推定できる。
F、ケトン体:糖尿病
→ケトン体(アセト酢酸、アセトン)はアルカリ性でニトロプルシドナトリウムと反応し、ケトン体濃度に依存して色を示す。
*糖尿病が重くなり、エネルギー源を脂肪に求めざるを得なくなると脂肪酸のβ酸化で産出したアセチルCoAからケトン体検出。
G、PH
→メチルレッド、ブロムチモールブルー混合指示薬によって、PH5〜)の範囲で色を示す。
H、比重:腎機能検査
→尿比重の決定因子である電解質(主にNaCl)とPh緩衝液との反応によるPh変化をブロムチモールブルー、チモールブルー混合指示薬で色を示す。
I、亜硝酸塩:尿道炎、細菌尿
→健常人は硝酸塩が排出される。亜硝酸塩は酸性化でスルファニルアミドと反応しジアゾニウム化合物を生じ、さらにN−(3−ヒドロキシプロピル)−α―ナフチルアミンとカップリング反応し色を示す。
J、蛋白質:オリゴ蛋白1日150mg排出
→テトラフェノールブルーのタンパク誤差法によって検出。だが感度は低い。
?特異的な尿簡易検査の例
イノムクロマト方式→イノムアッセイを利用した妊娠診断薬。
*妊娠検査用スティックでは妊娠によって尿中に排出されるヒト微絨毛性性腺刺激ホルモン(HCG)が免疫測定法(サンドイッチ法)に従って特異的に検出。
HCG:尿中HCGはαサブユニットとβサブユニットから構成されている。
*αサブユニット=黄体ホルモンと同様の構造
*βサブユニット=HCG固有の構造
A、尿を指定された部位にかける。
B、尿中にHCGが存在すると、金コロイド標識HCG抗体と結合。
C、形成された複合体が、固定化した抗β―HCG抗体と結合。
D、結合しきれなくなったHCG抗体複合体は固定化した抗マウスIgG抗体と結合。
→これによって検査終了ラインが出現する。
2、イノムアッセイ(免疫測定法)→抗原―抗体反応を利用して行う分析法。可逆的反応である。疎水結合である。
抗原(Ag)+抗体(Ab)←→Ag・Ab
親和定数Ka=[Ag・Ab]/([Ag]×[Ab])
*抗体はKa=10の8乗〜10の10乗の範囲内にあるものを用いる。
エピトーク:抗原決定基、蛋白質ではアミノ酸6〜10残基程度。多糖では単糖5〜6残基程度。
ハプテン:低分子で抗体を作る能力を持たないが、高分子(キャリヤー)と結合することで抗原機能を持つ。
→特異性は高く高感度である。また操作が比較的簡単。
?競合法(B−F分離が必要)
B:Agに標識をつけたAg*のうち、抗体と結合したもの。
F:Ag*で抗体と結合していないもの。
Bo:Agを添加しないAg*のみが抗体と結合したときのB。
B/T:結合Ag*割合。
B/Bo:Ag添加によるBoの変化。
→一定の限られた抗原に対して、測定対象となる抗原を一定量の標識抗原または固定化抗原と競合的に反応させる方法。
A、一定量の抗体に測定対象となる抗原に標識をつけたAg*と、通常のAgを反応。
B、B/F分離をして、いずれかのシグナル強度を測定。
?非競合法(サンドイッチ法)
→測定対象の抗原に対して過剰量の標識抗体を反応させ、定量的に形成される免疫複合体量を標識シグナル強度から計測。
A、固定化したAb1固相に目的抗原Agを加えて捕捉。固相を洗浄。
B、抗原分子上の異なる抗原決定基を認識する標識抗体Ab2を添加。サンドイッチ形成。
C、固相を洗浄し、シグナル強度を測定。
★RIA(競合法):B/F分離後、放射能を測定して計測。
→水素を3Hに置き換えたり、125I(放射性ヨウ素)に置き換えたりして計測。Bolton−Hunter試薬も存在(アミノ基測定)
★ETA(競合法):標識にアルカリホスファターゼ、ペルオキシダーゼ、β―ガラクトシダーゼを利用する。
★ELISA:EIAや抗原、抗体をプラスティック等に固定化したもの。
3、糖尿病検査
正常値 (空腹時血糖値)70〜110mg/dL、3.9〜6.1mmol/L
尿糖:6mg/dL、0.3mmol/L、30〜130mg/day
★血糖調節
A、神経系
摂食中枢:血糖が低下すると興奮。
満腹中枢:血糖が上昇すると興奮。
交感神経→?肝臓グリコーゲン分解
?インスリン分泌抑制
?グルカゴン分泌促進
?アドレナリン分泌(副腎髄質)
副交感神経→?肝臓グリコーゲン分泌抑制
?インスリン分泌促進
B、内分泌系
インスリン:グリコーゲンの分泌促進、肝臓での糖新生抑制、筋肉・脂肪組織でのグルコース取り込み促進。
インスリン拮抗ホルモン
?グルカゴン(膵臓):肝臓での糖新生促進、グリコーゲン分解。
?グルココルチコイド(副腎皮質):肝臓での糖新生促進、グリコーゲン分解。
?アドレナリン(副腎髄質):インスリン分泌抑制、グリコーゲン分解。
?成長ホルモン(下垂体前葉):肝臓での糖新生促進、筋肉でのグルコース取り込み低下。
★糖尿病:腎臓のD−グルコース排他闘値(180mg/dL)
A、糖尿病の種類
??型:膵臓ランゲルハンス島β細胞の破壊。
??型:後天的なもので、生活習慣によって起こる。
?その他:膵炎、薬剤副作用。
?妊娠:糖排他闘値低下、乳糖増加。
→糖尿病の3大合併症:目・腎・神経障害
B、測定法
?グルコースオキシダーゼ法:グルコースオキシダーゼ利用(GOD)。
α―D―グルコース
→β―D―グルコース+(GOD)→D−グルコノ−σラクトン+過酸化水素
さらに、
発色剤+過酸化水素+ペルオキシダーゼ(POD)→発色
?β−D−グルコース脱水素酵素法:グルコースデヒドロゲナーゼ(GDH)使用。
β―D−グルコース+(GDH)+NADP→NADPH(340nm吸収)
C、糖尿病診断
血糖値:FPG 126mg/dL以上。
OGTT:糖尿の疑いのある人に行う。→糖摂取後2時間放置、200mg/dL以上が糖尿病で120以下が正常。
蛋白質のグリケーション:グルコアルブミン、HbA1c。
ケトン体生成:アセトン等。
★血液学検査の標準値
赤血球:成人男子→500万/μl
成人女子→430万/μl
白血球:4000〜8000/μl
血小板:24万/μl
ヘモグロビン:男子→16g/dl
女子→14g/dl
ヘマクリット値:男子→45%
女子→40%
赤血球沈降速度:男子→2〜10mm
(一時間値) 女子→3〜15mm
体液=体重×60/100 *体重の60%が体液。
★約40L:体液
?10〜15L:細胞外液の内、7〜10Lは組織間液、3〜5Lは血漿である。
?25〜30L:細胞内液。
★血液
血球成分を除いたものを血漿、血液凝固因子のフィブリノーゲンを除いたものを血清という。
→血漿:採血時に抗凝固剤を加えて直ちに遠心分離。
例 EDTA:Ca2+とキレート形成。
ヘパリン:抗プロトロンビン作用。
赤血球と血漿中の化学成分の違い
?赤血球中に多い成分:K1+、Mg2+、Fe3+
?血漿中に多い成分:Na+、Ca2+(カルシウムは遊離型)
★水分摂取
1日2.5〜3.0Lである(飲水、固形成分、燃焼水)。排他量も同じくらいで、尿は1日1.2〜1.8Lである。
腎糸球体ろ過量:血液1200〜1700L
血漿量700〜1000L
ろ液として120ml/min
*基本的に99%が再吸収され、1%が尿として排出される。
尿量:男子1.5L、女子1.2L。
*昼に尿量が多く、夜は普通少ない。
外観:黄色、透明、比重は1.015。
*アンモニア臭は放置することで生じ、直後は芳香臭。
アセトン臭→糖尿病、腐敗臭→膀胱炎、メープルシロップ臭→アミノ酸代謝異常、ネズミ尿→フェニルケトン尿症。
*Phは4.6〜7.8(健康な人はPh6付近)
酸性尿→糖尿病、アルカリ尿→膀胱炎
1.尿検査
採取が簡単で、多量で繰り返し変化が可能。防腐剤としてトルエン、キシレンを得られる。正常成分や異常成分の量的変化を得られる。尿中のクレアチニン量によって尿量に関係なく検査できる。
?ドライケミストリー:支持体に数種の試薬を乾燥状態で保持させたものに、資料を接触させ資料中の測定成分を分析する方法。
試験紙法:尿成分の簡易検査法、Dip and read方式をとる。
Dip and read方式:短冊形プラスチックの一端に試薬類をしみ込ませた試験紙が貼ってあり、これを尿につけて色の変化を見る方法。
A、ビリルビン:黄疸、胆道閉塞の疑い
→ビリルビンに2,4−ジクロロベンゼンジアゾニウム四フッ化ホウ素酸をジアゾカップリングさせて色を確認する。
B、ウロビリノーゲン:溶血性黄疸
→ジアゾカップリングによって4−メトキシベンゼンジアゾニウム四フッ化ホウ素酸塩とウロビリノーゲンが反応し色を示す。
C、潜血、血尿:結石、膀胱炎、糸球体腎炎
→ヘモグロビン、ミオグロビンが有するペルオキシダーゼ作用によって、クメンヒドロペルオキシド存在下O-トリジンが酸化され色を示す。(O-トリジンが試薬)
D、ブドウ糖:糖尿病
→ブドウ糖は空気中でグルコースオキシダーゼによって過酸化水素を生じ、ペルオキシダーゼによってO-トリジンが酸化されて色を示す。
E、アスコルビン酸:還元作用チェック
→アスコルビン酸は還元作用を持つため過酸化水素を還元してしまう。そのため潜血やブドウ糖の検出ができなくなる。2,6−ジクロロフェノールナトリウムによってアスコルビン酸の量が推定できる。
F、ケトン体:糖尿病
→ケトン体(アセト酢酸、アセトン)はアルカリ性でニトロプルシドナトリウムと反応し、ケトン体濃度に依存して色を示す。
*糖尿病が重くなり、エネルギー源を脂肪に求めざるを得なくなると脂肪酸のβ酸化で産出したアセチルCoAからケトン体検出。
G、PH
→メチルレッド、ブロムチモールブルー混合指示薬によって、PH5〜)の範囲で色を示す。
H、比重:腎機能検査
→尿比重の決定因子である電解質(主にNaCl)とPh緩衝液との反応によるPh変化をブロムチモールブルー、チモールブルー混合指示薬で色を示す。
I、亜硝酸塩:尿道炎、細菌尿
→健常人は硝酸塩が排出される。亜硝酸塩は酸性化でスルファニルアミドと反応しジアゾニウム化合物を生じ、さらにN−(3−ヒドロキシプロピル)−α―ナフチルアミンとカップリング反応し色を示す。
J、蛋白質:オリゴ蛋白1日150mg排出
→テトラフェノールブルーのタンパク誤差法によって検出。だが感度は低い。
?特異的な尿簡易検査の例
イノムクロマト方式→イノムアッセイを利用した妊娠診断薬。
*妊娠検査用スティックでは妊娠によって尿中に排出されるヒト微絨毛性性腺刺激ホルモン(HCG)が免疫測定法(サンドイッチ法)に従って特異的に検出。
HCG:尿中HCGはαサブユニットとβサブユニットから構成されている。
*αサブユニット=黄体ホルモンと同様の構造
*βサブユニット=HCG固有の構造
A、尿を指定された部位にかける。
B、尿中にHCGが存在すると、金コロイド標識HCG抗体と結合。
C、形成された複合体が、固定化した抗β―HCG抗体と結合。
D、結合しきれなくなったHCG抗体複合体は固定化した抗マウスIgG抗体と結合。
→これによって検査終了ラインが出現する。
2、イノムアッセイ(免疫測定法)→抗原―抗体反応を利用して行う分析法。可逆的反応である。疎水結合である。
抗原(Ag)+抗体(Ab)←→Ag・Ab
親和定数Ka=[Ag・Ab]/([Ag]×[Ab])
*抗体はKa=10の8乗〜10の10乗の範囲内にあるものを用いる。
エピトーク:抗原決定基、蛋白質ではアミノ酸6〜10残基程度。多糖では単糖5〜6残基程度。
ハプテン:低分子で抗体を作る能力を持たないが、高分子(キャリヤー)と結合することで抗原機能を持つ。
→特異性は高く高感度である。また操作が比較的簡単。
?競合法(B−F分離が必要)
B:Agに標識をつけたAg*のうち、抗体と結合したもの。
F:Ag*で抗体と結合していないもの。
Bo:Agを添加しないAg*のみが抗体と結合したときのB。
B/T:結合Ag*割合。
B/Bo:Ag添加によるBoの変化。
→一定の限られた抗原に対して、測定対象となる抗原を一定量の標識抗原または固定化抗原と競合的に反応させる方法。
A、一定量の抗体に測定対象となる抗原に標識をつけたAg*と、通常のAgを反応。
B、B/F分離をして、いずれかのシグナル強度を測定。
?非競合法(サンドイッチ法)
→測定対象の抗原に対して過剰量の標識抗体を反応させ、定量的に形成される免疫複合体量を標識シグナル強度から計測。
A、固定化したAb1固相に目的抗原Agを加えて捕捉。固相を洗浄。
B、抗原分子上の異なる抗原決定基を認識する標識抗体Ab2を添加。サンドイッチ形成。
C、固相を洗浄し、シグナル強度を測定。
★RIA(競合法):B/F分離後、放射能を測定して計測。
→水素を3Hに置き換えたり、125I(放射性ヨウ素)に置き換えたりして計測。Bolton−Hunter試薬も存在(アミノ基測定)
★ETA(競合法):標識にアルカリホスファターゼ、ペルオキシダーゼ、β―ガラクトシダーゼを利用する。
★ELISA:EIAや抗原、抗体をプラスティック等に固定化したもの。
3、糖尿病検査
正常値 (空腹時血糖値)70〜110mg/dL、3.9〜6.1mmol/L
尿糖:6mg/dL、0.3mmol/L、30〜130mg/day
★血糖調節
A、神経系
摂食中枢:血糖が低下すると興奮。
満腹中枢:血糖が上昇すると興奮。
交感神経→?肝臓グリコーゲン分解
?インスリン分泌抑制
?グルカゴン分泌促進
?アドレナリン分泌(副腎髄質)
副交感神経→?肝臓グリコーゲン分泌抑制
?インスリン分泌促進
B、内分泌系
インスリン:グリコーゲンの分泌促進、肝臓での糖新生抑制、筋肉・脂肪組織でのグルコース取り込み促進。
インスリン拮抗ホルモン
?グルカゴン(膵臓):肝臓での糖新生促進、グリコーゲン分解。
?グルココルチコイド(副腎皮質):肝臓での糖新生促進、グリコーゲン分解。
?アドレナリン(副腎髄質):インスリン分泌抑制、グリコーゲン分解。
?成長ホルモン(下垂体前葉):肝臓での糖新生促進、筋肉でのグルコース取り込み低下。
★糖尿病:腎臓のD−グルコース排他闘値(180mg/dL)
A、糖尿病の種類
??型:膵臓ランゲルハンス島β細胞の破壊。
??型:後天的なもので、生活習慣によって起こる。
?その他:膵炎、薬剤副作用。
?妊娠:糖排他闘値低下、乳糖増加。
→糖尿病の3大合併症:目・腎・神経障害
B、測定法
?グルコースオキシダーゼ法:グルコースオキシダーゼ利用(GOD)。
α―D―グルコース
→β―D―グルコース+(GOD)→D−グルコノ−σラクトン+過酸化水素
さらに、
発色剤+過酸化水素+ペルオキシダーゼ(POD)→発色
?β−D−グルコース脱水素酵素法:グルコースデヒドロゲナーゼ(GDH)使用。
β―D−グルコース+(GDH)+NADP→NADPH(340nm吸収)
C、糖尿病診断
血糖値:FPG 126mg/dL以上。
OGTT:糖尿の疑いのある人に行う。→糖摂取後2時間放置、200mg/dL以上が糖尿病で120以下が正常。
蛋白質のグリケーション:グルコアルブミン、HbA1c。
ケトン体生成:アセトン等。
|
|
|
|
|
|
|
|
薬学生の薬学勉強会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
薬学生の薬学勉強会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6464人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19245人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208301人