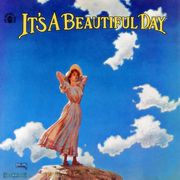みなさまいかがお過ごしでしょうか。
とよらと申します。
最近はめっきり足が遠のいていたのですが、
三浦パンダさんのお誘いもあり、また、短歌の世界に彷徨ってみたいという思いもあり、
4月の歌会のお世話をさせていただくことになりました。
4月の題詠は「糸・布」です。
「衣装」にしようか迷ったのですが、
衣装になる前の糸や布といった「もと」の部分、
織る・縫うといった行為に目を向けてほしいなという想いがありましたもので、
このテーマにさせていただきました。
しかしもちろん、「糸・布」を広くとらえて
「服」「飾り」といった視点で詠んでいただいてもかまいません。
みなさまがどのような歌を編まれるのか、
とても楽しみにしております。
どうかよろしくお付き合いくださいませ。
墨染めののころも憂き世の花ざかり折忘れても折りてけるかな (実方朝臣)
青柳の糸に玉ぬく白露の知らず幾代の春か経ぬらむ (藤原有家朝臣)
誰ぞたれ 我にかまえとなくきみの まといしころも誰ぞ縫い敢ふ (とよら)
とよらと申します。
最近はめっきり足が遠のいていたのですが、
三浦パンダさんのお誘いもあり、また、短歌の世界に彷徨ってみたいという思いもあり、
4月の歌会のお世話をさせていただくことになりました。
4月の題詠は「糸・布」です。
「衣装」にしようか迷ったのですが、
衣装になる前の糸や布といった「もと」の部分、
織る・縫うといった行為に目を向けてほしいなという想いがありましたもので、
このテーマにさせていただきました。
しかしもちろん、「糸・布」を広くとらえて
「服」「飾り」といった視点で詠んでいただいてもかまいません。
みなさまがどのような歌を編まれるのか、
とても楽しみにしております。
どうかよろしくお付き合いくださいませ。
墨染めののころも憂き世の花ざかり折忘れても折りてけるかな (実方朝臣)
青柳の糸に玉ぬく白露の知らず幾代の春か経ぬらむ (藤原有家朝臣)
誰ぞたれ 我にかまえとなくきみの まといしころも誰ぞ縫い敢ふ (とよら)
|
|
|
|
コメント(36)
三浦パンダさん
早速ありがとうございます。
「納豆のかき混ぜてこそ糸をひき尚も混ぜるとあぶくもまとう」
写実的なお歌ですね。
糸といっても、納豆の糸でくるとは意外でした(笑)
しかし納豆も菌糸も好物なのでどんと来いです!
納豆というと朝ごはんを連想してしまいます。
が、ここで深読みすると、
このお歌は人間関係にもあてはるのではないかと思いました。
「かき混ぜて」こそ発生する、人間と人間の関係性という糸。
そして「尚も混ぜるとあぶくもまとう」という。
いったいどんな泡なのか。
糸でつながった複数の人間で形成されたコミュニティか、
それとも、かき混ぜてかき混ぜたあげくに発生したなんらかのトラブルか。
人と人がつながって社会になるのですね・・・ときれいにまとめたいところですが、
いかんせん納豆という臭いモノのお歌なのが、一筋縄ではいかないところです。
まあだからこそ味が出て、ゲテモノのくせに日本を代表する発酵食品となり、
好きな人にはたまらない中毒性を持つのですが。
わたしが今築こうとしている人間関係は、
今後どんな泡をまとうことになるのか。
未来に思いを馳せつつ、明日の朝は納豆ご飯を食べて出勤したいと思います。
早速ありがとうございます。
「納豆のかき混ぜてこそ糸をひき尚も混ぜるとあぶくもまとう」
写実的なお歌ですね。
糸といっても、納豆の糸でくるとは意外でした(笑)
しかし納豆も菌糸も好物なのでどんと来いです!
納豆というと朝ごはんを連想してしまいます。
が、ここで深読みすると、
このお歌は人間関係にもあてはるのではないかと思いました。
「かき混ぜて」こそ発生する、人間と人間の関係性という糸。
そして「尚も混ぜるとあぶくもまとう」という。
いったいどんな泡なのか。
糸でつながった複数の人間で形成されたコミュニティか、
それとも、かき混ぜてかき混ぜたあげくに発生したなんらかのトラブルか。
人と人がつながって社会になるのですね・・・ときれいにまとめたいところですが、
いかんせん納豆という臭いモノのお歌なのが、一筋縄ではいかないところです。
まあだからこそ味が出て、ゲテモノのくせに日本を代表する発酵食品となり、
好きな人にはたまらない中毒性を持つのですが。
わたしが今築こうとしている人間関係は、
今後どんな泡をまとうことになるのか。
未来に思いを馳せつつ、明日の朝は納豆ご飯を食べて出勤したいと思います。
☆ききちいぃーさん
・ 好物のカップぜんざい持ちたれば幼きばばから白糸垂れる
これはまた、写実的(?)でありながら難問なお歌です・・・?(*゚ェ゚*)
まず「ばば」とは何なのか。
「婆」か、排泄物をさす「ばば」か。
「婆」だと意味がつながりにくい気がしますので、
ここでは「ばば」と仮定してよろしいでしょうか?
幼子のばばから垂れる白糸・・・が、好物のカップぜんざいを持っているから垂れるのだという。
どうも尾篭な訳になって申し訳ありませんが、
きっと母親の目線なのでしょう。
そうでなければなかなか詠めないお歌だと思います。
養育者にとっては幼子の幼子の下の世話など秘するものではなく、
日常の当たり前のひとコマです。
愛情深い母にとってはそれさえも可愛く、笑いをもって受け止められるのでしょう。
一転、ばばを「婆」として解釈すると、
孫ができておばあちゃんになりたての「幼きババ」が白糸を垂らしている
・・・という情景とも受け止められます。
ただ、そこにどうして、カップぜんざいが登場するのか。
そもそもカップぜんざいを持っているのは誰なのか。
カップぜんざいと「ばば」の存在感に、白糸が完全に負けてしまっていますね。
なんだか、解釈が迷路に迷い込んでしまったようです。
発想の貧弱さが恥ずかしゅうございますが、よろしければ解題をお願いいたします。
・ 好物のカップぜんざい持ちたれば幼きばばから白糸垂れる
これはまた、写実的(?)でありながら難問なお歌です・・・?(*゚ェ゚*)
まず「ばば」とは何なのか。
「婆」か、排泄物をさす「ばば」か。
「婆」だと意味がつながりにくい気がしますので、
ここでは「ばば」と仮定してよろしいでしょうか?
幼子のばばから垂れる白糸・・・が、好物のカップぜんざいを持っているから垂れるのだという。
どうも尾篭な訳になって申し訳ありませんが、
きっと母親の目線なのでしょう。
そうでなければなかなか詠めないお歌だと思います。
養育者にとっては幼子の幼子の下の世話など秘するものではなく、
日常の当たり前のひとコマです。
愛情深い母にとってはそれさえも可愛く、笑いをもって受け止められるのでしょう。
一転、ばばを「婆」として解釈すると、
孫ができておばあちゃんになりたての「幼きババ」が白糸を垂らしている
・・・という情景とも受け止められます。
ただ、そこにどうして、カップぜんざいが登場するのか。
そもそもカップぜんざいを持っているのは誰なのか。
カップぜんざいと「ばば」の存在感に、白糸が完全に負けてしまっていますね。
なんだか、解釈が迷路に迷い込んでしまったようです。
発想の貧弱さが恥ずかしゅうございますが、よろしければ解題をお願いいたします。
☆ユッコさん
・ さまざまな布突き合わせ配色を考えるのが目下の楽しみ
あーわかります。
お裁縫を趣味にしている人間にとっては、どの布を使うか、配色をどうするかは本当に楽しみで、最大の悩みどころですよね。
このお歌からはなんとなく、パッチワークの配色を考えているのかな、という印象をうけました。
たとえばお洋服づくりでは、複数の布を使うにしてもせいぜい3種類くらいで、
あとはリボンやらレースの配色を考えるだけなので、
「さまざまな布突き合せ」とまではいかないかな、と思ったのです。
まあ、色や柄だけで、同じ縫製でもぜんぜん違った印象になるので、
やはり布選びはたのしく苦悩するところなのですが。
「目下の楽しみ」と結んでいらっしゃいますが、
頭のなかが色とりどりの布で支配されるほどに考え、
そんな日々もまた楽し、という情景が浮かびました。
*+☆+*――*+☆+*――*+☆+**+☆+*――*+☆+*――*+☆+*
・ 手縫いには手縫いの良さがあるもので一針一針心進める
手縫いだっていいじゃないですか!いいですいいです!
やっすい既製品のほうがほつれやすいモンですよー!
むしろ細かいものはミシンより手縫いのほうが融通がきくしキレイに仕上がるってもんです!
・・・と、お裁縫談義に花を咲かせたいところですが(笑)
ユッコさんのこの二首はとてもストレートでわかりやすいですね。
素直でやさしいお人柄があらわれているように思います。
布の配色を考えるのと同じように、伝わりやすく、調和するように、と言葉を選んでいるのかな、と思いました。
欲を言えば、もっと冒険してもいいのかなと。
ちょっと大胆な色と柄で真意をつつみ、それでこそ真意を発色させるような。
そんなお歌をつむげたら完璧です。
針を進めるには両手を使うもの。
脳の科学者によると、両手をつかうと脳が活性化するとか。
針仕事をするとき、たしかに頭の中はいろんなイメージで忙しいです。
お裁縫中の考えを、過去の人たちが文章にまとめていたら哲学はもっと進歩していたのでは、と妄想してしまいます。
「一針一針心進める」
心を進めた先に、なにがまっているのでしょうか。
でもきっと、一針一針ていねいにつむいだ思いは、自分とだれかを幸せにできるのだと思います。
・ さまざまな布突き合わせ配色を考えるのが目下の楽しみ
あーわかります。
お裁縫を趣味にしている人間にとっては、どの布を使うか、配色をどうするかは本当に楽しみで、最大の悩みどころですよね。
このお歌からはなんとなく、パッチワークの配色を考えているのかな、という印象をうけました。
たとえばお洋服づくりでは、複数の布を使うにしてもせいぜい3種類くらいで、
あとはリボンやらレースの配色を考えるだけなので、
「さまざまな布突き合せ」とまではいかないかな、と思ったのです。
まあ、色や柄だけで、同じ縫製でもぜんぜん違った印象になるので、
やはり布選びはたのしく苦悩するところなのですが。
「目下の楽しみ」と結んでいらっしゃいますが、
頭のなかが色とりどりの布で支配されるほどに考え、
そんな日々もまた楽し、という情景が浮かびました。
*+☆+*――*+☆+*――*+☆+**+☆+*――*+☆+*――*+☆+*
・ 手縫いには手縫いの良さがあるもので一針一針心進める
手縫いだっていいじゃないですか!いいですいいです!
やっすい既製品のほうがほつれやすいモンですよー!
むしろ細かいものはミシンより手縫いのほうが融通がきくしキレイに仕上がるってもんです!
・・・と、お裁縫談義に花を咲かせたいところですが(笑)
ユッコさんのこの二首はとてもストレートでわかりやすいですね。
素直でやさしいお人柄があらわれているように思います。
布の配色を考えるのと同じように、伝わりやすく、調和するように、と言葉を選んでいるのかな、と思いました。
欲を言えば、もっと冒険してもいいのかなと。
ちょっと大胆な色と柄で真意をつつみ、それでこそ真意を発色させるような。
そんなお歌をつむげたら完璧です。
針を進めるには両手を使うもの。
脳の科学者によると、両手をつかうと脳が活性化するとか。
針仕事をするとき、たしかに頭の中はいろんなイメージで忙しいです。
お裁縫中の考えを、過去の人たちが文章にまとめていたら哲学はもっと進歩していたのでは、と妄想してしまいます。
「一針一針心進める」
心を進めた先に、なにがまっているのでしょうか。
でもきっと、一針一針ていねいにつむいだ思いは、自分とだれかを幸せにできるのだと思います。
☆くろやすさん
・ 布を裂くつもりで君の名前裂く何もないとは知りながら裂く
きゃあ、なにがあったのでしょうか。
「君」はおそらく恋人か、または恋人であった人でしょう。
その名前を裂く、とはずいぶん激しい感情を感じます。
裂いた先に何か、隠れているものはないか。もしかして自分への真意がどこかにあるのではないか。
しかし、「なにもないとは知りながら裂く」というのが、主人公の悲しみとか、やるせなさとか、せつない一種の憎しみを感じさせます。
現在の恋人というより、やはり心の離れてしまった人なのでしょう。
「布を裂くつもり」といっているのですから、紙よりは裂きにくいモノで、
裂いた時に悲鳴のような音をあげることを想像し、こちらまで悲しくなってしまいます。
どうか、断絶が縫い合わされるときが来ますように。
*+☆+*――*+☆+*――*+☆+**+☆+*――*+☆+*――*+☆+*
・ 端布から糸を引き抜くようにして自縄自縛の蜘蛛の巣を編む
この歌からは2つの場面を思い浮かべました。
ひとつは、
コートやジャケットの裾のほつれを引っ張って、長く引っ張りすぎてしまった男性の姿。
ふたつ目は、
慣れない針仕事をしていて、端の処理ができてないせいでほつれて、収集がつかなくなってしまったという場面。
具体的なイメージとしてはこんな感じなのですが、
このお歌の言いたい事は、もっと抽象的なものなのかもしれません。
なにかひとつ考え事をしていて、その考え事からさまざまな記憶や発想を喚起され、
どうにも収集がつかなくなってしまった、これでは自縄自縛の蜘蛛のようだ、
という感じでしょうか。
「蜘蛛の巣を編む」と能動的に終結していますので、
ご自分を蜘蛛になぞらえていらっしゃるのでしょう。
蜘蛛が自縄自縛とは面白いです。蜘蛛のヒトたちは、自分の糸にうっかり絡まってしまったらどうするのでしょうか。
そのまま絡まったままでいるか、なんとなく切り抜けているのでしょうか。
蜘蛛の身体は絡まらないようにできているってことは・・・あるのでしょうか。
すくなくとも、自分で編んだ蜘蛛の巣をわたり歩けるよう、長い8本の足を持っているのですよね。
絡まりそうになりながらも、その状態を短歌として表現する余裕を持つ。
それが言葉の蜘蛛の矜持でありましょう。
・ 布を裂くつもりで君の名前裂く何もないとは知りながら裂く
きゃあ、なにがあったのでしょうか。
「君」はおそらく恋人か、または恋人であった人でしょう。
その名前を裂く、とはずいぶん激しい感情を感じます。
裂いた先に何か、隠れているものはないか。もしかして自分への真意がどこかにあるのではないか。
しかし、「なにもないとは知りながら裂く」というのが、主人公の悲しみとか、やるせなさとか、せつない一種の憎しみを感じさせます。
現在の恋人というより、やはり心の離れてしまった人なのでしょう。
「布を裂くつもり」といっているのですから、紙よりは裂きにくいモノで、
裂いた時に悲鳴のような音をあげることを想像し、こちらまで悲しくなってしまいます。
どうか、断絶が縫い合わされるときが来ますように。
*+☆+*――*+☆+*――*+☆+**+☆+*――*+☆+*――*+☆+*
・ 端布から糸を引き抜くようにして自縄自縛の蜘蛛の巣を編む
この歌からは2つの場面を思い浮かべました。
ひとつは、
コートやジャケットの裾のほつれを引っ張って、長く引っ張りすぎてしまった男性の姿。
ふたつ目は、
慣れない針仕事をしていて、端の処理ができてないせいでほつれて、収集がつかなくなってしまったという場面。
具体的なイメージとしてはこんな感じなのですが、
このお歌の言いたい事は、もっと抽象的なものなのかもしれません。
なにかひとつ考え事をしていて、その考え事からさまざまな記憶や発想を喚起され、
どうにも収集がつかなくなってしまった、これでは自縄自縛の蜘蛛のようだ、
という感じでしょうか。
「蜘蛛の巣を編む」と能動的に終結していますので、
ご自分を蜘蛛になぞらえていらっしゃるのでしょう。
蜘蛛が自縄自縛とは面白いです。蜘蛛のヒトたちは、自分の糸にうっかり絡まってしまったらどうするのでしょうか。
そのまま絡まったままでいるか、なんとなく切り抜けているのでしょうか。
蜘蛛の身体は絡まらないようにできているってことは・・・あるのでしょうか。
すくなくとも、自分で編んだ蜘蛛の巣をわたり歩けるよう、長い8本の足を持っているのですよね。
絡まりそうになりながらも、その状態を短歌として表現する余裕を持つ。
それが言葉の蜘蛛の矜持でありましょう。
☆きょうこさん
・ 裾縫いを片方終えてガタガタの散らばる縫い目をまじまじと見る
あー裾縫い。なぜかガタガタになりますよね。
だからといってミシンを出すのも面倒だし。
いや、ミシンでやったほうがきれいで早いのはわかっているんですが。
几帳面なひとなら、ピンできちっととめて仮縫いしてミシンで縫うんだろうなあ。
初心者にとって、縫い目をそろえるのは結構難しいものです。
じつは私も、ミシンで縫ったにも関わらずガタガタにしちゃったことがあります。
なんでこんなにガタガタになっちゃたの?と不思議で、まじまじと見てしまう。
誰かしらにある経験だと思います。
そしてまだ片方。片方ってことはズボンの裾上げですね。
もう一方もこの調子でガタガタかしら、とため息をつく光景が浮かんできます。
しかし、もう一方がきれいに縫えてしまったら?
ガタガタなほうを解いてやり直しますか?
むしろ、わざとガタガタに縫ってそろえますか?
私なら、きれいに縫えたことに満足して、かたっぽきれい、かたっぽガタガタで外に出ます(笑)
「ガタガタの散らばる縫い目」をどう思うかで、その人の性格が表れそうですね。
・ 裾縫いを片方終えてガタガタの散らばる縫い目をまじまじと見る
あー裾縫い。なぜかガタガタになりますよね。
だからといってミシンを出すのも面倒だし。
いや、ミシンでやったほうがきれいで早いのはわかっているんですが。
几帳面なひとなら、ピンできちっととめて仮縫いしてミシンで縫うんだろうなあ。
初心者にとって、縫い目をそろえるのは結構難しいものです。
じつは私も、ミシンで縫ったにも関わらずガタガタにしちゃったことがあります。
なんでこんなにガタガタになっちゃたの?と不思議で、まじまじと見てしまう。
誰かしらにある経験だと思います。
そしてまだ片方。片方ってことはズボンの裾上げですね。
もう一方もこの調子でガタガタかしら、とため息をつく光景が浮かんできます。
しかし、もう一方がきれいに縫えてしまったら?
ガタガタなほうを解いてやり直しますか?
むしろ、わざとガタガタに縫ってそろえますか?
私なら、きれいに縫えたことに満足して、かたっぽきれい、かたっぽガタガタで外に出ます(笑)
「ガタガタの散らばる縫い目」をどう思うかで、その人の性格が表れそうですね。
☆柊さん
・ 運命の糸を指でそっと解いて布団の山に潜り寝ました
失恋したらフテ寝、これにかぎります。
想いの届かなかったひとが存在したのでしょう。
指でそっと解けるほど軽く巻かれた糸ということは、おそらく片思いだったのかもしれません。
付き合って何年、とかになるときつく絡まっていそうですから。
このお歌のミソは、天の配剤であろう運命の糸を、自分で解いてしまっていることでしょう。
でも、何回か恋愛すると、そういうことってあるものです。それも縁、ということかもしれませんが。
過去、大学の心理学の先生が「運命の糸は5m範囲なんだよ」と講義していました。
5m範囲内に常にいれば、好意は加点され、マイナス印象は塗りかえられると。
好きな人がいるなら5m範囲でウロウロしてなさい、と言ってましたね。
運命の糸といっても、けっこうアバウトなものかもしれません。
好きだった人を思い出して、好きだけれどもあの人のことは諦めましょう、
そんなことを私も思ったことがありまして、このお歌でそれを思い出しました。
そして、やっぱり布団の中でした(笑)
それなりに悲しく、くやしい事でしたが、人生が終わるわけではありませんものね。
そう自分に言い聞かせて、王子様があらわれるのを待つ日々です。
・ 運命の糸を指でそっと解いて布団の山に潜り寝ました
失恋したらフテ寝、これにかぎります。
想いの届かなかったひとが存在したのでしょう。
指でそっと解けるほど軽く巻かれた糸ということは、おそらく片思いだったのかもしれません。
付き合って何年、とかになるときつく絡まっていそうですから。
このお歌のミソは、天の配剤であろう運命の糸を、自分で解いてしまっていることでしょう。
でも、何回か恋愛すると、そういうことってあるものです。それも縁、ということかもしれませんが。
過去、大学の心理学の先生が「運命の糸は5m範囲なんだよ」と講義していました。
5m範囲内に常にいれば、好意は加点され、マイナス印象は塗りかえられると。
好きな人がいるなら5m範囲でウロウロしてなさい、と言ってましたね。
運命の糸といっても、けっこうアバウトなものかもしれません。
好きだった人を思い出して、好きだけれどもあの人のことは諦めましょう、
そんなことを私も思ったことがありまして、このお歌でそれを思い出しました。
そして、やっぱり布団の中でした(笑)
それなりに悲しく、くやしい事でしたが、人生が終わるわけではありませんものね。
そう自分に言い聞かせて、王子様があらわれるのを待つ日々です。
☆くろやすさん
さま付けはいりませんよー。どうぞ気軽にお呼びくださいまし(o´ェ`o)ゞ
・ ゆで卵を切るための糸を手に巻いて人混みに立つ殺人鬼われは
ゆで卵、切るのに糸をお使いになるのですか?
糸はけっこう強いですもんねぇ。ピアノ線で首を切られた、なんて都市伝説もありましたっけ。
糸のそういう禍々しいイメージを膨らませたお歌でしょうか。
糸・布というお題ではほのぼのとした連想が多いかな、と思っていましたので、
こういう斬新な切り口はまた面白うございます。
刃物や鈍器などの武器を持つ時、自分が強くなったような気になるものかもしれません。
じっさい、包丁を持つだけでも、隣の人の生殺与奪を握っているといっても過言ではないでしょう。
人の良心とはすごいもので、たとえ包丁を持っていても惨劇が起こることは、
日常では、まずありません。
しかし、ほそい糸でさえも凶器になる。
糸を手に巻いているだけで殺人鬼になってしまう、そんなこともありえる。
日常をくるりと反転させたときに、なんだかおどろおどろしい現実が顔をみせる、そんな恐ろしさがこのお歌にはあります。
まあ、悲劇が起こるにしても、想像の範疇のことは大抵どうにでもなるものです。
だからこそ、自分の想像の振り幅を広く持つために、怖い想像なんぞも普段からしておく。
都市伝説なんかもたしなんでおく。
えらそうな理屈をつけても、ほとんど怖いもの見たさの好奇心ですけれどね。
このお歌の主人公は、糸を手に巻いて人混みに立って、行き交う人々をどんな目で見ているのでしょうか。
人混みに、自分の思考に、眩暈をおこしている主人公を想像してしまいます。
殺人鬼の気持ちが時にわかってしまう瞬間がある。
殺人鬼になった自分を想像してしまうときがある。
同じ人間ですから。想像だけなら、あり得ます。
しかし殺人鬼になる人はなるし、ならない人はならない。
ゆで卵を切るようにやすやすと、両者の違いを明確にしてもいいものか、どうか。
わたしにはわからないのです。
さま付けはいりませんよー。どうぞ気軽にお呼びくださいまし(o´ェ`o)ゞ
・ ゆで卵を切るための糸を手に巻いて人混みに立つ殺人鬼われは
ゆで卵、切るのに糸をお使いになるのですか?
糸はけっこう強いですもんねぇ。ピアノ線で首を切られた、なんて都市伝説もありましたっけ。
糸のそういう禍々しいイメージを膨らませたお歌でしょうか。
糸・布というお題ではほのぼのとした連想が多いかな、と思っていましたので、
こういう斬新な切り口はまた面白うございます。
刃物や鈍器などの武器を持つ時、自分が強くなったような気になるものかもしれません。
じっさい、包丁を持つだけでも、隣の人の生殺与奪を握っているといっても過言ではないでしょう。
人の良心とはすごいもので、たとえ包丁を持っていても惨劇が起こることは、
日常では、まずありません。
しかし、ほそい糸でさえも凶器になる。
糸を手に巻いているだけで殺人鬼になってしまう、そんなこともありえる。
日常をくるりと反転させたときに、なんだかおどろおどろしい現実が顔をみせる、そんな恐ろしさがこのお歌にはあります。
まあ、悲劇が起こるにしても、想像の範疇のことは大抵どうにでもなるものです。
だからこそ、自分の想像の振り幅を広く持つために、怖い想像なんぞも普段からしておく。
都市伝説なんかもたしなんでおく。
えらそうな理屈をつけても、ほとんど怖いもの見たさの好奇心ですけれどね。
このお歌の主人公は、糸を手に巻いて人混みに立って、行き交う人々をどんな目で見ているのでしょうか。
人混みに、自分の思考に、眩暈をおこしている主人公を想像してしまいます。
殺人鬼の気持ちが時にわかってしまう瞬間がある。
殺人鬼になった自分を想像してしまうときがある。
同じ人間ですから。想像だけなら、あり得ます。
しかし殺人鬼になる人はなるし、ならない人はならない。
ゆで卵を切るようにやすやすと、両者の違いを明確にしてもいいものか、どうか。
わたしにはわからないのです。
評をありがとうございます。
「片方」という部分でズボンだと分ってもらえて良かったです。
彼の作業着のズボンの裾を縫った時の歌です。
私は裁縫は苦手でして。。。
ひとまず一周終ったーと達成感はあったものの、改めて見てみたらひどい仕上がりでした。
自分で縫ったのですが、目を疑うような酷さで、疲労感が増した感じでした。
まだ片方が残っているのでやらないわけにはいかず、なんとか頑張りましたけど。
私の感覚をストレートに歌に出したものをそのように受け取ってもらえて良かったです。
この歌は少し前に作った歌なのですが、今月のような題詠がまさがくるとは思わず、出すタイミングがあって嬉しく思いました。
どうもありがとうございました。
「片方」という部分でズボンだと分ってもらえて良かったです。
彼の作業着のズボンの裾を縫った時の歌です。
私は裁縫は苦手でして。。。
ひとまず一周終ったーと達成感はあったものの、改めて見てみたらひどい仕上がりでした。
自分で縫ったのですが、目を疑うような酷さで、疲労感が増した感じでした。
まだ片方が残っているのでやらないわけにはいかず、なんとか頑張りましたけど。
私の感覚をストレートに歌に出したものをそのように受け取ってもらえて良かったです。
この歌は少し前に作った歌なのですが、今月のような題詠がまさがくるとは思わず、出すタイミングがあって嬉しく思いました。
どうもありがとうございました。
☆きょうこさん
母親の手製の服着し幼馴染はベトナムにいると便りを寄こす
かなり破調のお歌ですね。 5・8・7・8・7の区切りでよろしいでしょうか?
私個人でいえば、破調の短歌づくりは苦手の部類でして・・・。
いつのまにか5・7・5・7・7になってしまう頭のかたい奴なのです。
口ずさんだ時のなめらかさも大事だと思うので、まあいいやとほったらかしですが、融通の利かないのも事実。
きょうこさんのこのお歌は破調ですが、なんだか真面目さとか、硬さを感じさせますね。
状況説明のような内容がそう感じさせるのでしょうか。
母親の手製の服をきた幼馴染がベトナムにいる、という珍しい状況を、
真面目に、そのまま伝えている。
ひねた歌詠みならば、読み手が正しく状況を理解などしなくてもよい、という風情で、へんてこな歌をつくりそうです。
理解、解釈は読み手にまかせ、おもしろい歌を作るか。
理解してもらう、ということを主眼におくか。
わたし自身も、この間でゆれうごく詠み人のひとりです。
さて、「母親の手製の服着し幼馴染はベトナムにいると便りを寄こす」というお歌。
「私」か「幼馴染」か、どちらの母親の手製の服を着ているのか、そこで風景が相当変わってきそうです。
私の母親の場合、家族ぐるみの付き合いの深い友達なんだろうな、という解釈になるわけです。
まるで兄弟のような、母親にとっても子供のような、そういう幼馴染を持っている、というのは世間一般では珍しい部類でしょう。
それをお歌の素材にすれば、いいお歌がたくさんできそうです。
というか、親しい幼馴染がいるというのがとてもうらやましいです。
どこかで読んだのですが、母親の手縫いのアイテムを身につける、というのは、風水的に見て「子どもを犯罪や災いから遠ざける」効果があるのだそうです。
幼馴染さんが、どれだけ愛情を注がれている存在であるか。
手製の服、というアイテムひとつで、きっと愛されている人物なのだろうなあ、と想像できるわけです。
歌のなかの「私」も、幼馴染からの便りを受け取り、ベトナムにいるという近況に驚きつつ、
元気そうでよかったな、楽しんでくるといいな、でも危ない目には合わないでね、と、
様々な思いを抱いている情景が浮かんできます。
・・・それにしても、「幼馴染」という単語、つっかえやすいのは私だけでしょうか。
六文字だし、なかなか短歌では使いにくい言葉かもしれません・・・。
母親の手製の服着し幼馴染はベトナムにいると便りを寄こす
かなり破調のお歌ですね。 5・8・7・8・7の区切りでよろしいでしょうか?
私個人でいえば、破調の短歌づくりは苦手の部類でして・・・。
いつのまにか5・7・5・7・7になってしまう頭のかたい奴なのです。
口ずさんだ時のなめらかさも大事だと思うので、まあいいやとほったらかしですが、融通の利かないのも事実。
きょうこさんのこのお歌は破調ですが、なんだか真面目さとか、硬さを感じさせますね。
状況説明のような内容がそう感じさせるのでしょうか。
母親の手製の服をきた幼馴染がベトナムにいる、という珍しい状況を、
真面目に、そのまま伝えている。
ひねた歌詠みならば、読み手が正しく状況を理解などしなくてもよい、という風情で、へんてこな歌をつくりそうです。
理解、解釈は読み手にまかせ、おもしろい歌を作るか。
理解してもらう、ということを主眼におくか。
わたし自身も、この間でゆれうごく詠み人のひとりです。
さて、「母親の手製の服着し幼馴染はベトナムにいると便りを寄こす」というお歌。
「私」か「幼馴染」か、どちらの母親の手製の服を着ているのか、そこで風景が相当変わってきそうです。
私の母親の場合、家族ぐるみの付き合いの深い友達なんだろうな、という解釈になるわけです。
まるで兄弟のような、母親にとっても子供のような、そういう幼馴染を持っている、というのは世間一般では珍しい部類でしょう。
それをお歌の素材にすれば、いいお歌がたくさんできそうです。
というか、親しい幼馴染がいるというのがとてもうらやましいです。
どこかで読んだのですが、母親の手縫いのアイテムを身につける、というのは、風水的に見て「子どもを犯罪や災いから遠ざける」効果があるのだそうです。
幼馴染さんが、どれだけ愛情を注がれている存在であるか。
手製の服、というアイテムひとつで、きっと愛されている人物なのだろうなあ、と想像できるわけです。
歌のなかの「私」も、幼馴染からの便りを受け取り、ベトナムにいるという近況に驚きつつ、
元気そうでよかったな、楽しんでくるといいな、でも危ない目には合わないでね、と、
様々な思いを抱いている情景が浮かんできます。
・・・それにしても、「幼馴染」という単語、つっかえやすいのは私だけでしょうか。
六文字だし、なかなか短歌では使いにくい言葉かもしれません・・・。
遅くなりましたが評をありがとうございます。
他にこのお題で歌が作れないかと考えておりました。
事実そのまま、という感じで面白みがない歌だったでしょうか。
昨年末手紙をもらい、丁度その子が今月誕生日という事もあり、その子は小学校の時、いつも母親(その子の母親)の手作りの洋服を着ていた子だったなぁと思い、この歌を作りました。
母親が誰の母親なのかで歌の解釈が異なるだろうというご指摘、なるほどと思いました。
確かに読み返すとどちらとも取れますね。
面白いですね。
上の句がかなり字余りでつっかえる感じだったでしょうか。
ご指摘のありました三句の「幼馴染は」ですが、5音の部分に使ったのでよりつっかえるかと思いますが、言葉の響き、調べが短歌にあまり適さないという感じでしょうか。
この歌ではかなりつっかえますが、7音のところに使うのであれば特に問題ない語句だと思いましたが。
>どこかで読んだのですが、母親の手縫いのアイテムを身につける、というのは、風水的に見て「子どもを犯罪や災いから遠ざける」効果があるのだそうです。
手縫いの洋服の愛情を更に感じました。
子供ながらにいつも素敵な洋服を着てるその子が羨ましいなと思っていたので。
歌の調べは重要だと感じます。今回は上の句はかなりつっかえますが、結句を定型に納めたからいいかぁと、そんな気持ちです。
歌の作り方は人それぞれなのでどんな作り方でもいいのではないでしょうか。
実際はこういう思いで作ったけれど、歌の印象から別の内容を読み手が感じる事はよくあると思いますし、又それが歌を面白いものにさせると思います。
長文失礼しました。どうもありがとうございました。
他にこのお題で歌が作れないかと考えておりました。
事実そのまま、という感じで面白みがない歌だったでしょうか。
昨年末手紙をもらい、丁度その子が今月誕生日という事もあり、その子は小学校の時、いつも母親(その子の母親)の手作りの洋服を着ていた子だったなぁと思い、この歌を作りました。
母親が誰の母親なのかで歌の解釈が異なるだろうというご指摘、なるほどと思いました。
確かに読み返すとどちらとも取れますね。
面白いですね。
上の句がかなり字余りでつっかえる感じだったでしょうか。
ご指摘のありました三句の「幼馴染は」ですが、5音の部分に使ったのでよりつっかえるかと思いますが、言葉の響き、調べが短歌にあまり適さないという感じでしょうか。
この歌ではかなりつっかえますが、7音のところに使うのであれば特に問題ない語句だと思いましたが。
>どこかで読んだのですが、母親の手縫いのアイテムを身につける、というのは、風水的に見て「子どもを犯罪や災いから遠ざける」効果があるのだそうです。
手縫いの洋服の愛情を更に感じました。
子供ながらにいつも素敵な洋服を着てるその子が羨ましいなと思っていたので。
歌の調べは重要だと感じます。今回は上の句はかなりつっかえますが、結句を定型に納めたからいいかぁと、そんな気持ちです。
歌の作り方は人それぞれなのでどんな作り方でもいいのではないでしょうか。
実際はこういう思いで作ったけれど、歌の印象から別の内容を読み手が感じる事はよくあると思いますし、又それが歌を面白いものにさせると思います。
長文失礼しました。どうもありがとうございました。
☆三浦パンダさん
かぎざきをつくろう友の針と糸オンナたちの傍ら痛し
「オンナたちの傍ら痛し」という下の句の効果で、歌の中にはないオトコたちの姿が見えてきます。
時代が進んでも、裁縫を得意とするのは、やはり男性よりも女性の方が多いのでしょう。
ですので、このお歌を読んだ時、針と糸を持っているのは男性なのか女性なのか、
そこが気になって仕方ありませんでした。
針と糸という言葉が持っている「女性的な」イメージと、言外にあるオトコの存在の間で、
なんとも言えないジェンダーの「ゆらぎ」を感じるのです。
そこを狙ってこのお歌を詠んだのだとしたら、
さすが三浦パンダさん、と脱帽せざるをえません。
でも、私の勝手な思い込みの可能性もありますね。そうだとしたらすみません。
そもそも、かぎざきはどうしてできたのでしょうね。
もしかしたら、このかぎざきは衣服についたものではなくて、
「とりつくろうべき不用意な発言」の暗喩なのかもしれません。
そこで、女性たちの容赦のない舌鉾が痛くて仕方ない、と。
自分のことではないのに、傍らで聞いているだけでも痛い。
オンナたちが集ったら強いですよねー。
おとなしい人だったら、口を挟むこともできないのでは。
繕い物ができて、針と糸が存在する空間というのは、じつに生活感があり、
それなりに親しい人間関係なのでは、と思わせます。
針と糸の持つ生活感、男女間の感覚があらわれた、おもしろいお歌だと思います。
かぎざきをつくろう友の針と糸オンナたちの傍ら痛し
「オンナたちの傍ら痛し」という下の句の効果で、歌の中にはないオトコたちの姿が見えてきます。
時代が進んでも、裁縫を得意とするのは、やはり男性よりも女性の方が多いのでしょう。
ですので、このお歌を読んだ時、針と糸を持っているのは男性なのか女性なのか、
そこが気になって仕方ありませんでした。
針と糸という言葉が持っている「女性的な」イメージと、言外にあるオトコの存在の間で、
なんとも言えないジェンダーの「ゆらぎ」を感じるのです。
そこを狙ってこのお歌を詠んだのだとしたら、
さすが三浦パンダさん、と脱帽せざるをえません。
でも、私の勝手な思い込みの可能性もありますね。そうだとしたらすみません。
そもそも、かぎざきはどうしてできたのでしょうね。
もしかしたら、このかぎざきは衣服についたものではなくて、
「とりつくろうべき不用意な発言」の暗喩なのかもしれません。
そこで、女性たちの容赦のない舌鉾が痛くて仕方ない、と。
自分のことではないのに、傍らで聞いているだけでも痛い。
オンナたちが集ったら強いですよねー。
おとなしい人だったら、口を挟むこともできないのでは。
繕い物ができて、針と糸が存在する空間というのは、じつに生活感があり、
それなりに親しい人間関係なのでは、と思わせます。
針と糸の持つ生活感、男女間の感覚があらわれた、おもしろいお歌だと思います。
☆きょうこさん
丁寧なお返事ありがとうございます。
「幼馴染」という単語がつっかえる、というのは、あくまで私の個人的な感想というか、
なんかうまく発音できない言葉みっけ!という発見の勢いで書いた事なのです。
文章まで舌っ足らずで申し訳ありません
>歌の作り方は人それぞれなのでどんな作り方でもいいのではないでしょうか。
実際はこういう思いで作ったけれど、歌の印象から別の内容を読み手が感じる事はよくあると思いますし、又それが歌を面白いものにさせると思います。
私もそう思います。むしろ、読み手に想像の幅をもたせる「あそび」のあるお歌にひかれます。
*+☆+*――*+☆+*――*+☆+**+☆+*――*+☆+*――*+☆+*
並べいるビーズの指輪をそっとはめ結び目チクリ中指を刺す
ビーズは可愛いですよねー。
ちいさくて、まるくて。色もとても綺麗で、中には美味しそうと思ってしまうものもあったり。
以前ビーズの指輪を作ったことがあるので、このお歌を拝見したときの感想は「あるある!」でした。
ビーズ細工の最後の仕上げは、糸の結び目をビーズの穴の中にしまうこと。
でも、いつの間にか糸がずれて結び目が出てきてしまう・・・。
手指は感覚が鋭いので、小さな結び目でもチクチクして気になって仕方なかったことを覚えています。
このお歌は、読み手によっては別の意味も感じさせるかもしれません。
それは「指輪」というアクセサリーが持つイメージによるものしょうか。
指輪=恋愛・結婚というイメージがどうも喚起されてしまうようです。
ですが、指輪をはめるのは薬指ではなく中指。
どうやら歌の主人公は恋愛中ではないらしい、ということがここからわかります。
かわいらしいビーズの指輪をそっとはめたときに、結び目が中指をチクリと刺す。
そのとき、どんな思いが胸に去来したのでしょうか。
「チクリ」という片仮名が効いていると思います。
丁寧なお返事ありがとうございます。
「幼馴染」という単語がつっかえる、というのは、あくまで私の個人的な感想というか、
なんかうまく発音できない言葉みっけ!という発見の勢いで書いた事なのです。
文章まで舌っ足らずで申し訳ありません
>歌の作り方は人それぞれなのでどんな作り方でもいいのではないでしょうか。
実際はこういう思いで作ったけれど、歌の印象から別の内容を読み手が感じる事はよくあると思いますし、又それが歌を面白いものにさせると思います。
私もそう思います。むしろ、読み手に想像の幅をもたせる「あそび」のあるお歌にひかれます。
*+☆+*――*+☆+*――*+☆+**+☆+*――*+☆+*――*+☆+*
並べいるビーズの指輪をそっとはめ結び目チクリ中指を刺す
ビーズは可愛いですよねー。
ちいさくて、まるくて。色もとても綺麗で、中には美味しそうと思ってしまうものもあったり。
以前ビーズの指輪を作ったことがあるので、このお歌を拝見したときの感想は「あるある!」でした。
ビーズ細工の最後の仕上げは、糸の結び目をビーズの穴の中にしまうこと。
でも、いつの間にか糸がずれて結び目が出てきてしまう・・・。
手指は感覚が鋭いので、小さな結び目でもチクチクして気になって仕方なかったことを覚えています。
このお歌は、読み手によっては別の意味も感じさせるかもしれません。
それは「指輪」というアクセサリーが持つイメージによるものしょうか。
指輪=恋愛・結婚というイメージがどうも喚起されてしまうようです。
ですが、指輪をはめるのは薬指ではなく中指。
どうやら歌の主人公は恋愛中ではないらしい、ということがここからわかります。
かわいらしいビーズの指輪をそっとはめたときに、結び目が中指をチクリと刺す。
そのとき、どんな思いが胸に去来したのでしょうか。
「チクリ」という片仮名が効いていると思います。
☆まめこさん
いつの日か ちくちく縫ってつながって すてきななにかに なるはずなのよ
あ、なんか好きです。この歌。
縫い物って、とにかく根気がいって細かくて、
縫い始めは「これが形になるのか?」とホントに疑問で。
型紙なんか立体と数学の世界です。ぜんぜん理解できません。
ちくちくちくちく、とにかくコツコツコツコツ、ちょっとずつ進めていって、
ふと気がつくと何かの形になっているのです。
スカートとか、バッグとか、お花の刺繍とか。
縫うことは祈りに似ている、とさえ思います。
だって、ほんとうに最初は、完成形が見えないような布の切れ端ですものね。
「すてきななにか」になることを願って、短気にならず、投げ出さずに続ける。
できれば時間をかけて、丁寧に綺麗な仕立で。
そうするとさらにすてきなものになるので。
「いつの日か ちくちく縫ってつながって すてきななにかに なるはずなのよ」
可憐な乙女が口ずさんでいるかのような、やわらかな語り口のお歌ですが、
じつは鉄のド根性が隠されているようです。
そうです、乙女の根気はすごいのです。じゃなけりゃ「すてきななにか」なんてできるわけがない。
今は先が見えないけれども、何とか信じてすこしずつやって行こう。
そんな気にさせてくれる、すてきなお歌です。
ありがとうございました。
いつの日か ちくちく縫ってつながって すてきななにかに なるはずなのよ
あ、なんか好きです。この歌。
縫い物って、とにかく根気がいって細かくて、
縫い始めは「これが形になるのか?」とホントに疑問で。
型紙なんか立体と数学の世界です。ぜんぜん理解できません。
ちくちくちくちく、とにかくコツコツコツコツ、ちょっとずつ進めていって、
ふと気がつくと何かの形になっているのです。
スカートとか、バッグとか、お花の刺繍とか。
縫うことは祈りに似ている、とさえ思います。
だって、ほんとうに最初は、完成形が見えないような布の切れ端ですものね。
「すてきななにか」になることを願って、短気にならず、投げ出さずに続ける。
できれば時間をかけて、丁寧に綺麗な仕立で。
そうするとさらにすてきなものになるので。
「いつの日か ちくちく縫ってつながって すてきななにかに なるはずなのよ」
可憐な乙女が口ずさんでいるかのような、やわらかな語り口のお歌ですが、
じつは鉄のド根性が隠されているようです。
そうです、乙女の根気はすごいのです。じゃなけりゃ「すてきななにか」なんてできるわけがない。
今は先が見えないけれども、何とか信じてすこしずつやって行こう。
そんな気にさせてくれる、すてきなお歌です。
ありがとうございました。
評をありがとうございました。
今更ですが初句を間違えておりました。
並べいる→並びいる
です。すみません。
指輪をはめる指は大事なのですね。
私は中指か人差し指にしか指輪をしないので、ほ〜と思いました。
手作りの雑貨屋での出来事を歌いました。
ビーズのアクセがあるといつも指輪を試しにはめてみるのですが、結び目が丁度指に当たる位置にきて痛っとなったんです。
そのショップは個人の作家さんが集まって商品を売っているので、そういう指輪がたまにありまして。
チクリの表記は片仮名で良かったですかね。
痛って感じを出したいなと思いました。
前回の歌ですが、ナ行は舌先が上顎に付く発音なので舌足らずな人は発音しにくいかもですね。
しかも「おさななじみ」は「な」が二つ重なりますので言いにくさも倍増かと思います。
話がそれましたが、優しい評をありがとうございました。
今更ですが初句を間違えておりました。
並べいる→並びいる
です。すみません。
指輪をはめる指は大事なのですね。
私は中指か人差し指にしか指輪をしないので、ほ〜と思いました。
手作りの雑貨屋での出来事を歌いました。
ビーズのアクセがあるといつも指輪を試しにはめてみるのですが、結び目が丁度指に当たる位置にきて痛っとなったんです。
そのショップは個人の作家さんが集まって商品を売っているので、そういう指輪がたまにありまして。
チクリの表記は片仮名で良かったですかね。
痛って感じを出したいなと思いました。
前回の歌ですが、ナ行は舌先が上顎に付く発音なので舌足らずな人は発音しにくいかもですね。
しかも「おさななじみ」は「な」が二つ重なりますので言いにくさも倍増かと思います。
話がそれましたが、優しい評をありがとうございました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
現代短歌会 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
現代短歌会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37846人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31947人