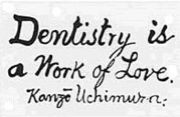昨年4月の保険診療改訂において,
「歯科衛生士は終わった.必要ない」という声を多々聞きました.今回,そこにある真意を探ります.
以下,「アポロニア:安田編集室」(1月号)より引用.
「歯科衛生士にスケーリングをさせると個別指導を受けますよ」と言われて本気にする開業医はいないはずです.
しかし,実際に個別指導の指導理由の中に,「歯科衛生士によるスケーリングが行われているため」という項目が見られることがあります.
これは,指導医療官と保険医との間に,SCに関する定義の違いがあるためのようです.
06年改訂に伴い,厚生労働省では,SCを縁下歯石の除去に限定する見解を示し,
通常,歯科衛生士が行っている縁上の除石は,SCで算定できず,基本診療に含まれることにしたのです.
それ以前にも歯科衛生士によるSCに疑義付箋を付ける技官も一部存在したようですが,
これが全国的なルールとされてしまいました.
他にも歯科衛生士業務とされてきた行為について,過剰とも言える規制が掛かっています.
この過剰な規制は,歯科医療現場の実体からかけ離れた規制であると言えます.
この規制の根拠となっているのは,日本歯周病学会のガイドラインですが,最近の保険行政においては,学術団体のガイドラインを恣意的に引用してくる傾向が見られます.
しかし,根拠となっているガイドラインと厚労省の示しているSCの定義との間には若干の違いがあり,関連性は薄いように思われます.
◆厚労省のSCの見解
歯周ポケット内の歯面に付着している歯石等の沈着物を除去することをいい,単に歯の露出部分に付着した歯石等の除去のみを行った場合の費用は,基本診療料に含まれる.
◆日本歯周病学会のガイドライン
歯に付着したプラーク,歯石,その他の沈着物を機械的に除去することであり,ルートプレーニングは,スケーリングに加えてポケットに面する根表面の粗造で細菌やその代謝産物を含む病的なセメント質を除去し,生物学的に為害性のない滑沢な根面にすることである.
このような恣意的に「学術的根拠」を持ち出す傾向が顕著になってくると,誰も厚労省の規制を守らなくなり,指導の場での技官の裁量が過大となると推測できます.
実際,06年改訂の後,かなりの数の歯科医院がメインテナンスを保険診療から切り離しているようです.
最終的に歯科衛生士業務の制限強化が目指しているものは,
★自費のメインテナンス+保険の治療という流れの確立で,
「保険医療の現場では歯科衛生士は必要ない」ということになります.
歯科衛生士業務の縮小は,時代の流れに逆行しており,なおかつ,保険診療の場からの歯科衛生士の排除に繋がるような規制であり,国民の誰にとっても利益になりません.
例の神戸の歯科衛生士による投薬問題においては,
厚労省は所要の条件と技量され整っていれば法に抵触しない旨を指摘しています.
つまり「診療補助」として行う歯科衛生士の業務範囲は非常に広いことを国は認めていることになります.
この事実と現在,一部で進んでいる歯科衛生士業務のへの規制は,明らかに矛盾していると言えるでしょう.
後編に続く.
「歯科衛生士は終わった.必要ない」という声を多々聞きました.今回,そこにある真意を探ります.
以下,「アポロニア:安田編集室」(1月号)より引用.
「歯科衛生士にスケーリングをさせると個別指導を受けますよ」と言われて本気にする開業医はいないはずです.
しかし,実際に個別指導の指導理由の中に,「歯科衛生士によるスケーリングが行われているため」という項目が見られることがあります.
これは,指導医療官と保険医との間に,SCに関する定義の違いがあるためのようです.
06年改訂に伴い,厚生労働省では,SCを縁下歯石の除去に限定する見解を示し,
通常,歯科衛生士が行っている縁上の除石は,SCで算定できず,基本診療に含まれることにしたのです.
それ以前にも歯科衛生士によるSCに疑義付箋を付ける技官も一部存在したようですが,
これが全国的なルールとされてしまいました.
他にも歯科衛生士業務とされてきた行為について,過剰とも言える規制が掛かっています.
この過剰な規制は,歯科医療現場の実体からかけ離れた規制であると言えます.
この規制の根拠となっているのは,日本歯周病学会のガイドラインですが,最近の保険行政においては,学術団体のガイドラインを恣意的に引用してくる傾向が見られます.
しかし,根拠となっているガイドラインと厚労省の示しているSCの定義との間には若干の違いがあり,関連性は薄いように思われます.
◆厚労省のSCの見解
歯周ポケット内の歯面に付着している歯石等の沈着物を除去することをいい,単に歯の露出部分に付着した歯石等の除去のみを行った場合の費用は,基本診療料に含まれる.
◆日本歯周病学会のガイドライン
歯に付着したプラーク,歯石,その他の沈着物を機械的に除去することであり,ルートプレーニングは,スケーリングに加えてポケットに面する根表面の粗造で細菌やその代謝産物を含む病的なセメント質を除去し,生物学的に為害性のない滑沢な根面にすることである.
このような恣意的に「学術的根拠」を持ち出す傾向が顕著になってくると,誰も厚労省の規制を守らなくなり,指導の場での技官の裁量が過大となると推測できます.
実際,06年改訂の後,かなりの数の歯科医院がメインテナンスを保険診療から切り離しているようです.
最終的に歯科衛生士業務の制限強化が目指しているものは,
★自費のメインテナンス+保険の治療という流れの確立で,
「保険医療の現場では歯科衛生士は必要ない」ということになります.
歯科衛生士業務の縮小は,時代の流れに逆行しており,なおかつ,保険診療の場からの歯科衛生士の排除に繋がるような規制であり,国民の誰にとっても利益になりません.
例の神戸の歯科衛生士による投薬問題においては,
厚労省は所要の条件と技量され整っていれば法に抵触しない旨を指摘しています.
つまり「診療補助」として行う歯科衛生士の業務範囲は非常に広いことを国は認めていることになります.
この事実と現在,一部で進んでいる歯科衛生士業務のへの規制は,明らかに矛盾していると言えるでしょう.
後編に続く.
|
|
|
|
コメント(9)
>arikaさま
お久しぶりです.コメントありがとうございました!
このトピですが,途中省略してあります.
たぶんarikaさんが疑問に思っている箇所ですので,記載しますね.
「なぜ,このような過剰な規制が起きているのでしょうか?
そこには,規制強化の一方,肝心の歯科衛生士業務の範囲について厚労省は,
統一的見解を出していません.
これは,歯科衛生士法の定める「診療の補助」の規定が曖昧であるからだと考えられます.
他の医療関連職種(例えば看護師など)に認められている「診療の補助」の範囲は,
具体的,かつ明確です.
では,業務範囲が明確でないと利益を受ける人(集団)がどこにいるか?
単純に考えれば,保険行政の実施に当たる指導医療官(指導の裁量権を拡大できるため)であるように思われますが,
必ずしもそれだけでなく,歯科医療において明確でない「診療の補助」は,解釈によっては非常に拡大させることができます.
咬合面の形態付与を含まないコンポジットレジン充填処置,レントゲン撮影のボタン押しはもとより,極めて強引に解釈すれば,麻酔下でなく,かつ非可逆的でない処置はいずれも「補助」の対象と言うこともできます.
この歯科衛生士の「診療の補助」の範囲には,地域差どころか診療施設ごとに差があると見てよいでしょう.
それによって最も利益を得ていたのは誰か?
仕事を丸投げできる歯科医師ではなかったでしょうか.
口では「コ・デンタルスタッフ」などど言いながら,仲間であるはずの歯科衛生士の業務範囲を曖昧にすることで,人件費を節約し,効率的な診療を続けてきた事実は,大きな欺瞞であると思われます.
それでは,現在行われいてる規制強化は,そのような欺瞞を解消すること繋がるのでしょうか?
業務範囲の明確化という場合,2つの方向性が考えられます.
1つは歯科衛生士業務範囲を拡大的に明確化すること.
もう1つは縮小的に明確化することです.
厚労省が行いつつあるのは,業務範囲を明確化せずに縮小のみを行うものであり,
歯科衛生士業務の将来像を暗いものにしてしまいます.
現在,歯科衛生士の行っている「診療の補助」は,
本来,歯科医師が行っていた業務の肩代わりという側面があり,これらの「コ・デンタルスタッフ」の業務は,「診療の補助」というよりは,歯科医師の業務を委託されているものと見られ,本質的には歯科医師が行う業務と見なされ易いのです.
>打破するためには、何をすべきか考えないと・・・。
歯科医師の意識改革と違法なことをやらされない=断る勇気,
そして,歯科衛生士法の改正しかないのでしょうか?
お久しぶりです.コメントありがとうございました!
このトピですが,途中省略してあります.
たぶんarikaさんが疑問に思っている箇所ですので,記載しますね.
「なぜ,このような過剰な規制が起きているのでしょうか?
そこには,規制強化の一方,肝心の歯科衛生士業務の範囲について厚労省は,
統一的見解を出していません.
これは,歯科衛生士法の定める「診療の補助」の規定が曖昧であるからだと考えられます.
他の医療関連職種(例えば看護師など)に認められている「診療の補助」の範囲は,
具体的,かつ明確です.
では,業務範囲が明確でないと利益を受ける人(集団)がどこにいるか?
単純に考えれば,保険行政の実施に当たる指導医療官(指導の裁量権を拡大できるため)であるように思われますが,
必ずしもそれだけでなく,歯科医療において明確でない「診療の補助」は,解釈によっては非常に拡大させることができます.
咬合面の形態付与を含まないコンポジットレジン充填処置,レントゲン撮影のボタン押しはもとより,極めて強引に解釈すれば,麻酔下でなく,かつ非可逆的でない処置はいずれも「補助」の対象と言うこともできます.
この歯科衛生士の「診療の補助」の範囲には,地域差どころか診療施設ごとに差があると見てよいでしょう.
それによって最も利益を得ていたのは誰か?
仕事を丸投げできる歯科医師ではなかったでしょうか.
口では「コ・デンタルスタッフ」などど言いながら,仲間であるはずの歯科衛生士の業務範囲を曖昧にすることで,人件費を節約し,効率的な診療を続けてきた事実は,大きな欺瞞であると思われます.
それでは,現在行われいてる規制強化は,そのような欺瞞を解消すること繋がるのでしょうか?
業務範囲の明確化という場合,2つの方向性が考えられます.
1つは歯科衛生士業務範囲を拡大的に明確化すること.
もう1つは縮小的に明確化することです.
厚労省が行いつつあるのは,業務範囲を明確化せずに縮小のみを行うものであり,
歯科衛生士業務の将来像を暗いものにしてしまいます.
現在,歯科衛生士の行っている「診療の補助」は,
本来,歯科医師が行っていた業務の肩代わりという側面があり,これらの「コ・デンタルスタッフ」の業務は,「診療の補助」というよりは,歯科医師の業務を委託されているものと見られ,本質的には歯科医師が行う業務と見なされ易いのです.
>打破するためには、何をすべきか考えないと・・・。
歯科医師の意識改革と違法なことをやらされない=断る勇気,
そして,歯科衛生士法の改正しかないのでしょうか?
>なんこっつさん
コメントありがとうございます.
ここでは,このような動き(歯科医師,行政など)があると,
皆様に知って頂きたく,記事を掲載しております.
実際,06年改訂の後,かなりの数の歯科医院がメインテナンスを保険診療から切り離しているようです.
こうなると,厚生技官の行う保険行政の対応する範疇ではありませんから,比較的自由に予防型歯科医療を実践できますし,保険者でもある厚労省にとっても,その歯科医院からの上がってくる請求点数が自然に制御されますから利益となります.
このような自費のメインテナンス+保険治療の流れは,
歯科医療の業態変化に繋がるものとプラスに評価できますが,それを強制的にナショナルスタンダードとすることには大きな疑問があります.
なんこっつさんは,たぶん「SCが行えなくなるのではないからいい」と考えられているのでしょうが,受益者側=患者さんにとってはどうなのでしょう?
却って迷惑な節もあると思います.
歯科医療が不振な昨今,皆が自費治療に走ったら,保険治療をしなくなったら,
それも様々な問題が起こると思います.
コメントありがとうございます.
ここでは,このような動き(歯科医師,行政など)があると,
皆様に知って頂きたく,記事を掲載しております.
実際,06年改訂の後,かなりの数の歯科医院がメインテナンスを保険診療から切り離しているようです.
こうなると,厚生技官の行う保険行政の対応する範疇ではありませんから,比較的自由に予防型歯科医療を実践できますし,保険者でもある厚労省にとっても,その歯科医院からの上がってくる請求点数が自然に制御されますから利益となります.
このような自費のメインテナンス+保険治療の流れは,
歯科医療の業態変化に繋がるものとプラスに評価できますが,それを強制的にナショナルスタンダードとすることには大きな疑問があります.
なんこっつさんは,たぶん「SCが行えなくなるのではないからいい」と考えられているのでしょうが,受益者側=患者さんにとってはどうなのでしょう?
却って迷惑な節もあると思います.
歯科医療が不振な昨今,皆が自費治療に走ったら,保険治療をしなくなったら,
それも様々な問題が起こると思います.
>aikaさま
コメントありがとうございます.
こうなると混合診療を認めるべきだと思うのですか・・・.
国民皆保険という日本のウリであり,よさでもある保険は,
国民誰もが平等に医療を受けられる利点があります.
したがって,歯科診療においても,疾病の治癒に関する部分は保険で,
その先の修復に関わる部分は保険か私費を選択できるようにする.
審美は,私費でも構わないと思います.それを選択するのは,患者さんだからです.
既に諸外国では行われているのですが,私費にも選択の幅を設ける.
例えば,私費の1級窩洞のCR充填は,1万円で,
複雑窩洞は,3〜5万円と選択することができるようにする.
もちろん私費であれば,歯科医院独自のスタイルを設けられますからね.如何でしょうか?
コメントありがとうございます.
こうなると混合診療を認めるべきだと思うのですか・・・.
国民皆保険という日本のウリであり,よさでもある保険は,
国民誰もが平等に医療を受けられる利点があります.
したがって,歯科診療においても,疾病の治癒に関する部分は保険で,
その先の修復に関わる部分は保険か私費を選択できるようにする.
審美は,私費でも構わないと思います.それを選択するのは,患者さんだからです.
既に諸外国では行われているのですが,私費にも選択の幅を設ける.
例えば,私費の1級窩洞のCR充填は,1万円で,
複雑窩洞は,3〜5万円と選択することができるようにする.
もちろん私費であれば,歯科医院独自のスタイルを設けられますからね.如何でしょうか?
続きを書きます.
以下,「アポロニア」2月号を引用しますが,今回は,「制度に負けないチーム作り」という特集で,最近多く話題に上っている「歯科衛生士の業務範囲」,「コ・デンタルスタッフ」に関して充実した内容となっています.
今回は,歯科衛生士の皆様に是非,購読をオススメします♪
内容が豊富すぎて,今回は,その一部しか説明できません.
知らないのは私だけかもしれませんが,皆さん知っていました?
2005年4月施工に業務改正で「コ・デンタルスタッフ」に,
「臨床検査技師」と「臨床放射線技師」が新たに加わったのです.これには驚きました^^
歯科医療の担い手が交替していく兆しなのでしょうか?
今回は,この辺りにフォーカスした記事の概略を記載します.
「コ・デンタルスタッフが拡大している.
プライマリケアの窓口:臨床検査技師による検査を実施.
生活習慣にへのアプローチを進めていく上で,大きな制度改正が2005年4月に行われました.
歯科医師の指示により,臨床検査技師,臨床放射線技師が歯科医師の診療の補助を行えるようになったのです.
彼らが行い得る「診療の補助」とは,従来の歯科医療現場では考えられなかったほど広く,例えば,臨床検査技師には,全身状態の検査を目的とした採血が認められており,
臨床放射線技師は歯科医師を「X線のボタン押し」から解放してくれるだけでなく,一般的な歯科医師が到底なし得ないような高度な放射線診断の知識,技量を備えています.
歯科に限ったことではありませんが,医療はチームで行うものですから,各種専門職を雇用することは,その歯科医院の総合力を広げ,高めます.
現在,臨床検査技師,臨床放射線技師は,その高度な専門性,教育水準にもかかわらず,労働市場であまり高く評価されていません.そのため,地域によっては歯科衛生士と同額程度の給与で雇用できるという利点があります.
康本歯科医院(千葉)では,既に2人の臨床検査技師を雇っています.
そこでは,主に血液化学検査による生活習慣病関連の定期検査,生活指導と金属アレルギーのリスク診断を行っています.また,全身の健康状態のチェックを定期健診,口腔ケアと同時に行う流れができれば,地域において,歯科医院がプライマリケアの窓口として大きな社会的意義を持つようになるものと期待できます.
本来的に歯科医師が行ってきた業務の「代行」に近い業務範囲に限定されてきた歯科衛生士,歯科技工士だけでなく,新たなコ・デンタルスタッフの雇用も可能になった現在,コ・デンタルスタッフの業務拡大,拡充は,歯科医療の将来像を予想しなかった領域にまで広げることに繋がるのではないかと期待できます.
今,コ・デンタルスタッフの業務範囲を確立し,さらに拡大していくことこそ,歯科医療の将来像を明るくするものではないでしょうか.
新たなコ・デンタルスタッフの仲間入りで,歯科医師の指示のもとにという非常に曖昧な括りで,私達は,学校で習ってもいない医療行為をさせられることが無くなります.
ある歯科大学の教授で歯科衛生士学校の校長もされている歯科医師がおっしゃいました.
違法なのは,その指導経験の無い者(歯科医師)が,例えば歯周処置や採血などを歯科衛生士にさせることが問題なのだと.
やらせる者,やらされる者は一蓮托生としても,
一番被害をこうむるのは患者さんであるということを忘れないようにしたいものです.
以下,「アポロニア」2月号を引用しますが,今回は,「制度に負けないチーム作り」という特集で,最近多く話題に上っている「歯科衛生士の業務範囲」,「コ・デンタルスタッフ」に関して充実した内容となっています.
今回は,歯科衛生士の皆様に是非,購読をオススメします♪
内容が豊富すぎて,今回は,その一部しか説明できません.
知らないのは私だけかもしれませんが,皆さん知っていました?
2005年4月施工に業務改正で「コ・デンタルスタッフ」に,
「臨床検査技師」と「臨床放射線技師」が新たに加わったのです.これには驚きました^^
歯科医療の担い手が交替していく兆しなのでしょうか?
今回は,この辺りにフォーカスした記事の概略を記載します.
「コ・デンタルスタッフが拡大している.
プライマリケアの窓口:臨床検査技師による検査を実施.
生活習慣にへのアプローチを進めていく上で,大きな制度改正が2005年4月に行われました.
歯科医師の指示により,臨床検査技師,臨床放射線技師が歯科医師の診療の補助を行えるようになったのです.
彼らが行い得る「診療の補助」とは,従来の歯科医療現場では考えられなかったほど広く,例えば,臨床検査技師には,全身状態の検査を目的とした採血が認められており,
臨床放射線技師は歯科医師を「X線のボタン押し」から解放してくれるだけでなく,一般的な歯科医師が到底なし得ないような高度な放射線診断の知識,技量を備えています.
歯科に限ったことではありませんが,医療はチームで行うものですから,各種専門職を雇用することは,その歯科医院の総合力を広げ,高めます.
現在,臨床検査技師,臨床放射線技師は,その高度な専門性,教育水準にもかかわらず,労働市場であまり高く評価されていません.そのため,地域によっては歯科衛生士と同額程度の給与で雇用できるという利点があります.
康本歯科医院(千葉)では,既に2人の臨床検査技師を雇っています.
そこでは,主に血液化学検査による生活習慣病関連の定期検査,生活指導と金属アレルギーのリスク診断を行っています.また,全身の健康状態のチェックを定期健診,口腔ケアと同時に行う流れができれば,地域において,歯科医院がプライマリケアの窓口として大きな社会的意義を持つようになるものと期待できます.
本来的に歯科医師が行ってきた業務の「代行」に近い業務範囲に限定されてきた歯科衛生士,歯科技工士だけでなく,新たなコ・デンタルスタッフの雇用も可能になった現在,コ・デンタルスタッフの業務拡大,拡充は,歯科医療の将来像を予想しなかった領域にまで広げることに繋がるのではないかと期待できます.
今,コ・デンタルスタッフの業務範囲を確立し,さらに拡大していくことこそ,歯科医療の将来像を明るくするものではないでしょうか.
新たなコ・デンタルスタッフの仲間入りで,歯科医師の指示のもとにという非常に曖昧な括りで,私達は,学校で習ってもいない医療行為をさせられることが無くなります.
ある歯科大学の教授で歯科衛生士学校の校長もされている歯科医師がおっしゃいました.
違法なのは,その指導経験の無い者(歯科医師)が,例えば歯周処置や採血などを歯科衛生士にさせることが問題なのだと.
やらせる者,やらされる者は一蓮托生としても,
一番被害をこうむるのは患者さんであるということを忘れないようにしたいものです.
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ベテラン歯科衛生士への道 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
ベテラン歯科衛生士への道のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77414人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209452人
- 3位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19955人