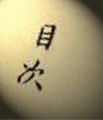訳者まえがき 福井信子
序 章 ミューズ的人間
第一章 基礎は胎児のときに形成される
胎児期のミューズ的意味
音と記憶
母親の声が果たす役割
運動と神経学
未熟児とミューズ的な新しい哺育器についての長い脚注
第二章 遊ぶ子どもは生きることを学ぶ
スウィングしなければ意味はない!
社会的能力が獲得されるまで
生まれてまもないわが子と一緒に歌いなさい
――たとえ歌が下手であっても!
子ども文化にいたる諸段階
第三章 遊ぶ子どもの文化
不快さの勝利
子ども文化の中で
遊びが世界を変える
エコロジー的な子ども
類推的対応
生命形態としての遊び――今ここで、時空を超えて
ジェシー・オーエンズになった「トテムの犬の負け犬」
子ども文化が打ち砕かれ子どもは学ぶ
赤いゴムボールの話
境界を突破する遊び
「ファンタジー」を生み出すもの
ロックギターとは何か
遊び、数学、認識、ユーモア
ユーモアの効用
ミューズ的命令
生命の足場としての遊び
遊び、音楽という概念についてより詳しく
全身で感じる音楽
歌と踊りがもたらす「全体感覚」
「ンゴーマ」は世界をつなぐ
「ミューズ的人間」のなりたち
「ナルニア国」が誕生するまで
第四章 三国における歌う子ども文化
――ノルウェー、ソ連、アメリカ
三国共通の子ども文化は存在するのか
ノルウェーの子ども文化から――オスロでの調査
観察の方法
オスロ
自発的な歌
歌の形式
歌の用法
形式と用法の相互作用
「決まり歌」の特徴
歌を通して自己を表現する
ペールの蝶々
即興と替え歌
私たちの音楽的母語とその機能
社会化への足がかり
質と音楽性
ロシアの子ども文化から――レニングラードでの調査
レニングラード
ソ連での研究
歌の形式――ノルウェーとの比較
決まり歌のイントネーション
なぜ、決まり歌が存在しないのか
歌の用法
機能と音楽性
『ソヴィエツカヤ・ムジカ』は「将来を」見つめる
アメリカの子ども文化から――ロサンジェルスでの調査
ロサンジェルス
ニール・ポストマンと「アメリカの失われた子ども時代」
子どもたちの自発的な歌
――世界に広がっている私たちの音楽的母語
歌の形式
歌の用法
自発的な歌の機能
「非音楽の普遍性」
:自発的な子どもの歌は普遍的な音楽的母語なのか
第五章 教室でのミューズ的人間
この世はうるわし
私たちの迷宮
子ども時代との決裂
学習エコロジーから学習の断絶へ
文字文化と声の文化
抑圧された者たちの教育
子ども時代を敬え!
文字が読めない者への賛辞
今日のアメリカにおける「二次的に文字が読めないということ」
ノルウェーはどうか
アメリカ、北欧、発展途上国における就学年齢の引き下げ
全日制学校と楽園中の楽園について
ソ連はどうか
学習エコロジーから授業エコロジーへ
ミューズ的教師
学年制度の再組織化
共同学習の効果――ノルウェーでの試みから
学校音楽隊
学校に音楽が増えると学習環境はより良くなるか
全身で学習すること
断絶を解消するための具体例
最初に喜び、最後も喜び
歌と母語の方言
驚嘆を学校の資源として
ミューズ的、創造的、美的、芸術的:概念の明確化
音楽か? 音楽だ!
失楽園:失われた子ども時代を求めて
――ある「指導者コース」の実例
学校、創造性、政治
第六章 子ども文化と音楽教育
カール・ニルセンの子ども時代
子ども文化のミューズ的学習の歌――音楽教育的指針
赤いゴムボールからトランペットへ
――楽器を初めて手にしてから一年の間に起こったこと
私たちは1987年9月に開始した
なぜ「レット・イット・ビー」なのか
まずは歌うことから
サッチモの翼に乗って
「バンドを作ろう!」
音楽教育史の概略
音と音符――音楽の世界における文字文化と声の文化について
音楽史の民衆文化と芸術文化における楽譜なしの演奏
子どもとと鳥、学習と音感
表現の限界としての音符表記
移調の技法
音楽と譜面、親近性と距離
消えた音楽――音楽教育の「壁にネズミ(mus-i-muur)」について
ルリーおばさんと「春のささやき」
楽器と身体
いつ、何から
子どもにあまり早くから始めさせないこと
歌、山賊の娘ローニャ
ルチアーノ・ベリオ
ドラム+歌+踊り
ベアンハート・クリステンセンと子どものドラム奏者
最初の楽器はピアノ?
管楽器
日本の音楽教育法についての小コメント
多面性
楽譜演奏はいつ導入すべきか
十戒――音楽を学ぶ生徒の日常
弾き間違いからユーモアへ
恐れずに音楽演奏?
早期の音楽経験とレパートリの幅
音楽のモダニズムと子ども
過去を向いた音楽レパートリ
コダーイと五音音階
モーツァルトの影から教則本『古典対位法』
(グラドゥス・アド・パルナッスム)へ
「音にあまり注意を払うな!」
頭よりも心で先に、真実を見つけなさい
第七章 もしあなたが誰かを愛しているなら
――彼らを自由にしてやりなさい!
引っ込め、審判!
産声と思春期
アメリカ、ノルウェー、ソ連――ロックの仕方は様々
移ろいやすさという力
「ザ・スナフーズ」
永遠の10代
ロックだけではなく
嵐は眠る
第八章 子どもとと芸術家
芸術家の内なる「子どもらしさ」
ディミトリ・ショスタコーヴィチ
――芸術的な展開をするミューズ的人間
ゴーゴリとともに若者の反乱
ロシア文学とカーニバル主義
笑いから不安へ
ユロツヴォ(Jurodstvo)
仮面の陰で
幕がおりる
交響曲第五番――恐怖の爪につかまれて
音楽家は歴史を記録する
第一楽章の最後に何が起こるのか
第二楽章は慣用を新たに破壊する
三楽章と四楽章は共通の特徴を持っている
交響曲第13番前史――雪解けと凍結
仮面を脱ぐとき
ユーモアよ、永遠なれ!
ロシアの内なる恐怖は死ぬ
社会全体が目覚めるとき――鼻なしで
ミューズ的句読点
第九章 三つの肖像
祖母の陣地
オスカーおじさんと金婚式のワルツ
足は踏み、心臓は打つ
第十章 合唱によるコラージュ
子どもらしい前奏曲
彼らは歌いながら死に出会った
「トレバーク」――ロシアの農民の踊り
When the Saints go marchin' in(聖者の行進)――黒人霊歌
Slipsteinsvailsen(砥石のワルツ)
En spelmans jordafard(ある楽士の埋葬)
子どもらしい後奏曲
参考文献
訳者あとがき 福井信子
*第五章まで:上巻
第六章から:下巻
序 章 ミューズ的人間
第一章 基礎は胎児のときに形成される
胎児期のミューズ的意味
音と記憶
母親の声が果たす役割
運動と神経学
未熟児とミューズ的な新しい哺育器についての長い脚注
第二章 遊ぶ子どもは生きることを学ぶ
スウィングしなければ意味はない!
社会的能力が獲得されるまで
生まれてまもないわが子と一緒に歌いなさい
――たとえ歌が下手であっても!
子ども文化にいたる諸段階
第三章 遊ぶ子どもの文化
不快さの勝利
子ども文化の中で
遊びが世界を変える
エコロジー的な子ども
類推的対応
生命形態としての遊び――今ここで、時空を超えて
ジェシー・オーエンズになった「トテムの犬の負け犬」
子ども文化が打ち砕かれ子どもは学ぶ
赤いゴムボールの話
境界を突破する遊び
「ファンタジー」を生み出すもの
ロックギターとは何か
遊び、数学、認識、ユーモア
ユーモアの効用
ミューズ的命令
生命の足場としての遊び
遊び、音楽という概念についてより詳しく
全身で感じる音楽
歌と踊りがもたらす「全体感覚」
「ンゴーマ」は世界をつなぐ
「ミューズ的人間」のなりたち
「ナルニア国」が誕生するまで
第四章 三国における歌う子ども文化
――ノルウェー、ソ連、アメリカ
三国共通の子ども文化は存在するのか
ノルウェーの子ども文化から――オスロでの調査
観察の方法
オスロ
自発的な歌
歌の形式
歌の用法
形式と用法の相互作用
「決まり歌」の特徴
歌を通して自己を表現する
ペールの蝶々
即興と替え歌
私たちの音楽的母語とその機能
社会化への足がかり
質と音楽性
ロシアの子ども文化から――レニングラードでの調査
レニングラード
ソ連での研究
歌の形式――ノルウェーとの比較
決まり歌のイントネーション
なぜ、決まり歌が存在しないのか
歌の用法
機能と音楽性
『ソヴィエツカヤ・ムジカ』は「将来を」見つめる
アメリカの子ども文化から――ロサンジェルスでの調査
ロサンジェルス
ニール・ポストマンと「アメリカの失われた子ども時代」
子どもたちの自発的な歌
――世界に広がっている私たちの音楽的母語
歌の形式
歌の用法
自発的な歌の機能
「非音楽の普遍性」
:自発的な子どもの歌は普遍的な音楽的母語なのか
第五章 教室でのミューズ的人間
この世はうるわし
私たちの迷宮
子ども時代との決裂
学習エコロジーから学習の断絶へ
文字文化と声の文化
抑圧された者たちの教育
子ども時代を敬え!
文字が読めない者への賛辞
今日のアメリカにおける「二次的に文字が読めないということ」
ノルウェーはどうか
アメリカ、北欧、発展途上国における就学年齢の引き下げ
全日制学校と楽園中の楽園について
ソ連はどうか
学習エコロジーから授業エコロジーへ
ミューズ的教師
学年制度の再組織化
共同学習の効果――ノルウェーでの試みから
学校音楽隊
学校に音楽が増えると学習環境はより良くなるか
全身で学習すること
断絶を解消するための具体例
最初に喜び、最後も喜び
歌と母語の方言
驚嘆を学校の資源として
ミューズ的、創造的、美的、芸術的:概念の明確化
音楽か? 音楽だ!
失楽園:失われた子ども時代を求めて
――ある「指導者コース」の実例
学校、創造性、政治
第六章 子ども文化と音楽教育
カール・ニルセンの子ども時代
子ども文化のミューズ的学習の歌――音楽教育的指針
赤いゴムボールからトランペットへ
――楽器を初めて手にしてから一年の間に起こったこと
私たちは1987年9月に開始した
なぜ「レット・イット・ビー」なのか
まずは歌うことから
サッチモの翼に乗って
「バンドを作ろう!」
音楽教育史の概略
音と音符――音楽の世界における文字文化と声の文化について
音楽史の民衆文化と芸術文化における楽譜なしの演奏
子どもとと鳥、学習と音感
表現の限界としての音符表記
移調の技法
音楽と譜面、親近性と距離
消えた音楽――音楽教育の「壁にネズミ(mus-i-muur)」について
ルリーおばさんと「春のささやき」
楽器と身体
いつ、何から
子どもにあまり早くから始めさせないこと
歌、山賊の娘ローニャ
ルチアーノ・ベリオ
ドラム+歌+踊り
ベアンハート・クリステンセンと子どものドラム奏者
最初の楽器はピアノ?
管楽器
日本の音楽教育法についての小コメント
多面性
楽譜演奏はいつ導入すべきか
十戒――音楽を学ぶ生徒の日常
弾き間違いからユーモアへ
恐れずに音楽演奏?
早期の音楽経験とレパートリの幅
音楽のモダニズムと子ども
過去を向いた音楽レパートリ
コダーイと五音音階
モーツァルトの影から教則本『古典対位法』
(グラドゥス・アド・パルナッスム)へ
「音にあまり注意を払うな!」
頭よりも心で先に、真実を見つけなさい
第七章 もしあなたが誰かを愛しているなら
――彼らを自由にしてやりなさい!
引っ込め、審判!
産声と思春期
アメリカ、ノルウェー、ソ連――ロックの仕方は様々
移ろいやすさという力
「ザ・スナフーズ」
永遠の10代
ロックだけではなく
嵐は眠る
第八章 子どもとと芸術家
芸術家の内なる「子どもらしさ」
ディミトリ・ショスタコーヴィチ
――芸術的な展開をするミューズ的人間
ゴーゴリとともに若者の反乱
ロシア文学とカーニバル主義
笑いから不安へ
ユロツヴォ(Jurodstvo)
仮面の陰で
幕がおりる
交響曲第五番――恐怖の爪につかまれて
音楽家は歴史を記録する
第一楽章の最後に何が起こるのか
第二楽章は慣用を新たに破壊する
三楽章と四楽章は共通の特徴を持っている
交響曲第13番前史――雪解けと凍結
仮面を脱ぐとき
ユーモアよ、永遠なれ!
ロシアの内なる恐怖は死ぬ
社会全体が目覚めるとき――鼻なしで
ミューズ的句読点
第九章 三つの肖像
祖母の陣地
オスカーおじさんと金婚式のワルツ
足は踏み、心臓は打つ
第十章 合唱によるコラージュ
子どもらしい前奏曲
彼らは歌いながら死に出会った
「トレバーク」――ロシアの農民の踊り
When the Saints go marchin' in(聖者の行進)――黒人霊歌
Slipsteinsvailsen(砥石のワルツ)
En spelmans jordafard(ある楽士の埋葬)
子どもらしい後奏曲
参考文献
訳者あとがき 福井信子
*第五章まで:上巻
第六章から:下巻
|
|
|
|
|
|
|
|
目次読書会 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
目次読書会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90055人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208312人
- 3位
- 酒好き
- 170695人