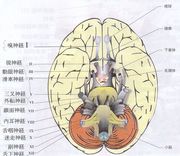|
|
|
|
コメント(11)
>ASCさん
お久しぶりです。
公益性の概念は、私個人が考えて云々してもはじまりません。
きちんとした定義があり、それに基づいて公益法人制度3法が制定されています。
NPO法の第二項に以下の条文があります。
第2条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
ここで定義されているとおり、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものでなければ公益とはいえないことになります。
また、第3条 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。
とあり、これに準拠して公益法人制度が制定されているのですから、その公益というのがあくまで不特定多数でなければならないわけです。
不特定多数は何人? という疑問もでてくるものと思われますが、それは別問題として、たとえば、自治会、同窓会などは特定多数となり、これは私益とみなされるため、公益性はないと判断されるわけです。
公共の保険、福祉を担う意味として医療のなかで広く社会に貢献するという趣旨での活動であれば、公益となりますが、医師会がそうであるように、内部留保が多くなると、今度の改正では公益法人とはみなされません。(年度内に消化し切れなかった事業で、次年度確実に行う事業のための原資であればこの内部留保は公益法人制度でもみとめられます。)
また、地域の現社団の医師会はこれにより、一般社団法人となる公算がたかくなっているといいます。
次に医療費と療養費ですが、支払い形態がことなっています。
医療は出来高払いの現物給付、そして療養費は、支払われたものに対してその現金分が給付される現金給付であるわけです。
つまり、医療行為そのものに対して支払われる現物給付に対して、物の対価として支払われるものが療養費の現金給付となるわけです。
公に必要な物・・・を売ったのだから、その代金を支払いますよ!
ということが公益ということになれば、たとえば自衛隊に戦闘機を売る業者の販売行為も公益であるということになってしまいます。
また、装具を作ったり、コルセットを作る会社も公益事業をおこなっている・・・ということになってしまいますが、それはおかしな話ではないでしょうか?
まして、受領委任についていえば、その手数料は、患者のためではなく、施術者、そしてその団体の職員の給与のために徴収されるものであって、そこに公益性があるのなら、受領委任を使わずに、償還払いを使ってもその手数料も公益であるといえてきてしまいます。
また個人で請求したり、償還払いを選択できる制度である以上、それらを使う人は受領委任を使わないことになり、不特定ではなく、受領委任を利用する特定された人の受益のため・・・といわざるを得ない状況になるものと思われます。
また、立替払い等のファクタリングは論外であり、健康保険法第61条に反するこれら行為に公益性は認められません。
つまり、これらは決済代行業務であり、クレジット会社などがおこなっているものと変わりありません。 その業務に公益性があるというのなら、クレジット会社などは国民の不特定多数の利便性を供与するとして、その手数料の含め、公益性があると解すことができてしまい、すべてのクレジット会社が公益法人になれてしまいます。
という観点から、営利目的の事業は公益とはいえず、制度改革により、その目的として取り上げられているものは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律別表に下記のように記載されています。
お久しぶりです。
公益性の概念は、私個人が考えて云々してもはじまりません。
きちんとした定義があり、それに基づいて公益法人制度3法が制定されています。
NPO法の第二項に以下の条文があります。
第2条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
ここで定義されているとおり、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものでなければ公益とはいえないことになります。
また、第3条 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。
とあり、これに準拠して公益法人制度が制定されているのですから、その公益というのがあくまで不特定多数でなければならないわけです。
不特定多数は何人? という疑問もでてくるものと思われますが、それは別問題として、たとえば、自治会、同窓会などは特定多数となり、これは私益とみなされるため、公益性はないと判断されるわけです。
公共の保険、福祉を担う意味として医療のなかで広く社会に貢献するという趣旨での活動であれば、公益となりますが、医師会がそうであるように、内部留保が多くなると、今度の改正では公益法人とはみなされません。(年度内に消化し切れなかった事業で、次年度確実に行う事業のための原資であればこの内部留保は公益法人制度でもみとめられます。)
また、地域の現社団の医師会はこれにより、一般社団法人となる公算がたかくなっているといいます。
次に医療費と療養費ですが、支払い形態がことなっています。
医療は出来高払いの現物給付、そして療養費は、支払われたものに対してその現金分が給付される現金給付であるわけです。
つまり、医療行為そのものに対して支払われる現物給付に対して、物の対価として支払われるものが療養費の現金給付となるわけです。
公に必要な物・・・を売ったのだから、その代金を支払いますよ!
ということが公益ということになれば、たとえば自衛隊に戦闘機を売る業者の販売行為も公益であるということになってしまいます。
また、装具を作ったり、コルセットを作る会社も公益事業をおこなっている・・・ということになってしまいますが、それはおかしな話ではないでしょうか?
まして、受領委任についていえば、その手数料は、患者のためではなく、施術者、そしてその団体の職員の給与のために徴収されるものであって、そこに公益性があるのなら、受領委任を使わずに、償還払いを使ってもその手数料も公益であるといえてきてしまいます。
また個人で請求したり、償還払いを選択できる制度である以上、それらを使う人は受領委任を使わないことになり、不特定ではなく、受領委任を利用する特定された人の受益のため・・・といわざるを得ない状況になるものと思われます。
また、立替払い等のファクタリングは論外であり、健康保険法第61条に反するこれら行為に公益性は認められません。
つまり、これらは決済代行業務であり、クレジット会社などがおこなっているものと変わりありません。 その業務に公益性があるというのなら、クレジット会社などは国民の不特定多数の利便性を供与するとして、その手数料の含め、公益性があると解すことができてしまい、すべてのクレジット会社が公益法人になれてしまいます。
という観点から、営利目的の事業は公益とはいえず、制度改革により、その目的として取り上げられているものは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律別表に下記のように記載されています。
別表(第二条関係)
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 公衆衛生の向上を目的とする事業
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵(かん)養することを目的とする事業
十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
となっています。
以上、公益の概念に規定されているものより私の考察を加えてみました。
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 公衆衛生の向上を目的とする事業
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵(かん)養することを目的とする事業
十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
となっています。
以上、公益の概念に規定されているものより私の考察を加えてみました。
公益とは文字通り、社会公共の利益ということですが、従来ですと、社団法人として認可された段階で、その法人の事業は公益とされてきましたが、今度の法改正で、単に社団法人となっただけでは公益認定しないということです。
しかし、株式会社とは異なり、社団法人では一律30%しか課税されません。
そして、公益認定事業については政府委員会での判断によります。
しかし、何をもって公益とするかの具体例は示されていません。
納豆先生の御指摘の通り、保険取扱事務料は営利事業と判断するのが普通です。
町内会費・商店会費・同窓会費なえどは消費しませんから、消費税の対象とはなりませんが、保険事務料は自家で行なうべき事務の委託ですから、場合によっては源泉税の
役務費に当ります。この場合は10%を源泉控除する義務が生じます(会員に)
つまり、事務料が1万円なら10%の1000円については差し引いて、その金員を源泉税賭して税務署に納付する必要があります。
事務手数料を一般消費で捉えるなら、消費税5%を会員から徴収すべきです。
さあ、答えはどれが正しいでしょうか?
次に社団の方々をはじめ皆さんが誤解さrてていますが、経過措置期間を過ぎますと自動的に一般社団となります。
そして、実は厚生労働省の管轄から外れ、総務省の管轄になります。
今度の法改正で1業種1法人という縛りはきえましたから、一般社団法人が雨後の竹の子状態で認可を得ると思います。
一般社団法人は定款を公証人役場で認証を得ます。この費用は確か4万円位です。
そして、」これをもって法務局で登記をします。これが6万円です。
僅か、11万円で法人格となりますから、各接骨院も一斉に社団法人にするでしょう
更に、それらはいっせいに公益事業の認定申請を総務省に出すでしょう。
公証人役場は大繁盛、法務局も総務省も公益事業認定委員会も大忙しです。
歴史でも分かりますように、こうやって公務員が増殖し国家の「獅子身中の虫」となって国家を滅ぼすのです。
納豆先生、ご指摘の通り柔政界もそうですが日本国も再度崩壊してから再生させる処方箋しか残ってませんかな(^_-)-☆
ガイは明日は歌手です。
中島みゆきチャンの「世情」でも唄ってみますか?
会費は2,500円です。納豆先生に限りワンドリンクサービスです。
場所は麻布台のショ―BARブルーシャトー03−3583−9536です。
是非、覗いてみて下さい。
しかし、株式会社とは異なり、社団法人では一律30%しか課税されません。
そして、公益認定事業については政府委員会での判断によります。
しかし、何をもって公益とするかの具体例は示されていません。
納豆先生の御指摘の通り、保険取扱事務料は営利事業と判断するのが普通です。
町内会費・商店会費・同窓会費なえどは消費しませんから、消費税の対象とはなりませんが、保険事務料は自家で行なうべき事務の委託ですから、場合によっては源泉税の
役務費に当ります。この場合は10%を源泉控除する義務が生じます(会員に)
つまり、事務料が1万円なら10%の1000円については差し引いて、その金員を源泉税賭して税務署に納付する必要があります。
事務手数料を一般消費で捉えるなら、消費税5%を会員から徴収すべきです。
さあ、答えはどれが正しいでしょうか?
次に社団の方々をはじめ皆さんが誤解さrてていますが、経過措置期間を過ぎますと自動的に一般社団となります。
そして、実は厚生労働省の管轄から外れ、総務省の管轄になります。
今度の法改正で1業種1法人という縛りはきえましたから、一般社団法人が雨後の竹の子状態で認可を得ると思います。
一般社団法人は定款を公証人役場で認証を得ます。この費用は確か4万円位です。
そして、」これをもって法務局で登記をします。これが6万円です。
僅か、11万円で法人格となりますから、各接骨院も一斉に社団法人にするでしょう
更に、それらはいっせいに公益事業の認定申請を総務省に出すでしょう。
公証人役場は大繁盛、法務局も総務省も公益事業認定委員会も大忙しです。
歴史でも分かりますように、こうやって公務員が増殖し国家の「獅子身中の虫」となって国家を滅ぼすのです。
納豆先生、ご指摘の通り柔政界もそうですが日本国も再度崩壊してから再生させる処方箋しか残ってませんかな(^_-)-☆
ガイは明日は歌手です。
中島みゆきチャンの「世情」でも唄ってみますか?
会費は2,500円です。納豆先生に限りワンドリンクサービスです。
場所は麻布台のショ―BARブルーシャトー03−3583−9536です。
是非、覗いてみて下さい。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
柔道整復師・接骨院 更新情報
-
最新のアンケート
柔道整復師・接骨院のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90056人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208314人
- 3位
- 酒好き
- 170696人