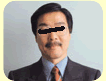もう各自質問の担当を決めているので載せる必要もにと思いますが、とりあえず論文を載せておきます!
部門番号 17
部門名 マーケティング
百貨店について(百貨店の現状と将来について)
―百貨店におけるメガフランチャイジー戦略について―
日本大学商学部 佐々木ゼミナール
代表者:谷崎 亮
参加者:太田 純子、大谷 真由、谷崎 亮、信國 健司
平林 宗十郎、細田 あゆみ、渡辺 邦彦
目 次
第1章 百貨店の現状と問題点
第1節 百貨店の定義
第2節 百貨店の現状
第3節 百貨店の特徴・仕組み
第2章 メガフランチャイジー戦略
第1節 フランチャイズ定義・特徴
第2節 メガフランチャイジー定義・特徴
第3節 成功事例
第3章 百貨店の形態
第1節 ライセンス契約
第2節 テナント契約
第3節 フランチャイズ契約との比較
第4章 導入によるメリット・デメリット
第1節 事例
第2節 メリット・デメリット
第3節 百貨店における成功可能なメガフランチャイジーのビジネスモデル
第5章 総括及び展望
第1章 百貨店の現状
第1節 百貨店の定義
総務省によって定められた日本標準産業分類(平成14年3月)において、百貨店は大きく分類すると卸売・小売業に分類され、その中でも各種商品小売業に分類されており、衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所で、その性格上いずれかが主たる販売商品であるかが判別できないものであって、百貨店、デパートメントストアなどにその例が多いとある。百貨店とは「衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50 人以上のもの」をいう。また、経済産業省によって定められた商業販売統計(平成14年9月)では、「百貨店とは、セルフ店(売り場面積の50 %以上について、セルフサービス方式を採用している商店)に該当しない事業所であって、かつ、売場面積が特別区及び政令指定都市で3,000?以上、その他の地域では1,500?以上の事業所」と定義している。さらに日本百貨店協会では、「物理的に独立した店舗面積が1,500?以上のもので、日本百貨店協会に加盟している百貨店」と定義している。
百貨店とは、衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所であり、その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できないもの、つまり商品の品揃えは総合的で、セルフ店に該当せず、対面販売を基本とした徹底した人的サービスを提供している大規模小売店だといえる。
第2節 百貨店の現状
1990年代初頭の百貨店の売上は、80年代後半からのバブル景気の影響を受けて、高い伸びでスタートしたが、バブルが崩壊すると92年以降は大きく落ち込み、その後、数年かかって盛り返したが、97年以降再び売上は伸び悩み、97年から2005年まで9年連続で売上が前年割れとなっている。
しかし、2005年は減収傾向に歯止めがかかった。特に4月以降はプラス基調に転じ、年後半の景気回復などをうけ、業績は堅調に推移している。2006年に入ってからも売上は好調だったが、4月以降再び大幅ではないがマイナスになり、8月まで5ヶ月連続でマイナスに転じている。業界全体では減収傾向に歯止めがかかりつつあるとはいえ、大都市と地方百貨店では状況が異なる。
東京地区の百貨店については、バブル後、売上の落ち込みが最も大きかったが、その後、売上伸び率の前年割れが小幅化し、1999年以降は全国平均を上回り、都心回帰で百貨店も復調したかと思われたが、2002年には全国平均を下回り、その後も全国平均を下回っている。
地方の百貨店についても、バブル後売上が落ち込んだが、その後、徐々に回復していった。しかし、地方百貨店の環境は、地域経済の低迷、消費不況、さらに、大型ショッピングセンターの進出が影響を与え、2001年には地方単独経営の百貨店企業の倒産、閉鎖が相次いだ。また、同じ百貨店であっても地方店や郊外店の場合は売れ筋商品を十分に供給してもらえず、このため地方の消費者が大都市へ買い物に出かけてしまう「ストロー現象」で消費流出を招いてしまっている。このように地方百貨店では引き続き厳しい事業環境が続いていたために生き残り策として、郊外ショッピングセンターのテナントとしての出店や、自らのショッピングセンター型新業態の開発も活発になっている。
商品部門別の売上に関しては、婦人雑貨などが含まれる見回品と食料品の伸びがよく、婦人服、食料品の売り場が拡大されていった。これにより、本来の百貨のバランスのとれた業態から、婦人服、見回品、食料品、食堂・喫茶の4部門に特化された業態へと変化し、特に婦人服売り場と、地下食料品売り場に力を入れるようになった。婦人服売り場に関しては、消費者の年代やニーズに合わせた、複数のフロアが存在している。また、地下食品売り場に関しては、話題の店舗を数多く投入し、売上も婦人服に次いで高く伸びている。
出所:麻倉佑輔 大原茜 『最新・全国百貨店の店舗戦略』 同友館 2003年5月25日 p.7
日本百貨店協会 http://
第3節 百貨店の特徴
百貨店の特徴を挙げてみると、百貨店は駅付近などの一等地に立地し様々な店が一ヶ所に集まっているため、電車などでのアクセスが容易で交通至便であり、同じ場所で消費できるワンストップショッピング性である。売場や商品の案内、各階の案内、買物の相談から高齢の方や障害者の消費者の手伝いなどの、行き届いたホスピタリティサービスである。百貨店と読んで字のごとく百貨を扱っているため、消費者が豊富な品揃えの中から商品を選択できる品揃えの良さ、ギフトに相応しい包装紙に代表される店ブランドの魅力。老舗ならではの信用、信頼感。美容マッサージ、旅行センター、フィッティングルーム、屋上遊園などの、贅沢でゆとりのある施設環境。美術館、ギャラリー、劇場、カルチャーセンターなどの文化性、などの特徴が挙げられる。
また百貨店には委託仕入、消化仕入という特徴がある。委託仕入とは業者が商品の販売を百貨店に委託し、百貨店は一定期間商品を預かって販売し、売れ残った商品は返品する。消化仕入とは百貨店が商品を業者から預かり、その商品が売れた時点で仕入れ販売する。このようにこれらは仕入リスクを負わないので棚卸資産回転率が良い。一方、リスクを負う業者はリスク分を価格に上乗せするため小売価格が高くなる。加えて返品制度、派遣店員制度が挙げられる。返品制度は、前に述べたように、百貨店が仕入れた商品に売れ残りが生じた場合、売れ残りをメーカー、問屋が引き取るものである。派遣店員制度は、メーカー、問屋が店員を百貨店に送り込み自社の製品を販売する、委託販売制度である。百貨店には以上のような特徴が挙げられる。
次にショッピングセンター(SC) の特徴を挙げ、百貨店の特徴と比較していく。まず、ショッピングセンターの特徴をあげる前に、ショッピングセンターの定義を明確にする。
ショッピングセンターとは、1つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設であり、駐車場を備えるものをいう。その立地、規模、構成に応じて、選択の多様性、利便性、快適性、娯楽性等を提供するなど、生活者ニーズに応えるコミュニティ施設としての都市機能のことであると定義している。
ショッピングセンターは百貨店と同様で、様々なショップがあり、豊富な品揃えとサービスを提供する。しかしショッピングセンターの大きな特徴は、ディベロッパーにより計画的に開発されるという点である。機能上から、駐車場設備であることは、すでに新しい商業立地であり、ここにキーテナントと、専門店が入り、その配置や、商品ゾーンが計画され、また種々の楽しむ機能や、遊ぶ機能、社会生活上必要な機能があり、ワンストップショッピングが可能となる。また形態的には、都心から離れた郊外にあり、低階層で、駐車場が十分あるため集客力に優れており、テナントミックスされた商業集積地である。
第2章 メガフランチャイジー
第1節 フランチャイズの定義・特徴
フランチャイズの特徴は、フランチャイザーが開発したフランチャイズシステムやノウハウと、それを象徴する商標もしくはサービスマーク、チェーン名など、事業を運営する上での方法を提供することである。つまり、フランチャイジーは、自分の資金を投入して、本部の開発した商売の方法やノウハウを使用して営業を行い、前者、後者がお互いに利益を得ようとする仕組みである。
[表-2] フランチャイズチェーンの仕組み
出所:社団法人日本フランチャイズチェーン協会
http://
フランチャイズチェーンにおけるフランチャイザーのメリットは第1に、急速な店舗拡大が可能であることがある。第2に、店舗増加によって即座に利益が得られること。 第3に、契約時の取り決めにより何%かのロイヤリティを受け取ること。デメリットは第1に、加盟店の募集に資金と人材が必要となることがある。第2に、フランチャイズチェーンは統一したサービス提供が基本となるが加盟店によりレベルのばらつきがブランドイメージの低下につながる恐れがある。第3に、レギュラーチェーンのようにトップダウンによる意志決定が難しく、戦略転換に手間と時間がかかること。一方フランチャイジーのメリットは第1に、事業成功率が高く、開業資金があればフランチャイズ契約により即座に開業が可能となり、開業資金は個人で開業するより少ない資金で開業が可能となる点がある。第2に、開業する前に本部から店舗運営、経営ノウハウなどの指導を受け、それに従えば利益が得られること、第3に本部が一括して広告を行うため販売促進において大きな影響力を得られること。デメリットとしては第1に、本部の指導のもとで経営を行うため活動の自主性の不自由が生じること、第2に、経営について本部は全体の利益を考えるため、個々の加盟店には不利益が生じる場合があること、第3に、契約期間中の中途解約には条件があり、契約期間が終了してから一定期間は同業種の営業が禁止されていることである。
第2節 メガフランチャイジーの定義・特徴
近年、メガフランチャイジーと呼ばれる企業群の存在が注目されている。メガフランチャイジーとは比較的新しい言葉であり業界団体や行政による明確な定義があるわけではないが、一般的にメガフランチャイジーとは、「フランチャイジーが多数(通常30店舗以上)の店舗を経営し、且つフランチャイジーとしての売上高20億円以上の規模」のフランチャイジーをいう。メガフランチャイジーの特徴は、さまざまなタイプの企業が含まれている。
[表-3]メガフランチャイジーのタイプ別分類
フランチャイズ加盟店事業の
売上高比率による分類
1)フランチャイズ加盟事業専念型……フランチャイズ加盟による売上高比率 )80%以上
?業態転換パターン(経営資源を本部からフランチャイズ加盟ビジネスに投入)
?最初からフランチャイズ加盟店としてスタートしたパターン
2)戦略新規事業型 )……フランチャイズ加盟による売上高比率30〜80%程度
3)副業型……フランチャイズ加盟による売上高比率30%以下
加盟フランチャイズブランドの総数、
及び種類による分類
1)単一ブランド特化型……ひとつのフランチャイズブランドに特化して事業展開
2)マルチフランチャイジー型……複数のフランチャイズブランドに加盟して事業展開
?同業種選択パターン
?異業種選択パターン
フランチャイズ加盟店専業か、
または本部兼業かという視点による分類
1)フランチャイズ加盟店専業……フランチャイズ加盟店事業のみに専念する
2)フランチャイジー/ザーハイブリット型……加盟店事業を展開しつつ、自ら本部としての機能も有する
?エリアフランチャイザー兼営型
?独自業態開発型
出所:小林 忠嗣『メガフランチャイジー戦略』ダイヤモンド社 2002 第4章 p167
次にメガフランチャイジー戦略のメリット・デメリットを考える。メリットとしては、第1に戦略的ポートフォリオが組めること、第2にフランチャイズ加盟店事業を通じて得た経営ノウハウを本業の経営にも生かすことが可能であること、第3に経営資源の有効活用が可能であること、第4に地元及びその周辺エリアで複数フランチャイズブランドの店舗をドミナント展開していくことで効率的な販売促進が行えることである。実際、日本最大級のメガフランチャイジー企業とされるタニザワフーズ株式会社は、東海地区でドミナント戦略を用いることで圧倒的な地域シェアを獲得して成功を収めた。
デメリットは、第1にメガフランチャイジー戦略をとることによって判断が難しくなるということがある。つまり、合わないと思った事業は早めに切り捨てる判断が必要となるということである。第2に自分の持つエリア内で展開できる事業の数には限りがあるというエリアフランチャイザーの限界もある。メガフランチャイジーを目指して成長する過程で自社ブランドの育成を考えたとき、二つの育成を両立させ成功している事例は極めて少ない。メガフランチャイジーとしての成功と、自社ブランドを育成して、さらにはフランチャイズ化することの両立は難しいとされる。
フランチャイジーとメガフランチャイジーの相違は、第1に、マルチフランチャイジー(複数ブランドのフランチャイズチェーンに加盟しているフランチャイジー)は、売り上げ規模にかかわらず、あくまでも複数のフランチャイズ本部に加盟しているのに対し、メガフランチャイジーは、先ほど述べた一般的な定義によりフランチャイジーとメガフランチャイジーの相違点には、売り上げがある。第2に、事業規模をみると、フランチャイジーは個人または零細企業で弱者という負のイメージがあるように思えるが、メガフランチャイジーの事業規模は、本部企業よりも小さいとは限らず、数百名もの社員を要する企業が、たかだか数十名しかいないフランチャイズ本部の加盟店になる例は珍しくない。このことからも、選択した本部への影響において相違がある。第3に、加盟者の資質・経営資源をみると、戦略的事業ポートフォリオの構築が可能である。フランチャイジーは事業が立ちゆかなくなると、再び立ち戻すのが大変で、潰れてしまったりするのに対して、メガフランチャイジーのように、複数のフランチャイジーに加盟(マルチフランチャイジー化)すれば、仮にそのうちの一つの事業が立ちゆかなくなっても、企業業績全体はさほど影響をうけなくてもすむ。また、スクラップ・アンド・ビルドを積極的に進めることができるため、安定した成長を維持することができる。フランチャイズ加盟店事業を通じて得た経営ノウハウは、本業の経営にも生かすことができ、既存業務とのシナジー効果が生まれることも相違点である。メガフランチャイジー化することによって経営資源を有効活用することができ、メガフランチャイジーであれば、押さえた土地の特性に適応しやすい業種・業態を自らのフランチャイズブランドのなかから選び当てはめることができるため、これにより、エリアフランチャイザー(フランチャイズ加盟店として成功を収めた企業が、そのフランチャイズチェーンの本部から一定地域でのフランチャイズ展開権を購入し、そのエリアにおけるフランチャイズチェーン本部として事業を展開するということ)契約を結ぶこともできる。第4に、メガフランチャイジーが参入することにより、フランチャイザーがフランチャイジーより力を持っていた時代から、メガフランチャイジーがフランチャイジーよりも力を持つような時代になってくる。
第3節 成功事例について
メガフランチャイジー企業として成功を収めた株式会社ゴトーがフランチャイズビジネスと出会ったきっかけは、過度な出店拡張が仇となり、バブルの崩壊とともに、93年から94年にかけて不採算店が増加したので、転貸先の一つであったブックオフコーポレーションとフランチャイズ契約を結び加盟店を展開したことである。これにより、店舗における赤字は解消されたものの営業利益を出すまでに至らなかった。このような状況下のなかでゴトーは補完的効果のある他の業務を導入して一店舗を多業務化した。具体的に言うと、ブックオフの店舗面積とバックヤード面積を少しずつ削って、テレビゲームの販売を開始した。この選択は結果的に新しいビジネスモデルを生み出し、1店舗当たり1000万円以上の利益をだすようになった。同社は95年にはカルチャーコンビニエンスクラブとフランチャイズ契約を結んだが、このときは最初の店舗からテレビゲーム販売とマルチタスク化した。97年には、1店舗で、TUTAYAとブックオフとテレビゲーム販売とを複合させ、現在につながるゴトー流のマルチタスク化店舗の展開を開始した。
ゴトーのメガフランチャイジー企業としての特徴は、複数のフランチャイズブランドに加盟しているマルチフランチャイジー型であり、異業種に属するフランチャイズブランドを複数選択して加盟する異業種選択パターンに分類される。また、同じくメガフランチャイジー企業であるタニザワフーズ株式会社は、マルチフランチャイジー化によるドミナント戦略を成功させ常に飲食店に特化してきた。またコンビニエンスストアを中心として展開している株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリアは、マルチフランチャイジー化しておらず、特定のフランチャイズブランドに特化して経営資源を集中することで事業の拡大を狙う単一ブランド特化型であり、出店戦略からしてゴトーとは大きく異なっている。
ゴトーの成功は、マルチタスク化したことのほかに、フランチャイズ展開の初期にブックオフとTSUTAYAを選んだところにあるともいえる。大型ロードサイド店を転業する際に、比較的、手掛けやすい業態にうまく凝縮できたのである。現在の両FC本部の発展を見れば、ゴトーの見る目は確かなものだったといえる。
店舗のマルチタスク化という新しいビジネスモデルの開発がフランチャイズの加盟店であるゴトーにより担われたのは明らかである。加盟店にとって一つの業務に徹底的に努力するより、複数業務に努力を振り分けるほうが収益改善上プラスになる。このような新しいアイデアがゴトーによって生み出され、フランチャイズシステムの進化に貢献したといえるであろう。
第3章 百貨店の経営形態
第1節 ライセンス契約
百貨店は、デザイナーやメーカーと提携し、提携先のデザイン、機能、ノウハウなどのライセンスをロイヤリティで支払うことによって商品を導入する。ライセンス契約の内容
の範囲も様々である。ライセンス商品のブランド名やマークなど商標の独占的使用にとどまるものから、ライセンス商品を日本で製造することを許すもの、さらに、その製造や販売における記述、情報、ノウハウなど広範囲にわたるものまである。基本的にライセンス契約を行えば百貨店が、そのブランドの独占販売権を獲得する。それとともに、衣服をはじめ、バッグ、財布などの小物、靴、帽子、服飾雑貨、化粧品などの多数のアイテムについても、そのブランド名を冠した商品展開権を得ることができる。
ライセンス契約を結ぶことにより百貨店は、ライセンスPB商品を生産することができる。伊勢丹では大手ブランドと組み、開発した商品を「伊勢丹」の名前を出さずブランド名で売り場に並べている。「伊勢丹メンズ館」では、売り場の商品の約70%が、有名ブランド品に見えて実はPB商品になっている。
ライセンスPB商品を生産することはメリットが3つ挙げられる。第1に、百貨店の来店客層や売れ筋商品などの調査をし、商品企画をするため、高い売り上げの望める商品を導入することができる。第2に、他店にはないその百貨店独自の商品を販売することにより、百貨店それぞれの個性を出すことができ、競争上の差別化政策につながる。ライセンスPB商品がない場合、他の百貨店と同じ仕入先から商品を仕入れることになる。そのため、同じような商品の品揃えがされ、同じような商品が販売されることになる。第3に、仕入れ商品よりも高いマージンがとれることになり、営業収益を高めることができる。
しかし、PB商品を生産することは問題点も生じてくる。PB商品の場合は、売れ残った商品をメーカーに返品するわけにはいかないので、的確な販売予測力と確実に売り切る販売力が必要になる。また、ブランドの価値を維持できなければならない。そのためには第1に、デザイナーの世界観を表現できるかどうかが問われる。第2に、NB商品も売り場に並べるケースが多いため、PB商品がNB商品とほぼ同じレベルでコンセプトを表現していないと、売り場で統一されていない印象を与えてしまう。
また近年、海外ブランド物においては、海外旅行が大衆化しているため、実際に本店で「本物」に触れる消費者が多くなってきている。そのため、PB商品が「似て非なるもの」と感じる人も出てきた。さらに、ライセンス契約をしていたデザイナーのブランドが、「○○ジャパン」として日本市場に乗り込んでくるケースも増加してきた。そのため、百貨店にはよりいっそうの努力が必要になってくる。
第2節 テナント
百貨店の経営形態の2つ目はテナント制である。テナントとは、ビルや百貨店・ショッピングセンターなどの一部区画を、その建物を管理・運営する企業から借り受けて運営する事務所や店舗のことをいう。百貨店がテナントを募集する方法には、ディベロッパーの選定、一般公募、推薦、の3つの方法がある。そこから、出店申込され個別折衝が行われる。そして、審議に入り決定される。
出店が決定された後百貨店とメーカーの間で出店契約が結ばれる。出店契約には、4つの方法がある。第1に、ほとんどのテナント出店の契約形態になっている「通常のテナント契約」である。これは、特定の独立した区画を出店者の占有の営業場所として使用し、その対価として確定金額を支払うものである。第2に、売り場内の陳列ケースの一部を貸与する契約である。これは、特定の場所に対する占有性や独立性の薄い契約である。第3に、売れた分だけ仕入れをし、特定の場所に対する占有性や独立性が非常に薄い「売上仕入方式の業務委託契約」である。これは日本の百貨店独特の方法である。第4に、ディベロッパーが建築した建物を出店者に分譲するもので、所有権の移転が伴う「分譲式」である。当然のことながらメーカー側は出店する際に、売上予想や収益予測をすることが必要である。既存の百貨店に出店する場合は、全体の売上、来店顧客数、年齢構成などの基本データを検証し、自社店舗がターゲットにする顧客と合っているかどうかを調べる必要がある。また、商圏の分析をすることも重要である。
百貨店にとってテナントとは、百貨店の勝敗を決定することになる。ブランドにもよるが、一店で集客が一日およそ千人変わるほどの影響力がある。
第3節 フランチャイズ契約との比較
ここでは、フランチャイズ契約、ライセンス契約、そしてテナント契約のメリット・デメリットについて述べ、それぞれ比較していく。
はじめに、フランチャイズにおけるメリットであるが、第1に、急速な店舗拡大が可能であること。第2に、店舗増加によって即座に利益が得られこと。デメリットとしては第1に、加盟店の募集に資金と人材が必要となることがある。第2には、フランチャイズチェーンでは統一したサービス提供が基本となるが加盟店によりレベルのばらつきが生じ、ブランドイメージの低下につながる恐れがあることである。
次に、ライセンス契約におけるメリットであるが、第1に、百貨店の売れ筋調査に応じて高い売り上げの見込める商品あるいはメーカーと契約することができる。第2に、単に自社で開発している商品であるため、仕入れ商品よりも高いマージンを見込めることができる。デメリットは、第1に、ライセンスPBは確実に売り切る販売力がなければ売れ残ってしまうことである。第2に、ブランドイメージを損なわないように、デザイナーの世界観を確実に表現しなければいけないことである。第3に、売り場での、PB商品とNB商品のコンセプトが難しいことである。
テナント契約のメリットは、出店者から店舗を貸す対価としてほぼ安定した確定金額を受け取ることができる。つまり、出店した場合の売り上げ予測がたてやすいことである。 デメリットとしては、百貨店自体が衰退している場合、より良い出店者を招き入れることに困難を要することである。
以上のように、それぞれのメリット・デメリットを述べた上で本題である比較、検討に入っていく。まず、それぞれの初期の店舗作りに関して、フランチャイズ契約は初期の店舗費用は比較的に低資金で本部指導によってあらゆる事業は効率的に行われる。ライセンス、テナント契約は、一から店舗を作り上げて、営業していかなければならないので、非常に多くの経費が掛かり、時間もかかる。そして宣伝効果という観点から比較していくと、フランチャイズ、ライセンス契約については自らのブランドの知名度を日本中、あるいは世界中に広げることができる。しかし、テナント契約については、一つ一つ単体であるため、宣伝効果という観点から述べるとこの上記二つには劣ることがあるのだ。
最後に、初期の店舗作り、宣伝効果において比較した結果、より多くの良い要素を備えているのはフランチャイズ契約であるということがわかる。
第4章 導入によるメリット・デメリット
第1節 事例
百貨店にメガフランチャイジーを導入した事例については、明確な事例がないため百貨店がフランチャイザーとフランチャイズ契約をしていると仮定したうえで論じていく。事例としては、株式会社そごうのそごう千葉店を取り上げて検討する。
千葉そごう店でフランチャイズシステム導入に影響を与える点を2点挙げる。
まず、第1に、10階ダイニングパークと称された24店舗のレストランフロアがある。ここにフランチャイズシステムを導入することを提案する。ここにフランチャイズシステムを導入することによって、フランチャイズ本部のオペレーションシステムをそっくり活用し、高効率の事業展開を行う。こうすることが最も有効な形で経営資源を調達・運用することにつながり、何より有限な資源である時間を節約できる。情報は業界動向から他の店舗情報まで細かく入手することが可能である。また、異なった種類の飲食業をさまざまな形で隣接させることによって複合効果を生み、集客力が大幅に向上するのであろう。だが、実際に導入するときのポイントは数多くあるフランチャイズチェーン本部のなかから非常に優れたフランチャイズチェーン本部を選択しなければ、ビジネスとして成功しない。したがって、本部企業の安全性、本部の協力体制、店舗の収益性、加盟へのリスク、その産業の状況などを配慮して事業展開すべきである。
第2に、フランチャイズ加盟店事業を通じて得た経営ノウハウは、本業の経営にも生かすことが可能である。具体的に言うと、フランチャイズチェーン本部が構築してきた各種経営ノウハウである従業員教育、日時決算システムなどを本部SVの指導つきでじっくり学ぶことができる。こういったことが基点となり、百貨店独自の新たな業態を開発することができる。そして、フランチャイズ加盟店として培ってきたノウハウが、今度はフランチャイズ本部として生かされてくる。また、人材育成においても、本部と契約している他の加盟店へと積極的に視察に行かせて、現場の工夫を吸収させる。本部が社内で構築した研修プログラムと百貨店が独自に培ってきた研修プログラムを共有することによって、新たな研修プログラムを創り出すであろう。
第2節 メリット・デメリット
百貨店にメガフランチャイジー導入におけるメリットとして、第1に一店舗を一業務で運営するのではなく、他の業務を導入して補完的効果をもたらすマルチタスク化による店舗形態が利益率向上を図ることができ、出店費用の効率化や管理費用の圧縮することもできる。そして、その複合的な店舗開発が集客力の増加へとつながる。第2に、本部と加盟店といった二つの枠組みのなかで事業を行うため、あらゆる情報または経営ノウハウを相互に共有し、それが新たなビジネス展開を生む可能性がある。第3に、本部主導で商品・原材料・消耗品などの大量一括購入による物流システムの合理化、またその地域に点在したブランド側と共有した物流システムを構築などがコストを削減し、本部主体の経営によりあらゆる加盟店の負担を軽減することが加盟店にとって店舗運営だけに集中して行うことが可能になる。第4に、加盟店側に種々の成功事例、アイデアや工夫が生まれ、それらを本部のフランチャイズ・パッケージに取り込むことにより、相互補完作用が得られる。こういったアイデア創出がうまく顧客に伝わることができれば、新たな戦略を作り競争の源泉となる。
デメリットは、第1に、百貨店が加盟店を呼びかけるためには、莫大なコストを必要とする。それは、加盟金や新たな店舗づくりの設備投資などさまざまな資金を要することになる。第2に、あらゆる業態が参入するため組織として機能するかどうか不透明であるため、明確な理念に基づいた組織づくりを要する。第3に、フランチャイズ化された事業を短期間のうちに収支の均衡を得るためには、相当のハードワークをこなすマネージャーや従業員を配置する必要がある。また、人材をいかに育成し、長くつなぎとめておくのも難しい問題である。第4に、メガフランチャイズシステムは通常の小売ビジネスとは大きく異なっている。したがって、こうしたシステムを構築するにあたって、本部と加盟店の連携が必要不可欠である。
第3節 百貨店における成功可能なメガフランチャイジーのビジネスモデル
第1に、百貨店の資金に余裕がないならば、成功しているメガフランチャイジー企業と業務提携することによって、新たなノウハウや資金を得ることができ、より付加価値の高いサービスを提供することができる。そして、その地域で店舗開発を行うことにより、共同販促、事業効率化、人事交流による新企画の創出、情報システムの共有などのメリットが挙げられてシナジー効果が期待できる。第2に、百貨店に子会社を設立し、その子会社がフランチャイザーとフランチャイズ契約を結び、百貨店の資金でロイヤリティ等を支払う。そして、様々な業種の加盟店となるメガフランチャイジー企業になることで、より多くのフランチャイズ経営のノウハウを取得して、百貨店における成功可能なメガフランチャイジーのビジネスモデルになると考えられる。
第5章 総括及び将来展望
日本の百貨店は長い歴史を持ち、人々に信頼を与え続けてきた。しかし、有名ブランドを売り場に寄せ集めた「場所貸業」や従来の経営(殿様商売)などの主体性のなさが顧客離れを招いた、また、バブル崩壊による顧客の買い控えや、他業界による低価格販売の影響により、92年以降、長期にわたって業績低迷に陥り、経営の縮小を余儀なくされた。その後、売り上げ減少はさらに続いたが、都市圏内において2005年には減少傾向に歯止めをかけた。ところが、地方百貨店は近隣のショッピングセンター、GMSの影響などによって苦戦を強いられている。そうした背景の中で、今後、地方百貨店が生き残るためにはどうするべきかという現状を踏まえ、問題点をさまざまな観点から探っていった。本稿では、この問題について考察していき、新たな戦略を提案することを目的とした。
本章で述べたが、メガフランチャイジー企業は集客力の向上、宣伝効果の向上、新規参入による産業の活性化、選択肢の拡大、便益性の向上、より良いサービス提供などのメリットがある。そこに、今後メガフランチャイジー戦略を百貨店業界において発展させる意義がある。
論文字数 11,932文字(図及び注釈を除く)
<参考文献>
・兼村栄哲 青木均 林一雄 鈴木孝 小宮路雅博 『現代流通論』
八千代出版1999年1月12日
・麻倉佑輔 大原茜 『最新・全国百貨店の店舗戦略』 同友館 2003年5月25日
・内川昭比古 『フランチャイズビジネスの実際』日本経済新聞社 2005年
・日本フランチャイズ協会『よくわかる フランチャイズ入門』 同友館 2005年
・小林忠嗣(監修)リンク総研(編著)『メガフランチャイジー戦略』
ダイヤモンド社2002年
・民谷昌弘 『成功するフランチャイズ戦略-FC導入9つのステップ』
ダイヤモンド社 2000年
・田島義博 『フランチャイズチェーンの知識』 日本経済新聞社 1990年
・川島蓉子 『伊勢丹な人々』 日本経済新聞社 2005年
・小山周三 『現代の百貨店』 日本経済新聞社 1997年
・岡田康司 『百貨店業界』 教育社 1988年
・三宅康治 川村俊一 市野和之 『競争激化のなかで成功するショッピングセンター、
テナント出店法』 経営情報出版社 1998年
・新原浩朗、高岡美佳 『組織科学 Vol.38 No.1』 白桃書房 2004年
・アーウイン・J・コイプ(著)木原健一郎(監修)藤本直(訳)
『フランチャイズ・バイブル』ダイヤモンド社 2006年
・生田目 正義『たかが百貨店 されど百貨店 繊研新聞社 2004年
・竹内 慶司『商店経営学の分析枠組み』同友館 2001年
・広瀬 薫『新版・実戦ショッピングセンター』誠文堂新光社 1994年
・三宅 康治『競争激化のなかで成功するショッピングセンター・テナント出店法』
経営情報出版社 1998年
<ウェブサイト>
・総務省 http://
・経済産業省 http://
・日本百貨店協会 http://
・経済産業省 http://
・社団法人日本フランチャイズチェーン協会 http://
・リアルタイム・リテール http://
・(株)アクアネット http://
・社団法人中小企業診断協会東京支部フランチャイズ研究会
http://
・墨流経営研究所http://
・チェーンストアエイジhttp://
・独立行政法人 経済産業研究所 「多店舗展開型加盟者調査研究報告」
http://
・社団法人中小企業診断協会東京支部 「メガフランチャイジーに関する調査研究報告書」 2005年1月 http://
・フリー百科事典ウィキペディア http://
・株式会社そごう 業績説明資料http://
・フランチャイズ情報提供サイト 「フランチャイズのメリット・デメリット」
http://
・三井物産戦略研究所 http://
・株式会社ゴトーホームページ http://
・http://
ryutsu_sangyo/ryutsu03.files/frame.htm#slide0002.htm
・リアルタイム・リテール「インタビュー」http://
・Takashimaya Recruiting Information 2007
http://
・百貨店のロイヤリティプログラムの検証と活用提案http://
BE%E8%B2%A8%E5%BA%97%E3%81%A8%E3%81%AF%22
・老舗百貨店における今後の経営http://
部門番号 17
部門名 マーケティング
百貨店について(百貨店の現状と将来について)
―百貨店におけるメガフランチャイジー戦略について―
日本大学商学部 佐々木ゼミナール
代表者:谷崎 亮
参加者:太田 純子、大谷 真由、谷崎 亮、信國 健司
平林 宗十郎、細田 あゆみ、渡辺 邦彦
目 次
第1章 百貨店の現状と問題点
第1節 百貨店の定義
第2節 百貨店の現状
第3節 百貨店の特徴・仕組み
第2章 メガフランチャイジー戦略
第1節 フランチャイズ定義・特徴
第2節 メガフランチャイジー定義・特徴
第3節 成功事例
第3章 百貨店の形態
第1節 ライセンス契約
第2節 テナント契約
第3節 フランチャイズ契約との比較
第4章 導入によるメリット・デメリット
第1節 事例
第2節 メリット・デメリット
第3節 百貨店における成功可能なメガフランチャイジーのビジネスモデル
第5章 総括及び展望
第1章 百貨店の現状
第1節 百貨店の定義
総務省によって定められた日本標準産業分類(平成14年3月)において、百貨店は大きく分類すると卸売・小売業に分類され、その中でも各種商品小売業に分類されており、衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所で、その性格上いずれかが主たる販売商品であるかが判別できないものであって、百貨店、デパートメントストアなどにその例が多いとある。百貨店とは「衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50 人以上のもの」をいう。また、経済産業省によって定められた商業販売統計(平成14年9月)では、「百貨店とは、セルフ店(売り場面積の50 %以上について、セルフサービス方式を採用している商店)に該当しない事業所であって、かつ、売場面積が特別区及び政令指定都市で3,000?以上、その他の地域では1,500?以上の事業所」と定義している。さらに日本百貨店協会では、「物理的に独立した店舗面積が1,500?以上のもので、日本百貨店協会に加盟している百貨店」と定義している。
百貨店とは、衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所であり、その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できないもの、つまり商品の品揃えは総合的で、セルフ店に該当せず、対面販売を基本とした徹底した人的サービスを提供している大規模小売店だといえる。
第2節 百貨店の現状
1990年代初頭の百貨店の売上は、80年代後半からのバブル景気の影響を受けて、高い伸びでスタートしたが、バブルが崩壊すると92年以降は大きく落ち込み、その後、数年かかって盛り返したが、97年以降再び売上は伸び悩み、97年から2005年まで9年連続で売上が前年割れとなっている。
しかし、2005年は減収傾向に歯止めがかかった。特に4月以降はプラス基調に転じ、年後半の景気回復などをうけ、業績は堅調に推移している。2006年に入ってからも売上は好調だったが、4月以降再び大幅ではないがマイナスになり、8月まで5ヶ月連続でマイナスに転じている。業界全体では減収傾向に歯止めがかかりつつあるとはいえ、大都市と地方百貨店では状況が異なる。
東京地区の百貨店については、バブル後、売上の落ち込みが最も大きかったが、その後、売上伸び率の前年割れが小幅化し、1999年以降は全国平均を上回り、都心回帰で百貨店も復調したかと思われたが、2002年には全国平均を下回り、その後も全国平均を下回っている。
地方の百貨店についても、バブル後売上が落ち込んだが、その後、徐々に回復していった。しかし、地方百貨店の環境は、地域経済の低迷、消費不況、さらに、大型ショッピングセンターの進出が影響を与え、2001年には地方単独経営の百貨店企業の倒産、閉鎖が相次いだ。また、同じ百貨店であっても地方店や郊外店の場合は売れ筋商品を十分に供給してもらえず、このため地方の消費者が大都市へ買い物に出かけてしまう「ストロー現象」で消費流出を招いてしまっている。このように地方百貨店では引き続き厳しい事業環境が続いていたために生き残り策として、郊外ショッピングセンターのテナントとしての出店や、自らのショッピングセンター型新業態の開発も活発になっている。
商品部門別の売上に関しては、婦人雑貨などが含まれる見回品と食料品の伸びがよく、婦人服、食料品の売り場が拡大されていった。これにより、本来の百貨のバランスのとれた業態から、婦人服、見回品、食料品、食堂・喫茶の4部門に特化された業態へと変化し、特に婦人服売り場と、地下食料品売り場に力を入れるようになった。婦人服売り場に関しては、消費者の年代やニーズに合わせた、複数のフロアが存在している。また、地下食品売り場に関しては、話題の店舗を数多く投入し、売上も婦人服に次いで高く伸びている。
出所:麻倉佑輔 大原茜 『最新・全国百貨店の店舗戦略』 同友館 2003年5月25日 p.7
日本百貨店協会 http://
第3節 百貨店の特徴
百貨店の特徴を挙げてみると、百貨店は駅付近などの一等地に立地し様々な店が一ヶ所に集まっているため、電車などでのアクセスが容易で交通至便であり、同じ場所で消費できるワンストップショッピング性である。売場や商品の案内、各階の案内、買物の相談から高齢の方や障害者の消費者の手伝いなどの、行き届いたホスピタリティサービスである。百貨店と読んで字のごとく百貨を扱っているため、消費者が豊富な品揃えの中から商品を選択できる品揃えの良さ、ギフトに相応しい包装紙に代表される店ブランドの魅力。老舗ならではの信用、信頼感。美容マッサージ、旅行センター、フィッティングルーム、屋上遊園などの、贅沢でゆとりのある施設環境。美術館、ギャラリー、劇場、カルチャーセンターなどの文化性、などの特徴が挙げられる。
また百貨店には委託仕入、消化仕入という特徴がある。委託仕入とは業者が商品の販売を百貨店に委託し、百貨店は一定期間商品を預かって販売し、売れ残った商品は返品する。消化仕入とは百貨店が商品を業者から預かり、その商品が売れた時点で仕入れ販売する。このようにこれらは仕入リスクを負わないので棚卸資産回転率が良い。一方、リスクを負う業者はリスク分を価格に上乗せするため小売価格が高くなる。加えて返品制度、派遣店員制度が挙げられる。返品制度は、前に述べたように、百貨店が仕入れた商品に売れ残りが生じた場合、売れ残りをメーカー、問屋が引き取るものである。派遣店員制度は、メーカー、問屋が店員を百貨店に送り込み自社の製品を販売する、委託販売制度である。百貨店には以上のような特徴が挙げられる。
次にショッピングセンター(SC) の特徴を挙げ、百貨店の特徴と比較していく。まず、ショッピングセンターの特徴をあげる前に、ショッピングセンターの定義を明確にする。
ショッピングセンターとは、1つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設であり、駐車場を備えるものをいう。その立地、規模、構成に応じて、選択の多様性、利便性、快適性、娯楽性等を提供するなど、生活者ニーズに応えるコミュニティ施設としての都市機能のことであると定義している。
ショッピングセンターは百貨店と同様で、様々なショップがあり、豊富な品揃えとサービスを提供する。しかしショッピングセンターの大きな特徴は、ディベロッパーにより計画的に開発されるという点である。機能上から、駐車場設備であることは、すでに新しい商業立地であり、ここにキーテナントと、専門店が入り、その配置や、商品ゾーンが計画され、また種々の楽しむ機能や、遊ぶ機能、社会生活上必要な機能があり、ワンストップショッピングが可能となる。また形態的には、都心から離れた郊外にあり、低階層で、駐車場が十分あるため集客力に優れており、テナントミックスされた商業集積地である。
第2章 メガフランチャイジー
第1節 フランチャイズの定義・特徴
フランチャイズの特徴は、フランチャイザーが開発したフランチャイズシステムやノウハウと、それを象徴する商標もしくはサービスマーク、チェーン名など、事業を運営する上での方法を提供することである。つまり、フランチャイジーは、自分の資金を投入して、本部の開発した商売の方法やノウハウを使用して営業を行い、前者、後者がお互いに利益を得ようとする仕組みである。
[表-2] フランチャイズチェーンの仕組み
出所:社団法人日本フランチャイズチェーン協会
http://
フランチャイズチェーンにおけるフランチャイザーのメリットは第1に、急速な店舗拡大が可能であることがある。第2に、店舗増加によって即座に利益が得られること。 第3に、契約時の取り決めにより何%かのロイヤリティを受け取ること。デメリットは第1に、加盟店の募集に資金と人材が必要となることがある。第2に、フランチャイズチェーンは統一したサービス提供が基本となるが加盟店によりレベルのばらつきがブランドイメージの低下につながる恐れがある。第3に、レギュラーチェーンのようにトップダウンによる意志決定が難しく、戦略転換に手間と時間がかかること。一方フランチャイジーのメリットは第1に、事業成功率が高く、開業資金があればフランチャイズ契約により即座に開業が可能となり、開業資金は個人で開業するより少ない資金で開業が可能となる点がある。第2に、開業する前に本部から店舗運営、経営ノウハウなどの指導を受け、それに従えば利益が得られること、第3に本部が一括して広告を行うため販売促進において大きな影響力を得られること。デメリットとしては第1に、本部の指導のもとで経営を行うため活動の自主性の不自由が生じること、第2に、経営について本部は全体の利益を考えるため、個々の加盟店には不利益が生じる場合があること、第3に、契約期間中の中途解約には条件があり、契約期間が終了してから一定期間は同業種の営業が禁止されていることである。
第2節 メガフランチャイジーの定義・特徴
近年、メガフランチャイジーと呼ばれる企業群の存在が注目されている。メガフランチャイジーとは比較的新しい言葉であり業界団体や行政による明確な定義があるわけではないが、一般的にメガフランチャイジーとは、「フランチャイジーが多数(通常30店舗以上)の店舗を経営し、且つフランチャイジーとしての売上高20億円以上の規模」のフランチャイジーをいう。メガフランチャイジーの特徴は、さまざまなタイプの企業が含まれている。
[表-3]メガフランチャイジーのタイプ別分類
フランチャイズ加盟店事業の
売上高比率による分類
1)フランチャイズ加盟事業専念型……フランチャイズ加盟による売上高比率 )80%以上
?業態転換パターン(経営資源を本部からフランチャイズ加盟ビジネスに投入)
?最初からフランチャイズ加盟店としてスタートしたパターン
2)戦略新規事業型 )……フランチャイズ加盟による売上高比率30〜80%程度
3)副業型……フランチャイズ加盟による売上高比率30%以下
加盟フランチャイズブランドの総数、
及び種類による分類
1)単一ブランド特化型……ひとつのフランチャイズブランドに特化して事業展開
2)マルチフランチャイジー型……複数のフランチャイズブランドに加盟して事業展開
?同業種選択パターン
?異業種選択パターン
フランチャイズ加盟店専業か、
または本部兼業かという視点による分類
1)フランチャイズ加盟店専業……フランチャイズ加盟店事業のみに専念する
2)フランチャイジー/ザーハイブリット型……加盟店事業を展開しつつ、自ら本部としての機能も有する
?エリアフランチャイザー兼営型
?独自業態開発型
出所:小林 忠嗣『メガフランチャイジー戦略』ダイヤモンド社 2002 第4章 p167
次にメガフランチャイジー戦略のメリット・デメリットを考える。メリットとしては、第1に戦略的ポートフォリオが組めること、第2にフランチャイズ加盟店事業を通じて得た経営ノウハウを本業の経営にも生かすことが可能であること、第3に経営資源の有効活用が可能であること、第4に地元及びその周辺エリアで複数フランチャイズブランドの店舗をドミナント展開していくことで効率的な販売促進が行えることである。実際、日本最大級のメガフランチャイジー企業とされるタニザワフーズ株式会社は、東海地区でドミナント戦略を用いることで圧倒的な地域シェアを獲得して成功を収めた。
デメリットは、第1にメガフランチャイジー戦略をとることによって判断が難しくなるということがある。つまり、合わないと思った事業は早めに切り捨てる判断が必要となるということである。第2に自分の持つエリア内で展開できる事業の数には限りがあるというエリアフランチャイザーの限界もある。メガフランチャイジーを目指して成長する過程で自社ブランドの育成を考えたとき、二つの育成を両立させ成功している事例は極めて少ない。メガフランチャイジーとしての成功と、自社ブランドを育成して、さらにはフランチャイズ化することの両立は難しいとされる。
フランチャイジーとメガフランチャイジーの相違は、第1に、マルチフランチャイジー(複数ブランドのフランチャイズチェーンに加盟しているフランチャイジー)は、売り上げ規模にかかわらず、あくまでも複数のフランチャイズ本部に加盟しているのに対し、メガフランチャイジーは、先ほど述べた一般的な定義によりフランチャイジーとメガフランチャイジーの相違点には、売り上げがある。第2に、事業規模をみると、フランチャイジーは個人または零細企業で弱者という負のイメージがあるように思えるが、メガフランチャイジーの事業規模は、本部企業よりも小さいとは限らず、数百名もの社員を要する企業が、たかだか数十名しかいないフランチャイズ本部の加盟店になる例は珍しくない。このことからも、選択した本部への影響において相違がある。第3に、加盟者の資質・経営資源をみると、戦略的事業ポートフォリオの構築が可能である。フランチャイジーは事業が立ちゆかなくなると、再び立ち戻すのが大変で、潰れてしまったりするのに対して、メガフランチャイジーのように、複数のフランチャイジーに加盟(マルチフランチャイジー化)すれば、仮にそのうちの一つの事業が立ちゆかなくなっても、企業業績全体はさほど影響をうけなくてもすむ。また、スクラップ・アンド・ビルドを積極的に進めることができるため、安定した成長を維持することができる。フランチャイズ加盟店事業を通じて得た経営ノウハウは、本業の経営にも生かすことができ、既存業務とのシナジー効果が生まれることも相違点である。メガフランチャイジー化することによって経営資源を有効活用することができ、メガフランチャイジーであれば、押さえた土地の特性に適応しやすい業種・業態を自らのフランチャイズブランドのなかから選び当てはめることができるため、これにより、エリアフランチャイザー(フランチャイズ加盟店として成功を収めた企業が、そのフランチャイズチェーンの本部から一定地域でのフランチャイズ展開権を購入し、そのエリアにおけるフランチャイズチェーン本部として事業を展開するということ)契約を結ぶこともできる。第4に、メガフランチャイジーが参入することにより、フランチャイザーがフランチャイジーより力を持っていた時代から、メガフランチャイジーがフランチャイジーよりも力を持つような時代になってくる。
第3節 成功事例について
メガフランチャイジー企業として成功を収めた株式会社ゴトーがフランチャイズビジネスと出会ったきっかけは、過度な出店拡張が仇となり、バブルの崩壊とともに、93年から94年にかけて不採算店が増加したので、転貸先の一つであったブックオフコーポレーションとフランチャイズ契約を結び加盟店を展開したことである。これにより、店舗における赤字は解消されたものの営業利益を出すまでに至らなかった。このような状況下のなかでゴトーは補完的効果のある他の業務を導入して一店舗を多業務化した。具体的に言うと、ブックオフの店舗面積とバックヤード面積を少しずつ削って、テレビゲームの販売を開始した。この選択は結果的に新しいビジネスモデルを生み出し、1店舗当たり1000万円以上の利益をだすようになった。同社は95年にはカルチャーコンビニエンスクラブとフランチャイズ契約を結んだが、このときは最初の店舗からテレビゲーム販売とマルチタスク化した。97年には、1店舗で、TUTAYAとブックオフとテレビゲーム販売とを複合させ、現在につながるゴトー流のマルチタスク化店舗の展開を開始した。
ゴトーのメガフランチャイジー企業としての特徴は、複数のフランチャイズブランドに加盟しているマルチフランチャイジー型であり、異業種に属するフランチャイズブランドを複数選択して加盟する異業種選択パターンに分類される。また、同じくメガフランチャイジー企業であるタニザワフーズ株式会社は、マルチフランチャイジー化によるドミナント戦略を成功させ常に飲食店に特化してきた。またコンビニエンスストアを中心として展開している株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリアは、マルチフランチャイジー化しておらず、特定のフランチャイズブランドに特化して経営資源を集中することで事業の拡大を狙う単一ブランド特化型であり、出店戦略からしてゴトーとは大きく異なっている。
ゴトーの成功は、マルチタスク化したことのほかに、フランチャイズ展開の初期にブックオフとTSUTAYAを選んだところにあるともいえる。大型ロードサイド店を転業する際に、比較的、手掛けやすい業態にうまく凝縮できたのである。現在の両FC本部の発展を見れば、ゴトーの見る目は確かなものだったといえる。
店舗のマルチタスク化という新しいビジネスモデルの開発がフランチャイズの加盟店であるゴトーにより担われたのは明らかである。加盟店にとって一つの業務に徹底的に努力するより、複数業務に努力を振り分けるほうが収益改善上プラスになる。このような新しいアイデアがゴトーによって生み出され、フランチャイズシステムの進化に貢献したといえるであろう。
第3章 百貨店の経営形態
第1節 ライセンス契約
百貨店は、デザイナーやメーカーと提携し、提携先のデザイン、機能、ノウハウなどのライセンスをロイヤリティで支払うことによって商品を導入する。ライセンス契約の内容
の範囲も様々である。ライセンス商品のブランド名やマークなど商標の独占的使用にとどまるものから、ライセンス商品を日本で製造することを許すもの、さらに、その製造や販売における記述、情報、ノウハウなど広範囲にわたるものまである。基本的にライセンス契約を行えば百貨店が、そのブランドの独占販売権を獲得する。それとともに、衣服をはじめ、バッグ、財布などの小物、靴、帽子、服飾雑貨、化粧品などの多数のアイテムについても、そのブランド名を冠した商品展開権を得ることができる。
ライセンス契約を結ぶことにより百貨店は、ライセンスPB商品を生産することができる。伊勢丹では大手ブランドと組み、開発した商品を「伊勢丹」の名前を出さずブランド名で売り場に並べている。「伊勢丹メンズ館」では、売り場の商品の約70%が、有名ブランド品に見えて実はPB商品になっている。
ライセンスPB商品を生産することはメリットが3つ挙げられる。第1に、百貨店の来店客層や売れ筋商品などの調査をし、商品企画をするため、高い売り上げの望める商品を導入することができる。第2に、他店にはないその百貨店独自の商品を販売することにより、百貨店それぞれの個性を出すことができ、競争上の差別化政策につながる。ライセンスPB商品がない場合、他の百貨店と同じ仕入先から商品を仕入れることになる。そのため、同じような商品の品揃えがされ、同じような商品が販売されることになる。第3に、仕入れ商品よりも高いマージンがとれることになり、営業収益を高めることができる。
しかし、PB商品を生産することは問題点も生じてくる。PB商品の場合は、売れ残った商品をメーカーに返品するわけにはいかないので、的確な販売予測力と確実に売り切る販売力が必要になる。また、ブランドの価値を維持できなければならない。そのためには第1に、デザイナーの世界観を表現できるかどうかが問われる。第2に、NB商品も売り場に並べるケースが多いため、PB商品がNB商品とほぼ同じレベルでコンセプトを表現していないと、売り場で統一されていない印象を与えてしまう。
また近年、海外ブランド物においては、海外旅行が大衆化しているため、実際に本店で「本物」に触れる消費者が多くなってきている。そのため、PB商品が「似て非なるもの」と感じる人も出てきた。さらに、ライセンス契約をしていたデザイナーのブランドが、「○○ジャパン」として日本市場に乗り込んでくるケースも増加してきた。そのため、百貨店にはよりいっそうの努力が必要になってくる。
第2節 テナント
百貨店の経営形態の2つ目はテナント制である。テナントとは、ビルや百貨店・ショッピングセンターなどの一部区画を、その建物を管理・運営する企業から借り受けて運営する事務所や店舗のことをいう。百貨店がテナントを募集する方法には、ディベロッパーの選定、一般公募、推薦、の3つの方法がある。そこから、出店申込され個別折衝が行われる。そして、審議に入り決定される。
出店が決定された後百貨店とメーカーの間で出店契約が結ばれる。出店契約には、4つの方法がある。第1に、ほとんどのテナント出店の契約形態になっている「通常のテナント契約」である。これは、特定の独立した区画を出店者の占有の営業場所として使用し、その対価として確定金額を支払うものである。第2に、売り場内の陳列ケースの一部を貸与する契約である。これは、特定の場所に対する占有性や独立性の薄い契約である。第3に、売れた分だけ仕入れをし、特定の場所に対する占有性や独立性が非常に薄い「売上仕入方式の業務委託契約」である。これは日本の百貨店独特の方法である。第4に、ディベロッパーが建築した建物を出店者に分譲するもので、所有権の移転が伴う「分譲式」である。当然のことながらメーカー側は出店する際に、売上予想や収益予測をすることが必要である。既存の百貨店に出店する場合は、全体の売上、来店顧客数、年齢構成などの基本データを検証し、自社店舗がターゲットにする顧客と合っているかどうかを調べる必要がある。また、商圏の分析をすることも重要である。
百貨店にとってテナントとは、百貨店の勝敗を決定することになる。ブランドにもよるが、一店で集客が一日およそ千人変わるほどの影響力がある。
第3節 フランチャイズ契約との比較
ここでは、フランチャイズ契約、ライセンス契約、そしてテナント契約のメリット・デメリットについて述べ、それぞれ比較していく。
はじめに、フランチャイズにおけるメリットであるが、第1に、急速な店舗拡大が可能であること。第2に、店舗増加によって即座に利益が得られこと。デメリットとしては第1に、加盟店の募集に資金と人材が必要となることがある。第2には、フランチャイズチェーンでは統一したサービス提供が基本となるが加盟店によりレベルのばらつきが生じ、ブランドイメージの低下につながる恐れがあることである。
次に、ライセンス契約におけるメリットであるが、第1に、百貨店の売れ筋調査に応じて高い売り上げの見込める商品あるいはメーカーと契約することができる。第2に、単に自社で開発している商品であるため、仕入れ商品よりも高いマージンを見込めることができる。デメリットは、第1に、ライセンスPBは確実に売り切る販売力がなければ売れ残ってしまうことである。第2に、ブランドイメージを損なわないように、デザイナーの世界観を確実に表現しなければいけないことである。第3に、売り場での、PB商品とNB商品のコンセプトが難しいことである。
テナント契約のメリットは、出店者から店舗を貸す対価としてほぼ安定した確定金額を受け取ることができる。つまり、出店した場合の売り上げ予測がたてやすいことである。 デメリットとしては、百貨店自体が衰退している場合、より良い出店者を招き入れることに困難を要することである。
以上のように、それぞれのメリット・デメリットを述べた上で本題である比較、検討に入っていく。まず、それぞれの初期の店舗作りに関して、フランチャイズ契約は初期の店舗費用は比較的に低資金で本部指導によってあらゆる事業は効率的に行われる。ライセンス、テナント契約は、一から店舗を作り上げて、営業していかなければならないので、非常に多くの経費が掛かり、時間もかかる。そして宣伝効果という観点から比較していくと、フランチャイズ、ライセンス契約については自らのブランドの知名度を日本中、あるいは世界中に広げることができる。しかし、テナント契約については、一つ一つ単体であるため、宣伝効果という観点から述べるとこの上記二つには劣ることがあるのだ。
最後に、初期の店舗作り、宣伝効果において比較した結果、より多くの良い要素を備えているのはフランチャイズ契約であるということがわかる。
第4章 導入によるメリット・デメリット
第1節 事例
百貨店にメガフランチャイジーを導入した事例については、明確な事例がないため百貨店がフランチャイザーとフランチャイズ契約をしていると仮定したうえで論じていく。事例としては、株式会社そごうのそごう千葉店を取り上げて検討する。
千葉そごう店でフランチャイズシステム導入に影響を与える点を2点挙げる。
まず、第1に、10階ダイニングパークと称された24店舗のレストランフロアがある。ここにフランチャイズシステムを導入することを提案する。ここにフランチャイズシステムを導入することによって、フランチャイズ本部のオペレーションシステムをそっくり活用し、高効率の事業展開を行う。こうすることが最も有効な形で経営資源を調達・運用することにつながり、何より有限な資源である時間を節約できる。情報は業界動向から他の店舗情報まで細かく入手することが可能である。また、異なった種類の飲食業をさまざまな形で隣接させることによって複合効果を生み、集客力が大幅に向上するのであろう。だが、実際に導入するときのポイントは数多くあるフランチャイズチェーン本部のなかから非常に優れたフランチャイズチェーン本部を選択しなければ、ビジネスとして成功しない。したがって、本部企業の安全性、本部の協力体制、店舗の収益性、加盟へのリスク、その産業の状況などを配慮して事業展開すべきである。
第2に、フランチャイズ加盟店事業を通じて得た経営ノウハウは、本業の経営にも生かすことが可能である。具体的に言うと、フランチャイズチェーン本部が構築してきた各種経営ノウハウである従業員教育、日時決算システムなどを本部SVの指導つきでじっくり学ぶことができる。こういったことが基点となり、百貨店独自の新たな業態を開発することができる。そして、フランチャイズ加盟店として培ってきたノウハウが、今度はフランチャイズ本部として生かされてくる。また、人材育成においても、本部と契約している他の加盟店へと積極的に視察に行かせて、現場の工夫を吸収させる。本部が社内で構築した研修プログラムと百貨店が独自に培ってきた研修プログラムを共有することによって、新たな研修プログラムを創り出すであろう。
第2節 メリット・デメリット
百貨店にメガフランチャイジー導入におけるメリットとして、第1に一店舗を一業務で運営するのではなく、他の業務を導入して補完的効果をもたらすマルチタスク化による店舗形態が利益率向上を図ることができ、出店費用の効率化や管理費用の圧縮することもできる。そして、その複合的な店舗開発が集客力の増加へとつながる。第2に、本部と加盟店といった二つの枠組みのなかで事業を行うため、あらゆる情報または経営ノウハウを相互に共有し、それが新たなビジネス展開を生む可能性がある。第3に、本部主導で商品・原材料・消耗品などの大量一括購入による物流システムの合理化、またその地域に点在したブランド側と共有した物流システムを構築などがコストを削減し、本部主体の経営によりあらゆる加盟店の負担を軽減することが加盟店にとって店舗運営だけに集中して行うことが可能になる。第4に、加盟店側に種々の成功事例、アイデアや工夫が生まれ、それらを本部のフランチャイズ・パッケージに取り込むことにより、相互補完作用が得られる。こういったアイデア創出がうまく顧客に伝わることができれば、新たな戦略を作り競争の源泉となる。
デメリットは、第1に、百貨店が加盟店を呼びかけるためには、莫大なコストを必要とする。それは、加盟金や新たな店舗づくりの設備投資などさまざまな資金を要することになる。第2に、あらゆる業態が参入するため組織として機能するかどうか不透明であるため、明確な理念に基づいた組織づくりを要する。第3に、フランチャイズ化された事業を短期間のうちに収支の均衡を得るためには、相当のハードワークをこなすマネージャーや従業員を配置する必要がある。また、人材をいかに育成し、長くつなぎとめておくのも難しい問題である。第4に、メガフランチャイズシステムは通常の小売ビジネスとは大きく異なっている。したがって、こうしたシステムを構築するにあたって、本部と加盟店の連携が必要不可欠である。
第3節 百貨店における成功可能なメガフランチャイジーのビジネスモデル
第1に、百貨店の資金に余裕がないならば、成功しているメガフランチャイジー企業と業務提携することによって、新たなノウハウや資金を得ることができ、より付加価値の高いサービスを提供することができる。そして、その地域で店舗開発を行うことにより、共同販促、事業効率化、人事交流による新企画の創出、情報システムの共有などのメリットが挙げられてシナジー効果が期待できる。第2に、百貨店に子会社を設立し、その子会社がフランチャイザーとフランチャイズ契約を結び、百貨店の資金でロイヤリティ等を支払う。そして、様々な業種の加盟店となるメガフランチャイジー企業になることで、より多くのフランチャイズ経営のノウハウを取得して、百貨店における成功可能なメガフランチャイジーのビジネスモデルになると考えられる。
第5章 総括及び将来展望
日本の百貨店は長い歴史を持ち、人々に信頼を与え続けてきた。しかし、有名ブランドを売り場に寄せ集めた「場所貸業」や従来の経営(殿様商売)などの主体性のなさが顧客離れを招いた、また、バブル崩壊による顧客の買い控えや、他業界による低価格販売の影響により、92年以降、長期にわたって業績低迷に陥り、経営の縮小を余儀なくされた。その後、売り上げ減少はさらに続いたが、都市圏内において2005年には減少傾向に歯止めをかけた。ところが、地方百貨店は近隣のショッピングセンター、GMSの影響などによって苦戦を強いられている。そうした背景の中で、今後、地方百貨店が生き残るためにはどうするべきかという現状を踏まえ、問題点をさまざまな観点から探っていった。本稿では、この問題について考察していき、新たな戦略を提案することを目的とした。
本章で述べたが、メガフランチャイジー企業は集客力の向上、宣伝効果の向上、新規参入による産業の活性化、選択肢の拡大、便益性の向上、より良いサービス提供などのメリットがある。そこに、今後メガフランチャイジー戦略を百貨店業界において発展させる意義がある。
論文字数 11,932文字(図及び注釈を除く)
<参考文献>
・兼村栄哲 青木均 林一雄 鈴木孝 小宮路雅博 『現代流通論』
八千代出版1999年1月12日
・麻倉佑輔 大原茜 『最新・全国百貨店の店舗戦略』 同友館 2003年5月25日
・内川昭比古 『フランチャイズビジネスの実際』日本経済新聞社 2005年
・日本フランチャイズ協会『よくわかる フランチャイズ入門』 同友館 2005年
・小林忠嗣(監修)リンク総研(編著)『メガフランチャイジー戦略』
ダイヤモンド社2002年
・民谷昌弘 『成功するフランチャイズ戦略-FC導入9つのステップ』
ダイヤモンド社 2000年
・田島義博 『フランチャイズチェーンの知識』 日本経済新聞社 1990年
・川島蓉子 『伊勢丹な人々』 日本経済新聞社 2005年
・小山周三 『現代の百貨店』 日本経済新聞社 1997年
・岡田康司 『百貨店業界』 教育社 1988年
・三宅康治 川村俊一 市野和之 『競争激化のなかで成功するショッピングセンター、
テナント出店法』 経営情報出版社 1998年
・新原浩朗、高岡美佳 『組織科学 Vol.38 No.1』 白桃書房 2004年
・アーウイン・J・コイプ(著)木原健一郎(監修)藤本直(訳)
『フランチャイズ・バイブル』ダイヤモンド社 2006年
・生田目 正義『たかが百貨店 されど百貨店 繊研新聞社 2004年
・竹内 慶司『商店経営学の分析枠組み』同友館 2001年
・広瀬 薫『新版・実戦ショッピングセンター』誠文堂新光社 1994年
・三宅 康治『競争激化のなかで成功するショッピングセンター・テナント出店法』
経営情報出版社 1998年
<ウェブサイト>
・総務省 http://
・経済産業省 http://
・日本百貨店協会 http://
・経済産業省 http://
・社団法人日本フランチャイズチェーン協会 http://
・リアルタイム・リテール http://
・(株)アクアネット http://
・社団法人中小企業診断協会東京支部フランチャイズ研究会
http://
・墨流経営研究所http://
・チェーンストアエイジhttp://
・独立行政法人 経済産業研究所 「多店舗展開型加盟者調査研究報告」
http://
・社団法人中小企業診断協会東京支部 「メガフランチャイジーに関する調査研究報告書」 2005年1月 http://
・フリー百科事典ウィキペディア http://
・株式会社そごう 業績説明資料http://
・フランチャイズ情報提供サイト 「フランチャイズのメリット・デメリット」
http://
・三井物産戦略研究所 http://
・株式会社ゴトーホームページ http://
・http://
ryutsu_sangyo/ryutsu03.files/frame.htm#slide0002.htm
・リアルタイム・リテール「インタビュー」http://
・Takashimaya Recruiting Information 2007
http://
・百貨店のロイヤリティプログラムの検証と活用提案http://
BE%E8%B2%A8%E5%BA%97%E3%81%A8%E3%81%AF%22
・老舗百貨店における今後の経営http://
|
|
|
|
|
|
|
|
植木ゼミなんだよ〜 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
植木ゼミなんだよ〜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6475人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19252人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人