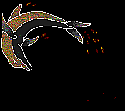開催終了映画『粥川風土記』上映会@美並(粥川谷)
詳細
2008年05月21日 14:00 更新
ORGAN主催の上映会のお知らせです。
以前から見たかった民族文化映像研究所(民映研)のドキュメンタリー映画。
他にも北はアイヌから日本全国様々な民俗記録活動をしています。
民族文化映像研究所
http://
長良川の支流「粥川」は、「かいがわ」と読みます。
山岳信仰で知られる高賀山に連なる瓢ヶ岳に源を発する粥川谷。
http://
その谷での生活の様子や自然と生きる姿を通して、映像人類学の第一人者、姫田忠義監督が、千年以上続く谷の暮らしを長編記録映画にしたというもの。
しかも今回の上映会は、映画の舞台である美並町高砂の粥川谷で行われるそうです。
現地でそのまま感じることのできる絶好のチャンス。
近くには星宮神社もあり、円空ゆかりの地でもあります!
〜以下、メーリングリストより転載
(文中最後の案内のある「みどりの祭り」は、5/20で受付終了となっていますのでご了承ください)
・・・・・・・・・・・・ORGAN映画上会・・・・・・・・・・・・
自然との深い対応と共生
そこで長い年月をかけて培われてきた人間の真に活きる力を学ぶ!
◆2008年5月31日(土) 17時より
◆民族文化映像研究所製作 長編記録映画『粥川風土記』
◆NPO法人校舎のない学校製作 実践記録映画『共に伴に友に生きる』
http://
http://
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
長良川流域に暮らすわたしたちにとって、
この清流のうつくしさを、人びとはどんな営みで守ってきたのか。
どう自然と向き合い、そこで生きていく知恵や力が、どう培われてきたのか。
わたしたちはこれから何を学び、受け取ることができるのか。
粥川の森で、貴重な記録映像を観る会を開催します。
ぜひこの機会に、ご参加ください。
【開催概要】
◆日 時:2008年5月31日(土)
17:00〜21:00(開場16:30)
◆場 所:星迎館
http://
◆入場料:2000円
◆プログラム
・長編記録映画『粥川風土記』 (民族文化映像研究所製作)
http://
・実践記録映画『共に伴に友に生きる』(NPO法人校舎のない学校)
http://
◆主催:ORGAN
◆申込み:ORGAN担当:平井(hirarin0621@yahoo.co.jp)
※だいたいの参加人数を把握したいので、参加していただける方は
ご一報いただけるとうれしいです。
【映画概要】
◆『粥川風土記』
長良川の水がきれいなのは、支流の水がきれいだからである。
自然の水、自然の流れがきれいなのは、その自然そのものの力であり、姿である。
と同時に、それと寄り添って生きる人の生活のありようと心の反映である。
日本屈指の清流長良川の源流、南端部に位置する支流・粥川。
長編記録映画『粥川風土記』は、この粥川流域に暮らす人びとが、
いかに山や水に接し、そこに育まれた草木・鳥・虫・動物などの生物たちと
接し、そしていかに人と人とのつながりを培ってきたかを記録したものである。
◆『共に伴に友に生きる』
NPO法人校舎のない学校は、地域から、生活から、人から、
地域のなかで、ほんものの生きる力を学ぶ体験研修を行っている。
3年半分の実践のなかで、多くの研修者が、
どんな人もそれぞれがもっている力を発揮できることが、
安心して暮らしていけることだと、地域の講師のみなさんから学んできた。
『共に伴に友に生きる』は、そんな地域のなかにある学びを
伝えてくれる実践記録映画である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★同時に、日中は郡上市「みどりの祭り」が開催されます。
併せてこちらもご参加ください。
【詳細】
◆郡上市第2回「みどりの祭り」
http://
◆テーマ「みんなで源流の森を作ろう」
◆日時5月31日 10時〜16時
◆場所 郡上市美並町高砂「粥川の森」
◆集合場所 星宮神社駐車場
【イベント内容】
粥川の森散策
間伐・森林教室体験 等
※受付期間は5月20日までです。
電話0575-67-1121 (内線234)
Mail rinmu@city.gujo.gifu.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〜以上
以前から見たかった民族文化映像研究所(民映研)のドキュメンタリー映画。
他にも北はアイヌから日本全国様々な民俗記録活動をしています。
民族文化映像研究所
http://
長良川の支流「粥川」は、「かいがわ」と読みます。
山岳信仰で知られる高賀山に連なる瓢ヶ岳に源を発する粥川谷。
http://
その谷での生活の様子や自然と生きる姿を通して、映像人類学の第一人者、姫田忠義監督が、千年以上続く谷の暮らしを長編記録映画にしたというもの。
しかも今回の上映会は、映画の舞台である美並町高砂の粥川谷で行われるそうです。
現地でそのまま感じることのできる絶好のチャンス。
近くには星宮神社もあり、円空ゆかりの地でもあります!
〜以下、メーリングリストより転載
(文中最後の案内のある「みどりの祭り」は、5/20で受付終了となっていますのでご了承ください)
・・・・・・・・・・・・ORGAN映画上会・・・・・・・・・・・・
自然との深い対応と共生
そこで長い年月をかけて培われてきた人間の真に活きる力を学ぶ!
◆2008年5月31日(土) 17時より
◆民族文化映像研究所製作 長編記録映画『粥川風土記』
◆NPO法人校舎のない学校製作 実践記録映画『共に伴に友に生きる』
http://
http://
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
長良川流域に暮らすわたしたちにとって、
この清流のうつくしさを、人びとはどんな営みで守ってきたのか。
どう自然と向き合い、そこで生きていく知恵や力が、どう培われてきたのか。
わたしたちはこれから何を学び、受け取ることができるのか。
粥川の森で、貴重な記録映像を観る会を開催します。
ぜひこの機会に、ご参加ください。
【開催概要】
◆日 時:2008年5月31日(土)
17:00〜21:00(開場16:30)
◆場 所:星迎館
http://
◆入場料:2000円
◆プログラム
・長編記録映画『粥川風土記』 (民族文化映像研究所製作)
http://
・実践記録映画『共に伴に友に生きる』(NPO法人校舎のない学校)
http://
◆主催:ORGAN
◆申込み:ORGAN担当:平井(hirarin0621@yahoo.co.jp)
※だいたいの参加人数を把握したいので、参加していただける方は
ご一報いただけるとうれしいです。
【映画概要】
◆『粥川風土記』
長良川の水がきれいなのは、支流の水がきれいだからである。
自然の水、自然の流れがきれいなのは、その自然そのものの力であり、姿である。
と同時に、それと寄り添って生きる人の生活のありようと心の反映である。
日本屈指の清流長良川の源流、南端部に位置する支流・粥川。
長編記録映画『粥川風土記』は、この粥川流域に暮らす人びとが、
いかに山や水に接し、そこに育まれた草木・鳥・虫・動物などの生物たちと
接し、そしていかに人と人とのつながりを培ってきたかを記録したものである。
◆『共に伴に友に生きる』
NPO法人校舎のない学校は、地域から、生活から、人から、
地域のなかで、ほんものの生きる力を学ぶ体験研修を行っている。
3年半分の実践のなかで、多くの研修者が、
どんな人もそれぞれがもっている力を発揮できることが、
安心して暮らしていけることだと、地域の講師のみなさんから学んできた。
『共に伴に友に生きる』は、そんな地域のなかにある学びを
伝えてくれる実践記録映画である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★同時に、日中は郡上市「みどりの祭り」が開催されます。
併せてこちらもご参加ください。
【詳細】
◆郡上市第2回「みどりの祭り」
http://
◆テーマ「みんなで源流の森を作ろう」
◆日時5月31日 10時〜16時
◆場所 郡上市美並町高砂「粥川の森」
◆集合場所 星宮神社駐車場
【イベント内容】
粥川の森散策
間伐・森林教室体験 等
※受付期間は5月20日までです。
電話0575-67-1121 (内線234)
Mail rinmu@city.gujo.gifu.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〜以上
コメント(4)
2008年05月21日 14:03
※粥川風土記情報(1)〜昨年の名古屋での上映パンフより
民族文化映像研究所作品「粥川(かいがわ)風土記」上映会
長編記録映画 2005年作品 16mmカラー 2時間42分
記録映画「粥川風土記」キネマ旬報2005年ドキュメンタリー部門第2位
日本屈指の清流・長良川の源流域南端部にある支流・粥川。
長編記録映画「粥川風土記」は、その粥川流域の人々が、いかにその自然の恩恵に寄り添って生きてきたかを足かけ7年にわたってたずね、記録したものである。
人々は山について、水について、森林について、虫や鳥や動物について、そして人間のあり方について語る。
本映画は本流・長良川の美しさを支える、支流に住む人々の生活のありようと心の反映を表すものである。
人間の生活・文化の向かう先が曖昧な今、自然と接しながら歴史を培ってきたこの地に生きる人々の心を知りたい。
監督 姫田忠義と民族文化映像研究所
日本の基層文化を映像で記録・研究することを目指して1961年設立。
所長姫田忠義(89年フランス芸術文学勲章オフィシエール受勲。
98年第7回日本生活文化大賞個人賞受賞)。
「自然との深い対応と共生」の中にある人間生活・文化のありようを見つめ、映像によって明らかにしようとする。
フランス・コレージュ・ド・フランスとの共同作業やハーバード大学での講演・上映会など、「映像人類学」の活動は世界各地に広がる。
2008年05月21日 14:07
※粥川風土記情報(2)〜民映研の映画案内文より
長篇記録映画「粥川風土記」(16mm 2時間42分)
日本は国土の70%以上が山地におおわれた山国である。
また、水に恵まれ、草木の成育条件に恵まれた水の国、森林の国である。
が、近年、その山や水、森林の荒廃が激しい。
いったい日本の自然は、そして人間の生活、文化はどこへ向かおうとしているのか。
日本屈指の清流・長良川の源流域南端部にある支流・粥川。
長篇記録映画「粥川風土記」は、その粥川流域の人びとが、いかに山や水に接し、そこに育まれた草木、虫、鳥、魚、動物などの生物たちと接し、そしていかに人と人のつながりの歴史を培ってきたかを、足かけ四年、初動から数えれば7年の歳月にわたってたずね、記録したものである。
長良川の水がきれいなのは、支流の水がきれいだからである。
粥川と長良川の合流点に立てば、それが誰の目にもわかる。一目瞭然である。
では、なぜ、粥川の水は、長良川の本流のそれよりきれいなのか。
「粥川風土記」は、おのずからその理由に踏み込んでいく。
自然の水、自然の流れがきれいなのは、その自然そのものの力であり姿である。と同時に、それに寄りそって生きる人の生活のありようと心の反映である。
この地の人々の心を知りたい。
この長篇記録映画には、おびただしい人びとの姿と声があらわれる。
本来、「風土記」とは、単なる表面的知識の羅列、集積物ではない。激変する歴史的激動期に、人間の生活、生存にとってぎりぎり何が必要なのか、それを必死に探し、考え、記したものである。
古代の出雲風土記に、例えば、菌類を含めて99種の草木類の名があり、それらはすべて薬草と考えられる。古代の人の生存にとって、薬草がどれほど大事なものであったか。
以下、近世には「新編風土記」が、さらに第二次大戦後には出版界に「風土記日本」があらわれている。
「粥川風土記」は、激変混迷する21世紀初頭のいま、私たちなりにはじめた映像による風土記編纂事業の嚆矢と言える。
そしてこれはまた、粥川流域の人びとが、山について、水について、森林について、虫や鳥や魚や動物について、そして人間のあり方について、交々語る「庶民風土記」、「語り部風土記」でもある。
「越後奥三面‐山に生かされた日々」(一九八四年・二時間二五分)、
「越後奥三面・第二部‐ふるさとは消えたか」(一九九五年・二時間三四分)など、その先達的作品群はすでにある。
2008年05月21日 14:08
※粥川風土記情報(3)〜2007年7月11日(水) 岐阜新聞朝刊「編集余記」より
山形の高級サクランボ盗難が今年は昨年の2倍、不作の年に追い打ち、と先日の本紙に。
農作物荒らしは県内でも頻々。農家の嘆きや憤激が本社にも伝わってくる。
いわゆる中山間地の山際の田畑では、イノシシ、シカ、サルなどの獣害も深刻だ。
郡上市美並町粥川谷の自然や生活文化を撮った長編記録映画「粥川風土記」
(民族文化映像研究所制作、2005年)にも度々出てきた。
大勢の住民が登場するが、山仕事の合間にもせっせと畑を耕してきた、
今夏米寿になる古川やゑのさんの話が印象的。
「土に預けておくとお天道さまがしとね(育て)ておくれる。その恵みで、6人の子を育てられた」。
先週末、小田雄三名古屋大大学院教授が代表を務める基層文化研究会が、
名古屋大でこの映画の上映とトークの集いを開いた。
映画にも出た地元の郷土史家池田勇次さんと古川さんが、獣害についても興味深い話をした。
「サルは悪いけど3分の1でも残す。人間は残さんで怖い。まんだサルの方がいいとこある」
と、古川さんは苦笑い。
「昔はサルは珍しかった。昭和30年代は学校の遠足で美濃市までサルを見に行った」
と、池田さん。
この映像による風土記は、
「木馬」やいかだ流しなど今は人々の記憶からも遠のいた
山と川の生業の風景を、地元住民の協力で見事に再現して見せた。
1000年の時を超えて風土を見る物差しを、
畑荒らしが横行するような今日のすさんだ世相にあてた時、
あらためて失われたものの大きさが見えてくる気がした。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
困ったときには