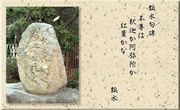- 詳細 2011年11月27日 21:25更新
-
地元播磨が生んだ異色の俳人・滝瓢水のコミュニティです。
遊郭の女を身請けしようとする友人を諫めて曰く
手にとるなやはり野に置けれんげ草
放蕩の末、愛する母の臨終に立ち会えず、墓前に涙して曰く
さればとて石にふとんは着せられず
飄々とした人生哲学と人情味溢れる言動の数々が、現実世界を生きる我々のこころにしみわたる…。
笑いと涙で、今もなお多くの人々に愛される瓢水の世界を語り合いましょう♪
※はじめまして♪&足跡帳はコチラ!
http://mixi.jp /view_b bs.pl?i d=75770 26&comm _id=944 980
『滝瓢水〜奇行重ねた異色の俳人』 三善貞司氏による解説
瓢水は風狂(風雅の道に徹すること)といえば聞こえはいいが、奇行を重ねたあげく家産を破り、大坂で客死した異色の俳人である。
彼は貞享元(一六八四)年、別府(べふ)村(現・加古川市別府)に生まれた。父は運輸業「叶屋」の主人の三代滝新右衛門政清、母はおさん。その一粒種で幼名新之丞、のちに四代新右衛門有恒と称し、俳号に瓢水のほか富春斎や自得庵などがある。
七つのとき父新右衛門が死亡。祖父の二代新右衛門清春に育てられるが、かわいらしい孫を溺愛(できあい)、家業はわしにまかせろと母おさんの兄で学者の福田貞斎に預け、好きなだけ学問させる。貞斎は俳諧も好み新之丞に手ほどきしたところ、十九歳のとき井上千山の撰集「当座払」に入集した。千山は臨終の芭蕉が形見の笠と蓑(みの)を与えた維然の弟子で、蕉風俳諧の宗匠。この若さで入集するとは大したものだとほめちぎられ、天狗(てんぐ)になった。
俺は芭蕉先生のように諸国を歩いて俳諧三昧(ざんまい)に生きたいと瓢水は、気ままな旅に出るが、芭蕉と違って金はうなるほどある。京や大坂の花柳界に入りびたって豪遊、遊女が香をたいているのを見て俺もやろと財布を火鉢の上で広げ、小判や小粒が音をたてて火種に落ちるや、さあ拾え、拾ったものに全部やると、熱い熱いと騒ぐ遊女たちを尻目にお大尽(遊び好きの資産家)ぶる。
東海道筋では哀れな親子の物もらいに同情、有り金残らずやって幼子の頭をなでて去り、次の宿場で得意になって話す。あるじからあほいわんとき、あら芝居や。赤ん坊借りてきて同情をひく商いやぞと言われると、ほほう、そうか…いや、こら商いの道を教わった、あの親子に感謝せねばと言ったという。
正徳元(一七一一)年、祖父清春がドラ孫のだらしなさに切歯扼腕(せっしやくわん)しながら死亡する。叶屋の経営は番頭どもがとりしきるが瓢水には要るだけ金を届け、後は好き勝手放題、さしもの大店も傾きはじめ、享保十八(一七三三)年、母おさんが死亡したときは、空っぽの蔵がたった一つ残るだけであった。
どあほの瓢水が慌てて帰郷したときは、とっくに母の葬儀は終っており、親類の怒号を浴びながら墓前にひざまづく。かつては千石船五艘(そう)も持っていた叶屋が、蔵一つになったことに顔色さえも変えなかった瓢水だが、地面に額をこすりつけて顔をあげることができなかった。道楽の限りを尽くしても、恨みごともいわず、甘やかし続けた母である。有名な彼の代表句「さればとて石にふとんは着せられず」は、このときの句だ。
もうひとつ句に関するエピソードを紹介する。あるとき後徳大寺(藤原実定。定家のいとこ・歌人)の「ほととぎす鳴きつるかたを眺むればただありあけの月ぞ残れる」(百人一首で知られる)を俳諧に直せるかといわれ、即座に「さてはあの月が鳴いたかほととぎす」と詠み、周りを絶句させる。また彼は須磨の佳景を好み、「ほろほろと露そふ須磨の蚊遣(かやり)かな」「本尊は釈迦か阿弥陀かもみぢかな」の秀句を残している。後者の句碑が禅昌寺(神戸市須磨区)に立つ。※トップ写真
瓢水は何度も大坂を訪れる。松木淡淡(一六七四−一七六一年)と親しかったからだ。淡淡は芭蕉・其角の流派を継ぐ蕉風派の俳人と自称し、「半時庵」という俳諧グループの宗匠だが、富と権力におもねり、高額の指導料をとって句商人(あきんど)と呼ばれたぜいたくな男でもある。その淡淡と破滅型の瓢水がどうして気が合ったのかは分からないが、互いに相手の句を褒めちぎり、親交を結んでいる。あるとき淡淡の門人が妓楼に通いだし、気の進まぬ太夫を大金積んで無理に身請けしようとした。このとき瓢水が彼をたしなめた句が、人口に膾炙(かいしゃ)した「手にとるなやはり野に置けれんげ草」である。
こんな人生哲学じみた句を詠むくせに、経済観念のなさは変わらぬ。ひどい暮らしぶりをみかねた画家如流が、十数本の白扇に俳画を描き、これを売ったら金になると与えた。数カ月後みすぼらしい着物姿の瓢水を見掛け、扇は売れなかったかねと尋ねると、「へえ、ふろしきに包んで売りにいく途中、橋から落ちて川にはまり、みんな破れました」と、ぬけぬけ答えたという。
宝暦十二(一七六二)年、五月大坂で没。享年七十八。淡淡が他界した翌年にあたる。遺骸(いがい)は持明院(大阪市天王寺区生玉町)に埋葬、境内に今も墓碑が残る。
『続近世畸人伝巻之二』より抜粋
播磨加古郡別府村の人、滝野新之丞、剃髪して自得といふ。富春斎瓢水は俳諧に称ふる所なり。千石船七艘もてるほどの豪富なれども、遊蕩のために費しけらし。後は貧窶になりぬ。生得無我にして酒落なれば笑話多し。
酒井侯初メて姫路へ封を移したまへる比、瓢水が風流を聞し召て、領地を巡覧のついで其宅に駕をとゞめ給ふに、夜に及びて瓢水が行方ヘしられず。不興にて帰城したまふ後、二三日を経てかへりしかば、いかにととふに、其夜、月ことに明らかなりし故、須磨の眺めゆかしくて、何心もなく至りしといへり。又近村の小川の橋を渡るとて踏はづし落たるを、其あたりの農父、もとより見知リたれば、おどろきて立より引あげんとせしに、川の中に居ながら懐の餅を喰ひて有しとなん。
京に在し日、其貧を憐みて、如流といへる画匠初、橘や源介といふ。 数十張の画をあたへて、是に発句を題して人に配り給はゞ、許多の利を得給んと教しかば、大によろこび懐にして去りしが、他日あひて先の画はいかゞし給ひしととふに、されば持かへりし道いづこにか落せしといひて、如流がために面なしと思へる気色もなし。所行、大むね此類なり。はいかいは上手なりけらし。おのれが聞ところ風韻あるもの少し挙。
ある堂上家へ召れし時、
消し炭も柚味噌に付て膳のうへ
何某の大納言殿賜し御句
名はよもにひゞきの灘の一つ鷹。
といへる、 にこたへ奉りて、
ひとつ鷹狂ひさめたり雪の朝
大坂の知己の者遊女を請んといふを諫て、
手に取ルなやはり野に置蓮華草
母の喪に墓へまうでゝ、
さればとて石にふとんも着せられず
駿河の白隠和尚賞美の句のよし、
有と見て無は常なり水の月
達磨尊者背面の図に題す
観ずれば花も葉もなし山の芋
京の巴人といふもの病すと聞てのぼりしに、伏見にてはや落命したりときゝて、
嘘にしていで逢ふまでの片時雨
生涯の秀句と人のいへるは、
ほろほろと雨そふ須磨の蚊遣哉
七十六七ばかりにて終れりとぞ。
※以下は西天庵主氏による解説
江戸時代の中期、瓢水と称する隠れた俳人がいた。裕福な 家に生まれたが、芭蕉に憧れて旅に出て、放蕩を続けるうちにすっかり、財産はなくなってしまった。
蔵売って 日当たりのよき 牡丹かな
そんな瓢水の晩年の話。彼を慕う一人の雲水が、茅(あばら)屋を訪れると、瓢水はその雲水を待たせておいて、風邪薬を取りに行った。それを聞いたこの雲水「瓢水は生命(いのち)の惜しくない人間だと聞いていたが、案外な男だった」と、言い残して去って行った。 帰ってきた瓢水、近所の人からそれを聞くと、まだそれほど遠くには行っていないだろうからと言って、一枚の短冊を認(したた)めた。
浜までは 海女も蓑着る 時雨かな
これを受け取った件(くだん)の雲水は、自らの浅慮を恥じ、再び瓢水の茅屋を訪れ、一晩中語り明かしたという。
私がこの句を知ったのは太平洋戦争の末期、戦場に赴く我々が、どうしてまだ勉強を続けるのかと問うた学生を前にして、黒板にこの句を書いた教師の話を読んだ時だった。そこまでの極限状況ではないが「どうせ何をやっても…」と思う場面は多い。しかし、それでもやってみようと自分を奮い立たせるときに、この句のことを想う。
「一切空だと悟ったところで、空はそのまま色に即した空であるかぎり、煩わしいから、厭になった、嫌いになった、つまらなくなったとて、うき世を見限ってよいものでしょうか。」高神覚昇は「般若心経講義」(角川ソフィア文庫)で瓢水の句を引いて、このように続ける。